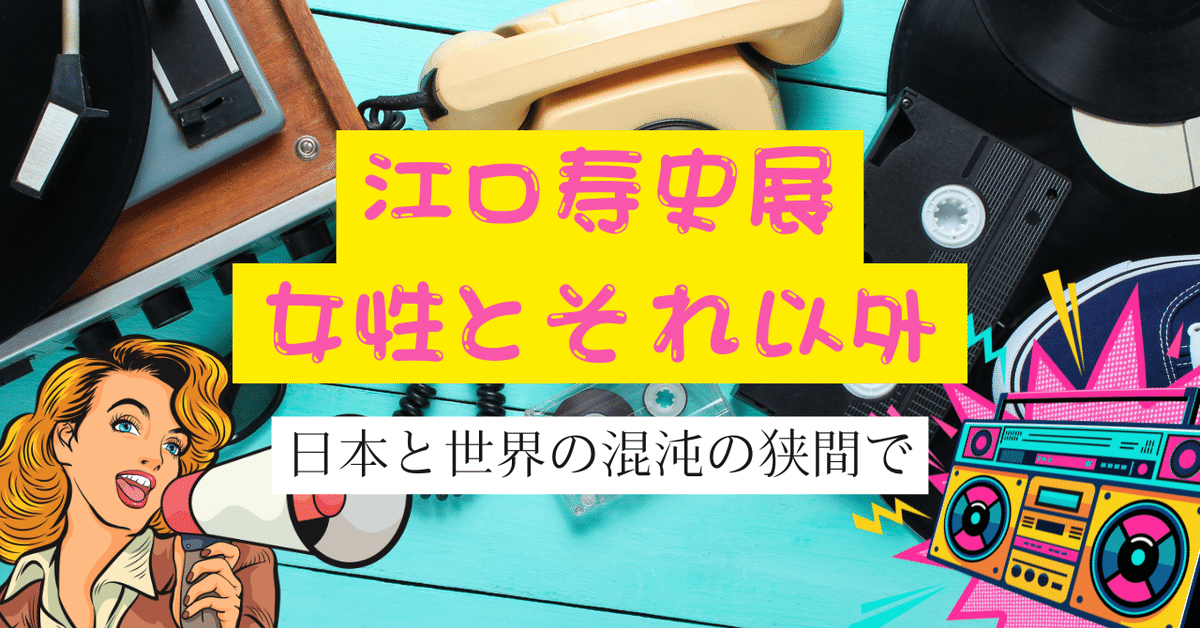
江口寿史展 女性とそれ以外 日本と世界の混沌の狭間で
福岡アジア美術館で開催中、江口寿史展の見応えについて。
さらに、この江口寿史展と同時に隣で行われていた「福岡アジア美術館開館25周年記念ベストセレクションII」のアジア女性の芸術における対比。
ああ、世界は混沌である。
コントラストが実に興味深かったのでその感想を書きます。
江口寿史さんの印象
7年前くらいに天神岩田屋で一緒に写真を撮って頂いた江口さん、昔から朴訥とされた印象とは裏腹に女性をなんとも上手く描かれるイラストレーターさんで、精力的にライブドローイングで普通の人を描くなど、次々作品を生み出す身近なアーティストというイメージです。
今回、ドキュメンタリー映像の上映があり
「女の子になりたい、ずっとなりたい女性像を描いているのかもしれない」
とおっしゃっていたのが興味深かったです。
そうか。だから色々な時代で色々なポーズで服装で、色々な場所に行く。
自由で明るくて可愛い女の子。それは理想の姿。
それがこの肉声を聞いて一番すんなり腹落ち。
今までより更に一歩、江口さんの表現の一端が垣間見えて、気持ち良い鑑賞となりました。
圧倒的な画力
展示について一番感じたのは
ポージングと主題、そしてファッションが素晴らしいということ。
人間の描写課題。それは構成力の難しさだと思います。
人間のみを主体として描くということは人物のポージングや背景を含めた構成力が、その絵のメッセージ性に大きく関わってくると思うからです。
その点、江口さんはライブドローイング=即興で大きなキャンバスにかかれるイラストも本当に上手い。

↑このポーズでこの大きさ(3m四方くらい)。
体全体を使って描くって相当の脳内キャンバス再現力が無いとチグハグになりそうなところうまくまとまっていて感嘆の極み。

↑この瞬間を捉えるテーマ選び。
マスクでアフターコロナでも逞しく生きる女子のみずみずしさをリアルに感じさせます。

漫画文化からの服の描写。
髪のかすかなはねと目の輝きで躍動感を感じさせ、そしてこのポーズ。
一瞬を魅力的に捉えた即興が画力の高さを感じさせました。
飽くなき追求
江口さんは見る人の意表を絶妙についてくる。
そのこれまでの想像を超えてくる、新しい表現に常に挑戦されているところが感銘を受けます。

2014年「漫画家による仏画展」参加(なんだその面白そうな展示は!)、イタリア文化会館所蔵の一枚。
観音様は女性!そうかイラストイケる!
という江口さんは女性イラストジャンルとして、もう可能性の宝庫。
本作も浮世絵のような線画と色彩表現と自身のスタイルが合致!
観音様の体をくねらせ、魚の形や波のうねりもあいまって流れる曲線美を感じさせながら、観音様の頭部の後光(後光がさすという、アレ)が頭頂部を中心に全体のセンターに配置。モノクロで表現することで全体のメリハリとバランスから「軸」を感じさせ安定感と安らぎに寄与する素晴らしい作品でした。
動画も素晴らしい!
ナイアガラ・トライアングル「A面で恋をして」MVでは映像で80年代ジャパンポップカルチャーを表現。

無限ループするようなイラストinイラストの世界観。
MV制作は日本のポップミュージックに造詣が深く、大滝作品のファンである、シンガポール在住インドネシア人の映像クリエイター・Ardhira Putra氏。海外からの視点で1980年代のジャパニーズカルチャーをオマージュ、そのMVには日本からアメリカポップカルチャーの憧れのような二重に背伸びをしているワクワク感を感じて素晴らしいの一言。
90年代のテレビで無駄にCGを使うオープニングのような、レトロの中にも未来的(当時から見た)な要素が、瑞々しくて爽快感満載でありました!
そんな中にバチッとはまるのが江口さんのイラストで、お見事。
漫画と浮世絵、昭和の影響
先ほどの錦絵のようなイラストしかり、浮世絵、漫画…島国で独自に日本人が歩んできた美術史の流れで生まれた江口さんの作品の数々。
浮世絵に影響を受けたアメリカポップカルチャーの代表的芸術家ウォーホル、さらにその影響を受けたグラフィックデザイナーの横尾忠則さん。
近しい画風で漫画家のつげ義春さん、さらにはフランスの漫画タンタンまで…ありとあらゆる芸術の相互影響関係。
先人たちの生きた証、現代へ続くアート魂の鼓動を感じて感動しました。

ギャグ漫画家が出発点である奇跡・軌跡
江口寿史さんは、ギャグ漫画家が出発点なことも特筆すべき才能の原点。
ドキュメンタリー映像では「自分は絵が下手でギャグ漫画だからいかに面白く描くか、笑ってもらうか、1ページにいくつギャグを盛り込めるかと思って描いていた」というお話がありました。
その経験がまさに今に活かされています。
はみ出した口紅から画面をぬりたくるような遊ぶ線に昇華させたこちらも好き。元々ギャグ漫画を描いていた江口さんの素地が生んだ「マス」を使ったストーリーある作品が日本らしい。


単純に色の組み合わせとバランスが素晴らしいと思いませんか?
やはり人間の脳もAIと同じでどれだけ物を見て、知識やイメージのストックをするかということに尽きると思います。
そういう意味で今回の展示はバリエーションが多くて大変勉強になり、心からおすすめの展示です。
その壁のお隣で
アジア美術館、その隣で行われていたのが「ベストセレクションIIーしなやかな抵抗」という記念展示ですが、江口寿史展のすぐ隣にこの社会的メッセージを強く持つ展示を持ってくるあたり、アジア美術館の感覚の鋭さを感じさせます。

江口寿史さんの展示作品はどちらかというと時代に消費される商業ベースの作品における女性像が多く、中心に立つ女性たちは作品によってはセクシーであったり見られることを厭わない清潔さを持ち合わせて存在しています。(私はこの世界観を否定する気はなく、その高い芸術性に尊敬の念を持っていることは述べておきたい)
しかし、隣の展示では世界中で性別や宗教など様々な要因により未だ虐げられ分断/差別された怒りや疑問をアートに訴えかけるたくさんの作品が展示されています。
例えば、入口すぐ、中国人アーティストのオブジェ作品「駱駝」。
一見ただ等身大の駱駝です。 しかし解説を読むと、そのコブの毛は刈られており、キリスト教の「金持ちが神の国に入るよりも、駱駝が針の穴を通る方がまだたやすい」新約聖書マタイによる福音書19章23-24節がフランス語で彫られています。
その駱駝はムスリムがお祈りの時に使う絨毯にひざまずき、展示の際はメッカの方角に展示するようにというアーティストの指示があるそう。
駱駝はシルクロードを行ったり来たりして東洋と西洋をつなぐもの。
アラブでは富の象徴であり、預言者ムハンマドの乗り物としてお祭りや儀式で神様への生贄として捧げることもあるそう。しかし一方でキリスト教では重荷のコブが人類の罪を背負ったイエス・キリストにも例えられる。
キリスト教とイスラム教、双方にとって重要な生き物の駱駝。
今日も続く異なる宗教同士の対立や経済的覇権をめぐる衝突を激しく批判する作品ということです。
このように、産後の作者自身の女性の不自由さを表現した中国人女性のオブジェ、カンボジアのクメール・ルージュにまつわる子供たちの悲劇を表現した展示、パキスタンとインドの自由と混沌、西洋のビーナスに対比させるイスラム教のブルカに全身を目元すら覆われた女性像で表現した絵画、などなど。
江口寿史展が表現する「消費するポップカルチャー」も、アジアの「宗教や経済対立に巻き込まれる女性や子供たち」もすべて現実に存在する。
この世界の混沌に、私、深く。
今生きている重みを感じたわけです。
先人から受け継ぐ感謝とも困惑とも取れる複雑な気持ち。
とにかく江口寿史展に行かれる方は、お隣の展示も解説書を片手に是非見てほしいと思いました。
勇気と気合がいりますが、それが教養として生きる糧にきっとなると思います。 体感する歴史、時代はいつも
求めよ、さらば与えられん。
探せよ、さらば見つからん。
叩けよ、さらば開かれん。
そして、同じフロアにあるアートカフェもたくさんのアートや文化関連書籍がたくさんあり読み放題。美味しいイエナコーヒーの飲食も併せて楽しまれることをお勧めします。私が超たまに働いています。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
芸術や映像、広告、女性子育てなどについて発信しています。
ご意見コメント楽しみにしています。
平日毎朝8時にnote投稿中。
内容が良かった時は、スキ、フォロー、お願いします。
いいなと思ったら応援しよう!

