
心がけ1つで集団の技術向上が変わっちゃう話
こんにちは、ニシジマです。
もうすぐ新年度ですね~
4月になると新たな趣味として楽団員が増えたり
新入生が部活動に入ってきたりして
「先輩」という位置づけになる方もいらっしゃると思います。
今回はそんな先輩のみなさんに
心に留めておいてほしい心得についてお話ししようと思います。

■先輩という響きがもたらす精神的ハードル
「先輩」という言葉からのイメージってどんなものがあると思いますか?
たとえば自分が新しい環境に入ったとして
もちろん周りにいる人はみんな初対面でみんな先輩。
こんな状況を想像してみてください。
この状況で不安を感じる人は多いのではないでしょうか?
自分から先輩に話しかけられるメンタルの人は「そう?」って思うかもしれないけど
自分からいくのはちょっと戸惑う人の方が多いのではないかな、と。
実は、先輩になる人たちは
このことを少し頭に入れておかないと
チーム全体の技術向上が遠回りになる可能性が高いんです。
一度ニガテ認定されちゃうとやりにくいこと間違いなしだし
チーム戦である吹奏楽においては不利そうだと思いませんか?
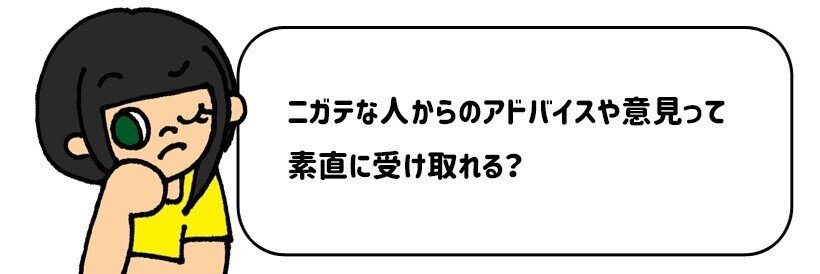
■分からないことを聞ける空気づくりの重要性
どうやら入学したての1年生の多くは
先輩=厳しい、怖い、怒られちゃうかな?
というイメージが多いらしです。
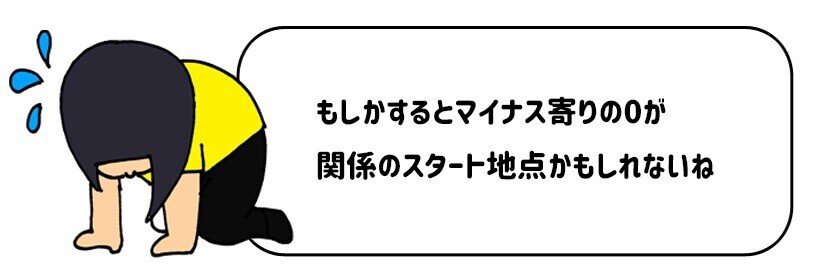
そんな意思疎通がうまいこと言ってない状態の中で
「これくらいあたりまえのことじゃない?」という前提で接すると
コミュニケーションがうまくいかないことはなんとなく想像できませんか?
1つのものを作り上げる合奏において
コミュニケーション(アドバイスとかね)がうまくいかないのは
私はあまり良い状態だと思えません。

■「ニガテな人」認定されやすい2つのNG行動
できれば「あの人ニガテ」の分類には入りたくないですよね
ニシジマ的ニガテ認定されちゃう人の特徴は
大きく2つあるんじゃないかと推測しています。

♦1回言えば身につくという思考
新入生(中1)は数か月前まで小学生。
先輩後輩なんて考えがそもそも存在していません
たとえばこんなことが起きませんか?
・ため口をきく(敬語が使い慣れていない)
・挨拶をわすれる(周りが見えていない)
意識的に行わないとできないレベルということは
忘れていたら教えてあげなくちゃ治りません。

♦本人がいないところでの指摘
気になるところは本人にちゃんと伝えないと変われません。
(分かってやってたら大物だけどw)
たとえば…
本人がいないところで「○○さんは挨拶をしない」
⇒これはただ陰口になる可能性が高い
もちろん
人に指摘したいことがあるときは
自分も率先してできていないとダメです。
例えばあいさつ
先輩からの意見:後輩が挨拶をしない
後輩からの意見:挨拶しても無視された
(だからしないっていうのもどうなのかね…とは思うけど。)
こんな感じのことって結構起きていませんか?
少しの違和感で関係は簡単に壊れるので
私はこれをとてももったいなく感じるのです。
■注意しない=優しい人 は勘違い
注意したら嫌われちゃうかもしれないから私はしないんだ~
って人も中にはいるでしょう。
そりゃ私だって嫌われることはやらなくていいならしたくないです。
でも
チーム戦の吹奏楽において
集団を上手に良い方向にもっていきたい時に
指摘ができないという状態はかなり不利だと思いませんか?
だって、みんなでいい演奏を作り上げなきゃいけないのに
違うなって思ってもお伝えしなきゃ直してもらうことができないわけじゃないですか。
なので
嫌われるような注意の仕方をしないように心がけてみてほしいんです。
■指摘を「怒られた」と表現するようなやり方はしない
私の中では「注意」と「指摘」には違いがあると思っていて
これは勝手な感覚なので正確にはわからないけど
・指摘⇒ここ違ってるよ~(直しておいてね~)
・注意⇒ねえ、なんで違ってんの?(切れ気味に)
と、ざっくりこんな感じだと思っています。

チョッとしたことの積み重ねで雰囲気は本当に変わるので
ぜひ頭の片隅に入れてみてください。
■まとめ
外部講師的な目線から見える皆さんの様子でいうと
上手い下手だけで後輩は先輩を見ている様子はありません。
だから
先輩だからといってすごむ必要はないし
一生懸命いっぱい話しかけたりする必要もないと思います。
アンサンブルが上手だな~と思う学校って
面倒見がいい先輩が多かったり
先輩に相談していたりする子が多いなと感じています。
コミュニケーションがうまくとれているというのはきっとこういう状態なんですかね。
自分がされて嫌なことはたいてい他の人も嫌なこと。
憧れる先輩や好感度の高い先輩にどんな時「いいな」と感じているのか
観察して自分も実践してみるのがベストなんじゃないかなと思います。
次回(3月16日配信予定)は
最近レッスンしていて気になった
メトロノームへの合わせ方についてお話ししようと思います。

いいなと思ったら応援しよう!

