
メロディーをうまく引き継ぐ
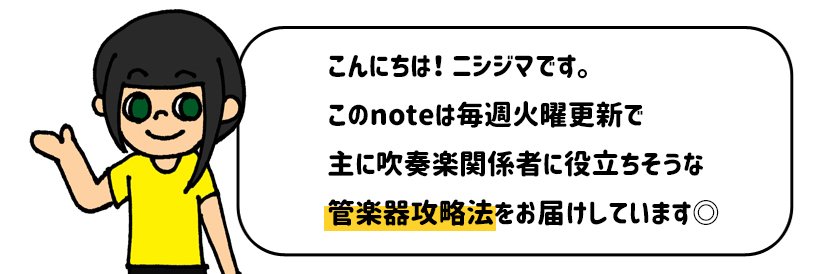
メロディーラインがリレーのように次々とバトンタッチされていく。
曲を吹いているとたくさん遭遇しますよね?
今回はこのメロディーを上手に繋いでいくコツを
一緒に考えていこうと思います
■前後の関係者の音をしっかりと聞いてみよう

ずーっと1つの楽器がメロディーを取り続けることは
まぁありえません。
必ずと言っていいほど
他の楽器に主旋律はバトンタッチされていくわけですが
この時に
自分は大きな塊の1パーツだという意識を持つことが大事です。
小学生の時、「交換ボール」という球技があって
2人1組で、お互いにドッジボールの玉を同タイミングで投げてボールをキャッチする、というものがあったのですが(これは全国区の球技…ですか?)
成功させるには相手のボールの高さ、投げるタイミングを目で見て予測をつけるか事前に決めておかないとうまくいきませんでした。
これと感覚は似ているのですが…伝わりますか?
■メロディーが上手に繋がらないように聞こえる原因

楽器が変わったときに
変わり目がデコボコしているのが主な原因のように思います。
音色がそもそも違うので
そう聴こえやすいのはしょうがないと言ってしまったらアレですが
色々とすり合わせておくと
楽器の音色が変わっても1本のラインで聴かせることは可能です◎
・音量の問題

デコボコに聴こえやすい一番の理由は
音量レベルが前任者と違う、という点です。
たとえば
メロディーを担当するところの部分に「mf(メゾフォルテ)」と書かれていたとします。
この場合に
自分が思う「mf」で吹くとうまく繋がらない
という現象が起こる、とこんな感じです。
ではさらに条件を足してみます。
ベルが前を向いているトランペットから
ベルが斜め後ろを向いているホルンへとメロディが移り変わったとします。
物理的に直管で音が前に飛びやすいトランペットと
管がグルグルしてて優しい音色が特徴のホルンが
同じ音の大きさで鳴ってほしいと要求された場合
恐らく各々の「mf」で吹いてしまうとうまく繋がらない可能性が高いのです。
なぜかというと
構造上の音の鳴り方を逆算しないと
どうしても音の届き方に違いが出てしまうからだと私は推測しています。
・吹き方(音色のイメージ)が違う

一番最初に自分は大きな塊の1パーツだという意識を持つことが大事
と書きましたが
このフレーズの性格?雰囲気?が統一されていないのも
うまく繋がって聞こえない原因のように思います。
どういうことかというと
たとえば
マルカート(一つ一つの音をはっきりと粒立てて吹く)と指示が出ていたとして
この場合、音と音の隙間を少し空けるような感覚で吹くと上手に聴こえるのですが
この音と音の隙間をどのくらい空けるのかの統一が上手にできていないと別物に聞こえてしまいます。

小さい音で、などの音量で指示されている時も
同じようなことが言えるのですが
小さくというのはどんなイメージか
(緊張の糸がピンと張ってる感じとか、夜のお墓のようなおどろおどろしい感じとか…)
こういうところを耳で察知したり
言葉ですり合わせていくことで
同じニュアンスを共有することがカギです◎
解決策を考えてみた

これらの解決策は
やはり耳でしっかりと情報をキャッチすること
だと思います。
ここでは便宜上
メロディーを先に吹いている方(メロディーを次に受け渡す方)を第一走者
メロディーを引き継ぐ方を第二走者
と名前を付けて考えていきます。

・第1走者は続きがあるように

これは無意識の領域かもしれませんが
塊が終わる時って無意識に「おわりました~」と吹いちゃいがちです。
足元を見ずに階段を降りたとき
次の段はもうないと思って一歩踏み出したらまだ1段あって
足がガクン!ってなったこと…ありませんか?
あんな感じに近いです。
↑こんな感じで
フレーズのお尻などで
もっていきかたが変わっちゃってることが多いのです。
なので、こんなときは
楽譜には書いてないけど
この続きも自分がまだメロディーを担当しているんだ!
という気持ちで吹きこむと
息の入れ込み方もだいぶ変わってきます◎
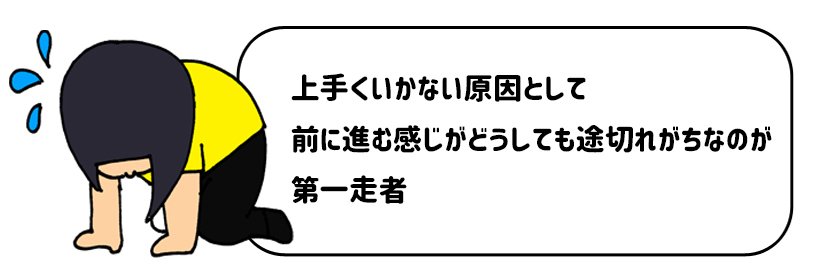
・第2走者は助走が大事

バトンを受け継ぐ第2走者は第一走者のスピード(前に進む感じ)
を殺しがちです。
これは
根底に流れている細かいリズムがシンクロしていないことが多いです。
少し前までリモート合奏が流行っていましたが
あれを聴いてちょっと不自然というか
何だかぎこちない感じがしませんでしたか?
各々でメトロノームに忠実に演奏しても
このリズムがみんなでシンクロしていないと
ぎこちなさが隠せなかったんじゃないかな~
とニシジマは分析しています。

これを解消するには
第一走者の歩幅というかリズムの刻みを自分にも落とし込む
もっと言えば
自分も吹いているつもりで待つ。
そんな感じが良いです。
■まとめ
メロディーが出てくると
よし来た~!!!とやりがちですが
(低音属の私はめっちゃ気持ちわかる、だってメロ少ないもry.)
そこをカッコよく聴かせるには
前の人からのバトンタッチを上手にこなす必要があります。
吹奏楽は集団競技なので…しょうがないです。
私の音を聴け!とやりたい場合は
無伴奏のドソロとか…オススメしておきますね…
(これはこれでなかなかの気持ちになりますw)
次回(12/21配信予定)は
音の出だしが荒れちゃうことについてお話ししようと思います。
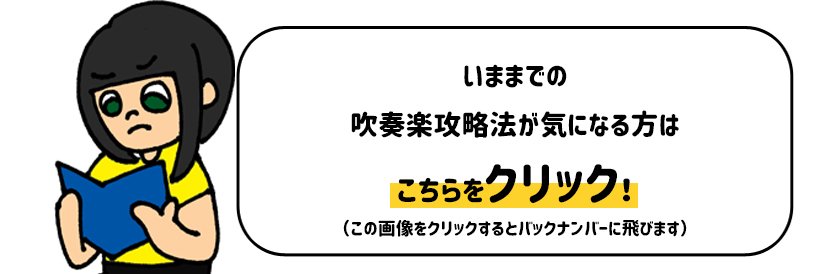

いいなと思ったら応援しよう!

