
アドバイスとは連想ゲームのようなもの。
こんにちは、ニシジマです。
顧問の先生、パートの先輩、外部講師の先生
いろんな人が色んな言葉でアドバイスをしてくれると思いますが
色んな言葉で説明されて
「で、どうすればいいの!?」ってなるときありません?
今回はそんな混乱状態になってしまう人にお伝えしたい
情報を制するアドバイスの取り入れ方(捉え方)
をご紹介しようと思います。

■混乱原因1:目に見えないものを言葉にする難しさ

音って紙やペンのように
物体として目に見えないですよね。
【目に見えないのによく出てくる説明】
・音の形
・音色
・口の中、使っている筋肉の動き
・空気がどこをどんな風に通っているのか etc.
音だけでなく楽器を吹いている時のリアルタイムな口の中の動き(舌とか唇とか喉とか)や筋肉自体もなかなか見ることはできません。
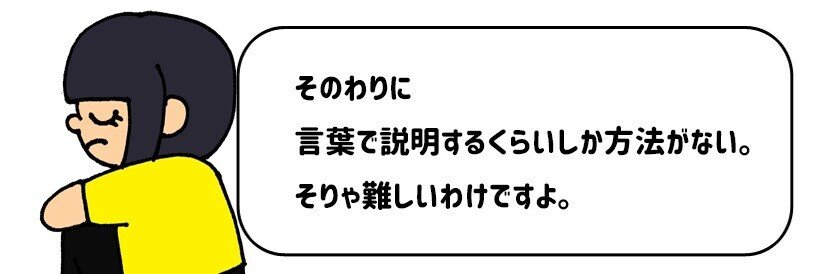
■混乱原因2:感覚は人それぞれ

例えば人気の辛~い料理を食べた、とします。
Aさん{すごくおいしかったよ!また食べたい!
Bさん{これはおいしくないよ~食べられる物じゃない…
同じ料理を食べても辛い料理をおいしいと感じる人と感じない人がいます。
同じ体験(体感)でも人のフィルターを通すと表現は変わってしまうんです。
■アドバイス=連想ゲームのようなもの

ではどうしたらいいのか、というと
あくまで私の見解ですが
アドバイスとは連想ゲームに似てるんじゃないか?という考え方です。
ここでひとつゲームをしてみます。
\クイズ!この楽器は何でしょう?/
今から4人がとある楽器の説明を1つずつします
さて、何の楽器でしょうか?
Aさん「金管楽器です」
Bさん「低音域です」
Cさん「小さい楽器ではないです」
Dさん「伸び縮みします」
さて、なんでしょうか?
正解は「トロンボーン」でした。
さて、みなさんはどの段階でトロンボーンだとわかりましたか?
きっと多くの方はDさんの伸び縮みをするって言葉で確信を得たのではないでしょうか?
アドバイスとはまさにこれで
同じ最終形態を説明しているんだけど
人それぞれに重要視しているところ、とらえる角度が違うので
いろんな表現が生まれてしまうわけです。

■アドバイス通り練習してるのにうまくいかない人へ

たとえば「リップスラーはできないといけない」みたいな
これをしなさいという指示やメニューをこなしている人もいると思います。
確かに金管族的にはリップスラーは楽器を吹くうえで外せない技術ですが
なんでできないといけないんでしょうか?
文章で説明すると大変なことになるので省略しますが
ざっくりいうとリップスラーができるということが最終目標ではなく
なにかをできるようになるための過程だと思ってもらえればいいです。
そのできるようになりたい完成形のものを作る手段として
その方は「リップスラー」という言葉をチョイスした、ということです。
だから
リップスラーすればいいんだ!
という言葉をそのまま受け止めて実行するだけでは必ずうまくいくとは限らないんです。
上の例でいう「小さい楽器ではないです」みたいな的を絞りずらいアドバイスと
「伸び縮みする」という自分にとってわかりやすい説明がある
ということを頭においてアドバイスを聞いてみてください。
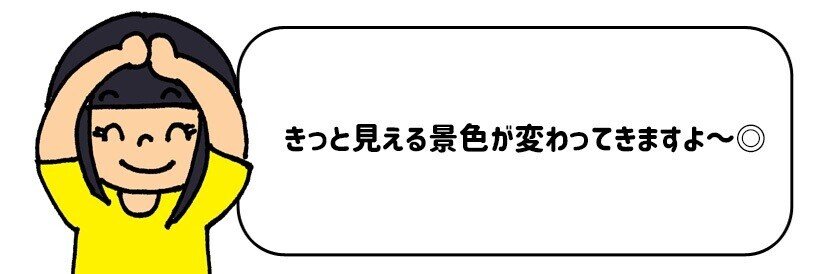
■まとめ
自分に刺さる魔法のアドバイスをもらえるかは
ソーシャルゲームのガチャ並みに運ゲー要素が強いと思います。
超一流の人からのアドバイスだからと言って全員に刺さるかっていったら謎です
(ある程度は刺さりやすいと思いますが)
だからと言ってたくさんの先生に習おう!
ということは私はお勧めしませんが
なかなか変化を感じられない、うまくいかないな
と思うときは最終形態はどんなものなんだろうかと
少し考えるのもアリかな、と思います◎
次回(3月9日配信予定)は
新入生を迎える前に心に留めたい
先輩になる準備についてお話ししようと思います。

いいなと思ったら応援しよう!

