
歌集を読む・その7
こんばんは。少し間があいてしまいました。
今回扱うのは吉野裕之『砂丘の魚』です。2015年、沖積舎刊行。魚にはうおとルビが振ってあります。あと、吉の字は下が長いほうです。

吉野さんは1961年生まれ。大塚寅彦とかも同世代です。1960年生まれに大辻隆弘、1962年に俵万智・穂村弘・荻原裕幸など。同世代にいろんなひとがひしめいていますねえ!おおよそ80年代後半のニューウェーブの時期に出始めたひとが多そうです。
まずこの歌集、装丁がおもしろくて、帯を外すと色が反転します。
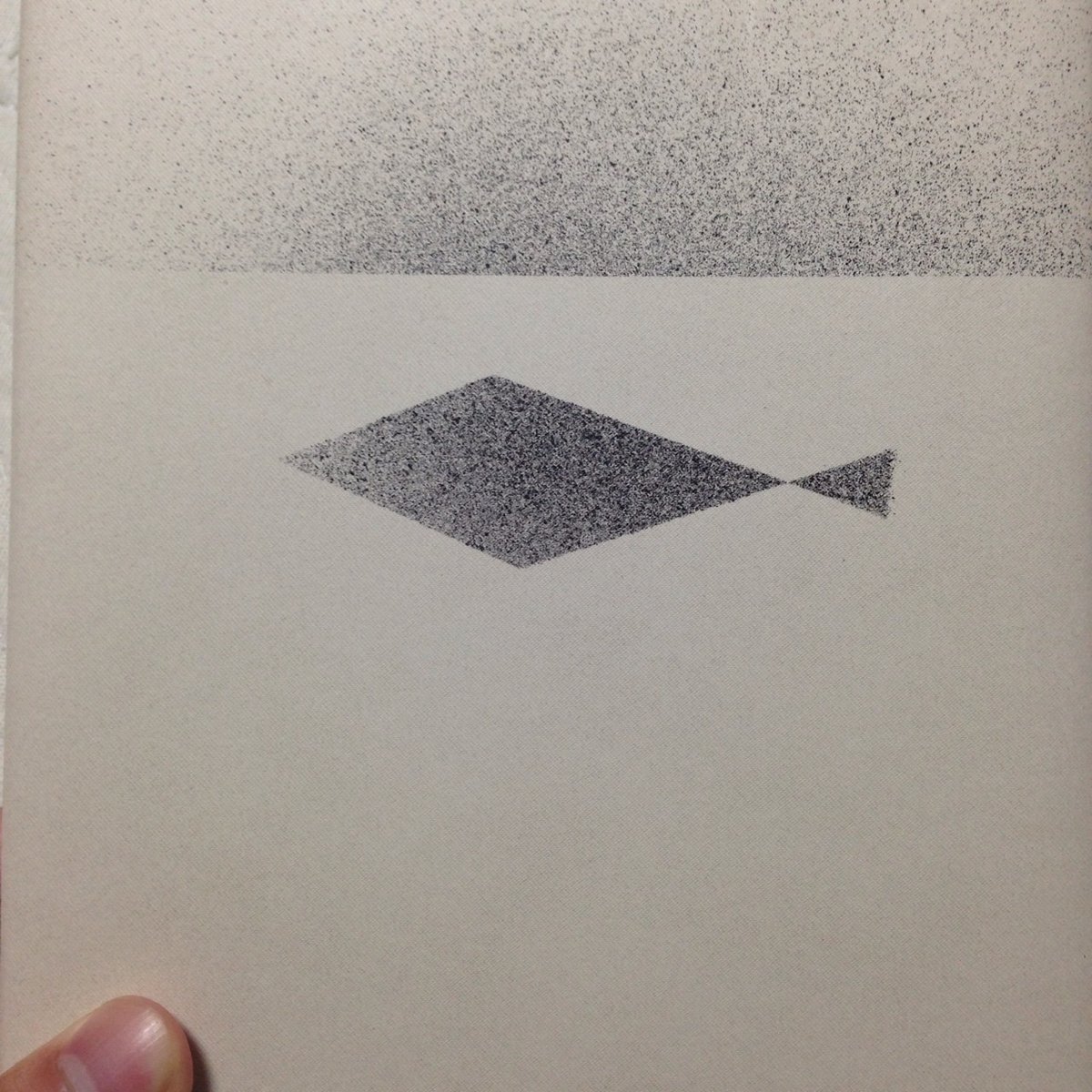
なんかおしゃれですね。いいぞ。では歌を見ていきましょう。
南からやって来た船大きくて横切ってゆく ゆっくり私
裸木の群れを遠くに立っている降るのだろうかこの夕方も
吉野さんの歌は、微妙にピントをずらすことで生まれる変なやわらかさがありますね。たとえば一首めは船が私の前を横切っていったんだろうけど、こういう言葉のはめ方をする。「ゆっくり」は副詞だから、「ゆっくり私」というのは明らかに欠落が生じています。歌の中で解消するのであれば、「船がゆっくり私を横切ってゆく」みたいな感じでしょうね。でも、こう書かれると、「私」自体がゆっくりと在るようにも見える。
二首めは、「群れを遠くに立っている」あたりが助詞ウマポイントでしょうか。これが「群れが遠くに立っている」だとだめなわけですね。裸木の群れを遠くに見ながら、遠くに置きながら、〈私〉は立っている、というような読み筋が妥当だとおもいます。こういう助詞やシンタクス(統語)のねじれというのは、どの程度まで読み手が受け取れるかみたいな問題を孕みがちですよねえ。私はこの歌はわかるし好きだけど、ここがねじれててわからない!ってひとがいても仕方のない歌だとはおもいます。けれど、短歌が定型とともにある限り、言葉の方がねじれてくるということはこれからも起こりうるのだろうなとおもいます。良い悪いの話じゃなく。
吉野さんの歌は情報量が詰まりすぎていなくて、かなり読んでいて心地良い。おしつけがましくないんですよね。それとリズムの作り方がやわらかいんだとおもいます。
春泥や小さな人が歩いてゆく大きな人に挟まれながら
こぼれたらたいへんだけどこぼれない珈琲きみのテーブルの上
この二首も何気ないけれど好きな歌ですね。春泥や、って俳句みたいに切れをつくって、そこから宇宙人が大男に挟まれてるみたいな図が浮かび上がってくるのが不思議で、かなりどうでもよく、けれどこういうもんなんだろうなあと思わされる。この3句めの「歩いてゆく」の字余りとか大事なんですね。「歩きゆく」とか「歩いてく」ではこの歌の感じは出ない。歩きゆく、だと重く、歩いてく、だと軽い。歩いてゆく、フラットで、性急じゃない物言いがすごく心地良い。小さな人とか大きな人とかが何なのか、というのはもう気にしなくていいわけですね。たぶん外で見た大人と子供とかかなあ。
こぼれたら、の歌、これは初読時にはノーマークだったけれど、名歌なんじゃないでしょうか。こぼれたらたいへんだけどこぼれない……。ただそれだけなんだけど。こぼれる可能性や予感というものに意識をはらっているわけです。ぼんやりとしたピントが、たまにこういう思索的な部分とつながっていくのはおもしろい気がします。
午後までの旅ってことになってたけど近くに立てる一頭の馬
かなしいとことばにすればひかりが来るあなたに教えられた通りに
すでに終わった恋のようなる秋の日にかがやく茄子をひとつもぎたり
歌を並べると、やはり韻律が心地良いなあっておもいますねえ。「旅ってことになってたけど」の「っ」(促音便)の使い方とか。「ひかりが来る」の6音とか。「かがやく茄子を」の細かい韻の踏み方とか。三首め、とても心地よい韻律だけどなかなか要素にばらせないのが面白いですね。3音や4音を中心として音が推移するからなのかなあ。
「馬」って何やねん、とか、「ひかりが来る」って何やねん、とか、茄子もいだだけかい、とか野暮なツッコミは色々できるんでしょうが、吉野さんの歌はずっとこんな調子に意味の余白を置いて、フレーズで魅せてくるものが多いです。「馬」は象徴でも、心象風景でも、実景でもいいような気がするけど、なんだかこの歌はかっこいいなあと思わされてしまう。午後までの旅と馬はきっと無関係だけれど、それをフレーズや定型のちからが一首に繋いでしまうのかもしれない。
なんだか、語ろうとすればするほど難しい歌人ですねえ。でも彼の歌も、決して奇をてらうような感じには見えなくて、本気でそう言ってるんだろうな、と私には読めてしまう。(少し贔屓目なのかもしれませんが) この人の目線のなかでは、空間がたわんでるような、そんな感じがあって、それが詩情につながるんだろうなとおもいます。
それでは今日は終わりにしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
