
2023年・フィンランド音楽のべストアルバム50選
2023年に発売されたフィンランド音楽作品からベストアルバムを50作品選び、感想を書きました。
50作品。自分で決めておきながら、ものすごい量だ。この記事を書き始めた当初は10作品に絞って2023年内に記事公開予定だったのに。
しかしそれは僕にとって難しいことだった。2023年は素晴らしい新譜がたくさん発売されたので、できるだけ多くの感想を書き残しておきたかったし、何よりこの記事にアクセスしてくださった方にフィンランドの興味深い音楽を紹介したいという思いが強かったのだ。
結局、10作品に絞ることをやめ、気付いたら50作品になり、公開も2024年2月となってしまったのだが、これでよかったと最終的には納得している。文章量が多すぎるし、人様に音楽を紹介する記事にしてはあまりにも読みづらい作りになってしまったけれど、自己満足という観点で言えば、充実感、やりきった感は相当なものだ。でも、それでよかったんだと思う。
今回はランキング形式ではなく、アーティスト名のアルファベット順で掲載しています。各作品、感想の最後に各ストリーミングサービスのリンクを設置していますので、もし気になる作品などあれば聴いてみていただければ嬉しいです。フィンランド音楽はものすごく熱く、面白い作品に溢れています。
A.Takalo『Kuva taivaasta』

A.Takaloは、キュメンラークソ出身のシンガーソングライター。2013年デビュー。自身のソロやリーダーバンドA.Takalo & Takavalot(2021年解散)で活動しつつ、Lasten HautausmaaやThe Souls、Titty Bar Tim Blues Band、The Mutants等様々なプロジェクトに参加。本作はソロ名義では12thアルバム。
聴いているときの感覚は、なんだか懐かしくなる、実家に帰ったときの安心感に近い。それは多分、本作がThe Byrdsとか、Kevin Ayersとか、John Simonあたりの60年代後半~70年代初頭のロックの音に近しいからだと思う(学生時代、その時代の音楽にどっぷり浸かっていたので)。A.Takaloは多作家で、ここ2013年~2023年の間で20作近くのアルバムを出しているのだけれど、どの作品も音楽性に大きな変動はない。何か新しいことに挑戦している印象を受けるかというとそれもない。しかし曲はどれも心踊らせる内容で、それは本作も例に漏れず「いつものA.Takalo」だ。しかし、そこが良い。少し気の抜けたボーカルに、キラキラとした幻想的な音、「陰」の要素は少なめでノリが良い…など、A.Takaloでしか味わえない旨味があって、それを本作でも存分に味わうことができるからだ。それは英、米のロックとはまた違った味わいなのではないかと思っている。冒頭で挙げた音楽家が好きな方は是非聴いてみて欲しい。
Absolute Key『Kevään Muoto』

Absolute Keyは、タンペレ出身のブラックメタル・バンドCircle Of Ouroborusのボーカル、Antti Klemiによるソロ・プロジェクト。2019年に1stデモを発売以降、多くの作品を発売しており、本作は恐らく7thアルバム。
一言で表すなら「暗闇で泥沼を這いずるときのサウンドトラック」。Public Image Ltdの1stからグルーヴを削ぎ落としてダークアンビエントに接近したような音が非常に格好いい。Circle Of Ouroborusは少しばかりユーモラスな要素もあるのだが、本作は終始シリアスな空気に包まれている。ボーカルは金切り声と生気を失ったクリーンボーカルを巧みに使い分け(それでいて「器用さ」「達者さ」は感じさせない、本能的なもの)、まるでブラックメタル化したダモ鈴木のようだ。アルバム全体としては、落としどころとは無縁の「現象の断片」のような曲が多く、出口のない感じが続くのだが、アルバムの流れは非常に良いので、最後まで楽しく聴けてしまう。最後の曲『Maailma ei ole sinua varten / Aamun siemen』では13分間の絶望に襲われつつも、この曲の構成の素晴らしさ力強さも相まって何故か気分は盛り上がるし日によっては爽快とさえ感じるのだ。最後まで聴き終わった後の不思議な感触は、本作を聴くことでしか味わえないものなのかもしれない。
ところで、「界隈」や「シーン」が存在するのかは定かではないが、フィンランドのアンダーグラウンド界隈では「エクスペリメンタル」や「パワーエレクトロニクス」などを軸とした精鋭な音楽家がここ4、5年の間で続々と名作を生んでいるように思う。2022年の年間ベストにも選出したShark VarnishやLupiinit、Viimeiset、そしてAbsolute Key。いずれもあまりにも個性に溢れているためジャンルで括ることは不可能だが、「暗闇で蠢く音楽」という点で僕の中では共通している。本人たちもシンパシーを感じているのかライブハウスで積極的に対バンをしており、名もなきシーンは既に誕生しているのではと感じてしまう。サウスロンドンのポストパンクシーンが巷に知られる前の雰囲気はこういう感じだったのだろうか。
Ahti Kulo『Ja niin mekin katoamme』

Ahti Kuloは、2023年7月2日にシングル『Kuu putoaa』でデビューしたシンガーソングライター。本作は1stアルバム。
ジブリなら『もののけ姫』は宮崎駿の最高傑作だと思うけど、結局一番好きで何度も観てる作品は『魔女の宅急便』かな…といった具合に、「凄い作品」だからといって「好きな作品(長期的に鑑賞する作品)」になるとは限らない、というのは興味深い。
ここで言う「凄い作品」を音楽アルバム当てはめるなら、壮大な演出が施されていたり、アルバム全体に明確な方向性やコンセプトがあったり、メッセージ性の強さ、重さがあったりと様々なのだが、こうした「凄い要素」があるアルバムはインパクト面の強度が高いので、聴取時は非常に楽しくエキサイトできるものだが、そのインパクトの強さゆえに、聴き疲れしてしまう作品も少なくはない。そういった作品は長期的に繰り返し聴くよりかは、年1回くらいのペースで思い出したように聴いてみて、「やっぱすげえな」となることが、僕の経験では多かった。
この記事に挙げている作品はもちろん全て「好きな作品」なのだが、Ahti Kulo『Ja niin mekin katoamme』は「凄い作品」でもあるという、ちょっと珍しいケースだ。
本作はアンビエント/エレクトロニカ寄りの歌モノという立ち位置になるのだろうか。全体的にFenneszに近い音がベーシックでありつつ、時にはmúmのような心地よい静かな曲もあれば、world's end girlfriendのような壮大なエクスペリメンタルが繰り広げられる曲もあって、振れ幅はかなり広い。でも元となる音の方向性は同じだから、アルバムとしては非常に統一感がある。曲順も相当考え込まれていると思う。曲が進むごとに本作の世界にじわじわと引き込まれて、「ながら聴き」してる場合じゃないと思わせるアルバムの流れも素晴らしい。
そういった一つ一つの要素が集約されていることで、僕にとって本作は間違いなく「凄い作品」になるわけなのだけれど、不思議なもので、通しで聴いても聴き疲れすることがなく、むしろ繰り返し何度も聴いているのだ。なぜだろう。歌のメロディが好き、暗すぎない、重すぎない、うるさすぎない、静かすぎない…つまり、とてもちょうど良い塩梅で作られたアルバムだからなのかもしれない。もしかしたら作者本人も「凄い作品」ではなく、繰り返し聴いてもらうことを重視していたのではないだろうか。絶妙なバランス感覚が成立した逸品である。
Arppa『Valeria』

Arppaは、シンガーソングライター、俳優。2019年にシングル『Helsingin hulina』でデビュー。本作は3rdアルバム。
本作の基盤となる要素は2つあると思っていて、1つがPuma BlueやConnan MockasinなどがやっているようなオルナタティヴR&B、もう1つは『Schmilco』以降のWilcoがやっているようなオルタナカントリー。曲ごとにいずれかの方向性にわりとハッキリ分かれているため、聴き始めた当初はアルバムとしての統一感がイマイチと感じていた。また、いずれかの方向性に振り切れず中途半端になっているのではという印象も持っていた。反面、曲単独ではどれもすごく好印象だったので、もったいないなぁという思いを抱きつつ、しばらく聴かない日々が続いていた。
そういった経緯もあり、この記事を書き始めた当初は本作は選外だったのだが、もったいないという思いが心のなかで引っかかっていたのだろう。僕は無性に本作が聴きたくなった。改めて聴いたら印象が変わっているかもしれないという希望を抱き、聴き直したところ… あれ?素晴らしいアルバムではないか!どういうことなんだと、自分で自分に驚いた。
本作を聴き直してみると、以前感じていた「アルバムとしての統一感がイマイチ」という点は大きく変わった。それはつまり、アルバムとしての流れが素晴らしいことに気付いたから。窓を開けた瞬間風が吹き抜けてくるように爽快に、壮大に始まるオープニング。中盤~後半になるにつれディープな方向に突き進んでいくR&B寄りのナンバー。長いトンネルを抜け、一面に広がる青空の下、ただただ穏やかなひとときを与えてくれる最後の2曲。その物語を30分弱で展開するという、ほどよい尺。いずれも素晴らしい。このような流れが重視されていることを実感すると、以前は「いずれかの方向性に振り切れず中途半端」と思っていたが、各セクションで必要なムードに合わせてアレンジを変えていると認識すると納得がいった。以前の僕はまだまだ聴き込みが足りていなかったのかもしれない。または聴きすぎて俯瞰して見れなくなったことで気付けなかったことがあったのかもしれない。時間を置いて改めて向き合うことは大切だと実感した。
本作への印象が変わった要因としてもうひとつ考えられるのは、2024年に入ってからアキ・カウリスマキ(フィンランドの映画監督)の作品を観るようになったことが関係しているかもしれない。カウリスマキの作品の中で流れてくる俳優の演技や音楽のムードは、Arppaの楽曲にも通じるものがある。感情を安易に曝け出さず淡々としているけれども、実は情熱はある、といったかんじ。そういった「フィンランド的」要素のひとつなのかも、と認識してから本作と向き合うと、本作はフィンランド的要素と米・英のインディーロックの要素を融合させた得難く魅力的な存在だという印象を受けた。
以上の理由で、僕は本作が好きになり、年間ベストにも選ぶこととなった。歌も音もクセが少なく非常に聴きやすいので、フィンランド音楽の入門としてもオススメしたい作品。
Auringonliitto『Kaikki jäljet』

Auringonliittoは、ヘルシンキで結成された6人組インディーロック・バンド。2019年にデビュー。本作は3rdアルバム。
とにかく多彩なアルバム。リードボーカリストが三人おり、(AuringonliittoのSaara LampelaとPaul Sainio、ゲストボーカリストのOnni Rajaniemi)三者それぞれ全く違った魅力を持っているのが大きいだろう。編曲の方向性も曲ごとに大きく異なる。Leonard Cohen、Joni Mitchell、Chicago、Area、ABBAなどなど、想起させる音楽は様々。あらゆる要素を貪欲に取り込みスタジアムロック化した音が素晴らしい。例に挙げたのは70年代のロックばかりだが、実際に提示された音は限りなく「現行」を感じさせる音だ。爽やかで、エネルギッシュで、美しい、大きな音楽。そういった点で、Arcade FireやBlack Country, New Roadに近いものを持ったバンドだと思う。
Bad Jesus Experience『Ovat muistojemme lehdet kuolleet』

Bad Jesus Experienceは、ヘルシンキとタンペレを拠点に活動する4人組のハードコアパンク・バンド。2009年に結成し、2010年に1stアルバム『I』でデビュー。本作は5thアルバム。
難しいことを考える暇を一切与えない音楽というのが少なからず存在するものだが、Bad Jesus Experienceは、まさにそのタイプの音楽だ。Merzbowを聴いているときの爽快感に近い、耳をつんざくギター、演者がドラムセット諸共ぶっ壊れるんじゃないかってくらい叩きまくるドラム、歪みまくったゴリゴリのベース、そしてVivisektioにも通じる、どの楽器よりも存在感のあるがなるボーカル。それらがひとつになったときのアンサンブルがあまりにも凄まじくて笑ってしまうのだが、そうこうしている間に本作は聴き終わってしまう(本作の総収録時間は9分22秒)。
そういった一連の音とアルバムの流れが、ただただ最高なのだ。ここに必要な言葉は「格好いい」の一言に尽きるだろう。僕はハードコアパンクはそのようなタイプのものを好む傾向があるので、彼らに出会えたことを嬉しく思う。本作があまりにも良かったのでBandcampで全作品大人買いしてしまうほどにこのバンドが好きになった。それぐらい強烈なインパクトがある作品だ。
Circle of Ouroborus『Lumi Vaientaa Kysymykset』

Circle of Ouroborus(以下CoO)は、タンペレ出身のブラックメタル・デュオ。2004年に、Atvar(全楽器の演奏)とAntti Klemi(ボーカル、作詞)の不動のコンビにより結成。多作家で様々な形式の作品を発売しているが、本作は23thアルバム。
たまらんです。CoO、どうも放っておけない存在なんだ。2022年に出したアルバムもすごく良かったので年間ベスト記事で感想を書きたかったんだけど、残念ながら選外となってしまったのだ。今回50作品選べるようにしたのは、CoOの選外対策といっても過言ではない。
CoOは基本的にどのアルバムも「だらっと」している。ブラックメタルならではの緊張感や疾走感の要素は大分薄め。だらっとゆったりしたリズムで曲が始まり、だらだらと7分~9分くらいの尺を使って気の長い時間間隔で曲が進行し、だらっと終わる。以上が、僕が持つCoOに対しての印象である。
こんな風に書くとただただだらしないだけの音というイメージを持たれてしまうかもしれないが、CoOのその「だらっと」したところに惹きつけられるのだ。聴き初めた当初はよく分からなかったのだが、冒頭に書いた通り、どうも放っておけない存在だった。一度聴いたら忘れないほどインパクトがあったのだ。繰り返し聴いていくうちに、これはローファイなオルタナティヴロックを聴いている感覚に近いのだと思った。だらしなさが荒々しい音と共存することで、他のブラックメタルバンドには湧くことのない「愛着」が湧いてくるのだということに気付いたときには、僕にとって大切なバンドとなっていた。
本作のだらけ具合も安定している。しかし本作はだらしないだけでなく、とてもカッコイイと思う。特に長々と繰り広げられるギターソロ、長い間奏終了直後の不協和音など、1曲7分~9分の中で、それらの旨味がたっぷり詰め込まれている。テンポが早くて凶悪でシリアスなブラックメタルを聴きまくって「そろそろ違うテイストのものを…」と思った方に是非聴いてみて欲しいアルバム。
Elsi Sloan『Pakko muuttua』

Elsi Sloanは、ヘルシンキを拠点に活動するシンガーソングライター兼女優。2018年にシングル『Mitä minä olen sinulle?』でデビュー。本作は1stアルバム。
この記事で選んだ50作品の中で最も「よくわからないけど凄い」アルバムだ。よくわからないまま聴き終わってしまうのだけれど、「なんか凄かったな」という後味がじわっと残っていて、しばらく経つとまた聴きたくなり、もう一度トライしてみてもやっぱりよくわからない。でも確実に前回聴いたときより凄みが増してるし好きにもなっている気がする…みたいなことを、本作とはおよそ1年間繰り返してきた。
どういった要素がよくわからないことに繋がっているのかこの機会にじっくり考えてみたのだが、気付いた二つの要素について書いていきたい。
まず一つ目は曲にある。本作の主となるジャンルはエレクトロ/アートポップなのだが、どの曲も気持ちよくポップとは言い切れない捻くれ具合…というよりElsi Sloan独自の癖やノリのようなものが強く反映されているので、「聴きやすいポイントはあるけど…ちょっとよくわからん」といった状態になる。中村佳穂の『NIA』を聴いたときの感覚に近いかもしれない。楽器を好きなように弾いていたらふわっとフレーズが降りてきた素材をもとにノリで作曲した(ように聴こえる)かんじ。この感覚は、慣れてしまえば作者独自の持ち味として楽しむことができるのだが、その領域に到達するまでにはそれなりに繰り返し聴いていく必要があるだろう。正直、僕はまだその領域に到達していない。
二つ目はアルバムの構成だ。これが一番「わからない」に繋がっているのだと思う。構成をざっくり解説すると、序盤は比較的聴きやすいエレクトロポップ曲が並び、中盤から3曲連続でスポークンワードのトンネルに突入し、トンネルを抜けた終盤は序盤のエレクトロポップな情景は跡形も無くなり、フォークなのかなんなのか、謎多きアレンジの楽曲によって終幕に至る…といった流れになっているのだが、中盤のスポークンワードのゾーンが聴き始めた頃はひたすら謎が増すばかりで、集中力を欠いてしまって気付いたら聴き終わっていたなんてことがよくあった。何度も聴いていくとアンビエント的に楽しむことができるし、スポークンワードのトンネルを抜けて終盤のセクションに切り替わる瞬間の快感を掴めれば、一気にアルバム全体を楽しめるようになる。実は終盤の曲は特に良いのだ。しかしこれも一つ目と同様、魅力に気付くには何度も聴いて感覚を掴んでいく必要がある。
わからない理由を色々と書いたけれど、本作はわかりにくい内容だが「わかるまで(ちゃんと「好きだ」と思えるまで)聴き続けたい」と思わせてくれる作品だというのを伝えておきたい。長きに渡って楽しめる作品というのは、持ち味を簡単には味わせてはくれないものだ。『Pet Sounds』や『Blonde』がそうであるように。その持ち味に少しでも気付けたときには、他では味わうことの難しい、本作ならではのかっこよさを感じ取ることができるだろう。僕はそれを少しだけ感じている。まだまだ、一番美味しいところに辿り着くまでにはほど遠いのだ。
Ēlūcescentia『Vuoret Jotka Laskeutuivat Taivaasta』

Ēlūcescentiaは、ユヴァスキュラを拠点に2020年に結成された4人組のバンド。本作は1stアルバムにしてデビュー作。
どのジャンルにも当てはまらないバンドというのはかっこいいものだ。ぱっと思いつくのだと、Ulver、Boris、CMX、Mr.Childrenあたり。彼らは活動時期によって音楽性が極端に異なるし、ひとつの曲の中ででも、あらゆる要素を織り込んでいて大本となる影響源が辿りづらかったりするバンドだ。しかしそのような姿勢や楽曲こそが彼らの個性であり、孤高の存在となっている所以なのだと思う。
Ēlūcescentiaもまた、ひとつのジャンルに当てはめるのが難しいバンドだ。ギターロックを前面に押し出したうたものバンドというのに間違いはないのだが、角度を変えて眺めてみるとさっきまで見えていたものと全然違った一面が見えてくるので、音楽性を一言で説明するのは難しい。敢えてジャンルに当てはめるならポストメタルになるのかもしれないが、僕はメタルよりも先に、90年のネオサイケデリアっぽい印象を受けた。The Verve『A Storm in Heaven』やSlowdive『Just for a Day』などだ。これら2作は、Ēlūcescentiaの音楽性とかなり近い。そこにUnholyや初期KatatoniaなどのデスドゥームやDuster的スロウコア要素を組み合わせ、消しゴムで消えかけたLô Borgesのような儚い歌を乗せたのがĒlūcescentiaの音楽と言えるのではないだろうか。やはり一言では説明ができず、長くなってしまった。
このように、Ēlūcescentiaはあらゆる要素を取り入れたバンドなのだが、本作『Vuoret Jotka Laskeutuivat Taivaasta』曲によって受ける印象も微妙に異なる。その上でアルバム全体として見ると音楽性は統一感のとれたものになっていて、「ただただダウナーな楽曲が揃ったスペースロック・アルバム」として纏め上げているところに、かっこよさを感じている。何より楽しいのは、聴く度に新しい発見があることだ。彼らは一筋縄ではいかないバンドなので、聴いたときの自分のモードやインプットの違いなどによって、印象は変わっていくだろう。僕がこの感想を書くまでに感じた印象もほんの一面でしかないだろうし、今後も時間をかけて、彼らの別の一面を見つけていきたい。
Haamusoittajat『Yhteytys』

Haamusoittajatは、オウルにてOlli Nikkinen(ボーカル、ギター、ソングライター)を中心に結成されたフォークロック・バンド。2020年にEP『Aikojen pyörteissä』でデビュー。本作は1stアルバム。
爽やかな木漏れ日サイケデリックフォークを求めている方には是非本作を聴いてみて欲しい。Yo La Tengo、Belle and Sebastian、Kings of Convenience、『Schmilco』期のWilco、Heron、『Eureka』期のJim O'Rourke辺りが好きなら高確率で気に入るはず。
僕は本作に出会ってからというもの、毎日のように部屋で流している。特に朝。本作のジャケットのような清々しい天気であれば、我が家のスピーカーから真っ先に流れ出すのは本作。すっかり朝のBGMの常連だ。もちろん朝に限らず、いつどんな状況で聴いても心地よい雰囲気を作ってくれる。そういった点で僕の中ではGal Costa and Caetano Velosoの『Domingo』と近い立ち位置なのかもしれない。
本作はとにかく飽きない。各メロディや構成が良い具合に薄味で覚えにくいからか、何度聴いても初めて聴いたときの「おっ!良いねぇ」という感覚が消えることがない。その上でアルバム全体の尺がほどよく短い(32分)ので、気軽に気長に楽しむことができる。大推薦盤。
Ihmissudet『Yö Saapuu』

Ihmissudetは、ヘルシンキを拠点に活動しているフォークロック・バンド。2019年にシングル『Yö saapuu』でデビュー。本作は1stアルバム。
ディスクユニオンの独特な匂いが好きだ。あの匂い、レコード屋さんに通っている方にはおなじみだと思うけれど、音楽に興味のない方が嗅いだらどのような印象を持つのだろう。あまり良い匂いとは言えないのかもしれない。しかし、こちとら十何年もあの匂いと接しているのもあって、どうにも安心感とワクワク感を伴った存在となってしまっている。
Ihmissudet『Yö Saapuu』を聴くと、ディスクユニオンの匂いを思い出す。音楽性が、Richard Thompson周辺の英国フォークロックに近いからかもしれない。本作を聴いていると、レコード屋さんで全く知らない70年代の超かっこいいフォークロック・バンドを見つけてしまったときのような嬉しい気持ちになる。
前半は(プログレッシブ)ロック寄りで攻撃的、後半はフォーク寄りで郷愁的。曲が進むごとに段々と雰囲気が寂しいものに変化していく構成もすごく良い。全体通してOpeth『Damnation』にも近い。Mikael ÅkerfeldtがRichard Thompsonをプロデュースしたらこういう内容になるのだろうかといった音楽性で、いずれも好きな僕としては好きにならない理由はなかった。各パートの音はかなり格好よく録音されているのだが、CDは作っていないので高音質で聴けないが残念。いずれBandcampで販売して欲しいところ。
Ikiranka『Sydänmaa』

Ikirankaは、「フィンランド民謡やオリジナル曲とエレクトロニクスの融合」がコンセプトのヘルシンキ出身の器楽トリオ。バスクラリネット+エレクトロニクス+リード&パイプオルガンという編成。2020年に1stアルバム『Ikiranka』でデビュー。本作は2ndアルバム。
本作の音楽性をジャンルで当てはめるならアンビエントジャズになるのだろうか。エレクトロニクスが活躍したエクスペリメンタルな場面もあるけれどカオティックな方向には行きすぎず、Floating Points, Pharoah Sanders and the London Symphony Orchestra『Promises』ほど壮大にもならない、聴きやすさの丁度いいラインを維持しつつ、のどかに繰り広げられるセッションが心地よい。聴いているとなぜか、タル・ベーラ監督の映画のワンシーンを思い出す。『倫敦から来た男』で延々と繰り広げられるアコーディオンのセッションのシーンとか。狂気とも憩いともとれる不思議な時間にいつまでも浸っていたい、そう思っているうちに聴き終わってしまう尺具合も良い。
Irvikuvotus『Arvet』

Irvikuvotusは、タンペレ出身のブラックメタルバンド。2014年結成。2017年に1stアルバム『Musta siemen』でデビュー。本作は2ndアルバム。
一昨年からブラックメタルの世界に足を踏み入れ、昨年からはフィンランドのブラックメタル沼に嵌り、今ではすっかり、自分の生活の中で当たり前のようにブラックメタルが存在するようになってしまったことに、今さらながら驚いている。
ブラックメタルを聴き始めた頃はプリミティブ寄りのものを好んで聴いていたのだけれど、最近はもっぱら、フォークやダークアンビエントなど、別ジャンルの要素を取り込んだ新鮮な印象を持たせてくれるタイプのものを中心に聴いていた。
そういった中で本作を聴いた。良い。これぞブラックメタル。しっかり音質が粗くて、しっかり暴れてて、しっかり喧しい。ボーカルが「何か」になりきっている感じもなく、自分という人間らしさを曝け出しているかのように歌っているところも好きだ。
全体を通して感じたのは、結局自分はシンプルなブラックメタルが好きなんだなということ。本作に新鮮な要素は特にないのかもしれない、しかし聴いていると、ブラックメタルを聴き始めた頃の感動が蘇る。まさに初心に帰ってくるかんじだ。原点に立ち返りたいと思ったときに、本作を聴くのだろう。
Ismo Alanko『Me olemme ihme』

Ismo Alankoは、ケラヴァ出身のシンガーソングライター。1979年より音楽活動を開始し、Hassisen KoneとSielun Veljetという、ニューウェイヴ/ポストパンクの最重要バンドのフロントマンとして活動。1990年からはソロ活動を開始し、音楽活動開始から45年を経てもフレッシュな作品を生み出し続ける「生ける伝説」である。本作は、ソロ名義としては8thアルバム。
Ismo Alankoは62歳で本作を生み出した。62歳…とても62歳の方が作ったとは思えない力強さ、勢い、挑発が伴った作品だ。例えば、本作の空気感に近いものを持った今をときめくBlack Midiというバンドがいるが、25歳前後の彼らが生み出す曲と同じくらい、本作にはエネルギッシュな楽曲がたくさん収録されている。Tom Waitsとか、Neil Youngとか、David Bowieとか、60歳を超えてもなおクレイジーな作品を生み出し続ける音楽家というのは稀に存在するが、Ismo Alankoもその一人なのだろう。
本作の音楽性を一言で表すなら、Tom WaitsとHenry Cowを取り込んだElvis Costelloのようなかんじで、捻くれてジメッとした一面がとても美しく、ポップに描かれている。暗いのに暗くないという矛盾。音質もすごく良くて、特にリズム隊の音がとても格好いいのもあって、リズムやビートが先行して耳に残る曲が多い。ジャケットはかなり人を選ぶデザインだが、Ismo Alankoの捻くれた、それでいて一度聴いたら忘れない訴求力を持つ音楽性にバッチリはまってはいる。ジャケットを見てちょっと…と思った方、お気持ちお察しします。ただ、これは傑作ですよ。是非聴いてみて欲しいです。
Jäkälä『Silmieni sivellin』

Jäkäläは、desibeli.netに掲載されているプロフィールによれば「詩人・アフォリストのEsko Lovénと音楽家・作曲家のPekka Kaksonenからなる、静かで平和な音楽を創り出すデュオ」。本作は1stアルバムにしてデビュー作。
年間ベストアルバムを選ぶにおいて、このアルバムを外すわけにはいかなかった。なぜなら本作は、僕にとって重要な存在である山本精一と頭士奈生樹に最も近い音楽からだ。
僕は18歳のときに羅針盤及び山本精一の音楽と出会い、衝撃を受けた。後を追うように渚にてや頭士奈生樹を知り、特に頭士奈生樹を猛烈に好きになった。21歳くらいまでの間、本当に毎日、彼らの音楽に触れていた。そしていつしか、僕は初めて聴いた音楽を好きになりそうかどうかの基準として、二人の存在が物差しになっていた。今現在は彼らの音楽を熱心に聴く機会は減ったけれど、久しぶりに聴き返せばそらで歌える。そして僕は、無意識のうちに「山本精一・頭士奈生樹的なもの」を追い求めている。彼らの音楽が血肉や「ツボ」になっているのだ。
冒頭で書いた通り、本作は山本精一と頭士奈生樹に最も近い場所にいる音楽と言っても過言ではないだろう。なんとも控えめで、必要最低限の打ちっぱなし打ち込みドラム、昔バンドをやっていたときにボーカルが送ってくれた、アンプを通していない生エレキギター弾き語りのボイスメモを思い出すシャリシャリのアコースティックギター、アトモスフェリックブラックメタル好きにはたまらない森林シンセ、僕にとっての神様・Jerry Garciaが編み出した、天の羽衣のようなディレイがかったクリスタルギター、そして最大の魅力である、感情や抑揚をとっぱらったボソボソっとささやく少し悲しげで柔らかな歌。
これはひょっとして…いや完全に、頭士奈生樹『現象化する発光素』であり、山本精一『童謡』ではないか!それでいて違った面もある。どこか「外」を感じさせるところとか。山本や頭士の音楽には「家感」がある一方、本作からは青空、雲、湖、木を連想させるような音が散りばめられている。それにしても、それ以外は物凄く近い音楽だと思う。聴いたときに心が「ジワァ」っとする感じとか、すごく近い。僕は本作を平日の15時、仕事の小休止のタイミングでよく聴くんだけど、おやつ食べながら聴いてるとすごく「ジワァ」っとくるのだ。それはまるで、クソ野郎な自分を包み込んでくれるような状態なのだけれど(その体験は横沢俊一郎の『ハイジ』を聴いたときにもあったなぁと今思い出した)、なんとも居心地がいいので仕事に戻りたくなくなるくらい。「切なさ」という表現が一番近いんだろうけど、少しだけ違う…そういう特別な体験ができるという点でも、山本精一や頭士奈生樹と共通していた。
音自体はこじんまりと小さくまとまった音楽なのかもしれない。しかし聴いたときの心への影響力は、計り知れないほど大きい。長く聴き続けるほど心に食い込んでくるのだろう。僕はもう、本作を手放すことはできない。なので、できればBandcampでの配信か、レコードもしくはCDを販売して欲しい。これほどの作品がサブスクだけの配信という状態は何とも勿体ないし、自分の手で、良い音で、側に置いておきたいのだ。
Jenna-Marie Laine『Vapaapudotus』

Jenna-Marie Laineは、トーマヤルヴィ出身のシンガーソングライター。フォークロック・バンドTanssiva Karhu(ボーカル)とパンクデュオiso pusu(ドラム&ボーカル)でも活動。本作は1stアルバム。
2021年のMaxine Funkeのレビューで、Nick Drake『Pink Moon』の空気感に近い作品を常に探し求めていると書いているのだが、Maxine Funke以降、そのような作品に出会う機会はなかった。しかし本作と出会い、僕の「Pink Moonの子どもたち」リストは2年ぶりに更新されることとなった。
本作は良い。なぜなら聴く機会がとても多いからだ。一人でいるときはもちろん、誰かと一緒にいるときでも。「FloristがAnne Briggsを弾き語りでカバーした」かのような曲に溢れたアルバムを流して嫌がる人なんてのはそうそういない。なので、流す音楽に迷った時はとりあえず本作を流している。そうすると素敵な空間が出来上がるのだ。どのようなシチュエーションにも順応してくれるところも魅力。朝でも夜でも合う。さらに1曲1曲が良い意味でそこまで印象に残らないので、何度聴いても飽きないのも大きい。
このように、気軽に向き合えるという観点で魅力が満載なので、本作は何度も何度も聴いた。「聴いた」というよりは「流した」と表現したほうがいいかもしれないけれど。いずれにせよ2023年の僕の生活に最も浸透した音楽作品のひとつなのは間違いない。これは恐らく僕だけでなく、多くの音楽好きの方にとっても気軽に楽しまれ、愛される作品なのではないだろうか。是非多くの方に聴いてもらいたい作品である。
Kaksonen『Universumin kuningas』

Kaksonenは、2005年に結成されたアーネコスキ出身のプログレッシブスラッシュ/スラッジメタル・バンド。本作は2ndアルバム。
僕が好きになるメタルの特徴は主に2点あって、1点目が「音が荒々しいこと」。2点目が「楽曲の構成や展開が凝っていて一筋縄でいかない、ドラマチックであること」。以上の2点を兼ね備えていれば大抵は好きになるが、どちらか1点が欠けているとイマイチハマらない傾向がある。
本作は、前述した2点がバッチリ兼ね備えられたメタルアルバムである。音は全体的に荒々しい。荒々しいけど、Fugaziみたいに一歩引いて冷静に丁寧に荒々しい音を出しているかんじがクール。構成も、全曲も非常に凝っている。特に素晴らしいのは後半3曲。いずれも7分以上の(5曲目『Kuolema』に至っては10分以上ある)長尺曲だが、長さを感じさせないドラマチックな展開が素晴らしい。静かなセクションでは爆音出す寸前のMogwaiを思わせるような演奏をしたりと、所謂メタルに留まらない要素をさり気なく入れつつ、トータルではちゃんと「(プログレッシブ)スラッシュメタル」しているところに彼らの強い拘りであり、魅力だ。いずれの曲も展開が凝っているので一筋縄ではいかないが、どの曲でもしっかり耳に残るポップなサビらしいサビを用意してくれている親切さも好き。
決して明るいアルバムではないけれども、その暗さには極寒の中一面真っ白の雪に囲まれたときの孤独感に通じるものがあり、そこはフィンランドから生まれた音ならではのものなのかもしれない。
Kalervo Riviera『Trapetsia ratakiskoilla』

Kalervo Rivieraは、東ヘルシンキを拠点に活動する3人組のバンド。ギター&ボーカルのVille Laamanen (Kalervo Rivieraという名義もあるらしい。Bon Joviみたいなものか?) を中心に結成され、2023年にシングル『Sopivat oireet』でデビュー。本作は1stアルバム。
晴れた日の朝、特に冬の朝にピッタリなAOR寄りのインディーロックといった感じで、ミツメの『Ghosts』やMichael Franksの『Sleeping Gypsy』が好きな方は気に入るかもしれない。ゲスト鍵盤奏者Harri Taittonenによるエレピが渋くて格好いい。バンドのお洒落な音と、無骨だけど愛らしいボーカルのミスマッチが寧ろクセになるし、それこそがKalervo Riviera独自の旨味なのだろう。
本作を聴いていると、2023年のあらゆる出来事が走馬灯のように蘇ってくる。朝から発熱して病院行って、帰宅後に静かな部屋の中で初めて聴いた3月、朝からコインランドリーに行って、帰宅後に薄暗い部屋で聴いた雨の日の5月…。何てことのない出来事もKalervo Rivieraの曲と共にあることで素敵な出来事だったと思えてくる。日常生活を彩る、特別なサウンドトラックだ。
KAUAN『ATM Revised』
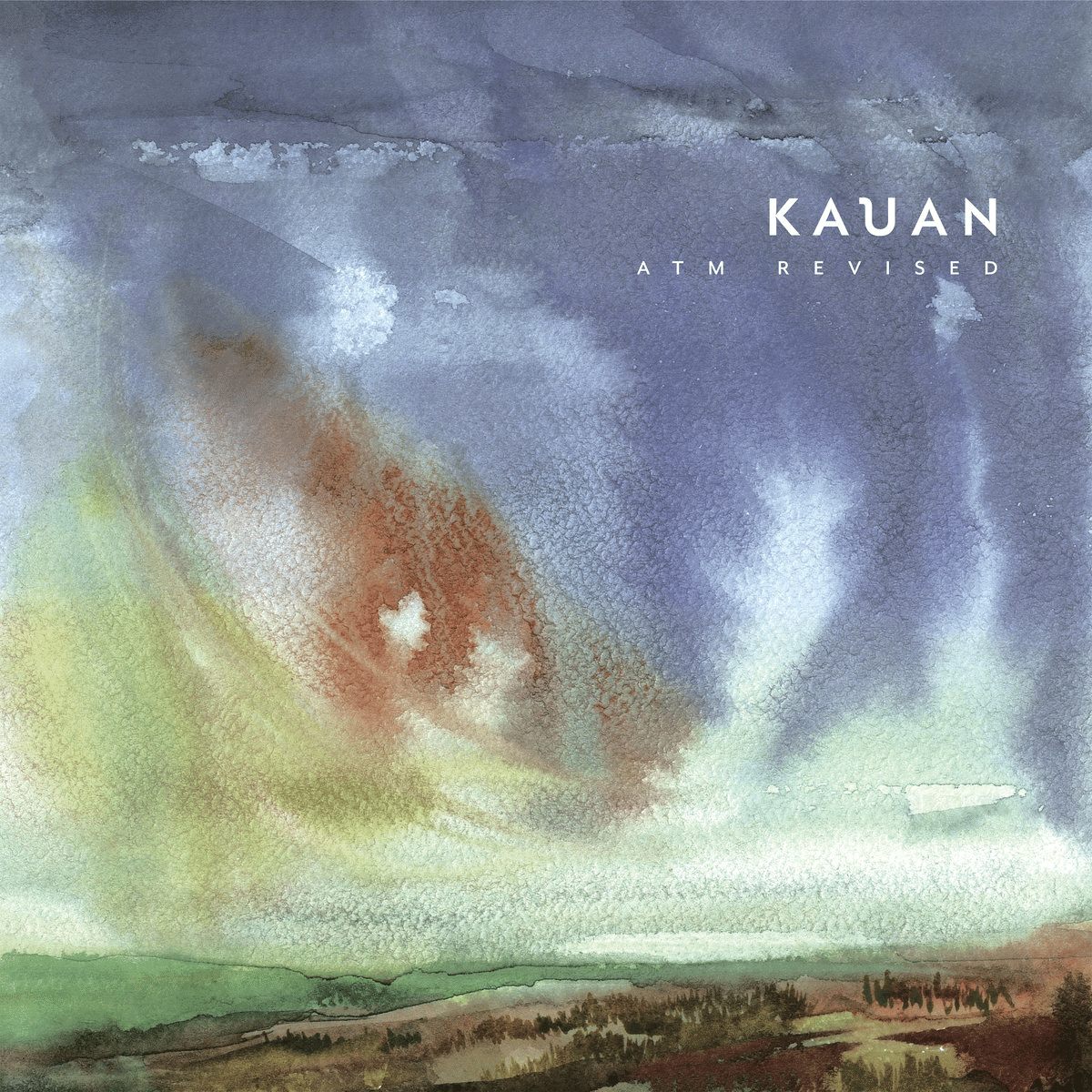
KAUANは、ヘルシンキを拠点に活動する3人組のバンド。2005年結成。本作は、2009年に発売された3rdアルバム『Aava tuulen maa』を2023年時のバンド編成で再構築した作品である。
人はどういうタイミングで音楽に没入したくなるのだろうか。そもそも没入というのがどのような状態なのかも人によって認識が異なるだろう。じっと静かに音楽に身を委ねている状態なのか、それとも我を忘れて舞い上がっている状態なのか。
僕はと言えば、まぁ四六時中音楽に没入しているようなものなのだが、「没入=音楽の世界にのめり込み現実逃避している状態」という意味なのであれば、少し落ち込んでいるときに没入したくなることが多い(この「少し」というのが重要。もの凄く落ち込んでいるときは音楽すら聴けなくなるのだ)。
物事がうまく進まなかったり、失敗したり、なんとなく寂しくなったり…ほとんどの場合原因はわかっていて、解決できるものだったりする。ただ落ち込んでいるときというのは、現実から目を背けたくなるものだ。僕はそういう時、音楽に没入する。当然、どんな音楽でもいいわけではなく、適したものを選んで聴く。
KAUAN『ATM Revised』は、2023年、そして2024年に、音楽に没入したくなるときに最も多く聴いたアルバムだ。本作で聴ける音は、とても冷たい。聴いていると、手がかじかんだときの感覚を思い出す。しかし同時に、とても美しい。本作の要となるピアノとエレキギターが生み出す旋律がそう思わせるのだろう。
僕は本作の音と、映画『レヴェナント: 蘇えりし者』で見られる雪山の景色を重ねている。あの映画で度々登場する雪景色は、自然の恐怖や厳しさと、気の遠くなるような美しさが共存する情景だった。KAUAN『ATM Revised』を聴いていると、あの果てしない雪道を孤独に歩いているような気分になる。それが辛いかというとそうではなく、曲が進んでいくごとに、その状態が悪くないと思えてきて、最終的には落ち込んでいたことをちょっと忘れて、落ち着きを取り戻していたりするものだ。
KAUAN『ATM Revised』は、MONO『You Are There』やUlver『Shadows of the Sun』に通じる面がありつつも、いずれの作品にもない、ただただKAUANでしかないオリジナリティが存在する作品だ。このバンドは、歌詞がフィンランド語でありながらメンバーの中でフィンランド人が一人もいない。唯一のオリジナルメンバーであるAnton Belov(ギター、ボーカル、キーボード、プログラミング)はロシア出身。Alina Belova(キーボード、バッキングボーカル)とAnatoly Gavrilov(ヴィオラ)はウクライナ出身だ。歌詞にフィンランド語を採用したのは、その響きの良さと、マイナー言語であるフィンランド語の意味が聴き手の音楽解釈に影響を与えないからだという。そういった、国にも言語にも囚われない姿勢こそが彼らのオリジナリティの源であり、音として表れているように思えてならない。
Kaunis Kuolematon『Mielenvalta』

Kaunis Kuolematonは、2012年にキュメンラークソで結成された5人組のメロディックドゥーム/デスメタル・バンドである。本作は4thアルバム。
Mr.Childrenが1996年に発売したアルバム『深海』に、『ゆりかごのある丘から』という曲が収録されている。ゆったりとしたメランコリックな曲で、演奏時間は8分53秒とかなり長尺。僕はこの曲が、『深海』を初めて聴いたときから大好きな曲で、これだけ長い曲にも関わらず、8分とは言わず50分まるごとこういう曲しか入っていないアルバムを作ってくれればいいのにと思っていた。
そのような僕の願いは、2023年の冬に叶うことになる。しかもそれはMr.Childrenではなく、フィンランドのメタル・バンドKaunis Kuolematonの新譜を聴くことで叶ってしまったのだった。
Kaunis Kuolematon『Mielenvalta』には、じわりじわりと進んでいく構成の中で、海底へと沈み込むようなギターのフレーズを回復の兆しのないメンタルで展開させていくような曲が収録されている。その雰囲気はまさに『ゆりかごのある丘から』そのものだった。加えてKaunis Kuolematonにはとてつもない轟音とメロディックデスメタル由来のリフ、悲哀のデスボイスまで持ち合わせている。これはもう、好きになる要素しか揃っていなかった。
Kaunis Kuolematonは曲のスピード感が独特で、所謂ドゥームメタルほど遅くはないけれどメロデスでよく見られるような疾走感も(一部を除いて)ほとんど無い。それでいてドゥームとメロデスの要素を兼ね備えていて、結果メロディックなフューネラルドゥームに近い音楽性になっているところも非常に好きなところだ。デスメタルの領域にいながら、その独自の音楽性によって絶妙な立ち位置にいるバンドであることが伝わってくる作品だと思う。
Korgonthurus『Jumalhaaska』

Korgonthurusは、2000年にヘルシンキで結成された4人組のブラックメタル・バンド。2度の解散を経て2017年に再々結成。本作は4thアルバム。
昔から、長い曲が好きだ。ここで言う「長い」は、6分以上あるかないかが判断基準となる。僕が初めて「長いな」と意識した曲って何だったっけ…多分、14歳の頃に聴いたNirvanaの『Endless, Nameless(6分43秒)』か、Janis Jplinの『18 Essential Songs』に入っている『Ball and Chain(8分13秒)』だったと思う。その当初から、長い曲に対して「格好いいな」と思っていた。他の曲よりも長い時間、作者の生み出した世界に浸れることにも惹かれていた。長い曲に惹かれる傾向は僕の音楽の趣味に大きく影響した。プログレやジャムバンド、ノイズやインプロの長尺曲を聴き漁ったり、iTunesにCDをインポートしたときに演奏時間が10分以上の曲があるとワクワクするようになったりなど、「行くとこまで」行ってしまったのである。
そういった僕の経験は、メタルを聴く際に役に立っているように思う。僕が意識的にメタルを聴き始めたのは2020年からなのだが、数年聴いてきた中での印象だと、メタルは長い曲が多い(僕が無意識にその手のものを選んで聴いているのもある)。そのような曲に対して割りとすんなり受け入れることができた、もっと言えば最高!と思える機会が多いというのは、やはり僕が元々長い曲を好んできたことが大きいからだと思う。
さて、そんな僕がここ数年で最も「長い曲好きでよかったあああ!!」と思えた作品が本作、Korgonthurus『Jumalhaaska』である。本作は収録曲数は4曲ながら、いずれの曲も11分以上あり(『Marraskehrä』に関しては16分)、長い曲だけで構成されたアルバムだ。そしてどの曲も非常に喧しく暴力的で、ボルテージが最大値の状態がほとんどのセクションで維持される。そういった中で構成は相当に練られており、ブラックメタルの闇の中でハードコアやドゥームへと彷徨いながら結末(真っ黒い絶望)に辿り着く流れが凄まじく格好いい。
暗い、長い、喧しい。人によっては受け入れられない音楽の三大要素が揃っているのかもしれないが、僕にとってはあったら嬉しい音楽の三大要素。なので本作は終始暗いのに、聴き終わった後の僕は謎の爽快感を得て、清々しい表情になっている。このなんとも特別な爽快感は、14歳の頃に『Endless, Nameless』を聴いていなければ得られなかったはず。あの時の経験を通して本作を好きになったことを嬉しく思う。
Lau Nau『Aphrilis』
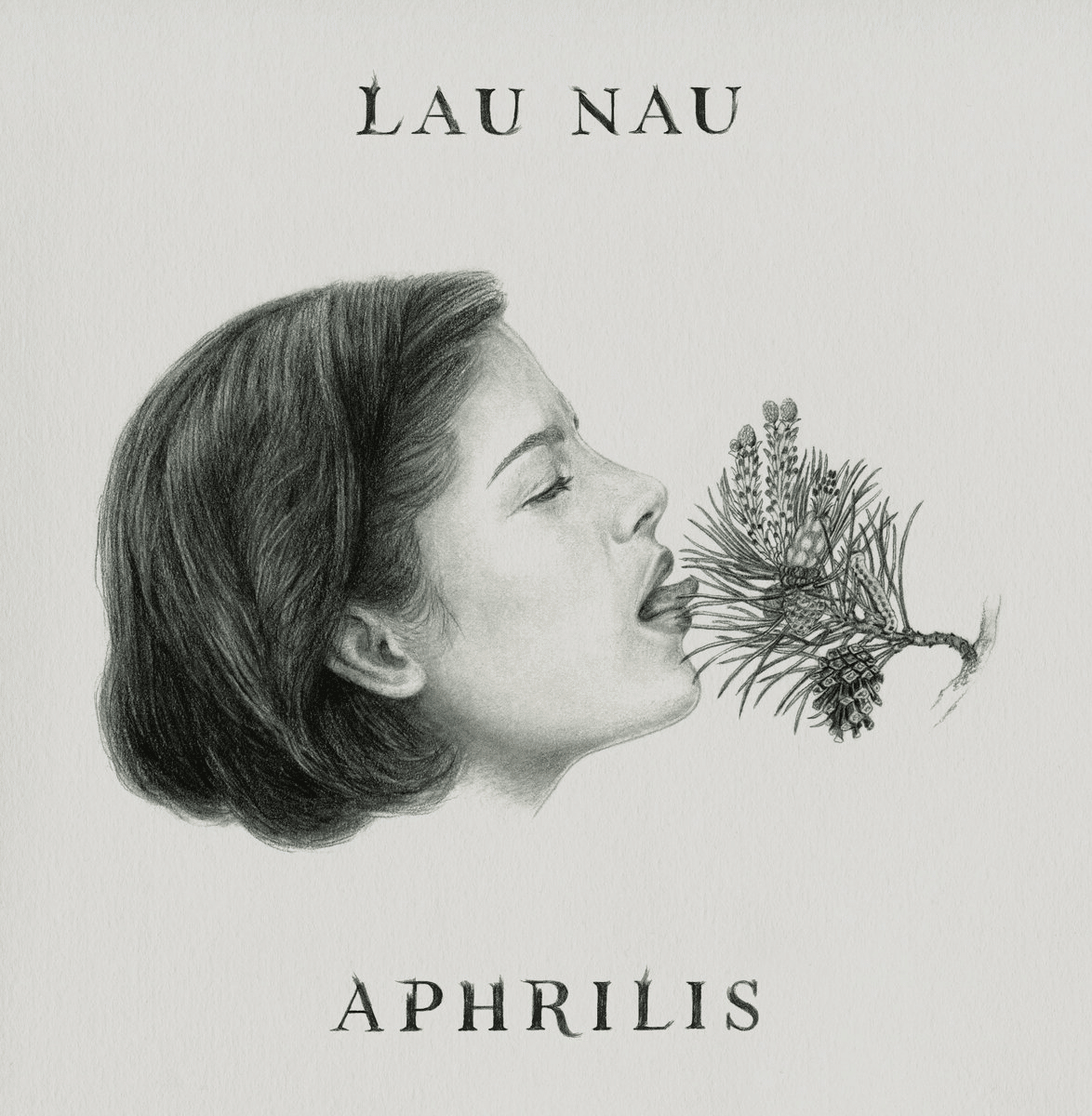
Lau Nauは、ウーシマー出身のシンガーソングライター。2005年より音楽活動を開始。作品ごとに音楽性が変化するのが特徴で、関連するジャンルはフォーク、ドリームポップ、アンビエント、ドローンなど多岐にわたる。本作は10thアルバム。
発売当初に聴いたときは、そこまでピンときていなかった。本作はストリングスを大胆に取り入れたうたもの作品で、そのコンセプトが終始一貫しているのもあってアルバムとしての完成度は非常に高いと感じた。けれども、ストリングスの力強さに圧倒されて、一度聴いただけでお腹いっぱいになってしまったのだ。「凄い作品だとは思うけど、日常的に繰り返し聴くのはしんどいかも」というのと、「自分の中での本作の立ち位置がイマイチ見えてこない」というのが第一印象で、2、3回聴いて以降、本作の存在すら忘れかけている状態だった。
変化が訪れたのは2024年1月某日のこと。僕は日暮里にあるカフェ「HAGI CAFE」でお茶をしていた。居心地の良い空間でコーヒーを飲み、チーズケーキを食べていると、何やら素敵な音楽が流れてくる。あまりにツボだったので思わずShazamしてみると、オーストラリアのシンガーソングライター、Tamas Wellsの『The Crime at Edmond Lake』という曲だった。
雨に濡れたら一瞬で消えてしまいそうな儚い歌と切ないギター。それらは決して活力に溢れているわけではないが落ち込んでもいない、聴いていると心が温まる音楽だ。歌も楽器も、一音一音とても人懐っこく存在感があるのに、お茶をしているお客さんの会話を邪魔することなく、そっとその場に佇んでいる。
恐らく、お店の雰囲気に合うBGMを相当拘りを持って選曲しているのだろう。HAGI CAFEでは、前述のような印象を持たせる音楽が終始流れていた(余談だが、寺尾紗穂と手嶌葵の間に立っているような日本の女性シンガーソングライターであろう方の曲もすごく良かった。Shazamでは特定できず)。
そのような空間にいて、「あぁ、俺はこういう雰囲気の音楽が大好きなんだよな」と再認識すると同時に、「HAGI CAFEに合う音楽を探してみたら楽しいかもしれない」と思うようになった。
お店を出て帰宅すると、僕は「HAGI CAFEっぽい音楽」を探し、聴いた。先ほどのTamas Wellsに始まり、The Innocence Mission、冬にわかれて、Vashti Bunyan…。いろいろ聴いていく中で、Lau Nau『Aphrilis』の存在を思い出した。「あれはもしや、HAGI CAFEっぽい音楽かも?」と。1ヶ月ぶりに聴き直してみると、予想は見事に的中した。か細くも存在感のある歌、その声と弦で彩られた、包み込むようなアレンジ、時折聴こえてはいつの間にか姿を消している、シブすぎるエレキギター…。勝手ながら、絶対に合うからお店で流してほしいとさえ思った。僕がもし本作の存在を知らずにHAGI CAFEに行って、本作が流れていたら間違いなくShazamしていたことだろう。そして本作は、Tamas WellsやThe Innocence Missionのような「儚く切ない、それでいて温かい音楽」を求めるときの自分が聴きたくなるのだということに、ようやく気付くことができた。
聴き始めた当初、どうして本作の魅力に気付けなかったのかはわからないのだが、HAGI CAFEを通じて視点が変化し、ピンと来ていなかった音楽がピンと来るようになったのは幸運なことだと思っている。音楽って不思議で奥が深いんだよ、と誰かから教えてもらったかのような体験だった。
Laura Moisio『Vieras maa』

Laura Moisioは、タンペレ出身のシンガーソングライター。2011年に1stEP『Hyvä päivä』でデビュー。本作は5thアルバム。
今回の年間ベスト記事では順位をつけていないのだが、1位だけは心の中でずっと決まっていた。それが、Laura Moisio『Vieras maa』だ。
僕は2020年にフィンランド音楽を本格的に聴き始めて、Laura Moisioの存在はonechord.netというブログでわりと早い段階で知ることができた。初めて聴いたのは3rdアルバム『Laura Moisio』で、場所はフィンランドだった。旅行で滞在していたサーリセルカという村にあるホテルの部屋で、iPhoneのスピーカーで流しして聴いていたのはなんとも思い出深い。その後帰国してすぐのタイミングで4thアルバムが発売されたのだが、とにかく素晴らしいアルバムで。当時は年間ベストをやっていなかったが、もしやっていたら確実に選んでいたであろう作品だった。
僕はLaura Moisioの音楽とそれなりの期間向き合っていたため、本作発売前の時点で思い入れの深い存在になっていたし、本作には大きな期待を寄せていた。なので2023年2月3日金曜日にYouTube Musicで配信されたときは、ドキドキしながら聴いた。
アコースティックギターとストリングスの美しい調和、曲に「寄り添う」という言葉がこれほど相応しいことはないくらい1曲1曲への確かな音選びと丁寧な演奏がなされたバンドの音、そしてLaura Moisioが紡ぐ歌とメロディ。それらがひとつになった曲を聴いたとき、僕の胸はキューッとなるような、じんわりと切ない気持ちになる。そして同時に、どこまでも優しく、温かい気持ちに包まれる。
Laura Moisio『Vieras maa』は、僕の期待を大いに上回る内容だった。発売当初は2月の寒い日で、気付けば冬を越え春になり、夏になって、秋になり、また冬になって…本当に何回も聴いた。レコードとCDも買って、家での中でも外でも聴いて(早朝に、土手で朝日を見ながら聴いたのは僕の中で最も印象的な音楽体験のひとつ)、誰かといるときも聴いて、しばらく聴かなくなって、また聴いて、やっぱ良いなってなって…あらゆるフォーマットで、あらゆるシチュエーションで聴いた。2024年1月の時点で、本作への想いは聴き始めたときとは比べものにならないくらい深くなっており、今後もその想いは更に深く、強くなっていくことだろう。本作のような、聴き手の心にいつまでもそっと残り続ける作品を「名盤」と呼ぶのだろうなと、僕は思う。
Lempi Elo『Huojuvat puut』

Lempi Eloは、Lempi Elo(ボーカル、ピアノ)を中心に結成された6人組バンド。2020年に1stアルバム『Observatorio』でデビュー。本作は2ndアルバム。
まるでLaura NyroとGenesisとGrateful Deadが感情も展開も目まぐるしく変化するセッションを繰り広げているような音は、聴いていると摩訶不思議な絵巻物を眺めている気分になる。
うたものだし一見聴きやすい印象を受けるけど実際はKing Crimson『Lizard』と肩を並べるハードコアアルバムなはず。なのに不思議とBGMとして流しても違和感なくお茶の間に浸透してしまうのは、それはLemp Eloの包み込むような歌声やファゴットを筆頭にバンドの音がスタイリッシュに仕上がっているからなのだろうか。
聴くたびにほんのちょっと謎を残してこのアルバムは終わってしまう。だからこそ気になってもう一回、もう一回、と聴きたくなってしまう癖のある作品なのである。
Lintudisko『Elämä lymyilee』

Lintudiskoは、ユヴァスキュラを拠点に活動するシンガーソングライター、Mikko Juhaniによるワンマン・バンド。2021年にEP『Asumus』でデビュー。本作は1stアルバムで、全曲の作詞、作曲、編曲、演奏、ボーカル、プログラミング、レコーディング、ミキシングをMikko Juhani一人で手掛けている。
R.E.M.のMichael Stipeをより気だるくさせて感情表現を遮断したボーカルと、グランジの影響を強く感じさせるロックな音の組み合わせ…分かりにくい例えだけれど、本作はCMX(フィンランドの重鎮ロックバンド)の遺伝子を持った音楽という印象を受けた。特に『Rautakantele』あたりのCMXに近い。つまりCMXが大好きな僕にとって、完全にツボな音楽だ。全体的にかなりCMXっぽくはあるが、ボーカルの歌い方や楽曲から生まれるほんの少しの浮遊感と爽やかさはLintudiskoならではの魅力。それらが備わっていることで、むしろCMXより聴きやすくなっているのかもしれない。特に真新しいことをやっているわけではないけれど、どうも放っておけない、好きな音楽だ。この手の音が好きな方にはたまらないと思うので、是非聴いてみて欲しい。
Lupiinit『Lupiinit』

Lupiinitは、ハードコア・バンドVainoaのボーカル、Riku JunttanenとIso Autoのギタリスト、Aleksi Saastamoinenによって結成されたヘルシンキ出身のエクスペリメンタル・デュオ。本作は1stアルバムにしてデビュー作。
アルバム全体で存在感を見せるのはMONOの影響を強く感じさせるギター。そこにKlaus SchulzeやEinstürzende Neubautenなどのジャーマンアンビエント/インダストリアルやシューゲイザーのキラキラした世界観と、ボーカル(恐らくRiku Junttanen?)の強烈な金切り声がドロドロと溶け合う。
聴いているとまるでCocteau TwinsとDarkthroneを違和感なく同時再生しているかのような気分へと導かれる。僕はドイツのテレビドラマ『ダーク』に一時期ハマっていたのだが、あのドラマでお馴染みだった仄暗い曇天の日に本作を聴きたくなる。それは本作に「ドイツ的暗さ」を強く感じるからなのかもしれない。
Luut『Luut』

Luutは、2012年に結成された3人組のバンド。本作は1stアルバム。
本作がどのような音楽を封じ込めているのかを説明するのは難しい。様々なジャンルの影響を感じるものの、そのどれにも当てはまらないからだ。敢えて例えるなら、Leonard Cohenがポストロック的音進行でアトモスフェリックなジャムセッションを繰り広げているかのような音楽、となるだろうか。
収録曲全8曲はどれも所謂ポップソングのようなかっちりとまとまった形ではなく、敢えてセッションの余地を残しているように思える(インタビューによれば、実際ジャムセッションで作られた曲も収録しているらしい)。うたものだが歌は少なく、紆余曲折あるセッションの合間にボソッと聴こえてくるところが好きだ。
本作を聴いていると、コテージで夜な夜な繰り広げられる怪しげなセッションを覗き見しているような緊張感を味えると同時に、ほどよいセッション感がなんとも心地よく、いつまでも浸っていたいという気持ちになる。曲はどれも決して明るい曲調ではないが、夜聴くのにピッタリな音楽なので、一人で過ごしているときに、部屋を少し暗くして、お酒を飲みながらBGMとして流しても楽しい。
Maailmanpuu『Kaimalkuu』

Maailmanpuuは、4人組のプログレッシブロック・バンド。2019年に1stアルバム『Maailmanpuu』でデビュー。本作は3rdアルバム。
気持ちのいい音である。
特にドラムの音。ひとつひとつの音が粒立っていて、各パーツが叩かれる度に炭酸飲料を口に含んだときのシュワーって感覚に近いものを耳で味わっている感じ。これはThe MillenniumやJ.K. & Co.などの良質なサイケデリックポップを聴いているときと似た爽快感を持っていて、この感覚を味わうために本作を聴いていると言ってもいいくらい、良い音してる。
そのような音質を最大限活かせているのは、やはり本作の内容が良いからこそだろう。Bandcampに掲載された解説によれば「プログレ、アートロック、プログレフォーク、ジャズ、フュージョン、シンフォニックプログレなど、さまざまなジャンルを取り入れたアルバム」とのことで、実際それらの要素は各所で感じつつも小難しい印象はなく、とても聴きやすいプログレだ。曲はどれも長いが、長いからこそ気持ちのいい音にずっと浸っていられるので、プログレというよりもアンビエントを聴いているような感覚に近い。
プログレを全く聴いたことがない人にもオススメしやすい内容だと思っているので、気になる方は是非、本作の音を浴びていただきたい。開始3秒のドラムの音でブッ飛ぶはず。
Malla『Fresko』

Mallaは、ユヴァスキュラ出身の女優兼歌手。2021年に1stアルバム『Malla』でデビュー。本作は2ndアルバム。
宇多田ヒカル『Somewhere Near Marseilles ーマルセイユ辺りー』の路線でアルバム1枚作ったかのような体温低めのダンストラックが聴いててとにかく心地良い。本作を聴いて、僕は冷房ガンガン効いた快適な部屋の中でゆらゆら揺れて聴くのがしっくり来るタイプのエレクトロ/ダンスポップが好きなのだと確信した。そういった音をお求めの方は是非本作を聴いてみていただきたい。
MeriTuuli『Runot』

MeriTuuliは、 Meri WalleniusとTuuli Walleniusの姉妹からなるフォークポップ・デュオである。2015年に1stアルバム『MeriTuuli』でデビュー。本作は3rdアルバム。
2023年は、実に沢山のフィンランド音楽の新譜を聴いてきた。
あの手この手を使って次から次へと発売される新譜の情報をキャッチし、それがフィンランド語で作られた作品であれば「フィンランド音楽 2023年新譜」という、僕の個人的なプレイリストに追加していく作業を毎日のように繰り返してきた。
そのプレイリストには最終的に280作品分の曲が集まったのだが、それら1作品1作品とじっくり向き合い、時間をかけて聴き込むというのは―それをやるのが理想ではあるが―どう考えても時間がいくらあっても足りない。なので、とりあえずプレイリストに入れてはおくけれど、実際に聴くかどうかはあらゆる判断材料をもとに決めていた。
その判断材料の中で僕が最も当てにしているのが、「ジャケットデザインが好きかどうか」である。
あくまで僕の経験の中での話にはなるが、ジャケットが好きな作品は大抵、内容も好きになるものだ。今まで数えきれない作品をジャケ買いまたはジャケ聴きしてきたが、ジャケットは好きだけど内容はイマイチだった作品は数えるくらいのものである。ジャケットが好きな作品は、多分80%くらいの確率で内容も好きだったんじゃないかなぁと思う。
そんなわけで、聴く新譜を選ぶときも、ジャケットが好きかどうかで判断することが多かった。MeriTuuli『Runot』もまた、まずジャケットが好きで聴き始めた作品だ。
僕がフィンランド音楽の新譜情報を集めるのに最も頼りにしているのが、フィンランドで最も品揃えが豊富なレコード屋さん、Levykauppa Äxのサイトだ。フィンランドのポピュラー音楽のフィジカルは、大抵はここで入手可能なのだ。このサイトにはその週発売される作品の一覧ページがあり、僕はそのページを、フィンランド音楽だけが表示されるようにソートした状態でブックマークし、毎週チェックしている(こんなかんじに)。
2023年の1月のある日、そのページをチェックしているとMeriTuuli『Runot』が表示された。僕は、赤と青の絵の具で描かれた何とも言えない表情の女性二人の絵を一目見て気に入り、配信されたら聴こうと決めた。淡く切ない、少し浮遊感のあるフォークかな?と、ジャケットからどのような音か想像を巡らしながら、本作の配信を待った。
2023年1月20日に本作が配信された。本作を聴くのととても楽しみにしていたので、同日に配信されたどの新譜よりも先に本作を聴いた。ヘッドホンを付けて、ながら聴きなんてしないで、ただただ部屋の壁やドアなんかを見つめながら、時々目を瞑ったりして…。最後の曲が終わった後の静寂の中、僕は「良い作品に出会えた」と、静かに喜んだ。
音については、ジャケットを見たときに想像していた「淡く切ない、少し浮遊感のあるフォーク」という予想は、概ね間違ってはいなかった。Bon Iverの1stアルバムとかFleet Foxes辺りの、ポストロックを経由したフォークロックに近い場所にいると感じた。そこにMeriとTuuliの絶妙な―それでいてテクニックをひけらかすこともなく淡々とした―コーラスワークが組み合わさることにより、独自の魅力を持った音楽になっているのだと思う。
同じく姉妹で結成されたスウェーデン出身のフォークデュオ、First Aid Kitに似ているかもと一瞬思ったのだが、いや彼女たちとは似て非なる、むしろ対称的な存在だと考えを改めた。姉妹のコーラスワークは共通しているが、First Aid Kitはアメリカーナ寄りの音楽性で、晴天の日に野原で誰かとお酒でも飲みながら聴きたくなるような「外向き」の音楽である一方、MeriTuuliはポストロック寄りの音楽性で、曇天の日に部屋でひとりで聴きたくなるような「内向き」の音楽という印象を受けたからだ。MeriTuuliはどちらかと言うと、同じくフィンランドのバンドScandinavian Music Groupに近いかもしれない(奇しくもこのバンドも、姉妹でボーカルを務めている)。
本作は小さな灯火がぽっと心の中で灯るような、または静かに熱いものが込み上げてくるような曲が集まっている。その「込み上げてくるかんじ」を楽しむなら、ひとりでじっくり聴くのが適しているのかもしれないが、本作には、多くの人の心を掴むであろうキャッチーな曲も数多く収録されている。MeriTuuliは、とにかく曲が良いのだ。なので、誰かと一緒に聴いて楽しめる作品でもあるはずだ。誰かと会話をしながらのBGMにしても良いだろう。運が良ければ、話し相手が「この曲、良いね」「何て人の曲?」なんて言葉をかけてくれるかもしれない。その時はどうか、MeriTuuliのことをご紹介いただければと思う。
最後に、僕が本作で最も好きで、尚且つ多くの人の心を掴むであろう曲『Tropiikki』を貼って終わりにしたい。
Miko Gale『näköissaaren pääsiäispatsaat // DEMOS from spring』

Miko Galeは、シンガーソングライター。情報が少ないため詳細なプロフィールは不明だが、本作は1stデモ集。
Jeff Tweedyに憧れたお兄さんが、曲作りを進める中でBrian WilsonやNick Drake、Tracey Thorn、Daniel Johnstonにも憧れて、最終的にそれらを全て組み合わせて完成したひとりオーケストラ…のような音楽。人に聴いてもらうことはあんまり意識していなくて、自分が作りたいものを宅録で完成することが目的のように感じ取れる。それ故にアイデアの断片状態の曲も無数にあるため、一見ラフで雑多な音源集かと思わせるが、聴き込んでいくうちにどの曲もじわじわと愛着が湧いてくる。荒々しい録音だからこそ刺激的だし、本作の宅録感は自宅で一人で音楽を聴いているときの居心地のよさと少しばかりの切ない心境と非常にマッチしているため、聴いているとすごく心が落ち着く。今後益々、僕の日常に浸透していく音楽となるだろう。
Musta Huone『Valosaasteen sekaan』

Musta Huoneは、2010年代半ばに結成された、ヘルシンキを拠点に活動するロック・バンドである。2019年にEP『Huove』でデビュー。本作は2ndアルバム。
再生ボタンを押して数秒も経たないうちに、「さぁ、僕はどうやらとんでもない40分間を過ごすになりそうだ。一体どうなってしまうんだろう?」と、期待とも不安とも言えない気持ちにさせる音楽というのは、実にかっこいいものだ。CAN『Tago Mago』、Slint『Spiderland』、想い出波止場『水中JOE』…そしてMusta Huone『Valosaasteen sekaan』。
本作を敢えてひとつのジャンルで当てはめるなら、ポストパンクになるだろうか。具体的にバンド名を出すなら、Black Country, New Road一番近いものを感じている。しかしBC,NRを意識して本作が生まれたというよりは、Slintが好きな人たちがクラウトロックやスペースロックっぽいジャムセッションをしたら結果的にBC,NRに近い音になった、みたいなプロセスを感じるところが本作の、Musta Huoneの面白さなのだろう。
前述した通りジャムセッションで作ったっぽい曲が多くて、カッチリとした曲らしい曲はない。いずれもその時その場の「現象」を封じ込めたような内容なので、「え、ここで終わり?」と思わせるような曲もある。しかしそのちょっとした物足りなさとか、カッチリとしていないが故のノリにくいかんじが段々とクセになってきて、一曲一曲にハッキリとした印象は残っていないものの「あの感じをもう一度味わいたい」となり、再び本作に手を伸ばすこととなる。聴き手と絶妙な距離感を持ちながら「良さ」を少しずつ教えてくれるような本作は、長きに渡って楽しむことができるロックアルバムだ。
Noiduin『Alinen』

Noiduinは、ポリ出身のダークフォーク・バンド。2022年に1stEP『Korven kolkon kainalossa』でデビュー。元々はJemina Kärvi(作詞、作曲、編曲、演奏、ミックス等担当)によるソロプロジェクトだったが、2023年にHenri Virolainen(ボーカル、タルハルパ、カンテレ)が加入を機にデュオとなる。ライブではサポートメンバーとしてMikko Lahti(ドラム)、Matilda Lepistö(何でも屋)が参加し、4人で活動している。曲はもちろんだが、メンバー全員の佇まいも非常にカッコイイバンドだ。
Tenhiを聴いてネオフォークやダークフォーク、ペイガンフォークと呼ばれる音楽に興味が湧いた僕は、BandcampやRate Your Musicを駆使してその手のカッコイイ音楽を探しまくった。Noiduinはその中で見つけたバンドだ。
本作は2ndEP。Noiduinの好きなところは、堂々としているところ。自分自身の持ち味と、フィンランド流ネオフォークな音(カンテレ等の民族楽器を用いたフォークソング)をうまく融合させて、かっこいいうたものとして昇華しているところが好きだ。
ネオフォーク関連の作品を色々聴いてみて、―これは特に歌の面で顕著に現れるのだが―「所謂ネオフォークってこういうもんでしょ?」と考えているとまでは言わないが、ダークに金切り声を上げていればいいだろうみたいな作品が結構多いという印象を受けた。自分ではない何かを演じていて、リアルさが希薄なもの。演じることがダメというわけでは決してないが、僕は作り手の人柄が滲み出た(と感じ取れるような)音楽が好きで、そこが重要な価値基準にもなっているので、ツボな作品はなかなか見つからなかった。
Noiduinの場合はネオフォークな音楽を作りたくて作ったというよりも、自分たちから滲み出てきた歌をただただ本能的に曲になるように構築していった結果、ネオフォーク的な音として完成したみたいなプロセスだったんじゃないかと勝手に推測している。彼女らが作る音楽にはそう思わせる「リアル」さがあって、僕はそこを魅力に感じている。
EPなのであっという間に聴き終わってしまうところは少し寂しい。もっと60分、80分とこの世界に浸っていたいくらいだ。フルアルバムの発売が待ち遠しい、期待の存在である。
Nössö Nova『Hyvä on sitten』

Nössö Novaは、ヘルシンキ出身のインディーポップ・バンド。2022年にシングル『Mennyttä kalua』でデビュー。本作は1stアルバム。
Andy ShaufにTahiti 80の陽気さを少々加え、映画『クレイマー、クレイマー』のオープニング『マンドリン協奏曲ハ長調』を聴いたときの清涼感で味付けしたかのような音楽性で統一された楽曲は、いつ、誰と流しても心地よいBGMとして成立するだろう。バンド名から想起させる通り、ちょっぴりボサノヴァのテイストが見え隠れするのでLampの『そよ風アパートメント201』が好きな方も気に入るかもしれない。アートワーク含め、可愛く洒落た雰囲気が愛おしい。僕が知る限り、最も気軽にオススメしやすいフィンランド音楽アルバムのひとつだ。
Oiro Pena『Puna』

思い返してみると、僕はいわゆるジャズの作品について感想を書いた経験がほとんど無い。
ジャズ自体は好きだ。と言っても僕がよく聴くのは、高校時代に図書館でCDを借りて好きになったMiles Davis、Bill Evans、Chet Baker、John Coltrane、Thelonious Monkなどレジェンド中のレジェンドのみで、あらゆる年代の作品を幅広くカバーしているわけではない。そのため、僕のジャズの知識はほぼほぼ70年代で止まっているのだが、その状態に特に不満はなかった(レジェンドらですら未聴の作品が果てしない数あり、それらを聴くだけで僕のジャズ探求欲は十分に満足していたからだ)。そのようなわけで、僕がジャズの新譜を積極的に聴くことはほとんどない。そのため、年間ベストにジャズの作品を選ぶこともないのだが、それは感想を書いた経験が無い大きな理由となるだろう。僕が感想を書く経験を積む場所はXか、note(ほぼ年間ベスト記事)くらいのものだから。
そもそも僕は、―もちろん全てに当てはまるわけでないが―ジャズはBGMとして聴くことがほとんどで、ライトに楽しむだけで満足していた。なので、作品とじっくり向き合って何度も聴き込んだ結果、感じたことを発信したくなったり、「これは素晴らしい作品だから色んな人に聴いて欲しい」という紹介欲が出て来たりといった「感想を書くキッカケ」が生まれようが無い状態だったのである。
そのような僕とジャズの距離感は、僕がフィンランド語の音楽を片っ端から聴くようになってから変化が訪れた。フィンランドはジャズが盛んな国だ。そしてフィンランド語でジャズをやっている音楽家も多数存在する。フィンランド語の音楽作品を四六時中探していれば、当然ながらジャズの作品と出会い、聴く機会も増える。そのような中で出会ったのが、Oiro Pena『Puna』だった。そのあまりの素晴らしい内容によって今回の年間ベストに掲載することとなり、晴れて僕は、ジャズ作品の感想を書く機会が生まることとなった。
とは言っても、ジャズについての自分なりの感想がどのようなものになるのかが、イマイチ掴めていない状態だ。僕にとってジャズは、今までほとんど「なんか良い」を感じるだけで満足していた音楽だったから。いざその「なんか良い」を言語化するとなると…経験がないだけに、ロック領域と比べあまりに引き出しが少ない、というか引き出しの中身は空っぽだ。なので、ロック領域で培った言語化のプロセスを活かして、本作及びOiro Penaと向き合い、自分なりの感想を書いてみようと思う。
Oiro Penaは、Soft Powerというジャズロック・バンドでサックスを担当していたAntti Vauhkonenが2018年に始動したソロプロジェクトである。2ndアルバム『Music From Moments(2020)』までは全曲の楽器演奏、ボーカル、録音、ミックスを全てAntti自身で手掛けていたが、3rdアルバム『Jani(2021)』以降は積極的に外部プレイヤーを起用。5thアルバム『Cooper's Test(2022)』以降は以下の編成がレギュラー化している。
Antti Vauhkonen:ドラムス
Johannes Sarjasto:サックス、フルート
Philip Holm:ダブル・ベース
Staffan ''Wolf'' Södergård:ピアノ
上記の名前の箇所にDiscogsのページをリンクしている。各ページを見ていただけると分かると思うのだが、メンバー全員ジャンルを越境し様々なプロジェクトに参加する売れっ子プレイヤーだ。大げさな表現かもしれないが、現在のOiro Penaは、Miles Davisの第2期黄金クインテットくらい強力なジャズ・バンドなのである。もちろん、6thアルバムである本作『Puna』も上記の編成で録音され、脂の乗ったバンドの音を存分に楽しめる内容となっている。
本作がどのようなジャンルの音楽なのかというと、本作のBandcampのページに付与されたタグによればコンテンポラリージャズ、スピリチュアルジャズに当てはまるようだ。実際、スピリチュアルジャズの要素はかなり強い。僕にとってスピリチュアルジャズは「妖しげで魅惑的な儀式を目撃してしまったような気分になる音楽」。John Coltrane『A Love Supreme』や、スピリチュアルジャズではないかもしれないがMiles Davis『In a Silent Way』などを聴いたときに感じたイメージだ。本作には、そのイメージに当てはまる音が封じ込まれている。
本作はスピリチュアルジャズに当てはまりつつも、『A Love Supreme』や『Karma』のコピーに留まらないオリジナリティに繋がる要素がいくつか含まれている。それはまず、音質だ。本作は2022年にヘルシンキ近郊のベッドルームやスタジオなどで録音されたとのことだが、不思議なくらい重ね録りしている感じがない。むしろ完全一発録音なのではというくらい、ライブ感のある音質だ。それはまるで、最寄り駅付近にあるジャズバーにフラッと立ち寄ったらたまたまジャズバンドがライブをやっていて、まだ演者の姿も見えない店の入り口でバンドの音漏れを聴き、あまりの凄まじい演奏を聴いたことによる静かな感動と、ライブを観てしまうことで自分の中の何かが大きく変わってしまうのではないかという不安と期待が入り混じる心境に、最寄り駅という身近な場所で至ってしまったかのような質感なのだ。『A Love Supreme』や『Karma』が、天空で神々の儀式を見ているかのような非現実的音楽体験なのに対し、本作は自宅付近での目撃が有り得そうな距離感の近い音楽体験という印象を受ける。それはやはり、録音の質感から由来しているのではないだろうか。
本作では、ゲストとしてMerikukka Kiviharjuが4曲でリードボーカルを担当している。彼女の芯のある歌にはどこかFẹla And Afrika 70の女性コーラスのようなアフリカンな空気やゴスペルの神聖さが漂っており、それこそが本作の"スピリチュアル感"に繋がっている印象を受ける。また、本作はうたものとインストの曲が交互に収録されており、彼女のポップな歌が、本作をシリアスなものでなく楽しいジャズアルバムになるための"調和"の役割を果たしている。その点でも、重要な存在となっているだろう。
カンタベリーロックへの影響も強く感じるのも、本作の重要な要素のひとつ。具体的にはSoft Machine『Fifth』やHenry Cow『Legend』などの、シンセサイザーを導入していない、管楽器が活躍するシリアスなフリー/前衛ジャズだ。アフリカンで煙たいスピリチュアルジャズと、冷めた表情で淡々とカオティックな演奏を繰り広げるカンタベリーロックを絶妙なさじ加減で配合し、そこに―これがまさにOiro Penaならではのオリジナリティと言えるかもしれないが―ほんのちょっとだけ「脱力感」や「ユーモア」に繋がるローファイさをまぶしているのが、本作の音楽性と言えるかもしれない。
どの曲も演奏は非常にテクニカルだしややこしい曲が並んでいるにも関わらず、全体を通して聴くとポップなジャズアルバムという、なんとも不思議な作品だ。しかし、そのポップさによって間口の広い作品になっていると思うので、前述したジャズやジャズロックが好きな方以外にも是非聴いてみて欲しい。ちなみに、僕はこのアルバムを夜聴くことが多い。ひっそり聴いて、とんでもないものを見つけてしまった!と静かに驚きながら聴くのが楽しいアルバムなのだ。
Oona Kapari『Voimasta ja puutteesta』

Oona Kapariは、ヘルシンキを拠点に活動するシンガーソングライター、ミックスエンジニア、プロデューサー。CMX、Juha Tapio、HIM、Children of Bodomなどの作品を録音したフィンランドの伝説的なレコーディングスタジオFinnvox Studiosで8年間勤め、現在はヘルシンキにある自身のスタジオKuohu Recordsでミックスとプロデュースを手掛けている。2020年に1stアルバム『Maailmojen murheet』でデビュー。本作は2ndアルバム。
雨の日は気が滅入るので好きじゃない。ただし雨の日に聴きたくなる音楽というものが少なからず存在する。それらを存分に楽しめるという意味では、雨の日にも良い面があると言える。
本作の、雨曝しにしたTaylor Swift『Reputation』のような音はまさにそんなピッタリなアルバムだ。曇り空で真っ白な雨天の景色を窓越しに眺めているときの、妙に落ち着いた心境を表現しているかのような音に安心感を覚える。5曲目『Tervapääsky』の吉村弘的アンビエントをフューチャーした音はその象徴と言える。熱い情熱や情念を持ちながらもそれらを内に秘め、テンションを一定以上上げない歌い方が、冷えた電子音と絶妙にマッチしている。本作は、僕の中の「雨の日はこの一作があれば乗り切れる」リストの仲間入りを果たした。
Orvokki『Kasvotusten』

Orvokkiは、ヘルシンキを拠点に活動するシンガーソングライター。2019年にEP『enkä palaa enää takaisin』でデビュー。本作は1stアルバムであり、全曲の作詞、作曲、編曲、プロデュース、ミキシングをOrvokki自身で手掛けている。
まるでAstrud GilbertoがBjörk(『Homogenic』〜『Vespertine』まで)の要素を取り込み熱を冷ましたかのような「陽」ではなく「陰」にフォーカスを当てたエレクトロポップで、その手の音を好む自分としてはたまらないアルバム。
本作の楽曲はどれもアレンジも素晴らしい。ドラマチックな展開や音選びの面白さ、それによりどの曲も「強い」曲となっているのだが、そこに控えめな、情念を削いだ(ように聴こえる)うたが加わることによってとても聴きやすいものになっている点も大きな魅力だ。それにより、じっくり向き合って聴くのはもちろん、BGMとしても楽しめる、末永く向き合うことができるうたもの作品の傑作だと思う。
Pambikallio『Parc de Pambi』

Pambikallioは、Lauri KallioとPauliina Koivusaariの二人のよって結成されたサイケデリックポップデュオ。2021年にシングル『Häntä』でデビュー。本作は2ndアルバム。
以前書いたレビューの通り、前作は『Lonerism』までのTame Impalaに靄がかったドリーミーなテイストを加えたような方向性でほぼ統一されていた。本作は前作の路線にダンスポップ、チェンバーポップ、クラウトロック、ソフトロック等の要素が加わり、バリエーション豊かで拡張されたPambikallioサウンドを楽める内容となっている。
レコードで聴くと、A面とB面で方向性をガラッと変えているのがわかって面白い。A面は全曲シングル級のポップなうたものが、B面はちょっとマニアックな、A面のような曲を期待したらドキッとしてしまうような路線の楽曲が並んでいる。
B面について詳しく解説すると、例えば『Suolapatsas』は、前半は坂本慎太郎の『幻とのつきあい方』っぽいムードで進行していくが、後半になると、あれ?いつの間にThundercatが加わったの!?と思うくらいに手数の多いジャズ・ロックへと変化する。『Am I?』~『Happy Pambi』ではGrateful Deadのダークなフィードバック・ジャムから電子ドラムが活躍するクラウトロック風のアップテンポナンバーへと展開。『Kulkue』~『Vesimusiikkia (Laguuni 1)』は不穏なトランペットと弦のイントロから、チェンバーポップを大胆に取り入れたPambikallioサウンドへと繋がる壮大なクライマックスへ…といった具合に、B面は1曲、または複数の曲の中で異なる路線の曲を自然な流れで繋ぎ合わせた、ある種プログレ的な楽曲が多く並ぶ内容となっている。
僕は、上記のA面・B面で路線が大きく変わっていることに、レコードで聴くまで気付けなかった。サブスクやCDはA面B面の区切りがないため、いつの間にかB面のトンネルに足を踏み入れている状態になる。その状態では「色々な路線を試してはいるけれど、方向性が散り散りになってしまっているような…」といった印象を受け、本作のアルバムとしての流れや、実験的な面白さに気付けていなかった。本作によってレコードで聴くことで見えてくるものがあるのだと改めて実感できたし、これからも気になる作品はできる限りレコードで聴きたいと思った。
分かりやすさと分かりにくさが入り混じった本作は、美味しく味わえるようになるまでにそれなりに時間を要する作品なのではないかと思う。しかしその魅力に気付きさえすれば、あっという間に自分の中での重要な1作となることだろう。本作は、僕がSNSで観測する限り、前作以上に日本の音楽好きにも広く認知されている印象を受けた。なのでそろそろ、フジロックかサマソニに出演していただきたいところ…絶対に盛り上がるはず。切に願う。
Radien『Unissa palaneet』

Radienは、2014年に結成されたヘルシンキを拠点とするポストメタル・バンド。2016年にEP『Maa』でデビュー。本作は2ndアルバム。
吹雪が舞う山奥にぽつんと佇む小屋での出来事。彼の精神状態は誰がどう見てもまともとは言えなかった。どこからともなく湧いてきた憎悪によって今にも我を失いそうな彼は、怒りと小屋の中の容赦ない寒さでガタガタと震えていた。必死に気を抑えてはいるが、その途方もなく大きな憎悪に主人公が飲み込まれてしまうのはもはや時間の問題だった。「時」が来ると、彼はプツッとスイッチが入ったかのように発狂し、残虐性をむき出しにした。その残虐性は主人公の周囲を血の海にし、血の量が増えれば増えるほど彼の残虐性は増加していく。そして物凄いスピードで、彼は獣へと変化した。もう切り刻むものなど何もなく、辺りには血の塊しか残っていない頃に、彼はようやく、何もかもを失ったことに気付く。もう彼に残虐性は失われていた。しかし正気な自分も失われていた。残されたのは、どこまでも深い憂鬱と悲哀の嗚咽だった。しかし哀しみも喜びも、いつまでも続くものではない。彼の憂鬱は段々と高揚へと変化し、全てを失ったことに対しての開き直りか、それとも我武者羅に暴れまわることでしか存在することができなくなってしまったのが、ともかく彼は再び残虐性を取り戻し、叫び、小屋から出ていった。そして、吹雪に紛れた彼の影は、少しずつ見えなくなっていった。
以上は、僕が本作を聴いて浮かび上がってきた妄想である。何というか、頭の中で描かれた情景を言語化すると、かなり怖いものがあるのだと自分でも驚いている…。Radienが本作を通じてどのようなことを伝えているのかは把握できていないのだが、僕の中では、上記の物語のような、一人の人間の精神状態の足取りを映し出した作品なのではないだろうか。本作は収録曲5曲を45分間切れ間なくひとつの曲して作り上げているのだが、そういったアルバムの構成の中で、とてもまともとは言えない状態から生まれた残虐性をRadienは冷静に、冷酷に音として表している。本作には多数のゲストミュージシャンが参加しているのだが、ボーカリストとして参加したDylan Walker(Full of Hell等)の貢献はかなり大きいのではないかと思う。肉を引き裂かれたときの叫び声(もちろん実際に聞いたことはないけれどイメージとして)のような彼の歌が「発狂」や「残虐」の面を克明に表していて、改めて素晴らしいボーカリストだと実感した。
冒頭のバンド紹介のテキストで、彼らのことを「ポストメタル・バンド」と表現したが、本人たちは本作のBandcampのタグでは「psychedelic drone doom」と定義している。当然ながらそれはそれでしっくり来るのだけれど、個人的には、本作はポストメタルの流れにある音楽だと思っている。Neurosis『Through Silver In Blood』やboris『flood』のような静と動の揺らぎを、Godspeed You! Black Emperor『Yanqui U.X.O.』のスピード感でジワジワと描いた音楽だと感じたからだ。ポストメタル/ポストロックの歴史に新たな1ページを刻んだ大作だと思うし、2023年に聴いたヘヴィな音楽の中で最も好きなアルバムである。
Radiopuhelimet『Radiopuhelimet』
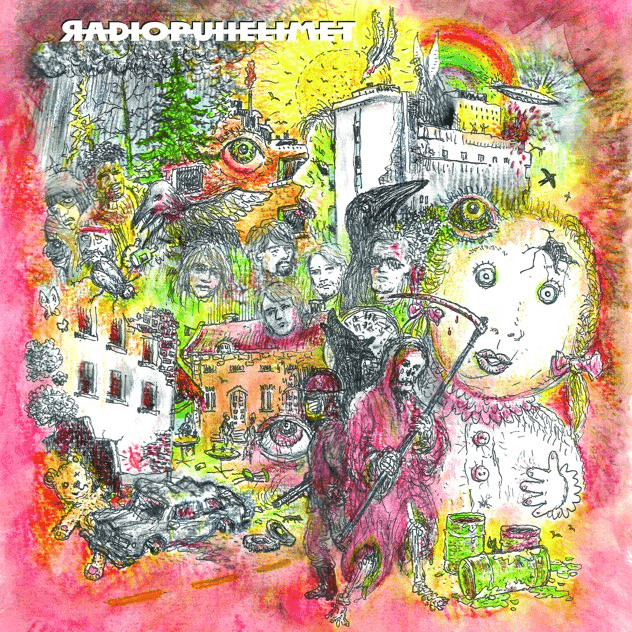
Radiopuhelimetは、1986年にオウルで結成された5人組のバンド。1987年にEP『Sinappia ja ketsuppia』でデビュー。本作は16thアルバム。
バカ騒ぎしたきゃこのアルバムを聴け!!!!
などと乱暴な言葉でオススメしたくなるような作品だ。僕は以前この本作を「ノイズロック化したJames Brown」と表現して感想をつぶやいた。それはそれで自分の中では納得のいく解釈なんだけど、何度も聴いていくうちに、これはパブロックなんじゃないか?と思うようになった。そう、Dr.Feelgoodである。どの曲もWilco Johnsonばりの強烈なギターカッティングがむちゃくちゃかっこいいのだ。パブロックを下敷きにハードコアパンクの要素を加えてより荒々しくしたかんじ。一杯やってハイになった状態で演奏しているような「イッちゃってる」テンションに、こちらもつられてハイになる。踊りたくなる。Radiopuhelimetはテンションの高さを維持し続ける作品が多い印象だけど、本作はその中でも最も飽きずに最後まで楽しく聴ける作品なんじゃないかな。
Radiopuhelimetはハードコアパンク、ノイズロック、グランジ旋風を経由し時代ごとに少しずつ音楽性を変化させながらコンスタントに40年近く活動している。メンバーチェンジもここ25年無く、長らく不動の5人組だ。。そのようなベテランバンドが、未だ(「未だ」なんてもんじゃないと思うが)にこれだけエネルギッシュな作品を生み出しているというのは世界的に見ても得難ぐ、貴重な存在なことであろう。今からでも全く遅くないので、ヘヴィな音楽好きだけでなくもっと広く知られて欲しい。そしていつか日本でライブをやって欲しいところ。実現したら、全力でバカ騒ぎするよ。
Rami Vierula『Erämaahan』

Rami Vierulaは、ヘルシンキを拠点に活動するシンガーソングライター。2016年にEP『Häilyt ja Synnyt EP』でデビュー。本作は2ndアルバム。
年間ベストの候補に度々挙げては外すを繰り返していた作品だったのだが、最終的にはこの記事に感想を掲載することができて本当に嬉しい。
なぜ候補に挙げては外していたのかというと、本作の魅力を、自分が納得いく形で気付けていなかったからだと思う。良い内容だとは思うけど、他の音楽家の作品にない強い魅力を持っているかというと…そこが見つけられなかった。なので、他に強い魅力を持った作品を掲載することを優先し候補から外し、でも諦めきれなくて(ちゃんと好きになりたくて)また候補に挙げ…というのを繰り返していた。そしてこの記事のレビューも残り10作品分となったタイミングで、「『Erämaahan』めっちゃ良い!」となり、掲載に至ったのである。
僕は元々、本作を「心地よいBGMとして活躍するフォーク作品」という視点で聴いていた。Nick Drakeのような、アコースティックギターと静かなうたが主体の作品だと。それ自体は、ひとつの視点として間違ってはいないだろう。しかし、その視点だけで、その路線だけを求めて聴いてしまうと、本作はあまりにロックすぎる。曲によっては結構ラウドなノリもあるのだ。なので―こうして文章にすると自分のあまりの都合のよさに辟易するのだが―「ちょっと自分が求めているものとは違うかな」「静かなセクションはすごく魅力的なのに惜しいな」という感想になってしまい、年間ベストに入れようというところに到達できずにいた。
見え方が変わったのは2024年1月26日のこと。Xのタイムラインでは音楽好きの方々がThe Smileの新譜『Wall of Eyes』を絶賛していた。僕はミーハーである。皆が良いと言っていると「ちょっと聴いてみるか」となり、僕もまた、『Wall of Eyes』を聴いた。素晴らしいアルバムだと思った。同時になぜかRami Vierula『Erämaahan』が聴きたくなり、「ひょっとして…」と思いながら『Erämaahan』を再生したところ、僕の予感は的中した。僕にとって、『Erämaahan』はフォークアルバムではなく、ロックアルバムだったのだ。
前述した通り、僕は本作を「心地よいBGMとして活躍するフォーク作品」という自分の中での位置付けに固執し、その視点でしか聴けなくなっていたのだが、『Wall of Eyes』の「フォーク由来で静かだけど確実にロックバンドの音をしたかっこいい曲」を聴いて、本作もその視点で聴けば非常にかっこいい曲が揃った作品だということに気付くことができた。僕は元々、本作にLau Nauのレビューで書いたようなHAGI CAFEに合うような、誰かと一緒にいるときに流れても違和感がないような音なのだろうと認識していたし、それを求めていた。それ故にしっくり来なかった。そこから視点を変えて、The Smileのような「一人で聴いて密かにテンションが上がるロック音楽」という視点で聴いて、初めてちゃんと、心の底から好きだと納得できたのだ。
初めて聴く音楽に対し、自分の経験を元に「こういう音楽かな?」と当てはめたり「この音楽はこういうシチュエーションで聴くべきものだ」と決めつけてしまうと、別の視点で見えるかもしれない魅力を見る機会を損失する可能性があるということを、本作を通じて学ぶことができた。幸い本作に関してはその機会を逃さずに今後も楽しんで聴けそうだが、今までもそのようなことがたくさんあったんだろうなと考えると、何とも勿体ない気持ちになる。今後は、あらゆる角度で骨董品を眺めるように音楽作品と向き合っていきたい。
Ruusut『Melankolia 1 & 2』


Ruusutは、ヘルシンキ出身の4人組エレクトロポップ・バンド。2016年に結成され、2018年に1stアルバム『Ruusut』でデビュー。本作は3rd、4thアルバム。
2作同時発売の大作。Björk『Vespertine』や三浦大知『球体』と並べて聴きたくなる、光と影のコントラストが美しい壮大なダンスミュージックで、凄味は伝わってくるのだが日常のどういうタイミングで聴きたくなるのかイマイチ掴めない…というのが第一印象だった。しかし定期的に聴き返すことで、スピーカーで聴くと重厚なシンセベースや電子ドラムが前面に出て非常に格好よく響くことや、夜に暗がりで家事しながらヘッドフォンで聴くとむちゃくちゃテンションが上がることなどが分かり、本作が好きになっていき、段々と僕の日常に浸透していった。あとはこの1年を通じてフィンランド中心にの数多くのエレクトロポップに触れたことでその手のサウンドを聴くことで心地良さを感じるようになったことも、本作への愛着が湧いたキッカケとして大きい。「経験」によって音楽の好みや印象が変わることが大いにあるが、その「変わった(ピンと来ていない→ピンと来た)」ことを感じ取った瞬間というのは、音楽を聴く面白さの醍醐味と言える。本作を聴いてそれがまた経験できたことを嬉しく思う。
Salaliitto『Portaat』

Salaliittoはトゥルクを拠点に2012年に結成された4人組のバンド。2015年に1stアルバム『Salaliitto』でデビュー。本作は4thアルバム。
2024年2月5日に、関東地方でびっくりするぐらい雪が降った。
雪が降る日に聴くポストブリットポップは格別だ。Coldplay『Parachutes』、Travis『The Man Who』、elbow『Asleep In The Back』…メランコリックなメロディと、綺羅びやかで時に激しく歪むギターが気持ち良い音楽。僕は雪景色を眺めながらこれらの作品を聴き、幻想的な気分に浸るのが好きだ。
本作もまた、雪と非常に相性がいいギターロック・アルバムだ。方向性は、前述した作品のようなポストブリットポップの音にかなり近い。しかしながらポストブリットポップをただなぞっているだけでなく、編曲はプログレッシブロックか?というくらい練られており、どの曲も一筋縄ではいかない。それでいて不思議と「分かりづらい」と感じることはない。1曲目の『Lasken raskaat luomeni』などは9分半ある長尺曲にも関わらず長いと感じるどころか気持ち良すぎるエレキギターの音にいつまでも浸っていたいと思わせるほどだ。そういった点は、Sonic Youthに近いかもしれない。
本作はレコードでは2枚組。15曲入り70分の大作だ。しかしその70分の途中で飽きることはない。どの曲もシングル級の名曲で濃い内容のはずなのだが、聴き疲れすることもない。それは繊細な歌のメロディや音が良い意味で印象に残りすぎず、聴き手と適度な距離感を保ってくれているからなのかもしれない。その距離感は、今後末永く本作を何度も聴きたくなるための重要になってくるのだと思う。
とにもかくにも、ポストブリットポップが好きな方には是非聴いていただきたい。曲で言えばRadioheadの『Knives Out』が好きな方には特におすすめ。僕の中のグラミー賞では、本作が最優秀オルタナティヴミュージック・アルバム賞を受賞しています。
Sir Liselot『Paprika, Quirky Girl Moshpit』

Sir Liselotは、ヘルシンキを拠点に活動しているミュージシャン、プロデューサーLiisa Taniによるソロ・プロジェクト。Sir Liselotの他にBig Fields、Ghost Worldというバンドでも活動。プロデューサーとしての活動はPintandwefall『Seventh Baby(2022)』での録音、ミックス、プロデュース、Kissa『Apinalinna(2023)』でのストリングスアレンジ等がある。Sir Liselot名義では2018年にデビュー。本作は4thアルバム。
フィンランドの音楽を聴くようになって…特に2023年になってから、いわゆる"宅録"や"ベッドルームポップ"などと呼ばれている音楽がすごく好きになった。この記事にも掲載しているmiko galeやVille-Veikka Silvolaもまさにそう。なんでだろうね。年を重ねるごとに、部屋で一人で聴く音楽が好きになってきているのが大きいからだと思うけれど。宅録の音楽って、聴き手一人だけに向き合ってくれるものが多い気がしていて。だから、聴いていてじわっとくるのかもしれない。
そのような僕にとって、Sir Liselot『Paprika, Quirky Girl Moshpit』は、まさに今(2024年1月)最も好きな音楽作品のひとつと言える。これほど宅録(だと僕は思っている)の魅力に溢れた作品に出会えたことを嬉しく思う。何度か聴いたときは、「『Sweet』あたりの、初期のCHARAっぽい」「Linda Lewisっぽさもあるなぁ」と思ったので、本作を聴いた後に『Sweet』や『Lark』を久しぶりに聴き直した。その後もう一度本作を聴いたら、初期CHARAやLinda Lewisを感じさせる要素はありつつも、ベーシックな要素はSir Liselot以外の何者でもない、「ジャンル:Sir Liselot」な作品だと感じた。というかもう、本作はぶっ飛んだ作品だ。フォークかと思ったらいつの間にダンス・ポップをやっているし、そうかと思えばポップパンクで爆音ヘドバン状態。思いついたことを勢いのままなんでも録っちゃう姿勢こそが宅録のかっこいいところで、本作はその「ごった煮感」を楽しみ、ひと目のつかない場所で密かに小躍りするような作品なのだと思う。
ごった煮でなんでもアリではあるけれど、どの曲もカオティックになりすぎず綺麗でソフトな歌と音で作られているということも伝えておきたい。本作は、カオスでありつつとても聴きやすいのだ。
Tanssiva Karhu『Luonnossa』
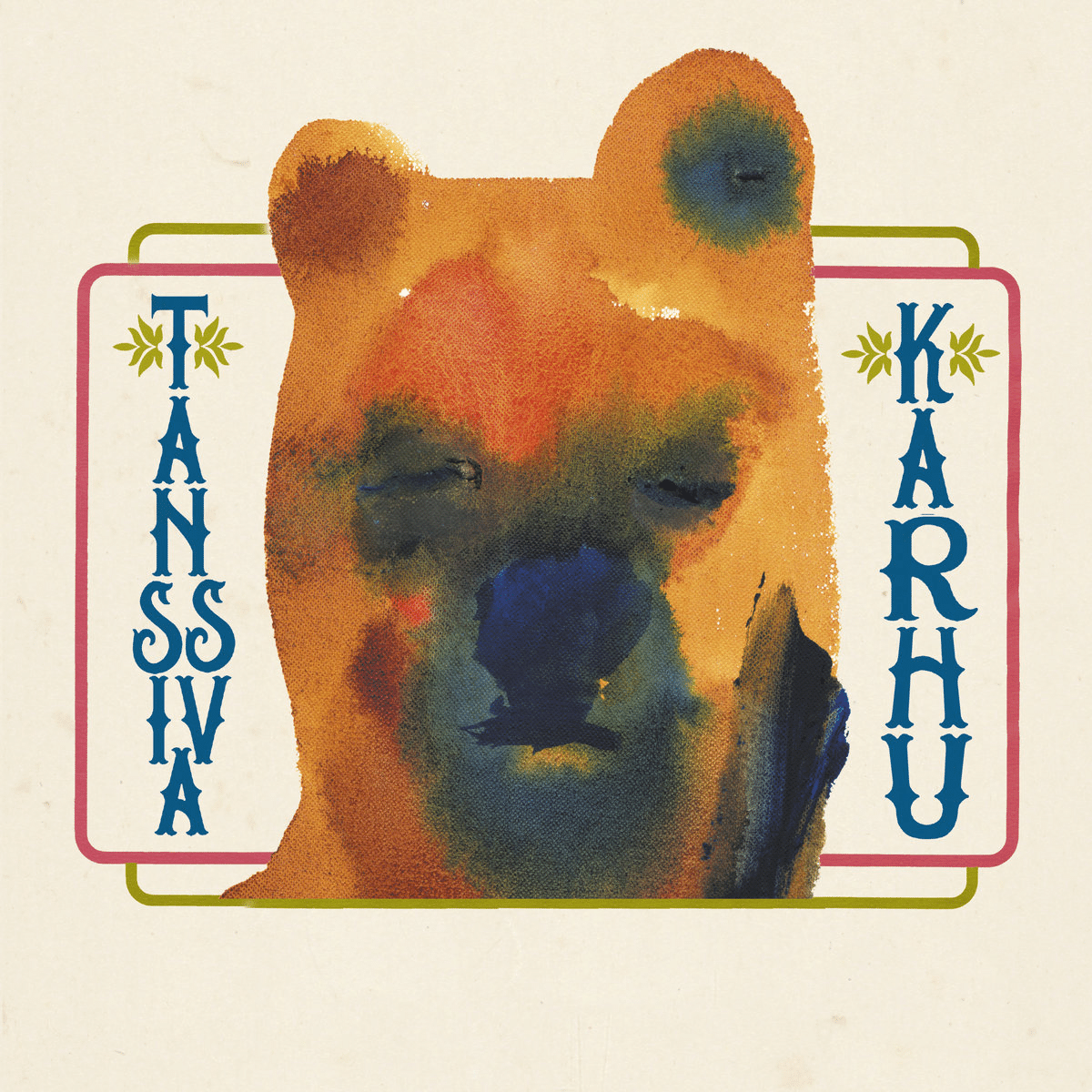
Tanssiva Karhuは、ヘルシンキを拠点に活動する6人組のサイケデリック・フォークポップ・バンド。2016年にEP『Kutsu e.p.』でデビュー。本作は1stアルバム。Tanssiva Karhuのボーカリスト、Jenna-Marie Laineはソロでも活動しており、彼女の1stアルバム『Vapaapudotu』も年間ベストに選出。
Nick Drakeで例えるなら、Jenna-Marie Laineの『Vapaapudotu』が『Pink Moon』で、本作は『Bryter Layter』。『Vapaapudotu』が暗がりで密かに生まれた内省的なうたものなら、本作は晴れた日の草原で生まれた開放的なうたものと言えよう。明るく、優しく、活発な楽曲が揃っている。活発さは特にベースに顕著に表れている。全曲ベースのぶりっとした音、演奏が格好良すぎるし気持ち良すぎる。2023年ベーシスト大賞がもしあるなら、僕はJarmo Vähähaka(Tanssiva Karhuのベーシスト)に贈りたい。Kevin Parkerが弾くベースの音にかなり近い。そういった観点で見れば、本作はまるで「Tame ImpalaがプロデュースしたJudy Collinsのアルバム(妄想)のよう」とも例えることができる。
魅力的なのはベースのみならず、もちろん楽曲そのものもだ。とても人懐っこくポップな曲ばかりで、難解な印象を持たせる箇所はほとんど無い。全曲素晴らしいのだけれど、僕が一番好きな曲は『Sellainen tyttö』。名曲。楽曲単位で言えば2023年で最も好きな曲かもしれない。『Sellainen tyttö』だけでもどうしても聴いて欲しいので、YouTubeの動画を貼り付けて本作のレビューを終わりにしたい。
Tenhi『Valkama』

Tenhiは、1996年に結成されたネオフォーク・バンド。1998年にEP『Hallavedet』でデビュー。本作は6thアルバムであり、オリジナルアルバムの発売は実に12年ぶりとなる。
Tenhiのことは、フィンランド音楽を聴き始めたわりと最初のタイミングで知ってはいた。2020年の11月、フィンランドに潜む先鋭な音楽家を探すためインターネットの海を彷徨っていた僕は、Rate Your Musicで作られた「Top 200 Finnish artists on RYM」というリストに辿り着いた。何やら興味深い音楽を作っていそうな魅力的な音楽家ばかりが並んでいるのだが、ここで3位に挙がっていたのがTenhiだった。僕はこのリストを上位順に片っ端からチェックしたので、すぐにTenhiを聴くこととなった。聴いたアルバムは『Kauan』だったかな。さらっと聴いただけだったけど、かっこいいと感じたのは覚えている。しかし僕は同じくこのリストで知ったCMXの方に強く興味を持ち、そのままCMXの沼にはまってしまったので、Tenhiとじっくり向き合うまでに3年もの月日が経ってしまった。
本作の収録時間は70分(デラックスエディションはボーナストラック3曲追加により80分超え!)と非常に長い。そして収録曲はどれも、決して明るいとは言えない「重み」を感じる曲調の、ゆっくりとしたテンポのフォークソングで統一されている。一度に最後まで聴き通すなら、聴く側の集中力やまとまった時間の確保などが必要とされる作品だ。僕は本作を聴き始めた当初、「聴くことに一点集中する」ことを怠ったため、自分のツボにすごくはまっている作品だと気付くまでに随分と時間がかかってしまった。つまり「ながら聴き」して、聴くというよりは流していたのだが、本作はその聴き方だと魅力を感じ取りにくい作品なのだ(これはあらゆる作品に言えることなんだけどね)。そのため、「悪くはないけど、ずっと聴いているのはしんどいかな…」というのが第一印象だった。
この記事を書く中で、聴き始めた当初はしっくりこなかった作品を聴き直す機会がたくさんあったのだが、そのほとんど作品が印象が大きく変わっていた(ほとんどがポジティブな印象)。それにより年間ベスト入りとなった作品も数存在している。そういった事象を見ていく中で、「もしかしたらTenhiもちゃんと集中して聴いてみたら、違った印象になっているのかも」とふと思い、改めて聴き返し、最高の作品であるということに気付けたわけだ。
本作から感じ取れる要素は以下の通り。
'88年以降のLeonard Cohenのようなバリトンボイスの歌
HeilungやSyvenのような民族的かつダークなネオフォーク要素
MONOの『Yearning』や『Moonlight』のような冷たくて切ない、哀しい情景を描いた曲調
上記の要素をドラマチックに展開させる楽曲構成
上記を挙げていて思ったのだが、ここ10年くらいのSwansにわりと近い音楽性なのかも?と思いつつ、Swansがエレクトリックな楽器を主体としカオティックな世界を追求しているのに対して、Tenhiはアコースティックギターを主体としたフォーク。そこを主軸に拡張させているような印象を受けるので、似て非なる存在なのだろう。
本作の中で僕が最大の魅力だと思っているのが、「ドラマチックに展開させる楽曲構成」だ。『Saattue』の7分45秒あたりからの、ドラムのフィルを合図に合奏が始まった瞬間、『Ulapoi』の3分7秒あたりから見られる、つかの間の「希望」を感じさせる瞬間(そしてすぐに、重苦しい現実へと引き戻される)…などなど、はっとさせられる場面がいくつもあって、それがあるからこそ、本作は聴き手の感情をしずかに揺さぶる作品になっているのだと思う。このような、はっとさせられる場面があることは、流し聴きではなかなか気付けないものだ。じっくりと本作を聴くことにだけ集中して、初めて気付けるものなのだと実感した。
しかし音楽とは不思議なもので、聴き始めた当初は「ずっと聴いているのはしんどい」などと思っていたのに、一度魅力に気付いた途端に何度も聴きたくなり、70分という尺も長く感じなくなり、年間ベストに入るほど好きな作品になっている。それだけでなく、本作をきっかけにTenhiの作品を順番に聴き込みたいと思ったり、ネオフォークやダークフォークといったジャンルに強い興味が湧いたりなど、僕の音楽ライフは本作によって大きく発展している。そういった影響の面を含め、僕にとって非常に重要な存在となっているのが何とも嬉しいことであり、音楽を聴く面白さを実感している。
Ursus Factory『IO』

Ursus Factoryは、2013年にエスポーでAllu(ドラム&ボーカル)とJussi(ギター&ボーカル)の二人によって結成されたオルタナティヴロック・バンド。2015年にEP『Virhe EP』でデビュー。本作は4thアルバム。
いやぁ、なんとも濃い!そして限りなく格好いいロック・アルバム。MudhoneyにRage Against The Machineのメタリックなリフを取り込んだ結果Nova Twinsっぽくなった…みたいな音が本作のベーシックな方向性ではあるものの、心地よいフォークロックをやったかと思ったら突然スタジアム・ロック化したり、一筋縄ではいかない要素がいくつもある。バリエーション豊かさの濃さと音としての重さが結託し、ヘヴィなロック・アルバムとして纏められている。それでいながら本作が聴きやすいのは歌の力が大きいと思う。アンディ・パートリッジを想起させる良い意味で軽い歌い方は曲全体が重くなりすぎないよう良い具合でバランスをとるための重要な要素になっているように聴こえる。音質も素晴らしい。特にギターとドラム。聴いているだけで爽快感を得られるほどに。今年一番聴いたロック・アルバムになりそう。
Veli-Rekka & Rokut『Veli-Rekka & Rokut』

Veli-Rekka & Rokutは、Veli-Rekka Ollilaを中心に結成されたロヴァニエミ出身のインディーロック・バンド。2017年にEP『Tummuneet Vedet』でデビュー。本作は2ndアルバム。
本作がどのようなタイプの音楽か説明するのは、僕のインプットではなかなかに難しい。非常にフィンランドらしい音楽であるとは言える。なぜなら、フィンランドには彼らに通じる音楽がいくつか存在するからだ(AmuriやCMXなど)。また、イスケルマ(フィンランドのムード歌謡のような音楽)のテイストをギターロックで継承したもの、とも表すことはできる。しかしこれでは、読んでくれた方には伝わりにくいと思うので、本作にまつわる僕の経験談を書くこととする。そちらを読みながら、本作がどんな音楽かご想像いただければ幸いだ。
2024年1月某日、僕は某駅付近のタリーズコーヒーにいた。雨が降り強い風が吹く不穏な天気の中、ノートPCでカチャカチャと忙しなく文字を打ち込み、この記事を書き進めていたのだ。進捗はやっと50%に到達したところで、果たして書き終わるのだろうか…と、途方に暮れていた。
20時頃、なんとか3作品分の感想を書き上げた僕は、時間も時間だったのでそろそろ帰ることにした。この日はものすごく寒かった。おまけに非常に強くて、冷たい風が吹いている。そのような街の景色を店の窓から眺めていると、妙に『Veli-Rekka & Rokut』が聴きたくなったので、ウォークマンで再生しながら店を後にした。
店を出ると、やはり非常に冷たく厳しい風が吹いていた。冷たさに顔が痛くなる中、最寄り駅までの300mあるかないかの道を歩いている時に『Puhun puille』の冒頭部分が流れたときに、僕は感じた。
これは負け犬のためのサウンドトラックだ。
「負け犬」の「負け」は、何に対しての負けなのか?特に何に負けたってことはないのだけれど、僕はあの日、寒くて人気が少なくて薄暗い道を歩いているときに、何かに負けたような気分になった。もっと深掘りすると、例えば何か壁に直面したときに悔しいとすら思わず、省みる気のない「無気力でダメダメな自分」にウンザリするときの気分。この気分、以前もどこかで味わったことがあるなと思い返してみると、4年前に行ったフィンランドのロヴァニエミで、マイナス20度の夜道を歩いているときに同じような気分になった。寒さが僕の気分をそうさせたのだろうのか。そして奇しくも、Veli-Rekka & Rokutはロヴァニエミのバンドだ。
『Veli-Rekka & Rokut』は、あの日タリーズを出たときの僕の心情にピッタリと重なる音楽だった。あの日の僕の姿を映像に収めるなら、バックで流す音楽は『Veli-Rekka & Rokut』の楽曲以外考えられない。Veli-Rekka Ollilaのダウナーで無気力なボーカル、楽曲の曲調、ロックだけどわかりやすく歪ませたりはしないギターの良い意味での煮えきらなさ、それでいてノリの良いベースとドラム…その全てが、自分は負け犬だと開き直ったときのヤケクソ感、高揚感へと導く。
恐らく僕は、『Veli-Rekka & Rokut』を聴くことで「酔える」んだと思う。でもその酔いはとても快感であり、安心するものでもあるからこそ、本作は名作なのだ。僕は僕が負け犬である限り、本作を聴きたくなるのだろう。負け犬じゃなくなったら聴かなくなるかって?大丈夫。人間ってのは、いつだって何かに負けてるものでしょう?
Ville-Veikka Silvola『Vuoret』

Ville-Veikka Silvolaは、ポリを拠点に活動しているシンガーソングライター。情報が少ないためそれ以上のプロフィールは不明だが、本作は恐らく1stアルバムにしてデビュー作。
愛聴盤。何度聴いたことか。本作はVille-Veikka Silvolaによる弾き語りを主軸にした静かなうたもの作品なのだが、ふわっとした、耳に残るフレーズひとつひとつがとても心地よいのだ。誰かといるときに流しても素敵なBGMになるだろうし、曲は一見シンプルな印象を受けるのだが、じっくり聴いてみると展開が非常に凝っている。一度入り込むと出られなくなるような深みへと導く編曲が素晴らしいので、一人でじっくり聴くのも楽しい。Tracey Thornの『A Distant Shore』やBen Wattの『North Marine Drive』が好きな方は気にいるかもしれない。
僕は本作を「立ち止まりたいとき」に聴くことが多い。人間生きてりゃしんどい気分になるときが大なり小なりあるもので、そんなときは本作を聴いて、聴いている30分弱だけは目の前にある面倒事を一旦全て無かったことにして静かに過ごすのだ。まぁ言ってしまえば現実逃避なんだけど、そういった状態のときに、ちょこまか動き回らず演奏しているような音楽が封じ込まれた本作を聴くと、リフレッシュできたりするものなのだ。
もちろん、メンタルが不調なときであろうとなかろうと、本作は楽しく聴ける作品だ。晴れた日にコーヒでも飲みながら聴いていると、とても居心地がいい。2024年2月時点ではBandcampでデジタル音源のみの販売のようだが、是非レコードでも聴いてみたい作品だ。
Virrentakoja『Kirouksia ja kuolinlauluja』

Virrentakojaは、ヨエンスーで活動するネオフォーク・デュオ。2022年にEP『Virrentakoja』でデビュー。本作は1stアルバム。
彼らもNoiduin同様、Tenhiをきっかけに始まったネオフォーク探索の中で出会った存在だ。
所謂ネオフォークと呼ばれている音楽作品を聴きまくる中で思ったのだが、僕は想像以上にこのジャンルにはまっている。不思議だったのが、ネオフォークの儀式的世界観や音に対して特に違和感がなく、すっと好きになっていること。決して明るい曲調とは言えないし重苦しい空気が漂っていると思うのだが、その音に身を委ねたいと思うくらいに居心地のよさを感じている。
それがなぜなのか色々考えてみたのだが、恐らくネオフォークに近い儀式的世界観の音楽にかつてはまっていた経験があったため、馴染み深い音楽のように感じたからなのだろうと気付いた。その音楽とは何なのかというと、Third Ear Bandだった。
僕がThird Ear Bandの存在を知ったのは2010年頃と記憶している。当時灰野敬二が好きになり、聴きまくっていた僕は、灰野敬二への興味が湧きすぎて毎日のように彼のインタビューをネットで探して読み漁っていた。そんな中で見つけたのが、とあるインタビューでの灰野敬二による「今でも最高に好きなのはサード・イアー・バンド」という発言だった。
当時Third Ear Bandを知らなかった僕は、さっそく聴いてみようと思い図書館で『Alchemy (1969)』と『Elements (1970)』を借り(今考えるとThird Ear Bandが気軽に借りれる図書館ってすごい)、衝撃を受けることとなる。歌はなく、不気味に鳴り響くバイオリンやパーカッション…ジャズでもなく、いわゆるインプロとも違う。セッションではあるけれど、楽しんでやっているといよりかは本能的な…信条としてやっているかんじがするのだ。そして、彼らの音楽の何が味わい深いかって、その「妖しげ」な様子だ。何やら見てはいけないものを見てしまって、でも目を離すことができなくなるような魅力に、ただただ圧倒された。こういう音楽もあるのかと。こういう音楽もアリなのだと。以来僕にとってThird Ear Bandは大きなルーツとなった。そして自分でも気付かぬうちに、このような儀式的な音が馴染み深い音楽となっていたのだ。
僕がVirrentakoja『Kirouksia ja kuolinlauluja』をすぐに好きなれたのは、Third Ear Bandに近い、妖しげな儀式を感じさせる空気なのだと思う。しかしながらVirrentakojaはThird Ear Bandと比べれば圧倒的に聴きやすく、ポピュラー音楽としての親しみやすさがあるので、Third Ear Bandのような音楽を聴いたことがなくてもそのかっこよさは伝わりやすいものだとは思う。「儀式」を感じさせる音楽を好きになれることがわかったので、今後もネオフォークに限らずそういった空気を感じさせる音楽と出会うのを楽しみにしたい。
