試作_1028

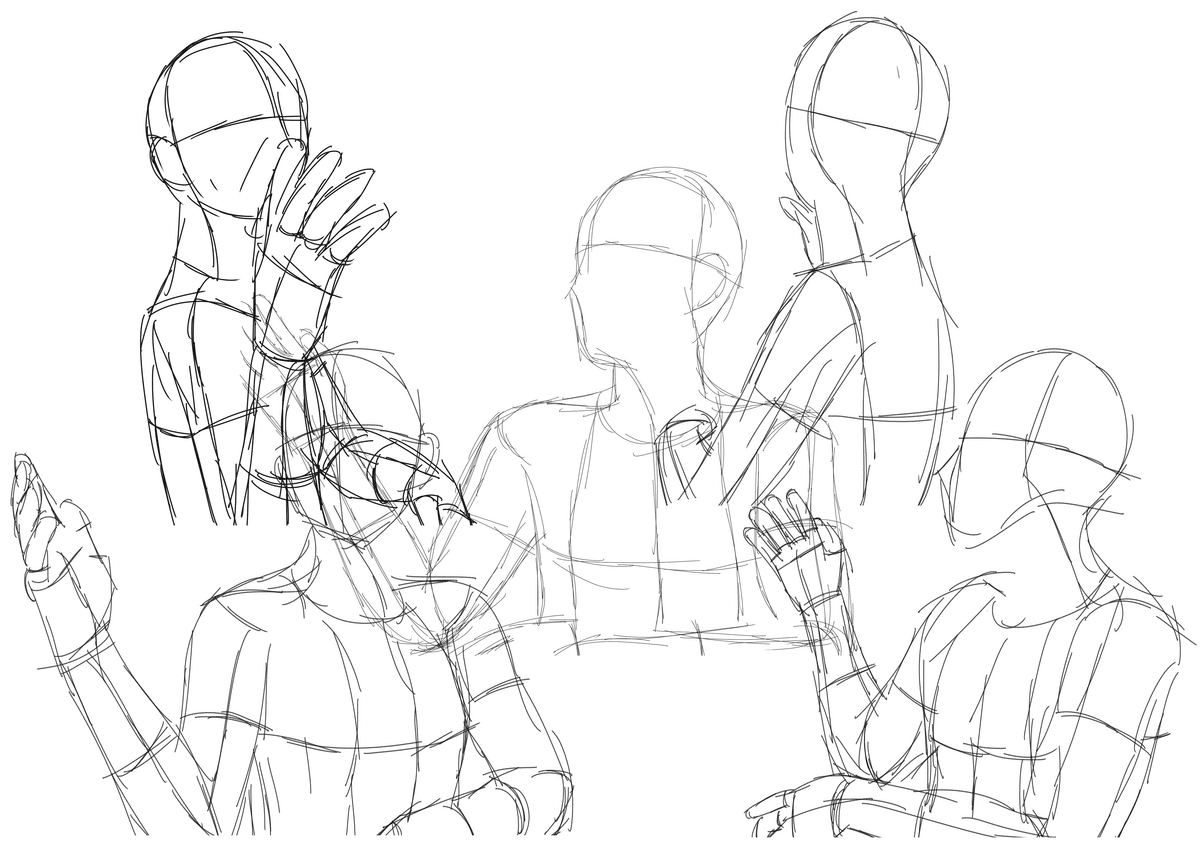
ボヌールの前に立ち、僕は自動ドアが開く音に一瞬耳を傾けた。
白く輝くカウンターの向こう側には、いつものように勇太がいる。優しい笑顔を浮かべながら、僕を迎える彼は、今日も変わらず穏やかな雰囲気だ。
「朦依君、いらっしゃい。」
その挨拶に軽く応えながら、僕は目的の品を告げる。
「ソフトクリームを一つ、お願いします。」
勇太は慣れた手つきで、ソフトクリームを機械から取り出し、綺麗な渦をコーンの上に作っていく。
目の前に差し出されたその白い柔らかさを見て、僕の胸には一瞬、ある好奇心が浮かんだ。
「君の作るソフトクリームは、毎日、食べても飽きないくらいなんだ。」
僕はお礼の意味も込めて言葉を添えながら、それを受け取った。そして、ふと浮かんだ考えを口に出す。
「もし、このソフトクリームを三倍の価格で他の誰かに売ったら、君は怒る?」
勇太は一瞬目を見開いたが、すぐに穏やかな表情に戻った。
「それはどういうことだ、朦依君?」
「ただの興味だよ。」
僕は、少し肩を竦めながら言った。
「君のソフトクリームは美味しいから、もっと高い値段で売ってもいいのかなって思ったんだ。」
仮にそれを僕が他の誰かに三倍の値段で売ったら、君はどう思うのか知りたくて。
勇太は少し考えるように視線を下げ、それから再び僕の方を見た。
「もしそれでその人が満足するなら、俺は怒らないよ。」
俺の作ったものが誰かの喜びになるのなら、価格はそんなに重要じゃない。
「しかし――――、朦依君。」
お前は、そういうことを本当にするつもりなのか?
その問いに、僕は軽く笑みを浮かべた。
「しないよ。」
ただの思いつき。君のソフトクリームは僕が楽しむためのものだから。
「そうか。」
勇太も微笑みを返す。
「なら、これからも、お前の為に作るとするよ。」
僕はそのソフトクリームを一口食べ、いつも通りの美味しさを感じた。
◇
ソフトクリームを一口食べた後、ふと思いついて僕は言葉を続けた。
「逆にさ、僕がタダでソフトクリームを食べたいって言い出したら、君はどうする?」
その問いに、勇太はまた少し驚いた表情を浮かべたが、すぐに真剣な思案顔に変わった。そして、しばらく考え込んだ後で、ゆっくりと口を開いた。
「別のもので払ってもらうかな。」
その言葉を聞いた瞬間、今度は僕が驚く番だった。思わずソフトクリームを持つ手が止まり、勇太の顔をじっと見つめる。彼の言葉が意外だったからだ。
「別のもので…………?」
僕は問い返すように、ついそう口に出した。
勇太は軽く笑みを浮かべながら、僕を見返してきた。
「君はイラストレーターだろう?」
例えば、君の絵とか、そういうもので払ってもらってもいいかなって。
その言葉に、僕は少し肩の力が抜けた。確かに、勇太らしい提案だなと納得する反面、僕の心の中には別の意味でも少し動揺が広がっていた。
「そういうことね…………。」
僕は軽くうなずきながら、再びソフトクリームに口をつけた。でも、どこか胸の奥がくすぐられるような感覚が残っていた。
◇
朦依が店を出て行くのを見送り、ドアが静かに閉まる音が響いた。
相変わらず、妙なことを言い出す奴だな、と俺は思わず笑みを浮かべながら、カウンターの片づけに取りかかる。
「三倍の価格で売ったら怒るか、なんて…………。」
朦依らしいと言えばそれまでだが、時々、本当に何を考えているのかわからない。でも、そんなところが面白いし、ついつい話に引き込まれてしまう。
店内が静まり返り、いつもなら気にしないはずの時間が、今日は少しだけ長く感じた。あいつが帰ってしまうと、こんなに静かになるんだな、とふと思う。静かすぎて、ついさっきまでの会話が頭の中に残響のようにこだましていた。
『もし、タダで食べたいって言ったらどうする?』
俺も自分が思ったより素直に答えたことに、少し驚いている。別のもので払ってもらう、なんて冗談半分のつもりだったけど、朦依が驚いた顔を思い出すと、ちょっと面白くなった。
「朦依君の絵か…………。」
悪くないかもな。
俺が作るソフトクリームはあいつにとっては特別なものらしい。それなら、あいつの作った何かも、俺にとって特別になるかもしれないな、とふと考えた。
静かになった店内で、俺はその考えを少し楽しんでみた。
