試作_1014
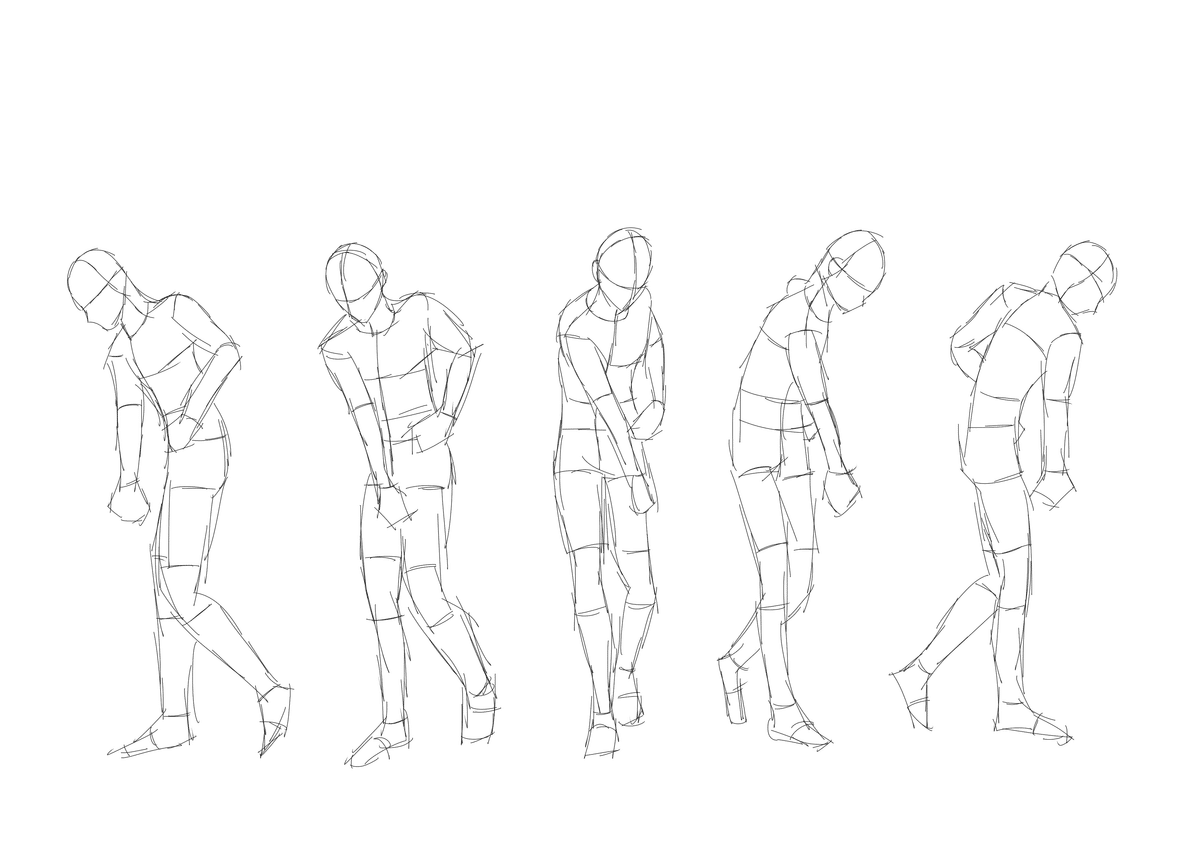

相変わらず、魔王は怖い表情で僕を見下ろしていた。
レグルスの鋭い目つきと完璧な姿勢は、見るだけで威圧感を感じさせる。それでも、今日はそこまで怒っている様子はない――――、はずだ。少なくとも、魔素は揺れていないし、紫の光も見えない。これは、ある意味チャンスかもしれない。
僕は、ふとした興味本位でレグルスの頬に手を伸ばし、その硬質な表情を柔らげられるか試してみたくなった。指先が彼の顔に触れ、冷たくも温かい肌の感触を確かめながら、両手で頬を包み込む。
「…………?」
一瞬、レグルスが眉をひそめる。彼の威圧感のある顔が少しだけ崩れたような気がした。僕は、思わず笑みがこぼれた。
なんだ、怖い顔ばっかりしていても、こうすれば――――。
「貴様…………、何をしている。」
その声は低く、重々しい。突然、空気が変わった。まるで僕の手の動きに呼応するかのように、周囲の魔素が震えだす。
ああ、やってしまった。
僕はすぐに手を引こうとしたが、時すでに遅し。
僕の両腕は力強く掴まれ、そして魔王は僕に顔を近づける。
僕の腕がレグルスに捕まれた瞬間、彼の冷たい瞳が真っ直ぐ僕を射抜く。
顔がぐっと近づき、息を呑むほどの距離にまで迫る。彼の息遣いすら感じられるほどだ。
恐ろしいほどに静かな空気が、部屋の中を満たしていた。
「貴様、軽々しく我に触れるとは…………、どこまで愚かか。」
レグルスの声は低く、鋭利な刃のように僕の耳に刺さる。
彼の怒りは爆発こそしなかったものの、押し殺されたその冷静さが、かえって恐ろしかった。
僕はただ無言で彼を見つめ返す。
言い訳する暇も、どうにかなると思っていた自分の愚かさを反省する暇もなかった。何か言おうと口を開いたものの、その言葉は喉の奥で止まってしまう。
「魔王に触れるということが、どういうことか理解しているか?」
その問いに、僕は返事をするべきなのかどうかも迷ってしまった。
レグルスの顔は僕に近づきすぎて、視線を逸らせる場所さえない。ほんの一瞬、あの鋭い表情が揺らいだのを思い出すけれど、それももう遠い過去のように思えた。
「――――、わ、分かったよ。」
悪かった…………、本当に。
必死で言葉を絞り出す。けれど、僕の謝罪がどこまで彼に通じるかはわからない。
レグルスの瞳に宿る鋭さは少しも和らがず、まるで僕を一刀両断しようとしているかのようだ。
「次はないぞ、朦依。」
彼はそう言い残し、ようやく僕の腕を放す。
自由になった手をじんじんする痛みとともに感じながら、僕は深く息をついた。
レグルスが去っていくその背中を見つめながら、改めて彼に触れることのリスクを実感する。
しかし、レグルスが去ろうとするその瞬間、僕は思わず口を開いた。
「じゃあ、手はいい?」
自分でも何を言っているのかわからない。怒られたばかりなのに、どうしてそんなことを言ったのか、僕自身が一番驚いていた。
でも、僕は無意識のうちに彼の隣に並び、そっと彼の手を握った。まるで子供が親に甘えるように、静かに、控えめに。
レグルスは立ち止まった。再び、あの威圧感が僕を包み込む。僕の指先が彼の手に触れた瞬間、再び魔素がかすかに揺れるのを感じた。紫の光がぼんやりと漂い、周囲の空気がピリピリと緊張に満ちる。
「貴様…………、何を考えている?」
声は静かだが、低く鋭い。怒っているというよりも、呆れているような感じだった。
僕は彼の手をそっと握ったまま、目を伏せて答えた。
「なんとなく…………。」
レグルス、君はいつも冷たく見えるけど、こうして触れると…………、少し違う気がして。
彼の手は思ったよりも温かかった。
冷酷で鋭利な魔王の印象とは裏腹に、その手には確かな温もりがあった。僕はそれを確かめたかったのかもしれない。
レグルスはずっと怖い存在だと思っていたけれど、その背後にあるものを少しだけ知りたくなったのだ。
しばらくの間、レグルスは何も言わなかった。
彼の瞳がどう動いているのか、僕には見えない。けれど、彼の手は僕の手から離れることなく、じっとそのままでいた。
「…………、貴様の好奇心には呆れ果てた。」
ついに彼がそう呟いた。僕は思わず顔を上げ、彼を見た。レグルスの表情は変わらず冷たいが、その目に以前ほどの鋭さは感じられなかった。
「だが、手くらいなら…………、許してやる。」
レグルスの言葉に驚き、僕は一瞬目を見開いた。あんなに怒っていたのに、手はいいと言ってくれるなんて――――。信じられない気持ちで、僕は少し笑ってしまった。
「ありがとう、レグルス。」
彼は何も返事をせず、ただ前を向いて歩き始めた。僕は彼の隣を歩きながら、手を繋いだまま、その温もりを感じていた。
怒られるのはわかっていたけど、こうして少しだけ、彼との距離が縮まったような気がする。
