試作_1104
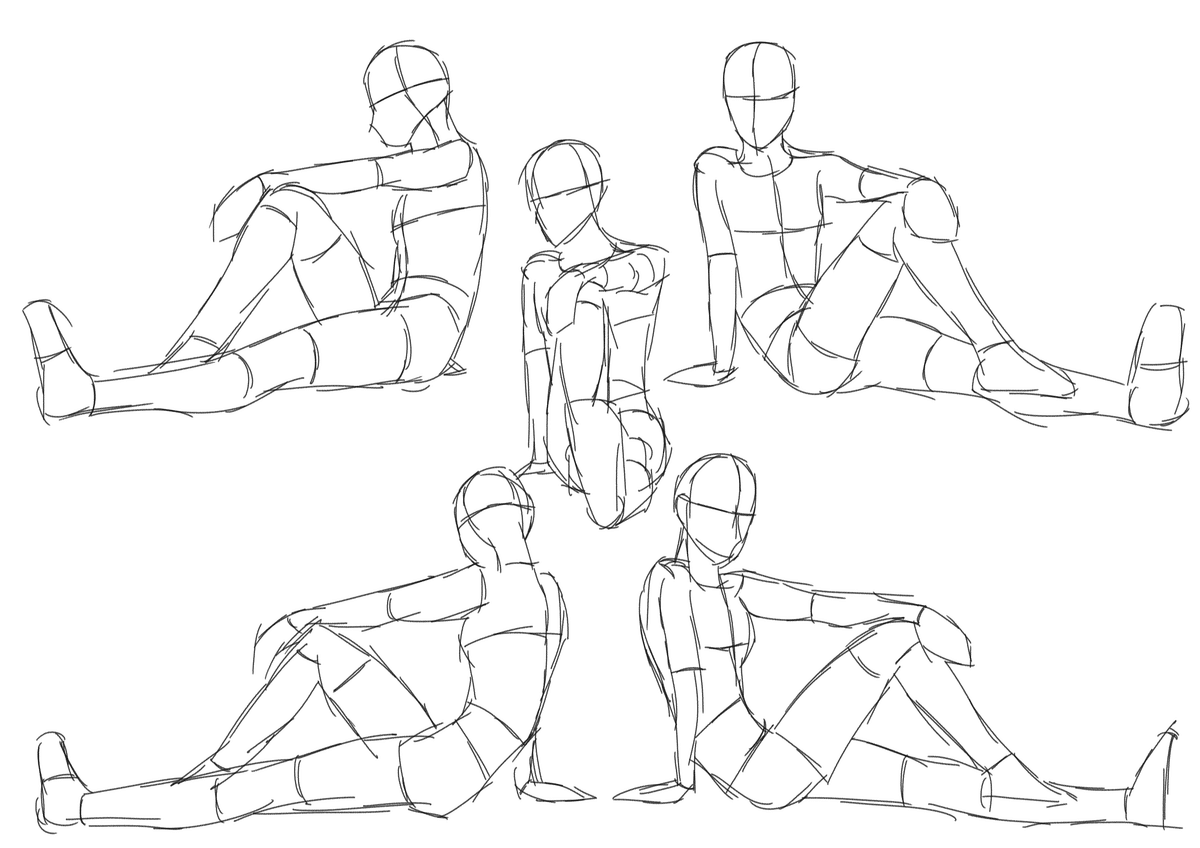

法学部のキャンパスの片隅で、僕は机に広げられた資料を眺める賢示を見つめていた。
彼は例のごとく真剣な表情で、眉間に皺を寄せている。いつも堅い表情をしている賢示が、今はうっすらと目を閉じ、ほんの少しだけ肩の力が抜けているように見えた。
「休憩中、なんだよね…………?」
僕はふと、彼の頬に触れてみたくなった。
普段なら到底許されない行為だ。けれど、今の彼はそれに気づくことなく、疲れた様子で椅子に深く腰掛けている。だから、僕は手を伸ばし、そっと頬を指先で撫でてみた。
「柔らかい…………。」
まるで小鳥のようにもふもふした手触りに、なんだか嬉しくなって、もう少しだけ指を滑らせてみる。
すると、賢示が突然目を開け、僕を睨みつけた。
「朦依、何をしている?」
その鋭い眼差しに背筋が凍る。いや、まさかここまでしっかり目を覚ますとは思っていなかった。
「いや、その…………。」
少し疲れているみたいだから、もふもふしたら気分が軽くなるかなと思って…………。
説明の途中で、自分が何を言っているのか分からなくなる。
賢示の表情はさらに険しくなり、深い溜め息が漏れる。
「君は…………、時々、わからない行動をするな」
嘴を引き結びながらも、怒っているようには見えない。
むしろその奥に、少しばかりの呆れと小さな笑いが含まれているような気がした。
僕の手が、まだ彼の頬に触れていることに気づき、慌てて引っ込める。
「次は気をつけろ、朦依。」
その一言と共に、再び資料に目を戻す賢示。しかし僕は、先ほどのもふもふの感触が忘れられず、口元に浮かぶ笑みを隠せなかった。
◇
講義が終わり、片付けをする賢示の姿をぼんやり眺めながら、僕はふと口を開いた。
「僕ね、心底、政治に興味が持てないんだ。」
自分で言っていて少し申し訳ない気持ちになったけれど、正直な気持ちを隠すのもどうかと思って相談してみた。
政治に対して無関心なままでいるのは良くない。頭では理解しているけど、どうしても関心が湧かない。
賢示は僕の言葉を聞くと、一瞬手を止め、大きく溜め息を吐いた。まるで一世紀分の溜め息をすべて吐き出すような重みのあるそれに、僕は少し身を引いた。
「朦依、君は本気で言っているのか?」
賢示の声には、いつも以上に重みがあった。僕は少し怯みつつも、曖昧にうなずく。
「別に、政治が嫌いってわけじゃないんだ。」
ただ、どうしても自分事って感じがしないっていうか…………。
説明しようとすればするほど、自分の無関心さが浮き彫りになってくるようで少し心苦しい。賢示の視線が鋭くなるのを感じながら、僕は口を閉じた。
賢示は机に資料を置き、腕を組んで僕を見つめた。
「君がそう感じるのも無理はないかもしれないが、政治というのは、君の暮らしや未来に密接に関わっているものだ。」
『自分事』でないと思っているかもしれないが、実際には君の生活にも大きな影響を及ぼしている。
賢示の口調はいつもと変わらない。しかし、その言葉には明らかに苛立ちと諦めが交じっているような気がする。
僕は軽い気持ちで相談したつもりだったけれど、どうやら彼にとってはそうではなかったらしい。
「――――、難しいな。」
僕には、どうしてもその大切さが実感できなくて。
賢示はもう一度深く溜め息をつき、眉間に皺を寄せながら僕を見つめている。
まるで「どうすれば君が分かるのか」とでも言いたげな顔だ。
「なら、少しずつでいいから考えてみろ。」
君の将来、君の周囲の人々、その生活すべてが、政治によって左右されることを。
彼の真剣な表情を見ていると、少しずつ僕の中にも『自分事』としての政治の影が浮かんできたような気がした。
◇
「でも僕、正直、長生きするつもりもないから。」
軽い気持ちで肩を竦めながらそう言った途端、賢示の顔色が変わった。そして、一瞬のうちに彼の大きな手が僕の顎を掴み、強制的に顔を上げさせられる。
「どういう意味だ、それは。」
低く静かな声。鋭い目が僕を捉えていて、彼が本気で怒っていることが手に取るように分かった。思わず目を見開き、戸惑いながら口を開く。
「へっ!?」
何故、こんなにも彼は怒っているんだ!?
焦って手を振ってみせたけれど、賢示は僕の言い訳なんか聞く耳を持たない様子で、視線を外そうとしない。
まるで、僕の心の奥底を覗き込むように、真剣な眼差しを向けてくる。
「長生きするつもりがない、などと軽々しく言うものではない。」
君がどう感じていようと、君の人生には価値がある――――。
「君自身が気づいていなくても、な。」
彼の言葉にはどこか苛立ちと共に、僕の想像を超えたような強い感情が込められている。
僕の他愛のない一言に、こんなにも反応するなんて思わなかった。
「賢示、そんなに真剣に捉えなくてもいいよ。」
その言葉に、彼の眉が少し寄る。そして、握られていた顎がようやく解放された。
賢示は一瞬目を伏せ、深い溜め息を吐く。
「朦依、君はもっと自分を大切にしろ。」
それが、他人をも尊重するということだ。
その一言が、どこか深く胸に刺さる。
彼がなぜここまで怒ってくれたのか、今はまだよく分からない。
だけど、賢示の表情には何か僕には理解しきれない思いが込められているような気がして、僕はただ無言で頷いた。
◇
嗚呼、苛立つ。
朦依の言葉が耳から離れない。
『正直、長生きするつもりもないから』だと?
まるで自分の人生をただの飾りか何かのように、軽々しく扱っている。
その肩を竦める仕草、冗談のつもりだったのかもしれないが、私にはそう思えなかった。
何故、彼は自分の人生をそんなふうに見ているのか。
何が彼にそう思わせているのか。
分からない。
理解できない。
それがまた、腹立たしい。
私が顎を掴んで問い質したときも、彼はただ驚いた顔で目を丸くしていた。
(何故だ?)
何故、私が怒っているのか。朦依は本当に分かっていないのか?
彼の顔には無邪気な表情が浮かんでいて、私はそれをただの鈍感さだと切り捨てることもできた。
だが、違う。朦依は鈍感というよりも、ただ自分を『他人事』として見ているのだ。まるで、自分の存在にはそれほどの意味も、価値もないかのように。
苛立ちと共に、かすかな恐怖が胸を締め付ける。
もし彼が、この先もそんな気持ちで生き続けるのなら、一体どうなってしまうのか。
彼は、私の知る限り、人の喜びや悲しみに寄り添うことができる人間だ。
それなのに、彼が自分自身を見つめるときだけ、なぜこんなにも曖昧で無関心なのか。
「君はもっと自分を大切にしろ。」
自分でも呆れるほど、理屈っぽい言葉を口にしてしまった。
けれど、それ以外に伝える術を持ち合わせていなかった。
私が何かを変えられるわけではないが、せめて彼が自分を無視するようなことだけは、してほしくないのだ。
◇
しかし、だ。
どうしてこうも苛立ちを感じるのかと自問すれば、その答えはすぐに浮かんだ。
結局、私は彼の持つ『空虚』に惹かれたのだ。
それが、彼との出会いの始まりであり、今でも変わらず私を縛り付ける魅力の根源だ。
朦依の描く『空虚』には、圧倒的な美がある。
彼の筆が生み出すのは、静寂に潜む影のような、冷たい美しさだ。
虚ろな空間と陰影が織りなすその世界に、私は心を奪われた。
あの美しさは、決して明るいものではない。むしろ、無関心で、内側から崩れていくかのような儚さすら感じさせる。
だが、それこそが私にとって、言葉にならない魅力だった。
『空虚』とは、通常ならば忌避されるものだ。
人は皆、その内側を埋めようと躍起になり、隙間なく満たされることを望む。
しかし、朦依は違った。彼はその『空虚』すらも受け入れ、時にはそれを意識的に描き出しさえする。自らの感情を削ぎ落とし、ただ静かに存在することを良しとしている彼の姿には、皮肉なほどに美しさが宿っている。
だからこそ、私は彼に苛立つ。彼の持つ空虚さと、それを美しいと感じてしまう自分に。
彼が自分の価値を見出せないのなら、私はその価値を見せつけるまでだ。
私が魅了されたものが、ただの虚ろな殻などで終わってほしくはないのだから。
