試作_0916

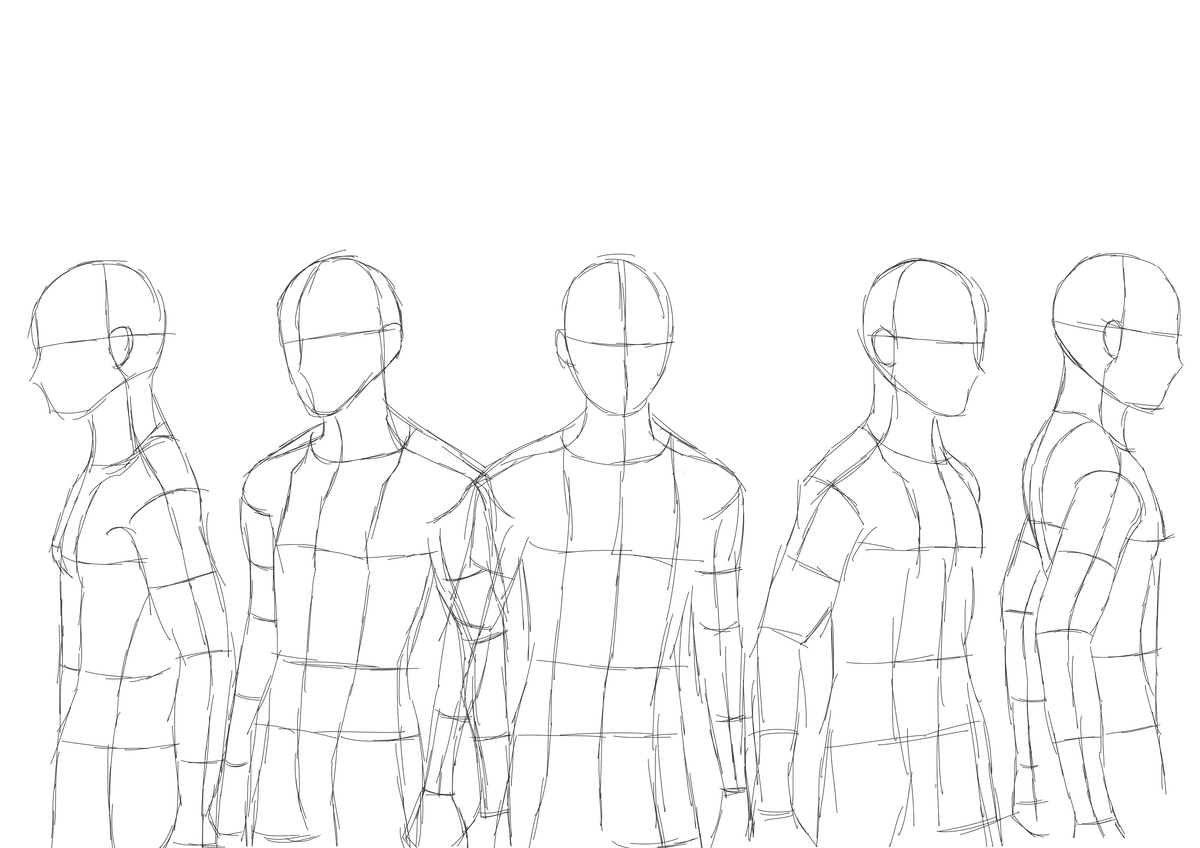


椅子に座って二時間。僕はペンを持てないままでいた。
絵を描くつもりがネットサーフィンに勤しんでしまっている。不真面目。しかしながら言い訳をさせてほしい。刺激が足りないのである。
創作意欲を突き動かしてくれる刺激。自分が見たいもの。それが漠然としている。わかりやすく言うなれば、やる気が出ない。
「んー…………。」
僕はスマートフォンを手に取り、シルヴァンに短いメッセージを送る。僕の数少ない創作の仲間。迷惑だろうが、このくらいは許してほしい。
数時間後、インターホンが鳴った。まさか――――。
「えっ。シルヴァン、何かあった?」
僕は狼獣人の訪問者――――、シルヴァンの顔を見上げる。まるで昨日、読んだ漫画のような展開である。あれは恋愛感情を抱いた者の行動であるが。
「困っているのだろう?」
「それは、まあ…………。」
正直、会うことになるとは思っていなかったが。もしかして、重症であると勘違いされているのだろうか。ならば、早い内に誤解を解かなくては――――。
「シルヴァン――――。」
「行くぞ。」
「へっ!?」
手を取る行動に、素っ頓狂な声を上げてしまう。慌てて戸締りを確認して、何となく、再びシルヴァンの手を握る。
――――。シルヴァンは重度の潔癖症ではなかっただろうか。僕は歩き始めた彼の横顔を盗み見る。相変わらずの無表情である。
「あっ。」
「どうした?」
「んーん。何でもない。」
…………。尻尾、少し揺れていた。
「で、どこに行くの?」
「ただの散歩だ。行き先はない。」
「そっか。」
二人で手を繋いだまま、静かな町を歩く。特に話すことはない。語弊があるだろうが、僕はシルヴァンに対して、気を遣うつもりはない。
「シルヴァン、あの茂みに連れ込んでもいい?」
「何故だ。」
「犬吸いするから。」
「俺は狼獣人だ。」
嗚呼、外の空気を吸うのも悪くない――――。
「君は家に籠りすぎだ。」
「で、でもぉ、外に出る用事がないしぃー。」
「ほう。用事があれば、外に出るのだな?」
「…………。たぶん。」
僕の言葉に、息を吐くシルヴァン。仕方ないだろう。春夏秋冬、僕は家の中にいたいのである。
「俺が連れ出してやる。」
「えっ。カッコイイね、シルヴァン。」
「うるさい。」
あっ。顔が赤くなった。かわいい。
「――――。今日はペンが動かなくて。」
「家に籠っているからだ。」
「否定はしないよ。」
僕が笑うと、シルヴァンも微笑んだ。やっぱりカッコイイな。
シルヴァンの言葉には、優しい響きがある。だから、心が落ち着くんだ。
仮に黙っていても、隣にいるだけで、心が安らいでいく――――。そういう不思議なものを、僕は彼から感じていた。
「そろそろ帰ろう?」
「もう大丈夫なのか?」
「うん。」
と言っても、万全ではない。今日は牛歩よろしく、無理をしない程度に作業を進めて休むとしよう。
「愛してるよ、シルヴァン。」
軽口を叩くように言葉が出たが、それは素直な気持ちでもあった。しかし、シルヴァンの表情が一瞬、変わった。苛立ちのようなものが伝わってくる。
「そう軽々しく愛を口にするな。」
「えー?」
おどける僕の手を強く握る。シルヴァンは重度の潔癖症――――。再び思い出す文句。しかしながら、顔を赤くする彼へ言うほどに、僕は愚かではない。
「照れてるの?」
「…………。」
「シルヴァン――――。」
「俺は、そう簡単に流されるつもりはない。」
シルヴァンの真剣な声に、僕は目を見開いた。軽率な発言を、彼は真面目に受け止めたらしい。
「相変わらず、君は誠実だね。」
「君にだけだ。」
「へっ!?」
耳元で囁かれて、顔が熱くなる。心の中で舌打ちする。憎たらしい狼獣人の男が微笑んでいる。
「僕が悪かった。」
「分かればいいさ。」
僕らの間に静かな沈黙が流れ、そして、再び歩き出す。
言葉は必要なかった。手を繋いで、一緒に歩く。それだけで、十分に心は温かいのだから。
