
プロジェクトのクオリティを高めるチームの作り方【デザイナー編】
こんにちは! アツラエnote編集部、UXプランニングチームの山下です。
【アツラエではたらく人】マガジンでは、アツラエで働くってどんな感じなのか、どんな人が働いているのか、ご紹介していきます。
アツラエはシステム開発だけではなく、デザイン・コンセプト・ブランディング・企画を強みとしており、アツラエではたらく人もまた、こだわりを持って働いている人が多くいます。
そんな一人ひとりのこだわりを覗いてみませんか?
今回は、クリエイティブチームでデザインを担当するスーパーデザイナー N氏とアートディレクターの小林をご紹介します。
スーパーデザイナー N氏
東京都出身。デザイン専門学校を卒業後、小さなデザイン事務所に就職し、雑誌やカタログ制作に従事。多忙な業務により2年で挫折するものの、体を動かす仕事を求めて配送の仕事のアルバイトを始める。そこでデザインのスキルがバレて、社内デザイン業務を担当。その後、紆余曲折あり、アツラエの親会社であるJMASに中途入社し業務アプリのUIやパンフレット制作に携わる。アツラエ創業後転籍。現在は、クリエイティブチームでアプリUIデザインやLPデザイン、コーディングやロゴデザイン等を担当。
小林
映像やWeb制作の現場で経験を重ねた後、ディレクターを兼務するかたちでデザイナーとしての活動を開始。
アツラエ創業とともに前進の会社から転籍し、現在はアートディレクターとしてDXや新サービスの立ち上げなど多くのプロジェクトに参加。
プロジェクトのクオリティを高めるチーム構築
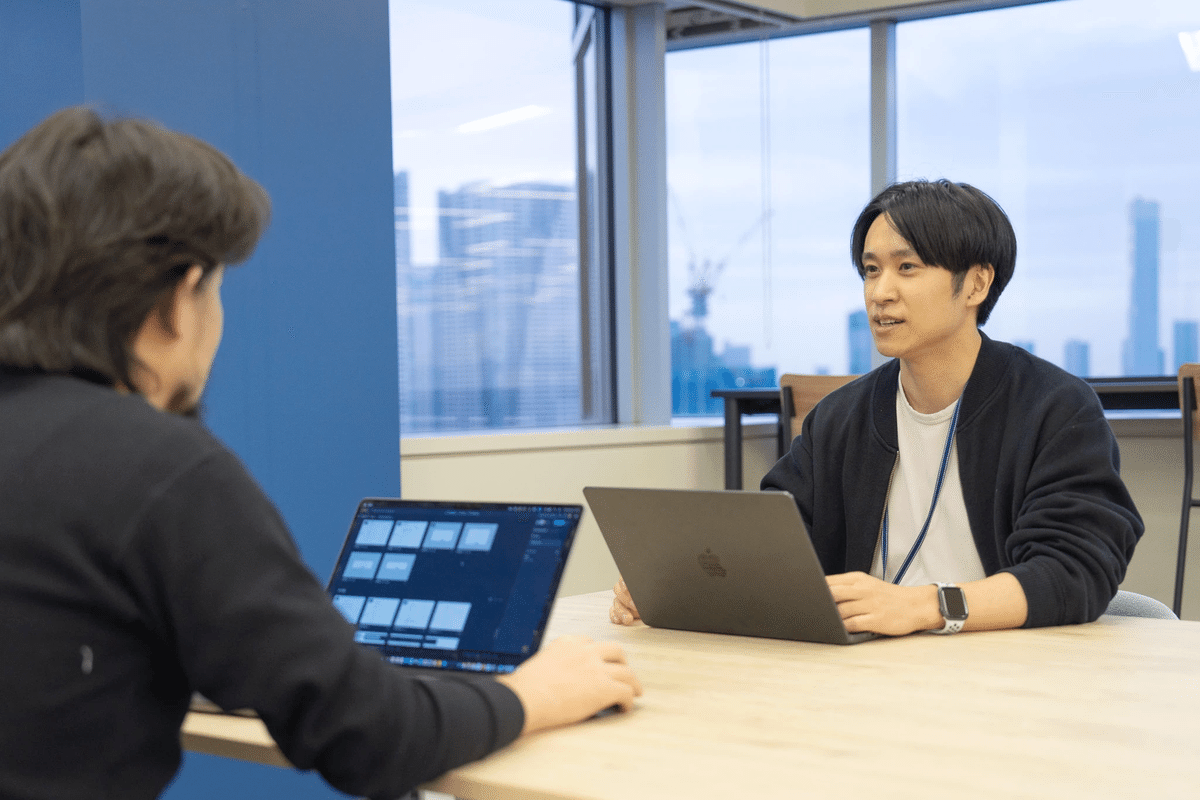
──デザイナーを志したきっかけはありますか?
スーパーデザイナー N氏:
モノを作る事が好きだった為と、自分がした事で誰かが喜んで貰える事がしたかったので。「デザイナー」を名乗ることで自慢ができそうといった、不純な動機もその一つ。
小林:
Webやサービス開発のディレクションをしていた期間がながく、大小さまざまなプロジェクトに参加してきました。
経験を重ねていくなかで「ユーザーが直接触れるデザインの領域にもっと深く関わりたい」という気持ちが強くなり、ディレクターと兼務する形でデザイナーとしてのキャリアをスタートしました。
──アツラエでは「デザイナー」と「アートディレクター」が相棒として、二人三脚でプロジェクトに取り組むと聞きましたが、なぜそのようなチーム制になったのでしょうか。
スーパーデザイナー N氏:
それぞれの専門性を活かし、プロジェクトのクオリティを高めるためですね。
デザイナーはビジュアル制作、アートディレクターは、戦略立案とクライアント対応を担当します。役割分担が明確なため効率的かつ柔軟な進行が可能であると考えています。
──専門性を活かした高品質なアウトプットと、効率的なプロジェクト進行。そして柔軟な課題対応が、このチーム制によってできるというわけですね。
スーパーデザイナー N氏:
クライアントにとっては、要望が正確に反映されたデザイン。戦略的で安心感のある進行。そして長期的なブランド価値の向上が望めます。
小林:
逆に、新しいサービスの検討を集中して行うプロジェクトでは、アートディレクターがデザインも行い、素早いサイクルで検証を行うこともあります。
アツラエでは、プロジェクトが目指すものに合わせて、最適な体制を提案しています。
──デザイナーとアートディレクターの違いはなんでしょうか?
スーパーデザイナー N氏:
デザイナーは「形を作る職人」、アートディレクターは「全体を導く指揮者」。両者が連携することで、魅力的なアウトプットを生み出すことが出来ると考えています。
視覚的にわかりやすく
思い込みを排除し
使う人の視点に立つことの大切さ
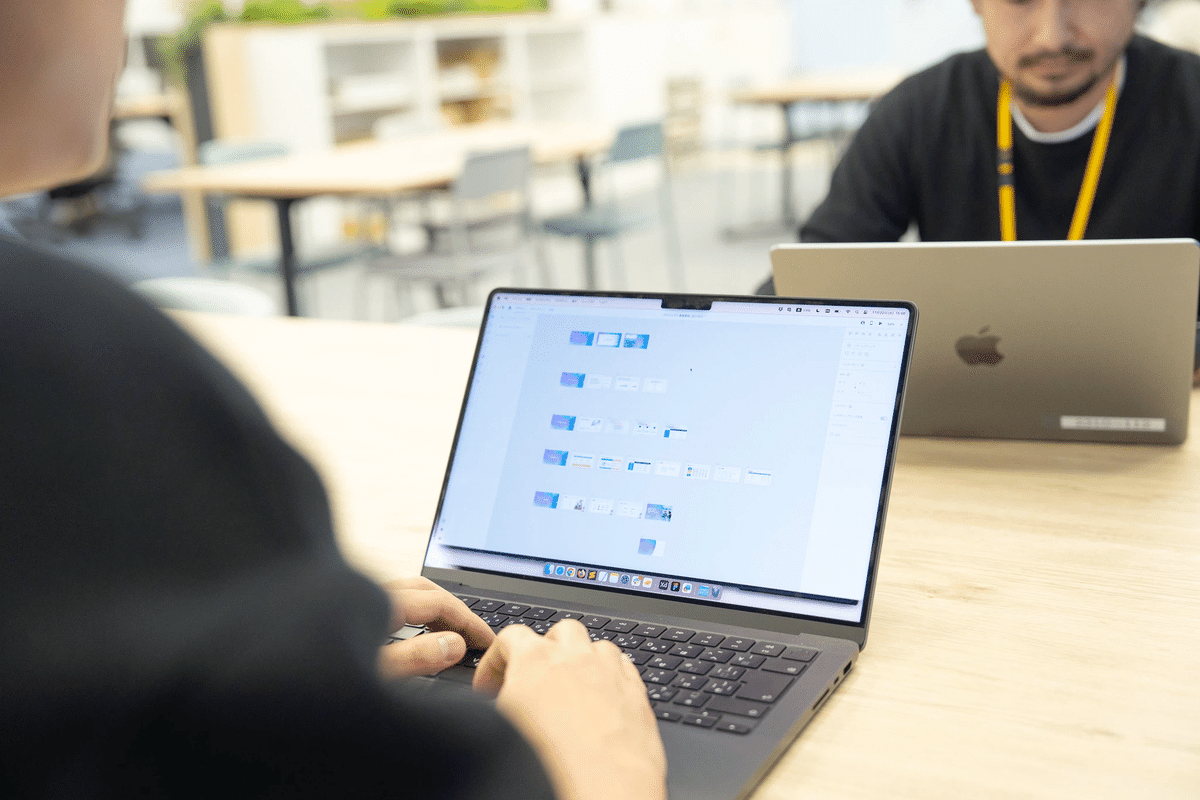
──これまでに印象に残っているプロジェクトはありますか?
スーパーデザイナー N氏:
印象に残っているプロジェクトの一つは、顧客応対管理システムのUI制作です。
顧客応対管理システムのUI制作では、まずクライアントから求められる要件を理解し、システム利用者の視点に立つことを大切にしました。
視覚的にわかりやすくするために、情報の配置やアイコン、ボタンの大きさや色の工夫など、細部まで気を配り、直感的に操作できるデザインを目指しました。
顧客応対の負担を減らし、効率的な業務が可能になるよう、UI改善にも力を入れたことが印象に残っています。
現場の利用者から、いろいろなフィードバックや感想をいただけたことが、大きなやりがいを感じた瞬間でした。
これからも誰かに喜んで貰えるデザインを作りたいと思いましたね。
小林:
まったく知らない領域を深く知ることができるのも、お客さまのサービス開発を担う面白さだと思っています。
例えば、幅広い層の方が利用するサービスを担当していた時に、生年月日の入力フォームひとつとっても、様々なご事情で、「生まれた日付や月を持たない方への配慮が必要」というリクエストを受けたときの「ハッ」とする感覚はいまでも覚えています。
生年月日の入力フォームは何度も制作してきましたが、生まれた月や日付がない可能性を検討したこともない自分の思い込みに気づかされました。
それ以降、新しくプロジェクトに関わるときには、その領域の「当たり前」と「可能性」のふたつには特に注意して取り組むようになりました。
そういう経験からも、より広い視点から人によりそったサービス開発が、できるようにしていきたいです。

──最後に、普段インプットなどは、どうされていますか? 面白かった本や映画があれば知りたいです。
スーパーデザイナー N氏:
旅行や音楽や自分が好きなことをして、刺激を受けることです。
SNSとかでもなんでも良いので。
「しなくちゃ」と思って、嫌いな本を読むインプットより、絶対効果的だと思います。
現実としては、ロゴデザインで中々思いつかない時は、ロゴデザインの本を見まくりますが。ヒントが見つかる時が絶対にあるので。
小林:
SNSをきっかけに紹介されている記事や本を読むことが多いです。
ただ、SNSはざっと見ているだけでも情報が溢れてくるので、最近では「Craft」というメモエディタアプリを使って、その日気になった情報を貯めて、後から一覧できるように整理をしています。
お勧めしたい一冊は「好き」を言語化する技術
「推しが好き」というポジティブな気持ちを軸に、それを言語化して伝える方法がわかりやすくまとめられています。
いまの仕事でも印象を言語化する作業が多く、それも改善に向けた言語化がほとんどなので、ポジティブな気持ちをどう形にするのか、という視点は新鮮でした。
「戦略とものづくり」と立場を明確に分けるチームビルドによって、魅力的なアウトプットを生み出すアツラエのクリエイティブチーム。
お客さまにとっても、提供できる価値の最大化ができている「デザイナー」と「アートディレクター」の二人三脚の様子をご紹介しました。
