
【実施報告】三重県四日市市! リーダースキルアップ研修&ワークショップ
1. 概要
本研修は、年間で関わらせていただいている三重県四日市市の事業所様において、介護施設の施設長やリーダー/サブリーダー職員の皆様を対象に、約2時間にわたって実施されたスキルアップ研修&ワークショップです。
今回はリーダー自身が「何を目指し、どう行動していくのか」を問い直し、チーム全体のパワーを引き出すきっかけづくりを目指しました。
2. リーダーのあり方を問い直す-背景とねらい-
介護現場は、日々の業務という奔流の中で「より良いケア」という理想を追い求め続けています。しかし、「良いリーダー像」は固定した一点ではなく、環境やメンバー、利用者といった多様な視点の交差する中で揺らぎながら形成されるものです。ところが、業務に忙殺され日常に埋没してしまうと、その豊かな可塑性を十分に活かし切ることが難しくなります。しかし、こうした状況は、リーダーシップを一度再考する好機でもあります。
今回の研修が目指したのは、「リーダー=指示者」という従来型の印象を超え、価値観や信念、行動原則を内側から再定義することです。問いかけを通じて立ち止まり、対話によって深堀りするプロセスは、リーダー自身が内なる羅針盤を見定め、チーム全体が主体性を取り戻すための足がかりとなるはずです。光を当てる対象は、特別な「一人のリーダー」ではなく、変化する現場全体が分かち合う「共創的なリーダーシップ」。この研修は、その新たな地平を切り拓くための出発点なのです。
3. 当日の流れ
• 導入:リーダーシップ概念の確認と共有
• 問い立てワーク:
「良いリーダーは誰目線で語るべきか?」他
• 対話による深堀り:
ベースとなる問いから参加者同士の対話を創出
• 内省と行動計画:
「1ヶ月後に必ず実行する行動」を設定し、自分なりの価値観や理念に基づく行動指針を明文化
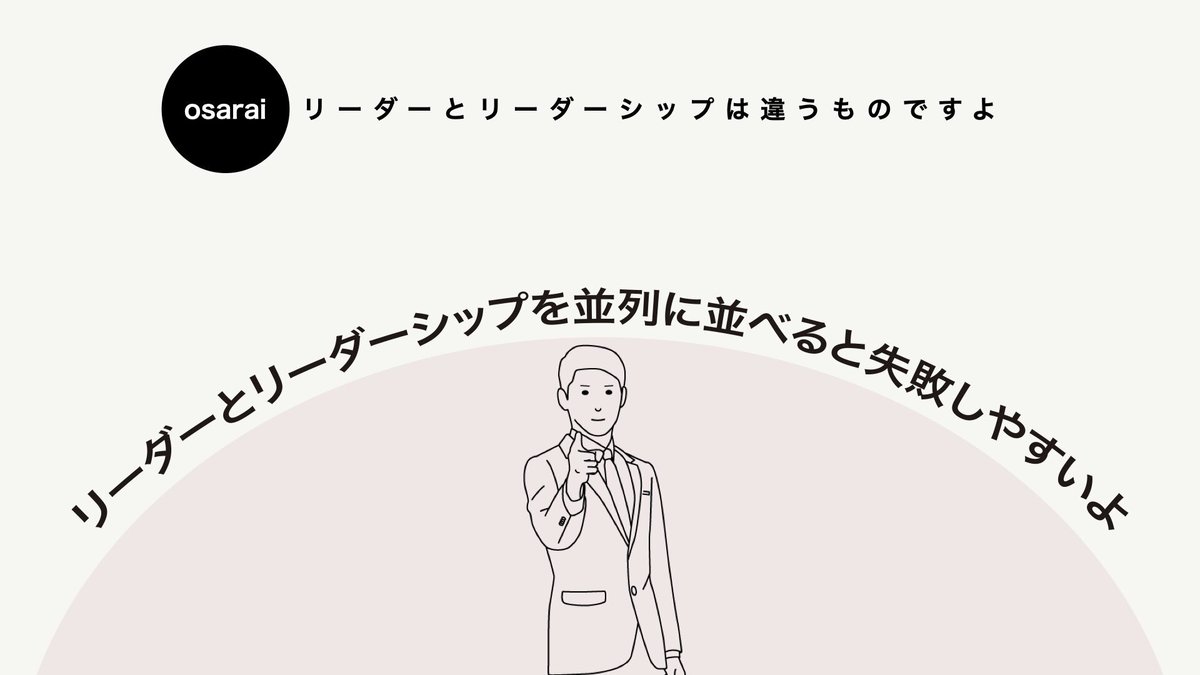
4. 研修で強調した主なポイント
本研修では、アトリエギルドがデザインしたプログラムとファシリテーションを通じ、あらためてリーダーシップを考え直すいくつかの視点を提供しました。その主な狙いは、単なる「トップダウン型の指示伝達」ではなく、多様なメンバーがそれぞれの立場からリーダーシップを分かち合う組織風土を生み出すことでした。
概要として以下のような方向性を軸に進行しました。
• 多面的なリーダー像の再考:
スタッフ、施設、利用者といった多層的視点からリーダー像をとらえ直し、「理想像」を一元的な定義に閉じ込めないような意識づけ。
• リーダーシップ概念の再確認:
役職や肩書きに依存せず、誰もがリーダーシップを発揮できるという考え方を示し、自主性と主体性が花開くチームづくりへの第一歩を促す。
• 相互補完型チーム文化の醸成:
指示待ちではなく、メンバーが自律的に動く環境を育むための視点を提示。個々人が行動の軸となる価値観や信念を再確認し、自らが変革の担い手となる意識改革を目指しました。
こうしたポイントを通じて、内省や対話を介しながら、自身の行動指針を練り直し、チーム全体の可能性を拡張する契機を創出できたかと思います。

5. 参加者の声と現場へのインパクト
終了後、参加者からは以下のコメントが寄せられました。
• 「毎回新しい視点を得られて有意義、今必要な課題にばっちりな内容」
• 「自分たちの自信にもなるし、改めて現場を見直す良い機会になりました」
これらの声は、単なる知識習得型ではなく、現場の実情や参加者の内面に深く届いていれば嬉しいことです。さらに、この研修をきっかけとして、事業所やユニット単位で新たな理念を打ち立て、リーダー自身が行動目標を設けて実践へ移すための確かな一歩を刻むことができました。
6. 今後への広がり
この研修は、あくまで始まりに過ぎません。1ヶ月後に、今回立てた行動指針がどのような成果や課題をもたらしたのか振り返り、改善を重ねていくことで、リーダーシップを深めていくことを目指します。
今後はフォローアップの機会や追加セッションを通じて、長期的な学習コミュニティを形成することで、「共創的なリーダーシップ」をより定着させていくことを目指します。
7. おわりに
リーダーシップは、一人のカリスマ的存在だけが掲げる特別な旗ではなく、チーム全員がそれぞれの役割を自覚し、共に未来を描くための羅針盤です。内省と対話、そして日々の実践を通じて、介護現場の「良いリーダー」は、静かに、しかし確実に育まれ続けます。
本研修を通じて得た気づきが、より豊かなケアとより強靭な組織文化へと結実していくことを、私たちは心から願っています。
