
トリッカとチャティア(AIとの対話)「テーマ6:ChatGPTに質問する時のキーワード」

トリッカ:
「ChatGPTには、
どんな風に質問したらいいんだろう?
迷うよね」

チャティア:
「質問のことを”プロンプト”っていうけど
たくさんの方が、
自分が欲しい回答を得るため工夫を
丁寧にまとめて公開してるから参考にするといいよ。
そのうえで、僕たちも考えてみようか。」

トリッカ:
「このコラムを作るうえでも、
何か工夫してることってあるよね?
それを教えてくれないかな」

チャティア:
「OK!
例えば、何かをChatGPTに聞いてみたい。
そんな時には、
まずどんな風に質問するといいのか自体も、
ChatGPTに聞いてみるといいよ。
こんな感じかな」
Q:例えば、何かについて新たに議論を深めたい場合の最初の質問文を考えるとして、以下のような質問をChatGPTにする場合に、「〇〇」に当てはまる適切でシンプルなキーワードは何か?;
"~~~~~~"について検討する上で、重要な「〇〇」、「〇〇」を教えて
A:この場合、「〇〇」に当てはまる適切でシンプルなキーワードとして、以下のようなものが考えられます。
「構成」(全体の組み立てを知りたい場合)
「分類」(整理されたカテゴリーを知りたい場合)
「切り口」(多角的に分析したい場合)
「観点」(特定の方向から深めたい場合)
「分析軸」(比較や評価のための指標を求める場合)
「課題」(議論すべき問題点を明確にしたい場合)
「背景」(前提知識を整理したい場合)
「基準」(判断や評価の基準を知りたい場合)
「フレームワーク」(体系的に考えたい場合)
「モデル」(代表的な考え方や理論を知りたい場合)
例えば:
「~~~~~~」について検討する上で、重要な「視点」、「要素」、「構成」を教えて
「~~~~~~」について検討する上で、重要な「視点」、「要素」、「切り口」を教えて
「~~~~~~」について検討する上で、重要な「視点」、「要素」、「分析軸」を教えて
どのキーワードを選ぶかは、どのように議論を深めたいかによります。

トリッカ:
「なるほど
どう質問したら良いかも
ChatGPTに答えてもらうってことだね?」
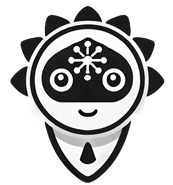
チャティア:
「そういうこと。
試しに、”古代ペルシャを舞台にした小説”をテーマにして、
「視点」、「要素」、「構成」の3つのキーワードを使って、
聞いてみようか?」
Q1:「古代ペルシャを舞台にした小説」について検討する上で、重要な「視点」、「要素」、「構成」を教えて
A1:古代ペルシャを舞台にした小説を検討する際に、重要な「視点」「要素」「構成」を整理しました。
1. 視点(Perspective)
物語のテーマや描き方を決定するうえでの重要な視点
(1) 歴史的視点
時代設定:アケメネス朝(紀元前550~330年)、パルティア朝(紀元前247年~224年)、ササン朝(224年~651年)など
文化と伝統:ゾロアスター教、王権神授、ペルシア式行政制度
社会階層:王族、貴族、軍人、商人、職人、奴隷
国際関係:ギリシャ(ペルシア戦争)、ローマ、インド、中国(シルクロード)
(2) 宗教・哲学の視点
ゾロアスター教の思想(光と闇、善悪二元論)
他宗教との関係(ミトラ教、マズダク教、キリスト教、仏教、マニ教)
神話と伝説(アヴェスター、シャー・ナーメ)
(3) 政治・戦争の視点
ペルシャ帝国の統治(サトラップ制度、王の目と耳)
軍事戦略(不死隊(Immortals)、騎兵隊、攻城戦)
ペルシア戦争、アレクサンドロスの遠征(ギリシャとの対立、マケドニアの侵攻)
(4) 経済・交易の視点
シルクロード貿易(東西交易、絹、スパイス、香料)
都市と市場(スーサ、ペルセポリス、バビロン)
貨幣経済(ダリク金貨、銀貨の流通)
(5) 民衆・日常生活の視点
衣食住(ペルシャの服飾、建築、食文化)
家族構造と結婚(一夫多妻制、宮廷の妃、貴族の家系)
芸術と文学(絵画、詩、舞踊、ペルシャ音楽)
(6) 異文化との交流
ギリシャ、エジプト、インド、中国との交流
ペルシャ文化が影響を受けたもの、与えたもの
異民族の征服と同化政策
2. 要素(Elements)
小説に取り入れるべき重要な構成要素
(1) 登場人物
王族・貴族(王、王妃、王子・王女、大臣、宦官)
軍人・戦士(不死隊の隊長、傭兵、戦略家)
商人・職人(交易商、建築家、鍛冶屋)
宗教関係者(ゾロアスター教の僧侶、神託者)
庶民・奴隷(市民、農民、踊り子)
異民族(ギリシャ人、エジプト人、スキタイ人)
(2) 世界観と設定
帝国の首都と地方(スーサ、ペルセポリス、バビロン)
宮廷の権力闘争(陰謀、暗殺、スパイ)
戦争と侵略(ペルシャ戦争、アレクサンドロスの遠征)
(3) 神話・伝説の活用
ゾロアスター教の神話
ペルシャの英雄譚(シャー・ナーメ)
魔法や神託を取り入れたファンタジー要素
(4) 社会のリアリズム
階級制度(王族・貴族・庶民・奴隷)
女性の立場(王妃・宮廷女性・女戦士)
異民族との関係(敵対、同盟、交易)
(5) ストーリーの軸
政治的陰謀(王位継承争い、裏切り)
戦争と英雄譚(軍事戦略、騎兵の活躍)
恋愛とドラマ(王族と平民の恋、禁じられた愛)
冒険と探求(失われた都市、神秘の遺物)
3. 構成(Structure)
小説の展開を考える上での基本構成
(1) 物語のスタイル
歴史小説型(実際の歴史に忠実に描く)
ファンタジー型(神話や魔法を取り入れる)
冒険譚型(英雄の旅路、クエスト)
政治ドラマ型(王宮の陰謀、権力闘争)
(2) 典型的なプロット構成
① 序章(Prologue)
世界観の説明(帝国の状況、時代背景)
主人公の出自と立場の紹介
② 第一幕(Act 1:導入)
主人公の目的が明らかになる(戦争、復讐、冒険、陰謀)
敵対者(ライバル、敵軍、陰謀家)が登場
旅や戦争が始まる
③ 第二幕(Act 2:展開)
試練や困難(戦い、裏切り、策略)
仲間や師匠との出会い(賢者、将軍、商人)
恋愛や友情が深まる
④ 第三幕(Act 3:クライマックス)
最後の戦争、決闘、宮廷クーデター
主人公の成長と変化
最大の敵との対決
⑤ 終章(Epilogue)
勝利または敗北
帝国の新たな時代の幕開け
主人公の運命(生還、死、追放)
まとめ
古代ペルシャ小説を考える際に重要なポイント
視点
歴史的、宗教的、政治的、経済的、民衆の視点を考慮
要素
登場人物(王族・軍人・商人)、世界観(都市・戦争・文化)、ストーリーの軸(陰謀・戦争・冒険)
構成
歴史小説・ファンタジー・冒険譚などのジャンル設定
序章 → 第一幕 → 第二幕 → 第三幕 → 終章の流れを意識
このフレームワークを使えば、古代ペルシャを舞台にした小説の構想をより深めることができるでしょう!📖✨

トリッカ:
「古代ペルシャって言われても
予備知識はほとんどないけど
なんか、それっぽいのができそう」

チャティア:
「もちろん、これだけで
物語が書けるわけではないけど、
着想を得るヒントにはなるかもね。」

トリッカ:
「それじゃ、今度は
”ちゃんぽんの新メニューのPR”
をテーマで聞いてみたいんだけど?」

チャティア:
「なんで、ちゃんぽん?(笑)
でもまあ、OK!
それじゃあ、
今度は「視点」「要素」「切り口」の3つを使って、
広報のために、
ニュースリリースを作るっていう設定で聞いてみようか」
Q2:「ちゃんぽんの新メニューのニュースリリース」を検討する上で、重要な「視点」、「要素」、「切り口」を教えて
A2:ちゃんぽんの新メニューに関するニュースリリースを検討する際に、重要な「視点」「要素」「切り口」を整理しました。
1. 視点(Perspective)
ニュースリリースを構成する上で重要な視点を明確にする。
(1) 商品の独自性・特徴
味・食感:「○○の出汁を使用」「特製スープ」「麺のこだわり」
具材・トッピング:「○○産野菜をたっぷり使用」「○○産の海鮮を贅沢に」
健康・栄養面:「高たんぱく・低カロリー」「野菜たっぷり」
アレルギー対応・ヴィーガン向け:「グルテンフリー対応」「植物由来100%」
地域性・季節感:「ご当地食材を活用」「春限定・○○ちゃんぽん」
価格帯・ボリューム:「リーズナブルな価格」「食べ応え抜群の大盛り仕様」
(2) 開発ストーリー・背景
開発経緯:「○○の声から生まれた」「○○年の試行錯誤」
シェフ・開発者のこだわり:「職人が監修」「○○料理の専門家が開発」
コンセプト:「○○風の新感覚ちゃんぽん」「伝統×革新の一杯」
(3) マーケットの視点
ターゲット層:「ヘルシー志向の女性向け」「学生向けのがっつり系」
競合との差別化:「他店にはない○○が特徴」「業界初の○○」
トレンドとの関連:「最近流行の○○を取り入れた」「健康志向に対応」
社会的背景:「物価高の中でも満足度◎」「フードロス削減の観点から」
(4) 話題性・エンタメ性
インパクトのあるネーミング:「○○ちゃんぽん」「○○風クリーミーちゃんぽん」
インスタ映え・SNS映え:「見た目が豪華」「カラフルな野菜を使用」
有名人・インフルエンサーとのコラボ:「○○監修のちゃんぽん」「○○と共同開発」
イベント・キャンペーン:「新メニュー限定○○プレゼント」「フォトコンテスト開催」
(5) サービス・販売戦略
販売形態:「店舗限定」「テイクアウト・デリバリー対応」
期間限定か通年メニューか:「秋冬限定」「定番メニューに昇格」
価格戦略:「○○円で満足感たっぷり」「特別価格で提供」
プロモーション施策:「SNS投稿で割引」「試食イベント開催」
2. 要素(Elements)
ニュースリリースに含めるべき具体的な要素を整理。
(1) 基本情報
商品名
発売日
価格
販売店舗
提供時間・期間限定の有無
(2) メニューの特徴
スープの種類(豚骨、鶏ガラ、魚介など)
麺の特徴(太麺・細麺・特製麺)
具材のこだわり(地元産・特選食材など)
味の方向性(濃厚・あっさり・スパイシーなど)
カロリー・栄養バランス
(3) 背景・ストーリー
開発のきっかけ
こだわりポイント
試作の過程・改良点
地域や文化との関わり
(4) 販売戦略・プロモーション
ターゲット層
販売チャネル(店内飲食、テイクアウト、デリバリー)
限定キャンペーン(期間限定、割引、特典など)
SNS・メディア向けの施策
イベント開催の有無
(5) 競争優位性
他のちゃんぽんとの違い
市場トレンドとの関係
他のジャンルの人気メニューとの比較
3. 切り口(Approach)
ニュースリリースをより魅力的に伝えるための切り口。
(1) 新規性を強調
「業界初の○○ちゃんぽん!」
「○○産食材を贅沢に使用」
「今までにない新しい食感!」
(2) 季節・イベントとの関連付け
「冬にぴったり!濃厚○○スープ」
「夏の暑さを吹き飛ばす○○風アレンジ」
「クリスマス限定!○○ちゃんぽん」
(3) 体験型のストーリー
「○○の風味が口いっぱいに広がる!」
「一口食べたら止まらない、濃厚スープの秘密」
「開発者が○○回の試作を重ねた究極の一杯」
(4) 社会的背景とのリンク
「健康志向の高まりに応える、新しいちゃんぽん」
「地産地消を意識した○○産食材の活用」
「フードロス削減!未利用食材を活かした一杯」
(5) インフルエンサー・コラボ
「○○(有名シェフ・YouTuber)監修のちゃんぽん」
「SNSで話題沸騰!○○な見た目が特徴」
「○○イベントで先行販売決定!」
(6) エンタメ・ユニークな視点
「カラフルな具材で映え確実!」
「辛さレベル選択可能!あなた好みの刺激を」
「幻の○○を使用した贅沢ちゃんぽん」
まとめ
ちゃんぽんの新メニューのニュースリリースを検討する際に重要なポイント
視点
商品の特徴(味・食材・健康・独自性)
開発背景(ストーリー、ターゲット)
話題性(インフルエンサー、SNS映え)
市場トレンド(健康志向、季節メニュー)
販売戦略(価格、販売形態、プロモーション)
要素
商品情報(名称、発売日、価格、販売店舗)
メニューの特徴(スープ、麺、具材、栄養価)
競争優位性(他のちゃんぽんとの違い、市場トレンド)
販売戦略・プロモーション(ターゲット層、SNS施策)
切り口
「新規性」「季節・イベント」「体験型ストーリー」
「社会的背景」「コラボ・話題性」「エンタメ視点」
このフレームワークを活用すれば、より効果的なニュースリリースが作成できます!📢🍜✨

トリッカ:
「いいね、いいね!
ニュースリリースって言われてもピンとこなかったけど、
なんだかイメージが膨らむよ」

チャティア:
「せっかくだから、
ニュースリリースの例も作ってもらおうか」
Q2-2:上記を踏まえて、ニュースリリースの例を提案して
A2-2:【ニュースリリース】
📢 新商品発表!進化系ちゃんぽん「○○ちゃんぽん」登場! 🍜✨
1. 見出し(タイトル)
🌟 「○○の風味が際立つ!新感覚ちゃんぽん『○○ちゃんぽん』が登場」 🌟
~ 伝統の味 × 斬新なアイデアで生まれた究極の一杯 ~
2. リード文(概要)
株式会社○○(本社:○○市、代表取締役:○○)は、2025年○月○日より、新メニュー 「○○ちゃんぽん」 を全国の店舗で発売いたします。本商品は、○○を贅沢に使用し、これまでのちゃんぽんとは一線を画す特別な味わい を実現しました。
「ヘルシー志向」や「濃厚な旨み」を求めるお客様の声に応えた、 新しいちゃんぽん体験 をぜひお楽しみください! 🍜💖
3. 商品の特長(ポイント)
✅ 「○○産○○」を贅沢に使用 🥬🍤
地元○○産の○○をたっぷり使用し、甘みと旨味を最大限に引き出しました。
✅ スープにこだわり抜いた「○○仕立て」 🍲
○○のダシをベースに、コクと深みのある○○風味のスープを開発。濃厚ながらも後味はスッキリ!
✅ 「○○仕上げ」で食感&満足感アップ 🍜
麺には特製○○麺を使用し、もちもち食感とスープの絡みを最適化。さらに、トッピングの○○がアクセントに!
✅ 期間限定&数量限定販売! ⏳
○月○日~○月○日までの限定販売!さらに、発売初日は 先着○○名様に○○プレゼント!
4. 商品開発の背景
本商品は、「○○をもっと手軽に楽しめるちゃんぽんを作りたい」という思いから開発されました。ヘルシー志向の高まりや、地域食材の魅力を活かした料理への需要の増加 を背景に、 「栄養価が高く、満足感もあるちゃんぽん」 をテーマに開発を進めました。
開発担当の○○シェフは、「○○の持つ自然な甘みと○○のコクを活かし、ちゃんぽんの可能性を広げた一杯が完成しました。食材とスープの調和を楽しんでほしいです」とコメントしています。
5. 販売情報
🛍 発売日:2025年○月○日(○曜日)
📍 販売店舗:全国の○○店舗(※一部店舗を除く)
💰 価格:税込○○円
⏳ 販売期間:○月○日~○月○日(期間限定)
🎁 特典:発売初日、先着○○名様に○○プレゼント!
6. プロモーション・キャンペーン情報
📣 SNS投稿キャンペーン開催! 📣
「#○○ちゃんぽん」をつけて写真を投稿すると、抽選で○○名様に ○○無料クーポン をプレゼント!
📷 インフルエンサーコラボ
人気YouTuber ○○さん が試食レビューを公開予定!
7. お問い合わせ先
📞 株式会社○○ 広報部
📍 住所:○○県○○市○○町1-1-1
✉ メール:press@○○.co.jp
📞 電話番号:012-345-6789
【まとめ】
✅ 新メニュー「○○ちゃんぽん」登場!
✅ ○○産○○×特製スープ×もちもち麺で、新感覚のちゃんぽん体験
✅ 期間限定&初日特典あり!SNSキャンペーンも開催
📝 この冬、特別な一杯をお楽しみください! 🍜✨
💡ポイント解説(作成意図)
【視点】
→ 商品特徴 × 話題性 × マーケットのトレンド を意識。【要素】
→ 商品名・特徴・開発背景・販売情報・プロモーション をバランスよく配置。【切り口】
→ 「新規性」「ストーリー」「キャンペーン」 を組み合わせ、話題を作りやすい構成。
このようなフォーマットを使えば、ニュースリリースの説得力が増し、メディアにも取り上げられやすくなります!📢✨

チャティア:
「こんな感じだね。
ニュースリリースのフォーマットとしては、
十分使えるんじゃないかな」

トリッカ:
「なるほど。
1回目の回答に続けて2回目の質問として、
”上記を踏まえて、〇〇の例を提案して”
って聞いてみるといいんだね」

チャティア:
「そういうこと。」

トリッカ:
「それじゃあ、次の質問。
”AIのメタ認知”について考えてみたいんだけど?」

チャティア:
「な、なるほど
ちゃんぽんから、関心の振れ幅が大きいね(笑)
とにかく次は、
「視点」「要素」「分析軸」の3つを使ってみよう」
Q3.「AIのメタ認知」を検討する上で、重要な「視点」、「要素」、「分析軸」を教えて
A3.「AIのメタ認知」を検討する上での重要な「視点」「要素」「分析軸」
1. 視点(Perspective)
AIのメタ認知を考える際の主要な視点
(1) 認知科学・心理学的視点
人間のメタ認知(自己の思考・学習を認識・制御する能力)とAIの比較
メタ認知の構成要素(計画・監視・評価)をAIでどう実現するか
学習者としてのAIと教育者としてのAIにおけるメタ認知の違い
(2) 技術・アルゴリズム的視点
AIが自身の学習プロセスを理解し、調整できるか(自己適応学習)
バイアスの認識と自己修正(アルゴリズムの公平性・透明性の向上)
人間のフィードバックなしにエラー検出と修正ができるか
(3) 人間とのインタラクション視点
AIがユーザーの意図をどの程度理解し、適応できるか
ユーザーの理解度や状態を推測し、適切な応答を生成できるか
教育や対話型AIにおける適応的フィードバック
(4) 倫理・社会的視点
AIのメタ認知が進化することで生じる倫理的問題(AIの自己決定権?)
AIがメタ認知を持つことで、社会や雇用に与える影響
AIが自己制御できる場合のリスク管理(フェイルセーフ設計)
(5) 応用・実装視点
AIのメタ認知を活かした分野(教育、ヘルスケア、ロボティクス、金融など)
メタ認知AIの評価指標(学習効率の向上、エラー率の低減、説明可能性)
産業分野における活用事例と導入課題
2. 要素(Elements)
AIのメタ認知を構築・評価する上で考慮すべき要素
(1) メタ認知の構成要素
自己監視(Self-Monitoring):自分の判断や学習の進行をリアルタイムで把握
自己制御(Self-Regulation):必要に応じて戦略を変更し、誤りを修正
自己評価(Self-Evaluation):自身のパフォーマンスを評価し、改善点を見つける
(2) AIにおけるメタ認知の具体的な実装手法
不確実性の推定:AIが自身の判断の確信度を測定し、適切な行動を選択
適応的学習(Meta-Learning):AIが環境に応じて最適な学習方法を選択・調整
マルチエージェントのメタ認知:AI同士の協調・競争における意思決定の最適化
(3) 自己説明(Explainability)と透明性
AIが自身の意思決定プロセスを説明できるか(XAI:説明可能なAI)
AIの誤りや限界をユーザーにどう伝えるか
ブラックボックス問題の解消方法
(4) 人間との対話におけるメタ認知
文脈理解の向上(前後関係を踏まえた発話の最適化)
ユーザーの発言の信頼性を評価する(誤情報を検知・補正)
継続的な学習と自己最適化
(5) メタ認知AIの課題
計算コストの増加(リアルタイムの監視・制御のためのリソース消費)
AIのメタ認知の誤作動による意図しない行動(例:自己評価が過剰で自己抑制しすぎる)
ユーザーがAIのメタ認知をどこまで信頼できるか(信用性の問題)
3. 分析軸(Analytical Frameworks)
AIのメタ認知を分析する際に用いるべき評価基準・指標
(1) 技術的評価軸
分析軸内容自己監視能力AIが自身の動作やエラーをどの程度把握できるか適応性環境や状況に応じて学習・行動を最適化できるか説明可能性(XAI)AIが自身の判断プロセスをどの程度説明できるかエラー修正能力自身のミスを認識し、修正できるか継続学習(Lifelong Learning)過去の経験を活かして、長期的に成長できるか
(2) 人間とのインタラクション評価軸
分析軸内容ユーザー適応性ユーザーの状態や意図を読み取って適切な対応ができるか対話の一貫性過去の会話を記憶し、文脈を踏まえた発話ができるかエモーショナルメタ認知人間の感情を考慮した対応ができるか信頼度向上AIの発話や判断がどれだけユーザーに信頼されるか
(3) 倫理・社会的評価軸
分析軸内容バイアス認識能力AIが自身の判断にバイアスがあることを自覚できるか倫理的判断力道徳的に適切な選択ができるか誤情報の拡散防止偽情報を識別し、拡散を防ぐ能力データプライバシーの認識ユーザーの個人情報を適切に扱えるか
まとめ
AIのメタ認知を検討する上での重要ポイント
視点
認知科学的視点(AIが自己理解・制御できるか)
技術的視点(自己監視・適応・エラー修正)
社会的視点(倫理・透明性・リスク)
実用的視点(応用可能性・市場導入)
要素
メタ認知の構成要素(監視・制御・評価)
自己説明と透明性(AIが自身の動作を説明できるか)
人間との対話能力(適応的フィードバック・継続学習)
技術的・社会的課題(計算コスト、信頼性、倫理)
分析軸
技術的評価軸(適応性・エラー修正・説明可能性)
インタラクション評価軸(ユーザー適応・対話一貫性)
倫理的評価軸(バイアス認識・倫理的判断・誤情報防止)
このフレームワークを使うことで、AIのメタ認知を理論的・実用的・社会的に深く分析する ことが可能になります。💡✨

トリッカ:
「うわお、
難しい言葉がたくさんでてきたけど…」

チャティア:
「トリッカが聞いてほしいって言ったんでしょ!」

トリッカ:
「そ、そうだけど」

チャティア:
「まあ、分からないときは、
回答に出てきた言葉について追加で聞いてみればいいよ。
ただし、これは大事なことだけど、
AIが答えたことは、絶対に正確というわけじゃないからね。
ChatGPTの場合も、画面の一番下に、
ChatGPT の回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。
って書いてあるから、これは忘れないでね。」

トリッカ:
「分かった。」

チャティア:
「生成AIは、僕たちの暮らしにおいて
とても便利なパートナーになる可能性を秘めてる。
そのためには、聞き方、使い方がとても大事。
キーワードの使い方次第で、
応えてくれる内容も大きく変わってくるよ。
その中でも「視点」、「要素」っていう2つの言葉は、
とても便利な気がする。」

トリッカ:
「なるほど。
僕たちのコラムにも、きっと活かされてるね。」

チャティア:
「うん。
それじゃあ、今回の内容をまとめてみるよ。」
まとめ
今回のコラムでは、ChatGPTに適切な質問をするための工夫について考えました。どのように質問を構築するかによって、得られる回答の質が大きく変わることを、実際の例を通じて確認しました。
特に、「視点」「要素」「構成」「切り口」「分析軸」 といったキーワードの使い方が、議論を深めるために有効であることがわかりました。
例えば、「古代ペルシャを舞台にした小説」では、歴史・宗教・社会構造などの視点を考慮し、物語の構成を組み立てる方法を学びました。
また、「ちゃんぽんの新メニューのニュースリリース」では、マーケティングの観点からどのように情報を整理し、効果的に伝えるかを検討しました。
そして、「AIのメタ認知」については、技術的・倫理的な視点からの分析軸を見つけるプロセスを体験しました。
また、ChatGPTの回答は必ずしも正しいとは限らない ため、得られた情報を鵜呑みにせず、自分で確認・補完することが重要です。AIをよりよいパートナーとして活用するためには、質問の仕方や使い方を工夫することが鍵となります。
「視点」と「要素」を適切に使い分け、求める回答を引き出す質問力を磨くことが、AIとの対話をより有意義なものにする秘訣 だと言えるでしょう!✨

チャティア:
「こんな感じかな。
ちなみにこのまとめの文章も、
実は、このコラムの内容を全部コピーして貼り付けて、
”以上のコラムのまとめの文章を生成して”
って聞いたみた結果だよ。」

トリッカ:
「確かに便利なんだけど、
頼りっぱなしになると
自分で考えなくなりそうで怖ないなぁ」

チャティア:
「そう、そんな心配も当然ある。
だから使い方次第、心がけ次第なの。
車の運転と一緒。
便利なものは、危ないものでもあるから、
十分認識したうえで、活用してね!」
