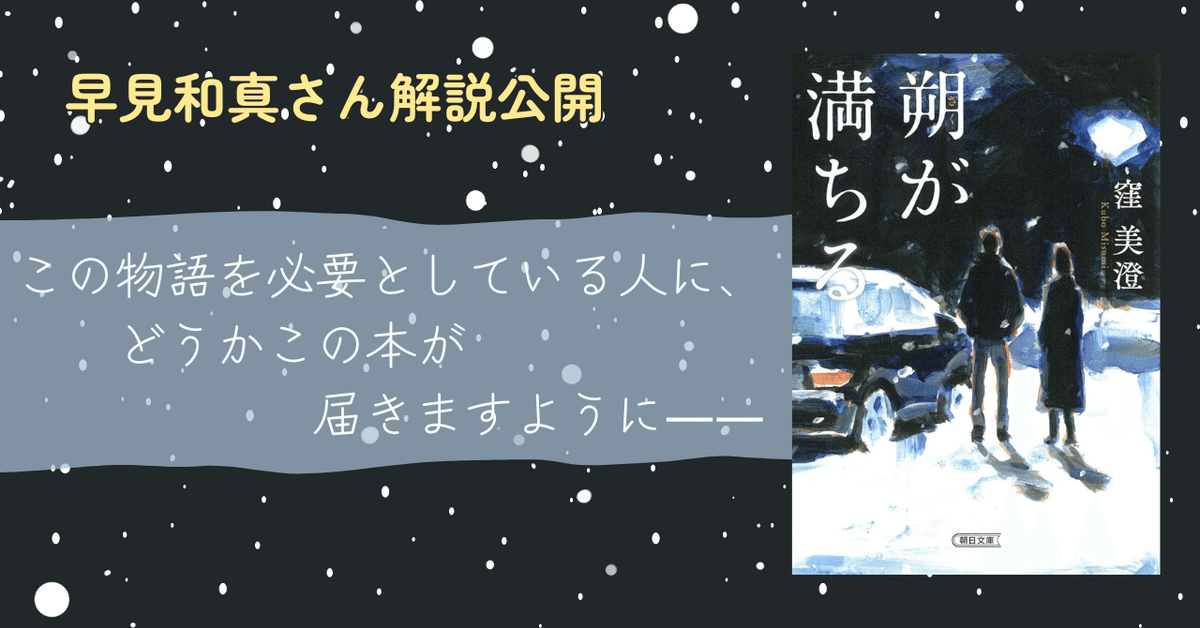
この物語を必要としている人に、どうかこの本が届きますように――。窪美澄さん『朔が満ちる』早見和真さんによる文庫版解説を特別公開

家に帰ると窓から"あたたかい光"が漏れている、ただそれだけの幸せを諦めたくないと思った。(女優・奈緒さん)
この物語を必要としている人に、どうかこの本が届きますように――。(小説家・早見和真さん)
家族のかたちを問い続けてきた窪美澄さんの真骨頂『朔が満ちる』がいよいよ文庫化されます。父からの暴力で抑圧された少年期の影に付纏われながら生きていた史也は、自分と同じ匂いのする梓と出会い、初めて家族に向き合い始める……。苦しみの先にある確かな希望に胸を打たれる傑作長編。刊行を記念して、女優の奈緒さんとともに帯にもコメントを寄せてくださった、早見和真さんの文庫解説を特別に公開いたします。

心臓で読む小説だ。
この解説の依頼を受けるずっと前、刊行されたばかりの本書『朔が満ちる』を読んだときの気持ちを、いまでも鮮明に覚えている。
この物語を必要としている人に、どうかこの本が届きますように──。
僕自身が犯罪をテーマにした小説を書いている最中だったこともあり、ナーバスになっていた面はあったと思う。
それでも今回文庫解説の依頼を受け、あらためて本書を読み返してみて、なぜあの日の自分がそう感じたのかよくわかった。
本を開けば、そこかしこに祈りの言葉が溢れている。史也の、梓の、千尋の、芙佐子の、水希の、吉田さんの……。もっと言えば、母の、父の。そして何より著者である窪さん自身の祈りの声だ。
読者である僕が祈りたくなるのも必然だった。
解説などという大役を仰せつかっておきながら、窪さんとはこれまでお目にかかったことがない。
それでも自分とほぼ同時期にデビューし、作家としての階段を颯爽と駆け上がっていく姿を、ずっと眩しく見上げていた。
……などと書いたら窪さんは間違いなくイヤがるだろうが、事実なのだから仕方がない。それほど『ふがいない僕は空を見た』でのデビューは鮮烈だった。
当時の〈R-18文学賞〉という新人賞の性質から、ことさら性描写がクローズアップされたが、僕は窪さんの“モノの見方”に一貫して感動していた。物事を広く見渡す俯瞰の目を持ちながらも、それが決して上から目線ではない。押しつけがましいところがいっさいなく、登場人物たちに自然と寄り添っているのが行間から滲み出ていた。
読者として、僕には「良い小説」の基準のようなものがいくつかある。その一つは「たとえ一行しか出てこないキャラクターであっても、その人物で一冊の外伝が書けるか」というものだ。
つまりは物語のために人間を駒のように扱っていないかということなのだが、実際に書いてみるとこれが意外と難しい。ふと油断すれば、ストーリーを転がすためだけに新しいキャラクターを生み出そうとしているし、動かそうとしている自分に気づく。
窪さんの小説にはそういう記号的な人間が出てこない。視点人物のみならず、すべてのキャラクターに対して対等に、慎重に目配りしようとしているのが伝わってくる。
ファンの方には、そんなの知っている、当然だろうと叱られてしまうかもしれないけれど、僕が窪美澄という小説家を信頼している一番の理由はそれだ。
物事に対する向き合い方、その眼差しにずっと信頼を寄せてきた。
当然、それは本作にも当てはまる。
物語は凄惨な暴力シーンから幕を開ける。酒に酔って暴れる父、腹部を蹴られてうめき声を上げる母、「目が見えない!」と泣き叫ぶ妹、そして明確な殺意を持って斧を手にし、「殺せ、殺せ」という心の内の〈龍の声〉を聞いている僕……。
すべて大人になった史也の回想によるものであり、暴力描写にそう多く分量が割かれているわけではない。
なのに全編を通じて重たい空気が垂れ込めるのは、作中で史也自身が〈今だけを見て生きていければそれはどんなに幸せなことだろう。けれど、今の僕の人生を作りあげているのは、今に繋がる過去だ。〉と独白している通り、過去から連なる今日を生きているからだ。
〈過去は過去のこと、水に流して、という言葉が心から嫌いだった。過去は今に繋がっているし、今は未来に繋がっている。記憶喪失にでもならない限り、父親と母親の記憶は永遠に僕のなかから消えてはいかない。そのことが、二十八になっても歯がゆかった。〉
史也の少年時代はまだ続いている。血にまみれた十三歳までの記憶は、二十八歳になったいまも拭えていない。
しかし、彼は今日まで生きてきた。必死に生き延びる中で見つけたのは、いくつかのささやかな出会いだ。
それぞれが大小の悩みを抱え、自らも決して強者ではない。そんな彼女ら、彼らとの出会いを経ても、史也の傷が簡単に癒えるわけではないけれど、そうした一つ一つの出会いもまた確実に未来へと通じていた。
そして、史也を〈世界の外側にひっぱりだそうとする人間〉が現れる。「生まれた家でなにかあった人間ってあたし、すぐにわかるんだよね」と言ってはばからない梓である。
ここから二人はお互いのか細い手を取り合って、それまで直視してこなかったそれぞれの過去と対峙していく。
生皮を剥ぐかのような痛みの伴う彼らの旅に、読者も心臓をちりちりとさせながらつき合うことになる。
そうして辿り着いた青森で、深い森の中にたたずむ洋風の、ちょっと変わった家で、再び史也が父と相対したとき、僕はそれまで悪漢としてしか存在していなかった父親という人間に対してはじめて思いを巡らせた。
それはきっと史也自身がはじめて父を想像したからだ。
父親はあいかわらず「怪物」のままだったし、「憎しみ」は心に滲んでいる。それでも、史也は梓の体を抱きしめた。
簡単に許せるわけがない。そんな史也の気持ちに同調しながら、血なまぐさい少年時代から彼が半歩だけ逃れた瞬間と感じられ、すっと心が軽くなった。
この物語には、たくさんの祈りの声が溢れている。
そしてもう一つ、本作を彩る大切なキーワードがある。それは「希望」だ。
最初に読んだときも、二度目も、僕は同じ箇所で「おやっ」と感じた。
それは第五章〈新月/見出すもの、見出されるもの〉の2節にある以下の文章と、そこから始まるさらなる物語だ。
〈僕らの最低最悪な子ども時代がやっと終わったのだ。そう思うと、あの家のことが脳裏をかすめた。いつか一人であの家に行かなくてはならない。あの家の最後を見て、僕らはやっとサバイブできた、と思えるのではないかと、そんな気がした。〉
自宅アパート近くの寂れた居酒屋で、ともにここまで生き延びてきた妹・千尋と、史也が言葉を交わす場面だ。
かつては酒そのものを憎んだこともあるはずの二人が、しみじみと飲み交わすシーンはとても美しく、充分にカタルシスを得られた。いずれの読書でも、僕はここで物語が閉じられるのが自然だと感じた。
ならば、そこから三十三ページという決して少なくない分量を使って、窪さんは何を綴ろうとしたのだろう。
蛇足であるはずがない。それこそが希望なのだと僕は思う。
生き延びた先にはきっと希望が待っている。
そう提示する必要が著者にはあったのではないだろうか。少なくともこのラストの三十三ページこそが本作の一番の特長であり、最大の魅力であると僕は捉えた。
彼らの旅につき合ってきて良かったと穏やかに思えた。
小説は決して高尚なものではない。もっとも手軽な娯楽であり、すべての人に開かれたエンターテインメントだ。高尚なものであるはずがない。
本気でそう信じている一方で、いいものを書いたからといって簡単に多くの人に届くものではないことを僕たちは痛いほど知っている。
でも、どうしても届いてほしい読者はいる。
〈「あたしたちみたいな子ども時代を過ごしている子どもがどこかにまだいるんだよね」
梓が僕の体を抱きしめる。
「その子たちが今夜だけでも、穏やかに眠れるといいね」〉
この物語を必要としている人に、その周囲にいる人たちに、どうかこの本が届きますように。
