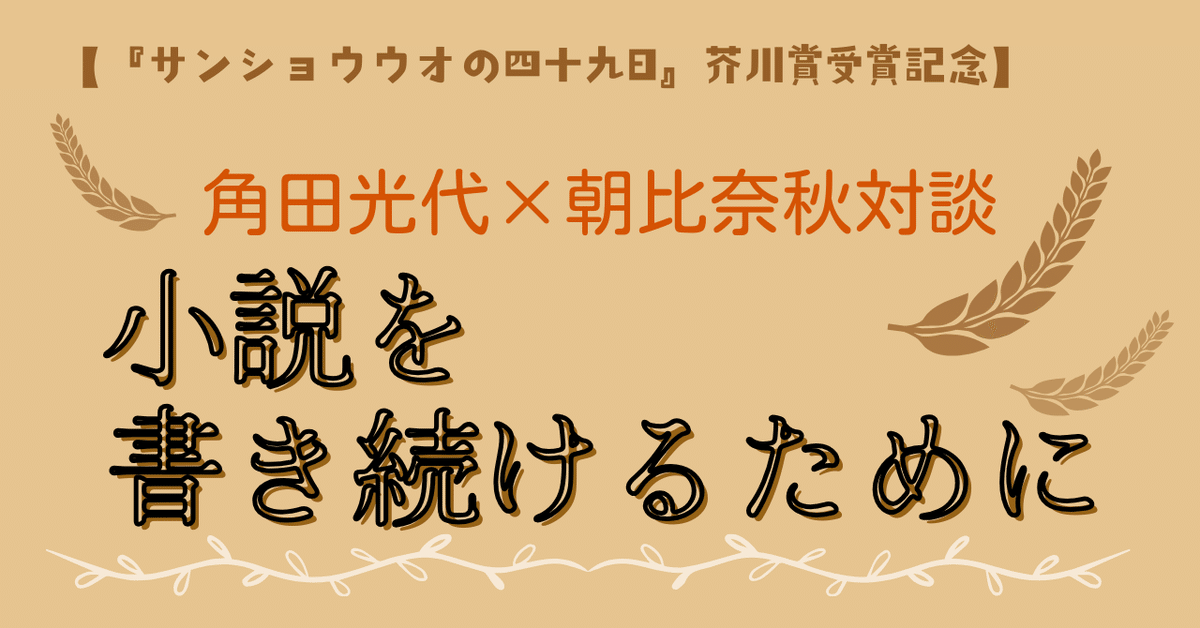
【朝比奈秋さん芥川賞受賞記念】林芙美子文学賞選考委員・角田光代さんとの対談を特別公開
『サンショウウオの四十九日』で芥川賞を受賞した朝比奈秋さん。デビューのきっかけとなった林芙美子文学賞の選考委員でもある角田光代さんとの初めての対談です。執筆方法の違いから小説との向き合い方、そして気分転換について。これからも「小説を書き続けるため」に何が必要か。その技術と秘訣について語り合った「小説TRIPPER」2024年冬季号での対談を特別掲載します。

■林芙美子文学賞から芥川賞へ
角田:芥川賞受賞、おめでとうございます。朝比奈さんが「塩の道」で林芙美子文学賞を受賞されたのは2021年でした。あのときの選考は評価が割れることもなくて、みんな朝比奈さんに丸印を付けたと思います。
朝比奈:そううかがっています。ありがたいことに、角田さんをはじめ、井上荒野さん、川上未映子さん3人から支持をいただいたと。
角田:選考委員が口を揃えて一番印象が強かったと言っていたのをおぼえています。私も描写の強度があると感じました。
朝比奈:角田さんにはたくさん褒めてもらったような記憶があります。選評に「力のある作品だ」とも書いていただきました。僕は都合のいいことしかおぼえていないタイプなのかもしれない(笑)。
角田:でもそれだけ朝比奈さんの作品のインパクトは強烈でしたから。確か、林芙美子賞を受賞する前にも何度か他の文学賞の最終候補に残ったことがあると聞いています。川上さんがあの時点で朝比奈さんが書いたものを4、5作ほど読んだことがあるっておっしゃってました。
朝比奈:はい。林芙美子賞を入れて、全部で四回ほど最終選考に残ったことがあります。じつは偶然、4つとも川上さんが選考に関わっている文学賞だったんです。しかも三島賞と芥川賞も選考委員を務められているから、僕は川上さんに計六回も選評を書いてもらったことになる(笑)。不思議な縁を感じています。
角田:そうなんですね。最終候補に残らなかった作品もあるんですね。
朝比奈:もちろんあります。これまで公募の新人賞には30作品くらい送りました。そのうちの四つの新人賞で最終まで残りましたが、あとはもっと手前で落ちています。
角田:ご自身で、受賞した作品とそうではないものの違いは、どこにあると思いますか。
朝比奈:自分ではよくわからないんです。ただ、書きはじめたばかりの頃の作品は何も分かってなかったなって思いますね。かぎかっこのあとには必ず「とだれだれが言った」と付けるものだと思い込んでいたくらいですから。自分で小説を買って読みはじめて、ようやくこう書くんやなってなんとなくわかっていきました。書き方というか、小説の方向性を決めたのは田中慎弥さんの『共喰い』と西村賢太さんの『苦役列車』です。それからは書けば書くほどよくなっていく実感はありました。
角田:朝比奈さんの小説は、デビュー作「塩の道」から芥川賞を受賞された『サンショウウオの四十九日』まで順を追って読ませていただきましたが、確かに一作ごとに凄みを増しているのがわかります。上からものを言うようで申しわけないのですが、この人はこんなところまで書けるようになったのか、このあといったいどこへ行くんだろうみたいな驚きがあるというか。
朝比奈:ありがとうございます。小説に親しむのが遅かった分、今は伸び盛りだと自分では思います。書けば書くほどマシになるし、小説を読めば読むほど新しい気づきを得られているという感覚は受賞前も今もずっとありますね。
■小説から届いてくる新しさの感覚
朝比奈:林芙美子文学賞の受賞作はどれも好きな小説ばかりで、とても肌に合うと感じていました。小暮夕紀子さんの「タイガー理髪店心中」とか高山羽根子さんの「太陽の側の島」とか。角田さんは第一回からずっと選考されているわけですが、選考会ではどのような議論が交されているんでしょうか。
角田:たとえば、高山さんと小暮さんは、どちらも面白かったのでみんな高い評価を付けたと思います。一般的に選考会はなんとなくの丸印が付くものよりも、強烈な評価か強く否定された作品の方が残ると言われています。ただ、これまで林芙美子賞を受賞した小説を思い返すと、やっぱり全員が評価したものが多いですね。
朝比奈:林芙美子賞の選考は厳しいんじゃないかというイメージがあります。僕が受賞したのは第7回ですが、第5回と第6回、それから第8回は「大賞なし」でした。大賞が出ないときはどのような議論がされるのでしょう。たとえば作品に決定的な何かが足りないとか。
角田:「大賞なし」のときは私がいいと思っても、他の二人の賛同を得られなかったケースがあったように思います。あと、少し具体的な話をすれば、現実描写からちょっと逸脱して、異界を出す、異形のものを出す、というような小説は、わりと厳しめの評価になることが多いような気がします。それは本来すごくむずかしいことなので、慎重に書いていかないと、ただ設定を甘くしている、書きづらいところから逃げているように見えてしまうんです。そうすると選考委員としては評価できない。「大賞なし」のときは、そういう作品が多かったような気がします。
朝比奈:逆に、この作品は良いと思うとき、角田さんはどこに評価軸を置いているか教えていただけますか。林芙美子賞に限らず、直木賞でも他の文学賞でも、角田さんが小説を評価する上で重要だと考える点というか。
角田:私が重視するのは「新しさ」ですかね。私が知らないこと、気づかなかった感覚が書かれているかどうか。
朝比奈:でも、その「新しさ」って角田さんが聞いたことのない知識とか職業とかではないわけですよね。情報の新しさを盛り込めばいいってことではないと思います。そのとき、「新しさ」とはいったいなんなのでしょう。僕も「新しさ」が大事だと思いますが、小説の「新しさ」とはどこにあるのかいつも考えてしまいます。
角田:朝比奈さんの小説で言えば、「塩の道」に描かれている死の日常性って、知識としては知っているけど感覚としては知らないことだったんですね。もちろん人の死に接したことはあるので、死がどういうものなのかはわかっているつもりです。そうなんですが、「塩の道」を読んで、田舎の村で暮らす無骨な漁師たちの肉体描写や、死んでいく祖父のかたわらで食事をする家族の様子など、これは私が知らないものだと思いました。「塩の道」という作品に流れている「小説の意識」と呼びうるものは私が初めて触れたものでした。
『植物少女』も同様です。ずっと植物状態だった母親が癌で亡くなったあと、お葬式の場面で「わたし」が、一瞬生きてるんじゃないかと思って母親の生死を確かめるシーンがあります。でもそれは気のせいで、「大丈夫。死んでる、死んでる」と言いながら安堵の息を吐く。そこにある感覚も私にとっては未知のものでしたし、植物状態のときは見舞いにもこなかった親戚の人たちが急に思い出を語り始めるシーンも新鮮でした。この母親は死を得てからあらたに生を受けたのかと、こうした人の生死のあり方は読んだことがないなって感じたんです。「新しさ」とは、きっとそういうことなんだと思います。
朝比奈:僕はただ自分の頭に浮かんできたものを書いているだけなんですが、それを「新しさ」として受け止めてもらえるのは、とてもありがたいです。
角田:だからといって、作者の知っていることが書かれているだけではダメなんだと思うんです。それは読んでいてわかる。自分がすでに知っていることをただ追っているだけの小説は読めばわかります。作者自身も知らなかったことを書いていくなかで知っていく、そこにひとつ新しさが生まれるんだと思います。朝比奈さんの作品も医師としての経験や、そこで起きた出来事だけが書かれているわけではないと思える。だからどの作品を読んでも新しいと感じられるんでしょうね。
■声を聞くための働き方改革
朝比奈:その点、角田さんはどのように小説を書いているのでしょうか。ご自身の知らないことを書くに至るまでの感覚というか、どのように「新しさ」を小説に取り込んでいるというか。
角田:私の場合は知っていることを書きがちなんですよ。だからどちらかというと、知っていることに頼ってはダメだと自分を諫めながら、この先が絶対あるはずだからもっと考えろと言い聞かせながら書いているというか。でも、どうやったら自分も知らなかった地点にたどりつけるかは書き終えるまでわからない。少なくとも私にとって小説を書くことは方法論ではなくて、ただ一生懸命に小説を書いていくなかで、一作ごとに気づいていくものなんです。小説を書くことに真摯に向き合えば、そこに行けることがあるということがわかっているくらいなんです。
朝比奈:これまで培ってきたノウハウを使えば、おそらく楽に書けてしまうわけじゃないですか。それなのに意識的に経験値に頼らないようにするわけですよね。僕のように小説を書き始めたばかりの人ならまだしも、角田さんのようなベテランの方がそうされるのはどうしてなんでしょうか。
角田:やっぱり小説を書くことがうまくなりたいからですね。うまくなるためには、朝比奈さんがおっしゃったようにたくさん書くことも重要だと思います。昔、小説を量産した方がいいと言われたことがあって、私も一時期たくさん小説を書いていたことがありました。そのときわかったんですが、自分なりに満足のいく小説って、50作書いて一つあるかないかなんです。でも、残りの49作が無駄だったかというとそうではない。それだけ書かないとその一作は出てこなかったわけだから。だから書けば書くほどうまくなるというのはそのとおりだと思います。
朝比奈:僕はどちらかというと、いまそういう状態なんです。一度書いて、ああでもないこうでもないと考えて改稿する。たとえば『サンショウウオの四十九日』も3回ほど一から書き直しました。
角田:文章を推敲するわけではなく?
朝比奈:はい。文章に手を入れるのではなくて、新しくWordを開いて白紙の状態から書き直します。しばらく直しながら、また何か違うなと感じて最初からやり直す。そのうち自分の頭に降りてきた物語の輪郭がよりクリアになってくるから、また最初から書いていく。「サンショウウオ」は最終稿が二百数十枚なんですが、そのかたちになるまでに千枚くらい書きました。だから量を書かないと見えてこないという感じはわかります。いま角田さんは小説を量産していないとおっしゃいましたが、それは納得できるものがすんなり書けているからでしょうか。
角田:それが、いまは書けていないんですよ。最近、自分なりに働き方改革をしたんです。というのも『源氏物語』の現代語訳を5年かけて完成させたんですが、その間に小説を一行も書かなかったせいからか、小説を書く感覚がなかなか戻ってこなくて。かつては割とスムーズに書けるタイプだったんです。テーマを決めて、資料を集めて、プロットを立てるという準備さえできていれば、いくつも連載を並行しながら書くことができました。
でも、『源氏物語』の現代語訳が終わった頃からそれができなくなってしまった。最初はただ書き方を忘れただけだろうから、きっとすぐに思い出せると踏んでいたんですが、気づけばその状態のまま四年も経っています。だから今年からは、もう依頼されて書くことはやめて、自分のペースで書きたいものをゆっくり書こうと決めたんです。
朝比奈:書き方を意識的に変えたんですね。
角田:そうです。なんでこんなに書きづらくなったのかなとこの一年間ずっと考えたんですが、きっと現代語訳をしていた五年間で私の小説観が変わってしまった。これまではストーリーを重視していたんです。プロットを面白くすることに力をかけていた。でも『源氏物語』の現代語訳を終えて、さあ、自分の小説を書こうとストーリーを組み立てていても、なぜかつまらない。それはきっと、あの五年間で『源氏物語』に出てくる登場人物たちの声を聞きすぎたからなんだと思っています。作業中は気づいていなかったんですが、終わってしばらくたって、訳すことは、千年前から投げかけられている声を聞き続けることだったと気がついたんです。それでなのか、自分の小説を書こうとなったときに小説から声が聞こえないことに、自分自身が「嫌だ」って感じるようになってしまった。
声が聞こえない限り、何を書いても嘘っぱちに思えてしまう。ではどうすればいいのか考えても、小説から届く声をどうやって聞けばよいのか、そんな対策なんてないわけです。どうしたら聞こえるようになるのかもわからないので、ひとまずは働き方を変えて、声がするのを待って、聞こえてきたら書いて出版社に持ち込むというように書き方を変えたんです。
朝比奈:だけど、小説から声が聞こえてくるまでに時間がかかるわけですね。
角田:そうなんです。『源氏物語』の直後に、読売新聞で『タラント』という連載小説を書いたときは、2、3人の声は聞こえたんです。だけど、主要人物の2人の声がどうしても聞こえてこなかったので、連載が終わってから本にするまで少し時間をもらって、なんとか聞こえるように書き換えていきました。そういう状態なので、まだどうやったらすんなり小説が書けるようになるのか手探りの状態です。
■嘘じゃない地点を探る
朝比奈:来年の3月で、小説家としてデビューしてから丸4年になります。もう4年なのかと思われるかもしれませんが、僕からしたらまだ四年しか経っていないのかという感じなんです。自分としては、ものすごく長い時間が過ぎたように感じているので、1年前に三島由紀夫賞をいただいたことですら、実感としては3年以上前の出来事と思っているくらいなんです。
それはつまり、この数年がそれほど苦しかった証拠でもあるんですが、こうして角田さんのように何十年も書かれている作家にお会いすると、果たして自分は続けられるのかと思ったりもします。さっき『源氏物語』の現代語訳を終えてから仕事のスタイルを変えたとおっしゃいましたが、角田さんはデビュー以降、小説との向き合い方を変えられたことはありましたか。
角田:私は「海燕」という純文学の文芸誌でデビューしたんですよ。なので、最初の十年間は七十枚くらいの中編や短編の依頼ばかりだったんですね。業界の事情に疎かったこともあって、なんでこの長さなんだろうと思いながら書いていました。ところが十年が経ったある日、ふと聞いたら、それは芥川賞を対象としているからですよって言われて、そうだったのかと初めて気づきました。でも、そのうち芥川賞や三島賞の候補から外れるようになると、文芸誌からの依頼が減っていき、その代わりにエンタメ系の小説誌から声がかかるようになった。そこで書き方を変えようと一度考えましたね。
朝比奈:すると、そこから『空中庭園』や『対岸の彼女』といった長編を書かれるようになったわけですね。僕の場合は思うように書くと、だいたい芥川賞サイズでした。「塩の道」が100枚くらい、「私の盲端」が180枚くらい、「植物少女」が220枚くらいの分量でした。でも、最近ようやく小説のなかの濠をより深く掘れるようになって、だんだん枚数が増えてきました。
去年、文芸誌に載せた小説を単行本にしている最中なのですが、掲載時は250枚だったものが手を入れていたら400枚くらいになってしまって、なかなか苦しい思いをしているところです。角田さんは中編を書くときと長編を書くときとでは、書き方の構えは最初から違うものなのでしょうか。
角田:私はこれまでずっと依頼ありきでやってきたので、媒体に合わせて考えていましたね。たとえば新聞連載だったら一年間を見据えてどう書いていくかを最初に決めていました。
朝比奈:物語がうまく伸びていかなくて悩むってことはないですか?
角田:連載の間に? それはあまりないかな。
朝比奈:すると角田さんは、書きながら作品がうまくいかずに困るという経験はなかったということでしょうか。
角田:うまくいかなくて悩むのは、どこまで自分が納得できる展開を作れるかっていう部分で、たとえば、ある男女がいて、2人には恋に落ちてほしいんだけれど、なかなかその雰囲気が作れないようなことはあったかもしれない。
朝比奈:うまく恋に落ちる方法が見つからないわけですね。
角田:はい。筆力が物語についていかないっていうのかな。恋に落ちるという展開を自分に説得できるだけの文章がうまく書けないときには、やっぱり悩みました。
朝比奈:そのときは、うんうん唸っているうちに「これだ!」って思いついたりするものなんですか?
角田:「これだ!」はなくて、ここまでなら許容範囲かなと思えるところを探る感じですね。これなら二人が恋に落ちると私も信じることができるか、嘘にならない地点に落ち着かせていくというか。
朝比奈:なるほど。角田さんの小説に驚くほどのリアリティを感じていたんですが、そういうふうに作られていたわけですね。
■登場人物のタフさに救われる
角田:朝比奈さんは、芥川賞の受賞スピーチで「物語の力に自分の人生が迷い込んで」いるとお話しされてたじゃないですか。他のインタビューでもある時期から物語が降りてくるようになったと話されていた。それは今も一貫して続いているんでしょうか。
朝比奈:ずっとそんな感じです。降りてくるというとかっこいいんですが、取り憑かれるような感覚でして、今はそれがすごく辛いんですよね。寝ても覚めても物語の映像が頭から離れず、それしか考えられない状態ですから、とにかくしんどい。ほとんどノイローゼに近いと言っていいと思います。そうなると他のことは何も手につかないから、日常生活もうまくいきません。誰と会っても楽しめない。頭のなかのイメージを追いやるためには、ずっと小説を書き続けるしかなくて、だから実質的にはプライベートの時間なんかないわけです。誰かに強制されているわけではないし、締め切りがあるわけでもないのに、頭のなかは小説のことばかり考えている。本当に白昼夢みたいなもんだと思います。
角田:小説を書き始めてから、ずっとそんな状態ですか。
朝比奈:7、8年前に初めて白昼夢のような映像が浮かんで、それを書き始めたら、どんどん浮かんでくるようになりました。頭のなかにあるイメージは現実ではないとわかっているのに現実のようなものと感じてしまっているので、心身が痛いし、苦しい。僕の小説は「塩の道」にしろ「私の盲端」にしろ、肉体的に辛い思いをしている人がたくさん出てくるので、書いている方も疲れ切ってしまうわけです。少しでも良くならないだろうかとか、この状態の身体でどうやって生きていけばいいのかとか思いながら書いてると、体力的にも精神的にもきつくて、早く終わってほしいと思いながらも、書き終わると、そのイメージが離れていくこともわかっているんです。
角田:書き終わったら解放されるんですか。
朝比奈:はい。でも早く解放されたいからといって、もうここで終わらせていいだろうと手を抜いてしまうと、そのあとまた違う映像が浮かんでくるんです。もう無理や、どうしたらええんやってずっと悩まされ続ける。
角田:朝比奈さんの頭のなかに映像がたくさんあって、ひとつが終わるとまた別のイメージに焦点が合ってしまう感じですか。
朝比奈:そうですね。合わせたくないのに、勝手に焦点が合ってしまう。半年、1年と休みたいのに、書き終えるとまたイメージが浮かんで振り出しに戻る。
角田:そのなかにハッピーな映像があったりもしない。
朝比奈:それがないんですよ(笑)。なぜかいつも大変な状況にある人たちのイメージばかり。
角田:でも、私は朝比奈さんの小説を読んでいても、そんなに苦しさを感じないんですよ。とれるはずの人工肛門がとれないとわかっても、腕を誤診で切断されてしまっても、とにかく悲惨な状況なのに登場人物たちはあっけらかんとしていて、どこか明るい感じを受けるんです。
朝比奈:時々そういう感想をいただきます。それは最終的に登場人物が軽やかな部分を出して終わることができたからだと思います。そこに至るまではとにかく辛い。ずっと、なんでなんや、なんでこんなことになるんや、と考えてばかりいます。「私の盲端」の主人公が人工肛門で今後も生きていくことになるイメージが浮かんだときも、最初はただただショックでした。書きはじめの頃は、半年だけ我慢すれば、きっとまた腸は肛門にくっつく、太い大便を出してラストを迎えられると思って、それだけを希望に書いていたんです。でも、2章に入ったあたりで、どうやら最後までくっつかないってことがわかって、そこからはもう苦しいだけでした。じゃあどうすればいいんだ、と。この先どうやって生きていけばええんや、と。ずっとそう自問しながら書いていました。
はっきり言って、舐めてたんだと思います。障がいはそんな簡単なもんじゃない。半年で終わるもんじゃない。病気もそう、治らない病気もある。そう気づいたときに、甘かったと痛感しました。だけど、登場人物たちはあっけらかんと乗り越えてくれるんですよね。それが自分にとっての唯一の救いです。さっき角田さんは自分が納得できる許容範囲を探るっておっしゃいましたけど、そうなってようやく僕もこれでよかったと思える。大便が自分の肛門から出ようが、人工肛門から排泄されようが、彼女が強く生きているなら一緒やないかと納得できるんです。
■小説を書きながら人間を理解する
角田:もしかすると朝比奈さんが辛いのは、作者であるご自身が登場人物たちの苦しい部分を引き受けてしまっているからかもしれませんね。だから、作者が辛さにシンクロすればするほど、登場人物たちはどこか底が抜けたような明るさを身につけることができる。
朝比奈:そうだったら嬉しいです。ときどき、僕がもしかしたら偏見まみれだからかもしれないと思うんです。障がいを抱えている人をどこか他人事として考えていたから、深く理解することができていなかったのかもしれないと。
角田:朝比奈さんの小説を読んで、私はむしろ逆のことを思いました。読んでいる方が、自分は偏見を抱いていて、本当のことをわかっていなかったことに気付かされたというか、作者である朝比奈さんに決めつけがないから、私の知らない感じ方を小説として書けるんだろうなと。
朝比奈:ありがとうございます。でも、途中までは僕も角田さんと同じ気持ちでいるんですよ。きっとこの病気を抱えている人はこうなるだろうと決めつけながら書いている部分がどこかにあるんです。けれど、それは違うと突きつけられる瞬間が必ずやってくる。自分が偏見まみれだったことに気づかされるわけです。毎回、小説を書きながら、自分の人間に対する理解が浅かったということを嫌というほど教えられる。そのたびに人間ってなんなんだろうかと考えざるを得なくなって、とても苦しくなります。
角田:だけど、作者はある意味では何をどう書いても自由ですから、半年で肛門からまた排泄できる展開にしようと思えば可能なわけですよね。それでもそう書かないのはどうしてですか。
朝比奈:間違った認識のまま書くと頭のなかの映像がとれないんですよ。ずっと「違う違う。そうじゃない」と言われ続けている感じがして。最初から最後まで物語が見えているわけではありませんから、途中でこっちかなと思って間違った方向に進むことはよくあって、だけど「なんかちゃうぞ」とまた戻る。それを繰り返しながら書いていくので、自分で筋書きを決めている感覚はなくて、物語が最初から自分の頭のなかに埋まってて、一部分だけ見えているイメージを掘っていくような作業が近いかもしれません。
幸いなのは物語に出てくる人たちがみんなよくできた人間ばかりなことです。必ず本人が前向きになってくれるから、最終的に悩まされることがなく、ようやく終わることができると感じられる。書き終わったあとは物語のすべてが忘れられます。たまに登場人物を思い出して、みんな元気でやってるんかなぁと思うくらいです。
角田:じゃあ自分の小説を読み返すことはありませんか。
朝比奈:本になったあとはないですね。自分が書いた文章も全部忘れてしまいます。たまに書評で引用されたものを読んでも、「あれ、こんな文章書いてたんや」って思うくらい(笑)。ただ、不思議なんですが、頭のなかに生まれたイメージは記憶からなくなることはないんですよ。元の原型から、最後に輪郭をもったイメージまでみんな思い出せる。
角田:これまでの小説は身体にまつわるものが多いですが、頭のなかに生まれるイメージも身体性と切り離せないものばかりですか。
朝比奈:そうじゃないもの、たとえば哲学的な観念みたいなものが見えたりもします。でも、なぜか観念小説として書くだけでは頭から消えないんですね。たとえば『サンショウウオの四十九日』を書いていくなかで、人の意識はどこにあるのか、脳に宿っているのか心に宿っているのか、文章でたどるだけでは頭に浮かんだイメージはなくならない。物語を通して日常的なリアリティとしてとらえていかないと頭に残り続けます。だからリアリズムとして身体性をともなう作品を書いているのだと思います。
角田:朝比奈さんの作品がテーマや題材ありきではないのは、そのせいなんですね。
朝比奈:そうじゃないと解放されないんですよ。身体を通さないと手放せないものがあることは嫌というほどわかったので、今後も観念や幻想ではなく、身体性のある小説を書いていくことになると思います。
■小説家にとってのワークライフバランス
朝比奈:角田さんは日常生活を送っていて、小説のことが頭から離れないという経験はありますか。
角田:20代の頃はそういう状態で仕事をすることに憧れて、頭から離れないフリをしながら夜通し書いていたときもありました。でも体質的に無理で、疲れてしまった。だから30歳でやり方を変えて、書く時間は9時から5時、午後5時以降は仕事をしないって決めたんです。意識的に5時以降は小説について考えないように訓練をすることで、その思い込みは克服できたのではないかと。
朝比奈:そうだったんですね。僕もこのままでは無理だという確信があるんです。そもそも小説のためならどうなってもいいみたいな覚悟があったわけでもないから、どうにかしたいと自分でも思っています。そうでないとこの先、何十年も書き続けられないのは間違いない。だからなんとかオン・オフで切り替えるみたいにして、小説と距離を置く方法を見つけたいんです。
角田:解決策になるかどうかはわかりませんが、私は仕事場を自宅と離れたところに借りて、そこで仕事をしています。帰ったらもう仕事はしないという生活を続けているんですが、そうすると自宅では小説のことはあまり考えなくなりました。
朝比奈:なるほど。いいことを聞いたかもしれません。確かに今、生活する場所と書く場所が一ミリもずれてないんです。
角田:だから小説のモードになろうと思ったらいつでも書けてしまう。
朝比奈:そうなんです。だからそのときに取りかかっている小説の空気が部屋に充満している気がいつもしています。もしかすると生活の場と別の空間を用意するとそれもなくなるかもしれませんね。貴重なアドバイスをありがとうございます。まずは物理的に場所を切り離すことで小説とも距離をとれるかもしれない。
角田:そのスタイルでいくなら、絶対に自宅には仕事を持ち込まない。ゲラもパソコンも一切だめ。持ち込んでいいのはお楽しみとして読む本だけです。
朝比奈:そうですね。よし、そうしよう。
角田:私が仕事場を借りて、時間を決めて小説を書くようにしたのは、自宅でも追い詰められている感覚になるのが嫌だったからなんですね。私の場合は朝比奈さんと違って小説のイメージではなくて、編集者に何か言われている夢でした。朝泣きながら起きるのがもう嫌で嫌で、仕事と生活を切り離すようになった。
こうしたスタイルを20年以上続けてつくづく思うのは、どれだけ忙しくてもとりあえず心身を病まずにいままでやってこられたのは、残業をしなかったせいではないかと。終わらない仕事があるときでも、必ず翌日の早朝に出直していた。夜に仕事をすることを許していたら、きっと身体を壊していたと思いますね。
朝比奈:いまのお話には思い当たるふしがあるんですよ。僕がまだ常勤医だったとき、自慢できる話ではありませんが、世界でもトップクラスに労働していました。月の残業が320時間を超えていた。
角田:ええ!? 残業時間だけですよね。
朝比奈:はい。1日、18時間以上働いていたんです。1年半くらい1日も休みがなかった。丸2日寝られないときもざらにありました。過労死ラインが残業80時間ですから、その4倍ほど働いていたことになります。
角田:身体は壊さなかったんですか。
朝比奈:身体は大丈夫でした。ただ、それ以外の何かが変化しました。たとえば、当時は現実と夢の境界がなくなりました。起きながら夢を見ているような感覚です。起きているときも、これが夢なのか現実なのかわからない。寝ているときも同様で、疲れ切っていびきをかいてる自分を自分が見ているんですよ。覚醒中なのか睡眠中なのか確信が持てない。もっと言えば、生と死の感覚もぐちゃっと混ざる。
そういった労働環境でなくなって、何年か経ったとき、今度は小説が思い浮かんでくるようになってしまった。角田さんのお話をうかがって、なるほど、あのときの労働のせいでプライベートが失われて、今に至っているのかと思いました。
角田:今も残業をしている感覚というか。
朝比奈:そうですね。小説のことばかりで、日常生活が破綻しているので、もう少し健全な生活を送らないといけない。まずは自宅と仕事場を分けるところから始めてみたいと思います。
■クラシックが励ましてくれた
角田:朝比奈さんが小説以外で楽しいなと感じるのは何をしている時間ですか?
朝比奈:それがないんです。しいて言えばクラシック音楽を聴いてるときでしょうか。支えというか、励まされるんですよね。
角田:クラシックに励まされる?
朝比奈:ベートーベンのように、ああいった人生を全うした人間がこの世にいたこと自体に励まされます。ショパンなどもそうです。さまざまな困難を抱えながら、自分の人生を全うした。
角田:ベートーベンみたいな人がいたことが希望だと思えたんですね。
朝比奈:はい、そうです。
角田:朝比奈さんはいろいろと思い悩みながら小説と格闘しているように思うのですが、過酷な救急医療の現場を経て、作家として軌道に乗ったいまの人生と、ストレスのない勤務医時代を過ごせたけど小説を書くこともなかった人生だったらどっちの方が幸せだと思いますか?
朝比奈:それは、うーん。小説を書きはじめた当初は、小説が書けることを面白がっていましたが、そこから数年経ったころには、あまりに物語が浮かんできて支障が出るようになりました。その時にはいくつもの小説ができあがっていましたが、質は低く、新人賞を受賞して職業作家になれるレベルではなかった。もっとも困ったことは、医師の仕事中にも浮かんでくることでした。なので、プロの作家になれていないなかで病院を辞めざるをえなかった。同僚たちが何の迷いもなく医者を続けられるなかで、まったく違う分野で一からやり直すというのは、なかなか複雑な体験でした。特に受賞する1年前はなんの仕事もせず、林芙美子文学賞に応募するときに職業欄に無職と書いた記憶があります。
そういったなかで、小説を書くことになった状況をポジティブに捉えるのは難しかったです。林芙美子文学賞を受賞した後でも「書くことになったものをすべて書いたら、さっさとこの業界を去ります」と新聞社のインタビューに答えていました。よくよく思い出せば、一年半前の三島賞の受賞会見でも「物語が浮かばなくなって小説が書けなくなってもそれでいい」と答えた記憶があるので、つい最近までそんな感じでした(笑)。
今では少し変わってきています。この分野に受け入れてもらっている感覚があり、なにより小説に受け入れてもらっている。ありがたいことに間違いない。きっと、恵まれているんだと思います。
この春くらいから、物語から逃げることは無理だと受け入れて、何とかうまくやっていける方法を模索している最中です。なので、先ほどの角田さんの、ご自分と小説の関係が変わった話などはとても励まされました。実践的なアドバイスもいただいたので、今日はホクホクした気持ちで帰れそうです(笑)。
(2024年10月31日 東京・築地にて)
構成/長瀬海
