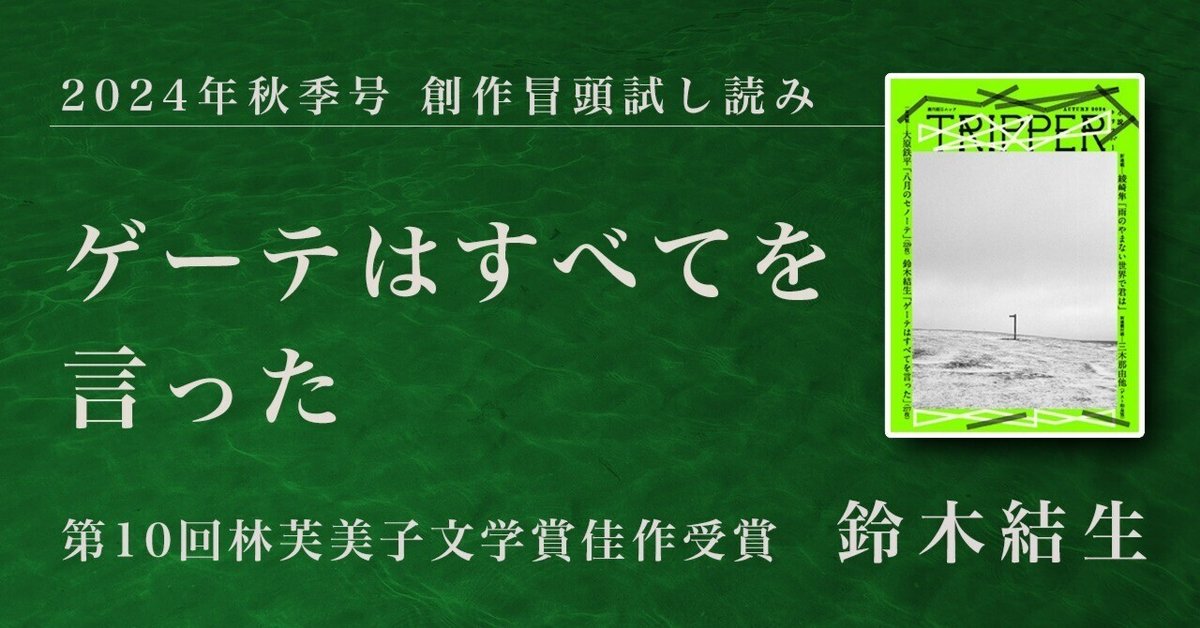
第10回林芙美子文学賞佳作受賞・鈴木結生さん受賞第一作「ゲーテはすべてを言った」冒頭特別公開!
各紙誌で好評された「人にはどれほどの本がいるか」で第10回林芙美子文学賞佳作を受賞された鈴木結生さん。受賞後第一作にあたる「ゲーテはすべてを言った」が2024年9月18日発売の「小説トリッパー2024年秋季号」に掲載となります! 冒頭を特別に公開いたします。

高明なゲーテ学者、博把統一は、一家団欒のディナーで、彼の知らないゲーテの名言と出会う。ティー・バッグのタグに書かれたその言葉を求めて、膨大な原典を読み漁り、長年の研究生活の記憶を辿るが……。ひとつの言葉を巡る統一の旅は、創作とは何か、学問とは何か、という深遠な問いを投げかけながら、読者を思いがけない明るみへ誘う。若き才能が描き出す、アカデミック冒険譚!
「ゲーテはすべてを言った」鈴木結生
端書き
先頃、私は義父・博把統一の付き添いで、ドイツ・バイエルン州はオーバーアマガウ村の受難劇を観て来た。統一が長年要職を歴任した日本ドイツ文学会から依頼を受けての取材旅行。といっても、間も無く定年を迎えようとする功労者に対し、ささやかな餞別といった意味合いも多分にある仕事で、PR誌「独言」に何頁でもいいから文章を書いて欲しい、との話であった。勿論、統一本人は至って真面目にこの仕事に取り組んでいたが、そうはいってもやはり久々のドイツ。二週間弱の滞在期間の隙間に細々としたプログラムを入れ込み、娘に旅の枝折を織らせることまでして、楽しみにしているのが側から見ていて、よく判った。
恐らくこれで最後となる取材旅行の同行人に、統一が妻でも娘でもなく娘婿の私を選んだのは、私が予々ヨーロッパの宗教劇に並々ならぬ関心を抱いていて、それを度々口にするだけでなく、方々に書いていたせいもあったろうが、それより本当は、単に丁度いい話し相手が欲しかったのだと思う。成田からヘルシンキを経由して、十時にはフランクフルトに到着した。翌日の昼過ぎにはもう村まで行って、劇の稽古を見学させてもらう手筈だったから、その日は一寸街を見て回るだけで、午後の早いうちからホテルの各々の部屋で身体を休めることにしたが、結局夜になったら統一から「自分の部屋に来て、酒を飲もう」と電話がかかってきた。
ワイン党の統一は、私が急ぎホテル近くで調達してきたビールには目もくれず、林檎酒を一寸口に含む程度だったが、併せて買ってきていたチーズとソーセージには手を伸ばしていた。明日からの旅程の確認と、日本にいる家族への連絡、私の最近の仕事に関する雑談などを一頻り終えた後、私が「そういえば六年前にも、一緒にフランクフルトに来ましたね」と話を振った。何故、今までその話をしていなかったのかは分からない。あるいは、互いにいつの間にか無用な気遣いが働いていてのことだったか。しかし、一旦話し出してしまえば、自ずから思い出話に花は咲く。枝葉は伸び、新たな種も芽吹こう。
普段寡黙な義父には珍しく――林檎酒もきっと旨かったのだろう――みるみる顔を紅潮させ、ドイツ旅行の話は果たして、「ゲーテはすべてを言った」なる言葉へと行き着いた。彼は言った。
「思い返してみれば、あの言葉が私の人生の示導動機だった。私は事あるごとにあのジョークを思い出しては、他人を、世界を、何より自分自身を洒落のめしたものだ。でもね、今になって確信するのだけれど、あれはやはり単なるジョークではなく、一種の天啓のようなものだったと思うよ」
そうして語り始めたのは、私も(そして恐らくは妻も)しっかりは聞いたことのない話。先のドイツ旅行の発端となった一連の騒動について。その話を私にするということは即ち、「書け」という指令なのか? あるいは「書いてもいい」という許可なのか? 驚きつつこの機会を逃してはならない、との職業的直感が働いて、
「御義父さん、折角ですから、録音させてもらってもいいですか?」
と尋ねたところ、彼ははにかみながらも首肯した。
それからは旅の間中、暇さえあれば、六年前の一件に関する統一の証言を済補で録っていった。生まれつき御饒舌な私もこの時ばかりは聞き役に徹し、長年大学で教鞭をとっていた統一は一人で喋ることにかけては言うまでもなくプロフェッショナルであるから、素材は続々溜まっていった。村に行ってからも、統一が受難劇の歴史や演出についてメモをとっている横で、私は専ら録音の書き起こしに熱中し、折角の受難劇の本番を見ている最中も、頭の片隅には義父の話を反芻していた。
訪独中に書き起こしは粗方済ませてしまって、帰国後、徐々に小説の形態へ――生憎、私はそれ以外の書き方を知らない――整えていった。即ち、統一が「私」とか「僕」とか言っている部分についてはすべて「統一」ないし「彼」と置き換え、家族以外で存命の関係者の名前が出てくる場合はアルファベット表記か仮名に差し替えた。必要を感じる部分については適宜説明を挿入れ、エピソードの順番を時系列順に並べた。最低限の事実確認と統一以外の登場人物(主にその妻と娘、時には私自身)の側からの意見の聞き取りもしないわけではなかったが、原則として統一の語った言葉そのままを文章化することを目指した。とはいえ、時には想像力を働かせ、勝手気儘に創作した部分も少なからずあって、実際、書き終わった作品を仙台の実家に送付したところ、統一からの返信には、「楽しく読んだ」と好意的で仔細な感想が述べられた上で、「私が私じゃないこと以外は全部本当の話だった」とあった。私はそれを本作への最大の御墨付と受け取り、こうして世に出す運びとした。そのため、本作を手に取る人の中には当然、博把統一の著作のファンも数多くおられることと思うが、そういった方々については、統一自身が既に発表している「未発見のゲーテ書簡について」(https://www.hakugei.site/backnumber/123)も併せて読まれることを強く勧める。本作の学術的記述に関し誤りがあれば、それはすべて作者の責任である。
最後に本作の執筆にあたり、何事につけ飽きっぽく忘れやすい作者が、物語の主題と構造を片時も見失うことのないよう、ノートPCの常に目に入る位置に貼り付けておいたゲーテの二つの言葉をここに書き写しておくとしよう(前者はトーマス・マンの講演からの孫引きだが、それはマンがゲーテの名言的性質と結び付けていることまで含めて、この句が私にとって重要な意味を持ったためである)。
われわれには、感じたこと、観察したこと、考えたこと、経験したこと、空想したこと、理性的なものと、できる限り直接に一致した言葉を見出そうとする、避けがたい日々新たな、根本的に真面目な努力がある。
自然界においては、色彩の全体性を具現しているような普遍的現象は、決して見ることはできない。完璧な美しさに満ちたこのような現象を見せてくれるのは実験である。しかし、この完全な色彩現象が円環をなしていると理解するためには、自分で紙に顔料を塗ってみるのが一番よい。
Ⅰ
博把徳歌が、父・統一と母・義子を郊外のイタリア料理店へ連れて行ったのは、十二月初めの火曜の晩のことである。その日は夫妻の結婚記念日で、しかも指折り数えてみれば銀婚式に当たるということが判明したため、娘が急ぎ祝筵を用意した次第。三田の自宅から店までの運転は彼女が担当した。統一は冬の夜の山路での徳歌の運転が危なっかしいので終始気が気でなかったのだが、やがて赤い屋根が見えてきて、その駐車場には「ROMA」という店名を樹の棒で綴った看板が掛かっているのだった。店内の照明は仄かで、平日の夜だったこともあってか客の入りは疎だったが、かといってそこに物寂しさのようなものはない。夫婦は二十二歳になった一人娘が、個人経営の塾のアルバイトをして得た薄給からディナーを御馳走してくれるという、その気持ちだけでも充分感激していたのに、その店の料理の旨さにはもっと驚かされることになった。
父親は赤ワインを、娘はアペロールのソーダ割を頼み、帰りの運転を担当する母親はサンビテールで乾杯をした。乾杯の音頭はいつも通り父がとる。
「Trauben trägt der Weinstock!/Hörner der Ziegenbock;/Der Wein ist saftig, Holz die Reben,/Der hölzerne Tisch kann Wein auch geben./Ein tiefer Blick in die Natur!/Hier ist ein Wunder, glaubet nur!」――この『ファウスト』からの引用は彼の学生時代からの十八番で、大学の教職員や学生を連れての宴席でも毎度これをやっているくらい。流石に義子も徳歌も何となく覚えていて、最後のところなんか一寸合唱みたいにもなった。前菜はビュッフェ形式で、カプレーゼ、ツナとわさび菜のサラダ、イワシのソテー、茄子ときのこのラザニア……と銘々取り皿に思い思いの品を盛ってきて、その彩りを競い合う。メインディッシュにはニョッキと仔羊のカツレツを注文した。カツレツの上にこれでもかと載せられたトマトは何とも甘くて美味しい。統一は今年で六十三になるが、まだまだよく食べた。まして娘からの祝いだから尚更張り切った。
徳歌にはこの機会に両親の恋愛時代について話を聞き出そうという隠れた目論見があった。それでちょくちょく、「デートはどこに行った?」だとか、「ラブレターは書いた?」だとか尋ねてみるのだが、そういったことについてシャイな統一が答えるはずがないし、そんな夫の前では妻も何も言わない。娘と二人きりの時はそんな話をしないこともない――何ならつい先日もそんな話になったばかりだった――が、彼女にとっては夫との二十五年より、娘との二十二年の方が余程語り甲斐があった。途中、その日五歳になったという女の子の誕生日を店内の皆で祝った。そのことが、「あのくらいのときののりちゃんは、そりゃもう可愛くって、手もかからなくって、周りのお母さんたち皆から羨ましがられて……」と義子の子供自慢に尚更拍車をかけた。統一は赤ワインを追加し、あくまで心地よくなりながら、妻が娘を褒めるのをただ聞いていた。
今や日本におけるゲーテ研究の第一人者とされる統一が、師である独文学者・芸亭學の次女と結婚したとき、彼はもう三十八になっていた。いよいよ不惑も射程に入り、「このまま独身を貫き、学問に身も心も捧げよう」と決心を固めかけていたところ、当時既に定年退官していたが相変わらず何かと世話を焼いてくれていた師からの、「これから教授としてやっていくつもりなら、やはり妻帯者でなくては……」との唐突な勧めは、まだ助教授になったばかりの統一の覚悟を呆気なく打ち崩してしまった。かくして紹介された義子は、どちらかというと強面な父親とは似ても似つかない可憐な容貌が、若い頃に師宅で見かけた少女時代の淡い面影は留めつつ、二十代後半の大人びた明朗さを確かに湛えて、統一の瞳の内から瞼の裏までを彼女の色で埋め尽くした。一方の義子はというと、かねてから実家に出入りのあった父の愛弟子のことをずっと慕っていたらしかった。娘の秘めたる恋心を妻から知らされた父は、常に家族より学問を優先してきた自分の罪滅ぼしをするように、己の権威を濫用して、一種の政略結婚を成立させたというわけである(この辺の事情については、徳歌は両親よりむしろ母方の祖母及び伯母の話から理解を深めていた)。半年足らずの交際期間を経ての結婚式は、芸亭家が通っていて、學も長年執事を務めているルーテル派の教会で執り行われた。
あれから四半世紀が経ったのだ、と統一は改めて思う。その間起こったことを並べ立てれば、それだけで「博把統一」という学者の経歴を満遍なく語ることになるだろう。結婚して間もなく、博士論文「ゲーテにおける世界の全一性について」(‘Über die Totalität der Welt bei Goethe’)を日本の一般読者向けに書き直した『ゲーテの夢――ジャムか? サラダか?』がサントリー学芸賞を受賞し、統一の名は学界中に知られるところとなった。同年、水曜堂出版ゲーテ全集第一巻『ファウスト』の翻訳でバベル翻訳大賞を受賞。その訳文は、原文の重厚感を保ちつつ、学者の文章にありがちな閉塞感がないと専らの好評で、ゼロ年代の新訳ブームも手伝い、これ以降も次々ドイツ古典文学の翻訳を手掛け、彼の名は一般の文学読者層にも着実に広がっていった。新世紀に娘を授かり、無事、母校の助教授ともなった。三四門出版「世界百科事典」の「ゲーテ」の項目を書き下ろし(これは同社の「ポケット文学大鑑」に於いても省略・転用されている)、ろごす書房「西洋古典文学精選」の編者にも名を連ねるなど、着実に実績を重ね、いよいよ教授となった。一昨年からは、日本ドイツ文学会の会長を務めている。統一は自分の人生を振り返って、「父の驢馬をさがしにいって王国を見つけた」という『ヴィルヘルム・マイスター』の中の言葉を思い起こさずにはいられない。唯一心残りがあるとすれば、徳歌が統一の勤める大学に入学しなかったことくらい。でも、これを口にすると、妻が娘に小言を言い(例「徳歌は真面目に勉強してなかったもんね。音楽三昧で……」)、娘は母を介して父を攻撃する(例「パパだって、読書漬けで浪人したのに……」)ので差し控えるが。
食後には三人それぞれの選んだケーキ――統一は葡萄のタルト、義子は栗のミルフィーユ、徳歌は苺の練り込まれたチーズケーキを食べる。それと併せて紅茶を飲むことにもなるが、何十種もの紅茶が並ぶ棚の中から、義子が選んできたアールグレイのティー・バッグを開いたとき、家族はそのタグの部分に何やら文字が刻まれているのに気が付いた。
「『Be strong, live happy and love, but first of all/Him whom to love is to obey, and keep/His great command.—John Milton』」娘が昨年までのロンドン留学中に入念に仕込まれたのであろう上等なクイーンズ(彼女が留学していた時はまだ)・イングリッシュで自分のタグに書かれた文字を読み上げる。「Paradise Lostね。まぁ良い言葉だけど、些と長い。ママのは何て?」
英語の実力は中学のレベルですっかり止まってしまっている母は、既に皿の端に寄せてあるティー・バッグのタグだけを切り取り、娘に差し出した。
「『At the touch of love everyone becomes a poet.』。お、プラトンですねえ。『愛に触れると、誰でも詩人になっちゃう』ってことよ。いいないいな、ね、ママ、私のと交換しましょ」
娘と妻が英詩の巨星と古代の大哲学者の言葉を交換し合うのを眺めながら、ああなるほど、愛に関する名言を集めたティー・バッグなんだ、と統一はすっかり酔いの回った頭でぼんやり思いながら、特段自分のものを確認しようとすることもない。そんな統一に、娘は当然、「パパのは?」と尋ねてくる。
「ん……」父親は娘に若干のコンプレックスを抱きながら、ドイツ訛りの(と彼は主張するが、実は単に学生時代から不得手なだけの)英語で読み上げた。「『Love does not confuse everything, but mixes.』」
「誰の言葉ですか?」義子が尋ねる。統一はそれには答えず、ただタグを示すに留める。件の文章の下には、「Goethe」の字。
「わ!」妻と娘が顔を見合わせて驚いた。それから、「やっぱすごいねえ」と二人して散々統一をほめそやす。徳歌など調子よく、「パパ、ゲーテと赤い糸で結ばれているんだ」と持ち上げた。これには統一も顔を赤くして、賛辞が行き過ぎて冷やかしめく前に、こらこら、と止めさせるが、内心まんざらでもなく、やはり私のゲーテへの愛は神もご承知らしい、と娘よりよほど大逸れたことを考えているのだった。このとき、彼の中で思い出されていたのは、二十三年前の新婚旅行中のとある出来事。
結婚してしばらくは前述の通り統一の仕事が何かと忙しく、二年越しのハネムーン(?)となった。すっかり所帯染みた新婚夫妻を中心に、妻側の両親・親族数名と學の教会のメンバーが加わり、図らずもミレニアム・イヤーで御祭りムードのイスラエルを、超教派のツアーに混じって巡礼ったのだが、途中、ガリラヤ湖畔の店でピーターズ・フィッシュなるものを食うことになった。これは、イエスが一番弟子のペトロに魚を釣るよう命じ、その魚の口に挟まっていたデナリオン銀貨で税金を納めさせた、という福音書の記述に由来する名物。何せ名物なので、三十名ほどの巡礼者たちは全員同じものを注文した。果たして蓋を開けてみれば、學の教会の牧師とカトリックの神父、当時はまだ会社員をしていたのだが、既に神学校に行くことを考えていた學の弟・收の前に置かれた魚の口にだけ一シェケル硬貨が挟まっていたのである。これを見た統一は、なるほど運命に選ばれた人というのはいるもんだ、と素直に感心した(と同時に、自分はやはり献身とは縁遠い俗物のようだ、という思いを固くした)わけだが、よもやこの歳になって自分がそれに類する体験をするとは思わなんだ。何の謂れもないティー・バッグであったとしても、やはり嬉しいことは嬉しい。ウットリ「Goethe」という文字を見つめていると、娘が父親の手からタグを引ったくり、
『愛はすべてを混乱させることなく、混ぜ合わせる』。そんな感じかしら?」とさらっと訳した。
「へぇ、いい言葉ねぇ」ドイツ語も英語も満足にできず、ましてミルトンにもプラトンにも最先の前菜のポタージュに浮かんでいたクルトンほどに何の思い入れも持たない義子は、その言葉そのものに対してというよりは、恐らく英語を解する賢い娘と大学教授の夫のいる理想的な我が家に満足している様子で言った。「どこかで聞いたことあったような……」
「多分、『西東詩集』だろうとは思うんだがね」と統一は付け足しておく。専ら学識だけで妻子への威厳を保ってきた家父らしい、厳しい言い方で。しかし、確信は全くない。別にそれでよかった。どうせ、妻は交際している時分から何遍説明したところで『西東詩集』が何たるか覚えようとはしないし、結婚後にプレゼントした『Hermann und Dorothea』も、統一が翻訳し彼女に献げた『親和力』も読んだのかどうかさえ分からない。多少話の分かる娘は娘で、小首を傾げながら、「英語の生硬さは翻訳だろうから仕方ないにしても……」などぶつぶつ呟いていて、結局、彼の言葉は誰にも聞かれず、虚空へ消え失せていくのだから。
*
「ゲーテはすべてを言った」そんな言葉が統一の脳裏に忽然と蘇ってくる。彼はそのジョークを、ドイツ東中部の大学都市イェーナに遊学していた時分、街外れの小高い丘の下宿で隣人となったヨハンという名の画学生から教わったのだった。太陽が葡萄茶色の屋根の連なりを染め上げ、涼しい風がベランダの洗濯物をパタパタ孕ませているのが見えた、一九八八年の夏の朝のことである。どういう文脈で、ヨハンがそんなことを言い出したかは全く覚えがないのに、その瞬間の情景と感覚は確かに記憶している(だから年号と時節は、後から思い出したものだ。町の景色が見えたということは、さしずめ二人はヨハンの方の部屋のベランダに出て、煙草でも吸いながら、夜通し話をしていたのだろう)。それは、やがて日本でゲーテの専門家として大成することを志していた当時の統一の耳には妙に予見的に聞こえ、やがて耳にこびりついて離れなくなった。
「ドイツ人はね」とヨハンは言った。「名言を引用するとき、それが誰の言った言葉か分からなかったり、実は自分が思い付いたと分かっている時でも、とりあえず『ゲーテ曰く』と付け加えておくんだ。何故なら、『ゲーテはすべてを言った』から」
何でもいいから試してみろ、と言われて、「ゲーテ曰く……」と若き統一はしばらく考え込んだ。限られたドイツ語の語彙の中から、すぐ気の利いた文句を持ち出すのは難しく、やっと口をついて出たのは、「ゲーテ曰く、『ベンツよりホンダ』」。
これを聞くや否や、ヨハンは腹を抱えて笑い出した。笑い過ぎた勢いででんぐり返しまでして、最終的には統一がドイツ語の日常会話を特訓してもらう返礼に伝授した座禅の格好に落ち着く。無論、統一に禅の心得などあろうはずもなく、ただ、ヨハンがしきりにその方法を聞きたがるので、口から出任せを教えてやったまでのことだった。しかしながら、このドイツ人はそれを真に受けて、「トーイチがあんまり面白いから、ゼンを組んで鎮めなきゃ仕方ないよ」と息を吸い、吐き、また吸って……と師匠の伝授してくれた作法を律儀に繰り返していた。
「流石にまずいんじゃないの?」と苦笑する統一に、
「いや、いけるいける。大体、ゲーテが何年前の人か分かっているドイツ人がどれだけいるかも定かじゃないんだから」とヨハンはまたゲゲゲと笑ってみせた。統一は隣人の似非座禅を見つめながら、自分が日本の伝統文化について同様のことを行っているように、このドイツ人もまた幼気な外国人に間違った知識を植え付けようとしているんじゃないかと疑ったが、次第に、いや案外そんなものかもしれない、何せ光源氏は源義経と一緒に平将門と戦ったと勘違いしている日本人もいたというくらいだから、といつだったか大学図書館の日本語新聞で読んだ話を思い出して、やがて自分でも無性に笑えてきたのだった。
それからというもの、統一とヨハンの間で、「ゲーテ曰く」と前置きしたり後付けしたりするのがお決まりのやり取りとなった。統一が古いドイツ語文献の読解に行き詰まっている際は、ヨハンが「大丈夫。ゲーテも言ってるよ。『神はスペイン語を、女はイタリア語を、男はフランス語を、馬はドイツ語を話す』。馬にできることが君にできないことはない」と励ましてくれたし、二人で入ったレストランで、とんでもなく不味いローテグリュッツェが出てきた時は、「『朝食は皇帝のように、昼食は王のように、夕食は貧乏人のように食べる』。これはゲーテも言っていることだ」なんて互いに言い合って溜飲を下げた。こうした「ゲーテ曰く」の濫用が、他人の「ゲーテ曰く」の信用性を損なったのはある意味、避け難い帰結というべきで、当時大統領だったヴァイツゼッカーが演説等でよくゲーテを引用するのをTVや新聞で見ていて何となくおかしかったし、授業中にある学生が「ゲーテ曰く、『芸術は限定において生ずる』」と発言したのに対しては、思わず眉に唾を塗った(後から、実際にゲーテが「芸術は限定において生ずる」と言っているのを、T・S・エリオットの引用で知った際は、かなりの羞恥と若干の罪悪感を覚えないわけにはいかなかったが)。ベルリンの壁が崩壊した時には、「ゲーテは言った。『万歳、万歳、万歳!』」と二人で喜んだ。あのアパートに滞在したのは一年と少しのごく短い期間ではあったけれど、それだけでも確かに「ゲーテはすべてを言った」ような気がしてきたものだ。
その後、他のドイツ人に「ゲーテ曰く」を試してみることは何度かあったが、皆して「君は僕よりドイツに詳しい」と褒めてくれるばかりで、一向ジョークと受け取る気配はなかったから、やはりあれはドイツ人なら誰しも知る、というのではなくて、ヨハン自前のジョークだったのかもしれない。彼のような芸術家志望の若者が、自身の特殊性を普遍的な事実と喧伝する、あるいは錯覚するなんてことはよくあることだから。いずれにせよ、統一にとって、「ゲーテはすべてを言った」という言葉はまず、青春時代の遊戯の象徴のような、言うなれば魔法の呪いのような意味合いを持っていたわけだ。が、一つの呪いに頼り過ぎれば、その効能の薄れゆくは必至。
日本でゲーテの専門家として身を立ててからというもの、統一には当然、学生や同業者、ゲーテ好きの素人らと会話しながら、ゲーテの言葉を引用したり引用されたりすることが度々あったが、それらの引用元がすぐにピンとくることなどはせいぜい二回に一回というところだった。最初の内はその場で出典を尋ねたり、後から自分で調べたり、という手間を惜しまなかったが、度重なれば段々そうもいかなくなってくる。特に彼がゲーテ協会の理事となったり、学部長を務めたりするようになってくると、一応日本におけるゲーテ研究の第一人者で通っている自分が、「そんなこと言っていたっけ?」なんて尋ねでもしたら、引用した相手は色んな意味で気まずかろうし、たとえ何かしら悪趣味な――いわゆる漱石の「猫」における迷亭のような――魂胆で名言を引用するような人間に出くわしたとしても、そういう連中にはやはり無言で返してやることが一番の薬なのである。だから、統一はいつからか、ゲーテの言葉と聞くと、ごく軽やかな風を装って、きっとどこかで言っていたのだろう、いや、確かあの本で読んだかな、うん、読んだ気がする、と、うんうんやり過ごすようになっていた。あるいは彼自身、ふとした会話の最中についゲーテの威を借り自分の意見を通そうとしてしまうときもあった。その度に彼は、「ゲーテはすべてを言った」という言葉を苦々しく思い出し、それが何度も繰り返されるにつれ、思い出すことすら忘れた。魔法の呪いは回り回って、今や統一の身を蝕む呪いと化していた。
だからといって、統一はその呪い、もとい呪いに振り回されることは最早なかった。妻の目の前で取り乱すマクベスじゃあるまいし。そう思って、ティー・バッグのタグを自らの尻ポケットに突っ込み、もう大分温くなった紅茶を飲み干した。
娘に金を出させるつもりは端からなかったから、「そろそろ会計を」と妻の膝を突いて合図を出す。しかし、そのタイミングで俄かに娘が立ち上がり、紅茶棚の方へすたすた歩いていくと、先ほどと同種のアールグレイのティー・バッグを大量に持って帰ってきた(実はその間に彼女は勘定も済ませてきていたのだが)。そして、それらを次々開いていっては、逐一文句をつけ出す。「『The love you take is equal to the love you make. —Paul McCartney』? いやJohnの『Love is old, love is new. Love is all, love is you. 』の方がいいけどなあ。ねぇ、パパ?」とか、「『Love conquers all things.—Virgil』? もう、そこはChaucerでしょー」とか何とか。その様子を見守りながら、統一は「PaulでもJohnでもいいが、こういった商業的利用は著作権に引っ掛からないのだろうか?」とかそんなことばかり考えていた。ゲーテのことなんてもうすっかり忘れて。結局、徳歌の調査によって、そのティー・バッグには少なくとも二十パターン以上の愛に関する名言が刻まれていることが判った。
「で、これ、どうするの?」卓上に溢れたティー・バッグを見下ろして、呆れ顔に義子が言う。
「勿論全部飲みます。余りはスタッフが美味しくいただきました」と娘は何食わぬ顔で返す。
「まあ、朝の珈琲は当分お預けだな」
しかして、徳歌のハンドバッグに詰め込まれたティー・バッグは結局、一ヶ月後の木曜日、博把家のゴミ袋に詰め込まれ、回収され、燃やされることになる。
*
帰宅後、徳歌は自室に直行し、身軽な格好に着替えて出てくると、「一寸走りに行ってくる」とさっさと外出してしまった。近頃急にダイエットの必要を訴え出した彼女は、毎晩欠かさずランニングに出掛けて中々帰ってこない。決してダイエットが必要な体型には見えないし、そういったことを気にする性格でもなかったはずだが、男親からそういうことに口を出すのは流石に気が引けるから、と統一は黙認している。しかし、これまた男親としては、こんなに遅くから一人娘が夜道をランニングすることに対する幾許かの恐怖感も拭い去れないのであった。そのことを以前妻に話したら、「大丈夫でしょ。あの娘、合気道やってたし」とまるで知らん顔をしていた。全く冷たいものだ。その妻はというと、既にリビングのTVのスクリーンに好きなYouTuberの動画を映し出して、それを観ながら、黙々とハーバリウムを作っている。彼女の熱中しているYouTuberは、ドイツ人のガーデナー。それ以上のことを統一は知らないし、知ろうとも思わない。かつて実家の広い庭で何十種もの植物を育てていた妻は、今ではそのYouTuberに私淑して、小さな寄せ植えやテラリウムを作って、これをアリスやピーター・ラビットの世界に見立てることに楽しみを見出しているのだった。これを統一は、徳歌の出産のタイミングで、義父から勧められるままに高層マンションの一室を購入し、庭付きの家というかねてからの夫婦間の約束を反故にした俺への当てつけだ、と受け止めている。先程まで愛の言葉を分かち合っていたはずの家族は、今や思い思いの趣味に没頭して、およそ三位一体とは程遠い。
間も無く統一も自身の書斎兼準寝室に退いた。革張りの背もたれの部分がすっかりボロボロに剥げた椅子に腰掛けると、尻ポケットの中に微かな感触。そういえば、と例のタグを取り出し、様々なメモが貼り付けてあるコルクボードにピンで刺しておいた。それから、デスク上に散らかる大量の文書を掻き分け、推敲途中のゲラを手に取る。
それは、あるTV番組のためのテクストであった。「眠られぬ夜のために」というのが番組のタイトル。毎週土曜の深夜二十五時からの放送で、月毎に変わる課題図書について専門家が招かれ、読書好きなタレント数名に授業するという形式の三十分×四夜の番組だった。数年前に上梓してからというもの、学術書としてはまずまずのペースで版を重ね、昨年末に晴れて新書化した『七人のファウスト』で初めて統一のことを知ったという若い番組プロデューサーから直々に申し出があり、統一は来年四月の『ファウスト』回を担当することになっていた。統一の知人で、出演経験のある者の多くが、「比較的自由にやらせてもらえるし、編集の仕方にも好感が持てる」と言っていたのと、何よりその話が来たと話した時の娘の反応が比較的よかったのとで(「あー、あの夜帰ってきてたまたまつけたらやってる番組か! 面白いよね、見入っちゃう」とのこと)、彼はその依頼を快諾した。結構意気込んで書き上げたテクストは、挿絵や図解などふんだんに取り入れ、数回の番組サイドとのやり取りも経て、いよいよ最終稿の締切が迫りつつあった――収録は約二ヶ月後で、テクストの出版はその一ヶ月後である。既刊の自著をパラフレーズしただけで特段修正を必要としない最初の解説部(「悲劇か? 喜劇か?」から「『ファウスト』の成立と構造」まで)を飛ばし、p.24「考える人」から推敲に取り掛かる。
「それでは早速、物語の序盤から見ていきましょう。あらゆる学問を修めたファウスト博士は、自分の人生を振り返って嘆きながら言います。
ああ、俺はこれまで哲学や/法学それから医学/果ては役立たずの神学に至るまで/熱心に学び抜いてきたわけだが/この通り、相も変わらず/哀れで阿呆な昔のままだ。
彼が長い学究人生で遂に知り得たことは、学問によっては何も知ることができない、ということだけでした。その手には、喜びも、尊厳も、金も財産も、名誉も権威も握られていません。そこで彼が頼ったのは魔法でした。彼は『この世界を奥の奥で統べている何か』を見出したい、と願います。そうすれば、これ以上、空しい言葉を重ねる必要はないからです。ここで問題になっているのは、ヨーロッパ的知の行き詰まりでしょう。ヨーロッパには古来、プラトン主義とキリスト教という二つの思想的源泉がありますが、『世界の根底を支えるイデア』を索めるプラトン主義は、教会の一神教的な思考モデルに偽装され、あらゆる思想家がこの問題に答えを出そうと努めてきました。ベーコンの帰納法も、デカルトの普遍学も……スピノザ……」
しかし、目の前に広げたテクストに、統一は中々集中することができなかった。そもそも、今晩は仕事をするつもりはなかったのだ。だからといって、あのままリビングにいても、娘はいないし妻と話すこともこれといって思い付かない。それで結局仕事に逃げ込むしかないわけだが、何遍自分の文章に目を通しても、言葉がてんでバラバラに感じられて仕方がなかった。なるほど多くの単語があり、それぞれに役割があって並べられている。一つの文字を他のところと取り替えたら、途端に全体の意味が通じなくなるだろう。しかし、だからといって、それら一つ一つの語彙が完全に必然性を持ってそこにあるとは、統一にはどうにも信じられなかった。具体的には、「物語の序盤」は「話の冒頭」でもいいし、「あらゆる学問」は「諸学」でもいいだろう、「言います」なんて「語っています」でも「こう独白します」でも何でもいい、大体最後の思想史めいた部分について自分は本当に熟慮したのか?……とこう考え始めたら全くキリがなかった。何より恐ろしいのは、これを書いていた数ヶ月前の自分はその必然性を確信していたということである。しかし、現時点の彼が信頼できるものは結局のところ、その数ヶ月前の自分だけなのも確かで、彼がよしとしたからには自分もよしと思えるだろう、と我慢して先を読み続ける。
「……ファウスト博士はふと、聖書の言葉を自分なりのドイツ語に訳してみようと思い付きます。選ばれたのは、ヨハネによる福音書一章一節にある『初めに言があった』という聖句。ファウストはこの『言』という部分から躓きます。本当に初めにあったのは『言』だろうか? そこで、『初めに思いがあった』、『初めに力があった』と私訳していきます。そして、最終的には『初めに行為があった』を採用しました。ここに、これから始まる物語の全てが詰まっていると言っても過言ではありません。元々、ファウストは学問=言葉の人でした。しかし、言葉は彼に何も与えてくれなかった。そこで、これからは人間に可能なすべての『行為』を為してやろう、というのです。こういうのを文学の世界でファウスト的衝動ということがあります。後の文学者の多くがこのファウスト的衝動を主題とした作品を書いています。バイロンの『マンフレッド』、バルザックの『絶対の探究』、フロベールの『聖アントワーヌの誘惑』、そしてこれは畢竟、文学者の欲望自体がファウスト的であることを示しており、やがてマラルメは……」
ここで耐えきれなくなって顔を上げた。上半身に熱が溜まり、目が回り出している。腹部に痛みを覚え、急ぎトイレへ駆け込む。数杯のワインがこんなに堪えるとは。俺の肉体も歳を重ねたものだ、と便座の上で自嘲しながら、「La chair est triste, hélas! et jʼai lu tous les livres.」という詩がまず思い浮かんだ。結局、何を食ったところで全部一緒くたに出てきちまう、なんて考えながら尻を拭う。トイレを出て、玄関に目をやると、そこにはまだ娘の薄桃色のホカのランニング・シューズはなかった。
部屋に戻って、潔くマーフィー・ベッドを開き、その上に寝転がるが、眩暈は益々非道くなるばかり。壁に掛けられたシェーデルの『世界年代記』とグーテンベルク聖書の揺籃印刷物の零葉も、歴代の学生たちからの御礼状も、園児だった頃に娘が描いてくれた家族の肖像――そこでは、大量の本に囲まれた巨大な鰐が画面の下半分を占めていて、父はそれに立ち向かい、母と娘がそれを後ろから眺めている。家族の上にかなり太い虹がかかっていて、心理学者に見せたらそれなりに興味を示しそうな構図――も、本棚に収められた学生時代に韋編三絶するほど読み込んだ文庫本の列も、平生「Publish or Perish」の通念を批判しているにも拘らず結局数年に一冊のペースを守って出版してきた自著の列も、知り合いの研究者からの献呈本と書評を頼まれている本も、今年の誕生日に娘からプレゼントしてもらった丸谷才一とデイヴィッド・ロッジの小説も(いずれも未読。何がj’ai lu tous les livres! むしろ、「数巻の書の読み残し」という方がいい。そういえば、もうすぐ漱石忌)、机の上のテクストも、来月の教授会の時までに目を通しておくべき資料も、コルクボードに突き刺さった途切れ途切れの思考の断片も、颱風さながら渦巻いていた。統一のあらゆる思い、力、行為の所産であるはずの言葉、言葉、言葉……しかし、彼は今、それらの内に新たな思いや力や行為の胎動を認められなかった。もしかしたら一度言葉にされた思いや力や行為は、ピンを刺され標本箱に整然と収まった蝶のように、二度と羽ばたくことはできないのではないか、とさえ彼は思いかけた。「Das Wort erstirbt schon in der Feder.」。ああ、まただ。結局、俺はすべてを言葉にしないと気が済まない。蝶は花の間を飛び交い、蜜をやりとりしている姿こそ美しいのに。しかし、颱風には必ず目があるもの。あらゆる言葉は実はその一点に向かって吹き込んでいくに過ぎなかった。言葉の濁流に運ばれるがまま、統一は身体をもたげ、その静止点をアリアドネの糸のように掴み取り、引き抜いた。
Love does not confuse everything, but mixes. —Goethe
じっと見つめていると、そこに並んだ文字がどんどん浮き立ってくるのを感じた。小さなタグ越しに、世界が丸ごとぼやけて見える。
*
この時、統一の心中で渦巻いていた昂奮とも不安ともつかない感情を詳らかにするには、やはり彼の学者としての主張について軽くでも触れておく必要があるだろう。それを理解するための格好のテクストといえばやはり、一九九九年初版の彼にとって初めての単著『ゲーテの夢――ジャムか? サラダか?』(百学館)になろうか。
「世界の多様性。それは世界の複雑性に直結している。この複雑性を豊富さととる人もいれば、難解さととる人もいる。豊富さととる人の中には、それを広げようとする人もいれば、自分たちのためだけにとっておこうとする人もいる。難解さととる人の中には、理解しようとする人もいれば、拒絶する人もいる。その対処からして、多様であって、複雑である。複雑さは決して混沌を意味しない。しかし混沌と見誤っても仕方のないほどのスピードで現代の情報社会は流動し、あれもこれも今すぐいっぺんに押し寄せる。それはほとんど、一個人のキャパシティを超えてしまっている。多くの場合、人々はそれに対し、反射的に畏怖こそすれ、あるがまま愛することは難しい。世界は多様である、という真理と同じくらい、世界はいかに一つであるべきか、という問いの出自は古い。その二つはいわば抱き合わせで、特に一神教をその基盤とする西洋的知性において、何度も繰り返し問われてきた。……そして、この多様性と統一性の問題について、ゲーテほど悩み抜き、書き残した人は他にいない」という一文で始まる本書には、ゲーテの二つの警句が重要なキーワードとして登場する。
世界は粥やジャムでできているのではない。固い食物を噛まねばならない。
世界はいわばアンチョビ・サラダ。何もかも一緒くたに平らげねばならない。
統一はこの二つの異なる世界観をそれぞれ、ジャム的とサラダ的と名付ける。曰く、ジャム的世界とは、すべてが一緒くたに融け合った状態、サラダ的世界とは、事物が個別の具象性を保ったまま一つの有機体をなしている状態を指す。こうした世界観の類型について、アメリカ社会における「坩堝」と「サラダボウル」、日本的「和」と西洋的「全一」についてなどに触れた後、ゲーテの世界観の揺れについて、主に彼の文学作品及び、『色彩論』、世界文学理論等を引用しながら辿っていく。結論に至っては、『ファウスト』におけるメフィストフェレスの台詞、「まあ、聞いて下さい。私は数千年もの間/この世界という固い食物を嚙み締めてきたが/揺籠から棺桶までの道程で/この古いパン種を消化せた奴などついぞいないのです/噓などつくものですか。この宇宙という御馳走を消化せるのは/ただ神あるのみだ」(1776-1781)を引きつつ、ゲーテは、人間はその限界性において、世界をサラダ的に理解し、かつ構成しなければならない、と考えながらも、ジャム的世界の理想を神に委託していた。「もしかしたら、その理想は詩的な次元の間で見出されうるものかもしれない」と締め括る。
本書は発表当時、単なる学術書の枠内に留まらず、現代的な世界理解の視座を示す画期的な人文書としてかなり話題になった。既に多様性という言葉が氾濫し切った社会に生きる読者からすれば、いささか時代遅れに感じられる部分はあるに違いないが、ポストモダン・ブームが下火になる中、文学作品のテクスト読解に根差しつつ平易に語られる世界理解は、ジャンルを問わず多くの人々から受け入れられた。表紙に採用されたマグリットの「ヘーゲルの休日」の絵も、それに一役買ったと思われる。発表から一年後、このポンペイアン・レッド(という言い方に装丁家の某氏は拘っていたが)の表紙の本がまだまだ駅前の本屋の店頭に平積みされている中、EUが「多様の中の統一」という標語を打ち出し、統一には更なる執筆依頼が舞い込んだ。また、当時物議を醸していた「チーズはどこへ消えた?」事件についても語ることになり、文庫化した際にはそれぞれに関する評論が追加されている。
ジャム的とサラダ的。このキーワードを統一はこの二十年の間、発展させ続けてきた。ただ本を書くだけでなく、たかが文学の研究者が口を出すことではない、と言われかねないことを危惧しつつ、国際情勢・文化問題について、社会学者や哲学者との対話も盛んに行った。幸い、大方の人間が、博把統一といえばジャムとサラダと覚えてくれて、話はスムーズにいく場合が多かった。統一が最も頻繁にメディアに露出していた頃は、ジャムではなくサラダを! と主張する彼を、国民的アニメのキャラクターに比して、「サラダおじさん」と呼ぶ若者がいたくらい。尤もこれが親しみに見せかけた蔑みに過ぎないことは統一も重々承知していて、それでもなお、「サラダおじさん」を演じていたのであった。
しかしながら、ヨーロッパ的共同体性を核に据える統一の理論は、ブレグジット以降何かと旗色が悪く、昨今のウクライナ情勢はそれに追い討ちをかけるようであったのもまた事実。そんな中、最初こそ単なる御神籤の大吉のように輝いていたが、段々「ゲーテはすべてを言った」という呪い/呪いの象徴かのように見え始めて打ち捨てた言葉が、統一の目の前に再び輝きを取り戻した。しかも、その輝きは一度目より眩く、また妖しくもあった。
「Die Liebe verwirrt nicht alles, sondern vermischt es.」統一は目の前のゲーテの名言をドイツ語に直訳し、試しに口にも出してみる。すると、途端にゲーテらしくないような気がして驚いた。とはいえ、これが本当にゲーテの言葉であったとしたら、十八、九世紀のドイツ語をいつかの誰かが英語へ直し、それをまた現代の日本人がドイツ語へ直しているのだから、当然といえば当然のことではある。
「愛はすべてを混淆せず、渾然となす」と今度は日本語に直してみる。そうすると、一寸はゲーテらしくなったか。そのとき、統一の念頭にあるのは勿論、ジャム・サラダのこと。愛はすべての事物を、ジャム的に混淆せず、サラダ的に渾然となす、とファウスト博士のように私訳してもよい。しかし、mixをどうとるべきかは、まだそれほど自明ではない。「confuse」(混同)、言うなればジャム的統一への対立概念として、「mix」(混ぜる)をサラダ的統一と解釈したが、本当にそれでいいのか?
それはこの言葉の原文を探し当て、文脈の中で判断するより他なかった。もし、これが思った通りの言葉であるなら、これこそ我がゲーテ学の真髄を言い当てる至言である。しかし、そうでなければ……。いずれにせよ、統一はこの名言を単に、「ゲーテがすべてを言った」で片付けることはできない、と思ったのだった。
(「小説トリッパー」2024年秋季号収録「ゲーテはすべてを言った」より)
最後までお読みいただきありがとうございました。続きは「小説TRIPPER」2024年秋号でお楽しみ下さい。
