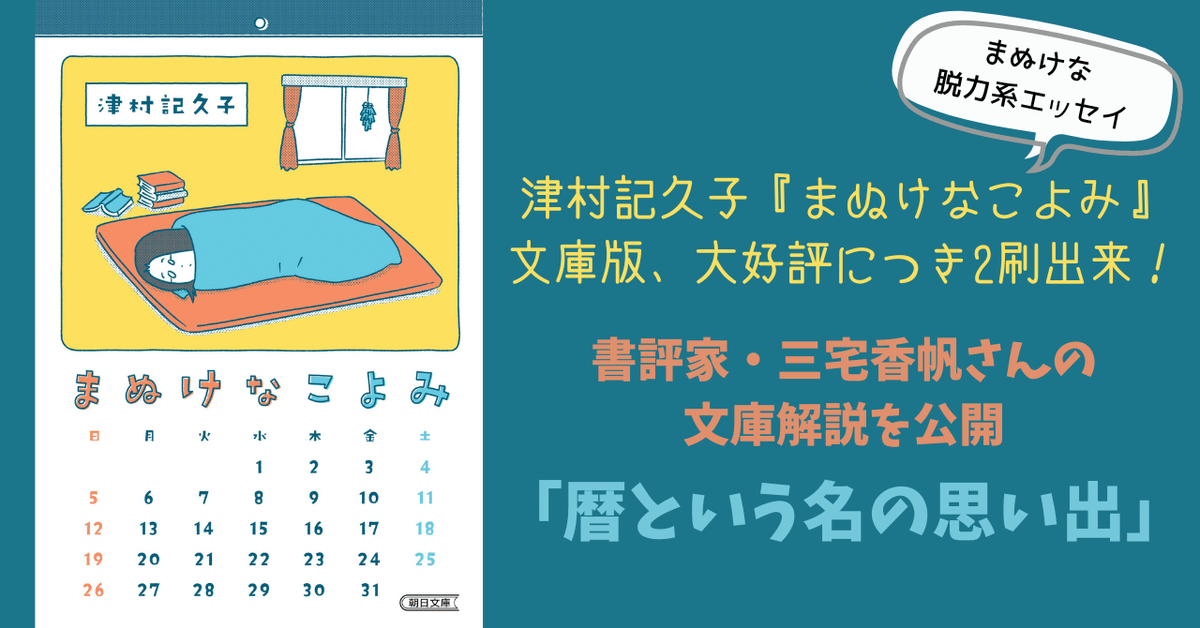
「津村さんが語るのは、ほかでもない、私たちの生活の肯定のことだと思う。」書評家・三宅香帆さんによる津村記久子著『まぬけなこよみ』朝日文庫版、解説を特別公開!
津村記久子さんの歳時記エッセイ『まぬけなこよみ』が待望の初・文庫化となりました。季節の言葉や、行事、ものにまつわる思い出がつづられた脱力系エッセイ集で、平凡社から2017年に刊行された単行本の、初めての文庫化です。卒業、入学、入社、引っ越しなど、季節の行事が多い今、ぜひお読みいただきたい一冊です!
発売後、大好評につき早くも増刷も出来、これを記念し、巻末に収録した、書評家・三宅香帆さんによる解説を特別に公開します。

暦という名の思い出
季節の変わり目だあ、と感じた瞬間、ふわりと昔のことを思い出すことがある。「あ、高校時代もこんなふうに自転車のハンドルを握る手が『寒すぎて痛い』って思ったな」とか、「就職したての春もなんだかもんわりした空気で憂鬱だったな」とか、なんてことない実感が季節の変化によって急に記憶の底から引っ張り出されるのだ。たしかに毎年季節の変わり目はやってきて、そして同じように次の季節にうつってゆく。毎年の夏の記憶が積み重なり、また今年も夏がやってきたとき、重層的な記憶が自分の目の前に現れる。本書を読んでいると、なんだかその感覚が幾度も呼び起こされ、私は不思議な気分になった。一冊読んだだけなのに、一年分の季節の変わり目を体験したような心地になったのだ。そんな本書は、津村さん流の「歳時記」。一年分の季節にちなんだ、さまざまな思い出が綴られている。
個人的な感想で恐縮だが、私は津村さんの小説を読むといつも自分のみみっちい思い出を頭の片隅で回想してしまう。どういうわけか小説を読む行為と記憶を回想する行為が同時並行でなされる。津村さんの小説は、人の記憶を刺激する何かがあるのだと思う。「ああっこういう人、部活の先輩にいたわ、でもめっちゃ苦手やったな」「でも私は結局一回もちゃんと反論できんかったな、それがいまだにむかつくな」など、もごもご記憶を反芻しつつ小説を読み進めてしまう。そしてその記憶は、なぜか、いつだってみみっちい。自分のけち臭い部分、人間としてよろしくない部分が詰まった記憶ばかりなのである。当然だがこれは津村さんの小説がみみっちいからではない(当然だ)。津村さんの小説はいつも面白くて、ユーモアと生活の細部のリアリティに溢れている。が、読む自分はその素敵な小説から変な記憶ばかり呼び起こしてしまう。『君は永遠にそいつらより若い』を高校生のときにはじめて読んだとき、ものすごく後悔した小学校時代の友人関係を思い出したことを鮮明に覚えている。『ポトスライムの舟』を社会人になって読み返したときも、『この世にたやすい仕事はない』を会社をやめて読んだときも、私の頭の中は会社ですごく面倒な発言をしてしまって微妙な空気にさせたなあという記憶で充満していた。
たぶん津村さんの小説には、人間に昔から備わっているしんどさを掬いあげるものがあるのだ。しんどさの中身といえば、たとえば人間同士が集まれば恐怖にも似た人間関係の滞りがどうしたって生まれてしまうこと。あるいは年齢を重ねるにつれて憂鬱な午後が増えること。そして思い出すだけでもっと何か言えることがあっただろうとむかついてくるような人のこと。そういう、生きてるだけで増えるしんどさを、津村さんの小説はひとつひとつ物語にしてくれる。だからこそ、「あああの時の自分って、いったい……」と後悔する記憶も、そっと掬い上げられたような気になってしまうのだ。
そしてその特性は、エッセイにおいても変わらない。小説家には二種類いて、小説とエッセイのテイストがまったくもって異なる人と、小説とエッセイのテイストがわりと似通っている人がいる。そして津村さんは後者だ。と、言い切ってしまうと、津村さんの小説にもいろいろなテイストの作品があり、一括りにしてしまうのは乱暴な行為だと思う(そして津村ファンからも怒られそうだ)。それでも根本的な書く姿勢は、小説もエッセイも変わらない、と私は思う。小説もエッセイも、津村さんは日常の重たい憂鬱とちょっとした歓喜をひとつひとつ書くべきものとして掬い上げる。まるで小学生のころの宝物箱のように、日々あわただしく生きていると忘れそうになってしまう、夕暮れの匂いや、ボタンの可愛さ、貯金通帳を渡された日のことを描いている。
そんな津村さんの、本書に収められた季節に伴う思い出のエッセイたち。それはやっぱり私たち読者のなんでもない記憶まで呼び起こす。たとえば「税務の妖精」の章ではアルバイトの収入の関係で、はやくから税金のことを考えていた友人の話が綴られる。この話を読んだ私は、津村さんの友人と同じように学生のうちから「100万をこえないように」とアルバイトの時間を調整していた同級生をみて、自分は就職すらしたくないと思っているのにえらいなあ、と情けなくなった日のことを思い出してしまった。今もなお私は、税金という言葉には、腹立たしいやら情けないやら恥ずかしいやら、不思議なつらさを感じてしまう。たぶん自分が税金の仕組みを把握しきれていないのではという不安があるからなのだが。――と、こんな話を津村さんはエッセイでひとこともしていないのに、なぜか頭の中では回想が始まってしまうのだ。本書を読んで、私は「こういう、人の記憶を呼び覚ます言葉っていったいどうやってできるんだろう」と考え込んでしまった。
情けない記憶も、陰鬱な記憶も、すべて津村さんの言葉にかかれば、なんだかマシな記憶に見えてくる。子どもがひとつひとつの宝物を並べるのを眺めるように、私は津村さんの紡ぐ季節の記憶を読み通す。それはしんとした冬の静けさのなか、ひとりでラジオを聴いた深夜の記憶に似て、自分だけの幸福な読書であることを実感する。ラジオを通して語られている言葉が「みんな」に向けて語られていることは百も承知でも、それでも「私だけ」に向けて語られているような感覚になる。津村さんの語る言葉も同じで、これはいろんな人が共感するエッセイなのだとわかっていても、それでも感情は「ああその感覚私もわかるっ、というか私にしかわからないと思う」と深く重たい共感を覚えてしまう。
実際、本書の生まれる契機となった「暦」というものは、人間の共通の記憶をつくるために生み出された文化装置なのかもしれない。暦をとおして、津村さんと読者は同じ生活感覚を共有する。どんどん移り変わる季節のなかで、少しだけ掴まえておきたい、季節の変わり目のしっぽを一緒に思い出す。元旦になるとなぜか生活がリセットされた気がすること、会社でコンビニおでんを食べたこと、こたつが恋しくなること。暦という私たちの生活に根差した風習を通して津村さんが語るのは、ほかでもない、私たちの生活の肯定のことだと思う。なんでもない生活のなかで、それでも忘れたくない記憶を抱えることは、私たち庶民の抵抗にも近い贅沢なのかもしれない。
