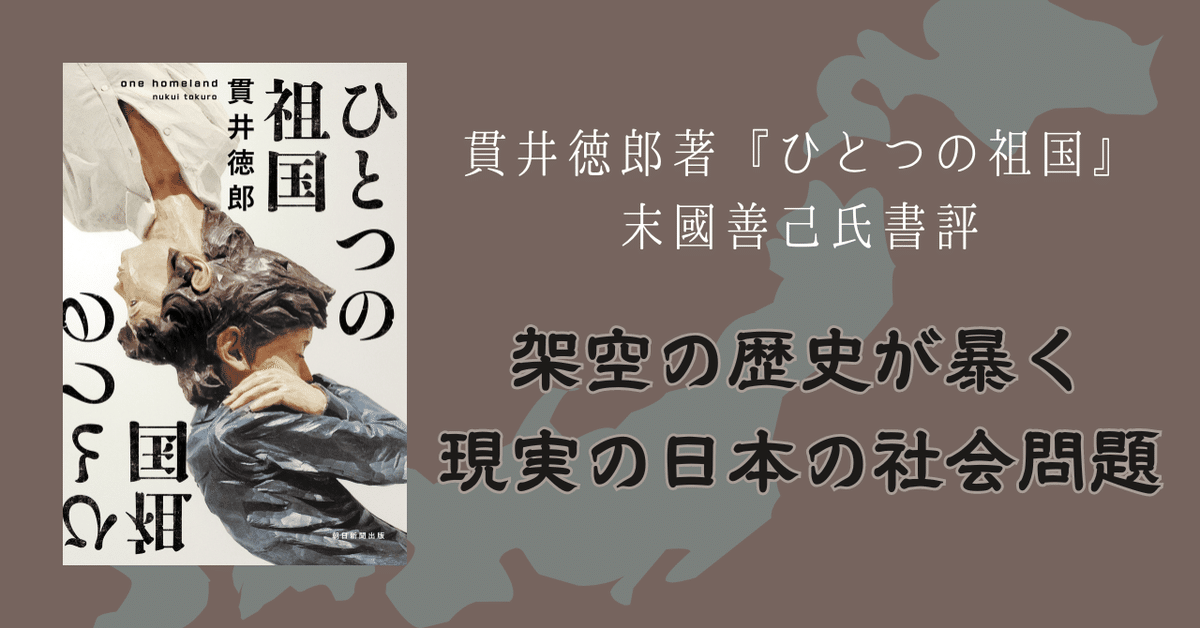
もし日本が分断されていたら…架空の歴史が暴く現実の日本の社会問題/末國善己氏による貫井徳郎著『ひとつの祖国』書評を公開
貫井徳郎さんの最新作にして最高傑作『ひとつの祖国』が2024年5月7日(火)に刊行されます。第二次大戦後に分断され、再びひとつの国に統一されたという設定の架空の「日本」。その日本は統合された後も、東西の格差は埋まらず、東日本の独立を目指すテロ組織が暗躍しており……。意図せずテロ組織と関わることになった一条昇と、その幼馴染で自衛隊特務連隊に所属する辺見公佑の二人の青年の友情が交差する、極上の社会派エンターテインメント巨編です。書評家の末國善己さんが「一冊の本」24年5月号でご執筆くださった書評を転載します。

架空の歴史が暴く現実の日本の社会問題
架空の島を舞台に、明治初期から平成末までの近現代史を17の物語で追った全3冊の大作『邯鄲の島遥かなり』を刊行した貫井徳郎の新作は、第二次世界大戦後に東西に分割された日本という架空の歴史を描いている。実現はしなかったが連合国は日本の分割統治を検討していたので、本書はあり得たかもしれないもう一つの歴史を題材に、現実の日本が直面している諸問題に切り込んでいる。
先の大戦末期、北海道を制圧したソ連軍が本州に侵攻した結果、西日本に民主主義国が、東日本に共産主義国が誕生した。経済大国の西日本と停滞する東日本は国民性も違ってきたが、東西ドイツが統一された影響もあり一つの国になった。しかし東西の経済格差が埋まらない間に西日本は競争力を失い、急成長する新興国に追い抜かれた。
物語は統一から30年後、東日本の搾取を続ける西日本からの独立を目指し武装闘争を行う〈MASAKADO〉がテロを活発化させている東日本の東京から始まる。東日本出身の一条と西日本出身の辺見は、父親が共に自衛官だった縁で小学校時代に知り合い、中学卒業後に別れた後も友情を育んでいた。大学卒業後、父と同じ自衛官になった辺見に対し、一条は有期雇用の契約社員になっていた。
日本統一後の流れはバブル崩壊後の長期経済低迷に重ねられており、特に就職氷河期世代は高学歴なのに肉体労働しか仕事がない一条への共感が少なくないだろう。また自発的ではなく、日本がドイツに倣うように統一した設定は、外圧がないと変われない日本社会への皮肉に思えた。
一条は同僚の聖子に、経済学者・春日井の講演会に誘われ、さらに春日井の自宅にも招かれ、思わぬ形でテロ組織とかかわることになる。追われる身になった一条は、〈MASAKADO〉の理論的指導者の春日井、構成員の聖子により、アジトに匿われた。春日井は、新規メンバーで信頼できる一条に、聖子が所属している〈MASAKADO〉のセクション(支部)に潜入しているスパイを捜し出して欲しいと頼む。
一条が顔合わせの名目でセクションのメンバーと会い、誰がスパイかを推理する前半は、本格ミステリーの作家としてキャリアを積んできた著者らしい犯人当てとなっている。聖子によると、〈MASAKADO〉はテロで独立を果たそうとする武闘派と、テロでは独立は実現できないと考える穏健派が対立しているという。ただテロを批判する穏健派も、格差、差別を生むシステムそのものの破壊を目論んでいた。この穏健派の計画は、『灰色の虹』『悪の芽』などで悪とは何かを追究してきた著者が、悪と正面から向き合い、それを根絶する方法を提示したともいえるだけに、壮大なビジョンも含め衝撃を受けるのではないか。
穏健派の計画に一定の理解を示していた一条だが、武闘派や異なる意見を認めずに排除し、強引な手法で計画を進めようとする穏健派に違和感を覚える。穏健派の主張は、正義が次第に独善となり最後には悪に転じることも珍しくないネット言論の戯画ともいえるので、生々しく感じられるはずだ。
〈MASAKADO〉にかかわった一条は、身分証明書なしでスマホ、宿泊場所を確保する方法や、限られた資金を何に使うかを考えるが、普通の生活空間が冒険の最前線になるだけに圧倒的なサスペンスがある。著者は、独善と気付かず悪を実行する穏健派、心の中に揺れはあるが国家の敵を悪と断じて戦う職務に忠実な辺見、無私の心で一条を助ける小さな個人の善意を対比することで、本当に社会を改革できるのはどの考え方かと問い掛けており、考えさせられる。
本書は、経済格差、特定地域への差別、よい国を造るよりも集票が期待できるポピュリズムに走る政治家、沖縄に負担を押し付けている米軍基地問題など、現実の日本と重なる社会問題を俎上に載せている。現状に不満はあるが改革を訴えてこなかった一条は、はからずも政治的な闘争を経験したことで、持たざる者は努力しても持てる者になれないため、自分より下の人間がいると満足し、あらゆることに無関心になっている状況が、社会の変革を阻んでいる現実を知る。これは無関心と無気力が停滞を是認するどころか、不満を口にしたり、改革を主張したりする人たちを批判する声が大きくなっている現実の日本も同じである。
一条を追う辺見が最後にたどり着いた境地は、苦しくても生き続けること、諦めず理想を追うこと、上からの押し付けではなく下からの声を集めて社会を動かさないと、真の改革は実現しないことを気付かせてくれるのである。
