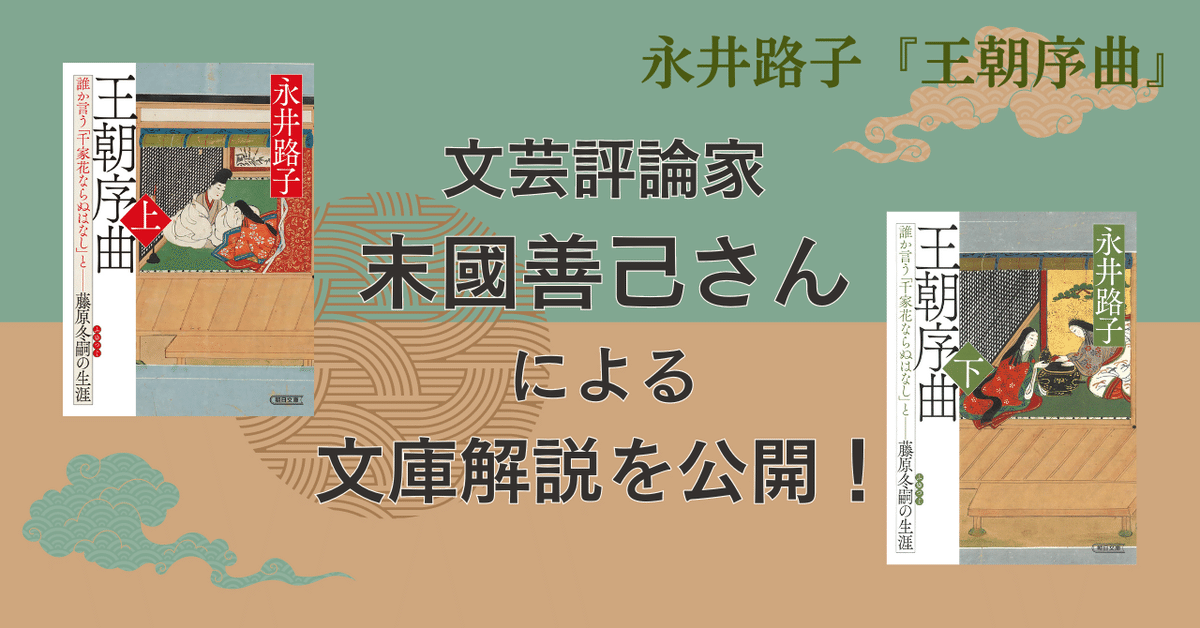
永井路子さんの『この世をば』『望みしは何ぞ』に連なる、歴史巨篇『王朝序曲』/文芸評論家・末國善己さんによる文庫解説を公開
永井路子さんの『王朝序曲 誰か言う「千家花ならぬはなし」と──藤原冬嗣の生涯』上・下(朝日文庫)が刊行されました。藤原道長に連なる藤原北家の基礎を作った冬嗣を中心に、桓武・平城・嵯峨天皇三代にわたる宮廷闘争を描いた、「平安朝三部作」の幕開けとなる傑作歴史巨篇。奈良朝を終わらせ、平安朝への道を開いた彼が目指したものとは――? 文芸評論家の末國善己さんが寄せてくださいました解説の全文を掲載します。

持統天皇8(694)年から和銅3(710)年まで置かれた藤原京は、現在判明している限りでは中国の条坊制を採用した日本最初の都城で、昭和9(1934)年に始まった発掘調査で大極殿跡などが発見された。藤原京から都を移した平城京は、遷都後に放棄され都の面影は消えていたが、明治22(1889)年に建築史家の関野貞が小高い芝地が第二次大極殿の基壇であることを発見し、大正11(1922)年に平城宮跡は国の史跡に指定された(昭和27〈1952〉年には特別史跡、平成10〈1998〉年には「古都奈良の文化財」の構成遺産の一つとして世界遺産になっている)。
延暦3(784)年、桓武天皇は長岡京に遷都するが、長岡京は建築途中で放棄されたというのが長く定説になっていた。西京高校教員の中山修一(後に京都文教短期大学名誉教授)と教え子の袖岡正清による発掘調査が始まったのが昭和29(1954)年で、大内裏朝堂院の門跡、大極殿跡などが発見され、“幻の都”とされてきた長岡京が平城京、平安京に匹敵する完成された都であった事実が判明した。長岡京跡は、昭和39(1964)年に国の史跡に指定されている。
発掘調査で判明した長岡京の当時の最新の知見を駆使し、平城京・長岡京・平安京へと都が移った桓武天皇・平城天皇・嵯峨天皇の時代を描き、平安時代の始まりを捉えたのが本書『王朝序曲 誰か言う 「千家花ならぬはなし」と――藤原冬嗣の生涯』である。本書と『この世をば――藤原道長と平安王朝の時代』『望みしは何ぞ――道長の子・藤原能信の野望と葛藤』は、永井路子の“平安朝三部作”と呼ばれていて、物語の時系列では本書が最も古い時代を扱っている。他の2作は既に朝日文庫で復刊されているので、併せて読むと著者の歴史観をより深く理解できるはずだ。
物語は、桓武の第一皇子・小殿(安殿、後の平城天皇)、策略を用いて白壁王(光仁天皇)を即位させ山部親王(後の桓武天皇)を皇太子にした藤原百川の息子・緒嗣、藤原北家ながら傍流だった藤原内麻呂の息子・真夏という同じ宝亀5(774)年に生まれた3人を軸にして進むが、中心になるのは翌年に生まれた真夏の弟・冬嗣である。後半まで政治の表舞台に出ない冬嗣は、安殿、緒嗣、真夏とその縁者が繰り広げる凄まじい政争を、傍観者として冷静に見ている。冬嗣の立ち位置は、アメリカの作家ロス・マクドナルドが生んだ冷静な観察者として有名な名探偵リュウ・アーチャーを思わせるものがある。
百川による光仁の擁立は、壬申の乱以降続いていた天武系が天皇になる流れを止め、皇位を天智系に取り戻したという意味で政治的なインパクトが強かった。百川は、革命の年である辛酉の年に山部を即位させ、天智系による皇位継承をとアピールするつもりだったが、その前に没してしまう。著者は、即位した桓武が、すぐに長岡遷都を決めたのは、百川が生前に立てていた政治構想を実現するためだったとしている。
遷都直後、まだ造営が続く長岡京で、工事の進捗状況を視察中の藤原種継が矢で射られ死亡する事件が起こる。射手の腕が見事だったことから近衛府と中衛府の兵士らが実行犯として捕まり、計画を立てたのが中納言大伴家持と証言した。家持が皇太子御所の内政を担当する春宮大夫だったため、桓武の同母弟で東宮の早良が首謀者とされた。早良は乙訓寺に幽閉され、皇太子の座を剥奪され事件は迅速に処理されたが、種継暗殺事件は、その後の桓武の治世に大きな影響を与えることになる。
桓武は、天武系の天皇が行った仏教の儀礼を否定し、先進国唐のような都を造り、唐の皇帝に倣った冠・服を着て、唐風の祭祀を行った。さらに山野を駆け巡って覇をとなえた皇帝のように、蝦夷攻略のために東北へ大兵団を送り込み領土拡大を目論む。大陸への憧れが強い桓武は、渡来人の末裔である百済王氏系の女性を内裏へ入れ、真夏、冬嗣の母・永継も女官になる。桓武の手がついた永継は安世を生むが、永継は正式の妃と認められず、安世は親王宣下を受けられないまま成長する。近代日本がヨーロッパに倣って近代的な天皇制・憲法・国民国家を造って帝国主義的な政策を進め、戦後日本が政治・経済・文化いずれもアメリカに追随していることを思えば、唐を模倣した桓武の頃から日本人のメンタリティは変わっていないのかもしれない。
死後も百川を敬愛する桓武に重用され、父に寵愛されている伊予親王に近い緒嗣に対抗するため、真夏は安殿の信頼を得ることで出世をしようとする。政治とかかわる機会がなく、かかわりたいとも考えていない冬嗣は、似た立場の異父弟・安世の庇護者のような立場になる。安殿が藤原縄主の娘を後宮に入れると、母の薬子も宮仕えをするようになった。安殿は縄主の娘ではなく薬子に溺れ、片時も手放さなくなる。それを見かねた桓武が薬子を追放し、これが後に桓武と安殿の断絶へと繋がっていく。
長岡京は水害に見舞われ、早良の怨霊が起こしたかのような怪異も相次ぎ、桓武は遷都を考える。合理主義者の冬嗣は、占いをして凶事の前触れなどというのが陰陽師の常套手段と平然としているが、天変地異の原因がはっきりしなかった古代の社会では、怨霊が凶事の原因になるというのは社会常識だった。だからこそ、怨霊の正体を暴き、怨霊を祓うと信じられていた陰陽師が支配階級の支持を得たのだろう。桓武は仏教を嫌っていたが、怨霊を恐れ「天台」という新たな仏教を学んだ最澄に傾倒していくことになる。
早良の怨霊に怯える桓武は、編纂を命じていた歴史書(『続日本紀』)に書くよう命じていた早良の事件を削除させた。早良の罪がなくなった結果、暗殺された種継の功績が小さくなり、それが平城天皇の即位で復権した種継の娘・薬子と兄の仲成には不満で、平城に訴えて削除部分を復活させた。一連の流れは徹底した史料調査で有名だった著者が、国が編纂する正史であっても権力者の思惑で簡単に事実がねじ曲げられる現実を暴いたといえる。歴史は現在も政治的に利用されるだけに、この史書完成までのエピソードは、誤った歴史を語ったり、歴史修正主義に騙されたりしないためにも、史書が編纂された背景を探り、複数の歴史書を比較検討する重要性を教えてくれるのである。
桓武は延暦13(794)年に、平安京へ遷都する。ここから平安時代が始まるとされるが、この定説に著者は一石を投じている。平城は、薬子との仲を引き裂いた桓武を憎み、その憎悪は桓武に愛された伊予にも向けられた。それを知る薬子は、伊予の排除(伊予親王の変)にもかかわり、論功行賞で出世する。だが著者は、平城と弟の嵯峨天皇が争った薬子の変は、平城を籠絡した薬子が主導したとの従来の解釈を否定し、天皇と太上天皇(上皇)が同等の権力を持っていた律令体制下にあって、平安京の嵯峨と平城京に居を移した平城の対立が深まり、嵯峨が迅速に兵を動かして二元体制に終止符を打ったとしている。近年は、薬子の変という呼称を使わず平城太上天皇の変とする高校の日本史の教科書も出てきているようだが、著者の歴史解釈はその先駆をなしていたといえる。
日本の天皇制は、権威を持つが権力をもたない特殊な統治制度とされる。確かに、平安時代の摂関政治、鎌倉から江戸時代までの幕府など、天皇は政治権力を公家や武家に委ね、(建武の新政を行った後醍醐天皇などの例外はあるが)親政を行うことはなかった。だが古代の日本では、中大兄皇子と中臣鎌足が宮中で蘇我入鹿を討ち中大兄皇子が天智天皇として即位した大化の改新(乙巳の変)、天智天皇の後継の座をめぐって弟の大海人皇子と息子の大友皇子が争い勝利した大海人皇子が天武天皇になった壬申の乱など、武断的な手法で皇位についた天皇は少なくない。その伝統は、早良を排斥した桓武、伊予を排除した平城の頃まで続いていた。だが独裁的だった桓武、平城の失敗を間近で目撃し、自身に政治的な能力がないと自覚していた嵯峨は、長く雌伏していた冬嗣の優れた能力を見抜き、その手腕に委ねる決意を固める。著者は、古代の天皇制の根幹だった律令制が限界を迎え、天皇が政治的な権力を持たなくなった平安初期に王朝が誕生し、そこからが平安時代になり、現代まで続く象徴天皇制の祖型ができたとする。
著者が、天皇親政の終焉を描いたのは、集団指導体制は、合議に時間がかかり迅速な政策決定をするのは難しいが、集団的知性でよりよい施策が作れ、間違った方向に進みそうでも修正を主張する人間が現れる可能性があるので、武断的で独裁的な体制よりも優れていることを示すためだったようにも思える。ここには、武断的で独裁的な体制により戦争に突き進んだ時代を生きた戦中派の著者の強いメッセージも感じられる。
いわゆる薬子の変の時、高官と天皇を繋ぐ役割として蔵人という役職が新たに作られ、初代の蔵人頭に冬嗣らが任じられた。蔵人所の新設についても、著者は史料に基づき独自の歴史解釈を展開しており、歴史に詳しい読者ほど驚きが大きいだろう。
窮余の策で作られた蔵人所のトップである蔵人頭を経験することは、後に政界進出の必須条件に近くなり、藤原道長の父・兼家、『小右記』を書いた藤原実資も務めている。また天皇の皇子、皇女を祖とする賜姓皇族の源氏は、天皇別に21流があり、その最初は嵯峨から分かれた源氏(嵯峨源氏)である。嵯峨源氏の源融は、紫式部『源氏物語』の主人公・光源氏のモデルとされており、本書の終盤は、藤原北家が天皇の外戚として政治の実権を独占した道長の時代の原点になっている。NHKの大河ドラマ『光る君へ』は、まひろ(紫式部)と道長の関係を描きながら進んでいるが、本書を読んでおくと、平安中期までにどのような歴史があり、なぜ優雅な貴族文化が生まれたのかがよく分かり、ドラマの世界がひときわ興味深く感じられるのではないだろうか。
