
【ストレイライト】if(!Straylight)について【シャニマス】
本記事はゲーム、「アイドルマスターシャイニーカラーズ」のイベントシナリオコミュ【if(!Straylight)】のまとめ・感想です。ネタバレをします。まだ読んでいなくてこれから読もうと思う人は本編を読んでからご覧ください。読む予定がない人は、本記事を読んで本作に興味を持っていただければ幸いです。
挨拶
こんにちは。ご機嫌な皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
今年は季節と言えるような梅雨がありませんでしたね。気付けば茹だる暑さの夏です。時折降る雨に癒やしを得て、同時に、湿気を不快に思っていることでしょう。
僕もそうです。しかし、おそらく皆とは違うところがある。非常に厳しい電力状況を鑑みた政府からの要請を聞き及び、律儀に節電をしているのです。僕の自室にエアコンがないことは完全無欠に無関係であると声を大にして言いたい。信じてもらえないのなら、快適な冷気のもと安眠するあなたたちの部屋に備え付けてあるエアコンの全てを破壊し尽くすその日まで、張り上げる声を大きくしていきたい。
でも、まだまだ夏は始まったばかりらしい。もう冬が恋しい。早く冬になればいいのにな。もしも夏が一週間だけだったなら……。
それではよろしくお願いします。
前書き
記事の長さ
この記事は25,000字程度です。インターネットで見つけた出典不明の情報から日本語は一時間に500字読めると考えると、全部読むと50分程度かかります。
主体と客体について
本文で使うので適当に説明しておきます。
「小説というものは『心情の変化』を書くものだ」などと言われますが、より詳細には心理、つまり人間の自己認知(自意識)を書いています。
まず動物の認識機能は、世界のことを行為する存在である主体と行為の対象となる客体に分けているようです。「やるかやられるか」という言葉や西洋の言語に見られる男性名詞女性名詞の風習などは、この認識というものの根本を表しているよう思われます。科学が明らかにしたように、世界では必ずしもそのような単純な様態をしているわけではありませんが、私たちの目に見える世界はそうなっているようです。
認識というものそれ自体も、世界に実在する実際のものを定義付け、言葉にすることによって抽象化するという行為です。つまりあなたが何かを認識するとき、あなたは認識するという行為の主体だと言えます。そして、認識された対象は、定義付けの対象として客体と見なされる、つまり客体化を受けることになる。
これは自分自身に向けられる認識である自意 識においても変わりません。そして、その自意識の状態によって能力や資質は左右されるらしい。そういった様々な事情で、外在する諸々を客体化し、客体化され、自分の能力に色々な影響を与え、与えられ、私たちは懊悩しながら生きている。
例えば、人間はこの主体と客体についての欲求を共に持っています。正確には、自らの混沌とした欲求というものを、抽象化し、主体と客体に分類することで単純化しています。動物由来らしき食欲や自由でいたいという主体に紐付くよう見做される欲求、注目されたい良く見られたいというような客体に基づくよう見做される欲求があります。それでいて抽象化の常として、その認識の過程で実際の有り様を様々に損なうので、これらの欲求は対蹠的であるとして感じられるが、度々矛盾もする。
そういった抽象化された認識というものを組み合わせ、論理を構築することで、様々な心情を抽象理論化したものが人文系の哲学であれば、そこから発展した娯楽が小説だと言えるでしょう。
変身願望
おそらく生殖機能と結び付き発達したものと思われますが、人間の有する巨大な客体についての欲求──承認欲求、あるいは不安は「神」や「思想」といった抽象観念をすら主体と見なすことで集合することを可能としました。その結果として、蟻のそれなどとは異なる、個体の機能における多様性を維持した社会が構築され、高度に複雑化した機能を発揮するようになったと言えるでしょう。しかし、その一方で複雑になるほど強力なる客体化の力は、社会の発展に伴ってますます大きくなっています。
そして、現代に生きる私たちは、一人の人間として恋する相手を持てないほどに忙しく、孤独でありながら、一方で動物としては社会から耐え難いほどの客体化を受け続けている。
そしてそんな僕たちの中にはある妄想が生まれる。「──もしも私が、今の私でない何かであったならば。」今の全てを投げ出してしまいたいという欲望が生まれる。
今回のイベントシナリオコミュでは、そういった「変身願望」を主題として取り扱っています。
カリスマ
原義的カリスマは、神からの恩寵を享けた魅力溢れる存在とされています。しかし、現代でのカリスマというものは、極度の客体を有し、外界からの刺激に対する過敏な反応とその体験を通じて自己の見せ方を追求し、さらに自己の経験に基づいて他者の客体に干渉する方法を習熟した存在だと言えます。実存的カリスマは、概ね主体たるものである美へ精巧に擬する存在です。
つまり、カリスマであることを存在証明としたカリスマには、一定のリスクが存在します。即ち、その美への素晴らしい模倣が、どこまでいこうと模倣に過ぎないという点です。理想的な美への擬態が行われていない状態が露呈すると、カリスマという存在は「カリスマの偽物」として認識されることで客体化されます。カリスマは、名もなき孤独な一般人に「ファン」という存在証明を与えているわけですから、この「ファン」達は自己の依拠する主体が揺らぐことによる不安を覚えることになります。いわゆる「炎上」という現象は、自己の存在症に係る主体の存在が揺らぐことにより不安が惹起されることに端を発するものであると言えましょう。
そして、カリスマ自身の「カリスマ」たるという存在証明も、ファンとの間の相互承認の関係が崩れることで揺らぐこととなります。カリスマという存在の類型は、概して元来感受性が高いわけですから大きな不安に苦しむことになります。
カリスマは魅力的ですが、その有り様は常に危ういのです。
シナリオのまとめ
ここからは各話をまとめながら振り返ります。どのような文脈であったかを抑えながら、大雑把に書いていきます。
オープニング:ORDINARY
オープニングでは、夏休みに浮足立った世間の人たちと、アイドルとして活動するストレイライトのメンバーたちの姿を描く。
若者割れでありアイドルでもある彼女たちは、それぞれの所属する集団から異なる要請を受けている。
和泉愛依は、夏休みに芹沢あさひや黛冬優子と遊びたいと弟から頼まれる。学校と仕事で忙しい彼女たちも、学校の夏休みなら余裕があると考えてのことらしい。和泉愛依はこれを気軽に承諾する。

一方で、アイドルの仕事でも、学校のない夏休みを当て込んでの依頼があった。しかもかなり熱意を伴う依頼のようだ。
ストレイライトのメンバーを雛形としたテレビアニメ作品に関連した仕事らしい。当のアニメは人気作で、依頼者と以前に仕事を共にした実績もあれば、仕事相手としてストレイライトが限定されてもいる。申し分のない仕事であるよう思われる。

芹沢あさひも夏休みを迎えている。教師から芹沢あさひに宿題を渡すよう言われた級友がいたようだが、彼女はそれをしなかった。

場面は転じて、ストレイライト一行は雑誌の取材を受けている。彼女らにされた最後の質問にて、陳腐な質問──『もしも、ストレイライトのメンバーじゃなかったら今何をしていたと思いますか?』──がなされる。

またも場面は転じて、ストレイライトはコンビニで流すPR音声を録音する仕事をしている。

更に場面は移り、黛冬優子は秋葉原の一般オタクが楽しそうにするアニメの話を立ち聞く。

そして最後に場面転換の黒駒として挿入が続いていたキャラメイク画面が表示される。

オープニングでは、来る夏休みを中心に、「あちらが立てばがこちらが立たぬ」状況が三者三様に描かれる。和泉愛依はアイドルと家族、芹沢あさひはアイドルと学校、黛冬優子はアイドルとオタク活動あるいは友人、がそれぞれ両立できない。
「忠ならんと欲すれば孝ならず、孝ならんと欲すれば忠ならず」という言葉がある。これは、支那由来の思想で言うところの主君に対する「忠」と親に対する「孝」が一致しない状況に相対した平重盛が言ったらしい。臣の忠と子の孝は、一般化すればいずれも君主あるいは親という主体に対して客体の立場を取ることと言える。
昔から、異なる存在から相互に矛盾する命令が下ると人は苦しい思いをすることは知られてきた。現代の僕たちも、助教と教授に異なる研究をやれと言われれば苦しい思いをする。課長と部長とが異なる教育方針を語ってくると甚だ困る。これはごく一般的な苦境であり、自意識に矛盾が生じると人間は苦痛を味わうことになる。

また、彼女らが対応できない要請についての自意識には微妙な濃淡がある。
まず、和泉愛依は弟から直接の要請を受けており、分かりやすいとはいえ彼の抱く思慕のような繊細な気持ちにすぐに触れている。個人の資質においても、彼女は非常に客体に寄っている。人の気持ちに敏いのだ。故に、今回のイベントシナリオコミュではストレイライトで最も強く矛盾を感じている。
次に、芹沢あさひはこの矛盾した状況に気付いてすらいない。彼女は無意識的で、客体に関する自意識の非常に乏しい存在として描かれている。教師や生徒同士の人間関係の希薄さによって学校とアイドル活動が両立できないが、それに気付くことさえないという状況が象徴的に彼女の性質を暗喩している。
最後に黛冬優子は無意識的、あるいは意識的に矛盾を生む欲求を無視しているようだ。
黛冬優子は、秋葉原で友達と馴れ合い、夏休みにはバイト以外には特にやることもなく持て余した時間でアニメを見る普通の学生を眺めるが、意識してか無意識であるか、深い思考を避けていた。
第1話:LINK
プロデューサーはストレイライトの面々に仕事を打診する。
持ち掛けられた好条件の仕事はであったが、その仕事は、ストレイライトの彼女たちが持つ二面性の裏側を強調するようなものだった。
プロデューサーはストレイライトの面々に、新しい仕事の打診をしている。先方からの強い希望のもと、人気のあるメディアミックス作品の舞台企画の主役としての出演依頼だ。条件は良いよう思われる。一方で、その仕事を受ければ夏休みはほとんどなくなってしまうらしく、更に懸念事項もあるようだ。
黛冬優子と芹沢あさひは乗り気だったが、和泉愛依は躊躇っている。


夏休みがなくなることを聞くと嫌そうにする

打診を受け終えたとき、その仕事に乗り気であるよう思われる黛冬優子と芹沢あさひに対して、和泉愛依は未だ躊躇があり、そしてそれを言い出せない。ストレイライトの面々は仕事で忙しく、三人で相談する機会を持てなかった。
しかし、後ほどレッスンの予定が重なった芹沢あさひを相手に話す機会を持てたようだ。和泉愛依は遠慮がちに話を振る。ほとんど服従に近いほどの謙譲があり、その内容に至るまでは些か婉曲した相談だった。
芹沢あさひはこのときの和泉愛依のような心情や態度を体験してことがないように思われる。彼女の様子から曖昧で微妙な心情を持っていることには気が付かない。

その後の仕事では、まだ受けることが確定していないにも関わらず、芹沢あさひは部外者のメイクスタッフに『〈if〉』の話をしている。さらに、黛冬優子や和泉愛依の事情を気にすることもなく、メイクスタッフに送ってもらった動画を「楽しいだろう」とストレイライトの二人に送る。

そして夜、黛冬優子は台本を読み進める一人の部屋でプロデューサーの躊躇の理由を理解する。配された役は、アイドルユニット「ストレイライト」として脚光を浴びる彼女らの裏側を描くようなものであった。
しかし、彼女は気にしていない。彼女の在り方は常に主客の二律背反にあり、主体に延長する客体、あるいは客体に延長する主体の混沌とした様態を意識的に肯っている。
かえって、二人に分けられた主人公『モモ』の役を一人でやれると呟く。

そして最後に和泉愛依も台本を読み、キャラクターの設定を知る。「現実ではクールな彼女が仮想現実では超ギャル」な役らしい。

この話では、オープニングで提起された複数の存在からの矛盾する要求が発生する様子を具体的に描く。
合理的判断、可能性のある快楽の追求、自己主張への恐れという三者三様の動機で、夏休みにはアイドルの仕事が優先された。黛冬優子は友達と睦む時間への羨望に蓋をし、芹沢あさひは宿題の未提出により悪化していくであろう同級生や教師との関係を知る由もなく、和泉愛依は弟との約束を反故にすることとなった。
更に、受ける仕事自体にも問題がある。
仕事の内容は既存の「人気作品」の実写化である。ここでの「人気作品」というものはいわゆる「覇権作品」だろう。つまり、その作品を見ている人間で規模感のあるファンコミュニティを形成している。この状態は、「覇権作品」を主体としたいわゆる「クラスタ」に属するという形式で視聴者が客体化を受けているものである。そして、この覇権作品〈if〉は「推し」を作る類型のいわゆるキャラクター物らしい。
従って、この作品での中心的主体はキャラクターである。必然的に、その存在証明を揺るがし得る実写化という事件は、コミュニティに属する人間に不安を齎す。炎上の原因は集団的不安である。黛冬優子の言う通り、この企画は炎上する可能性が高い。
さらに、和泉愛依は、その上に危険な役を受けてしまった。以前、動画配信者によって引き起こされ今では燻るように有耶無耶になった「和泉愛依のギャル疑惑」を思い出させる役である。「愛依サマ」を主体としているファンたちはその主体が「ギャルの和泉愛依が演じていたものである」という事実によって客体化されてしまうことで不安に苛まれるだろう。
そして、彼女はストレイライトの他の二人とは違い、仕事に向き合う態度にも未だ自分自身の主体としての意思の確認はできず──覚悟は決まらぬままである。
第2話︙MEET
ストレイライトは舞台の仕事を請けた。演者との顔合わせの場で初めての挨拶をする。彼女たちの姿勢はそれぞれ変わることはない。彼女たちがこれまでに重ねてきた成功の経歴は、必ずしも彼女らを幸福に近付けるわけではないようだ。
舞台のための仕事が始まった。稽古には様々な出演者がいる。作品内で同じ人物としてされる演者は、お互い似ているように見えるらしい。

挨拶を終えた後にはPRのために、作中で同一人物とされる二人での写真撮影が行われた。『モモ』役の新人女優は黛冬優子を推すストレイライトのファンらしい。その熱量は高く、女優を志したのも可愛く、格好良い彼女への憧れのためだという。
直接思いの丈をぶつける新人であったが、黛冬優子はあくまでも仕事相手としての社交辞令を言うに留める。

仕事は終わりに撤収となった。エレベーターにて芹沢あさひと和泉愛依はプロデューサーに送迎してもらうことを前提に話しているが、黛冬優子は寄るところがあると一人で帰りたがる。

そこに例の新人が乗り合わせてきた。本日あったらしい不手際を謝るとともに、おずおずと黛冬優子との交流を希望している。

面と向かって断ると礼儀の要請にそぐわず角が立つ。彼女はおそらく最も無難な「プロデューサーに皆と送ってもらうことになっている」という都合の良い誤解を招くような物言いをする。ここでは異なる二つの存在による矛盾する客体化というものが有り触れた言い訳にもなることの暗示も行う。

こういった媚態に基づく振る舞いに疎い芹沢あさひに嘘を暴かれそうになったが、すぐに察した和泉愛依が制止した。
かくして何とか一人になれた黛冬優子だったが、通行人から声を掛けられる。悠然たる孤独に水を差した相手はファンを自称している。ファンを前にしたのなら彼女はアイドルなのだろう、即座に優雅を捨て去りアイドルとしてこれに対応した。

一方でプロデューサーに送られている和泉愛依は、同じく送られている芹沢あさひの「ポテトが食べたい」という突拍子もないわがままから、急遽コンビニに寄ることになった。
コンビニには彼女たち自身が以前収録したPR音声が流れている。そして店には花火が並んでいた。芹沢あさひが純粋な喜ぶ一方で和泉愛依は弟からの「うそつき」の言葉を思い出していた。

第2話では、ここまでに提示されてきた異なる存在による客体化について詳述する。特にアイドルとして媚態を示す自己とエゴイスティックな私生活の自己を区別している黛冬優子に注目している。
始まった舞台の仕事現場では、彼女と同じ人物を演じることになった新人女優が現れる。紛れもない新人らしく、やや要領の悪いところがあるようだ。それだけでなく、黛冬優子に憧れているらしく、「私もふゆちゃんみたいに可愛くて、かっこよくなりたい」と口にする。ここでは、本編の主題である変身願望、あるいは自己を理想に同一化したいという衝動であるところのエロースが不可分な状態で提示されている。後者には美へのエロースが含まれており、あくまでも現在の自己が自己たることが冀求される一方で、前者には現在の自己を棄却する企図が含まれている。
この場面では、黛冬優子が切り上げたために新人が持っているのが変身願望であるかエロスであるかの区別は示唆されるに留まるが、少なくとも他者からの憧れの言葉は、精神の発達した人間にとって喜ばしいものではない。
なぜなら、憧れの言葉には自己を卑下する印象が滲むことが多く、それでいて褒められること自体には少なからず客体化の要素がある。他人同士といえども、人には常にどこか似たところがある。存在証明が対面した相手と何一つ共通していないという可能性は存在しない。さらに質の悪いことに、他者への高評価であるという観点から、躊躇われるべきであることに思い至らないまま短慮に言われることが多い。さらに、感情に任せて、面と向かって相手にそれを指摘してしまうのは相手以上に直接的な無礼だ。
細かい点を挙げればまだあるが、他人への褒め言葉は、少なくとも自己を卑下する心理が存在しないことを確信できる場合においてのみ多少は許される。発言者に自己への肯定と覚悟が必要なものだ。従って、AR世界である〈if〉では臆病な自分を変えてアイドルとして活躍する主人公に共感している新人が口にした──変身願望に基づく憧れの言葉は不快なものである。
この新人は、慣れない舞台仕事の不安と劣等感をひけらかし、無意識であろうが、そのまま「憧れの相手」から不安の解消を目的とした承認を要求する。そしてその状況から、対価のように投げ出された安っぽい言葉で相手を評した。
このような状況では相手への悪口から傲慢の演技まで様々な対応が考えられるが、ほとんどの場合では「ありがとう」の言葉が最も無難である。ただし、この対応では言う筋合いのない感謝を言わされることへの不満や、安い褒め言葉という侮辱を無視せねばならないことなどによって沸き起こる様々な感情に耐える必要がある。
ここで、黛冬優子はアイドルとして望ましいとされるであろう通り一遍のお礼の言葉を口にしている。表面的には何でもない風を装わなければならないこの状況に精神的な負担を感じているよう思われる。また自己紹介に難のあるストレイライトメンバーのフォローなどを含めて、かなり疲労が溜まったようだ。
彼女が一人で帰ることにしたのは仕事が終わってからだろう。顔合わせの疲労感は、ユニットの仲間やプロデューサーといった、比較的楽に過ごせる親しい他人との時間でさえ億劫になるほどのものだったのだらしい。
偶然乗り合わせてきた新人には、芹沢あさひの性質を知りながら、短慮に一般性のある社交辞令を言ってしまうというやや粗雑な対応をとる。
そしてようやく一人になれたにも関わらず、帰り道では、アイドル黛冬優子に対して、ファンを自称する通行人から声が掛かる。彼は仕事時間外に話しかけるばかりでなく、私生活を詮索する不躾な質問までも行ってくるのだった。
アイドルとしての活動は楽しいばかりではないらしい。手にした名声、成し遂げた成功は、彼女を不自由にしている。
第3話:EMPTY
主役である新人の不手際など、〈if〉の舞台化は、人気作品だけあり良くも悪くも話題になっていた。プロデューサーは忙しいストレイライトのメンバーに困ったことはないかと心配している。
この仕事に向けたレッスンも始まり遅くまで練習をしている。日が落ちて、和泉愛依は家族旅行で空っぽの家に帰宅する。
『〈if〉』の舞台化は本格的に始動したようだ。出演者を集めての稽古が行われている。モモ役の新人は、合わせる稽古にも関わらず、その前提になる台詞入れが十分でなかった。
共演者であるストレイライトの彼女たちはそれを見守るしかない。

舞台化企画は公報でも活発化しているようだ。それを受けてSNSは実写企画としての「良くも悪くも」話題になっている。
その中にはストレイライトのファンのものと思われる書き込みもあった。

それを受けてかプロデューサーは、様々な意味で忙しない夏休みを迎えるストレイライトのメンバーに不自由がないか確認する。

『〈if〉』のための活動は彼女ら三人の練習でも始まっている。芹沢あさひは『〈if〉』アニメシリーズのCGを用いたライブシーンの完璧な再現を目指しているようだ。

長い練習を終えた和泉愛依は、家族旅行で空っぽになった夜の家に帰宅する。

第3話では、本格化した『〈if〉』舞台化企画を中心とした様々な出来事を中心に、複雑に客体化されていく彼女らの日常を描く。
舞台稽古では、もう一人の主役である新人が、舞台そのものの新人でありながら、衆人環境で覚えた台詞を思い出し、台詞を読み、役の存在を考察し、役の振る舞いを再現し、周囲の様子を観察し、周囲の様子にそぐうように調節し、……なければいけない。彼女は突然に複数の行為を同時に行う場を経験している。
人間が意識的にできる行為は一時に一つだけである。新しいことをする場合、一つずつの行為を一つずつ意識し、つまり一つずつ集中する他ない。複数のことに意識を払わないといけない場合、失敗の可能性は飛躍的に上がる。
練習とは、この一つ一つの行為の質を上げるために行われるものでもあるが、それ以上に行為を無意識化するための手続きでもある。特に基礎練習、反復練習はそのために行われる傾向が強い。

彼女は新人ながら、つまり発声などを含む無意識の所作や、台詞を思い出す認知的手続きなどといった、経験という肉体に結びついた無意識の財産を持たず、主役という注目と期待と容赦のない評価を浴びる役柄にさえ割り振られている。
おそらく、〈if〉のストーリーライン──自分を変えたいと願う少女がAR世界で無双する──を反映するために、デフォルトネームとして内定していた黛冬優子に「なりたい」という彼女をキャスティングしたと思われる。
従って、演出家等の制作側には、彼女の内にある自己への不満や現状への不足が見出されている可能性が高い。エロスであるか変身願望であるのかは不明であるが、オーディション時には少なくともその源泉になる自身の欠損の自覚が発見された。舞台への情熱のためと言えば聞こえは良かろうし、人権軽視と言えば聞こえは悪かろうが、彼らは舞台の完成のために様々なものを切り捨てる残酷な舞台制作の方法を取っている。

次に黛冬優子は〈if〉の実写化に際しての意見を「五分五分」の賛否両論と評しているが、その実取り上げられた意見は直接ないし間接的に忌避的なもので占められている。
作品の実写化が忌避される理由は一定の説明が可能であり、先に述べた通りである。
そして、その原因であるコミュニティを形成する主体の変化については、コミュニティの主体たるストレイライトの彼女たち自身にも起こることだ。ファンの前に立つとき、彼女たちはファンの安穏を守るためにファンがファンになったときの「ありのまま」の彼女らでなければならない。

これは自己を客体化する存在の変化によって起こる不安という一般現象だ
特に誰かに注目するなら和泉愛依だ。彼女が演じることになった「アオ」という役はいわゆるギャルである。「和泉愛依はギャルである」と配信者に暴露された過去があり、幸いそれは有耶無耶になっている。しかしこの暴露というものは切実な問題だ。「愛依サマ」というファンにとってのありのままは、これにより覆ってしまう恐れがある。そのような危機を蒸し返すかもしれない配役にファンは不安を感じている。

一方で、第2話の終わり際に現れた自称黛冬優子のファンも書き込みを行っていたようである。曰く、「好感度が上がった」と。黛冬優子は疲れを押してファンにとっての黛冬優子として対応したわけであるが、実のところ相手はファンではなかったらしい。

また、プロデューサーがストレイライトに多忙であることに困っていないか聞き取りを行ったときに、黛冬優子がグッズの受け取りという如何にも軽く、それでいてしっかりエゴイスティックな頼み事をしたのに対し、和泉愛依は反故にしてしまった約束の話を持ち出すことができない。
こういった聞き取りが自発的に行われる場合、相手は直接力になれずに何もしていないのに自分が苦しんでいる状況になっていることが多い。そういう、相手が手持ち無沙汰な場合には、「力になれた」という承認を確保するためにだけにでも、敢えて自己の主体から発生する、不要不急で実現が容易な、それでいて本当に自己中心的な欲望を要求をくれてやるのがよい。
黛冬優子が要求したグッズの受け取りなどというのは実に好ましい。
一方で、和泉愛依の悩みは比較的重大なものだ。異なる存在から複数の客体化が行われる状況というものは人間にとって耐えるべからざるものだ。そして、プロデューサーの職責にスケジュールの管理は含まれており、悩み事の根本的な解決に向けて有効な仕事ができる機会が得られるのであれば、お互いにとってこれほど望ましいこともない。
しかし彼女は言い出すことができなかった。

『〈if〉』のためのレッスンでは、芹沢あさひが特に張り切っている。彼女は原作のCGによるライブシーンの「完璧」な再現を目指している。
そしてその動機には以前プロデューサーからの「求められた仕事をしないといけない」という言葉が含まれている。そしてプロデューサーから昼食にとGRADで彼女がお世話になった蕎麦屋の出前が届いている。
この場面では、客体についての自意識が発達してきている芹沢あさひが描かれている。
まず、完全への冀求というものを描いている。例えば、体操の金メダリストが体育館を後にするとき、その顔には深い翳がある。理想の形態を目指す人間は、その理想と自己の絶えざる相対化によって強烈に客体化される。どれほど素晴らしい動作が行われたとしても、それは理想との相対化によって、常に拙劣な失敗としての烙印が刻まれる。
芹沢あさひはアイドルになった当初から同じことをしていたとも言えるが、その動機は彼女はプロデューサーの言葉を振り返っている。彼が語った「客体における動機で仕事をしなければいけない、『やらされる』仕事がある」という旨の言葉によって、つまりプロデューサーに対する彼女の客体的自意識による動機によって完璧というものを目指しているのだと自らを認識して、つまり客体化している。
やってくる蕎麦屋もまたGRADで描かれた感謝──他者存在に主体意思が存在することを前提とした礼儀というものの典型──を通して、社会性とも言われることがある客体的自意識が発達する様子と結び付いた人間である。
以前の芹沢あさひがしていた練習は好奇心と遊びによるものであったが、現在の彼女は誰かの存在を前提として仕事に臨んでいるというところに大きな違いがある。

ストレイライトは日が暮れるまで練習を続けた。家に帰った和泉愛依は一人の部屋の暗闇をより深い静寂に感じている。
ここでは直接的かつ端的に、アイドル活動が家族の中の自分に優先している様子を示している。

『〈if〉』の企画が動き始めると同時に、彼女たちはアイドルと一人の女の子としての乖離を感じている。アイドルでありながら女の子であることも、女の子でありながらアイドルであることも、とても難しいことに思われる。
第4話:RUMOR
ストレイライトの出演シーンのリハーサルは上手く行った。舞台裏では新人が憧れを深めている。黛冬優子と和泉愛依は自主練習をすることにしたが、現場を後にする際に、舞台の裏方が彼女らを含む出演者の噂するのを聞いてしまう。
自主練習の最中、彼女ら二人は、これまでの自分の振る舞いを省みて話し合った。
ストレイライトが演じる舞台の山場であるライブシーンのリハーサルは上手くいったらしい。演出家を始めとした舞台出演者一同から好評価を受ける。
舞台裏では、ストレイライトのファンで原作に共感する新人が直接言葉をかけている。

評価を受けたものの、「芹沢さんはさすが」という演出家の言葉を不服とした黛冬優子は自主練習をすることにした。和泉愛依存も当然同行するものとして誘う。

現場を後にしようとしているとき、偶然に舞台の裏方が話しているのを立ち聞いてしまう。
彼らは大役を背負うことになった新人が「何とか形になりそう」であることから、黛冬優子が二役を演じるべきだったのではないかという話や、「和泉愛依が実はギャル」であるという噂の話にもなっている。

自主練習中に、黛冬優子は先程の事実である噂を耳にして表情を曇らせた和泉愛依を気遣っている。

それに対し、和泉愛依は自分で決めたことだからと後悔はしていないそうだ。黛冬優子はその返答に覚悟ができていると感心する。

しかし、覚悟ができているわけではないという。そうしてぽつりぽつりと、「もしも」の話を始めた。
現実にはあり得ないことで、そうするしかなかったことに疑いはないけれど──もしも、もしも……ギャルの疑惑が立ったときにそれが真実なのだと告白していれば、もしも、始めにキャラクターを演じていなければ……もしも、もしも、自分が緊張する自分でなかったならば……。
自己否定と紙一重の危険な自答の続きを、彼女は黛冬優子へ投げかけた。

しかし、黛冬優子はわざとらしくとも素知らぬふりをすることにした。あまりの陳腐さに茶化さずにはいられなくとも。彼女の後ろ暗い感情と、それでもそれを口にせずにはいられない大きな不安に対し、自らの覚悟を、つまり全力の強がりを示す。

そんな折、プロデューサーから電話が掛かってきた。それは新人の怪我とそれに伴う舞台の降板を知らせるものだった。

第4話では、新人の成長とともに、彼女の中での黛冬優子の存在が変化する。また、ここまで描かれてきた弟との約束を反故にしたことに対することを含めて、和泉愛依の変身願望にかかる客体化を通してもたらされた苦境に対しての解決が描かれる。
まず、新人は「なんとか形になりそう」なほどの成長と適応を見せている。客観的な第三者であり、これまで何度も舞台を見てきたであろう彼らがそう言っているのだから、確かに一定程度安心できるほどになったらしい。

そして第1話の彼女は黛冬優子のことを「可愛くて、かっこいい」としていたが、今話の舞台裏では、彼女は黛冬優子のことを、まさしく作中の登場人物である「デフォルトネーム」のようだったと感じていた。
ここには微妙な変化がある。

まず、第1話での彼女は不安を抱いていた。その不安は自己の存在が舞台にそぐわないのではないかという不安である。そして黛冬優子と自己の比較の中で、存在に準じた憧れを口にした。
一方で、舞台裏で口にした憧れは、よりパフォーマンスに近い形で演技をする黛冬優子の行為に準じている。そしてそのとき比較されるのは当然ながら彼女自身の行為である。つまり、そこにいることにさえ自信が持てなかった彼女は、一人の役者として黛冬優子を見ていた。
そして行為への憧れであることにより、自意識的問題が解決する。第1話での羨望の言葉は、存在への評価であるが故にエロスによるものであるか、それとも変身願望であるかは曖昧であった。しかし、素晴らしい行為は美に漸近する。従って、その憧れが行為への憧れであるならば、それはエロスによる憧れだと言えるだろう。自己を棄却することはない。なぜなら、美へのエロスの根本にあるのは、自己主体の最高の自主自立を目指すものだからだ。
彼女は「デフォルトネーム」を素晴らしく演じた黛冬優子に対して決意を表明する。黛冬優子がそうしたように、「私もこの作品の、一部になれるように」と。

この評価は第1話での評価とは異なり、黛冬優子にとっても嬉しい評価である。なぜなら、第1話の言葉にある不快感は、
その褒め言葉が耐えざる不安から出たものだったからだ。状況として、承認の代価として投げ出されたものに見え、そしてそれにより客体化されることへの屈辱があり、さらに変身願望に含まれる嫉妬の可能性にも危機を感じる、そんな言葉だった。
しかし今の彼女の言葉は違う。彼女は、確かに新人といえどもれっきとした一役者として、黛冬優子のパフォーマンスを、憧れるに足るものだったと見做した。彼女が黛冬優子の前で言ったのは決意であって、評価の言葉ではないが、それが逆説的にこの新人が何らかの見返りを求めて言った卑小な言葉ではないよう感じられる。
この言葉を聞いた黛冬優子は満足気な表情を浮かべている。
この新人は確かに新人であったが、オーディションに選ばれるほどには才能があったようだ。そして役者としての才能というものには、おそらく欠損の自覚していることがある。それにより生まれるエロス、あるいは自己否定すら、他者からの己がどのように映るかということを絶えず意識させる。
演じるという行為は、行為である点において美しいが、その一方でその擬態によって美しくあることが必ずしも有利に働かず、つまり役者としての美しさには繋がらない。中世ヨーロッパにおいて、女性が唯一職業人として男性と同等に認められたのが舞台役者であったというのはそこに理由があるよう思われる。
次に、これまでに描かれてきた複数の存在から客体化される和泉愛依の変身願望についての解決が描かれる。
その解決方法は、概ね自己の行為が自己の意思によるものであると確認すること──覚悟である。
しかし、和泉愛依は自身で覚悟を否定している。確かに彼女はなるべくして今の彼女であるものの、その折々、不断に覚悟を決められていたわけではない。後になって振り返れば過去時点の認識という曖昧模糊としたものは、幾らでも決めつけ、あるいは疑えてしまえる。
現存している苦しさを前にして、過去の決断を疑わない、そしてその延長上に自己を棄却する変身への望みは湧かないと言い切るのは、誰にでもできることではない。
彼女は自らの決断に対する不安を解消し切ることができなかった。あり得ないことだと分かっていながらも、その決断をしなかった仮定の自分のことを考えてしまいそうになった。
そして抱えようとしてそれでも抱えきれなくなった不安が、質問として黛冬優子に手渡されている。ここでの和泉愛依は、変身願望という不毛な妄想を抱いてしまう自分への承認を求めていると言えてしまう。
黛冬優子はこの質問に対して、私は違うと言っている。「もしも」を口にするとすれば、より多く挑戦する状況を望むと主張した。ここでは、和泉愛依が失敗した覚悟ができている。そしてそれにより、「ストレイライトの今の自分としてやっていく」ことに胸を張れると勇気付ける。それだけでなく、質問を通して、勇気の要請に適わず不安を晒し、そしてその後ろ暗さが相手にも存すると仮定する非礼を働いてしまった和泉愛依の暗い発言は見なかったふりをしている。彼女は極端な二面性を有している。アイドルとしての彼女と普段の彼女よりも、むしろ主体意識と客体意識の強烈な二面性を。
また、黛冬優子が強がりに成功しているのは、無論これまでの決断に自己の意思を確認し続けてきたことにより、そしてそれだけでなく他者の失敗に対する指摘が不要であることを知り、そしてそれをしないための演技という形での気遣いができている。
彼の人生を大変なものにしている相反する意識は、しかし彼の人生とその魅力に欠くべからざるものである。
そしてこの一連のやり取りを通して、和泉愛依は勇気付けられた。そして、彼女も見てみぬふりをしてくれた黛冬優子の意図を察してあくまでも彼女の覚悟のみを、自然な様子で称賛する。

しかし、〈if〉の仕事に前向きに取り組んでいけるだろうと思われた矢先に、新人が自分の行為による怪我で舞台を降板することになってしまったことを知る。
第5話:PRACTICE
黛冬優子は怪我で入院することになった新人を見舞う。
和泉愛依と芹沢あさひは事務所で練習を練習を続けている。
黛冬優子は新人の病院へ見舞いに行っている。新人は怪我をするに至った自分の振る舞いを悔やんでいる。そんな彼女に〈if〉の実写化に際して自分が受けたインタビューが掲載された雑誌を渡し、その場を後にした。

事務所では和泉愛依が倉庫で台詞の練習をしている。そこにやってきたプロデューサーは、彼女に向けて『〈if〉』の仕事を持ち込んだこんだことによって、「アオ」役であることを中心に様々な悩みを抱えさせてしまったのではないかと思っていることを打ち明けた。
彼女はそれに対して、弟との約束を反故にしたことを打ち明けつつも後悔はないと答える。そしてこれまでの自分の在り方についても同じだと語る。
プロデューサーはそれに応じて自分の行為に後悔はないとした。

病院では新人が手渡された記事を読んでいる。そのインタビューには、「もしもストレイライトでなければ」という質問への黛冬優子の回答が載っている。

そして芹沢あさひはレッスン室で練習をしている。夕暮れ時にやってきたプロデューサーは、既に十分なパフォーマンスをしている芹沢あさひに、練習を続ける理由を問う。
芹沢あさひはそれに対して、「デフォルトネーム」を見に来るのだから、彼女の演技は原作の完璧な再現でなければいけないと答える。

その返答にプロデューサーは感謝を伝え、練習を続ける彼女にスポーツドリンクの差し入れとともに、本当は学校で出ていた課題を手渡す。そして『仕事には求められるものがあって、それに応えなくちゃいけない』というかつての自分の言葉を繰りかえす。
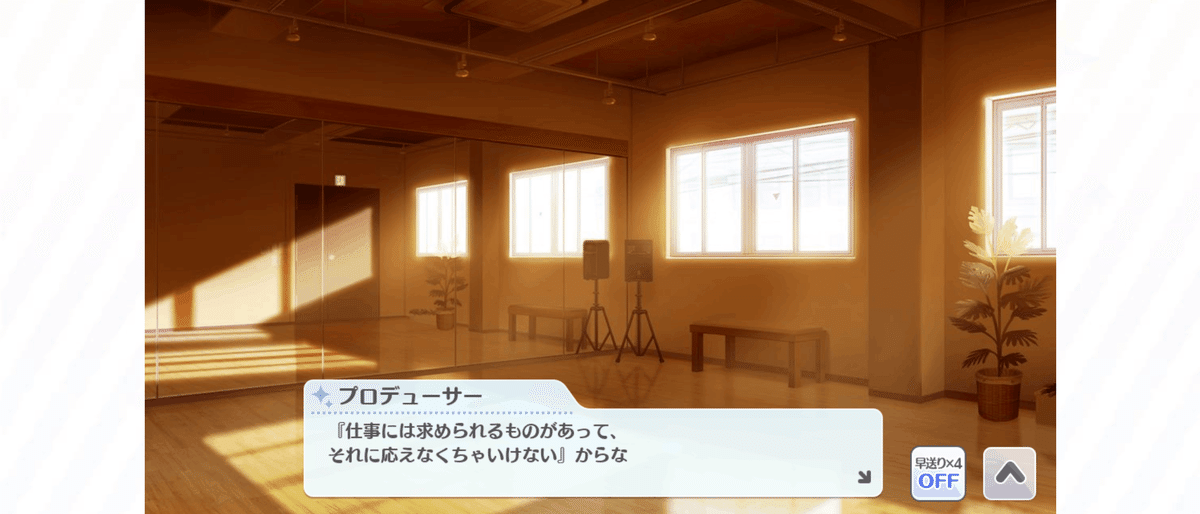
第5話では、雑誌の記事により前話のような礼儀の要請を受けない状況での黛冬優子の覚悟とその動機が語られる。また、練習する和泉愛依と芹沢あさひを通して、プロデューサーの行為に対する不安への解決が描かれる。
奈落に落ちたという新人の怪我は、入院を必要とするほどのものだったようだ。病院を見舞いにいくと、気丈に振る舞おうとしていたが落ち込んでいるようだ。
黛冬優子が見舞いに来てくれたこと、そして自らの代役をすることになったことに感謝を伝える。しかしその感謝の言葉から、自然に舞台関係者の一部が言っていた「黛冬優子が一人で主役を演じればよい」という記憶へ接続し、自分が怪我をしたことはかえってよいことだったのかもしれないと弱音が漏れている。
それを聞いた黛冬優子は不快感を覚えている。

この不快感は、一人の役者として彼女を承認した主体である彼女が自己を卑下することによる不快であり、厳密に不安に近しい。
黛冬優子は、新人に本当にそう思っているのかと問う。
先ほどの弱音は彼女の全てではないらしかった。そんなわけないと答える彼女は、敬語も忘れて自らを悔やんだ。自分の夢が叶う機会だったこと、自分が自らの思いで一歩を踏み出した舞台だったことを思い、怪我に繋がった一歩を踏み出したことを悔やんだ。

病院の眠れない夜にずっと考えていた色々なことがあったのだろう、夢に近づいた一歩も、失敗に繋がった一歩も、自分自身の思いのための一歩だったのだろうか。周囲の言葉が怖かったからではなかったか。もしそうだとしたら、あの日に踏み出さないべきだったのだろうか。直向きに努力をするべきではなかったのだろうか。夢を抱くのは間違いだったのだろうか。
踏み出しても失敗にならなかったのなら、踏み出さなくても夢が叶っていたのなら──。
「もしも、私がふゆちゃんだったら」と声が漏れる。

叶うはずもない妄想を口にして、その場に蹲って心を慰めるだけの姿に、何かを求めて一歩を踏み出した彼女はいない。哀れだ。同情したくなる。悲しい姿に心を寄せて、甘いことを言って慰めたいと思う。あるいはお前は悪くないと言ってやっても良い気がする。そうすれば心は安らぐような気がする。そうすれば自分が彼女の役を取り上げる罪悪感も薄れるような気がする。そうすれば気持ちよくなる予感がある。
しかし、それでは、彼女が幸せになるのだろうか。それでは、最近の舞台裏で彼女が見せた静かな感動が、そしてそれによって得られた自らの喜びは汚れてしまうのではないか。それでは、いつか真剣に高みを目指した決断が彼女にとっては永遠に後悔されてしまう。
黛冬優子には誇りがある。いつか挑戦することを決断し、そしとその決断には覚悟が伴い、それによってここまで来たと自覚している。そしてこの状況を──周囲に比べられ自由な時間もなく嫉妬もされれば失礼なことを言われもすることを、アイドルとしても一人の人間としても全人的に肯っている。
誇り高い黛冬優子は、彼女の頽廃に安っぽい同情を寄せるのを嫌った。
しかし、当座の問題として自分にできることはない。なぜなら、誇りは覚悟に基づくからだ。つまり自己の主体が存することを確認することとその決断にある。
従って、「黛冬優子が何かの言葉を掛けて、私がそれを聞かされた」という事態になってしまえば、「彼女の言葉で立ち直れた」などと客体の余地が混じり覚悟が乱れる。それは彼女の誇るところてはない。
そして、かといって無視して立ち去るほどに黛冬優子は薄情にはなれない。そうして彼女は、変身願望を惹き起こす「もしも」の質問に答えた雑誌を置いていくことにした。この雑誌では、彼女の態度がどういったものかが端的に語られている。

前話の和泉愛依や今の新人のように、相手を気遣うこともなく素直に、そして馬鹿にするなと言わんばかりに真剣に答えたものだ。これは彼女が受けた役「モモ」が普段と『〈if〉』で強烈な二面性を持つと知ったとき、自らの覚悟を振り返った痕跡であるようにも思われる。
この雑誌を渡すという行為についても、「読め」という命令に近しいところは確かにある。 彼女を客体化する行為でないとは言い切れない。しかし、やや婉曲にはなっている。
新人はこの手渡された記事を読んでも良いし読まなくても良い。雑誌の記事を読んでだとして、それを受け入れても良いし受け入れなくても良い。そこには新人に委ねられたいくつかの段階があり、そしてそれの数だけ、自分の意志を確認するときに用立つ可能性を残している。 自分が直接伝えるわけではない。だから、そこには伝わるだろうかという不安が残る。けれど黛冬優子はこの不安を抱えることを承諾、つまり勇気を出している。この謙譲には勇気が必要だ。可能性に賭けており、十分に期待し十分に恐れることから逃げていない。
そこまでしてやる理由には、彼女への自己投影があるのだろう。つまり、「もしも自分だったら一人では立ち直れなかったかもしれない」という謙虚さがある。
そうした過程を踏んで、せめてもの祈りを捧げるようにその場を去った。

一方で、事務所の倉庫では和泉愛依が練習をしている。場所を選ばぬ練習とは、本気で何かの上達を目指す人間によくある態度だ。雨が降っているだとか、いつもの場所が使用中だから休みにするだとかは、本気の思いを妨げる理由にはならない。黛冬優子とのやり取りを経て、彼女も迷いを断ち切れたようだ。
プロデューサーはそんな練習中の彼女に会った。彼は、『〈if〉』の仕事を受けたことにどこか後悔を覚えているようである。彼は良い仕事だったから受けたのだと振り返るが、それでも不安は拭い切れない。

そんな彼に対して、目下、最も「難しい役」であると思われる和泉愛依はこの役は自分に相応しい役だと答える。
ここでは、彼女は覚悟の確認しつつ、正義の一類型──最も良い笛は最も笛の上手い奏者に──に至る様子から、客体の素地が大きい彼女にとっての状況への向き合い方を示している。

そして「もしも」と思う自分の気持ちがまだ消えることはないことを伝えている。そしてその上で、自分にも迷わないだけの覚悟ができたこと、そしてその客体が大いに混じる不完全な足跡も含めた自分を肯う。
そしてプロデューサーは──彼女にキャラクターを演じさせ、役を受けさせた者は、その態度を聞いている。彼は、自分にできることなどない苦境に彼女たちを追いやっているとも言えることについて、彼女から意図しない承認を受けている。

そしてプロデューサーは芹沢あさひの元へも向かう。彼女は「デフォルトネーム」の「シロ」として完全な原作再現をしなければいけないと考えている。
完全への冀求が人間を客体化することは前に述べた通りである。ここでは更にその過程について詳述している。示されているのは、完全というもの、実存上の客観的な美は、畢竟他者からの評価によってのみ判断されることだ。客観というものはその意味において公平性の保たれたものであるが、実存においては文字通りに認識という主観による限定で以て成立するものである。主体たることの美と客体たることの卑は、対蹠であるようでいて単純な対蹠でない。実存上の諸論理は、人間の認識というその前提において様々な誤りを持ち、矛盾を孕む。
芹沢あさひは完全を目指している。それは以前と変わらない、遊びの、美しい営みである。しかしその一方で、完全な再現を目指すために彼女の素晴らしい行為は「違う」ものになっているし、日が暮れようとしているというのに練習は終わらない。
更に、彼女は言う「みんなデフォルトネームを見に来る」「だから、一緒じゃないとダメ」「『デフォルトネーム』にならないと」と。
彼女の胸に去来する曖昧な観念「仕事には求められることがあって、それに応えなくちゃ行けない」は、紛れもなく以前のプロデューサーが言ったものだ。

以前の彼女の傍若無人な力を、自由を、完全な美を、穿ち毀つ者の中、むしろその中心に自分がいる。
アイドル以前にも孤独を覚えていたといえど、曖昧なそれを形にしたのは、あるいはそれを埋める仕草を、純粋で自由な手足に覚えさせるよう仕向けたのは、間違いなく彼だ。彼女の肉体は意味を得た。彼は芹沢あさひの美を毀損したのだ。そして、これからもそうする。これからも彼の願いの理想は、他でもない彼自身の手によって壊れていくだろう。自分の行為には過ちがあったのではないか。プロデュースなどしなければよかったのだろうか。
──しかし、彼は感謝を述べる。
彼は自らの行為を肯っている。何がそうさせたのだろう。それは、和泉愛依が今の自分を誇ったことで、黛冬優子が今日も偉そうな態度を取っていることで、これまで関わった人々が胸を張っていたことだ。彼と彼が育てたアイドル達との日々、そして彼女らの姿が確かに魅力溢れるものであると感じたこと、そしてそれを誇りに思えることが、自らの行為への不安を抱え込む勇気に繋がっている。
そして、芹沢あさひの意味を持った踊りも、完全への無謀な挑戦も、彼女自身の意志で行われる行為だ。それが観客への媚態を含むものであったとしても、彼女の行為なのだ。自らの言葉を受け入れたことさえ彼女の行為だ。これから、彼女は「誰かのために」と思うことによって様々な悲劇を迎えるかもしれない、矛盾に苦しむかもしれない……それでもその選択を尊重した。
彼は感謝を口にする。自分が彼女の完全さを損なったことを確認し、彼女の行為が彼女の意志による行為であることを確認する。そしてそれを後悔しないことを確認する。

彼女は理解していない。こんなことは自意識に苦しんだことのある人間にしか分からない。だから今はそれで良い。これから知っていこうとも、それでも良い。なぜなら彼女はただ美しいだけの子ではなく、一人の人間なのだから。
そしてプロデューサーはこれからの練習の扶けになるようにとスポーツドリンクを渡す。さらに学校から課された夏休みの宿題を。彼女はアイドルだけでなく生徒としても生きなければならない。彼は、複雑な、苦しい状況に彼女を置くことを決意している。

そして、文句を言う芹沢あさひに向かって、プロデューサーは以前の自分の言葉を繰り返す。自分の責任を確かめるように。

第6話:STAGE
開演前の最後のリハーサルを終えて開演を待つ。SNSには数多くの投稿がある。ストレイライトの面々は開演に向けた最後の決意を固め、そして舞台に躍り出た。
黛冬優子は、演じる役が主役一人分大量に増えたにも関わらず、仕上げることができたらしい。ストレイライトの二人や舞台の裏方達は感心している。

入場時間になった。開演は目前だ。関係者席の受付には怪我をした新人も来ている。

SNSには開演を待つ観客の投稿が並んでいた。見る限りは概ね期待されているようだ。

ストレイライトは投稿を眺めている。期待を裏切らなければ良いがと笑う。

それにプロデューサーは良い舞台になると言う。
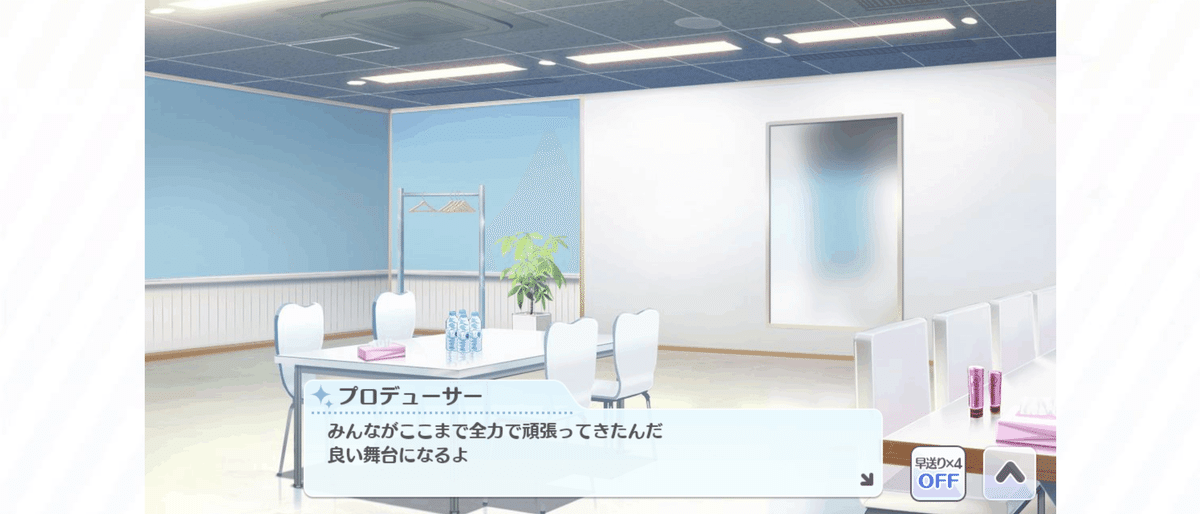
芹沢あさひは良い舞台にすると楽しそうだ。

プロデューサーは今日の舞台の打ち上げについての話をしていたと言っている。

そして舞台の幕が開けた。

第6話では、これまでのシナリオで描かれた彼女らの様子を総括する。
新人は、自分が降りた舞台を見に来た。どのようなことを思ってきたのかは明らかでない。今受付をしているこの裏方は、おそらく彼女の聞いているところで「どちらの主役も黛冬優子がやった方が良い」と言っていた裏方で、そして彼女の知らぬところで「何とか形になりそうで良かった」と言っていた裏方だろう。誰に聞かせるわけでもない言葉であるがゆえに真率なように聞こえる言葉は彼女に大きく影響を与えていた。
怪我をした彼女に席までの案内を申し出る彼に対して、彼女は「ひとりで、歩けます」と答えている。ここではその発言がこの裏方を象徴とした他者からの評価に対する彼女の敵意を示す客体の表出であるか、あるいはそれからの独立を示す主体の表出であるかは不明である。

そしてSNSには様々な投稿がある。悲喜交交の投稿であるが、直接的にいわゆる「ネガティブなことを言わない」という至極表面的で、最低限もいいところの規範に何とか準じつつ、いわゆる「攻撃性」を示さないだけで精一杯の痛々しい投稿が溢れている。SNSは不安だ。
そして、いわゆるクラスタに関して言えば、『〈if〉』とストレイライトのファンという異なる存在がいる。炎上が起きやすい状態は揃っている。
彼らは彼らの属するいわゆるクラスタの主体が揺るぐことがあれば、すぐに冷静さを失い自らの認知を歪めるだろう。そして薄っぺらな道徳は閑却され、「モヤモヤする」だの「あいつが悪い」だの、安い「攻撃性」を発揮する可能性が高い。不安を解消するというその一意のために。
そうして起こる相互の主体への連鎖的批判である炎上の後に、彼ら彼女らの奉じたクラスタの主体が立派に存立している可能性は下がる。いわゆる反転アンチが産生される様式の一つでもある。
原作への冒涜も、ストレイライトへの粗雑な扱いも、彼らを惨めにさせる舞台の失敗も、全て炎上の原因として十分だ。この舞台は完璧な成功以外が許されない。

黛冬優子は、不安の後に広がる歓喜と絶望の距離は紙一重であることを知っている。舞台のの始まりという待機の終わりに近付き、評価を受ける目前の、開演前のこの状況は、客体化される自己とそれに相対化される主体としての自己の矛盾する自意識が激しく強調されていく。
黛冬優子がSNSを眺め、そしてそれを敢えて簡単で陳腐なものに評することで客体化する試みは、あるいはその評価者たちに対峙することになる自分の臆病な心に負けないための、切実な手続きであるのかもしれない。

そこにプロデューサーが現れる。もしもSNSに集まる不安が発火する事態になればただでは済まないという彼女自身の不安に対して、彼は「絶対に上手くいく」と励ます。励ましとは、埋まらないまま肥大する不安を、「上手くいく」という言葉で競合的に阻害する試みだ。

そして芹沢あさひは不安を知らない。楽しみのままに、「良い舞台にする」と。自己が行為に及ぶという純粋な行為への追求は、存在として評価される自意識とは無縁だ。彼女の肉体は緊張を知らない。
黛冬優子は「わたしたちが」という彼女の楽しい声を聞いていた。

おそらく言葉というものは何らかのexcuseのために生まれたんじゃないか。饒舌の影には弱さがあり、愛の囁きには愛し切れない自分の肉体から要請されたmimicryがあるのだと思う。本当の自分で構わないのなら、ありのままの身振り手振りで、自らの溌剌たる肉体が全てで、良いはずだ。
だから、自分を信じる決意ができたのなら、それを汚すような言葉はなくていい。

そして舞台の幕が上がる。
開始早々のライブシーンで彼女らは宣言する。これからの最高の自分を。
インタビュー記事の黛冬優子が語った言葉を踏まえて劇中劇『〈if〉』のストーリーラインが補正される。つまり、変身願望に基づく「トラックに轢かれて現世の自己を棄却し、異世界に転生した自己は「チートスキル」で好き勝手に無双しつつ持て囃されるモテモテライフ」類型の作品ではなく、本シナリオ【if(!Straylight)】と同様に、絶えざる克己と美へのエロスを賞賛するロマンス作品であるらしい。ぶちかませ!黛冬優子!!


エンディング:HANABI
打ち上げにはストレイライトがいない。彼女たちは欠席して和泉愛依の家で花火をしていた。
会場で新人から労いの言伝を頼まれたプロデューサーは電話を掛ける。
黛冬優子は彼に質問をした。
どうやら舞台は成功に終わったようだ。感謝を伝えたいとストレイライトを探す関係者が多かったが彼女たちは欠席している。その中には例の新人もいた。

ストレイライトの彼女たちは急いで和泉家へ向かっていた。

和泉家では花火が行われている。以前の和泉愛依が弟と約束した通りの花火だ。

そんな折、黛冬優子の携帯電話にはプロデューサーから連絡がある。思ったように和泉家で花火ができているか手短に確認しつつ、新人に頼まれた伝言を果たす。

そこに電話越しのプロデューサーに和泉愛依が改め感謝を伝えにやって来る。今彼女たちが和泉家にいるのは、和泉愛依が約束を願い出たからであり、そしてそのためにプロデューサーが打ち上げを欠席する不義理なことについて関係者各位に根回しをしていたかららしい。

束の間の一幕からは、和泉愛依と芹沢あさひには課されている学校の宿題と、家族からの呼び声で引き戻される。

不図、賑やかな花火の光の影、夏の夜の一瞬の静寂に世界を遠く感じた黛冬優子が、質問をする。
──もしも、と。

それに対して、プロデューサーは簡潔に答えた。

そして周りを見渡せば、芹沢あさひは、以前の和泉愛依の質問に衒いなく答えている。もしも舞台の仕事がなければ和泉家で花火がしたかったと。
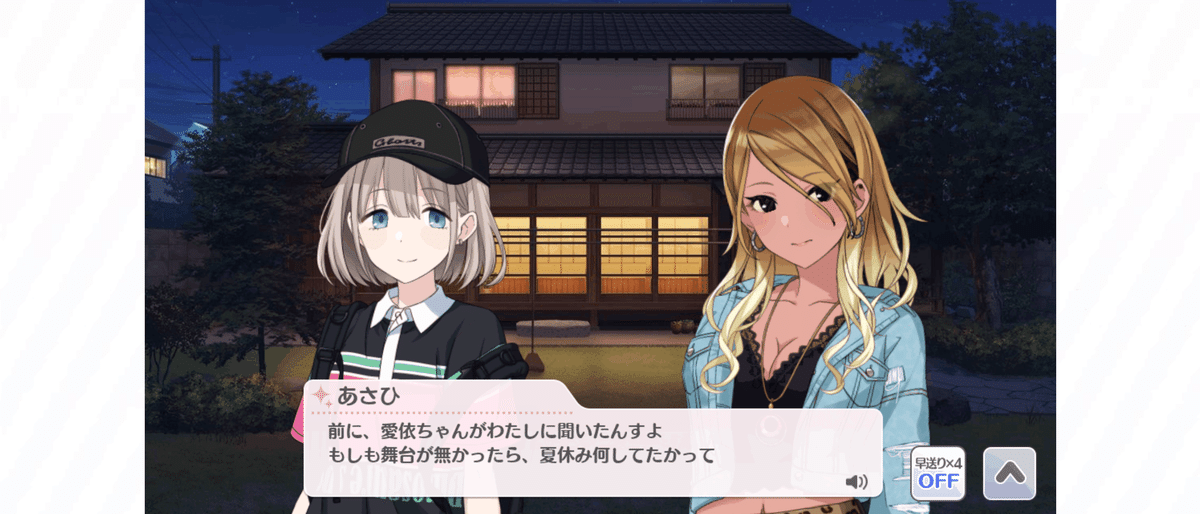
和泉愛依は可笑しくなって笑っている。

それを眺めている黛冬優子も笑っていた。

エンディングでは、新人の再起と黛冬優子への承認が描かれる。主体たることのみを目指すだけが全てではない。
舞台の出来に安心するなり、すぐに調子に乗るオタクたちが描かれる。

また制作企業はこのようなやや危うい案件を持ちかけた事態に対して、そして新人の怪我という事故によって黛冬優子が過大な役を受けることになったことを含めて感謝を伝えようとしている。
しかしストレイライトは欠席している。感謝であれ謝罪であれ、それは相互に主体を確認する儀式であるため、それを受け取らないというのは礼儀において望ましくない場合が多い。
礼儀が守られるかというのは信用に関わり、今後の仕事に関わる。
故に、大きな仕事をしたのであれば打ち上げには出席することが望ましい場合が多い。プロデューサーは開演前までその振る舞いを不義理としないための根回しをしていたわけであるが、伝えきれない相手もいたようだ。

ストレイライトの若者たちは、そういった細々とした物事を知らずのうちにプロデューサーという大人に任せている。
打ち上げを欠席した彼女たちの感慨は様々だ。芹沢あさひのそれは、街のモニターに『〈if〉』を認めて懐かしむ程度の淡いものである。

会場には例の新人が黛冬優子へ伝えたいことがあるようだった。
ここでは、彼女の再起が描かれる。
華々しい成功の後に現れたのは、その成功に携われなかった人間だ。そして、彼女は、「何とか形になりそう」だった程度で、もしも彼女が出演していれば、今の成功はなかったかもしれない。
そんな人間が怪我を押して現れた。打ち上げには裏方だって参加する。彼らはきっと、誰に何を言いに来たのだろうと噂するだろう。打ち上げ会場に降板した女が現れるなんて、危険な香りが感じられる。話の種には持ってこいだ。
そんな、どう思われるか分かったものではない不安な場所に彼女は現れた。
そうして怪我に不自由をしながら、痛みに耐えて、彼女は誰の得にもなりはしない、身勝手な決意だけを伝えに来たらしい。
彼女が上手くいくかは知らないが、怪我が治ってリハビリを終えて、そうしてもっと良くなりたいと思う彼女は、きっと良い演技が出来るようになっていくと思われる。

和泉家では花火が行われている。
「ふゆねーちゃん」への恋心とは別に、和泉愛依の弟は少年らしく花火を楽しんでもいるようだ。

そして彼の幼い恋心を良いように利用して怪我をしないように窘める様子には恋愛とはかけ離れた一方向性を感じる。

そんな折にプロデューサーから電話が掛かってきた。和泉家の年少への気遣いから彼女は席を外す。
和泉家での花火をする一時が友人との時間であることを思ってか、彼の仕事の領分としての到着確認については手短だ。
そしてそのまま新人から託された言葉だけを伝えた。誰からの言葉かは名前を出さなくても分かるようだった。それだけ気にしていたようで、傍目にも分かることだったらしい。

そして約束を守れて安心している和泉愛依が感謝を伝えに来た。
『LOG IN TO 〈IF〉 』を選択する他に見守ることしかでかなかった僕たちのように、プロデューサーも彼女らの内心にできたことなど大してない。「何でも言ってくれ」という言葉の裏には何もできなかった自分がいたのだろう。
十分な時間でなかったとしても、彼にとってもストレイライトでない彼女らの時間を確保する大切な仕事ができたのは良いことだった。

感謝を伝えるなり家族の声に引き戻され、和泉愛依は花火に戻ろうとする。そのとき高校で課された宿題のことも思い出したらしい。芹沢あさひにもやらなければいけない中学校の宿題があった。げんなりする彼女らを他所に黛冬優子はブルーレイでも見ることにすると笑っている。

──黛冬優子には兄弟はいない。夏休みの宿題もなければ学校での深い付き合いもない。花火の音は少し遠い。静かだった。望む闇は遥か遠く、夏の夜の空気は肌の内側と変わらない。睦み合う学生と、友と、家族と、花火の光は、如何にも幸福であるという印象を与える。自分は賑やかな花火の光の、その影にいた。静かだった。
──口から漏れたのは「もしも」という言葉だった。「もしもストレイライトのプロデューサーでなければ」と質問をする。後悔は早かった。そして、聞かれたままの言葉を使ったと、皆が聞くからと言い訳をして……戒めたものに搦め取られていた。彼女の後悔は始まっている。

プロデューサーは覚悟を鈍らせるこの言葉を聞いてしまった。それからプロデューサーは少し考える。会場の賑やかな歓談のせいにして聞かなかったふりをしてしまおうか、笑って有耶無耶にしてしまおうか、色んな事が思い浮かぶ。
──しかし彼は素朴な思いを口にした。
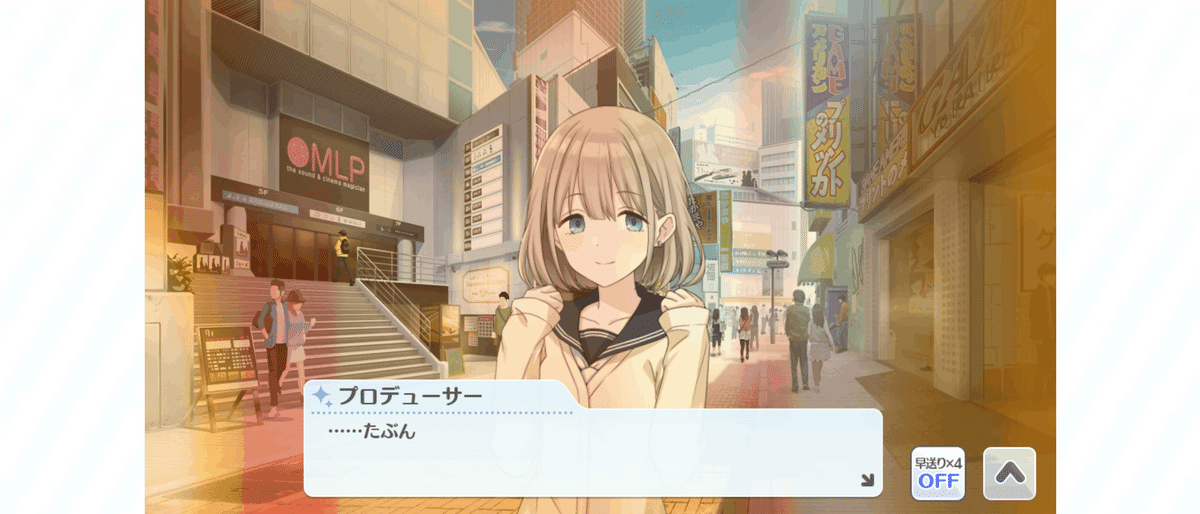


ストレイライトのプロデューサーでなかったとしたら、まだ「みんなのこと」を探していたのだろうと。
自分がストレイライトのプロデューサーでなかったとしても、つまり彼女たちがストレイライトでなかったとしても、そして今ふいに一人ぼっちになった彼女がストレイライトのメンバーでなかったとしても、彼女たちは、彼にとってはもはや「みんな」なのだ。日常に潜む淋しさに襲われた彼女にそう語る。
そして、その自然な、おそらく彼の胸に一番に浮かんだこの思いは、プロデューサー自身がストレイライトのプロデューサーであることを肯うことを前提にする。彼はストレイライトのプロデューサーであるこれまでと、これからの自分を誇りに思う。かつて彼女が和泉愛依や、怪我で降板したあの友人にそうしたように、あるいは黛冬優子に勇気付けられた和泉愛依がプロデューサーにそうしたように、彼の自然な感想で、それでいてよく考えられた、無垢で複雑な言葉は勇気も与えたようだった。
黛冬子は感謝を伝えた。

明るい花火へ目を向けると、ストレイライトの仲間が、──自分と一緒のみんなが、他愛もない話をしている。
芹沢あさひは、かつて和泉愛依が不安から口にした「もしも舞台がなければどんな夏休みだったか」という質問を思い出して答えた。「愛依ちゃんの家で花火!」と、まるで無邪気な笑顔で。

和泉愛依は少し驚いて、それから笑った。今花火が楽しくて、それなら「もしも」と自分を呪ったことなど、まるで無意味なことだったことに可笑しくなって。

自分のような皮肉の交じる決意とは無縁の場所に芹沢あさひがいて、自分のような器用さのない和泉愛依が笑っていて……黛冬優子はそれを見て、彼女たちと同じように笑った。
──そう、彼女たちはストレイライトなんだ。

感想
王 道 を 往 く────。
二律背反な人間の精神の有り様について、昨今、実現の途が開け始めたようなARを交え、変身願望を題材にする。彼女たちそれぞれの自意識の有り様を通して、現実の苦しみを述べ、その超克を描く。また、厳然と存在する(、というのもおかしなことだが、)人間の不安とどう向き合うのかを示す。
媒体の特性に準じた表現の限界などから注目しないとそれと分かり難いものの、シャニマスくんの夏シナリオは風景と情景の関連を出そうとしていて良かったよ。思うに、本邦の創作、特に小説の美点は、風景と情景の混淆にあると思う。花火の夜の「エモい」雰囲気の作り方はその辺りで、突如襲い来る日常の不安の構成を含めて魅力溢れる出来だった。
PANOR@MAの、展ける視座の部分についても立体的で良かった。
無意味も良いところのケチを付けるとすれば性別だろうか。黛冬優子とかいうやつ、日本男児なんだよなあ……というのと、芹沢あさひが少女であるがゆえにその変化を記述する文章がどうしても若干のキモさが出てくるものに仕上がる点がやや不満だ。『もしもストレイライトが男だったら──【TStraylight】合同』の発刊を予感せざるを得ない。
ちなみに、あさひPラブ論は理想主義的措定に対する現実主義的反措定であり、異教徒としての弾圧はかつてのキリスト教が様々な哲学者を異端としたことと同じ。だから僕は叫ぼう。それでも……あさひはPラブなんだ……!
終わりの挨拶
今回も大変そうな仕事をお疲れ様でした。
高山を始めとしたアイドルマスターシャイニーカラーズ製作者さんたちと、BANDAI NAMCO各位、eプラス等関連企業の皆様の今後の御健勝と、僕にライブチケットがご用意されますようにと祈りを込めて本記事を終えたいと思います。もうゲーム先行まで外したし、ふるさと納税で届いた赤いリボンの麦わら帽子は思った以上に海賊王すぎて使いにくいし、雨が降ったり止んだりする。それなのに蝉は例年通り煩くて、とにかく喧しい夏です。
オタクが溢れ返るクソ暑東京ガーデンシアターに僕も行けますよう。
敬具

