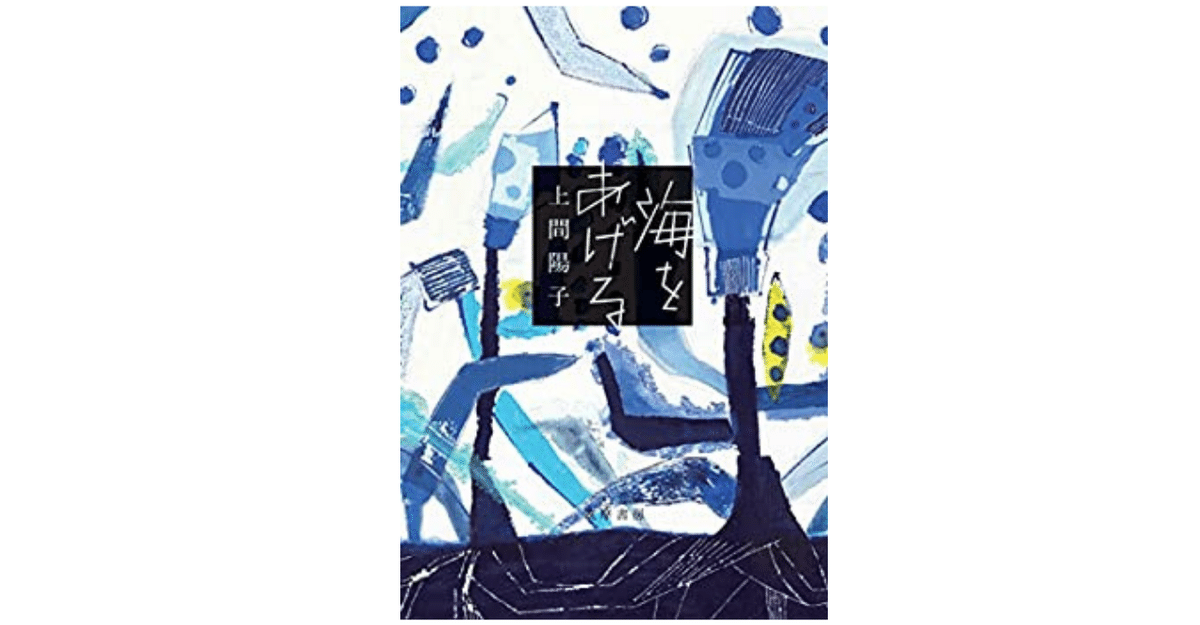
海水浴に行くこともなくなった孤独な東京人である。
『海をあげる』上間陽子
おびやかされる、沖縄での美しく優しい生活。幼い娘を抱えながら、理不尽な暴力に直面してなおその目の光を失わない著者の姿は、連載中から大きな反響を呼んだ。ベストセラー『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』から3年、身体に残った言葉を聞きとるようにして書かれた初めてのエッセイ集。
「半分つぶされた虫のように、地面の上をのたうちまわるような打撃をうけた人々には、自分の身に起ったことを表現する言葉がない」
――シモーヌ・ヴェイユ 「神への愛と不幸」(渡辺秀=訳)より
着替えを済ませた娘は私のお布団に移ってきて、「まだ夜? 朝来た?」と尋ねてくる。「まだ真夜中だから眠ってね。かーちゃん、今日は辺野古に行く」と言うと、「風花も一緒に行く」と娘が言う。「今日は、海に土や砂をいれる日だから、みんなとっても怒っているし、ケーサツも怖いかもしれない」と言うと、娘はあっさり、「じゃあ、保育園に行く」と言う。
暗闇のなかで、娘は私に「海に土をいれたら、魚は死む?ヤドカリは死む?」と尋ねてくる。
「そう、みんな死ぬよ。だから今日はケーサツも怖いかもしれない」
娘の髪をなでながら、ついに一二月一四日が来てしまったと目を閉じる。
(「アリエルの王国」より)
『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』とパラレルになっていて、『裸足~』が社会学者の調査記録であり、三人称で描かれているのに対して『海をあげる』は一人称のエッセイ。それは私が「沖縄」を引き受けるという、難しい話でもなくて、生活基盤として子育てをするということで、娘に引き渡す「沖縄」なんだと思いました。その中でオバアの戦時中の話も出てくるのですが、そのすべてを娘に伝えたいという母なる願いが感じられます。「海」というは、その漢字の中に母がいるということじゃないかな。それを次世代へ伝えていく沖縄の共同体としての。
美味しいごはん
夫の不倫。相手は親友だった。親友に裏切られて、そこから立ち直るまで。娘に語る母の物語形式(エッセイだが)になっている。恋愛が一生涯続くものだと恋愛中は信じるが、いずれかはさめる。それが事実だと思う。
主観的に一人称の私の悲しみは、彼女のものだが、世界は彼女のものではない。だって、彼女の場合、夫は元カノが親友だったのだ。それを知っているからここで描かれているのは元カノの真弓さんの強さだろう。それが元カレの彼女に出してあげることが出来た美味しいごはんだったのだ。
沖縄で出会った風俗嬢の女の子も、親友が自分の恋人と浮気をしていた話が出てくる。
「ああ、だって三人の関係があるんだもんね」
ここはすごく大事なことなのだ。三人称の世界なのだ。だから、ごった混ぜのぶっかけうどんなのだ。ぐちゃぐちゃの。そういうことを発露する相手がいるということはいいことだろう。そう言いながら飯(ごはん)を食べられることも。それが家族かもしれない。
ふたりの花泥棒
祖父が死んで仏教式じゃなく、親族で海に入って死者を見送る沖縄の習俗。「ニライカナイ」というと柳田国男の黄泉の世界。沖縄にまだそういう習俗が残っていることに羨ましく思う。柳田国男『先祖の話』じゃないけど、先祖とつながっているのだ。日本ではとっくに断ち切れていたと思ったのに。
きれいな水
沖縄の水が米軍の廃棄する汚染水で汚れているという話。子供を持つ親に取っては死活問題で、福島原発事故のときも沖縄へ移住する者がいた。環境汚染は世界的な問題であり、こうした社会問題は地域住民の市民運動がより安全な街をつくり、黙っていると子供が住みにくい経済だけの開発地域になってしまう。
そこで沖縄の海の話。集団自決したオバアの話。そして捕虜になり、米軍の廃品を売っては食つないだ話。米軍の砲弾に喰われなかったという。そのオバアのたくましさを見習いたいと思うが子供たちには安全な暮らしを残したい。その中で沖縄のオバアの話を後世に伝えていく。きれいな水を残していくことの難しさ。
ひとりで生きる
『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』で少女に売春させていたホストの取材インタビュー。金の稼ぎ方が半端ないが、それも親姉弟や親戚に消えていく。一人で生きるというタイトルだが、ちょっと違う。父に殴られて少年時代を過ごす。今はその父も半身不随だという。たかられる家族にたかる女という構図なのか?最終的に一人で生きていることになるのか?利用するものは利用して、捨てるもの捨ててという感じか?最後の寺山修司の短歌
「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや 寺山修司」
「祖国ありや」は反語で「祖国はあるのだろうか、ない。」
波の音やら海の音
沖縄の風俗嬢の少女は十代で子供を産んで孤立していく少女たちのインタビューを通して、彼女の怒りは沖縄の海を見ることで静まる。
「波の音やら海の音。娘の寝息は波のゆれる海を思わせる。もう少し待てば、東の空が明るくなって、たぶんもうすぐ朝がくる。」(上間陽子『海をあげる』)
優しいひと
「ムーチービーサー」という沖縄の風習を通して娘と餅菓子作り。その後に元山仁士郎さんの『基地のない平和な島』を求めての住民投票署名のためのハンガーストライキの話が出てくる。これは今年の沖縄復帰50年でも行われたというニュースが流れてきた。
そのハンストがどの程度効果があるのかはわからい。ただ思い出すのはガンジーの 非暴力不服従運動だ。それは、鬼に対する娘の気持ちと繋がっていく。
「私たちの島には鬼がいて、夜になるとそこらじゅうを歩き回ると娘は言う。ムーチーを食べると強くなって、鬼をやっつけることができると娘は言う。毎日ごはんをたくさん食べて、大きくなると娘は言う。」(同書)
三月の子ども
保育園のママ友との共同子育てレポート。子供のつながりが母親同士のつながりも生んでいく。その結果としての共同体活動と子供たちの卒業式。そこには大学の教え子の生徒が新人先生として悩みを相談する姿も描かれる。
私の花
娘の風花の子育てエッセイ。沖縄のDV少女は、母親のDVを見て育ち逃げられない現実を知る。そんな少女とフラワー・デモの話。
何も響かない
父親の性暴力を受けてPSTDになった女の子。彼女もシングルで子育てをしながら施設に入り病院に通っていた。母親との関係性で孤立していく。結局母にとって自分は必要ないのではという思考から誰にも頼らず出ていく。彼女は誰も信じることが出来なかった。
空を駆ける
104歳まで生きた祖母のエッセイ。(著者の)母との関係。祖母の看病している母は祖母が好きじゃないという。幼い時の母の記憶は祖母の虐待の記憶だった。それでも祖母の面倒を見ながらいつしか関係性が逆転していく。祖母の日記は、母(お母様と書いてある)に叱られたこと。それでも貴方という言葉に著者はそのときはボケていなかったと思う。祖母の葬儀は、家族に見送られて魂は天に上っていく。
アリエルの王国
娘に聴かせるお話に『リトル・マーメイド』の「アリエル」という妖精の嬢様になって、一日の出来事をその中に組み込んでいくという。保育園での上級生にいじめられた話や優しかった先生の話など。著者はその日は辺野古の埋め立てに土砂を入れるのを阻止するデモに行く。汚され死んでいく海という現実。おとぎ話を信じている娘がそれを理解する日に、娘はこの島を出ていくのだろうか?と考える。
海をあげる
沖縄の怒りを羨む東京の人。彼らはけっして東京で反対運動をしない。沖縄にも生活のためにその話題はタブーになってしまうことも。父親や家族が米軍で働いていたりする。著者の怒りは生活を守ることが東京の住民活動に直結しないで、ニュースの傍観者になっていることなのか?
いつまでも観光客でいられる東京の人々への怒り。それは見当違いだろうという賛否両論あると思う。たまたま沖縄に生まれなかっただけで、東京育ちの負い目かな。
