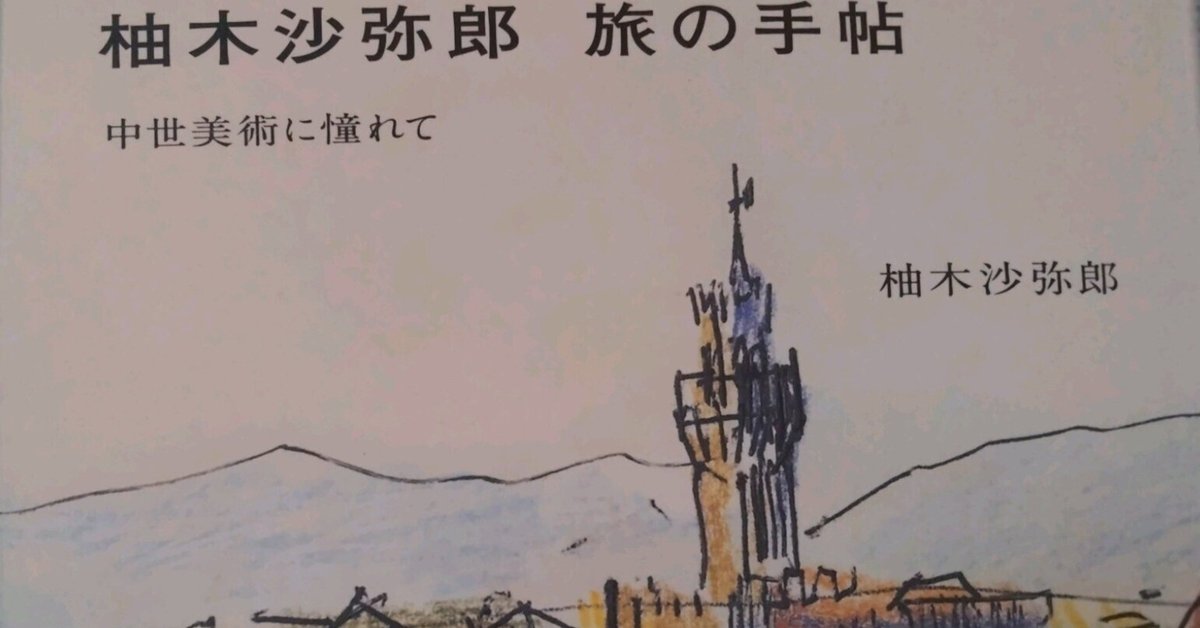
「柚木沙弥郎 旅の手帳」を味わう
今年101歳で亡くなった柚木沙弥郎が、1967年、44歳のときに、初めてヨーロッパを回り、スケッチや日記を残したものが、本になった。柚木は柳宗悦の「民芸」に出会い、染色家となり、女子美の学長も務めたという。
本人作成の計画の地図が、折り込みで入っている。3月25日から6月1日まで、アフリカ、カサブランカやオーストリア・ザルツブルグ・ウィーンなども入っていたが、それらはかなわなかったようである。羽田で大勢に見送られ、香港・バンコク経由で、まずカイロに入り、イスタンブール、アテネ、ローマ、そしてイタリアを回り、ミラノからバルセロナ、バレンシア、マドリッド、パリ、ヘルシンキ、ストックホルム、コペンハーゲンから帰国、全日程69日間である。スケッチは黒のペンで、色鉛筆であろうか色を付けたものも、カラー図版のページに載せてある。例えば、表紙に使われたフィレンツェだ。
自分がエディンバラに滞在したのは1976年からの3年なので、それより前の、まだ1ドル360円の時代である。しかし、1978年に訪れたバルセロナ、バレンシア、マドリッドや、1982年に訪れたイスタンブール、アテネは、あまり変わっていなかったのではないかと推察する。そんな親近感を持って、スケッチを眺め、旅日記を拝見した。
節約を意識している様子は、両替が気になり、食事やホテルの値段が気になる。飛行機で飛び立つ日に、残りいくら使ってよいか、食事に使い過ぎたり、タクシー代が足りるかとか、一日中計算しているようなこともある。そんな思い出は、アテネの最終日や、ナポリでの自分にかさなり、懐かしい。言葉の不自由さをあまり感じさせず、けっこう、電車やバスの乗り継ぎはきわどかったりしながらも、体調不良にもならずに、大過なく過ごせたのは素晴らしい。
バチカンでは、ミケランジェロの「最後の審判」に感動している。細部の色と全体の構成に、他の作家と違うものを感じたとある。ミラノでは「ラストサパー」、レオナルドの中では一番いいという。さて、ミラノには2回くらい行っているはずだが、「最後の晩餐」の記憶がない。ということは、見なかったのか、見れなかったのか、忘れたのか?パロディ製作の最後の晩餐をニューヨークのMOMAで見た気がするが、そちらはよほど覚えているのだが。
マドリッドでは、ベラスケスが気になる。「ラスメニーナス」のことと思われるが、「ベラスケス自身の姿も描き込まれている貴族家族の絵」と記している。パリでは、ルーブルを楽しむが、「日本人が沢山来る。皆絵の前で写真を撮る。婦人の着物が安っぽくて残念である。」というのは、ルーブルに見に来ていた日本人を評してのことか。フランス人は東洋日本に対する憧れは強い。だから、日本のよいものを見せろ、というのである。ホテルのマダムの対応がよかったからなのか、パリの人は人間関係がスマートで、街の人も親切だという。自分のヨーロッパを回った時の印象は、フランス語をしゃべれなかったせいもあろうが、オランダ、ドイツ、スペインと比べて、フランス人は、冷たく感じたことと随分異なる印象だ。人は、ちょっとしたことで、国全体に好感をもったり、そうでなかったりするものも知れないと思った。
ヘルシンキでは、東工大清家研の学生八木が登場する。アアルトを見に来ている様子。我々の世代より、少し上の人ということになるか。さらには、事前に会うつもりだった、元菊竹事務所に居たというトンプソンという建築家が登場し、菊竹夫人の名前も出てくる。民芸を仕事としているのだから、建築家がもっと登場しても良さそうではあるが、最後にまた、距離感が縮まった感じがする。ストックホルムのまちも、コペンハーゲンのまちも、一人で歩いたこともあって、懐かしく想像できる。アンカレッジ経由での、無事帰国は、すばらしい旅の成功に乾杯したい思いだ。
副題に「中世美術に憧れて」というのがあることも、読もうと思った理由になってはいるが、そのことからの発見はあまりなかった。「ドイツ文化読本」や「修道院からモダニズムへ」は、はるかに多くを語っている。これは、自分の覚えとしての旅日記であって、中世美術を人に語るものではないということかも知れない。スケッチは、旅をしていることが実感されるし、スケッチに、中世美術から感じたことが表現されていると読み取るとよいのだろう。30代、40代にヨーロッパのまちを訪れて、受けた自分の印象を思い出し、比べながら楽しめたという本である。
