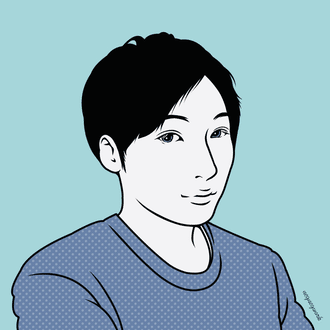幼稚園で出会った架空の友達。
昨日、noteを久しぶりに投稿した。これから投稿頻度を週3回にしていきたいと思う。
さて、noteをお休みしているあいだ、短編小説をいくつか読んだ。読んだのは小川洋子さんの『口笛の上手な白雪姫』という文庫本だ。主に孤独をテーマに全部で8つの短編小説が収録されている。
そのなかでも、特に気になった『先回りローバ』という作品を今日は紹介したいと思う。
この作品は、吃音に悩まされていた主人公の「僕」が、とつぜん現れた老婆との出会いによって自分の声を取り戻す物語である。
物語は「僕」が七つのときに、初めて電話が引かれたことから始まる。そのため、両親が集会に出かけているあいだに電話が鳴ると必ず出て、両親が留守であることを伝えることを余儀なくされた。
しかし、「僕」は吃音のため上手く話すことができない。だから彼らが集会に出かけるときまって、ダイヤルを1、1、7に回した。時報のお姉さんと会話をしているあいだ、電話がかかってこなくて済むからだ。そして、彼女は決して「僕」に質問を投げかけたりしてこない。喋らずに済むし、こちらが黙っていても怒られたりしない。
吃音の原因は両親にあった。両親はズルをして、自分の出生届を六日間ずらした。おそらく、その日が集会にまつわる記念日なのだろう。そのため、僕の言葉はその空白のなかに消えていってしまった。
そんな「僕」がある老婆との出会いで自分の人生を大きく変えることになる。そのお婆さんは手のひらに乗せられるくらい小さく、動きが素早いため正確に輪郭をとらえることができない。おそらく、自分にしか見えない奇妙な存在だったのだろう。「僕」はその老婆の要望により、カタカナの「ローバ」と呼ぶようになった。
「僕」はローバと話すとき、すらすらと言葉を口にすることができた。そして、ある年の誕生日を機に、「僕」は自分の声を取り戻す。この物語は、そんな声と孤独がテーマとなっている。
小川洋子さんの小説は、一つひとつの言葉が丁寧に、繊細に紡がれているのが特徴だ。気になった人は、ぜひ手に取って読んでみてほしい。
幼稚園で出会った宮越さん
ぼくがこの物語を読んだとき、自分自身の幼少期を思い出した。幼稚園に入ったばかりのころ、まわりの同級生たちと上手くなじめず、ひとりでいることが多かった。
当時のことは断片的にしか思い出せないので、あまり詳しいことは分からない。ただ、記憶の断片をのぞいてみると、あまり楽しい思い出ではなさそうだ。
滑り台に乗りたいけど、先客がいて躊躇してしまったり、職員室で先生に何かを頼もうとしてもできず、入口のまえでうろうろしていたり。そんな変なことばかり覚えている。
のちに親から聞いたことだが、自分にも架空の人物がいたらしい。ぼくが幼稚園から帰ってきて、母親が「今日何をしたか」と聞くと、必ずその人物が話題に出てきたそうだ。名前は宮越さんというらしい。ずいぶんと昔のことなので、どんな人だったのか、まったく覚えていない。
両親は、はじめは新しい友達かと思ったそうだが、調べてみても宮越さんは同じ組にも違う組にもいない。もちろん、先生でもない。
もしかしたら、幼少期のぼくにも「ローバ」のような存在がいて、話し相手になってくれていたのかもしれない。
いいなと思ったら応援しよう!