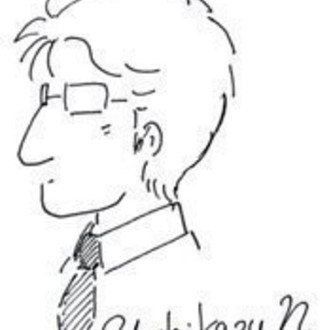7月29日 コミュニティで自分を変えた人々から得る刺激
7月29日ですね。
この週末、CLS道東に参加していました。
今回で5回目の参加です。皆勤です。
今回も学ぶところが多かったです。今まで、他のイベントではお見掛けしていて、話したいと思っていた方ともじっくりと話すことができました。
先日参加したCLS三島らへんとあわせて、コミュニティが各地で隆盛を極めつつある実態を知るのは貴重な機会です。
CLSに登壇するような方はコミュニティーの成功者です。各地で何かしら発表できるようなコミュニティーを立ち上げ、それを何かの形で継続で開き続けられている人が登壇します。
それぞれの人と人とを点と線として結び、各地のコミュニティをつなぐ。
それに成功した方の事例やノウハウを登壇を通して聞ける機会は貴重です。自分たちにもできるはず、と言う勇気がもらえます。
それにしても、コミュニティーを通して自分の生き方に自信を持ち、生き生きしている方の輝いていること。
本来、コミュニティが持つ機能は、会社や職場でも担えるはずなのです。ところが、企業の場合、囲い込まれてしまうのか、統制の名の下に閉じた形になっています。それが閉塞感を生んでいます。
自社内のコミュニティを作ろうとしたのはよいですが、自社内の文化で固めてしまうと、それはそれで閉鎖的になってしまうのですね。
そもそも職場の場合、仕事という建前のもと、仮面をかぶって、単なる生計を維持するための場として参加している場合、コミュニティにやらされ感が出てしまい、コミュニティーとしての力が発揮できません。
利益重視や生活の維持といった観点ではなく、より広い視点からコミュニティに参加する。
そうすることで自分自身の知見が広がります。
しかも仕事と違い、勤務時間や賃金に見合った成果を出すプレッシャーから自由になった活動ができます。
趣味のサークルでもコミュニティの機能はありますが、同じメンバーでの活動が続いてしまうと、それはそれで閉じてしまいます。
そうではなく、コミュニティーとは開かれ、お互いが影響しあい、その効果によって自分自身をの新たな可能性に気づくことができるものです。それがコミュニティーではないかと思っています。
慣れ親しんだ場ではなく、違う場に出て、よく知らない方と会話するのが苦手。だから、新たなコミュニティーに参加するのが億劫だ。その気持ちは良くわかります。
まさに、そうした方こそ、CLSのような場に出て、コミュニティーによって自分の可能性を拡げた人たちを見て刺激を受けるべきだと思います。
わたし自身もまだまだ。自分を変えていかなければと思っています
いいなと思ったら応援しよう!