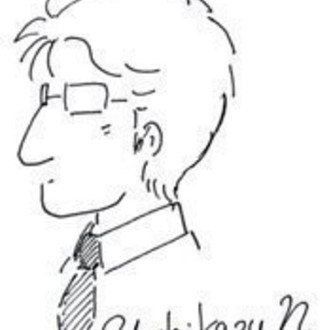4月12日 介護ロボットに慣れておく
4月12日ですね。
さっき妻子と話していて、町田市には老人ホームが多いという話になりました。
妻子に駅にまで送ってもらう間にも数軒の老人ホームを見かけました。
こうしてみると、もう、わが国が否応なしに高齢化社会に向けて待ったなしで進んでいる印象があります。
そして、私も間も無く老人の一人に加わる予定です。
見掛けたホームでは、介護で働いてらっしゃる方の姿もみかけました。
今はまだ介護は人間がしています。ですが今後は、人間に介護されること自体が特権、または贅沢な老後になるのでは、と感じます。
おそらく老人を介護する側の求人需要はますます増えるでしょう。でも、そもそも介護する方の数が足らなくなるのは間違いないと思います。
そうなると、人のかわりに介護ロボットがどんどん進出し、私たちの大多数はロボットに介護されることが当たり前になるでしょう。
その時、ロボット介護や、ロボットそのものに慣れていないと、老人ゆえの頑固さからか、それに拒否反応を示してしまうことも考えられます。
そうならないよう、今のうちから、ロボットに慣れておかないとな、と思いました。
慣れておくべき人とは、今の若い人ではなく、むしろ、私と同年代、つまり第二次ヘビーブームの申し子たちです。
私たちの世代は、ロボット介護に慣れるにはまだ若いです。慣れる機会もないでしょう。
ですが、若いうちからロボットに慣れておけば、拒否反応は薄らぐはずです。
では、どうやって慣れるか。
最近、街のあちこちにプログラミング教室を見かけます。それらのほとんどは子どもたちを対象にしています。
でも、老人予備軍にロボットに慣れさせるためのロボット教室もあっても良いのではないでしょうか。
自分たちでロボットを組み立て、ソフトウエアを組み込み、それをもとにうごかしてみる。
その繰り返しによって、ロボットに慣れ、愛着も湧き、少しは将来に味わうはずの拒否感も和らぐような気がします。
いいなと思ったら応援しよう!