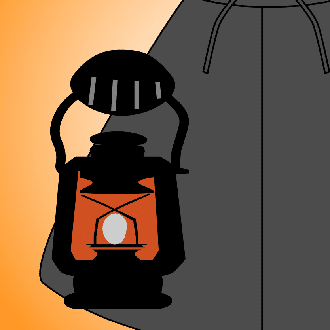文字情報の限界と「世界観」の共有【HARD】
「絵っていいよね」
「そうだね」
「私には見れない世界が見えるの」
「文字にはできないことだ」
(ある師匠と弟子の日常)
こんばんは、LearnTernのAkiです。
最近ちょっとLearnTern更新サボってます。今週中に2記事くらいは更新するはずです。僕は僕を信じてる。
その裏ではLearnTernの代表コンテンツをつくっています。「学習者のレベルアップ」を目指すコンテンツです。
(今の目論見では、その制作過程をnoteで発信していこうと思っています。完全オープンにするのは恥ずかしいので有料マガジンでの公開です。つくっているコンテンツの方は完全無料なので、この辺りで稼いでおきたい僕です)
今日のnoteではちょこっとコンテンツ制作に関する話をします。
ある程度のサイズを持つコンテンツをつくるときに気をつけたいのは「世界観」の共有です。もちろん小さなコンテンツでも大事ですが、大きくなればなるほど大事になってきます。
理由はいろいろありますが一つは「長い時間浸ってほしい」からです。
言い換えれば、大きめのコストを支払ってほしいからですね。
コンテンツの世界では利便性などよりも大事なのが「面白さ」で、それは世界観のフィット具合で変わってきます。
だから世界観をどう表現するかを、僕らは気にしなくてはなりません。
ここで僕らの武器である「文章」、文字情報の限界がやってきます。
文字情報の限界とは
もちろん文字情報でも世界観は表現できます。長い時間をかけて文化を醸成していけば、それは可能です。
しかし元来、文字にはイメージ属性がありません。僕らはいちいちイメージを込めなくていいので、絵や動画よりはラクに使えます。
けれど、僕らはイメージを扱って生きています。
なので文章を読んでいるときもイメージが使われています。
しかし使われるのは書き手のイメージではありません。
――読み手のイメージです。
書かれている言葉に対して、読者が持っているイメージを呼び出しているのです。
文章とは、読み手の持っているイメージを予測し、それを上手く使って、書き手が抱いてほしいイメージを描き出す技ということになります。ゴリムズです。
文字情報の限界。
それはイメージが読み手依存になってしまうことでした。
絵が超える限界
絵や図、画像などはイメージをそのまま使います。
否応なく、発信者と受信者が(ある程度)同じイメージを共有できます。
文章では表現しにくい細部のイメージを共有できるのです。
僕らはコンテンツの世界観を伝える時、絵などの表現を使ったほうがいいのかもしれません。
今、僕がつくっているコンテンツでもイラストやデザインの力を全力で使います。僕は絵がうまいわけではありませんが、そこは練習です。仮にも「学習」をテーマにしている人なので、そこはやります。
(↓練習中↓)

今日は「世界観を表現するために何を使うか」という話でした。
ではまた。
ーーAKIーー
ー音楽も大事(がんばる)ー
いいなと思ったら応援しよう!