
天華恋墜 第一章:青春物語【蓮ノ空二次創作】
あたしにあなたが無いとしたら――
ああ それは想像も出来ません
想像するのも愚かです
あたしにはあなたがある
あなたがある
そしてあなたの内には大きな愛の世界があります
あたしは人から離れて孤独になりながら
あなたを通じて再び青春の生きた気息に接します
人間喜劇の中に活躍します
すべてから脱却して ただあなたに向うのです――
天華恋墜 第一章:
青春物語
1
歓声が聞こえる――。
愈々決勝の幕が上がり、舞台上にはスポットライトの光が降り注ぐ。飛び交う応援の声援で大気が震え、無数のサイリウムが煌煌と輝くドーム内。肌がびりびりとひりつくのがわかる。ステージ袖から見える光景はあまりにも眩しくて、思わず目をつむりそうになる。昂奮と緊張が入り交じった会場の空気は熱く、ぎらつく視線がスクールアイドル達を容赦なく射抜く。でも、きっと、ステージから見える景色はもっと最高なのだろう。客席を埋め尽くす人、人、人の波、その全てが自分だけを見ているのだと思うだけで背筋が震える。観客席からの視線一つ一つを受け止めながら、髪を振り乱し、言葉に記憶と想い出を乗せ、その瞳には強い意志を宿している。その姿は何度見ても、儚くて、だからこそ、美しい。ああ、少女たちは必死に叫んでいる。おのれの声を、誰かに、貴方に、世界に届けるために――。
蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブの出番はもうすぐ。舞台袖で全身が震えるほどの高まりを感じる。歌声と歓声、サイリウムの波が寄せては引いていく。彼女たちはこの瞬間のために生きてきたんだと思った。みんなと一緒なら、どこまでだって行けるはず。そんな想いを信じて、そんな夢のステージでスクールアイドルは歌っていた。
「――やっぱり、スクールアイドルは凄いな。」
音は止み、彼女達は舞台に歩みゆく。九人のスクールアイドル達を送り出す、ひとりの制服姿の少女。ポニーテールにまとめた茶褐色の長髪には、大切な人から贈られたというピンクと黄色のふたつの髪留めをつけている。遠い響きに耳を澄ます。彼女ら第一〇二期生にとっては、これが最後の決勝の舞台。黄昏があたしの身体を貫いている。少女はステージへと踏み出す彼女たちの後ろ姿に目を奪われると同時に、期待と不安とがごちゃ混ぜになって胸が締め付けられるような痛みを感じていた。この感情は何だろうか?頭上から照らし出す木漏れ日を受け煌めく瞳の色味に感化されてふと心惹かれた者もあるかも知れない。あるいは水面に立つ波頭が映り込む折だけ景色が変わるような心地良さに打たれたかも知れない。でもまた、誰にも頓着せぬように彼女達は再び歩み始めるだろうし、いま、この瞬間だけは、それだけで満足だったと思うことができたから――。
「見ててね、沙知さん。このラブライブ!決勝のステージが、あたしたち、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブの――」
歌声が鳴り響き始めると同時に照明が一斉に点灯し始め、観客席の雰囲気が一変し、眩い光が視界を覆い尽くす。湧き上がる歓声は地鳴りのように会場全体を包み込んだ。その圧倒的な熱量に全身が揺さぶられる。さあ、吠えろ、少女――。
「百合亜の見つけた、煌めきだよ――!」
変わらないものと変わっていくもの、旅立つものと遺されるもの。新しい風は次の蕾を綻ばせる。その中で煌めく青春を生きる九人と、そして二人の少女たち。限りある時間の中で、精一杯に花咲こうと藻掻く。これは、そんな彼女たちの、恋を知る運命の抒情詩――。
2
――「あれだねぇ、キミはまだ‥‥‥」
――「女の子には、なりきれていないね。」
四月一日、金曜日。入学式当日。
あたしは三時に目を覚まし、窓の外が暗いのにがっかりし、また床に入った。眠れないでいた。それでもうとうとしたのか四時を知らず、五時のアラームの音にはっきりと目ざめた。窓を開け耳をすまして聞くが雨ではないらしい。夜半の雨も晴れて、今朝はいい天気になるのかしら。六時、近所の真宗寺院から朝のお告げの鐘が鳴る。この時には既に身支度を終えていたあたしは、暫く別れを告げることとなる居候先を蒼惶として飛び出し、急かされたように蓮ノ空女学院へと向かった。人生の節目というものはどうも焦りすぎてしまう。到着してもまだ七時半。待ち合わせ時間までは早すぎる。日は仲春、空は雨がすっかりあがった、実に春らしく爽やかな朝である。
アマリリスの薄紅がその頬に形容できる、ひとりの少女は湖の畔で、蓮ノ空女学院の制服を着た鏡の中の女の子を睨みつけていた。えんじ色のセーラーワンピース。制服の襟と袖口は白地で、縁に金色の線が二本入っている。水鏡に映るあたしの姿はすっかり女子高生の制服姿で、宛ら本物の女子校生みたいだった。でもまだだ。まだ足りないものがある。あたしは鞄からリボンタイを取り出して首に巻いた。そしてスカートの裾を摘まんでお辞儀をする。うん、完璧だ。これでどこからどう見ても立派なお嬢様JKだ。
彼女――いや、あたしの名前は大賀美百合亜(おおがみゆりあ)。
――「ううん、いいや、違うんだ。気を悪くしないでくれよ。」
まさに青天の霹靂であった。昨日沙知に投げかけられたその一言は、百合亜の心を動揺させるには十分だった。
――「あたしが言いたいのはね、キミにはまだ女の子になりきれていない部分が、「少しだけ」あるということだよ。いやまあ、何処がって返されたら、此方としても窮してしまうんだけどねぇ。」
電話口の声色だったが、沙知は百合亜を試すかのように真っ直ぐと答えた。あの約束から、三ヶ月間。あたしは変わったんだ。この蓮ノ空女学院に入学して、使命を果たすために。弱気だった性格を無理やり矯正した。努力することも覚えた。愚図愚図して億劫がる癖も少しは治した。そういった自覚があったからこそ、沙知の一言は、そんな彼女に重くのしかかった。目覚めてからもこの一言がずっと頭から離れなかった。蓮ノ空女学院の制服を身に纏って、実際に登校してみて、初めてわかることがあるか若しれないと期待したのだが――。百合亜は汗ばんだ額を思うまま春風に曝さらして、粘り着いたウィッグの、逆に飛ばぬを恨む如くに、手巾を片手に握って、額とも云わず、顔とも云わず、頸窩の尽きるあたりまで、くちゃくちゃに掻き廻した。ああ、せっかく〈女の子〉らしく整えたのに、これではいけない。
――「あっはっは!大丈夫大丈夫!あたしもフォローするからさ。あたしが誘った協力関係なんだ。諄いようだけど、困ったことがあれば何でも相談してくれたまえよ。」
飄々とした沙知の笑い声が耳に響く。結局何もわからなかったし、むしろ余計にわからなくなっただけだった気がする。どんなに固い決意で臨んだつもりの九十日も、結局は枕流漱石の言い逃れにしかならないのか若しれない。でもまあ、いいのだ。だって、そんなこと最初からわかっていたし、覚悟はしていたから。そう、今のあたしは女の子を演じているだけの、偽者。でも、あの日々の道化よりは、きっと、楽しいはず。きょうからは、名実ともに蓮ノ空の、ホンモノの女子高生になる――いいや、なってみせる。眉尻を下げた神妙な面持ちで何度も言い聞かせた。弱い自分とは別れを告げたはずだろう。
四月の太陽は、二日酔にでもかかったように睡そうに懶けきっている。帛漉しに漉したようなその柔かい光――光と謂うよりも、いっそ匂いと謂った方が良さそうな、夢と触感と香気とに充ちた影のようなものを浴びて、どの木の花もがしらじらと輝いている。が、よく見ると、そのなかで花弁をぱっと派手やかに開いているのは、早咲きのソメイヨシノを除けばまだほんの二三分で、残りの七八分方は言い合せたようにふわりと膨らんだ蕾のままだ。蕾の多くは刻々にそのふくらみをゆるませ、窄んだ唇を半ば綻ばせて、春を満喫すべく、われがちに花弁を開こうとしている。何か目に見えぬものの不思議な力に動かされでもしているかのように。
――「ね?明日からキミと同じ学び舎に通うって謂うのも、実は結構楽しみにしてるんだぜ。そして、何より!」
水面に映る少女はまだ不安そうな顔をしている。あたしは鏡の中の女の子に、にっこりと笑いかけてみる。
――「花の高校生活を楽しみたまえ、百合亜!」
「うわァ、なんてぎこちない笑顔。」
百合亜は自嘲するように、情けなく笑った。若し愛嬌の天才である幼馴染が見たら腹を抱えて笑いそうだ。湖に映る女の子は既に表情を崩し、まるで別人になったかと謂うが如く暗い表情をしていた。生温い春風は頻りに、そして柔らかく吹きおろす。枝、木の葉の相軋く音が、密かにだが止む間なく聞える。彼女の長い茶褐色の髪をふわりと揺らす。だがそれも暫らくで、湖は元のひっそりとした景色に還えっていく。彼女はぼんやりとした目つきで再び水面へと目を向ける。唯だ、すべてが薄暗く、すべてが隈を持ったように、朧になって来たようだ。百合亜は頭を掻きながら、鏡に映った少女の瞳に視線を向けた。
「まあでも、やるしかないよねぇ。」
自分に言い聞かせるように呟き、改めて懐中時計に目を移す。沙知さんとの待ち合わせ時間まであと半刻ある。時間が余っていてもどうせ碌なことをしないのに、いつも時間がもったいないと思ってしまうのが人間のイヤらしいところだ。中学生の頃に比べれば随分と時間の有意義な使い方を心得てきた気はするが、然しこうも奇妙な高揚と憂惧とが背反する一日というのは、思い返せば人生の中で何度か経験しているのもので、決まって興が乗らない。イヤな焦燥感と、彼女の言葉が反復する。
――「それじゃあ、また明日!校舎前の噴水で待ち合わせしよっか!」
徐に待ち合わせ場所へと歩みを進める。青空を仰ぎながら、百合亜は今日から始まる学校生活に想いを馳せる――つもりが、却って妙な緊張感と疲労のせいか気障な詩人くさい感傷が思考を遮る。朝霜の晴れて来た湖畔にて深呼吸を一服。春とは謂いながら時折はじっと冷たいものがちらつこうという北陸の四月、素肌のまま土塊をおし分けて立ち上り、牙彫のような円くつめたい腕を高々とさし伸べ、しなやかな指につまみ上げた金と銀との盃に、日光の芳醇な滴りを波々と掬い取らうとする花々の姿には、年若な尼僧にでも見るような清浄さがある。数多い草木のなかで最も派手やかな花と謂えば、春が豊熟した頃に咲きほこるもので、そんな花の肌理の細かい滑らかな花弁に、むっちりと膩が乗った妖艶さは、観る人の心を捕えずにはおかないが、然しほんとうに根強い草木の生命そのものの復活を暗示し、純一無垢な自然の欲望の止みがたさを如実に歌っているものは、春の先駆者である梅や水仙のやうなものに求めなければならぬ――。
もう一度周囲を見回してみる。空は青く澄んでいて、雲一つ見当たらない。湖面にさざ波一つなく、水面に映った桜の木々の彩は微動だにしない。うん、今日はほんとうに良い天気だ。日常遣いには鼠色に古びた印象を受けるこの慣用句も、今日ばかりは処世術以上の嗜みを肌身で実感できる。これから三年間を過ごすことになる学校を独り占めしているような優越感に浸りながら、期待と不安を隣り合わせに抱え、ゆっくりと歩く。気休め程度に、安心できるのだ。幼い頃、金沢の古い町並みを両親に連れられた時にも経験した感覚とも似ている。ステキな学校だ、あの陽炎の立っている一帯すべてを、此足で、隅から隅まで歩いて見たい――。
3
「いやぁ、ほんとうに広い学校だよねぇ。」
蓮ノ空女学院――石川県金沢市から奥まった場所で、蓮の花の咲く湖の傍らにある私立高校。金沢といえば、清きと、美しきと、二筋の大川、市の両端を流れ、真中に城の石垣なお高く聳え、その森黒く濠蒼く、国境の山岳は重畳として、湖を包み、海に沿い、橋と、坂と、辻の柳、甍の浪の町を抱いだいた、名実ともに北陸の都である。然し当地は、白山山系から続く丘陵地域が金沢の市街地に溶け込んでいく境界の辺りに位置しており、そのところはほんとうに金沢にあるのかと疑わしいほど長閑な、或いは田舎くさい場所にある。唯だ一つ確信できたのは、校内の条件の整う場所からは、百万石の城下町の雑然とした情景とどんよりとした日本海の波濤が、あるいは白山山系の尾根がいつものように、深雪を纏って、大輪の朝顔のような、冴えた藍色を帯びて匂やかに望むことができるのは心地良いということ。百年の歴史を誇る本校の理念は「厳粛な規律と、確固たる伝統」だと沙知さんから聞いていたが、むしろその外観はどちらかというと近代的なデザインをしていて、視界に入る限りでは手入れも行き届いている様子だ。
湖から歩いて暫くすると、正門と桜並木の間に校舎の姿を認められるようになった。正門の門柱には二本の大きな広葉樹がその影を重ね合い、まるで一枚の絵画のように調和している。桜は満開に咲き誇り、風に揺れる度花弁が舞い落ちる。校舎に近づくにつれて徐々に人通りが増えてくる。登校時間にはまだ早いというのに、みんな同じ制服を身に纏い、談笑しながら歩いている。百合亜と同じくリボンタイの色が青緑色の生徒は見当たらない。これから始まる入学式に向けて準備を進める先輩方だろう、矢張り百合亜は新入生の中では一番乗りだったのかもしれない。まだ時間的余裕はあったが、百合亜は小走りで校舎の方へ向かっていく。新たなる出会いを歓迎するかのように舞い落ちる桜花に目を奪われる。一片の花弁を視線で追っていると、噴水の前、親しみのある後姿へと辿り着く。緑色の長髪が、艶かしくも可憐に靡いている。
「――沙知さん。」
少女の声は静かなる春風をひやりと斬った。大賀美沙知(おおがみさち)は百合亜の声を認めて振り返り、ふっと微笑んで手招きした。男勝りで剽悍な口調でつい忘れそうになるが、彼女の、満開のネリネのような可憐な笑顔は、あたしにとってはいつも頼り甲斐すら感じてしまうのだ。
「早いですね、沙知さん。すみません、待たせてしまいましたか。」
百合亜は急いで駆け寄ると、申し訳なさそうに頭を下げる。固くなって、へんな応え方をした。ひどく力んでいたのである。
「いやいや、まだ集合十五分前だぜ?むしろ早すぎるくらいだ。どうにも、祭事の日っていうのは目が覚めてしまうもんでさ。」
それに寮からはすぐの距離だし、と続ける。どうやら沙知さんも、あたしと同じせっかちなところがあるようだ。ただし百合亜と同じえんじ色の制服姿はどこか着慣れているようであって、少なくともあたしのように着せられているかのような印象は全くない。一〇一期生の黄色のリボンタイは、彼女に先輩としての威厳を強調させる。
「ふぅん。なるほど、なるほどねぇ。」
沙知さんは悪戯っぽく口角を上げると、あたしの全身を不躾にじろじろと見回す。そして顎に手を当てて何度も頷き、不敵なその眼差しにあたしは思わずたじろいでしまう。途端に百合亜の顔は真っ赤に染まり、思わず後ずさる。
「‥‥‥ちょっと、姉さん!なんなん、急に!」
スクールバッグの取っ手を握り直し、つい身体を隠すような仕草をしてしまう。
「なーっはっはっは!」
沙知はその様子を見て満足そうに、あまりにも大げさに笑うとぽんぽんと軽く百合亜の肩を叩いた。
「いやいや、うん、やっぱり似合うねぇ、うんうん、大変結構!実に蓮ノ空らしい感じがするよ!」
前言撤回。ほんとうに掴みどころのない姉だ。豪快な笑いと褒め言葉に対してどう反応すれば良いかわからず、あたしはただ曖昧な笑みを浮かべるしかなかった。
「ちょっと‥‥‥あたしだって結構恥ずかしいんだから‥‥‥!もう。それで、どうですか!?ちゃんと〈蓮ノ空女学院の生徒〉になりきれていますか!」
あなたがこう仕立てたんでしょうが、と不平不満の一つでも言いたくなる。百合亜の抗議を聞き流すかのように沙知は満足げにうんうんと大きく頷いた。その仕草があまりにも自然体で、まるで子供のように無邪気だった一方で、どこか大人の余裕を感じさせるような絶妙な雰囲気でもあった。
「ああ、大丈夫さ。キミはまさしく蓮ノ空女学院の生徒だよ。自信を持っていい。なんたって、このあたしが仕立て上げたんだからね。」
うんうんと頷き腕を組む沙知。
「やっぱりだねぇ、もともと睫毛が長いのもいいよねー。百合亜の長身にすごーく似合ってるよ。可愛いよ、うん。可愛い可愛い。‥‥‥ふふっ!」
もはや昨日の発言の真意を問いただす気にはなれなかった。その声色はどこか楽しげで、まるで新しいおもちゃを見つけた子どものように、弾んでいた。三ヶ月の間にこの人がどういう人かは知っていたつもりだけれど――。
日はぽかぽかとあたたかい、まるで春の野原にでも寝そべっているようだ。話をするのも懶くなってなんだか投げ遣りな態度となってしまう。
「ねぇ、百合亜!回って!一回転してみて!それでキミは合格だから!」
「ハァ。」
沙知の言葉は依然弾んでいる。然も面白くなさそうな顔をしながら、百合亜は捻くれた物言いで恭しく指示に従う。なんだこれは、土偶でも回した方が絵になるのではないか。ただ然し―――この人の側にいればなんとかなるという奇妙な安心感があった。ずっと心のどこかに微かな違和感や猜疑心があったのも事実だ。でも、あたしがいまこうして高校生で居られるのも彼女の青眼があってこそ。飄々とした言動の裏には現実を見据えた彼女なりの将来像が確かに描かれていて、実際にあたしを導き孤独を埋めてくれた。百合亜は沙知の要望に従い、改めて自分の姿を確認するようにゆっくりと一回転してみた。スカートがひらりと舞い上がり、再び元の位置に戻る。
「――よし、ほんとうに、大丈夫だ!」
沙知は満足げに頷いた。百合亜もつられてほっと胸を撫で下ろす。その一連の動作を何度も脳内で繰り返しながら自分の中で反芻した。うん、確かにこれは悪くないか若しれない。いや、まったく自信はないのだけれど、なんとかあたしは蓮ノ空女学院の生徒になっているらしい。恰も校舎の鐘が鳴り響き、噴水から水飛沫が舞い上がる。その音が合図だったかのように、沙知は両手を広げてゆっくりと、力強く切り出す。
「改めて――ようこそ、蓮ノ空女学院へ!キミを家族として、先輩として、心から歓迎しよう、大賀美百合亜くん!」
今度はしっかりと目と目が合う。透き通るその艶やかな声は、あたしの心に波紋を生み出すかの如く染み渡る。沙知と約束した、あの冬の日の情景を深々と思い出す。
「キミも知っての通り、蓮ノ空は伝統ある名門女子校だ。厳格な規律だとか生徒の自主性だとか、芸術分野で秀でているとかなんとか喧伝していてもね、ふん、その実態はひどいもんさ。これからキミには学院の行く末についてあたしと一緒にたくさん悩んでもらわないといけないし、願わくばスクールアイドルクラブの一員としても、あたしたちをサポートしてほしいと思ってる。」
勿論、と謂わんばかりに首肯く百合亜。百合亜の胸の内を読んだかのように、沙知は満足げに大きく息を吸ってこう告げた。
「一緒に立ち向かってくれること、ほんとうに心強く思っているよ。」
改めて有難うと、沙知はにひっと微笑む。沙知の屈託のない笑顔はいつも眩しい。
「それと、だ。」
鐘と水の音はもう聞こえない。
「――あたしたちは三年間この学園に通う訳だけど、長いようで意外と短いもんさ。変わらないものと変わっていくもの、旅立つものと遺されるもの。あたしは遺される側だったけれど、そんなことを考えているとね。もう一年経っちゃったよ。あはは。」
沙知の言葉に息が詰まる。その瞳は空を見つめ、目に見えない何かを確かに見ているようだった。
「――キミの将来を奪ったあたしが言えたもんじゃないけどさ。限りある時間の中で、精一杯に花咲こうと藻掻く。そんな青春だから、楽しいのさ。さあ、一緒に楽しもうじゃないか、百合亜!」
潤いある春の大気の感触と春風の柔らかい吹き方とが、沙知の言葉一つ一つに鮮やかに溶け合って運ばれている。奪われたなんて、思っていない、あなたはあたしに、居場所と役割を与えてくれたんだ。百合亜はただ黙って頷くことしかできなかったが、彼女の真摯な眼差しに心を動かされるのを確と感じた。沙知は満面の笑みを浮かべ、百合亜に手を差し伸べる。彼女はいつも自信に満ち溢れているし、小さい身体に秘めた大鵬の志に向かって全力で突き進んでいる。そんな彼女の姿を見て、あたしも勇気づけられた。そして何より、この人と出会えたことがほんとうに良かったと思っているのだ。だから、あたしは――。
心地よい春の青空を見上げる。そして、目を落とす。声が漏れる。
「はああああぁぁぁぁぁぁぁ‥‥‥‥。」
「おーーーーーーーーーーーい‥‥‥。」
凸凹なふたりは、いまにも崩れそうな溜息を吐き出す。沙知は天を仰ぎ、百合亜は地を拝む。ふたりはふたりして大げさに頭を抱えていた。
「いや、ほんとうにごめん、沙知さん。せっかく良いこと言ってくれたのに!でもさ、やっぱり不安だぜ!わかるだろ!ほら、あれだよ!8番らーめん行ったときにさ、味噌野菜ラーメン食べたくて行ったのにさ、メニュー見てたらチャーハンセットにしようとか餃子付けようとか考えてたらさ、ふと唐麵に心惹かれちゃうときってあるじゃんか!?なんつーか、どっちつかずっていうかさ、心がちょっとぐちゃぐちゃしてる感じなんだよ!」
お、おう、と最初はたじろいだ沙知だったか、次の瞬間には思わず笑いながら呟いた。
「まあねぇ、そりゃそうだ。不安だよねぇ。わかるさ。ま、一緒にがんばろうぜぃ!」
わかってくれたようだ。よかった。やっぱり心強いじゃないか。そんな百合亜の気持ちを知ってか知らずか、沙知は相変わらず飄々とした態度でニタリと笑い、そして不躾に話を畳み始めた。
「それじゃあ、あたしは用事があるから先に行くね。午後の新入生歓迎ステージ、ぜったい見に来てよね!」
沙知はローファーを心地良く鳴らしながら、此方に手を振り駆け足で校舎へ向かっていく。ほんとうに忙しない、猫みたいな人だ。
「あ、それと。」沙知は息を吸い、態とらしいくらいの元気な声で吐き出す。
「今日はあたし、くるまやラーメンで味噌の気分だから――!」
にかっと微笑んだ笑顔は、それだけで此方を幸せにした。
「‥‥‥!あたし、も、大好きだーーー!!」
桜並木に響き渡る大胆な告白に視線が集まる。女の子の特権だ。瞬間百合亜ははっとし、耳まで朱色に染めて、恥ずかしさを隠すように足早に反対方向へ駆け出した。
そんな百合亜の後姿を眺めながら、沙知は独りでくすくすと笑うのだった。
「――あはは。うん、最高のスタートダッシュだ。いいねぃ。」
4
「――結びつる心も深き元結ひに、か。」
沙知との約束を改めて反芻する。なんだかんだこうして制服に袖を通すことで、ようやく自分が高校生に、蓮ノ空女学院の一員になったという実感を得た気がする。ありきたりな表現だが、まるで新しい世界への第一歩、だ。微風。日光。野花。野鳥。春は穏やかで暖かかった。花を蒸し人を蒸し、大地を蒸し草を蒸す。そうして何事もなかったのように、女子高生としての初めての一日を終えられれば良いのだけれど――。
そう思った刹那、誰かとすれ違った。ふわっと優しい匂いに包まれ、一呼吸分だけ鼓動が大きく脈を打つ。天幕の隙間から春の陽が、百合亜の心臓に黄金の征矢を投げかけた。その少女はえんじ色の制服に艶やかな白い肌がよく映え、銀髪に紅色のインナーカラーが入っており、綺麗なショートヘアーに整えられている。瞳は燦然と輝く桃色で、底に一抹の黒味を湛たたえ、表面は紅玉のように光っていた。背丈はあたしと同じほどだろうか。あたしはその凛と立つ姿を一幅の絵の様に観ていた。横顔の美しさと、僅かな儚さに、百合亜は眼が眩んでしまう。朝露が葉を滑り、地面に吸い込まれていく。彼女は百合亜に関心を示さず、そのまま立ち去って行った。
「――綺麗な子だなぁ。」
百合亜は彼女の後ろ姿を見送りながら呟いた。蓮ノ空女学院では学年ごとにリボンタイの色が異なる。あたしたち一〇二期生は青緑色のリボン、つまり、あの女の子もおのれと同じ新入生ということになるのだろう。しかも、この学校の制服によく似合う美しい容姿と凛とした立ち振る舞いからして、かなり育ちの良いお嬢様に違いないはず。いや、沙知さんやめぐちゃんも相当に可憐だが――。
いやいや、いちいちこんな感慨に浸っていては身が持たない!蓮ノ空女学院、ここは女子たちの花園。これから先も、何度も、こんなに胸を踊らせるつもりなのか。ひどい青年の動悸だ、鎮めなくては。紙上談兵を得意とする専門家気取りの鍍金が剝がれてしまう前に、せめて、沙知さんからの期待に応えられるあたしであるのだと、成る丈早くに示さなくては。
「よし。」
百合亜はしばらく立ち尽くして思考を巡らせ、念のため彼女の姿を反芻した。
「おいおいおい。」
再度息を呑んだ。その儚げな少女は、まるで萎んだ風船のように地面に蹲っていたのだ。百合亜は一瞬竦むが、歩み寄り声を掛けようとする。人助けの時の第一歩は、いつも私を後ろめたい気分にさせる。思い出せない。こんなときは何の言葉をかけるのがいいんだろう――。
「あのォー、大丈夫ですか‥‥‥?」
百合亜の、自信のない声色が言下に遮られる。
「かっぱ。」
「かっぱ?」
話しかけられたのかと思ったが、どうやら独り言のようだ。その声はとても澄んでいて綺麗だけど、なんだかぼんやりとした温かみがある。
「エェと、大丈夫?」
もう一度、今度は少しだけ自信のある声で、然しはっきりとした発音で語り掛けると、少女は此方を向いて僅かに首を傾げる。瞳は碧く澄んだ海の色をしている。透き通る肌に長い睫毛。血の気をあまり感じずどこか病弱な印象を受けるが、それはきっとその無二の美貌のせいだ。よくよく見ると頬は薄く赤らみ、血色は良いように感じられ安心した。むしろ寒緋桃の花棚のように麗しく、薄い唇の隙間から控えめにこぼれる吐息もほんのり桜色だ。彼女は目を丸くして口を半開きにして、
「? かわいいよ。」
とだけ言った。一瞬感じた凛とした印象とは乖離した、子どもっぽさの滲み出た雰囲気にたじろいでしまう。百合亜はその言葉の意味をすぐには理解できなかったが、よく見てみると、彼女の手元には何かの動物が蠢いているのが認められた。
「カワウソ。」
そう言って彼女は手に持っているモノをそっと差し出すと、黒い手袋を嵌めた華奢な手で抱きしめて見せてくれた。確かにカワウソだった。蓮ノ空にはカワウソが棲息しているらしい。その円らな目でじっと見つめられているような気がしてドキッとしたが、無垢な表情が愛らしくてつい頬が緩む。
「好きなのかい?カワウソ。」
「どうだろ‥‥‥。ボク、カワウソってよくわかんないから。」
「そっかぁ‥‥‥。」
不思議な空気感に呑まれていく。彼女はカワウソを大事そうに地面へ放ち、今度は此方に向き直りじっと此方を見つめる。なんだか妙に居心地が悪いような気がして目を逸らそうとしたが、それより先に彼女が口を開いたのでできなかった。
「きみは―――なっとう?」
なっとう。納豆だろうか。わからない。わからないのはこの幻惑的な彼女の言葉なのか、それともあたしの頭の方なのだろうか。
「君も一年生、だよね」
百合亜が尋ねると彼女はよいしょと徐に立ち上がり、スカートを正して目を瞑ると、突然くるりと一回転する。再び開いた彼女の瞳は、どこか虚空を見据えている。
「うん、そうだよ。ボクは一年生のつづり――夕霧綴理(ゆうぎりつづり)だよ。」
彼女の視線が改めてあたしに移る。儚さの中に情熱的な深みのある瞳だ。その瞬間、全身が熱くなった気がした。
夕霧、綴理――。山里のあはれをそふる夕霧に、だろうか。初対面のあたしですら面食らわせる、実直で不器用な感は確かにあるが、そんな些細な印象をすっかりと忘れさせてしまう、光る容貌にどうしても見惚れてしまう。然し同時に、何故だかはわからないが、彼女となら仲良くなれるか若しれないという期待感も湧き上がってくるように思えた。
「あ、あたしは大賀美百合亜。よろしくね。」
「そっか、百合亜――ゆり。きみは、いい色をしてるね。」
いきなり渾名を付けられた百合亜はまたまた面食らった心地がした。そして、色、か。情緒的な響きだ。きょうこの情景はまさしく、地に空に春風の亘るほどは物みな燃え立って富貴に色めくを、或いはひそかなる少女たちの煌めきを、一本の細き桜の末にいただいて、住むまじき世に肩身狭く憚はばかりの呼吸を吹くようである。石仏に愛なし――道化のあたしに色は出来ぬものと覚悟を決めたつもりであったが、愛というのはいつも、愛せらるる資格ありとの自信に基づいて起るものだ。ただし、愛せらるるの資格ありと自信して、愛するの資格なきに気付かないものもある。この両資格は多くの場合において反比例する。愛せらるるの資格を標榜して憚からぬ者は、いかなる犠牲をも相手に逼る。相手を愛するの資格を具えざるがためだ。倩たる巧笑におのが命を托するものは必ず人を殺すだろう。おのれのためにする愛を解する。人のためにする愛の、存在し得るやと考えた事もない。詩趣はあっても、道義はないから――。
さて。春の陽気は些細な出会いさえその情景を羽化登仙の心地に表明したがるものであるから、困ったものだ。百合亜は長い睫毛を必要以上にパチパチ動かし、
「ハァ、芸学家ですなァ。」
おのれに問いかけるような口調で言い放つ。更にはジトーっと目を細めて顎に手を当ててみる。然し彼女はにこりともせず、おちついて淡々と去意を返した。しまった、訝しく思われたか。
「じゃあまたね。」
「エッ、あっ、うん!またね!」
彼女は楚々とした足取りで過ぎ去っていった。あたしはしばらく茫然と立ち尽くし、彼女の背中を視線で追っていた。鎌居達みたいな女の子。恰も白昼夢のような出来事とは、こういった経験を謂うのだろうか。
「――綺麗で、不思議な子だなぁ。」
夢想家――嘲笑の的としての蔑称ではなく、なんだか共感できるような、彼女の魅力としてこの言葉がぴたりと当て嵌まるように思われた。世の現実家、夢想家の区別も錯雑している如くの輻輳した俗世に、あたしは、この世の中に生きている。然し、それは、あたしのほんの一部分でしか無いのだ。そう思われてならない。同様に、彼女も、またあのひとも、その大部分を、他のひとには全然わからぬところで生きているに違いない。あたしだけの場合を例にとって言うならば、あたしは、この社会と、全く切りはなされた別の世界で生きている数時間を持っている。それは、あたしの眠っている間の数時間である。あたしはこの地球の、どこにも絶対に無い美しい風景を、たしかにこの眼で見て、しかもなお忘れずに記憶している。あたしはおのれのこの肉体を以て、その風景の中に遊んだ。記憶は、それは、現実であろうと、また眠りのうちの夢であろうと、その鮮やかさに変りが無いならば、あたしにとって、同じような現実ではなかろうか。そんな幻惑的な経験を、この夢見心地に目撃した。
春風と共に深呼吸をして、新鮮な空気を胸いっぱいに溜め込み、無意識に張り巡らされていた、駘蕩とは程遠い緊張感を少しだけ解きほぐす。
「よし、行くか。」
記憶の彼方に思い出す。ああ、そういえば〈夕霧〉は筒井筒から始まる物語だった。あたしは自分のことを「まめ人」だと評価するつもりは全くないし、そもそも彼女へ抱くあの感情の正体が何なのか、解釈することを意図的に避けてきたけれど。それでも、彼女との再会には高揚感を抑えられずにはいられない。
百合亜は懐中時計に目を落とす。そろそろ、幼馴染との待ち合わせの時間だ。
5
…
……
吹く春風にどこからともなくいい花の香りが流ながれてきて、木々の上では小鳥が楽しそうに囀っている。ツーサイドアップに纏められたグリーンブラウンの髪が、そよそよと心地よさそうに揺れる。降り注ぐ陽光に目を細めながら、蓮ノ空女学院校門の近くで少女は立ち止まった。ふと、長い髪が頬に当たってくすぐったいのか、彼女はそっと髪を耳にかけた。その横顔には誰もが見惚れてしまう愛くるしさがある。
「ふぅーーー。」
藤島慈(ふじしまめぐみ)、きょうから華の高校一年生。この胸の高鳴る鼓動が緊張から来るものか、それとも期待から来るものなのか分からないまま、私は立ち尽くしていた。今日からここで三年間を過ごすことになるんだ。そう思うと自然と背筋が伸びてしまうのを感じる――いや、ぜんぜんちがう!ぜんぶ、あいつのせいだ。散々私を心配させておいて、待たせておいて。ムカつく‥‥‥!まさか蓮ノ空に一緒に通うことになるとは思いもしなかったけれど‥‥‥。でも、言いたいことはきっちり言ってやるんだから。
遂にその時がやって来た。
「うわ。」
ほんとに居たよ。しかも女の子の格好で。最後の最後まで実感が無かったけれど。あいつは溌剌とした声を響かせながら、笑顔で手を振り此方へ駆け寄っていく。
…
……
あたしは小ぶりな桜の木の近くに親愛なる幼馴染の姿を認識し、思わず大きな声で呼びかけ走り出していた。
「めぐちゃーーーーん!久しぶりーーーー!」
その屈託のない笑顔で、尻尾を振る子犬のように駆けよって来るのを見た慈。
「はあぁぁぁぁぁぁぁ――――」
地の底に届く溜息を吸い上げ、百合亜に負けないくらいの愛嬌たっぷりの笑顔で答えた。
「思いっきりあんたのこと、ビンタしたい☆」
指ハートの決めポーズ。鈴の音色のように弾む声からは信じられないほど毒気づいた一言が春風に運ばれる。真珠に見紛う美貌の藤色の瞳は、全く笑っていない。なんと、感動的な再会であろうか。
「御尤もだ!ほんとうに心配かけてごめん!」
あたしはこの格好でなければ滑り込んで土下座で若してやりたいのだという気持ちを抑え、反省の意を込めて手を合わせて謝る仕草を見せたが、それは慈をさらに呆れさせただけのようだった。
「やだなぁ、百合亜ちゃん。冗談だよ~。今日から高校生、可愛い可愛い藤島慈ちゃんがぁ、そんなことするわけないでしょ~☆」」
タレント業で鍛え上げられた、なんとも社交辞令的な愛嬌仕草が胸に突き刺さる。こういうときの彼女は、決まって不満がいっぱいなのだ。痛い、痛いぜ。そして一変、慈は冷徹な眼差しを此方に向けてくる。百合亜はその真剣な表情を覗き込み、う、とたじろぐ。
「あんたねぇ、私の気持ち考えてみたことある?音信不通だった幼馴染から久しぶりに連絡来たと思ったら蓮ノ空女学院に入学しますー、なんて訳わからないこと一方的に言われてさ、それで、なんだかんだ私も入学することになったけどさ、全然あんたから返信来ないじゃん!そんでもって先週急に待ち合わせ時間と場所だけこれまた一方的に言ってきてさ、今日はじめて、あんたの「可愛らし~い」蓮ノ空の制服姿を見る、ってわけよ!流石の大天使めぐちゃんでも怒るからね!どんな再会の仕方よ!?」
遂に堰は切れたようで、三ヶ月間ため込んでいた彼女なりの鬱憤を右ストレートでぶつけられる。痛い、痛いぜ。
「返す言葉もございませぬ。こんな状況故、他人に多くを伝えぬようにと、出資者から指示を受けておりました故に‥‥‥。」
俎板の上の鯉は歯切れの悪い返事しか返せない。武士は食わねどこの瞬間ばかりは食われる切身だ。さあ、刺身にして食ってしまえ。
「というか、」
慈は腰に手を当て、態とらしいくらいにぷくっと顔を膨らませる。
「結構似合ってんのが腹立つ!なんなの!?確かに良い素材は持ってるな~って前から思ってはいたけどさ!ムカつく~!!」
「はっはっは、お褒めの言葉ありがとうございます慈お嬢様。」
スカートの裾を摘まんでお辞儀をしてみせ、慈の方へ目を移してウインクして見せる百合亜。
「なにそれ。全然面白くないんだけど。」
「えーーー。」
彼女の表情はすっと平凡な石ころを見る目に変わり、いつもの声色と口調に戻った。ああ、これだよこれ。あたしがよく知る藤島慈だ。
「と・に・か・く!」
「おっと。」
慈は少し俯きながら、勢いよく右の拳をあたしの胸の前に突き出す。
「――あんたが無事で、ほんとによかった。心配したんだから、バカ。」
あたしは自然とその力強くも優しい拳を両手で握りしめ、
「うん、ほんとうにありがとう、めぐちゃん。」
精一杯の感謝を込めて、真心を伝えた。こうして彼女と冗談を交じりで会話するのも懐かしい。互いに異なるその境遇から日一日とその心までが遠ざかって行って、折角の幼馴染も遂には赤の他人に等しいものになってしまうという不安があったのだ。こうして再開できるのは――たとえあたしの一方的な思い込みであったとしても、嬉しいことには相違ない。これには青年らしい照れくささも全くない。純真な安堵感だ。
「――まあ、わかればよろしい!」
慈はふっと顔を上げ、普段の明るく快活な口調で語りかける。
「いまは良いよ。いまだけはね!ほんとうは聞きたいこと山ほどあるけど!!あんたもあたしも今日はめちゃくちゃ忙しいだろうから、後でた~っぷり聞いてあげる☆」
蓮ノ空女学院は全寮制、時間はたっぷりあるしね、と続ける。
「まあどうせあんたのことだし、誰かの頼み事でも引き受けちゃったんでしょ。流石にそんな格好させるのは趣味が悪いけど。」
百合亜はギクリとした。慈の指摘に返す言葉もない。銀鈴の鳴りつづけるような空白が彼女を充たしていた。慈の正論の中に含みがあったこと、そしておのれが殺風景な妄執の道を辿って来た事実に改めて気付かされること、それが僅かに嬉しいような、哀しいような気がしていた。流石はめぐちゃん、図星だ。痛い、痛いぜ。
「悪い。その通りだ。あたしも、めぐちゃんに話したいことは山ほどあるんだ。後でしっかり伝えるからさ、もうちょっとだけ待ってくれると助かる。でもさ、」
「ん~?」
百合亜は語調を明るくした。大空の高みから金粉をふり撒いたような陽光が、下なる大地にこうして氾濫して来る時、草木は急に昨日の睡眠より覚め、しなやかな諸手を伸べて、軽く大気のなかに躍りさざめき、小鳥は花樹の梢に飛び交わす。燕雀は玉を転ばすような美しい歌曲に謡い耽っている。
「めぐちゃんの制服姿も、めちゃくちゃ似合ってるよ。天使みたいなっていうか、ううん、修飾はいいや、とにかく可愛いと思う。いやまあ、めぐちゃんは昔から最強に可愛いんだけどさ。」
少女の饒舌はまだ続いてゆく。慈は聞き飽きたものか照れくさいものか、スカートを翻して横を向き、腕を組みながら百合亜の言葉に耳だけ傾ける仕草をしてみせる。
「――兎も角さ、なんかさ、こういう複雑な状況だからこそ、めぐちゃんと一緒にいられるのはすっごく心強いし、ふつうに高校生活楽しみだなーって思えるっていうかさ。」
話し続けて漸く照れくさくなったあたしは頭をポリポリと掻いて、
「これからもまたよろしくね、めぐちゃん!」
百合亜は眩しい笑顔を振り撒く。慈は頬を赤らめながら目を逸らすしかなかった。
「――そう。そうね。」
落ち着いた優しい一言が漏れる。
「――よろしくね、百合亜。」
二人は再び顔を見合わせ、苦笑し合った。
それはそうと。
「そのキモイお世辞はなに。いままで一回も「めぐちゃん可愛い~☆」なんて、直接言ってくれたことなかったのに。なんなの?誰かにやれって言われたの?」
慈の冷ややかな目線が再び突き刺さる。めぐちゃんはほんとうに勘が鋭い。あたしは思わず怯んでしまった。
「エッ、それ拾う?これからあたしたちの新たなる学生生活が始まるんだーって、めちゃくちゃ良い雰囲気だったじゃんかよ。」
などと繕った回答で疑念を笑い飛ばそうと努める。いやいやまさかと手をぶんぶん振って否定するが、その動作も虚しく空を切る。それでもって慈は愛嬌外交モードの表情に逆戻りだ。
「あれ~?ど・う・し・た・の・か・な、百合亜ちゃ~ん☆」
「まーたそうやって妙なとこで疑り深いんだからさ、めぐちゃんは。ほんとうになんでもない、なんでもないんだぜ。」
「それとも、れんたろ――」
続く単語が咄嗟に想起され「慈!」それはダメだ、と言下に遮る。いまのあたしは〈大賀美百合亜〉以上の何者でもないのだから。慈はびくっと肩を竦め一瞬怯えたようだった。
「あ、ごめん、急に大きな声出して‥‥‥。」
だからって、まだ事情を知らない彼女に押し付けてはダメだ。あたしは目を泳がせ、弾かれたように肩を硬くしていた。一呼吸おいて、申し訳なさそうに、そしてぶっきらぼうに言い放った。
「――教わったんだよ、沙知さん、あの後世話してくれた人に、ね。蓮ノ空に通うんなら女学院の流儀を学びなさい、そんでもって、JKはとりあえず〈褒める〉〈可愛い〉〈やばい〉を多用しなさい、だってさ。」
歯切れよく澄んだ声で言った気がする。発音もきれいだったと思う。慈はジト目で百合亜を睨みつける。その眼差しには、どこか呆れと心配が入り交じっているようにも見えた。罪悪感のあるあたしはただ黙って、めぐちゃんの言葉を待つしかなかった。彼女は訝しげな眼差しを向けて吐き捨てる。
「――あっそ。なーんか大体察しはついてたけど。あんた、その沙知さんってやらに騙されてるんじゃないの?」
あたしは思わず口を尖らせる。確かに、あの人の言うことはすべて正しかったかと言えば――それは違うだろう。先ほど確信したばかりだ。得体の知れない人物、という評価がぴったり当て嵌まる。とはいえ、騙されている、という表現は少し強いのでは――またまた慈の視線から思わず目を逸らしてしまう。それでもなお、百合亜は剽悍とした表情のまま押し通したいと思ってしまった。
「いや、騙されてはないよ。ただ、」
余裕のある笑みを浮かべようと努め、そして話題を変えるかのように、芝居がかった調子で言った。
「――あたしがそうありたいと願う限りは、きっとあたしは大賀美百合亜だよ。」
「……。」
自分でも驚くくらいの気障な台詞だ。あたしは、嘘をついた。いや、やっぱり、嘘ではない。おのれにとって、現実の事を言ったのだ。慈の生暖かい視線が投げかけられる。
「――そ。」
また大袈裟にため息をつくと、呆れ顔で肩をすくめて言う。
「まあでも、思ったよりはしっかりと女の子してるみたいだし。いいんじゃない?気になるところも山ほどあるけどね!あとでその「沙知さん」のことも教えなさいよ。」
素っ気ないその一言にはどこか温かみを感じた気がした。慈はくるっと身体を回し、校舎に向かって徐に歩き始める。あたしも鞄をしっかりと肩に掛けなおし、めぐちゃんのあとに続く。桜は、こぼれるように咲いていた。
「散らず、散らずみ。」
「いや、散りず、散りずみ。」
「ちがうよ。散りみ、散り、みず。」
ふたりして笑った。
6
蓮ノ空の校舎前にはクラス分けの用紙が仰々しく掲げられ、女学生たちは思い思いに群がり、歓声や悲喜こもごもの歓声を上げている。特に一〇二期生の新入生たちは皆興味津々で自分のクラスを確認している。蓮ノ空は一学年あたり百二十人の四クラス制。この広大な敷地の割には学生数が少ない気もするけれど、だからこそ保たれる伝統もあるか若しれないと詮索してみたりする。
「いやー、盛り上がってるねぇ。」
その様子を一歩離れてあたしたちは眺める。とはいえ流石に紙面上の個人名は判別できない距離であるので、混雑の隙を見計らって掲示板に近づいた。自分の名前を探す。大賀美百合亜。大賀美百合亜……あった。
「一年百合組。」
花の名前を付けるというのは如何にもお嬢様校らしい。百合組の、百合亜。うん、しっくりくる。いいじゃないか。というか今更ながら、あたしの学院への登録とか、あとは戸籍とかってどうなってるんだろうか。今度機会を見計らって理事長に聞いてみよう。そして再び目を凝らすと、同じ表には見覚えのある名前が視界に飛び込んできて、思わず安堵の声を漏らした。藤島慈、一年百合組。
「よっっっしゃぁぁぁああ‥‥‥!」
「まあ、なんとなく予想はできてたけど。」
眉をハの字にして溜息混じりにぼやいた慈だったが、ふっと目を瞑り安堵の微笑を浮かべる。続けて髪を払い、照れ隠しにも思える突き放した口調で、
「先に言っとくけど、一日中一年中ずっとあんたをフォローできるわけじゃ、ないんだからね!私は私なりに花のJKライフを楽しむつもりだから、それはちゃ~ん、と覚えといてよね!」
「うんうん、わかってる!心強すぎるぜめぐちゃん‥‥‥!」
見慣れたぷいっとする姿も頼もしく感じる。
談笑するあたしたちに、赤色のリボンタイを付けた三年生の先輩方が通りがかり挨拶をしてくれた。うふふ、かわいいねぇ、新入生。あたしとめぐちゃんは同時に、元気よく、
「おはようございます☆」
「ごーきげんよーう!」
と可愛らしい返事をする。先輩方はうふふと手を振りながら去っていった。よし、完璧なお嬢様を演じていたに違いないぜ。百合亜がそんな感傷に浸って居るのを見た慈は、一瞬足を止めて辺りを見回すと、小さな溜息とともに優しく語りかけけたのだ。
「――ねえ、百合亜。」
「ん?」
慈は腰に手を当てて仁王立ちし、得意げな表情で胸を張る。あたしは思わず目を逸らしそうになる。このポーズの時のめぐちゃんは、いつも、かなり手強い。
「後で聞くって言った手前、ここでうだうだ言いたくないんだけどさ、ちょ~っと諄い、かな☆ その沙知さんって人の言葉、信用しすぎないようにしなさいよ。やっぱり、あんたみたいなお人好しが騙されないわけないんだからさ。」
「なっ‥‥‥!」
幼馴染から鋭い指摘に思わず息が詰まる。完璧なお嬢様演技が出来ていたつもりだったのに‥‥‥。沙知さん、諄いって、言われちまったぜ‥‥‥!
――いやいや、考えてみれば、別段あたしは唯だ余裕飄々とした彼女の風采の故に惹き付けられているわけでもないようだぞ。喪失感あるいは寂寥感からであろうか。本人には頗る言いにくい話ではあるが、沙知とふたりで歩いていると彼女はにひひと笑い、結論を断じることなくあたしをさり気なく褒めて話を畳もうとするきらいがある。親愛と不安と信頼のあいだには、この上なく微妙な相互作用がたえず働いているものらしく、彼女との豐潤の状態があたしにとって幾分魅力になっていたことも争われない。然し、これは、ひょっとしたら、沙知と百合亜との交際は、はじめつから女将と家來の關係にすぎず、徹頭徹尾、あたしがへえへえ牛耳られ、弄ばれていたという話に終るだけのことのような気もする。ああ、どうやらこれは語るに落ちたようだ。つまりこの三ヶ月間のあたしは、金魚の糞のやうな無意志の生活をしていた自覚がどこかにあり、金魚が泳げば私もふらふらついて行くというような、そんな儚い状態で沙知と付き合いをもっていたに違いないのである。なるほど、昨日の一言が尾を引いてしまうわけだ。そして、騙されている、か。もう一度反芻してみる。まあ、冷静に考えればそう評されることもは予想できていたのだが、いざ現実に直面すると不安に駆られてしまうのも事実だ。でも、もう遅い。沙知さんと、彼女の言葉を信じて努力し続けたおのれを信じて進み続けるほか、ないのだ。我が万全の道化というものは、少しの蹉跌があったからといって滅びるようなものではないのだから――。
百合亜が暫く黙って頷いていると、慈は肩をポンと叩いてきた。
「――なんかさ、あんた口調も性格も変わった?わざわざ外向きにお嬢様っぽく振舞う必要はないと、私は思うんだけど。」
無理してはいないか、との趣意を込めたような暖かい口調だった。
「――なにより、女の子はあんたが思ってるほど鈍感じゃないんだからね!」
素っ気ない物言いの中に配慮が溢れている。言葉の端々までも、真実を感じて、聞き入ってしまう。慈と再会し、久しい間私の念頭にあったこの人間感情の見出した時の喜び、それは全く感激そのものであった。あの夜の声、あの夏の山、海なりの音、懐かしい想い出である。何から何まで無駄な努力を積み重ねて来たような過去の生活であっても、その中からきょうという一日が生れたと思えば、十五年の月日はわたしにとって決して無意味ではなかったと思い直される。人を変えるのは、過去か未来か。まだ踏みも知らぬ――。
「変わりもする、よ。いまのあたしは、」
慈の優しさが胸の奥深くまで沁みる。そう、むかしからそうだ、彼女の前だけでは、強がりたいのだ。
「大賀美百合亜なんだ~~~!」
百合亜は春風で乱れた髪を押さえながら駆け出し、校舎に入っていく。吐き捨てた彼女なりの強がりを置き去りにして、幼馴染の温気は軽く払う春風に、ひっそり閑かんと吹かれている。
「はぁ、もう!」
笛のやうな若々しい春陽が空から落ちて来た。
「――どんな高校生活が始まることやら。」
7
教室棟の案内板には「一年百合組」の文字が掲げられている。きょうからあたしも高校一年生、か。漸く込み上げ来た期待感を胸に抱きながら、あたしは肩のスクールバッグを改めてぎゅっと掛けなおし、そのクラスへと歩みを進め、自分の名前が貼られた席を見つける。出席番号一番、所謂あいうえお順。申の方位最前列、窓際の席だ。南向きの窓からは中庭の風景が開かれ、ここからも爛漫たる春の訪れがよくわかる。
そしてあたしのすぐ後ろの席には――お淑やかで落ち着いた雰囲気を纏う少女。視界が一瞬開けたような感覚。教室の中で桜が舞う、いや、蕾が一気に満開になるかのような華々しい情景が開かれた気がした。彼女の肩まで伸びた紫髪のポニーテールがふわりと春風に揺れ、左手で軽く髪を押さえる所作すらも可憐で見惚れてしまう。窓に目を遣る翡翠のように澄んだ瞳はどこか思い憂げなようでもあり、彼女の気品を助長しているかのようであった。今日は美少女とよく出会うな――などと、中学生染みた感慨は意識して緊張感でもって振り払う。いちいち女学生たちの勢いに呑まれていてはあたしが充電切れになってしまう。彼女も、今日からあたしのクラスメイトなんだ。友達として、気楽に接してみればいいさ。自問自答の末に小さな覚悟を決める。兵は神速を尊ぶ、だ。
よし、と活き込んだあたしはにぱっと笑って、彼女に目いっぱい明るく挨拶してみる。机に貼られた彼女の名前を一瞥して、
「おはよう、乙宗梢(おとむねこずえ)さん!」
明快な声を届ける。百合亜を認識した梢はやや驚いた様子を見せたが、すぐに優しく微笑んで会釈してみせた。
「ええ、おはよう。そういうあなたは‥‥‥大賀美さん、ね?」
少し間を置いてから彼女はニッコリと微笑んだ。彼女の声は潺湲たる清流の一滴一滴のような耽美さを秘めており、あたしの耳に実に心地よく響く。
「そう!あたしは大賀美百合亜。よろしくね、乙宗梢さん!」
梢の双眸には依然若干の驚きと困惑が宿っていたものの、たじろがず百合亜の挨拶に丁寧に受け答えした。
「ふふっ。よろしくね、大賀美さん。私(わたくし)は乙宗梢と申します。ごめんなさい、少し緊張していて。」
右手を胸に当てながらぎこちない笑顔が彼女に表れたが、それもまた高校生の少女らしい。百合亜は自分の机に荷物を置くと、席に腰かけ梢のほうに身体を向けて会話を続ける。
「いや~、梢ちゃん!素敵な名前!ねぇ、梢ちゃんって呼んでもいい?あたしはこの通りフランクだからさ、堅苦しいのって逆に息苦しくなっちゃうんだよね。」
梢はその提案を吟味するように思案顔になったが。数秒経たないうちに首を縦に振った。
「ふふ、そうよね。私もあまり肩肘張るのも良くなさそうだわ。それで構わないわよ。よろしくね、百合亜さん?」
彼女がふわり笑ってくれたことに百合亜は内心安堵し、お日様のような笑顔で元気よく応えた。
「うん!よろしくね、梢ちゃん!」
続けて百合亜は彼女と会話を弾ませる。矢張り〈距離感〉というものは難しい。昔の癖でつい勇み足になってしまい内心焦っていたが、よし、第一印象は大丈夫そうだ。好印象、好印象。数年ぶりに友達というものを作った気がする。こんなにも冷や汗をかかされる挑戦だったかしら。
「この制服もさ、入学前に何回か着ているわけなんだけども、いざ学院に足を踏み入れてみると、漸く実感が湧いてきて、なんだかドキドキするっていうか。‥‥‥」
とはいえ初対面の他人と雑談らしい雑談をして過ごすというのもなかなかに難しい。教室を見渡すと数分前よりも一層姦しくなっており、徐々にクラスメイトが集まってきている様子であった。慈もいつの間にか教室に居て、既に周囲の女子たちと楽しそうに談笑している。流石は愛嬌の天才。すっかりクラスの人気者だ。そしてもう一人、見覚えのある顔があった。
「あの子は‥‥‥なっとうの子だ。」
夕霧綴理さん。彼女も同じ百合組だったとは、これまた奇遇な縁もあるものだ。低血圧なのかな、彼女は二度の欠伸を手で軽く隠しながら、周囲の席を物憂げに見渡すと人の輪にも入らず机に突っ伏してしまった。矢張り、同級生とは思えないほどの美人であることは間違いない。それでいて、クールというか、将又子供っぽいというか、兎角沙知さんとは違った意味で掴みどころがない感じで、独特の勢いを纏っているように思えた。
「‥‥‥なっとう?」
あたしの独り言を耳にした梢が首を傾げる。暫く綴理に見惚れていた百合亜は口が半開きとなっており、却ってほのかな、こみあげ笑いを誘う位の事になっている。
「うん、いや、ね……?」
気恥ずかしさから言い繕うと思案したが、とっさに言葉は見つからなかった。おのれのことを知らない人にズケズケと内情を表すのは少し恥ずかしい。いや、あたし、とりわけ納豆が好物だというわけでもないのだけれど。慌てて視線を逸らす。
「あたしはね‥‥‥納豆が、好きなんだ‥‥‥。」
梢は一瞬きょとんとした顔をしながら「うふふ。そうなのね。」と相槌を打った。その反応に少し拍子抜けする。てっきり引かれるものだと思っていた。優しい、優しいぜ梢ちゃん。
「意外だったかい?」
「いいえ。ちょっとびっくりしただけ。私はね、紅茶と湯豆腐が好きよ。」
人差し指を立ててウィンク。うふふと微笑を浮かべる彼女と百合亜の呆けた顔が対比される。めっちゃ気ぃ遣ってくれるじゃん――優しい、優しいぜ梢ちゃん。梢は耳にかかる髪を上げる。矢張りその仕草一つ一つに気品が溢れていて、どこか板についたような雰囲気を漂わせていた。あたしは気障な自分の現在の未熟が恥ずかしくて、頬が赤くなった。
「‥‥‥ごめん。独り言だよ、気にしないで!」
あたしは慌てて話題を切り替えて、彼女との会話を続けようとあたふたした。
「それでねそれでね、部活動もたくさんあるし、入学式後の勧誘がこれまたすごいって噂で聞いてさ。‥‥‥」
そうして二人の間に言葉が尽き果てた頃、今度は梢が言葉を選びながら口火を切った。ヒスイカズラの妖艶さが似合う少女へと徐に視線を戻すとその犀利な眼光に研ぎ澄まされた美しさをを感ぜられ、艶やかな口調の奥には強い意志と覚悟のような重みが木霊していた。
「――ねえ。百合亜さん。あなたはどうして、蓮ノ空女学院を選んだのかしら。やりたい部活でもあるのかしら?」
寝耳に水だった。考えたことも無かった。あたしは「蓮ノ空女学院」に在籍するという手段を、どこか当たり前のこととして飲み込んでしまっていた。なんだかんだで、大人たちはおのれの母校に誇りをもっているというではないか。詰まらない学校を出たから一生損をすると言って歎く人も時稀あるようだが、本心は果たして何だろう?学校には元来相当の考慮をして入るものと聞く。西瓜を買ったが、割って見たら赤くなかったというのとは場合が違う。とくに蓮ノ空女学院は百年の伝統を誇り、北陸でも有数の文化活動に秀でる高校ということもあってか、最初から学びたいものがあってやって来る子が多い、だからこそそれなりの偏差値の入学試験があり、一芸入試も可能な推薦制度がある。いま、梢に聞かされて初めて知った学院の事情。そんな事情を殊更に語るということは、おそらく彼女自身も蓮ノ空へ夢を携えて来たひとりなのであろう。年来思慕の学校に入学するというのであれば、これ以上ない満足感でもって今日を迎えているはず。いや、そうだ、ふつう、学校とはそういった想いを載せて決心すべきものに違いない。対するあたしは、口車に乗せられたまま、裏口入学。最悪だ。
「うーん、そうだねぇ‥‥‥。強いて言えば、憧れのセンパイが居るから、かな。」
百合亜は少し照れくさそうにしながらあははと笑い、その場を誤魔化した。
「ふふっ、素敵な理由ね。」
「そういう梢ちゃんは、どうして蓮ノ空に?」
「そうね、私は――」
刹那、ホームルームの始まりを告げる鐘が響き渡った。タイミングを見計らったように教室の引き戸が開き担任が入ってくると、生徒たちは足早に着席し始める。
「おっとごめん、また後で話そうね!」
日射しが柔かく衰えてきていた。
「――ええ、そうね。」
8
最初のホームルームが終わると、あたしたちは学院の広大な敷地に点在する各施設を横目に講堂へと向かった。講堂は教室棟からは少し離れた場所に建っており、その外観はゴシック様式の教会建築にも似ていて、新年度の幕開けに相応しい荘厳な雰囲気を放っていた。蓮ノ空女学院が創設された当初からある建物で「歴史を感じさせる重厚な造り」といえば体裁は良いが、どちらかというと古臭い文化財といった印象だ。ふかふかのカーペットが敷かれた廊下、壁面に飾られた絵画、窓に嵌め込まれているステンドグラスはその情緒をさらに掻き立てる。講堂内には三色の異なるリボンタイを付けた蓮ノ空女学院の生徒でひしめき合い、新学期特有の華やいだ雰囲気を醸し出している。天上は高い。静かなる高揚感が漂う中、上級生達が向ける視線が四方八方から突き刺さる感覚に耐えかねて思わず拳を握り締める。どこを見渡しても、女子、女子、女子。あたしは内心で嘆息した。覚悟していた状況とは謂え、これはなかなか緊張するぜ。窓から差し込む陽光は柔らかい。
式典は紋切り型で厳かな雰囲気の中で始まった。全国大会常連だという吹奏楽部による感動的な演奏の後、蓮ノ空女学院理事長が登壇する。白髪にスーツ姿の似合う穏やかで紳士的な佇まいで、北陸人らしくおちついた温厚な人柄を醸し出しているこの老人こそ、この三ヶ月間、実質的にあたしの親代わりとなってくれた人物である。澱みのない、それでいて非常に渋みのある低い声で、ありきたりな時節の挨拶を述べている。こうして公の場で姿を見るのは初めてであるから、なんだか身内特有の気恥ずかしさすらある。あたしは前の冬において、この老人に就いて感心したことが一つある。黄昏の銭湯に連れられた時、この老人は流し場の隅でひとりこそこそやっていた。観ると、そまつな日本剃刀で鬚を剃っているのだ。鏡もなしに、薄暗闇のなかで、落ちつき払ってやっているのだ。あのときだけは唸るほど感心した。何千回、何万回という経験が、この老人に鏡なしで手さぐりで顔の鬚をらくらくと剃ることを教えたのだ。こういう具合の経験の堆積には、あたしたち若者も、逆立ちしたって負けである。そう思って以後気を付けていると、植木を植え替える季節は梅雨時に限るとか、蟻を退治するのにはこうすればよいとか、この冬の間にいろいろと教えてくれて、なかなか博識であって、また、教育者としての威厳を確かに感ぜられた。あたしより五十も多く夏に逢い、五十回も多く花見をし、とにかく、五十回もその余も多くの春と夏と秋と冬とを見て来たというのだ。けれども、こと学院運営に関してはそう順風満帆にはいかないようで、「点三年、棒十年」などというやや悲壮な修業の掟は、昔の職人の無智な英雄主義にすぎない。鉄は赤く熱しているうちに打つべきである。花は満開のうちに眺むべきである。蓮ノ空では入学式が二回あり、きょうは一年生の初登校日で生徒のみの参加、明後日の休日に、父兄参観の体でより一層賑やかに執り行われる。そんな見栄張ってるから経営苦しいんだろ、一回で終らせろよ。
などと、大賀美老人を細目で睨みつけていると退屈な話は既に終わっていて、在校生代表として生徒会長の祝詞、そして新入生代表による答辞へと続く。いよいよ新入生代表が壇上に立つ――見覚えのある、紫髪のポニーテールを上品に靡かせる少女だ。
「なんと。」
梢は堂々とした態度で挨拶文を読み上げ、その凛とした佇まいに見惚れてしまう。あの独特な艶かしい声色が会場全体を心地良く包み込んでいる。それと同時に、この学校における彼女の立場の重さも感じ取れ、あたしは少しだけ身震いした。
「――なるほど、やっぱり優等生だねぃ。」
挨拶を終えた梢は在校生らの細やかな噂声に見送られながらクラスの席へと戻り、空いていたあたしの隣の席へお淑やかに腰掛けた。なんて美人な子なのかしラ、あの新入生可愛いネェ、梢サマのファンになっちゃいそうダワ‥‥‥。そんな声は彼女の耳にも勿論届いているようで、その横顔には達成感と共に脱力感、そして気恥ずかしさも見受けられた。
「お疲れ、梢ちゃん。ばっちりきまってたよ。」
小声で真心を伝える百合亜に、梢は安堵したかのように微笑みを返す。然し百合亜は茶化すようににひっと笑いながら、半分本気にさせるような口調で続ける。
「やっぱり梢ちゃん、すごいね。あたしもファンになっちゃいそう。」
「もう‥‥‥!あなたまで‥‥‥!」
梢は恥ずかしそうに顔を赤くした。両手を胸の前でぎゅっと握りしめるその仕草は年相応の少女らしく可愛らしい。
式典は、伝統校にありがちなしっとりとした校歌斉唱でもって締めくくられる。大げさな合唱ではなかったが女学生らの歌声は綺麗に揃い、水面をすべる波紋の如く講堂内に響き渡った。一時間ほどで入学式は滞りなく終わり、式典特有の重苦しさから漸く解放される。さて、退場まで座して待っていると、ふっと背中に何かが柔らかく当たるのを感じ、後ろを振り向くと、銀髪に紅色のインナーカラー。ああ、夕霧綴理さん、すっかりお休みのご様子だ。校庭で出会ったばかりの彼女、あたしに「なっとう」と「ゆり」の名を授けてくれた少女。まるで警戒心のない、気持ちよさそうな寝顔だ。あまりにも美しいその寝顔に気後れしてしまうのだろうか、付近のクラスメイト達は唯だ眺めるばかりで声をかけようとはしない。
――仕方が無い。
「夕霧さ~ん、起きて。入学式終わったから、教室帰るよ。」
「すう、すう‥‥‥。」
肩を揺らしてみるが起きてくれそうな気配はこれっぽっちも無い。どうしよう、という乞食姿の貧しい眼つきで梢に視線を向ける。
「あらあら‥‥‥。それじゃあ百合亜さん、夕霧さんをおぶってあげたらどうかしら。彼女、背が高いから、あなたが適任じゃないかしら。」
あれ、梢ちゃんってそういう突拍子もないこという性質なの!彼女は素っ気ない微笑みで、然も我が意を得たかのように返答したのであった。よもや先ほどの意趣返しではあるまいな、やってしまった、出しゃばらなければと思った時にはもう遅い。少し離れた席の慈を探し出し、アイコンタクトで助けを求める。ぷいっとされた。何故だ!諦めきれないあたしは、もう一度綴理に目を覚ましてもらうべく呼びかける。
「ねえねえ夕霧さん、赤ちゃんみたいに、おんぶなんかするのは、可笑しいから。さあ、歩いていきましょう。」
綴理の瞼がゆっくりと開いていく。独り焦る百合亜とは対照的に、綴理は至ってマイペースだった。そして二度三度瞬きして周囲を一瞥したかと思うと、眠たそうに目を擦りながら百合亜の顔を見上げて、そして特に緊張した様子もなく再び目を瞑り、それからふにゃりと言うのだ。
「‥‥‥ゆり、おんぶ。すぅ、すぅ‥‥‥。」
周囲を顧みない堂々とした態度はもはや頼もしく見えたし、羨ましくも思えた。彼女のような寝心地こそをまさしく春風駘蕩と評するのかもしれない。此方としては瑞々しい春の底冷えだというのに。ああ、くそっ、これほどあどけなく可愛らしい寝顔に物言いすることなんて!卑怯だぞ、美少女よ!
「うふふ、ご指名が入ったようね。」
「おんぶするのはあたしですからね‥‥‥!」
「そう深刻に考えないで。」
ええい、南無三!
周囲の視線を集めながら、梢に先導されながらゆっくりと教室へと帰る百合亜。彼女の鍛えられた腰つきはしっかりと綴理を支えている。その身長は百合亜と同じくらいで女子高校生にしてはしっかりとした体躯であるが、支えてる百合亜にしてみればむしろ軽い。もっと食べさせたほうが良いなと思うくらいだ。そして、ヒソヒソと噂声が聞こえる。いったい何かしラ、あらおんぶなんてしているワ、あの美人な子はダアレ‥‥‥。
あたしは綴理の柔らかな身体をしっかりと抱き寄せる。綴理はいま、あたしの背中で気持ちよさそうに眠っている。なんだろう、この状況は。耳元で彼女の吐息が聞こえる。彼女の体温を直接に感じる。いけない、イヤな汗が出てきた。落ち着けよ少女百合亜、心頭滅却せよ!心臓の鼓動が高まるのを抑えるかのように、あたしは思考を巡らす‥‥‥これだ――太初に言あり。言は神と偕にあり。言は神なりき。この言は太初に神とともに在り。万の物これに由りて成り、成りたる物に一つとして之によらで成りたるはなし――。
「むにゃ、むにゃ‥‥‥。」
綴理はあたしの肩に顔を擦りつけてきた。一瞥しようと頭を動かすと、彼女の柔らかな髪がくすぐったく鼻に触れる。往来の真ん中で動悸が早鐘を打ち始める。脚が竦んだ気がして、心臓がドキンドキン音を立て立て鳴り出し、いまにも破裂しそうだ。その恐ろしさを紛らすために自戒を続ける‥‥‥之に生命あり。この生命は人の光なりき。光は暗黒に照る。而して暗黒は之を悟らざりき、云々。
――そろそろ起きてほしいところだ。
夕霧さんは普段からあまり感情を出さないような印象があるが、どうなのだろうか。それとも、感情表現が苦手なだけなのだろうか。僅かな時間しか関わりをもっていないが、蓋しそういう点はおのれと一脈相通ずる所があるように感ぜられて、あたしはひそかに彼女に親しみを感じ、自分の蓮ノ空での親愛すべき学友の一人が早くも此処に現れたような気がしていた。あたしが将来若し真相を誰かに語ることがあるとすれば、誰よりも先に彼女に認めてもらいたいと思い、或いはそういう日が来るであろうかと、夢のような空想に耽ってしまう。
「じーーーーー。」
そんな百合亜の動悸と内情を嘲笑うが如く、慈が距離を保ったまま睨みつけてくる。こういう時こそ助け舟出してくれよめぐちゃん‥‥‥!梢は談笑しながらうふふと笑うばかりだ。成るべく肩の凝らないような、そして一般の女子高生らしい適度な情熱を帯びた日常を送ろうとしていたのだが――肩に重みが圧し掛かっている。人の感情は、難解で、苦手だ。
蒼穹を見上げればすっと抜けるような天が一面に広がり、太陽も明るい微笑みを降らせていた。桜並木の花々は所狭しと咲き乱れ、その色鮮やかな花弁たちはまるであたしたちを迎え入れるかのようにひらひらと舞い散っている。新しい日常の始まりにはお誂え向きな舞台装置だ。それでもいまの眼にはその日差しがキラキラ眩しく反射して痛く、一層暑い感じがした。
9
学院を包み込んでいた入学式特有の高揚感は次第に更けていった。あたしたち百合組は再び教室へ戻ると、若い担任教師に連れられて学院の敷地を案内された。石畳を踏みしめながら教室棟を通り抜けると緑の芝生で彩られた庭園とよく手入れのされた花壇が目に入る。その他にも図書館や食堂、グラウンドにテニスコート、学生寮に部活棟などなど。それでも全て案内しきれたわけではない。いやぁ新入生の学友諸君、あの長閑な蓮の湖を知っているのは未だあたしだけかね!そして昼過ぎには解散となり、むしろここからが今日の本番、各部活動の新入生勧誘が始まる。既に校内の至る所から楽器の演奏や合唱などさまざまな音が聞こえて来る。ゆったりとした楽しげでワクワクとした心地を演出しており、その空気は新入生にも伝染し学院全体に和やかな雰囲気が漂っているように感ぜられた。
斯く謂うあたしは一階の大食堂に来ている。ここも入学式の厳かな雰囲気はどこへ去ったものか、腹を空かせた新入生と在校生が入り乱れてごった返している状態だ。対面する慈から明らかに含みのあるジト目で睨みつけられる。
「あんな美人な子と密着出来て。良かったね、百合亜ちゃん☆」
「よせやい、茶化すな茶化すな。死ぬほど恥ずかしかったんだぜ、こっちは。それにあたしはさ、目立ちたくないんだよ。」
「ふーーーーーーーーん。」
頬杖をつく慈の視線が百合亜に突き刺さる。こういう時のめぐちゃんは何を言っても見透かされている気がして堪らない。ほんとうはもっと話したいことがあったけれど――いまではこうして馬鹿みたいにじゃれ合う時間も貴重だと感ぜられ続く一言が喉奥に詰まってしまう。久し振りの学友との昼食時間をここに浪費するのも良いものだ。
「あれっ、この金沢カレー結構旨いな。どちらかというとアルバっぽい。」
「ふーーーーーーーーん。」
それでも慈のジト目攻撃が止まらない。キャベツに追いソースとマヨネーズをかける百合亜。しばらくスプーンを進めたものの、あたしは遂に居心地が悪くなり、観念して突っ伏してしまう。きょうの昼食、金沢カレー550円也。ごちそうさまでした。慈に対して気取ってみたって、淋しさが残るばかりだ。満腹感は、冷静さと、それから、言い訳を教えてくれる。無抵抗主義の成果、見るべし、である。
「‥‥‥ごめんごめん、めぐちゃん。あたしが悪かった。ちょっと浮かれすぎてました。以後気を付けます。」
「‥‥‥別に、謝ってほしいとは一言も言ってないけど。」
慈は少し拗ねたような口調で呟いた。百合亜はそんな慈の態度に苦笑しつつ、彼女と過ごした日々をどこか噛み締めるようにゆっくりと見つめ返した。どんな記憶にもそれ相応の特色がある。良い想い出、悪い想い出のうちにも一つ一つ違いがある。折から白い花を咲かせているスノーフレークにも毒があって、長らく見つめていると執念深い烈しい薫りが漲み出てくる感じさえする。脳神経がこれを言語化しようと迎えていて、正か負か、遑てていよいよ緊張する。百合亜はそういった情景の一頁を恰も幼馴染が齎らして来たもののように懐かしんでいるのである。そんな、取り替え難い、愛しい女の子との想い出と、更にはいまこの瞬間を独り占めしていると思うと、多幸福というか、優越感を覚えてしまう自分がいる。幼馴染の、特権。あたしにしか見せてくれないような、むすっとしたところのある素の表情も、やっぱりめぐちゃんだ。
――そうだといいな。
おかわりの水を汲んできた百合亜は話題を替えて慈に問いかける。
「――それで、午後からなんだけど。めぐちゃんはこれからどうするつもり?」
「ん-、特に予定はないかな。でも早く寮に入って部屋の整理したい気もするから、軽く部活動紹介だけ見て帰るつもり。」
何気ない返事の中の、ふとした耳にかかる髪を上げる所作に見惚れてしまう。長い睫毛、形の良い鼻、柔らかそうな唇。やっぱり美人だなあ、なんて今更ながらに思う。勿論彼女の魅力は外見だけのはずがない、内面の良さもここで筆硯に託すには憚られるほどたくさんあるが――。
百合亜はこの時間を心地良く思う気持ちを確かに感じつつ、おのれに不釣合いな幸福を畏れる気持ちを呑み込んだ。兎角あたしは、めぐちゃんのそういった「女の子らしさ」を見習わなければならないのだ。天性の愛嬌で誰とでも仲良くなれる彼女は、その果てしない美貌や射干玉に艶めく髪のみならず、マシュマロのような柔らかな肌や整えられた桃色の爪、潤いのある赤い唇など、彼女を構成する一つ一つのパーツは他者から見られていることを意識して、入念に磨き上げられている。同時に彼女は、自身を構成するパーツの魅力を余すところなく引き出す術にも精通している。早速今晩、弟子入りのお願いをしないとだ。
ここで百合亜は心意を素直に伝えたい気持ちに駆られ、努めて大袈裟に感情を込めながら、懇願するかのように言葉を捻りだした。
「――それじゃあさ、一緒に観に行こうよ!スクールアイドルのステージをさ!」
慈は唐突な百合亜の言葉にきょとんとしたまま首を傾げる。
「スクールアイドル?なにそれ?」
「――スクールアイドルは、不完全でも熱を持ったみんなで作る芸術。」
百合亜は沙知から聞かされた言葉を咄嗟に、そのままに慈へ伝える。でも、ここから先はおのれ自身の言葉が続く。
「――スクールアイドルのステージを始めて観た時ね、すっごくキラキラしててさ、あたしも頑張らなくっちゃって、勇気を貰えたんだ。いまのあたしはさ、そんなスクールアイドルが大好きで、近くで応援したいんだ!だからめぐちゃんも!」
それでも慈の相槌があからさまな作り笑いだったので、少しでも興味をもってもらおうと百合亜の説明にもくどくどと熱が入る。「面白いの?」と言えば「面白いよ!」と言うだけで手を叩いて愉快がったり跳び上って喜んだりするようなことはなかったが、賢い犬が遠い物音を聞き澄ましているように、黙って、悧巧そうな眼をパッチリ開いて話す饒舌な顔つきは、余程その〈スクールアイドル〉に思い入れがあると察せられたに違いない。慈もふわりとした微笑で何度か頷いていたものの、然しそれが恰も聞かされているといった具合なのは百合亜も勘付いたようだ。どちらかと謂えばそのまま怪訝そうな表情を浮かべていた――スクールアイドルなんて、ただの暇つぶしでしょ、本気になれるわけないじゃん、と瞳の奥では冷めた眼で訴えかけてくるのが伝わる。いや、でも、伝えたいことはぜんぶ伝えた気がした!無理強いするのはオタクの無作法だし、めぐちゃんは耳を傾けて聞いてくれた。「推し」の布教ができて心地良い。
スクールアイドルについて語る百合亜の表情はとても楽しげで、口火を切った途端そのどこか虚ろな瞳には情熱が宿り、眼差しはどこか遠くを見据えているようにも思えた。慈はスクールアイドルそのものよりむしろ、いったい何が彼女を熱中させたのかという一点に深い関心を抱いた。何秒かの沈黙の後、慈が言葉を選びながら口を開く。
「――そ。考えとく。」
10
めぐちゃんと一旦別れたあたしは勇んでライブ会場へと向かった。会場となる音楽堂ではスクールアイドルクラブのほかにも幾らかの部活動がライブパフォーマンスを行っている様子で、その余熱が会場の外からでも容易に確かめられる。ええと次は‥‥吹奏楽部か。気付くと屋外を行く散歩者の姿もめっきり疎となり、音楽堂の中では昂奮した女学生たちの黄色い歓声がだんだん高くなっている。時計は午後三時半頃、あたしも箱詰めの音楽堂へと足を踏み入れる。その途端に素破こそというので、客席から割れるような拍手が起った。客席側の灯がやや暗くなり、それと代って天井から強烈なスポットライトが美しい円錐を描きながらステージへ降って来る。
「うわーッ、ユキセンパイだワ!」
「我らの蓮ノ空吹奏楽部に声援を!」
「うわーッ!」
その色めいた声に迎えられて、一様に揃った制服姿で吹奏楽部の面々が明るいスポットライトの中へ飛びこむようにして現われた。部長らしき女学生が指揮棒を構えると客席はすっかり静まりかえって、鈴を転がすような滑らかな演奏だけが、音楽堂の高い天井を揺すった。
「‥‥‥。」
百合亜はなんとなく心細く、息苦しい気分になり中座してしまった。
音楽、というものはとても難しい。いまの吹奏楽部の演奏だって綺麗に揃っていて美しいものに相違ないとは思う。勿論あたし如きがその深淵さを評するべきものではない。或いは――ロマン主義時代の哀愁の詩人ミュッセが小曲の中に謳った趣意を記憶から引き上げてみると、青春の希望元気と共に銷磨し尽した時、この憂悶を慰撫するもの音楽と美姫との外はない。かつて若き日に一たび聴いたことのある幽婉なる歌曲に重ねて耳を傾ける時ほど嬉しいものはない、という。
あたしはこの三ヶ月間、沙知さんからスクールアイドルのイロハをさまざまに叩きこまれた。そして銀幕の上に彼女を間近に眺めるのは二度目である。先代のスクールアイドルクラブの先輩方とともに四人で立った、あの眩い煌めきの、学園祭での最後のステージ以来だ。忘れもしない、限界のその突き当たりが、生命の歓声が充ちるまで、我あればこそ、電燭のさながら水晶宮の如く輝いた劇場。ああ、一翳の雲もないのに、緑紫紅白の旗の影が、ぱっと空を覆うまで、花やかに目に飜った、と見ると颯と近づいて、眉に近い樹々の枝に色鳥の種々の影に映ったかの如くのスポットライト。蓋し劇場に向って、高く翳した手とマイクの、夢の矜の幻影――あの情景を想い出すだけでも武者震いがするわい。然し今日は沙知さんのワンマンライブ――いや、あたしが心配する了見ではないだろう。あたしの大好きなスクールアイドルなら、きっと、最高のパフォーマンスを見せてくれるに違いないから。
「――スクールアイドルは、不完全でも熱を持ったみんなで作る芸術。」
沙知さんのその表現は正鵠を射ていると思う。あたしがスクールアイドル達の活躍を、殆ど毎夜聴くことを楽しみと為したのは、十五年来青春の笈を負うて駆け回った往時のこと、そしてこれから将来の青春の希望とが歴々として着想されるが故である。思うに、全ての革新運動と同様に、音楽や芸術の革新運動もまた、精神と形式とが常に相伴うものとは限らない。とりわけ、そうした潮流の中で発出した異端児とも謂える〈スクールアイドル〉という分野に於いては、その精神と称するものが往々にして観念の遊びに過ぎなかったり、または単なる感覚のニュアンスに留まったり、また一概に形式と言っても、技法の末に拘ることや衣裳の新奇を衒うことに尽きる場合、これは本質的に云えば〈音楽〉〈芸術〉の名に値しないと断ずる者もあるかもしれない。然しそれは、スクールアイドルの本質を取り違えている。スクールアイドルとは、あたしたちみたいな普通の女の子が部活動としてアイドル活動をし、自分たちで曲を衣装を舞台を作りステージの上で歌に想いを乗せて届ける。凡そ一つの芸術作品が、芸術としての存在を主張し得る為に、創造者の霊感が、直接、そして純粋に、美の表現に到達していなければならないとすれば、そこには、平俗なる感情との妥協や、偶然が齎らす効果の期待などがあってはならない。即ちスクールアイドルはその性質上、そういう不純な、間接的な、動機に束縛され、左右され易いが、それこそが青春の無窮さであり、結果としてあたしたち観客全てをも輝かせるのだ。ミュッセの詩に謳われた如く、スクールアイドルはあたしにとって「かつて聴き覚えのある甘く優しき歌」なのだ。あたしはその情景に立ち会う度に無量の感慨に打たれざるを得ない。
斯くの如くしどろもどろな述懐を反芻していると、音楽堂の喧騒は既に静まっていた。愈々スクールアイドルクラブの出番が近づいてきていたとわかり、あたしは足早に音楽堂へと踵を返した。よし、と百合亜は自分の両頬を軽く叩いて気合いを入れ直し、緊張の面持ちで音楽堂へと再び足を踏み入れる。吹奏楽部による演奏の余韻と次番の出場者への期待が昂る独特の雰囲気が漂う空間で、まず視界に入ってきたのは親しみ慣れた愛くるしい人影――。
「めぐちゃん!来てくれたんだ!」
「――まあ、ね。暇だっただけだよ。」
予感は確信へと変わった。きっとめぐちゃんなら来てくれると、そう思っていた。慈は照れ隠しの素振りで指先でくるくると髪の毛を弄びながら言う。彼女の返事は例の如く素っ気無かったが、その声色とは裏腹に期待に揺れる感情が瞳の中で垣間見えたような気がした。更に会場を見渡すと別の知った人影がふたつ――梢ちゃんと夕霧さんだ。なあんだ、流石沙知さん、やっぱり杞憂だ、今年度もスクールアイドルクラブは大人気じゃないか。百合亜は思わず安堵の笑みを零した。そして――。
「いぇ~い、みんな~!そして、新入生諸君!盛り上がってるか~~い!!」
蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブの登場だ。沙知が、アイドル然としたピンク色のワンピースを基調としたステージ衣装で舞台上に現れ、百合亜は瞬く間にその光景に釘付けとなる。うわぁ、めちゃくちゃかわいい!いぇぇぇーい、と、百合亜は閾下に裂帛の気合で叫んでしまったが、その声も吹きとばされ闇に消えていった。周囲の観客たちも一斉に手を上げながら甲高い歓声をあげていて、音楽堂内の視線は沙知へと集中していく。
「きょうは、新入生歓迎会の特別なステージだ。このライブを観て、あたしと一緒にスクールアイドルをやりたいって子がひとりでもいてくれるなら、嬉しい。」
哀愁を秘めた発言の中にあってそれでも沙知は朗らかな表情を変えなかった。百合亜の瞼が震えた。固唾を呑み込み、ぎゅっと両手を握り締め、やがて、その大きな瞳を見開くと、視線を再びステージへと向ける。沙知は堂々とした佇まいで、独りレビューに挑む。
「それでは、聴いてください。蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブで――」
ぎゅっとマイクを握り締める。
「――『Dream Believers』。」
11
♪「一緒に見たいんだ 消えない 夢〈ドリーム〉I believe!」
刹那、あたしの視界一面が沙知さんを中心にキラキラと明滅しまるで別世界に迷い込んだかのような感覚に誘われる。百合亜の脳裏に浮かぶ場面は、色彩溢れる花びらが優しく吹き乱れる平原の情景――あらゆる種類の春の花を受胎に誘う微風は、花から花へ渡っていた。泡沫の幻影に思わず息を呑む。微風に舞う彼女の華やかさはまるで虹を天から持って来たかのよう。沙知が靡かせる羽風に春陽が揺れ、舞台上の陰影が延び縮みする。そうして旋律が聞こえる。スクールアイドルの想いが百合亜の魂を揺さぶり、一つの魂に一つの物語が生れ、一つの音楽は多くの心に新たな煌めきを灯す。それは一つの世界の始まりに思えた。
♪「胸に舞いおりた 小さなヒカリをもっと 追いかけてみたい…もっと!」
彼女たちは遥かの地底、平原の向こう、波濤の彼方から聞こえてくる、沙知の楽しげな叫びを耳にした。沙知の指先が軽やかに躍る。
歌声、ダンス、照明、音楽、演出、尚附け加えれば香――これらの要素が単に感覚のみに訴える美感から如何なる形式の芸術が生れるか。これは観客の想像に任せるより外はない。試みに、これ等の要素を結合排列して、或る「場面」が創られるとしよう。それは自然現象の成るものを聯想させる光景でなければ、立体派の絵画、未来派の音楽、ダダイストの詩を想わせるだけの一種の舞台表現にしか値しない。而もそれが心理的に何等の情緒を誘起するものであってはならないとすると、その印象の範囲は極めて局限されることになるが――。
♪「これは 新しい日々の始まりなんだ 知らない世界へ 思いっきり飛ぶよ」
沙知の身体いっぱいに生み出された音楽は、まるで魔法のように会場を包み込んでいく。手足がしなやかに艶めかしく動く。軽やかに弾む身体はいつまでも揺籃の中に居る様な感覚をあたしに与えた。スクールアイドルのステージは百合亜をどんどんと深い処に誘っていた。
――スクールアイドルのステージはこれらの感覚的要素を以て、或る心理的効果、例えば喜悦、恐怖、悲哀等の感じから進んで、尚一層複雑な印象を与えようとする。一般的な演劇等であれば、どの程度までそれが成功するか、殊にどの程度まで、それが芸術的であり得るかが疑問となるだろう。単に雷と風の音を出し、電光を見せ、雲らしき色と形を示して「嵐」と題をつけても、それは〈見せ物〉以上の何ものでもないような気がしてしまうからだ。恐怖とか凄愴とかいう印象は与え得ても、それがどこまで芸術的感銘を伴うかは別問題であり、若しそれならば、まだしも、単に感覚的美感に止めて置いた方が意味深長であるとさえも推察し得る。然しながら、スクールアイドル達の眩い煌めきの本質はそこではない――。
♪「Sky, my sky ミライの太陽へ手を伸ばそう Sky, my sky 輝きたい気持ちで 僕らの夢」
――そこで〈芸術的要素のみによる舞台〉から〈少女達の青春喜劇〉に遷る。現実的・心理的要素を加味するということは、即ち舞台に〈情熱〉を核心要素として与えることになる。青春は人生の花だと謂うが、また一面、焦燥、孤独の地獄である。どうしていいか、わからないものである。そう、実際に、苦しいに違いないから。然しそれに〈身振り〉や〈歌声〉が加わって複雑味を増し、〈主題〉が〈筋〉扨ては〈物語〉に発展して益々完全な心理的要素となり煌めきを纏う。
演者の体温で空気を暖めて、その熱を観客に潜ませる。ゆらりゆらりと揺れているのは此方も同じだつた。あたしの頬も染まっていて、思考回路が柔らかくなってしまっている有様。舞台で踊る沙知には百合亜に気付いている筈もないのに、確かに目が合った気がしてどきりとする。十人十色の笑顔が咲き乱れた観客席へはスクールアイドルの情熱が伝播し心を掴んで離さない。それはまるで、湖に浮かぶ蓮の葉の上にいるような、沙知の歌声が高らかに響くと共に、彼女の若い生命と漂渺たる想いが心の奥底へと響いてくる。スクールアイドルとは何か、夢を望み、挑み、叶えるとは一体どういうことなのかをキミに教えよう!夢見る少女達は止まらない。
♪「強くなる 強くなる 願いを叶えながら進もう――」
そして、そう、この煌めきこそが‥‥‥!!
世界の時間が止まったような、感覚。
「スクールアイドル!!!」
「スクールアイドル‥‥‥。」
「スクールアイドル‥‥‥!」
「スクール、アイドル‥‥‥。」
騎士星花を約束に翳した少女のどこか虚ろな目に確かな炎が宿る。
鈴蘭水仙に奏でられた少女は愛嬌の帯びた声色の中に確かな決意を光らせる。
翡翠葛に魅せられた少女は情熱的な夢を忘れずに胸に刻み直す。
寒緋桃をも虜にしてしまう少女はどこか寂しげにその夢を呟く。
姫彼岸花を舞台に咲かせる少女は、過去、現在、そして未来の少女たちの想いを受け止めてその手を伸ばす。いつかまた会う日を夢見て――。
♪「――行こうよ! なんだってやっちゃえば楽しい いまを頑張ることが楽しい デコボコの道だって 大丈夫さ」
沙知が眩いライティングの下で手を高く差し上げるとぱっと鮮やかな光線が立ち上り、その情熱的なパフォーマンスは観る者全てを魅了する。彼女はステージの上で、その小さな躰を目いっぱい使って踊った。そういう風に作られた絡繰り仕掛けの人形が、命を吹き込まれて動き出したかのような躍動感が、確かな生命をもって物語を刻んでいた。あたしの胸にはこんな感じがぶら下って、始終お祭り騒ぎを起す様な熱度で全身を揺り動かされていた。
♪「行こうよ! なんだってやっちゃうと決めて いまを抱きしめたら」
廻転する光の色が踊りにつれて変化する。沙知は誰よりも眩く、輝いていた。あたしはぼんやりしていた。だんだんと熱を帯びて色々の灯で彩られていくステージの沙知の様子に唯だ唯だ見惚れていたのである。
――美学者は例の定義癖から「スクールアイドルの芸術性とは如何なるものか」という問題を解決しようと努める。蓋し我われが実際知ろうと思うのは、知る必要があるのは「スクールアイドルの少女達が秘める煌めきとは如何なるものか」ではないだろうか。絵画とは如何なるものか、彫刻とは、音楽とは‥‥‥小説とは、詩とは‥‥‥こういう問題に答えることが、さほど重要だろうか。同様にして戯曲とは‥‥‥これまた十分とは行かなくでも、正当な答案は少し芸学の道に頭を突っ込んだものから求め得る。或いは音楽というものを全く習ったこともなく、その才能も全然持ち合せていない者が、なんでもいい、クラシックなり、ジャズなりの〈音楽らしきもの〉を聴き、これは〈音楽〉だと言う。誰がそれを「音楽ではない」と断言できるだろうか。それと同様に、スクールアイドルの存在証明も千差万別であって「これはスクールアイドルだ」と謂って示された一篇の〈作品〉を見て、「これは芸術ではない」と評することなど神仏でさえ到底あり得ず、単なる伝統的な形式以外の、なんら審美的法則を必要としない。
♪「夢をえがいて ときめきながら繋がろう」
沙知の歌声とあたしの鼓動は共振し音楽に溶けていく。情熱が形になり、声になり、動作になる。これは成る程、芸術の分野では一定の共通性を見出せる美しさではあるが、その印象は美の本質に於いて異なった類であるとここに実感する。スクールアイドルは決して芸術の観点のみによる表現が目的ではない。彼女達が実際に経験してきた青春の情熱そのものによって声、形又は動作を暗示する、全く新奇なる芸術の一形式であると謂って差支えないと思う。それはスクールアイドルが奏でる旋律が、戯曲の言葉或いは小説又は詩の言葉に対して、一種特別な内容を要求する所以なのだ。
♪「――Dream Believers I believe!」
――スクールアイドルもまた、数多の芸術や音楽と同じく、或いはそれ以上に、こうした現実の認識から、即ち少女たちの声に間近に接するところから出発するに新しい発展の道が開かれるのだとあたしは熟思う。スクールアイドルを愛すると謂う。その愛し方には、さまざまな程度と質とがあるのだ。これこそが、スクールアイドルのライブなのである。
観る者全てを魅了した音楽が止むと、劇場全体を未知の静寂が占領した。そして刹那、観客席からは音楽堂全体が揺れ動くほどの歓呼の声が上がった。その夕刻、蓮ノ空女学院音楽堂の観客は、かつて彼女らを有頂天にした如何なる大レビューにもまして、華やかに、物狂わしく、躍動的な、前代未聞のスクールアイドルの煌めきを、手に汗を握り、胸おどらせながら、嵐のごとき激情をもって見物したのであった。客席からの拍手が鳴り止んだ頃には既に百合亜の頬は濡れていた。彼女の中にあった靄が熱を浴びて忽ち気化して行く。百合亜の心臓はまだどきどきと早鐘を打ったまま、ワーッと叫んで、全力で駆け出したい昂奮で一杯になりながら、最後の最後まで沙知のステージから目が離せずに立ち尽くしていた。
「今日は蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブのライブを観に来てくれて、ほんとうに、ありがとうございました!!」
夢のような時間はあっという間に過ぎ去り、ライブはもう閉幕の時間を迎えていた。沙知の締め括りの挨拶と共に観客たちは再度一斉に彼女に向かって歓声をあげた。それと同時に万雷の拍手が起こり始めると、卒業式で目撃した、唯だ形式的な手拍とは全く趣意の異なる、熱狂的な、音の嵐。人間らしい感銘の音楽は劇場を割れんばかりの勢いだった。
感想なんて!筆舌に尽くせないとは恰もこの瞬間だ。まるい卵も切り様一つで立派な四角形になるじゃないか。伏目がちの、おちょぼ口を装うこともできるし、たったいま高天原からやって来た貴種そのままの素朴さの真似もできるのだ。断じて、否、それは上手だったとか感動したとか、やたら女学生くさいリリシズムで評すべきものでもない。あたしにとって、ただ一つ確実なるものは、おのれ自身の肉体である。こうして立ち尽くしている間に、十指を観る。うごく。右手の人差指。うごく。左の小指。これも、うごく。これを、しばらく、見つめて居ると、「ああ、あたしは、ほんとうだ。」と思う。他はみな、なんでも一切、千々に千切れ飛ぶ雲の思いで、生きて居るのか死んで居るのか、それさえ分明しないのだ。よくも、よくも!感想だなぞと。恍恍惚惚からこの状態を眺めている此方の少女ひとり在りて曰く「たいへん簡単である。生の実感。これ一つである。」と。ああ、これか、これがスクールアイドルなんだなあと、あたしはきょう改めて思った。後はなにがなんだか、破れかえる騒ぎで、実に空前の大喝采、空前の昂奮だった。
草原の虹の色は次第に薄れて見えなくなっていった。百合亜はここで漸くはっとし、ずっと隣に居て一緒にステージを観てくれた幼馴染へ、昂奮のまま声をかけた。
「めぐちゃん!ほんとうにすごかったね!スクールアイドルのステージ!わーって盛り上がって、うおーって感じになって、キラキラ―って輝いて!それがなんかもうメッチャ眩しくて!やっぱりすごーい!って、思った!」
彼女は両手をぶんぶんさせながら、その頰には朱色が差していて、やっと満足したように、息を凝らして慈の方を視つめる。その声へ、慈は夢から醒めたように応えた。
「――そうね。まあ、良かったんじゃない。」
また淡白な返事であったが、彼女の睫毛の微かな震えと、目縁の皮膚と頬の紅みを百合亜は見逃さなかった。艶のある唇は固く結ばれているように見えた。あたしは喜んでいた。それは一つには慈に自分の本心を明かせると謂う幸福感があった事も原因だったけれど、もう一つには、スクールアイドルの魅力が学院の皆に理解して貰えなかったらというもどかしさを烏有に帰したと断じて構わない、確かな昂奮でもあった。あたしの胸の内ではいままで思いも附け無かった、大義の為とかそんな仰々しいものではない、純粋に、大胆で、空想的な時めきが騒いでいた。
「ねえ、めぐちゃんもやってみない?スクールアイドル!」
「――え?」
慈はサッと顔色を変えた。百合亜の突っ込んだ語気が鋭さを帯びていたのと、不意を打たれた為だろう。呆気に取られた慈は暫くの間立て板に水となった百合亜の声を聞き流すようにして、その切れ切れの言葉に耳を傾けていたが、次第に彼女自身にも昂奮の色が濃くなり、然し矢張り唯だ声も出せずに黙って幼馴染の熱弁を聞き入り、僅かに頰をぼうっと紅らめる体であった。
「めぐちゃんならピッタリだと思う!ぜったいに世界中を夢中にできる!」
さも嬉しそうに叫んだものだ。百合亜はあの頃と同じ、真剣で、無垢で、情熱的な瞳で慈を覗き込んでくる。そんな彼女の澄み切った眼差しに射竦められて、慈は思わずたじろいだ。
「――そんなこと、急に言われても。だいいち私はアイドルじゃなくてタレントだし、スクールアイドルだって、きょう初めて知ったんだから。たぶん柄じゃないよ。」
慈は百合亜の昂奮を宥める様に含みを持った笑みを返したが、
「ううん、ぜったいそんなことない!めぐちゃんならできるよ!一緒にはじめようよ、スクールアイドル活動!あたしたちで!」
百合亜は慈へと期待の手を差し出し、そうしてまた無邪気に突拍子もない口説き文句を恥ずかしげもなく言い放つものだから、今度は慈の方が気まずくなった。百合亜の双眸には依然として慈への真摯な熱意が宿っている。慈は昔からこの眼差しに弱かったのだ。そんな百合亜の幼気な期待に応えるべく、精一杯の照れ隠しの微笑みを返しながらそっと手を差し出しす。百合亜は、ぐっとその手を握り返してきた。少し温かくてごつごつした掌。百合亜の手に触れた瞬間、彼女は自身の心音が一瞬跳ね上がったのが分かったが、それを悟られないように平静を装って歩みを進めることにした。
百合亜はそんな慈の心を見透かすわけでもなく、例の如くにかっと元気よく笑った。
「ありがとう、めぐちゃん‥‥‥!うれしい!!それじゃあ、待ってるから――!」
「あっ、ちょっと‥‥‥!」
百合亜は幼馴染を残して子供のように駆け出し、会場に充満する濛々たる余韻と、騒々しい人声の中をうろつきながら、きょう知り合ったばかりのクラスメイトふたりを取っ掴まえては気焔を挙げた。
「梢ちゃん!スクールアイドルのステージめちゃくちゃ良かったね!‥‥‥」
「夕霧ちゃん!一緒にスクールアイドルクラブの見学行こうよ!‥‥‥」
などとたたらを踏みそうな昂奮のまま言葉を捲し立てる百合亜へ、梢は困惑と動顛の表情を、綴理は羨望と怪訝の表情を浮かべ、慈をその光景を慌てて遠くから見咎めていた。その日の百合亜の有頂天に、衰えの気配が見えなかった。
12
月曜日、放課後。東から弱い風がそよそよ吹いている。部室に暖い小春日の光が溢れていた。ここだけ早枯れした花壇の一角に、名前の知らない花のなかにもう小さくしか咲けなくなった花が一輪だけ、茶色に縮れた枝葉のあいだから、あざやかに白い葩をつつましく覗かせていた。
「――こほん。それでは、諸君!きょうは来てくれてほんとうにありがとう!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブへようこそ!あたしは大賀美沙知、スクールアイドルクラブ部長の二年生だ。これからよろしく!」
件の一〇二期生四人をそれぞれ見据えて、部長・沙知は胸を張り溌剌な声を高らかに発した。大仰な身振りで立つ彼女の背後のホワイトボードには大きく「ようこそ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブへ!」と書かれているのが微笑ましい。けれど百合亜は「おー。」と気力が抜け落ちたような生返事が出るだけで、勢いに嘆息してしまいたいほどの緊張を感じ取っていた。綴理はぼんやりと虚空を追いかけている。慈は顎に手を当ててぼんやり俯いている。梢はそんな同級生ふたりを品定めするかの如く睨んでいる。更にはそれを沙知が「なるほど‥‥‥なるほど?」と腕組みながら訝しみ始めたのが居た堪れなかった。尚ぐずぐずしているのも本意ではなかった故、あたしは〈百合亜〉としての意義を果たすべく意気揚々と口火を切った。
「あたし、大賀美百合亜!改めてよろしく~!」
木製の椅子をがたっと引き摺りながら元気いっぱいに名乗りを上げた百合亜は、ニコやかに揉み手をしながら、五尺七寸ばかりの体躯をちょっと屈めて、あるいは身振り手振り品を変える賑やかな表情で自己紹介をはじめた。これでも彼女は、沙知との関係、スクールアイドルクラブへの想い、皆で仲良くわいわいしていきたい趣意、等々を端的に伝えようと試みたのである。
「――そうだね、えーっと、とりあえず自己紹介してもらおうかな。初めてだし。じゃあ‥‥‥乙宗ちゃんから。」
自己紹介タイムで場を和ませようというあたしの意図はどうやら沙知さんに伝わったようだ。そして沙知の促しに一拍置いてから、梢は礼儀正しくお辞儀をしてそのたおやかな唇を開いた。
「はじめまして。乙宗梢と申します。目標は――ラブライブ!優勝です。」
「「「「おー。」」」」
ぐっと情熱的に右手を握り締めた彼女なりの決意表明に反して、部室には再び疎らな拍手が虚しく響いたのだった。更にここで、百合亜の奮闘を無情の一突きで折ったのは綴理だった。
「‥‥‥ラブライブ!ってなに?」
百合亜は視線を梢と綴理の間で行来させ、最後には綴理へと流すように流し目をくれてみたが、結局その明眸皓歯からは何一つ読み取れず、加えてその純粋な瞳には悪意などさらさら無い、ひどく鷹揚な態度であった。衝撃の光景を目の当たりにしたあたしは、むしろ全身から一気に力が抜けていくのを感じた。夕霧ちゃん、大胆不敵だぜ‥‥‥!数秒間の沈黙の後、梢は大きく息を吸って口を開いた。
「なんですって?夕霧さん――」
急に声のトーンが下がった梢は、すっかり取乱した様子で詰っていた。あたしは取り繕う暇もなく今度は一気に身体をぴんと張りつめ、憮然としてふたりを眺めて閉口する外なかった。こええよ女子。逆に、何処までも謹恪で細心に思われる梢の性格が、あまりに痛々しく綴理の前に曝け出されようとするのが剣呑にも気の毒にも思われた。梢は一度ぴょんと子供っぽく活き込んで、
「あなたね夕霧さん、そんなことも知らずにこの名門に――」
と、口を尖らせながら不満を顕わにしようとした。その声はどこか上擦っていて、更に震えたり詰まったりと不安定に揺れ動いている。教室だったらぜったいに見せなかった表情だ。然し目を剥いた梢が説教するより先に沙知が遮った。
「わー、待った待った!はい、じゃあそんな夕霧ちゃん次よろしく!」
「?よろしく~。‥‥‥?」
気怠げに手を上げて会釈する綴理。一瞬訪れた沈黙の後、百合亜は安物のマリオネットの如くぎこちない動作で隣に座る彼女に向き直った。泰然として綴理は梢のジト目を受けてもずっと何処吹く風といったところで、大袈裟に首を傾げるばかりの、甚だ不明瞭な声明で自己紹介が終わってしまったのである。彼女の無垢な挨拶を聞き終えた沙知はがくりと肩を落として項垂れるわけでもなく、一呼吸置いてから言葉を選んだ。その声音には微かばかりの哀愁を孕んでいた気がした。
「‥‥‥OK、じゃあ最後、藤島ちゃん。」
「はーい、藤島ちゃんでーす。呼ばれたので来ましたー。スクールアイドルってあんまり良くわかんないんですけどー、まぁ暇つぶしならやってもいいかなーって。まあ、私のネームバリューは使えると思いまーす☆ あ、私の邪魔をしないならなんでもいいでーす!」
氷の塊を背中に押し当てられ身を竦める幼馴染を横目に、慈はメンバーの悶着など歯牙にもかけず朗らかな声を投げかけた。愛嬌たっぷりの仕草を添えて、最後にウインクピース。梢の鋭い視線と綴理の無頓着な視線を浴びながら、めぐちゃんは然も悪戯っぽく笑って自己紹介を終えてしまった。いや、その表現は適切ではない、彼女はいつも紹介の限度を飛び越して、自分褒め、自惚れになってしまうのだった。流石はあたしの幼馴染、さすめぐだ‥‥‥!いや、この前の感動はどこ行ったんだよ!肩まで届く長い髪がふわりと彼女の輪郭を覆うようにして流れる。然し梢はそんな慈の態度にもすかさず嚙み付いて、霊峰から吹き下ろす寒風のような、静謐な声が空気を切った。
「藤島さん‥‥‥どうやらあなたにも、スクールアイドルのなんたるかというものを教えなければならないようね。」
「え、なに?乙宗さんってばそーゆー感じ?沙知先輩、止めてあげてください☆」
「チョコのケーキ食べたい。」
「あ、あたしお菓子持ってるよ夕霧ちゃん。食べる?あははっ!」
百合亜は匙を投げたようにお道化て笑い出した。あたしは彼女達の言葉をそのままに聞いているだけでその胸の内を別段何も忖度してはいないのだと謂うところだけはすぐにも見せなければいけないと思ったから、できるだけ餘念無さそうな口調で言って、前方の沙知に対してもほわほわした微笑みを送ることにした。顔色を窺うのも疲れて来た。へんにはしゃいでいた。対する沙知はすぐとその場を引き締めるだけの用意は欠いておらず、眉を顰めて苦笑いした後、両手をぐっと握り締めて立ち上がり、
「よぅしわかった!これが第一〇二期蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブだ!ちくしょー、やってやるー!」
大仰に、然しどこかやけっぱちな様子でそう宣言した。部室内の視線が彼女に集まる。言下にふうっとため息をつくのも聞こえた気がした。それでも、沙知のその一言は、恰も時間の流れまでをも支配したかのように感ぜられ、それを唱えるだけで何かが起こるような予感さえする、そんな深みがあった。沙知さんの太い声は不思議と聴き心地が好かった。
「いやはや、」百合亜も便乗して流石に軽く笑いながら呟くのであった。嚆矢濫觴、波乱の予感だ。
――若し真に所謂〈運命〉が如きものがあるとすれば、必らずや個人、若しくは組織、若しくは国家、若しくは世界、その悉くが須らく運命の支配を受くべきものと、之を支配するところの運命との間に、何らかの関係の締結約束され居るものが無くてはならない。勿論古よりの英雄豪傑には「我は運命に支配せらるるを好まず、我自ら運命を支配すべきのみ」と謂うが如き、熱烈鷙悍の感情意気を有したものの存することは争われぬ事実であって、彼の「天子は命を造る、命を言ふ可からず」と喝破した言の如きも「天子といふものは人間に於ける大権の所有者で、造物者の絶対権を有するが如くに命を造るべきものである、それが命の我に利せざるを歎じたりなどすると謂うが如き薄弱なことの有る可きものでは無い」と英雄的に言い放ったものである。確かにそれは如何にも面白いことばであつて、凡そ英雄的性格を有して居る人には常に是の如き意気感情が多少存在して居るものと評するのが学者肌かもしれないが、兎角凡夫たるあたしにとっては満足に溜飲を下げることができない。運命が善いの悪いのと駄々を捏ねて、女々しい泣事を並べつつ、他人の同情を買わんとするが如き形跡を示す者は、あたしたち庸劣凡下の徒の日常だ。思春期の少年少女とは往々にしてそういった感性で生きているものだ。
運命とは何であるか?時計の針の進行が即ち運命であると、あたしは思う。一時の次に二時が來り、二時の次に三時が來り、四時五時六時となり、七時八時九時十時となり、是の如くにして一日去り、一日来り、一月去り、一月来り、春去り、夏来り、秋去り、冬来り、年去り、年来り、人生れ、人死し、地球成り、地球壞れる、この大道が即ち運命ではないか。組織や個人にとっての好運否運と謂うのは実は運命の一小断片であって、そしてそれに対してヒトである個々人の評価を附したに過ぎない。然し既に好運と目すべきものを見、否運と目すべきもの実在を覚えてしまった以上は、その好運を招き致し、否運を拒斥したいと願うのは至極当然の欲望でもあろうが、若し運命を牽き動かすべき線條があるとするならば、人力を以てその幸運を牽き來り招き致しさえすれば良いのだ。即ち人力と好運とを結び付けたいので、人力と否運とを結び付けたくない――それが万人の欺かざる欲望である。それ即ち、瞬く間に過ぎ去る青春の時間を彩りたいと希求するのは、自然な人間精神の顕れであるのだ。
さて、第一〇二期蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブはこうして結成された。ああ、彼ら彼女らの辿る〈運命〉には、果たしてどのような結末が待ち構えてることであろう――。
天華恋墜 第一章:青春物語 終
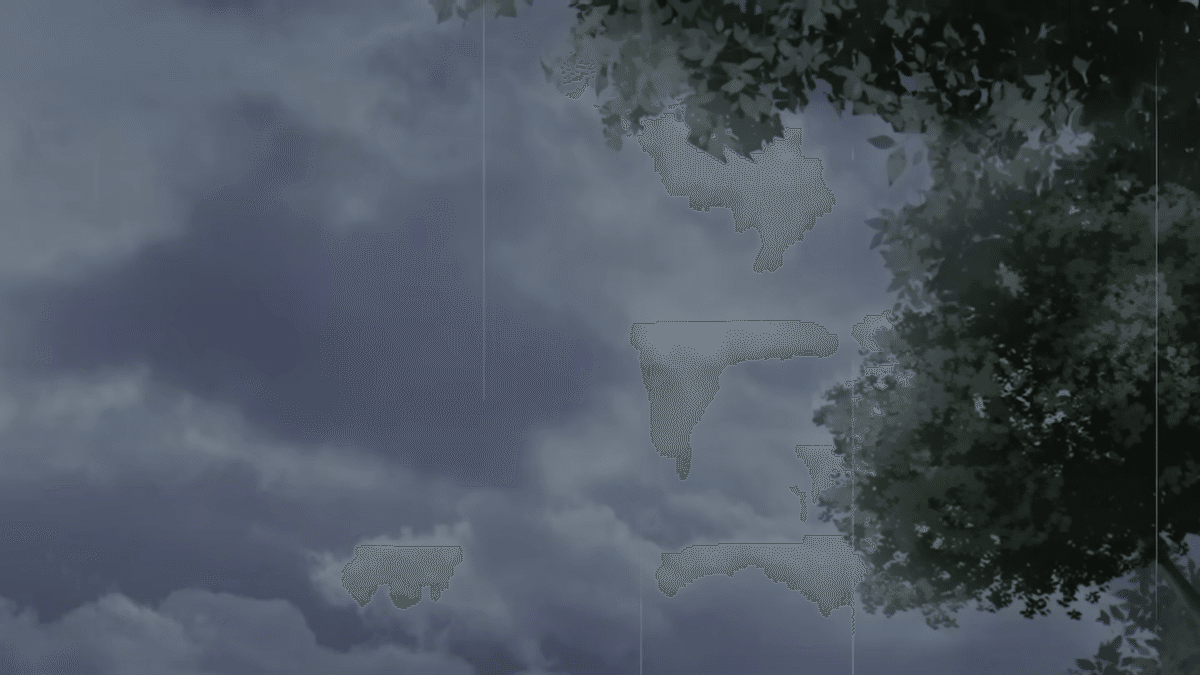
沈め掻き臥せ哀歌の沼に――。
