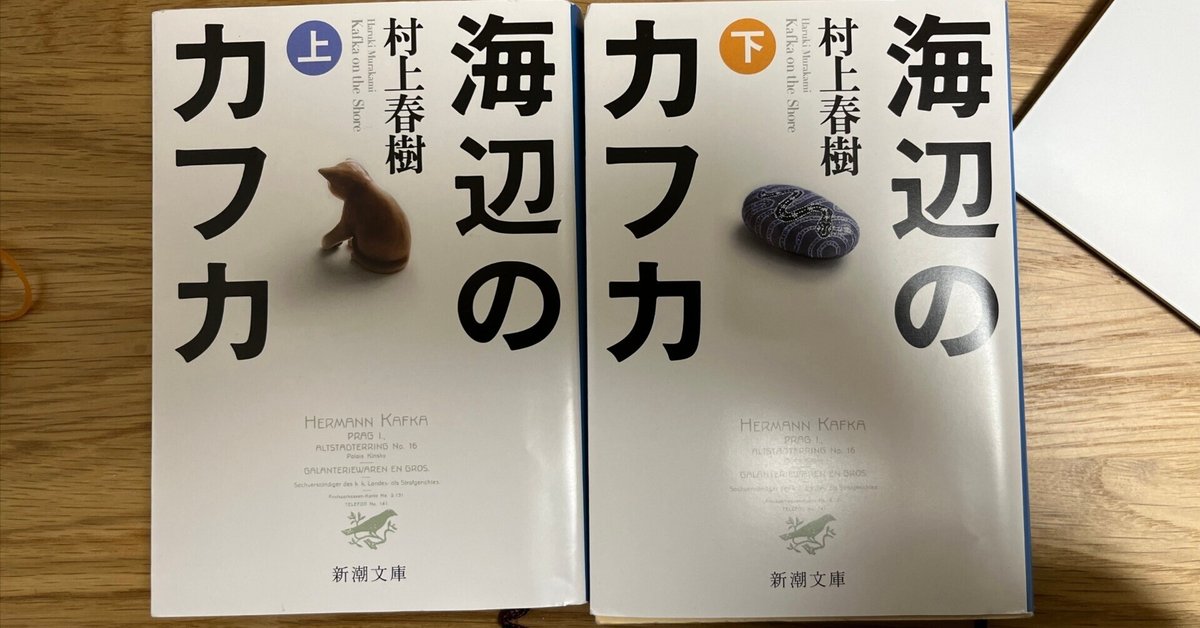
村上春樹が「海辺のカフカ」で伝えたかったことを考えてみた
「海辺のカフカ」を読み終わり、うわ〜格別におもしろかった、、、と感動し、ひと通りみんなの感想などを読んでみたのですが、わたし的に納得できるものが発見できず、それならちょっと書いてみたいなと思いました。
以前、脚本の書き方について学んだ際、「あらゆる物語には、作者が伝えたいテーマが存在する」ということを一番に教えられました。どんなシナリオや物語でも、ストーリーを通して一貫したテーマがあると。親を大事にしよう。他者を理解しよう。などがそれで、複雑なストーリーでもテーマは意外とシンプルなのだと教わったのです。
それからというもの、映画や本を観たり読んだりする中で、この作品のテーマはなんだろうと自然と考えるようになっていきました。
「海辺のカフカ」も、例のごとくテーマは何かと考えながら読んだわけですが、これが、実にいろいろと発見できるわけです。
例えば以下。
・子どもから大人への成長
・囚われからの脱却
・人を赦すということ
・悪とは何か
・世界は自分の考えようによっていかようにもできる
どれも間違いないだろうけど、何かどうにも「コレだ」という感じがない。なぜだろう、、と考えていたときに、この小説「海辺のカフカ」刊行時に特別サイトが設けられ、読者から広く質問を募集していたということを知り、あ、そうか。とピンときました。そして、文庫本版に解説が掲載されていなかったことにも、なるほど。となったのです。
村上春樹は「海辺のカフカ」で結局何を伝えたかったのか?
最初に結論を。本作のテーマ、それは「物事は、深く考え抜くことでようやく理解できるのだ。まずは何事においても考える。話はそれからだ」ということなのだと私は考えました。
なぜそう思うのか。書いてみたいと思います。
<以下ネタバレ有り。未読者要注意>
小テーマがいろいろあるから複雑。でもめちゃくちゃ面白い
本作は先に述べたようにテーマがいくつもあり、同時進行的に進んでいくため、少し分かりにくく感じます。でも、マルクスの「資本論」のように文章が難しくて理解が追いつかない…ということは決してなく、すいすい読める。中学生でもきっと楽しく読める。なぜなら、村上春樹の語り口が実に巧みであるということに他なりません。
とにかく文章が上手。カーネル・サンダースが出てきたり、猫があまりにもこの世のことわりを知っていたりと、突拍子もないことが急に起こったりするのだけど、あまりに自然に書いているし、内容自体がおもしろいから、「え?」と思うまもなく、だってそういう世界なんだしね。とすんなり飲み込んでしまいます。
村上春樹の小説は20年以上前に「ノルウェイの森」を読んだ程度でして、しかもその時に「私は春樹じゃなくて、完全に龍派だわ」と思ってこれまで過ごしてきたので、現実と幻想がシームレスに繋がった世界に最初は面食らいました。でも、読み進めていくうちに面白さが加速度的に増し、下巻は本当にすぐに読み終わりました。村上春樹はとにかく文章が巧みです。
2つの物語が交互に展開される理由
「海辺のカフカ」は、15歳のカフカ少年パートと、60歳のナカタさんパートが交互に展開する構成になっています。この2つのパートは、実はとっても対照的に描かれています。
まず年齢。中学3年生という、これから青年になろうとする年齢のカフカに対し、ナカタさんは大人を超えて老年に差し掛かろうという60歳であること。
それから、読書が大好きで暇さえあれば本ばかり読んでいるカフカに対し、ナカタさんは文字が一切読めないということ。
さらに、過去に父親にかけられた「父を殺し、母と姉と交わる」という呪いに囚われ続けるカフカに対し、ナカタさんは過去の出来事には一切関心がなく、”今ここ”しか重要ではないこと。
そして、人間の三大欲求のひとつ「性欲」に衝動的に支配されるカフカに対し、ナカタさんは「これまで性欲を抱いたことがない」と発言した上で、残る2つの欲求「睡眠欲」と「食欲」には支配されていること。
キャラクターが対照的なだけではなく、それぞれの物語も対照的で、カフカパートが抽象的な概念多めでシリアスに進んでいくのに対して、ナカタさんパートは具体的かつユーモラスに展開していきます。
これによってナカタさんパートのほうが軽妙で読みやすく、感情移入もしやすいよう設計されています。
さまざまな点で対照的な2人の物語が、異なる切り口から展開されることによって、ものすごく”うまみ”のある小説になっています。カフカパートだけではどうにも読みにくいし、ナカタさんパートだけでは表面的すぎる。深さ・浅さの両面を楽しみつつ読み進めていくうちに、2人の物語が交差し始め、まるで竜巻のように面白さが加速度的にぶわっと広がるのです。
人生の節々で刺さる箇所が違うだろう
さまざまな小テーマが描かれることによる分かりにくさはあるものの、一方で、いつ読むかによって心に残るテーマが異なってくるだろうなと思います。
10代であれば、「よく理解できなかったけど、カフカのように人生を切り開いていきたい」と感じるかもしれないし、20代であれば「世界はメタファーでできているんだ」とハッとするかもしれない。
30代であれば「過去に苦しめられるのはもうおしまいだ」と勇気をもらうかもしれないし、60代であれば「自分の正しさは間違っていなかっただろうか」と振り返るきっかけになるかもしれない。
非常にチープな言い方になってしまうけど、読み応えがある。心のどこかには引っかかるよう、あちこちにホックが仕掛けられた小説だなと思いました。
ちなみに今の私の心に残ったのは、星野青年がベートーベンの大公トリオに傾倒していく箇所でした。
星野青年は元来物事を表面的に捉え、その場その場で人生の判断を下すような人でした。それが、ナカタさんとともに行動する中で、ベートーベンに興味を示すようになったり、喫茶店のマスターと身のある話をしたりするような人物に変わっていきます。
星野青年は、かつての自分はとても浅はかだった、ナカタさんと一緒に過ごしたからこんな風に変わっていった、と言っていました。ただ、ナカタさん自身は、どこからか降りてくる予言に従ってそのまま動いているだけにすぎず、別に、ものごとの見方が鋭角だとかいう訳ではありません。
それではなぜ、星野青年は変わったのか。
人はひょんなことがきっかけで変わります。私もかつてはパンクロックが大好きで、クラシックなんて退屈でつまらない音楽だとしか思っていませんでした。しかし、ある時何かのきっかけでベートーベンの第九が好きになり、続けてチャイコフスキーやヨハン・シュトラウス2世も好んで聴くようになった経験があります。
ベートーベンもチャイコフスキーもヨハン・シュトラウス2世も、私が生まれてから今まで一音たりとも変わらずにそこに存在していました。しかし、かつての自分と今の自分では、確実に音楽そのものが違って聴こえてきます。
これはどういうことか。
人は元来孤独です。なぜなら、どんなに親しい人、たとえ肉親であっても心の中を覗くことができないから。「きっとこんなことを考えているのだろう」と予想はできても、本心は全くわからない。どこまでいっても真っ暗闇です。同じように世界全体を見渡しても、わからないことだらけです。
そんな孤独な世界で、わかることはただひとつ、自分だけです。結局人はどこまでいっても自分というフィルターを通してしか世界を見ることができません。ちょっと飛躍すると、自分が捉えている世界そのものがすなわち自分である、ともいえるのではないでしょうか。
自分の捉え方次第で、音楽、引いては世界全体が豊かにも貧しくもなる。星野青年は、ナカタさんと行動をともにする中で、これまでとは異なる価値観で動くはめになりました。ナカタさんにしぶしぶ付き合ったり、風俗嬢の哲学に触れたりすることで、いろんな刺激があったに違いありません。この経験を経て、なぜ他人はこんな風に考えるのだろうと思うようになった。そして、これまで短絡的に行動していた自分も俯瞰して見ることができ、世界に対する解像度が少し高まった結果、ベートーベンの音楽がこれまでと違って聴こえてきた。
世界は自分の写し鏡であって、どう捉えるかは自分次第、相手がどうかは関係ない。今の私にはものすごく納得感がありました。
ほかにも気になったこと
カフカくんは父親に呪いをかけられたと言うし、ひどいことをされたと言う。そのことでひどく落ち込んでいるし、囚われ続けている。しかし、具体的に父親とどのような暮らしを送っていたのかは物語の中では明かされません。
同じく、カフカくんの母親なのではないかと思われる佐伯さんの過去も明かされない上、過去をすべて書き記したファイルを燃やして欲しいとナカタさんに頼み、ナカタさんはそれを遂行。読者にも彼女の過去が明かされることは一切ありません。
原因があって結果がある、言うなれば因果関係。村上春樹はカフカパートで因果関係と徹底的に向き合わない態度を取り続けます。過去に何があったのかは関係ない、割れたお皿は元には戻らない。それよりも今何をするかに意識を向けるべきだ。それがタフであることなのだ。そういう意思を感じます。
ちなみに、ナカタさんの過去はたっぷりと語られます。事故に遭い、それでもなんとか生きのびて家具職人として生計を立て、でもある日職を失ってしまい、知事から障害者補助金をもらいながら細々と暮らし、猫探しをしながらたまのウナギを楽しみに生きている。感情移入しやすい人物だといえるでしょう。カフカくんと佐伯さんには一切感情移入できないのに。
考えること。知識を得ること。その大切さ
結論です。「海辺のカフカ」で村上春樹が伝えたかったことは、
「物事は、深く考え抜くことでようやく理解できるのだ。まずは何事においても考える。話はそれからだ」
ではないかと述べました。
小テーマが積み重なっている上、奇想天外なストーリー展開で物語がどんどん進んでいく「海辺のカフカ」。引っ掛かりがあちこちに用意され、読者はカフカパートで時につまずきながら、ナカタさんパートではほっこり和みながら、最後まで読み終えることでしょう。こういった読書体験は、なかなか他では味わえないものだと思いました。
・佐伯さんは本当にカフカの母親なのか
・ジョニー・ウォーカーは何者なのか
・森の中のあの世界はいったいなんなのか
・山梨の山中で巻き起こった小学生集団昏睡事件は結局なんだったのか
いろんな疑問が最後まで明確にされないまま、終わりを迎えます。私はこれは、乱暴なストーリー展開なのでは決してないと強く言いたいです。「風呂敷を広げ過ぎて畳めなくなっている」というように評する人物を見かけましたが、そうではない。村上春樹はあえてこのような形を取ったのだと思いました。
なぜなら、これは伏線回収が気持ちいいタイプの物語ではないから。そうではなくて、あちこちに引っ掛かりを残すことで、読者に「考えさせる」という能動的なアクションを求める”体験”だからです。
この世はとても複雑です。思い通りにならないことばかりだし、他人の気持ちはわからない。カフカも、父親の気持ちがまったく理解できずに苦しみます。そのうえ、自分の関与できないシステムがあちこちで動いていて、若くてちっぽけな自分は何もできない。それが悔しくてやるせない。でも、そんな世界でも諦めてしまわず、とことん考え抜いて、次の一手を出し続ける。それが世界でいちばんタフなことなんだ。村上春樹はそう言いたいんじゃないでしょうか。
もちろん闇雲に「考えろ」と言っているのではなく、村上春樹はどう考えればいいのかきちんとヒントを出してくれています。物語の重要な舞台となっている甲村図書館です。つまり本、引いては知識。本をたくさん読んで知識をたっぷり蓄えて、そのうえでしっかり考える。話はそこからだ。そんなメッセージを私は受け取りました。
どの文庫版の巻末にも大抵入っている「あとがき」が「海辺のカフカ」にはなく、手近な答え合わせができないのも、読者に考えさせるため。
小説刊行時に特別サイトをオープンさせ、質問を募ったのも、読者に考えさせるため。
そう考えると、実によくできた小説であり、体験であるなと思うわけです。
ちなみに、ナカタさんと星野青年が入り口を開け、カフカが踏み込んだ森の中のあの場所は、この世が辛くて何も考えられなくなった人が最後に逃げ込む場所(概念)だと理解しました。15歳の佐伯さんがスープを作ってくれたり、「サウンド・オブ・ミュージック」に癒やされたりと、カフカにとっての都合のいいことばかりで構成された、複雑なことは何もない、やわらかな世界。でも考えることをやめてはダメだと気づいたカフカは、大人の佐伯さんにも背中を押されて脱出します。
最後にちらっと大島さんのお兄さんが登場し、何気なく森の中の兵隊たちの話をするのですが、私はこのシーン、ちょっと感動してしまいましたね。
大手広告代理店で働き、退職して地元でサーフショップを経営している、自由気ままなお兄さんでも、閉じたやわらかな世界に行くことを夢見たことがある。つまり、このお兄さんですら、かつて何か人に言えないような辛いことが起こったんだな、と。あ〜人ってやっぱり一面的ではない、みんなあらゆる過去を抱えているし、それでも生きているんだなと、ぐっときました。
以上です。非常に長い投稿になりました。
「海辺のカフカ」は読むべき小説のひとつだと強く思いました。私自身読んでから2、3日「海辺のカフカ」のことばかり考えていて、非常に有意義で、かつ思考のデトックスのようなものができたひと時でした。
他の村上春樹作品もぜひ読んでみたいと思い「羊をめぐる冒険」を買ってきました。まだ積ん読中なのだけれど、休みの日にガッと読めるよう楽しみにしているところです。
読んでいただいた方、おつかれさまでした。ありがとうございました。

