
【調剤と情報/2024年7月刊行】病院薬剤師が学んだ"薬の粉砕について"
大学の製剤学などでも学習した
製剤上の工夫や薬の粉砕による影響。
病院という場で働いていると
実は患者さんが服用する時に居合わせる
というタイミングはそう多くありません。
しかしながら
今後在宅医療に関わる上では
服用困難な患者さんに対する課題に
直面するケースが多くなると思われます。
一歩踏み込んだ治療の提案を目指し
7月発刊の「調剤と情報」等を参考に
改めて製剤の勉強していきます!
そもそも粉砕が必要?
錠剤が飲み込めない場合の対応として
まず1番に看護師さんから聞かれるのは
「粉砕できるかどうか」かもしれません。
粉砕可否の判断をするにあたり
まずは"インタビューフォーム"を確認。
他には"錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック"等
データが集積されている資料を調べます。
一方で、まず1番初めに考えるのが
「粉砕以外の選択肢」という方は
どれくらいいらっしゃるでしょうか?
粉砕以外の対応について
本書では以下の方法が紹介されています。
*粉砕以外の対応例
▷外用剤への剤形変更
▷口腔内崩壊錠への剤形変更
▷小さい錠剤への変更
▷1日1回投与製剤への変更で負担軽減
粉砕可能であれば粉砕しよう!ではなく
薬剤師としての知識を最大限に活かして
剤形変更なども提案していけるといいですね。

粉砕で起こる問題点
●粉砕のデメリット
粉砕により生じる問題点は
色々な側面から考えることが大切です。
・効果や安全性の変化
・苦味やにおいが強くなる
・潰瘍や麻痺
・暴露
▶︎苦味やにおいが強くなる
食事に混ぜることで
食事拒否につながる可能性もあり
注意が必要です。
▶︎潰瘍や麻痺
代表的な薬剤はビスホスホネート製剤。
直接粘膜に作用しないように
服用上の注意点の指導は大切です。
▶︎暴露
抗癌剤など医療従事者にも危険がある薬品は
Hazardous Drugs(HD)と位置付けられ
個人防護具の着用が推奨されています。
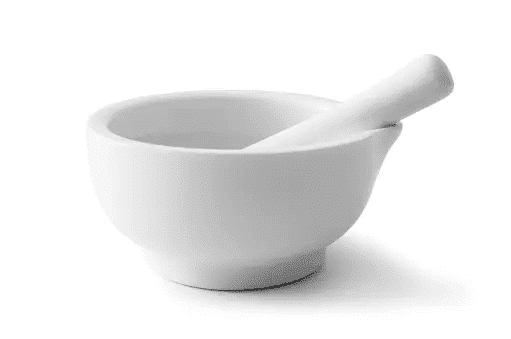
●現場で気をつけるべき具体事例
pHの観点から配合時に生じる問題について
今回は以下の2種類を例に紹介します。
酸化マグネシウム
オルメサルタンメドキソミル
内服薬の場合
胃酸(pH1)を通過することから
比較的、酸に強い薬物が選択されます。
一方で、胃酸で分解する薬物は
腸溶性製剤となっています。
したがって、考える必要があるのは
塩基(アルカリ)性での安定性になります。
<酸化マグネシウム>
最も使用されている薬剤の1つです。
酸化マグネシウムの懸濁液は
pH10-11の強アルカリ性を示します。
そのため、混合した薬剤の
色調変化や含量低下などの問題を
起こす可能性があります。

<オルメサルタンメドキソミル>
オルメサルタンメドキソミルは
オルメサルタンをエステル化した
プロドラッグ製剤です。
このエステル結合の加水分解は
酸性では可逆的ですが
アルカリ性では非可逆的に起こります。
そのため
アルカリ性での溶液では
分解が起こりやすくなります。

以上から
プロドラッグ化を目的として
エステル化されている内服錠と
酸化マグネシウム錠の混合粉砕は
避けるのが望ましいといえます。
今回勉強してみて
今回は臨床現場で行われている
錠剤の粉砕に関する問題について
薬学知識を活かした対応を学びました。
処方監査では
腎機能や相互作用など様々な側面から
最適な医療を考えていきます。
今後はさらにもう一歩
実際の服用場面も考慮して
よりよい医療を届けられたらと思います。
今回学習した本書では
徐放性製剤の特徴や製剤上の工夫について
まだまだ興味深い情報が記載されています。
ぜひ皆さんも手に取って
日々の薬剤師業務のなかで
ご活用いただけたらと思います!

