
人類はなぜ戦争をするのかー選挙に絶望したナチ党員の政治学者の哲学ー
皆様、なぜ戦争は起きるのでしょうか。
それは敵がいるからです。
あるナチ党員の政治学者はそう論じました。
そして現代政治学でも彼の理論は生き続けています。
ミリタリーサークル徒華新書
@adabanasinsyo
主催の久保智樹です。
さて、ミリタリーを扱う弊サークルと切っても切れない問があります。
それは「なぜ戦争が起きるのか」という命題です。
多分この答えを出せて、そして処方箋を書ければ僕はノーベル平和賞をもらえると思います。
まぁそんなこと無理だと言ってこの問いから逃げるが最も賢いです。
しかし不器用なのでこの命題について考えてみたく思いました。
そこで本日の主役。
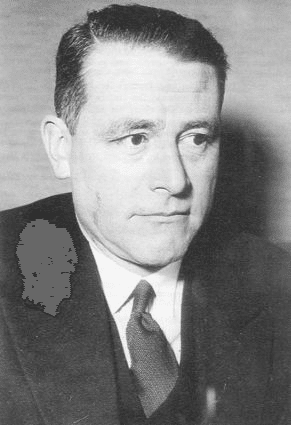
カール・シュミット教授
『政治的なるものの概念』です。
1933年、ナチスドイツが政権を奪取すると、従来より議会民主主義に批判的であったシュミットはナチ党に入党し、この1933年に『政治的なるものの概念』の第3版を刊行しました。
ナチ党の教義に整合するように過去の論文に手を入れたこの小冊子は、それがナチと極めて親和的であれど、いや親和的であるが故に全体主義体制の本質を突き、今日でも読まれる政治学の代表的なテキストです。
ところで「オッカムの剃刀」をご存知ですか?
必要が無いなら多くのものを定立してはならない。少数の論理でよい場合は多数の論理を定立してはならない。
物事はシンプルイズベストと説く科学の鉄則です。
シュミットの議論はまさに剃刀のようです。
戦争があるのは敵がいるから。
あまりにシンプルなこの議論はいまだ突き崩しきれません。
本日はそんなシュミット教授の戦争観を観察し、なぜ戦争が絶えないのかという哲学的なれど実用的な話をしようかと思います。
本日のお品書きです。
クラウゼヴィッツは間違っている
ミリタリーで政治哲学とは如何かとなるがシュミットのクラウゼヴィッツ批評をまず引用してみたい。
クラウゼヴィッツは「戦争とは、他の手段をもってする外交政略の継続に他ならない。」(中略)戦争には戦争独自の「規約」(即ち、戦術上特別な法則性)がある。だが、政治は依然として戦争の「脳髄」である。戦争は「自らの論理」を持たない。即ち戦争は、敵味方の概念からのみ、自らの論理を獲得しえるのである。
今すぐこれが納得いったらブラウザバックして大丈夫です。
もうあなたに語ることは今日はなさそうなので。
しかし、政治学者の立場から徹底的に戦争を考えた人物とその時代性、そして彼がなぜナチスを受け入れたのかそれを明らかにすることは、第二次世界大戦をいつもと違う角度から理解し人類の歴史を俯瞰する手掛かりになると信じています。
ご興味あればぜひ読み進めて下さい。
なぜ人は戦争をするのか、じっくりと検討します。
1933年のドイツと世界
カールシュミットを語るにあたり、1919年のドイツの状況から物語を始めるとします。
1914年に勃発した第一次世界大戦はヨーロッパ全域を戦場とした総力戦でした。1918年にドイツ帝国内での国民生活の窮乏から革命が勃発し帝国は崩壊し共和国が建国され、そしてドイツはこの混乱により敗北しました。
1919年ヴェルサイユ条約が締結され、ドイツワイマール共和国は天文学的な賠償金や、領土の削減、軍備の厳しい制限など過酷な処置がとられます。
1919年はドイツにとって最悪の時代の幕開けでした。
とそう単純ではない。
1919年からの数年は革命と反革命によりドイツは準内戦状態にあり、多数の武装勢力が闊歩する状況にありました。一部の司法関係者や軍人は陽に陰に右派の暴力組織を支援したことでドイツにおいては共産主義革命は阻止され、20年代後半には一定の治安秩序が回復されます。
経済においても一時は国民の大半が食うに困るような状態であったのが、アメリカを中心とした多くの投資が復興を目指すドイツに注がれたことで経済も上向いていました。
1920年代後半はドイツ、ワイマール共和国、の絶頂期でした。
黄金の20年代とさえ言われる活況を呈していました。
しかし1929年、アメリカのウォール街でのバブル崩壊に端を発した金融危機によって、世界恐慌が発生すると、アメリカの投資により経済を維持していたドイツは、そのアメリカの経済不況に引っ張られる形で大不況に陥ったのです。
混乱は過激な解決策を提示する怪物を舞台に押し上げます。
ナチスドイツの台頭です。
1930年ナチ党は最大野党に躍り出、人気は衰えず1932年には議会の最大会派となった。1933年ヒンデンブルク大統領がその人気と暴力性を抑え込むための妥協策としてヒトラーを首相に任命せざるを得ませんでした。そして反ナチス派の最後の賭けである総選挙でナチスは議会第1党を守り切ると、ヒトラーは国会議事堂放火事件を口実に共産党を排除し、議会の過半数を確立し全権委任法を可決させ、ヒンデンブルク大統領に承認させました。
1933年3月23日、この日ヒトラーは全権を委任された独裁者となりました。
議会制民主主義 ー絶望ー
シュミット教授はキリスト教の改革派の多いドイツにあって南部のカトリック出身者でした。第一次世界大戦では兵役に召集されるも訓練中に負傷し、前線でなく後方の検閲業務に従事します。シュミットは戦後自らの教鞭を執った大学があったストラスブール大学がその領土ごとフランスに併合されたことで職も一時失うこととなりました。
シュミットは一言で言えばマージナリーマンです。
ドイツの伝統的宗教の流れから疎外され、この時代の人々らしく兵士となる機会も持てず。彼の中には体制からの疎外感が色濃くあったのです。
だからナチスに入党したという単線系ではないです。
シュミットは確かにナチスに与したが、そこに至るにはいくつもの経験と偶然があったのは見過ごせないことです。20年代、ナチスの台頭以前から議会制民主主義の欺瞞と独裁の可能性を常に模索していたことは無視できないでしょう。
奇妙に思えるかもしれないがシュミットにとって自由主義的な議会制民主主義よりも、大衆の意図を直接組んだ独裁の方が民主的であるとさえ考えていました。
1921年に『独裁』、1926年に『現代議会主義の精神的状況』といった論文を執筆しています。ここに見られるのは自由主義と民主主義は相反する概念であるという立場です。むしろ人々の意見を直接聞き入れる「独裁」こそが民意に適う統治体系であるとさえ考えていました。
シュミットの同時代を見れば議会制民主主義はそれまでの特権階級による制限選挙から普通選挙に移行する中で混乱を極め、対照的に東ではポーランドやトルコにおける独裁体制、ソビエトのプロレタリア独裁といった体制が一定の成功を収めていた事実は見逃すべきではないでしょう。
新たな民主主義 ー喝采ー
シュミットにとって独裁というのは民意を反映する可能性であり、それ故にヒトラー体制を受け入れたと言うべきでしょう。
自由と民主主義は不可分では無いとシュミットは論じました。
むしろ敵対概念であるとさえ言います。
『独裁』のなかでは古代ローマを例にとり、議会が一時的に全権委任を行い独裁を認める事態を挙げて、独裁と民主主義の共存を書いています。
そう、まさに議会により全権委任をされたヒトラーと重なるような体制の在り方を1920年代前半から唱えていたのです。
そして1933年5月に彼は正式に党員となりました。
シュミットはナチが力をつけたからナチ党に入党したのではなく、ナチを受け入れる思想的背景を持っていたから自然と入党を決断したのでした。
敵と味方 ーそれこそが政治であるー
さて、ここまで長々と書きましたが、本筋は「戦争はなぜ起きるのか」という問いです。
政治に固有なる区別は、敵と味方という区別である。
『政治の本質』「政治的なるものの概念」
中央公論新社、2017年、P119
「友敵概念」として知られるシュミットの代表的な理論です。
そうなぜ戦争が起きるのか。それは敵がいるからです。
これは他のあらゆる価値からも独立した政治に固有の概念と言います。
即ち、道徳上、悪であり、審美上、醜であり、経済上、害であるものも、それだけではいまだ敵であるとは限らない。道徳上、善で、審美上、美で、経済上、利あるものも、それだけではいまだ政治的意味における見方にはならない。かような敵味方と異様な特殊な対立を、他の区別から切離して、独立的なるものとして把握することができるという点において、すでに政治的なるものの独立性が示されている。
個人的に好きな部分です。
例えば冷戦中のアメリカ。自由民主主義を守るために共産主義のソ連と戦いました。そのために独裁者に対して軍事援助を与えていたのは広く知られる話です。
まさに敵たる共産主義者と戦う見方であるから、道徳上、悪であり、審美上、醜であり、経済上、害であるものと手を組んだと言えるでしょう。
「敵」は誰が決めるのか。
軍事的戦闘そのものは、たいていの場合誤って引用されるクラウゼヴィッツの有名な言葉のような「別の手段をもってする政治の継続」ではなく、それは軍事的、戦術的、その他戦闘固有の規則と観かたを有するものである。だがそれらの規則や観方はいずれも、敵は誰かという政治的決定が既に存在することを前提している。敵を決定するのは兵士ではなく、政治家である。
言われれば、なるほどと思うのです。
ある兵士が個人的に市民を銃撃したら罪であるが、暴徒鎮圧を命令され群衆に発砲した兵士の責任は命令者に帰結されるはずであるから。
では、政治家が敵を探さなければ戦争は無くなるのか。
いやそうではない。
と言いつつ、次の引用箇所は難しいので、流し読んで続く解説を見てください。
戦争は決して政治の帰趣及び目的でなく、その内容でさえもない。だが、それは、全般の行為と思惟を独特な方法で規定し、かくして政治特有な挙惜をとらしむるにいたる前提であり、しかも、実存的可能性として常に存在するところの前提なのである。
多少整理をしましょう。
①戦争=政治 ではない。
②戦争→政治の前提 である。
③戦争→実存的可能性 である。
※実存的=仮定でなく、事実そこにある問題
シュミットの世界観を思い出してください。
「政治に固有なる区別は、敵と味方という区別である。」
敵味方の区別をする、即ち実際に起きる戦争を想定する。だから政治は存在する。
で、究極的な平和常態についてこう述べます。
戦争の実存的可能性一般が失われれば、一切の政治は消滅し、戦争を回避せんとする政治もまた消滅する。かかる最後的場合、即ち現実的戦争の可能性、及びかかる場合が存在するや否やに関する決定が、政治の基準である。
戦争について考える必要性が消滅すれば、友敵関係に基づく「政治」は消失する。
荒唐無稽に思えるが、個人的にはおもしろい考え方であると思います。
近世の東アジアは「政治」が消滅していたのではないか。
中国に清王朝、朝鮮に李氏朝鮮、日本に徳川幕府。その領域を圧倒的に支配する勢力が自らの勢力範囲に満足し互いに緩やかな関係だけを持っていた。
人間が思いつめる状況が無くなれば、政治的なるもの、即ち敵味方という思考は消滅する。
シュミットはこの人間が思いつめている状況を「例外状況」と定立する。
日常でなく、戦争と言う異常事態。まさに例外状況になれば敵味方という政治に特有の区別が剝き出しになる。
敵は内側にもいる
ここまでの議論でイメージされていたのは国家と国家が敵味方に分かれて闘争する姿です。しかし政治はそれだけではないとシュミットは語ります。
決定的政治単位至る国家は、巨大な権能、即ち戦争を遂行し、かくして公然と人間の生命を支配する可能性を掌握した。(中略)
ところで、正常的国家の仕事は、就中、国家及びその領土内において完全な満足をもたらし、「平和と安全と秩序」を作り出し、それによって正常的状態をもたらす点に存する。かかる正常的状態は一般の法律規範が妥当しえるための前提である。蓋しすべての規範は正常的規範を前提し、いかなる規範でもこれに対して全く異常的な状態では打倒することが出来ないからである。かかる国内的満足の必要は、非常時局には、政治的単位としての国家が自ら存在する限り「内敵」をも決定するに至らしめている。
国家は例外状況においては外側に敵を決定できる力である。
しかし、それができる力であるということは、国内にいる誰が犯罪者やテロリスト、危険分子かといった「内敵」の決定もできることを意味する。
それはそうである。正常的国家の一般の法執行としての死刑という殺人行為は合法な殺人行為である。国家の治安の敵に対する合法的処置として。
シュミットは内敵に対する取り扱いとその後の展開を示している。
追放、破門、人権はく奪、平和の剥奪、法律保護の停止、約言すれば国内的対敵宣言が存在するものである。それは、異分子のいない同類だけの社会ないし政治的単位の再建であるか、それとも国家の敵たる宣言を受けたものの行動如何に応じて、内乱、即ちそれ自体で自足的生活を営み、領土的にそれ自体を纏った、他国人には入りがたい組織的政治単位としての国家の解体の兆候であるか、のいずれかである。
20世紀前半を生きる時代人らしいものの見方だなと感じます。
自らの祖国ドイツ帝国の崩壊、隣国オーストリア=ハンガリー二重帝国は四分五裂に分解、オスマン帝国は解体されトルコ人の内乱で一党独裁のトルコ人国家に、ロシア帝国は共産主義者の内乱により形を変える。
そのさなかに起きた事実とレトリックこそがここに詰め込まれている。
人類の名を借りて
個人的にその後のナチスドイツを予言的に書いたとも読める一節を紹介する。
或る国家が人類の名において彼の政治上の敵を攻撃することがあるが、それは人類の戦争ではなく、特定の国家が(相手方を犠牲として、)自らを人類なる概念と一致させるために、その戦い相手から普遍的概念を押収しようと試みるような戦争なのである。同様に、平和、正義、進歩、文明などという言葉を自己のために要求し、これらを敵からはく奪するために、これらの意味を濫用することがある。
(中略)
敵から人間の属性を剝奪し、敵は法律の保護外にあり、且つ人道に外れたる旨を宣言し、かくして戦争を極端な非人道的なものにまで駆り立てようとする恐ろしい要求を示すも似に過ぎない。
そして次のようにこのテキストは締めくくられる。
かかる政治性を剥奪された組織においては、相手方は最早「敵」とは呼ばれない。だが、その代わりに彼は「平和の侵犯者」及び「平和の攪乱者」として、法律の保護を停止され、人類の外に置かれることになる。
(中略)
自由主義的両義性の中には、確かに驚くべき体系性と論理性が示されている。けれども、このいわば非政治的な、しかのみなず一見反政治的な組織は、既存の敵味方の集団化に役立つか、さもなければ新しい敵味方の集団化を導くものであって政治的なるものの結果を免れることはできない。
アーリア的である、即ち人類的である者。
ユダヤ、スラブ、ロマ、障碍者、即ち人類でない者。
ナチスは「生きるに値しない命」をその内在原理に持った。
シュミットに対する批判の大きな部分は彼がナチスの残虐さを予見できずに入党したというよりも、国家権力の持つこの残虐性に対する明晰な分析眼を持っていてなおナチ党に入党したという事実に帰せられるところが大きいのではないか。
生き死にを決するのが政治であり戦争は結果
さて、まずは長旅お疲れ様です。
ここまで読み進めていただき感謝です。
なぜ戦争が起きるのか。
政治はその固有の領域として敵味方の区別を持つからである。
敵味方の区別をなくすとどうなるか。
それを否定すると法執行という正常的国家の秩序が維持できない
だからこの権能を認めないと国家は存立しない。
我々が法の支配のもとで、確実に法が執行されると思うような正常的国家の秩序を欲すれば、それは外の世界において未必性を持った戦争を認めなければいけない。
これがシュミットの書いた世界像である。
ところでフランスの哲学者フーコーも国家の強力な権力とは「生権力」であると説いたのはご存じだろうか。
フーコー曰く、警察誰家の国家は権力の弱い国家である。
逆に警察が見張らなくても人々が法を守るのは権力が強い国家である。
そしてその究極が、生き死にという「生権力」を国家が握っている状況であり、社会保障など我々の寿命と直結する機能を握った今日の国家は極めて強い権力であるという学説である。
フーコーの議論を極めて先取りした性格をシュミットから感じる。
その点をもっても卓越した論理構造であるように感じる。
あとがき
この原稿を思いついたのは偶々です。
後輩がシュミットを読んでいて読書会に誘われたためです。
で、読み返してみると昔は気にならなかったが、今の自分にはこの本があまりに生々しく戦争について語る本であると感じたのでした。
ということで、普段の実存的な戦争を離れて、思惟としての戦争について考えてみた次第でした。
参考文献
マックス・ウェーバー、カール・シュミット・著西田幾太郎訳『政治の本質』中央公論新社、2017年
蔭山 宏『カール・シュミット-ナチスと例外状況の政治学』中公新書、2020年
ヤン=ヴェルナー=ミュラー著、板橋拓己、田口晃訳、『試される民主主義 20世紀のヨーロッパの政治思想』岩波書店
気に入ったらサポートいただけると嬉しいです。 頂いた分はさらなる調査の資金にあてます。 気になるテーマなどがあれば教えてください。
