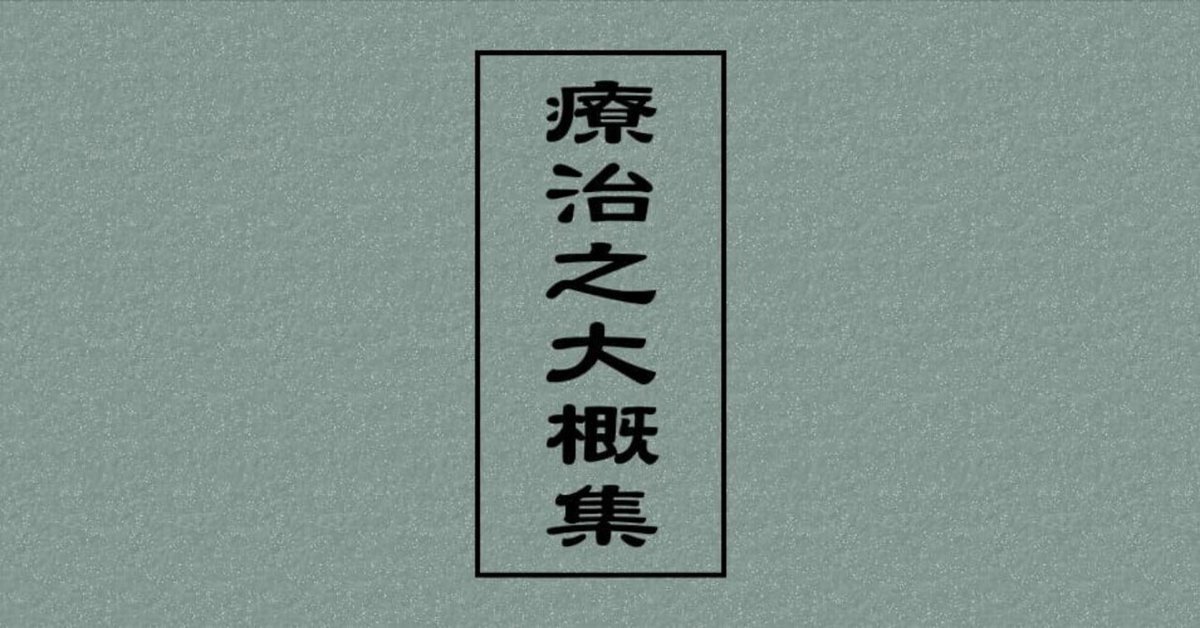
江戸時代の鍼灸術の書『療治之大概集』⑧
こんにちは、やまと治療院です。『療治之大概集』の8回目です。
しばらくは病の説明と使用穴が続きます。
※『療治之大概集』の原文はこちら。
積聚
【原文】
積聚
五積六聚有り。五積は定まる所有りて陰に属し、六聚は定まる所もなし形もなく気に属す。
一、心の積を伏梁と云ひ、其の状臍の上に起こり大きさ臂の如く、胸の頃に横たふ。肝の積を肥気と云ひ、其の状左の腋の下に有り大きさ杯を覆けたるが如く、手足頭など有るが如し。腎の積を奔豚と云ひ、臍上に起こり或いは心の下に升り降りすること有り、豚の状の如し。肺の積を息賁と云ひ、其の状右の脇下に有り大きさ杯の如し。脾の積を痞気と云ふ、其の状中脘に見はれ大きさ杯を覆けたるが如くして塞がって在るなり。其の他に有る塊は痰と食積、死血なり。三里、中脘、建里、不容、章門、上脘、聚によし、下脘、聚によし
【意訳】
積聚
積聚は五種類の積(五積)と六種類の聚(六聚)がある。
五積は、定まった場所にあり、陰に属している。
六聚は、場所も形もなく、気に属している。
・心の積を「伏梁」という。肘くらいの大きさで、臍の上から胸まで横たわっている。
・肝の積を「肥気」という。左の腋下にある。覆杯くらいの大きさで、ごつごつと突起があり、手足頭などがあるように感じる。
・腎の積を「奔豚」という。臍の上に起こり。心下に昇っていったり降りてきたりする。豚のような形である。
・肺の積を「息賁」という。右の脇下にある。大きさは杯くらいである。
・脾の積を「痞気」という。中脘あたりに発生し、大きさは覆杯くらいであり、気の上下の昇降を塞いでしまう。
・その他に塊として現れるものは「痰」と「食積」による「死血」である。
使用穴は、三里、中脘、建里、不容、章門、上脘(聚に用いる)、下脘(聚に用いる)などである。
自汗
【原文】
自汗 あせかく事、附たり盗汗はねあせなり
一、夫れ心の液を汗と云ふ。心熱する時は汗出づ。自汗は陽虚に属し常に出づ。盗汗は陰虚に属す。寝入りたる内に出で覚むる時は止む。自汗には腎の兪、肝の兪、章門。盗汗には角孫、中脘。
【意訳】
自汗・盗汗
心の液を汗という。心が熱すると汗がでる。
自汗は陽虚に属しており、常に汗が出るものである。
盗汗は陰虚に属しており、寝ているときに汗が出るものである。
自汗の使用穴は、腎兪、肝兪、章門、である。
盗汗の使用穴は、角孫、中脘、である。
癲癇
【原文】
癲癇 くつちかきの事
一、夫れ癲は心血の不足なり。好んで笑ふ事常ならず。仆れ錯乱す。
一、癇は卒に目を廻し仆れ、身軟て歯を噛み涎沫を吐き人を知らず頓て醒むる。痰の故なり。鳩尾、人中、間使、肝の兪、上脘、天突。
【意訳】
癲癇
癲は、心血の不足で発症する。急に笑い出したり、錯乱して倒れたりする。
癇は、にわかに目を回して倒れ、身体に力が入らず、歯を噛みしめて、口から涎沫を吐き、人事不省となる。しばらくすると症状は治まり、目が覚める。痰が原因で発症するものである。
使用穴は鳩尾、人中、間使、肝兪、上脘、天突などである。
吐血
【原文】
吐血 血をはく病の事
一、夫れ積熱の至す所なり。衂血も同じ。肺の兪、上脘、天突、巨闕、鳩尾。衂血には少海、郄門。
【意訳】
吐血
吐血と熱がこもることで発症する。鼻血も同様である。
使用穴は、肺兪、上脘、天突、巨闕、鳩尾である。
鼻血には、少海、郄門を使用する。
下血
【原文】
下血 大便に血下る病の事
一、大腸に風有れば必ず大便より先え血下る。近血と云ひ。臓毒の下血は必ず大便より後に血下るを遠血と云ふ。気海、補、脾の兪、補、百会、腎の兪、妙なり、関元。
【意訳】
下血
大腸に風邪がある場合、便の前に血がでる。これを「近血」という。
臓毒による下血は、便の後に血がでる。これを「遠血」という。
使用穴は、気海(補)、脾兪(補)、百会、腎兪(効果的)、関元、などである。
脱肛
【原文】
脱肛 肛門の出る病の事
一、肺の臓虚し寒る時は肛門出るなり。女産の時力を出し、又は幼児久しく腹下り臓寒る時は出るなり。懸枢、中脘、百会。
【意訳】
脱肛
肺が虚して冷えてしまうと肛門が出てきてしまう。女性がお産の際に力をだして出てしまうこともある。幼児が長く下痢をして臓が冷えると出ることがある。
使用穴は、懸枢、中脘、百会などである。
遺尿
【原文】
遺尿 覚えず小便たるる事
一、心腎の気虧け陽気衰へ寒て出るなり。関元、石門、中極。
【意訳】
遺尿
心腎の気が少なくなり、陽気が衰えて冷えてしまうことで尿漏れが発生する。
使用穴は、関元、石門、中極などである。
遺精
【原文】
遺精 夢に精泄るる事
一、邪気陰分に在りて神舎りを衛らず心に感ずる所有りて夢に精漏るるなり。腎の兪、大補、気海、補。
【意訳】
夢精
邪気が陰の部分に在り、神が舎りをまもれなくなったために、心が過剰に興奮し夢を見ている際に精液が漏れるのである。
使用穴は、腎兪(大きく補う)、気海(補)などである。
上気
【原文】
上気 気の上る事
一、下寒る時は気上るなり。三陰交、三里、百会、風市。
【意訳】
上気
下半身が冷えると、気があがってしまうものである。
使用穴は、三陰交、三里、百会、風市、などである。
腹痛
【原文】
腹痛 腹のいたむ事
一、腹の痛みは寒熱、食結、湿痰、蟲、虚実の故なり。
一、痛み増す事もなく減とる事もなく痛むは寒なり。腹俄に痛み卒に止するは熱なり。腹痛んで下り下って後痛み寛ぐは宿食なり。痛み所変らず一所にて痛むは死血なり。小便通ぜずして痛むは湿痰なり。腹引きつり腋の下鳴るは痰なり。腹痛み或いは止み面白く唇赤きは蟲なり。手を以て按せば腹柔かに痛み寛ぐは虚なり。腹張り硬く痛で手にて按されざるは実なり。内関、天枢、上脘、中脘、胃の兪、巨闕、梁門、石門、三陰交、三里。
【意訳】
腹痛
腹痛は寒熱、食結、湿痰、寄生虫、などによって起こされる。虚でも実でも発症する。
痛みが増すことも減ることもなく持続するのは、寒邪が原因である。
急に痛くなり、痛みが急におさまるのは熱邪である。
腹痛のあと下痢をして、その後痛みが楽になるのは宿食が原因である。
腹痛の場所が変わらずに、同じ場所が痛むのは死血である。
排尿困難で腹が痛むのは湿痰が原因である。
腹が引き攣り、腋の下が鳴るのは痰が原因である。
腹痛がしたり、おさまったりして、顔色が白く、唇が赤いのは寄生虫が原因である。
手で押したときに腹が柔らかく、痛みが楽になるのは虚である。
腹が張り、硬く、痛くて手で押すことができないのは実である。
使用穴は、内関、天枢、上脘、中脘、胃兪、巨闕、梁門、石門、三陰交、三里などである。
今回はここまでです。
一応、ここで「巻の上」が終了です。次からは「巻の中」です。
続きはこちら
