
1日10分の免疫学(58)IgE介在性免疫⑤
本「アレルゲンによって表皮の下のいるマスト細胞が活性化され、ヒスタミンが放出されると蕁麻疹(じんましん)と呼ばれる瘙痒(そうよう)を伴う膨疹(ぼうしん)が出現する」
大林「あの痒くてブワーッと腫れるやつね」
本「皮下深部で起こると、より広範囲で起き、血管性浮腫となる」
WEB「蕁麻疹は、真皮内の肥満細胞(マスト細胞)からのヒスタミン放出による血管透過性亢進により表皮を盛り上げる境界明瞭な膨疹。血管性浮腫は真皮深層、皮下組織深部での血管透過性亢進により局所的に膨隆した境界不明瞭な浮腫」
大林「どちらもマスト細胞の出すヒスタミンによる血管透過性の亢進で起こるけど、真皮内だと蕁麻疹、真皮深層だと血管性浮腫ってことか」
本「昆虫の刺咬傷は蕁麻疹の典型的な原因の1つです」
大林「えっ、じゃあ、蚊に刺されて痒くて腫れるのも蕁麻疹に該当するの?」
日本皮膚科学会「蕁麻疹は全体が平べったく膨らんだり、赤い輪のような形になる。数時間以内に跡かたなく消えてしまう。虫刺されとは異なる」
大林「なるほど」
アトピー性皮膚炎には未解明が多い
本「持続する皮膚のアレルギー反応はアトピーの小児に見られる」
大林「アトピー性皮膚炎!まだまだわからないことが多いんだよね…だからエセ治療法を信じてしまう人がたくさん……」
本「アトピー性皮膚炎の病因に関してはまだよく解明されていない。思春期で治癒する理由もよくわかっていない」
大林「そういえば私も小さい頃は関節のとこがアトピーだったけど中学とかで症状消えてた!」
本「アトピー性皮膚炎は、皮膚の防御機能が失われてアレルゲンが皮膚に侵入し、Th2による免疫応答を刺激されて起こるとされている」
大林「めっちゃ荒れてると隙間から樹状細胞が突起を出して抗原を捕まえに行ってるよね……教科書でそんな図を見たぞ。最近では乳児の肌ケアはともかく保湿!って言われてるよね。どこかの研究で、保湿した乳児とそうでない乳児のその後のアレルギー発生率に有意な差が出たとか。ソースは忘れた、ごめん」
本「遺伝的に皮膚の防御機構が弱い人はアトピー性皮膚炎の発症リスクが高いとの報告がある」
大林「皮膚はそもそも第一防壁だもんな、ケア大事」
本「皮膚の防御機能を維持するには、角質層が正常に形成されることが重要」
大林「角質……一番外側か」
本「プロフィラグリンが分解されてフィラグリンが作られ、フィラグリンの中の親水性アミノ酸が皮膚の保湿に重要である」
大林「フィラグリン?」
WIki「プロフィラグリンは、フィラグリンが10個から12個繋がった巨大なタンパク質。フィラグリンは、塩基性タンパク質の1種で、ヒスチジン・リッチ・プロテインとも呼ばれる」
大林「ん?なんか聞いたことあるような」
Wiki「フィラグリンが作られないと角質に異常が発生し、皮膚のバリア機能が低下する」
本「アトピー性皮膚炎の患者の約2割がフィラグリン遺伝子に変異を有する」
大林「フィラグリン……初めて聞いたけど大事だということは覚えておきたい」
本「皮膚の角化も大事なので、角化に関与する70個ほどの遺伝子の変異もアトピー性皮膚炎に関与している可能性も高い」
花王「角化とは皮膚のターンオーバーのこと」
大林「ターンオーバーなら化粧品屋で耳にタコができるほど聞いた。内側からどんどん新しい皮膚細胞ができて古い細胞が外側へ押し出される……硬くなって皮膚表面を守り、古くなり、剥がれ落ちていく……」
食物アレルギーについて
本「次は食物アレルギーについて」
大林「待ってました!経口の免疫寛容が気になります!免疫システムはどうやって色んな食べ物を排除か寛容かを判断してるの?!」
本「ヒトの食物は膨大な種類のタンパク質を含んでいて、すべて免疫応答を起こす可能性がある」
大林「食物はどんどん分解されていくよね、まず、タンパク質はペプチドに……」
本「そのペプチド段階でTh2細胞に提示されうる」
大林「せやね」

本「ある食物アレルゲンに一度感作されると、次にその食物を摂取したときに激しい即時型反応が起こる」
大林「えーと、そのアレルゲンに特異的なB細胞がつくったIgEがマスト細胞上のレセプターに結合し、そのIgEにアレルゲンが結合するとマスト細胞内部にシグナルが送られてヒスタミンとかを出す!そして血管透過性の亢進!」
本「その通り。血管透過性の亢進により血液から液体成分が消化管内腔へ滲出し、胃壁の平滑筋が収縮し、急激な腹痛と嘔吐が起きる。これらの反応が腸で起きれば下痢となる」
大林「しんどいやつだ……」
本「本来は、消化管に入り込んだ寄生虫を排除する目的で起こる反応」
大林「切ない。その食物が毒で有害なら役に立つ反応なのにな……」
本「無害な食物にアレルギー反応が起きると、腹痛や嘔吐によるダメージだけでなく、せっかく食べた物を排出してしまうという無駄も生じる」
大林「……で?本来は排除する必要のない食物にアレルギー反応が起きてしまう理由とは……?」
本「次はアレルギーの予防と治療について」
大林「いやいやいやもしもし?」
本は答えない!なんでや!そこ一番知りたいとこ!
アレルギー症状の緩和戦略
本「アレルギーの症状を緩和する戦略は3つある。1つ目は予防」
大林「アレルゲンを避けるってことか。食べないようにしたり、原因の動物に近寄らないようにしたり、使う製品を選んだり……」
本「2つ目は薬剤の使用。例えば、薬剤によってIgEとFcεRⅠやFcεRⅡとの結合を止めたり、炎症を抑えたりする」
大林「抗ヒスタミン剤とかアドレナリンとか……」
本「3つ目は、免疫学的手法」
大林「おっ、免疫学きた!どんなの?」
本「アレルゲン特異的IgEの産生を抑制する」
大林「なるほど、IgEが作られなければアレルギー反応は起きないよね。それはどうやるの?」
本「たとえば、抗体反応をIgG抗体優位に切り替えるという方法がある。脱感作desensitizationと呼ばれる」
Wiki「感作(かんさ、Sensitization)とは、繰り返される刺激によって、それに対しての反応が徐々に増大していく非連合学習プロセスである」
大林「なるほど、IgG優位にするってどうやって?」
本「患者にごく微量のアレルゲンを注射し、その量を徐々に増やしていく」
大林「なんかアレルゲンに慣らしていく感じ?舌下療法に似てるね」
本「脱感作に成功すると、Th2細胞応答でアレルゲン特異的IgG4が作られ、IL-10がつくられる」
大林「IL-10!それはたしか炎症を抑えるサイトカイン……抗炎症性サイトカインだよね?!」
◆復習メモ
T細胞:胸腺(Thymus)で分化・成熟する免疫応答を担う細胞。
ヘルパーT細胞は、サイトカインの分泌により様々な免疫応答を誘導・強化する、いわば「免疫の司令塔」の役割を担うT細胞。
ヘルパーT細胞には種類があり、メジャーなタイプはTh1,Th2,Th17,Tfhなど。
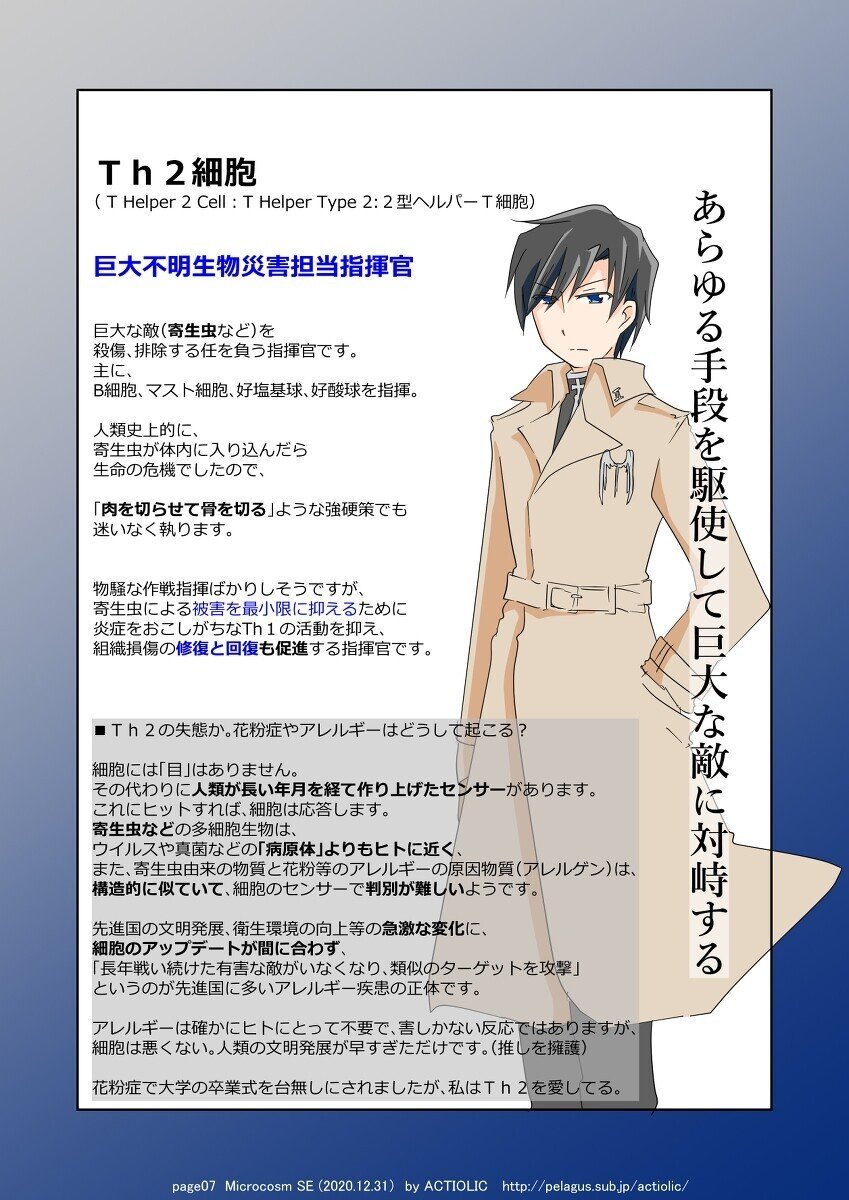
Ig(アイジー):免疫グロブリンimmunoglobulinの略記。抗体のこと。IgG、IgA、IgM、IgD、IgEの5種類のクラスがある。
「Y」の形をしていて、上半分の「v」がFab領域 (Fragment,antigen binding)と呼ばれ、抗原を掴む。下半分の「I」はFc領域 (Fragment, crystallizable) と呼ばれ、食細胞などの表面にあるFc受容体と結合する。「v」の先端(可変領域)は、アミノ酸配列を変更することができるので、多種多様な抗原に対応が可能。
サイトカイン(cytokine)
:細胞が分泌する低分子のタンパク質で生理活性物質の総称。細胞間の相互作用に関与する。cyto(細胞)+kine(作動因子※)の造語※kinein:「動く」(ギリシア語)に由来する
サイトカインの種類
>ケモカイン(Chemokine):白血球(免疫細胞)をケモカインの濃度の濃い方へ遊走させる(普段は血流等の流れに乗っている)。
>インターフェロン(Interferon;IFN):感染等に対応するために分泌される糖タンパク質※。(※タンパク質を構成するアミノ酸の一部に糖鎖が結合したもの)
>インターロイキン(Interleukin;IL:リンパ球等が分泌するペプチド・タンパク質。免疫作用を誘導する。)※見つかった順でナンバリング
>腫瘍壊死因子(Tumor Necrosis Factor;TNF):その名の通り、腫瘍を壊死させる機能を持つ。
本「IgG4は1価で反応して抗原抗体複合体を形成するが、エフェクター細胞は誘導しない。105ページを参照せよ」
大林「おおおい!えらい戻るな?!今424ページやぞ」
大林「復習ね……えぇと、IgGには4つのサブクラスがあって、IgG1,IgG2,IgG3,IgG4がある。H鎖(重鎖Heavy Chain)のC領域が異なる。IgG4は最も少ないサブクラスで、機能的には1価。中和作用でしか感染を制御できない。IgG4がアレルゲンに結合することでIgEとアレルゲンとの結合を阻害してアレルギー反応を軽減する…」
本「他の脱感作の方法として、アレルギー患者喘息患者の腸管に蠕虫を感染させるというものがある」
大林「聞いたことある!」
今後の治療法の研究
本「Th2細胞による適応免疫応答を阻害する単クローン抗体がアレルギーに有効な治療薬として期待されている。これを使うと、アレルギー症状を緩和できるし、他の病原体に対する免疫応答に副作用が報告されていない。寄生虫が根絶された環境にいる人はTh2細胞の免疫応答に必要な細胞や分子がなくとも健康に生きられる」
大林「あの……推しが……ちょっと哀しいんですが……存在価値……」
本「蠕虫感染が蔓延している発展途上国では生後すぐに蠕虫に感染し、寄生虫特異的IgEを母親から受け継ぐ」
大林「推しが活躍……」
本「先進国では、蠕虫由来の抗原に遺伝的にも構造的にも類似したアレルゲンに対するアレルギー疾患が出現。蠕虫が排除されたことで、蠕虫免疫で自然選択されてきた正常なTh2応答まで排除され、Th2応答は自然選択を受けないという異常な方向に発達してしまった」
大林「あ!待って?!なんかわかった気がする、その説明わかりにくいけど、なんで推しが敵を間違えてアレルギー起こしてるのか?それだ!それが理由だね???!自然選択を受けることができていない!!!」
本「蠕虫感染が蔓延している地域では、寄生虫への免疫応答はバランスがとられ、免疫系が発達する。つまり、寛容すぎれば寄生虫に苦しみ、免疫が強すぎればそれに苦しむ。寄生虫への寛容と抵抗のバランスにより健康を保つ」
大林「なんとなくわかってきたような?!免疫応答がバランスを手に入れるには、免疫応答が生ぬるいと寄生虫に負ける、免疫応答が強すぎると自分にダメージすぎるという両側からのプレッシャーが必要ってこと?どれくらいがいいのか、自然選択を繰り返していくうちに免疫はよりよい応答を手に入れるってこと?かな!?」
本「次回は第15章 組織と臓器の移植」
大林「おっ、自己非自己な話かな~たのしみ!」
今回はここまで!
★細胞の漫画を描いています。よろしければどうぞ!↓
