
成熟経済下において有効な財政政策を考える
まず、直近の衆院選のマニフェストにおいても、立憲民主党を除き、全ての野党が、"消費税の減税"という財政政策を掲げておりました。
しかし、小野善康氏の著書『資本主義の方程式 経済停滞と格差拡大の謎を解く (中公新書)』に記されている通り、今の日本経済の状態は、戦後からバブル崩壊までの日本が経験したような成長経済ではなく、バブル崩壊後からは、成熟経済に移行していると見て、間違いないと思います。
ですから、後述するように、"消費税の減税"のような成長経済下で有効とされる政策は、今現在の日本においては、企業の内部留保や富裕層の貯蓄を増やすだけに終始し、財政赤字を拡大してしまうだけの無意味な政策となってしまう可能性が高い訳です。
ですから、今回は、成熟経済の持つ性質と成熟経済下において有効な政策について、私見を述べさせていただこうと思います。
1.成熟経済特有の現象

①消費よりも、貯蓄や投資を優先する国民が大半となる
まず、成熟経済下においては、"国民の所得を増やせば、消費が増える"という図式が成り立たなくなります。
何故なら、一定程度以上の金融資産を持つ国民は、消費欲よりも、資産選好の方が強く、所得が増えたとしても、消費ではなく、貯蓄や投資に回すという性質を持っているからです。
ですから、ベーシックインカムや所得税の減税等の手段で、高所得者や金融資産をある程度保有している国民に対し、その所得を更に増やすような財政出動を行ったとしても、消費を増やす効果は、殆ど無いと言えるという事です。
②基本的に、企業による設備投資や人材への投資が伸びる事は無い
また、同様に、資産選好が強い国民が多いと、いくら供給力を延ばしたとしても、需要は殆ど伸びないという結果も得られます。
つまり、供給力を増やしても意味が無い以上、基本的に、企業による設備投資が伸びる事は無いという事です。
同様に、賃上げ等の人材への投資についても、同じ事が言える訳です。
ですから、結果的に、国民が、消費を行わず、貯蓄や投資を選好する事に伴って、企業も、設備投資や人材への投資を控えるようになり、内部留保を貯め続けるようになるという事です。
2.企業や富裕層は、成熟経済下においては性悪な主体となる
冒頭で述べたような、"消費税の減税"という政策は、企業が、性善的な主体として、企業収益が増えた分、従業員の給与を引き上げる、あるいは、商品価格を引き下げるという行動を起こして、初めて有効となる訳です。
しかし、前述の通り、人件費を増やしたり、商品価格を引き下げるという、言わば、供給力を増やすという行為を行っても、成熟経済下においては、売上が増える事はありませんから、企業は、性悪的な主体にならざるを得ず、企業収益が増えたら、ただ内部留保を増やすだけという結果になってしまう訳です。
また、前述の通り、一定以上の金融資産を持つ国民も、所得が増えても、消費を増やしませんから、同様に、政府にとっては、性悪的主体であると見做せる訳です。
3.具体的何を行うべきか?
本章では、具体的に、成熟経済下において、有効だと思われる政策について4つの政策を提唱させていただきます。
①国民年金支給額を増やす
確かに、一定以上の資産を持つ国民の所得を増やす政策は、何の意味も成さないと言える訳です。
しかし、逆に言えば、可処分所得が低い国民については、財政出動を行えば、消費に直結する作用があると言える訳です。
なので、国民年金しか受給出来ていない高齢者は、困窮している場合が多いため、財政出動を行えば、直ちに、消費を向上させる効果があると考えて問題無いと思います。
②20代~30代の若者をターゲットに財政出動を行う
①の場合と同様に、20代~30代の若者は、年功序列制度によって、基本給が低めに設定されているにも拘らず、社会保険料の支払いや奨学金の支払いに加え、家庭を持つ方々であれば、子育て費用も掛かる訳で、高齢者と同様に、貧困に窮している若者は多いと考えられます。
ですから、20代~30代の若者に対しては、社会保険料の大幅減免を行ったり、住宅手当や公営住宅の提供等の現物支給等も多様しながら、しっかりと財政出動を実施する事が、景気の向上に繋がると共に、出生率の増加にも繋がり得ると考えております。
③国民の貯蓄欲を満たすような金融商品を作る
成熟経済下において、一般的な国民は、資産選好を持っており、株や債券等の金融商品に対する支出は、当然に高まる事が考えられます。
しかし、そういった典型的な金融商品に加え、不動産、高級車や高級時計、一部には、ポケモンカード等、成熟経済下においては、ただ消費するだけで終わるだけではなく、その商品を持ち続ける事自体に価値が見い出せるような、言わば、投資の側面を持つような、"人々の投資欲を満たすような商品"の人気が高まるとも言える訳です。
ですから、規制緩和や補助金による産業誘導によって、そういった金融商品や準金融商品を作る事業者を支援する事が、消費の活性化に繋がる可能性は大いにある訳です。
地方の不動産価格を向上させる事によって、大幅な経済成長が期待出来る
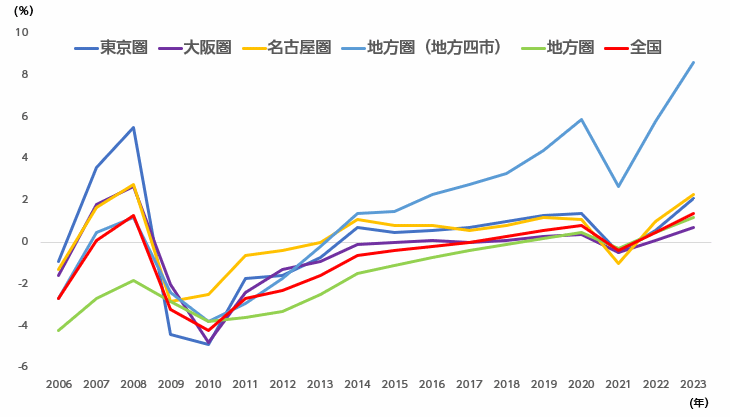
特に、地方の不動産については、東京への人口流入が続いている事もあり、全国的に、地価は向上しているという事情背景はあるものの、東京の不動産価格に比べれば、まだまだ伸びしろがあると言えるでしょう。
なので、政府主導で、地方創成を成功させる事が出来れば、地方の不動産価格を向上させる事が出来、それに伴い、消費が一気に膨れ上がり、大幅な経済成長が見込める可能性が高い訳です。
④規制緩和によって、新たな商品・サービスを作り出す
そして、非金融商品であったとしても、目新しい商品やサービスであるならば、一定程度、消費が伸びる事が期待できる訳です。
ですから、規制緩和やベンチャー企業に対する投資誘導等によっても、消費を活性化する作用は見込めるでしょう。
まとめ.
以上をまとめれば、成長経済下において有効な政策は、成熟経済下において有効な政策とは、180度異なると結論付けられる訳です。
なので、基本的には、企業や富裕層、高所得者は、貯蓄や投資に専念するような性悪説に基づくような主体となってしまっており、消費税減税等を行っても、小規模事業者を除いては、良い効果が見込めない事が推定されます。
ですから、一般庶民である労働者や高齢者が得をするような政策を実施する際には、高い消費税や高い社会保険料を事業主から取った上で、労働者や高齢者の所得やその他福祉に還元するというやり方を取らざるを得ないという事です。
また、所得を増やすような財政出動を行う場合は、国民年金受給者や20代~30代の若者世代等、可処分所得が低い国民に的を絞って実施するという事が、消費を増やし、景気を向上させるという目的を果たす上では、財政的に見て、最も効率が良いと言えるでしょう。
更に、成熟経済において、特筆すべき点は、"経済の主体が、非金融商品から、金融商品に転換される"という事です。
何故なら、資産選好を持った国民が大半となるため、そういった国民にとっては、従来の非金融商品は魅力的に映らず、消費の対象とは成り得なくなるからです。
そのため、第二次安倍政権が実施したアベノミクスによって、日本の株価が大幅に上がった訳ですが、そういった観点から見ると、賛否両論はあるものの、成熟経済に適した、非常に良い政策であったと言えます。
また、前述の通り、今後、日本が、大きな経済成長を果たせるか否かというのは、地方創生を成功させ、地方の不動産価格を向上させる事が出来るかどうかという事に、全てが掛かっていると言っても過言ではないと思っております。
なので、そのための手法として、"地方分権"というのは、年々予算の制約が増している今の日本政府にとっては、最も現実的で、唯一の手段であると考えられる訳ですので、各地方自治体に対し、立法権の譲渡を伴う本来の地方分権が推し進められる事の必要性は、今後更に高まっていくと考えております。
参考文献.
・資本主義の方程式 経済停滞と格差拡大の謎を解く (中公新書)
いいなと思ったら応援しよう!

