
ベストアルバム 2024
はじめに
2024年もおつかれさまでした。
ストリーミング時代以降、「アルバム」という概念が揺るがされるのに伴って「年間ベストアルバム」という価値づけに疑問が呈されるようになっています。多くのライターを擁する大手メディアであっても、無数に存在する世界の音楽作品を一つの視点から捉え、その良し悪しを判断すること自体も不可能だと浮き彫りになってきました。
さらには、選出したアルバムを順位づけすること自体も過去のものとなりつつあり、ベストアルバムの「リスト」といった風に、作品をアルファベット順に発表するメディアも増えてきました。
それではリスナー個人単位の年間ベストはどう発信するべきか。毎年この時期になると悩みますが、今年は素直に慣例に従って、私が「よく聴いた」「衝撃を受けた」アルバムを25枚選び、1位から25位に順位づけすることにいたしました。
あくまで今年私が個人的に楽しんだ作品の羅列であり、何かを代表するリストではありません。私の音楽遍歴、あるいは音楽名刺としてお読みください。
またこのランキングでは、2023年12月1日から2024年11月30日にリリースされたEP、LP、ミックステープを「アルバム」と定義しています。
25. Bells Collection - M.I.A.

🕊🇵🇸🕊🇵🇸🕊🇵🇸🕊🇵🇸🕊🇵🇸🕊🇵🇸🕊🇵🇸🕊🇵🇸🕊🇵🇸🕊🇵🇸🕊🇵🇸🕊🇵🇸🕊🇵🇸
24. No Name - Jack White
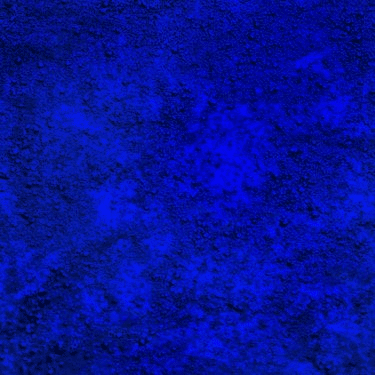
この手のギターロックを全く聴かない私でも良いと思ったのだから、とりあえず聴いてみてほしい。The White Stripes(ザ・ホワイト・ストラプス)かと思うほどにシンプルで大味。雑で乱暴なように聴こえて、全く嫌味がない。ロックの定義を「大きな岩がゴロゴロと転がっていく感じ」とするならば、この作品はそんな音がする。
匿名になることも制度に取り込まれないことも難しい時代において、極秘の販売方式で「名無し」の作品をリリースしたこと自体に、一定の価値があるはずだ。
Best Track: Old Scratch Blues
23. Where the Butterflies Go in the Rain - Raveena

ジャズからサイケロック、ニューソウルとネオ・ソウルまでを網羅し、そこにインドのオリジナリティを合わせたコンテンポラリーR&B アーティストの3枚目。
本人が受けた音楽的影響を包み隠さず、上手くブレンドしてアウトプットしたのが今作だ。どの楽曲もバンドサウンドを主体としており、ときどき聴こえるシタールやタブラ(インドの打楽器)のバランスは、まさにRaveena(ラヴィーナ)のアメリカとインドのアイデンティティを体現しているよう。ブラックミュージック由来の快楽とグルーヴのドラミングと、インディロック版Jill Scott(ジル・スコット)のような発声を有していながら、結果的に私たちが受け取る印象は、妖艶さと癒し。さまざまなサウンドを取り入れてリスナーを刺激すると同時に、唯一無二の「Raveenaサウンド」に仕上げている。
Best Track: Rise
22. C,XOXO - Camilla Cabello

ROSALÍA(ロザリア)やSampha(サンファ)のプロデューサーとして知られるEl Guincho(エル・ギンチョ)が全面的にプロデュース。この情報だけで察する通り、今作はFifth Harmony(フィフス・ハーモニー)時代の音楽や、これまでのソロの馴染みやすいラテン・ポップとは決別している。このレコードを聴く上で、前作までのCamila Cabello(カミラ・カベロ)を参照するのは無意味だ。ピッチフォークは今作を「誤って声明/ステートメントアルバムというレッテルを貼られしまった、過渡期のレコード」を評しており、今作は32分という短尺も相まって、何かが「始まる」のには早急で、何かが「終わる」のにも粗雑でたしかに説得力に欠ける。
つまり今作には「何も無い」と言えてしまうのか。いや、それは言い過ぎだ。彼女が挑戦は間違いなく新しいことに挑戦してはいるし、プロデューサーの絶妙なプロダクションによって、トラックの各々の完成度は高いところに収まっている。巷ではグリッチ/ハイパーポップへの接近と評されているが、それは早合点な気もするし、模倣にしかならないことは本人も重々承知だろう。
この状況を逆手にとって、彼女はあえてカオスを表現しようとしたのではないだろうか。ほとんどのリリックには脈略がないし(「Chanel No.5」のフックの意味のなさ!)、「pretty when i cry」で突然シカゴ・ハウスが鳴り始めるように、『C,XOXO』は文脈から解放されたカオスだけで成り立っている。
一方でそのカオスは計算されたものでもある。反復のメロディや緩急のあるボーカルアレンジは、これまで比べてポップさよりも Hip-Hop やクラブミュージックのリズム感を追求した結果であるように感じる。やはりPitchforkが評したように、彼女の中にある音楽性を一度すべて解体して乱雑に組み直した、「これからのための」一枚なのかもしれない。
Best Track: HOT UPTOWN (feat. Drake)
21. TYLA - Tyla

プエルトリコのレゲトン、韓国のK-POP、ナイジェリアのアフロビーツに続く、ローカルの大躍進。南アフリカ音楽の旗手をたった一人で担うことになったTyla(タイラ)はそのデビュー作において、気負うことなくローカルのプライドとグローバルポップの感性を提示する。北米での商業的な反応などもろともせず、Sammy Soso(サミー・ソソ)やBelievve(ビリーヴ)などのアマピアノ/アフロビーツのプロデューサーたちとがっつりチームを組んで、南アフリカの総合力を見せつけた。
若くして圧倒的なディーヴァ然を魅せるTylaは、同じくローカル出身で北米のアウトサイダーであったRIhanna(リアーナ)の姿を追っている。2010年代のマルチ・カルチュラリズムの果てに起こった、世界が祝福すべきデビューアルバム。
Best Track: Water
20. What Now - Brittany Howard

ジャズ、ソウル、ファンク、ロック、サイケデリア、ハウスに至るまでを丸ごと飲み込むその演奏力とアレンジは、Alabama Shakes(アラバマ
・シェイクス)から引き継がれるさすがの才能としか言いようがない。
幽玄なボーカルコーラスに包まれ、アートワークのように大空の下で大地に身を任せたくなる反面、何かに怒り、何かを渇望するようなパワフルさと切迫感も感じる。それはおそらく、彼女の音楽性に脈々と流れるブラックネスやクィアネスがそうさせる。彼女は私たちを祝福してくれるが、随所で疑問もばら撒いてくれる。「今はどうなってる?」と。
Best Track: Prove It To You
19. Baggy$$ - Fcukers

2024年のダンスシーンは緑色に染まったわけだ(もちろん『BRAT』のことだ)。緑色一派の一員として、「Guess」をプロデュースしたニューヨークの新星The Dare(ザ・デア)ことHarrison Patrick Smith(ハリソン・パトリック・スミス)がデビューLP『What’s Wrong With New York?』をリリースしたまさに同日、同じくニューヨークからもう一つの星が輝きを見せていたのをご存知だろうか。名門Ninja Tune傘下のTechnicolorからデビューしたFcukers(ファッカーズ)は、無鉄砲なニューヨークのパーティライフをさらに鮮やかに彩る。ステディながらもハードな「Bon Bon」、PinkPantheress(ピンクパンサレス)以降のブレイクビーツ「Heart Dub」、カウベルが心地いいプリミティブなハウスの「Homie Don’t Shake」、マイアミベースとハウスで二度美味しい「Tommy」など、これさえあれば何もいらないと思ってしまうほどの満足感。
Best Track: Tommy
18. Two Shell - Two Shell

ロンドンの覆面エレクトリックデュオ、Two Shell(トゥー・シェル)のセルフタイトルデビューLP。彼ら/彼女らの鳴らすサウンドには、いのちが宿っている。いのちと言っても体温を感じるような人間の肉体ではなく、ダンスフロアに迷い込んだエイリアン(ヴェノムのようなスライム状の生命体を想像してもらいたい)が、音に合わせて身体部を触手状に伸ばしながら感情を獲得していくようだ。おどろおどろしくて近くに抱き寄せたい存在ではないが、幾分かの有機性をもった無垢な存在のように思える。ハイパーポップ以降のUKクラブシーンの雑多な状況とTwo Shellの匿名性(=得体の知れないモノ)が、そういった感覚を生み出すのだろう。
Best Track: (rock☆solid)
17. Deceltica - Koreless

煮えたぎる。私はこの表現が好きだ。怒りの文脈ではなく、音楽性の文脈において。私にとって最も煮えたぎっているサウンドは、Funkadelic/Parliament(ファンカデリック/パーラメント)のベースと、D’Angelo(ディアンジェロ)のシャウト。ファンクに肉体性だけでなく、いかがわしさとおぞましさを感じるときに、「煮えたぎってるな」と表現したくなる。ファンク以外の例外こそが、Koreless(コアレス)が構築するようなエレクトロニックサウンドだ。お湯は煮えたぎる直前に微かに音を立てて燻っているように、あるいはビッグバンが起こる直算に真空が揺らいでいたように、Korelessは膠着状態と爆発とを同時に表現する。膠着と爆発とは、ダンスミュージックの必要最低限の公式でもある。
Best Track: Deceltica
16. CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator

ヒップホップはもはや、メインストリームの隅に追いやられた、音楽オタクたちのための嗜好ジャンルに成り下がっている。いや、むしろ成り上がっているか。というか、右往左往している。まさに縦横無尽。つまり今のヒップホップのキャンバスは無限に広がった状態で、自分の好きな筆で、自分の好きなスペースに、自分の好きなように描くしか方法がなく、それが最適解として落ち着いている印象がある。つまりそれは、Tyler, The Creator(タイラー・ザ・クリエイター)の音楽性そのものではないか。
「ラッパー」や「ヒップホップアーティスト」というより、「コラージュアーティスト」の肩書きの方がTylerには合う。彼が良いと思ったサウンドをひとつずつ重ねていくプロダクション然り、ジャンルという概念が端から放棄されている越境的なアイデア然り、そういったところにユニークさとギークさを感じる。彼の音楽はヒップホップではなく、嗜好ジャンルとして聴いた方がしっくりする理由だ。
対話(Tylerの場合は母との対話)を通じて自己の内省に耽るという点で今作をKendrick Lamar(ケンドリック・ラマー)の『Mr. Morale & The Big Steppers』と比較する声は多い。今作はいくつものコラージュで覆い隠された「自己」を剥がしてく、これまでの作品とは逆の性質をもったアルバムという説明もできるのではないだろうか。アートワークで着けている仮面は「自己」を覆い隠す象徴だ。
加えて、今年10周年を迎えた主催フェスCAMP FLOG GNAW CARNIVALのステージでサプライズ共演を果たしたChildish Gambino(チャイルディッシュ・ガンビーノ)の新作『Bando Stone and The New World』も併せて聴いてもらいたい。かつて”stay woke”と歌ったChildish Gambinoは民主党政権の終焉と共に幕を自ら閉じ、Tyler, The Creatorへバトンを繋いだのだから。
Best Track: Noid
15. ORQUÍDEAS - Kali Uchis

Tyla(タイラ)然り、Rauw Alejandro(ラウ・アレハンドロ)然り、ローカルな音楽をグローバルに展開していくには、ハウスやR&Bのフォーマットに乗せるのが常套手段のひとつになりつつある。そういった意味でKali Uchis(カリ・ウチス)は、デビュー当時からコミットしているソウルやコンテンポラリーR&Bの音づくりに、ラテンポップを多層的にブレンドする手法をとっている。
例えば M5「Diosa」はダンスホールの響き。しかし、ラテンの感覚で解釈したアマピアノという捉え方もできる。ボレロの M6「Te Mata」にしたって、キューバ音楽としてプレゼンしているのではなく、ユニバーサルなスロウなダンスナンバーとしてプレゼンしている気概を感じる。ROSALÍA(ロザリア)の「BIZCOCHITO」を思わせる M10「Muñekita」に参加しているEl Alfa(エル・アルファ)とCity Girls(シティ・ガールズ)のJTのラインナップがKali Uchisの音楽性を体現していて、ドミニカとマイアミの両方のフレイバーを楽しめる。
Kali Uchisが現代のクイーン・オブ・ラテン・ポップなのは間違いない。彼女が今のプロップスを築いているのは、最新の音楽トレンドに食いつく姿勢のみならず、過去の音楽への深い造詣と愛情も有しているからだろう。
Best Track: Igual Que Un Ángel (with Peso Pluma)
14. Alligator Bites Never Heal - Doechii

2024年がこんなに汚い年になるとは思わなかった。いや、思いたくなかった。特にツイッターの話だ。しかしそれでも私たち音楽オタクは、ツイッター上で人生の一部を費やす運命にある。抜け出せるのなら抜け出したい。こちらがどれだけ誠実でいても、意見が異なる人との対話は成り立たず、同じ意見をもった人との言論空間はエコーチェンバーでしかない。結局自分で取捨選択していくしかないのだが、「自分」という絶対的な存在は、自分にとって案外難しい。自分は結局、他者という相対的な存在の産物に過ぎないのか。他者と心地よい距離を置いて、自分の夢のために居場所を求めて彷徨っても、そこでも発生する家賃。あぁ、また物質だ。働かなきゃ。でも、自分のスタイルを忘れちゃダメだぞ。こんな世の中、ワニのように凶暴に、そしてニヒルにいなきゃやってられない。
Best Track: NISSAN ALTIMA
13. All Born Screaming - St. Vincent

幾度となく自身のペルソナを変化させ、数多くのコンセプトアルバムを作ってきたSt. Vincent(セイント・ヴィンセント)が、今度はありのままの姿を見せてきた。
インダストリアル、グランジ、P-Funk、サイケデリアなど、異なるテイストのトラックが矢継ぎ早に展開されていくが、不思議ととっ散らかった印象がないのは、すべてのサウンドが彼女のアイデンティティに即したアクチュアリティを有したものだからだろう。すべて、「ギターを手にしたAnnie Clark(アニー・クラーク:彼女の本名)」から生まれた愚直なほどに真っ直ぐな音楽なのだ。
アルバム自体はシアトリカルに進んでいく。M6「Violent Times」以降終盤に向かって、一つの大きなうねりが収束していく。それもそのはず、彼女が愛を隠さずに表現しているNirvana/Foo Fighters(ニルヴァーナ/フー・ファイターズ)やNine Inch Nails(ナイン・インチ・ネイルズ)、Radiohead(レディオヘッド)は、どのバンドも劇場音楽の常連。『All Born Screaming』は、脚本、監督、プロデュースを彼女が単独で担当したSt. Vincentの伝記映画であり、ドキュメンタリーのようなアルバムだ。
Best Track: Broken Man
12. Naya - Dawuna
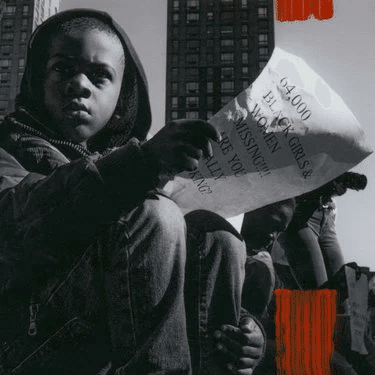
【Dawuna『Naya』の作り方】
① Sly & The Family Stone(スライ・アンド・ザ・ファミリー・ストーン)、Prince(プリンス)、D’Angelo(ディアンジェロ)の代表作を聴いてください(すでに熟知している方は、この工程は飛ばして構いません)。
② 身体で感じたグルーヴを、各パーツに分解してください(ベース、ドラム、ボーカル、ギターといった具合に)。
③ 分解したパーツに、良い感じに小さな傷をつけてください。
④ 散らばったパーツをいくつか拾い、あなたの思うように組み直してください。すべてのパーツを使う必要はありません。他のアーティストのパーツを拝借してみてもいいでしょう。
⑤ 脱構築されたファンク、もとい『Naya』の完成です。
Best Track: Brian
11. Night Reign - Arooj Aftab

以下、「音楽」と「歌詞」と「言語」と「批評」に対する私なりの反抗。
〜〜〜〜〜------------〜〜〜〜〜
/ \
/ \
| = = = = = = = = = = |
\ /
| |
\ ______ /
\_/ \_/
Best Track: Aey Nehin
10. Lives Outgrown - Beth Gibbons

誰もいない早朝の海岸沿い。コートを着た一人の女性が足を組んでベンチに座っている(この女性を演じるのは、自分の想像ではCate Blanchett(ケイト・ブランシェット))。右手にタバコをかかえながら、女性は思索に耽る。年を重ねて得たものといえば、白髪と顔のシワと、友人への上っ面の同情の仕方くらいだろうか。そんなことを今にも呟きそうな表情を浮かべている。
この10年で、私はいろいろなものを失った。時が私の側を通り過ぎる度に、私の一部も一緒に、連れ去られてしまう。自分を形作っていたはずのものがなくなっても、私は私でいられるのだろうか。こう考えた瞬間には、少なくとも3人の「私」が同時に存在している。私が思い描く私と、実際に存在する私、そしてその2人を観察する私。可能性意味論的に言えば、どの私の存在も正解で、同時に間違いである。だからキャリア30年にして初めてのソロアルバムは、一次元的な聴かれ方を拒絶する。アートワークのピントの合わない4人のBeth Gibbons(ベス・ギボンス)は、私のそれぞれの変異体として、私の中に同時に存在しているからである。オーケストラ、アンビエント/チェンバーフォーク、どこかソウル漂うボーカル、映画音楽としての過去のPortishead(ポーティスヘッド)のニュアンスが、2024年のBeth Gibbonsを創りあげていることを、この作品は真摯に訴えかけている。
ふらふら歩いていたコートの女性が足を止めた。諦念にも希望にも哀愁にも感じられる表情を、彼女は浮かべいている。
Best Track: Beyond The Sun
9. Fabiana Palladino - Fabiana Palladino

Quincy Jones(クインシー・ジョーンズ)が逝った。80年代の音楽を彩った星がまた一つ、消えていった。しかし、形を変えて、あるいは現代の望遠鏡を使うことで、かつての星たちは未だ観測可能である。Jai Paul(ジェイ・ポール)と兄のA. K. Paul(A. K. ポール)が立ち上げたレーベルPaul InstituteからデビューしたFabiana Palladino(ファビアナ・パラディーノ)は、ポストJessie Ware(ジェシー・ウェア)世代を担うUKジャズシーンの新星としてその命を灯し始めたばかり。
デビュー前から多くの著名アーティストと共演していたこともあってか、この作品はデビュー作とは思えないほど自信に満ち溢れている。AOR、アーバンコンテンポラリー、あるいはMTV時代のポップスを作ってきた当時の巨匠たちの軌跡を丁寧に辿るようにして紡がれた10曲のトラックには、的確な理解とアプリシエーションがある。その基盤があるからこそ、彼女の大胆性と自信のすべてが魅力に変換されるのだ。大きなリバーブだって、彼女の音楽的な開放感と自由の精神を音像化したようなものではないか。
Best Track: Can You Look In The Mirror?
8. Mahal - Glass Beams

オーストラリアはメルボルンから出てきたNinja Tune所属のスリーピース覆面バンドのEP。音楽性の中心を成すのは60年代サイケ。オーストラリアのサイケと言えばTame Imapla(テイム・インパラ)ことKevin Parker(ケヴィン・パーカー)がまず思い浮かぶが、彼との違いは、Glass Beams(グラス・ビームス)にはインドを中心としたアジア宗教音楽のニュアンスがビビッドにバンドサウンドに取り込まれていること。且つアレンジは比較的シンプルでLo-Fiの要素さえ感じさせる。茶色を基調としたシンメトリーのアルバムアートワークに、宗教感漂う覆面(『Dune』のベネ・ゲセリット的な)と、彼らの世界観を完全に構築している。2024年最優秀「何コレ?!」アルバム。
Best Track: Mahal
7. Only God Was Above Us - Vampire Weekend

「“世界なんてクソくらえ”
静かに君は言った
誰にも聞こえない
僕以外の誰にも」
(「Ice Cream Piano」)
「紛い物の占い師は
運命に呆れ返る」
(「The Surfer」)
「判決は覆る
殺人犯は釈放される
法廷は中断される
希望は裏切られ
訓えが届けられる
君が全部手放せばいいのに」
(「Hope」)
増幅するノイズに紛れ、視界を失った世界市民。その希望は、本当の希望なのか。そんなことを考えていたら、神だけが残っていた。
Best Track: Hope
6. Still - Erika de Casier

今や「NewJeansの作曲家」と言った方が伝わりやすいだろうか。2021年の『Sensational』でその名の通りR&Bシーンにセンセーショナルを起こしたErika de Casier(エリカ・デ・カシエール)は、同作よりももっと多くのレイヤーを重ねた『Still』で帰ってきた。
若い頃にデンマークに落ち着いた多国籍なバックグラウンドをそのまま体現したようなサウンドメイキングが彼女の魅力そのもの。北欧のエレクトロニクス/クラブミュージックがまずベースにあって、そこに90's R&B、80'sバラッド、2ステップをはじめとしたUKクラブミュージックをブランドしていく。生楽器、冷たいシンセ、断片的なサンプルの階層的な使い方は、ジャンルの階層性に説得力をもたせるのに一役買っている。
さらに面白いのは、M1「Right This Way」やM5「ice」から感じられるGファンクのフレイバー。強めに鳴るキックとスネア、太めのベースは、どこか西海岸の香りがする。彼女の流動性は楽々と海を超えている。
Best Track: Lucky
5. Two Star & The Dream Police - Mk.gee

Z世代の私からしたら、80年代は不思議な時代だったのではないかと事あるごとに思う。多くのジャンルがクロスオーバーして「MTV時代」と後に形容され、今でも現役の名電子楽器が数多と登場してサウンドが再定義されていった時代。煌びやかで大衆的な「大ポップカルチャー時代」のイメージがありながら、新自由主義の闇の部分と数々の紛争が影を落としていたことも、私たちは後から学んでいる。
それでもMk.gee(ミック・ギー)をはじめとした若いアーティストが未だに未知の時代、80年代を参照するのは、まだ80年代のサウンドに再定義、再解釈の余地があるからである。『Two Star & The Dream Police』を一聴した頭に浮かぶのはもちろん、Prince(プリンス)、Phil Collins(フィル・コリンズ)、The Police(ザ・ポリス)などのレジェンドたち。しかしMk.geeのサウンドはもっと自由で直感的である。DIYの延長にあり即興性を大切にしていながらも、80年代のシグネチャーサウンド(Princeのギター、ゲートリバーブスネア、煌びやかなシンセなど)に対する一つ一つの選択は、緻密で間違いがない。Mk.geeはキャリアを始めた頃は元々ボーカリストとして歌うことは意図していなかったようだが、彼のボーカルデリバリーもトラックの一部としてしっかりピースにハマっている。彼は、Princeの歌声を脱構築したFrank Ocean(フランク・オーシャン)の歌声を我が物にした後に、またさらに80年代のサウンドに合うように解釈し直しているように感じる。このアプローチを経ることで、オーディエンスは「郷愁」の80年代に、幾分かの新鮮味を見出せるようになるのだ。
『Two Star & The Dream Police』の楽曲群は、はっきりとした輪郭を持たない。曲の構成はないも同然で、一曲聴いて非道く感動したとしても、どんな旋律が鳴っていたか思い出そうとすると、指の間をすり抜けていく感覚がする。まるで夢のよう。まぁしかし夢とはそういうものだし、だからこそ美しい。目が覚めて「幻想的な夢を見た」ことは覚えていても、実像は思い出せない。残るのは、儚い感覚だけだ。『Two Star & The Dream Police』は、いつかの夜に見たことのある夢そのもの。
Best Track: How many miles
4. Cascade - Floating Points

あの頃の気持ちいい音を鳴らしてみろ。何者かにそう諭されたかのように、Floating Points(フローティング・ポインツ)こと Sam Sheperd(サム・シェパード)はマンチェスターで過ごした少年期に立ち返る。
Floating Points単独名義での前作『Crush』はどこか内向きな緊迫感があり、何かが爆発する寸前でずっと燻(くすぶ)っているようなアルバムだった。対する今回の新作『Cascade』は音響の総合芸術作品というより、もっと直感的でシャープなクラブバンガー集だ。
オーケストラやジャズ、アンビエントに至るまでの広い知見と演奏力をもつSam Sheperdのこれまでのディスコグラフィが、彼がいくつもの点を絶妙な距離感覚で配置していく過程を示していたのならば、『Cascade』は点をひとつポツンと、時にもうひとつ点を足して豪快に線で結ぶ過程をキャプチャーした作品だ。点と点の比喩は大袈裟でも何でもなく、彼はFloating Points(浮動小数点数)なのだから、全く的外れな表現ではないはず。
人間の身体には微弱な電気が流れている。こういった話は神経科学のPhDをもつ彼の専門分野であるはずで、『Cascade』からもその電気の感覚は伝わってくる。しかし彼の音楽の面白さは、電気の無機質さの中にも一抹の人間らしさ、言い換えれば筋肉、もっと言えば肉の塊を感じるところだ。M7「Afflecks Palace」の終盤にアグレッシヴな生ドラムが入ってくるあたりはまさにそう。感覚的、快楽的でいることに重きを置いていながらも、人間という肉の塊からは解放され得ないことを十分に理解しているのだ。
Best Track: Key103
3. COWBOY CARTER - Beyoncé

“It’s more than a concert. It’s culture.(これはただのコンサートじゃない。文化だ)”
『RENAISSANCE』ワールドツアーのコンサートフィルムの中でBeyoncé(ビヨンセ)は語った。そう、Beyoncé(ビヨンセ)とは今や文化であり、産業そのものだ。3部作の第2章にあたる『COWBOY CARTER』で彼女は焦点をグッと広げ、アメリカの埋もれてきた歴史にスポットライトを当てる。ここでの彼女は、Beyoncéというメディアと化す。同作が架空のラジオステーションというコンセプトを有しているのはそのためだ。
カントリーのみならず、サイケ/ポストサイケ、バロック、ゴスペル、ひいてはオペラまで取り込んだ壮大なタペストリーの情報量の多さに圧倒されるが、それこそが本来のアメリカポピュラーミュージックの歴史の厚み。
歴史から無視され、歪められ、消えていったいくつもの魂たち。彼女は自身のプリズムを通して、その魂たちにもう一度息吹を吹き込んでいく。
歴史の守護神を引き受けた彼女は白馬に乗って、東西南北、過去現在未来を縦横無尽に駆け巡る。このアルバムは、聴く者の罪すらをも浄化する作用をもった「救済」と「再生」の物語。終わりゆくアメリカに「祈り」を。
Best Track: YA YA
2. HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish

このレコードをポップな作品と感じるか否かで意見が分かれるのは面白い(私は前者だ)。そのこと自体が、それだけ間口の広い、リスナーの感性に委ねられた優れた一枚であることをすでに証明している。
前作『Happier Than Ever』で半ばポップアイコンの座から降りた彼女は、今作では背負うものが何もない。FINNIAS(フィニアス)とともにプロデュースされたウェルメイドなトラックが10曲並ぶだけだ。
SoundCloudから登場した彼女の、いかにも時代の寵児らしいデビュー初期の特徴であったジャンル・ブレンディング、トラップ以降のヒップホップとのサウンド面での親和性は幾つもある作家としてのアイデンティティの一部となって後景化し、今作では特にバンド形式の音作りが目立つ。2人の緻密なDIY精神と、ある種のこの形式的なサウンドアプローチの両立が、この作品をポップな作品と捉えるか、あるいは本格的なインディロック/エレクトロポップの作品と捉えるかの余白を生み出しているのだろう。無論、今作で初めてボーカルトレーニングを受けた彼女のボーカルスキルの著しい向上が全体のサウンドをまとめ上げているのも忘れてはならない。
今作最大のシングルヒットである「BIRDS OF A FEATHER」についても触れておきたい。2024年の顔となったSabrina Carpenter(サブリナ・カーペンター)とChappell Roan(チャペル・ローン)然り、Y2Kと並行して80年代レミニスは続く。80年代サウンドのポップカルチャーの共通言語化はここ数年で加速した(来年ファイナルシーズンを迎える『Stranger Things』など)。Wham!(ワム!)「Last Christmas」を連想する「BIRDS OF A FEATHER」もその現象の上にある。
ユニバーサルなラブソングに、彼女なりのトキシックさとツイストを加えて強力なポップソングに仕上げている。ドラムパターンは基本ステディでありながらも曲の展開に合わせたフィルが施されることで、ドラムがむしろトラックの躍進力となって聴くものの心をえぐっていく。
本人曰く、この楽曲は「ヴァース」「リフレイン」「プリコーラス」「コーラス」の順に成り立っているらしい(もちろんリスナーが自由に解釈すればいいと前置きした上で)。つまりTikTokなどでよく切り取られてる”Birds of a feather, we should stick together, I know”の部分は「プリコーラス」として書かれている。「バズり前提」「キャッチーな構成前提」の時代におけるこの良いメロディラインのコラージュ感/チグハグ感は、それこそ60年代のThe Beatles(ザ・ビートルズ)以降のポップソングライティングを感じさせるというのは、私の行き過ぎた妄想だろうか。
歌詞については、特にセカンドヴァースにその真髄がある。“I want you to see how you look to me. You wouldn't believe if I told you(あなたは私にとってどんな風に見えているか、見てほしい。伝えても信じてくれないだろうけど)”のラインは、一途なメッセージである以上に、セルフィッシュなパースペクティブの話でもある。この曲はそもそも幸せではない。どこか虚しい。その虚しさは、自分の視点にしがみついてしまって(たとえそれが愛だとしても)、トキシックになっていく自分に気づかない哀れな主人公から来ている。他人の視点に立つことなど不可能にも思えてきた2024年に、自分の視点からだけで愛する人(=「推し」)にしがみつく至高のポップソングが自然とグローバルヒットしたのは、なんとも皮肉なことだ。
Best Track: BIRDS OF A FEATHER
1. BRAT - Charli xcx


※ 私の意図で、『BRAT』と『Brat it's completely different but also still brat』を連続した二部作と捉え、まとめてランクインさせることとしました。
“brat”とは何か?ある人は「クールな人/様子」と答えるだろうし、ある人は「ムーブメント」と答えるだろうし、ある人は「プロテスト」と答えるだろう(トランプが大統領に再選した後に行われたタイムズスクエアでのゲリラライブは、80年代以降のニューヨークで起こってきた人権獲得のための数多の抗議運動の延長のように感じた。あの緑色にはそう感じさせるパワーがあった)。
『BRAT』とはつまり、Charli xcx(チャーリー・xcx)の「解体」の試みだ。彼女が愛してきたクラブカルチャーと私生活を一度「解体」してみて、2024年のクラブシーンとポップシーンの接合点はどこにあるのか、私は誰なのかを検証していく試みだ。
デラックスバージョンでは、リリースしたばかりのアルバム自体を「解体」してしまっている。『Brat it's completely different but also still brat』のリリースに際して、彼女は興味深いメッセージをソーシャルでシェアしていた。
i've always had a bit of an issue with songs coming out and being cemented as one thing for eternity.... i think songs are endless and have the possibility to be continuously broken down, reworked, changed, morphed, mutilated into something completely unrecognizable. that's what i was wanting to do with this record (...)
「楽曲がリリースされて、一つのものとして永遠に固められてしまうことに、私はいつも少し違和感があった... 楽曲には終わりがなくて、壊され、作り直され、変換され、変形され、バラバラにされて全く認識できないものにされる可能性を常に秘めていると思う。それがこのレコードでやりたいと思っていたこと」
Charli xcxがニクいのは、「解体」したくせに「再編成」せずにそっぽを向いていることだ(カマラ・ハリスが“brat”なのかは、誰にもわからない)。まぁたしかに、「再編成」してしまったらまたそこから新たなイデオロギーと対抗が生まれてしまう。「白黒つける必要なんてない。緑色でいいじゃん」ってことなのかもしれない。“brat”の答えが出るのは、数年後かな。
Best Track from Brat: Club Classics
Best Track from Brat it's completely different but also still brat: 365 featuring shygirl
おまけ: 2020年代ベストアルバム
2024年をもって2020年代は折り返しを迎えるということで、2020年から2023年にリリースされた各年のベストアルバムも振り返ってみましょうかね。
2020年
【本命】 folklore - Taylor Swift
【対抗】 After Hours - The Weeknd


2020年、パンデミックの年です。私は当時大学1年で「大学生はたくさん音楽を聴くぞ!」と意気込んでいたので、今に比べたらそれこそ倍以上は音楽を聴いていたと思います。その中でも一番聴いたのがこの2枚。
テイラーのアルバムからは「温もり」も、ウィークエンドのアルバムからは「ドラッグ」を摂取して、なんとかクアランティンを生き延びてた感じですね。ベッドに横になってずっと聴いてたな〜、この2枚。
2021年
【本命】An Evening with Silk Sonic - Silk Sonic
【対抗】Mother - Cleo Sol


2021年はどちらもソウルアルバムですね。アメリカのD'Mile、イギリスのInfloといった感じで、R&Bの良作がここから増えていった印象があります。
あとこの年は『Donda』の年でもあったんですけど、あれは諸々難しいアルバムなので、年間ベストには入れづらいですよね。
2022年
【本命】MOTOMAMI - ROSALÍA
【対抗】RENAISSANCE - Beyoncé


どちらも裸のお姉さんになってしまいました。それにしてもこの年は激戦ですね。他にもSZA『SOS』とケンドリック『Mr. Morale & The Big Steppers』が控えてます。
正直、ロザリアとビヨンセのこの2枚は、聴いた瞬間にピンときた作品ではありませんでした。聴いていくうちに何がやりたいのかわかってきたというか、なんなら『MOTOMAMI』は今聴いても新しい感覚に襲われますね。
ちなみにNewJeasは選考外です。全部NewJeansになってしまうので。
2023年
【本命】GUTS - Olivia Rodrigo
【対抗】BB/ANG3L - Tinashe


こちらは珍しい選出なのではないでしょうか。どちらもロングヘアーのお姉さんです。ヴィクトリア・モネが『JAGUAR II』でやっと正当評価された年でもあるんですけど、振り返ってみたらあんまりパッとしないです。個人的には。
ちなみにNewJeasは選考外です。大事なことなので2回言いました。
来年、2025年の今ところの本命はFKA twigsです!!
いいなと思ったら応援しよう!

