
働く中で”自分らしさ”がすり減った事はありますか?評価の観点から考える、自分らしく働ける組織のあり方
こんにちは!夏川真里奈です。
この記事は、私の所属するMIMIGURIという会社のアドベントカレンダー企画で書いています。
アドベントカレンダー企画というのは、会社のみんながクリスマスに向けて1記事づつ公開していくというものです。
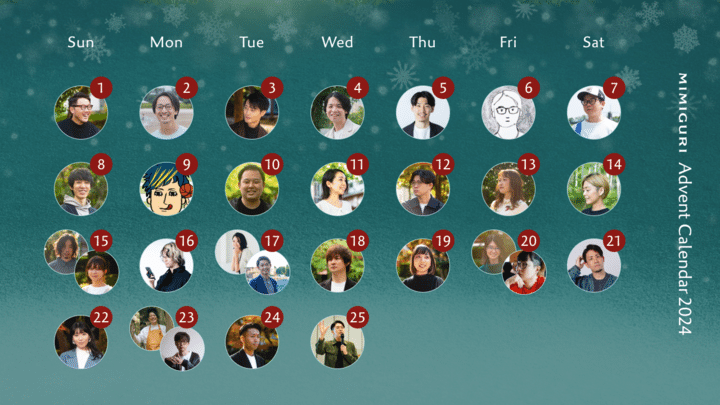
せっかくの機会なので、私も自分の所属している会社について改めて紹介しながら、自分の働き方について向き合う記事を書いていきたいと思います!
組織に所属しながら、”自分らしさ”を諦めない
MIMIGURIってどんな会社ですか?と聞かれた時、「組織に所属しながらも、自分らしく在ることを応援し続ける会社です」と紹介することが多いです。

事業開発・人材育成・組織開発・評価制度など多岐にわたる方法で、個人が自分らしく在りながら、組織に所属して働いていくを応援している会社だと私は解釈しています。
「誰の影響も受けずにただ自分らしく働きたいのであれば、フリーランスになればいいじゃん」という声もあるかと思うのですが、「組織に所属しながらも、自分らしさを諦めない」というところがポイントかと思います。
「会社のために、何をしないといけないか?」ではなく、「自分はどう在りたいか?」そんな想いを組織で尊重し合い、お互いに探究しながら働いていく。そして、そんな働き方によって、個人が幸福になるだけでなく事業のインパクトも増していく。
上層部の指令を伝えていくような管理主義的な働き方ではなく、ボトムアップ的に、個人の想いが根元に在りながら組織で働いていく、そんな冒険のような働き方を実現していくためどうすればいいのか?
そんな思想を「軍事的世界観」から「冒険的世界観」へのパラダイムシフトなんて言い方をしながら、私たちは試行錯誤しています。(ここら辺をもっと詳しく知りたい人は代表の安斎の記事を読んでください)

安斎のnoteより引用/https://note.com/yuki_anzai/n/n175f7f299e59
いやいやいやいや……そんなうまくいくんかい!!!
と思う方も多いかと思います。
そうなんですよ!!!!!
難しいんですよ!!!!!!!!!!
もちろん思想としては魅力的なので「できたらいいよね〜」と思う方も多いかと思います。実装・実現するに至ってはやはり難しさが多くあります。
ちなみにこの考えを提唱する代表の安斎も「冒険的世界観とは、ある意味で軍事的世界観以上に厳しい世界観です」といっています。
働く中で”自分らしさ”がすり減ったことありますか?
「組織に所属しながらも、自分らしさを諦めない」なんて綺麗事だと思う方もいるかもしれません。
正直、私自身も初めて社会人として働き始めた時、念願の教員になったものの働き方が性に合わず、萎縮したり多忙さの中で余裕を失って、少しずつ自分が自分じゃなくなっていくような「私じゃなくなっていく感」を体験しました。
そんなこんなで転職して、今の会社に落ち着いたわけですが、このような体験を通して環境や組織の重要性強く感じました。
環境、組織、体制の力というものは、凄まじいです。
人間一人の考えや性格を容易に変えてしまうし、なんなら身体だって、合わない環境に無理してい続けたら、壊れてしまうことだってあります。
組織の中で”自分らしい働き方”を支える評価制度とは?
「組織に所属しながらも、自分らしく在れる会社」そんなことできるのでしょうか?
夢物語にするのではなく、実現を支えていく1つに、評価制度のあり方があります。
今回簡単に、私の会社の評価制度について紹介したいと思います。(※あくまで一社員目線での紹介です!)
MIMIGURIでは2024年現在「ミグシュラン」という評価制度が採用されています。
ミグシュランとは、定期的に半期の”期待”を振り返り、翌半年の”期待値”を対話を通して定めていく取り組みです。
これは社内でよく”期待値評価”なんて言われているのですが、私はこの評価のあり方が「組織に所属しながらも、自分らしく在る」ことを支えている心臓だと感じています。
「評価」と聞くと、学校の成績のように、国語の点数が良かったから「5」とか、悪かったから「1」など、過去やってきたことを振り返り、それにレッテルを貼るように成績をつけるような印象を持つ方が多いかと思います。

ミミグリでの「評価」の仕組みは全くそれと反対です。
過去ではなく、”未来”を評価します。
上司(マネージャー)と対話しながら、過去の働き方や経験を通して、これから半年の自分はどんな自分で在りたいのかを共に話し合っていき、未来の自分への”期待値”を作っていきます。
マネージャーが一方的に評価する場ではなく、共にどう在りたいのかを考え、対話しながら、自分が在りたいと思うことと、会社にとって期待していることを擦り合わせていくのです。
そうして、「こう在りたい」と対話を通して生まれた姿を”期待値”として評価します。

※期待値を作っていく営みを”ミグシュランフィードバック”といいます
すごくざっくりいうと、MIMIGURIでの評価は、他者が自分にレッテルを貼ることではなく、自分自身がどう在りたいのか深く内省し、時に社内の仲間にフィードバックをもらいながら形作る、未来に向けた評価です。
それぞれなりたい自分の姿が多様であるため、社内でのキャリアの歩み方も多様になっていきます。
課長になって、部長になって、役員になって……と、出世=素晴らしい!という外的な物差しで測りません。
それぞれやりたいことも目指したいことも在りたい姿も違うので、まずは自分の内面と向き合いながら、そして対話しながら自分がこの会社で一番自分らしく在れること、そんな自己実現を果たしていくキャリアを探索していきます。
その営みは楽しさも、時に苦しさも伴う時間になります。
私はこの会社に入った時、この評価の仕組みにとても感動しました。
自分1人だったら気づけなかった自分の可能性を、対話を通して発見していく瞬間などに、この組織に所属していてよかったなと感じます。
学校教育の側面から考える、内面を評価することへのリスクとは?
期待値評価の試みは、新たな会社の体制を作っていく上で画期的だとは思いますが、もちろん完璧なものではありません。
単純に業務成績だけでA・B・Cなど評価するより、はるかに時間がかかりますし、評価される方も常に自分はどうありたいのか?対話が求められるので時に悩んだり、葛藤したりします。
このような評価体制で働く社員として、感じる難しさを素朴に言葉にしてみると、下記のような点でしょうか。
・自分のやりたいことをとても尊重してくれる会社なので、どこからどこまではMIMIGURIでやって、どこまでは私自身がやりたいと思っていることなのか線引きが難しくなる。
・課長になって、部長になって、役員になってというわかりやすい道ではなく、自分がどうありたいのか向き合い、全員がオリジナルのキャリアを歩んでいくため、常に自分の歩む道を自身で創っていく胆力が求められる。(もちろん上司やチームのサポートもあるけど)
難しい点はやはり、評価における”内面”との向き合い方かと思います。
私は元々教員をやっていたこともあり、評価と聞くと、どうしても学習指導要領の改訂の歴史が思い浮かびます。
学校教育においても、”内面”を評価するあり方へと変わった時代がありました。
学力を評価する際に、知識や技能を中心にを評価するあり方(1958年改訂)から、学びへの関心や態度も評価の項目に入れようとした変革です。(1989改訂)
そのような試みの試行錯誤は、現代の子どもの主体性を尊重したアクティブラーニングといった学びにつながっています。
この試みは素晴らしいと思います。
しかし、この評価によって生まれたのは素晴らしい学習の場だけでなく、負の側面もあります。その1つとして挙げられるのが、子ども”荒れ”の形の変容です。
結果だけが評価されていた時の子どもの”荒れ”のあり方はわかりやすく、いわゆる不良といった、リーゼントや暴力行為など外に向かうような荒れの形でしたが、
学びへの意欲や態度などといった、内面への評価が観点に入ることにより「不登校」や「引きこもり」といった内への”荒れ”変容していったのではないか?という考えがあります。(池上彰「池上彰の「日本の教育」がよくわかる本」より)
知識や技能に偏重した評価だと子どもたちの主体的な学びを尊重できないため、子どもたちの意欲や態度などの内面を評価しようとしたが、その試みによってかえって先生に向けた”偽の主体性”を演じようとしてしまったり、先生の前でだけ良い子であればいいというような、”内面”にまで負の側面を与えてしまう可能性が生まれてしまったということです。
私の会社で行なっている期待値評価の試みも、そこには内面の対話が欠かせません。私はこの会社でどうありたいと思っているのか?言葉にします、対話します。時にはぶつかります。
企業内でも内面の対話を丁寧にしていく試みは、良さはあれど、会社のために都合の良い自分になろうとしてしまったり、本当にやりたいことを隠してしまったり、そもそも自分がわからない、そこまで踏み込んでほしくない、逆に自分がわからなくなってしったなど、また別の課題を生んでいくことでしょう。
ここまでの記事を読んで、それなら一周回って、機械的に結果だけで評価した方が、学校においても企業においても内面が阻害されない分、もはや良いのでは?なんて思う人もいるかもしれません。
でも私は、一周回ったから内面は一切考慮しないで業務成績だけみます。という結果に落ち着くのは勿体無いと思っています。
だからこそ、理解した上で、また新しい形を作っていくことが重要だと考えます。
この評価形式で大事なのは、内面を評価することへのリスクをどれだけ理解できているかということです。それは新しい組織体制をつくろうとしている私たち自身も常に考え続けなければいけないことだと思います。
最後に。
長くなりましたが、この記事では組織に所属しながらも自分らしくあることを実装する難しさを”評価”の観点からご紹介しました。
なんかかなりニッチな記事になってしまいました。一部の人がせめて「面白いな〜」と思ってもらえたら嬉しいです!
もし、この記事を読んでいるあなたが、他者を評価する立場であるなら、内面を評価することのリスクについて考えるきっかけになると嬉しいです。
もちろん、評価など全く関係ないわ!という方にとっても、あなた自身が”自分らしく在る”ことについて考えるきっかけになれば幸いです!
🔽冒険的世界観について安斎が本を出版するので、興味ある方はぜひご予約ください!
この記事では冒険的組織の実装の難しさについて書きましたが、そんな組織の作り方についての知見が詰まっております!
いいなと思ったら応援しよう!

