
奴隷だった哲学者から学ぶ考え方5選
ご覧頂きありがとうございます。
この記事を通じて一人でも多くの方が
これからの時代を乗り越えて行く為の考え方や
きっかけになって頂けたら幸いです。

働くうえで人との関わりは
切っても切れないものですよね。
職位や職種によって多くの外部業者や
他部署と関わる必要があり
業務を円滑にする必要から
コミュニケーション能力は必須になってきます。
私は上場企業で17年間
製造部門のオペーレーターから
マネージャーまでを経験し
さまざまな考え方から
自分らしく乗りきる道を見つけてきました。
そんな中、考え方を学ばせてくれたのが
古代の奴隷だった哲学者
エピクテトスという人物が残した本でした。
勿論全てを共感できた訳ではないですが、、、
この記事は
エピクテトスが残した哲学書で
共感できた考え方の一部を抜粋し
私見も交えながら解説したものとなります。

日本人同士でさえ伝えたいことが伝わらなかったり
聞きたいことが聞けなかったり
リモートが主流となっている昨今でも
表情が見えない分、相手のトーンによって
変な気遣いが発生したり
同じ建物内で同じ人と毎日一緒に働くとなると
嫌なところも見えてきてしまい
憂鬱な気分になってしまう事もありますね。
一部の場合
海外就労者の方とのコミュニケーションになると
伝えることが更に難しいものとなり
考えるのではなく悩みの種になってしまう事が
珍しくない現代かと思います。
ここでお伝えしたいことは
気になりあとで振り替える事があっても
「自分を攻めるのはやめましょう」
ということです。
あなたはそのときできる最善の判断をしたのですから
それだけで立派であると受け入れることです。
日々人数に関わらず
年齢、性別、担当部署、階級など
様々な状況で
誰かと関わっていると思います。
毎日、毎回、毎時、気付けば
「どう話そうか」「話さないべきか」
めっちゃ考えていませんか??
このような現代で少しでも負担の少ない生き方を
選択できるよう一読していただけたら幸いです。
ー奴隷の哲学者エピクテトスとはどんな人物かー

紀元50~60年頃に
奴隷の両親から生まれた苦労人で
彼自身も若い頃は奴隷として過ごし
解放された後は私塾を開いて生計を立てた。
同時代のストア哲学といえば
政治家で弁護士のキケロ
劇作家で政治家のセネカ
16代ローマ皇帝マルクス・アウレリウス
こうした系譜の中核にいるのが
エピクテトスという奴隷出身の哲学者なのです。
マルクス・アウレリウスの書といえば
ドラマ「ミステリと言う勿れ」に登場する
自省録が有名です。
謎解きに使われていましたね。
余談でしたが
解放奴隷出身の哲学者とは
哲学史上でも珍しいのです。

いわゆる「学者」でも、ましてや「エリート」でもない。奴隷としての出自、慢性的な肢体不自由
国外追放の辛酸、塾講師としての不安定な収入
といった多くの困難を抱えながら
当時の流行思想でもあったストア派の哲学を
自分自身の「生き方」として学び取り
それを洗練させていきました。
地位や財産や権力とは無縁な、ごく平凡な市井の庶民が、いかにして真の自由を享受し、幸福な生活にあずかることができるのか。
そのためにいかなる知恵が大切なのか――。「隷属と自由」という彼自身の課題は、そのまま現代人の生活の場面にまでつながっているのです。
あなたは奴隷と聞いてどのような生活を想像しますか?
さらにエピクテトスは体が不自由の身であったことから
壮絶な人生だったのではないかと思います。
そのような環境でも彼は「幸せとは考え方次第」であることを唱えています。
自分が同じ境遇だったとき、彼のような考えができるか
わたしに自信はありませんが、現代なりに導いてくれた
考え方です。
それでは古代哲学者から2000年語り継がれてきた
現代人へのメッセージを読み解いていきましょう。
奴隷だった哲学者から学ぶ考え方5選

①「我々次第ではないものを軽くみること」
そのままですが、自分でどうにかできないものは深く考えてもどうにもならないという事です。
冒頭にも申しましたが良くも悪くも開き直る
と言うことです。
どうにもできない事を考えすぎてしまうのは、心を蝕み豊かになれない原因になるのです。
とは言えわたくしも人に言うのは簡単なのですが
心身の疲れもありますし、考えを切り替えるのはなかなか難しいことですよね。
そんな時は、まず「疲れているということ自体」を
受け入れてください。
開き直るのは諦める事とは違います。
開き直るとは一度固着した考えから頭を切り離す為の
「作業」です
一瞬でも全く別のことを考えたり一度忘れると
ふとした瞬間に壁に感じていたことに突破口となる
思い付きが広がることが多々あります。
わたしもこの考えに幾度となく救われてきました。
マネージャーを勤めているときは50台の機械と
50名の従業員の長をしていましたが
機械は年季が入り故障続き、人間関係には
それぞれ派閥がありました。
それでもお客様の要望や会社の目標を達成するため
自分のグループや他部署との連携を取るため
開き直りながら、また考えることを繰り返し
改善に努めていました。
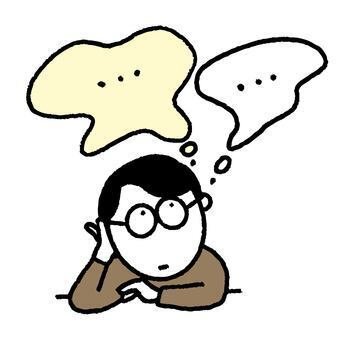
②「心像に拉致されるな」
これはエピクテトスがもっとも大事にしていたことだと言われています。
「心像に拉致される」とは心の想像に惑わされると言うことです。
有名な人、有力な人、評判の良い人や華やかな人を見たときに「幸せそうだな」と感じることはありませんか??
わたしもそうですし、誰しも思うことです。
しかしここでお伝えしたいのは、表面的な華やかさを見たままに信じ、想像で羨ましいと思う気持ちは心が疲れてしまう要因になると言うことです。
「この人は本当に幸せなのか?」
そんな疑問をもって見る。
俯瞰してみるということがとても大事になります。
そうすると以外に自分の方が良いのではないか
と思えたり肯定感が高まるキッカケになると思います。

③「君が出きることまさにそのこと励めばよい」
周囲には「なぜこの人はそうなのだろう」という事が
頻繁にあります。
しかし、このことこそ人間関係において心労となる
原因になっているのです。
他人への不快感は、いわば自分のその人への
「望みや願望」と言えます。
ただ奴隷として悟りを開いたエピクテトスは
このように言っています。
「他人は自分にどうにかできるものではない」
「自分にどうにかできるものとできないものを
混同するな」
「その上で何かを望む必要があるのであれば
自分にどうにかできるものかを良く吟味しなければならない」と
仕事は人脈、繋がり、信頼からなり
従業員どうしでもこの関係は必要だと思います。
そのため何かをやって欲しい、覚えて欲しいという
必要が出てきますよね
自分で出きることだけを全力で行えばよいのです。
人間関係に悩んだ時は、自分にどうにか出来たことか
出来ないことかをしっかり分けて
出来ないことは仕方ないと開き直ることが大切です。

④「何がやってこようとそれから利益をえることはできる」
例えば嫌な夢を見たことはあるでしょう。
何かに追われていたり、もがいているといった
起きたあとに不快な感覚の夢
夢占いでは内容によって吉夢と紹介されている
ことがありますね。
これは見たから良いのではなく
今あなたが何かから抜け出そうと努力している最中に
潜在的に見ているものと言えるのです。
そのまま思考を巡らせ、失敗しても解決を目指せば
良い方向に進むという暗示です。
悪夢を見て吉夢と期待し、ただ待ってしまっては
何も起きないのは言うまでもありませんね。

⑤「事前のこころ構えがあなたを救う」
「そんなことはわかっている」
と言われそうですが、自分に言い聞かせて芯から思う事が大事です。
上司に報告や何かを提出する際
「こう言われたらどうしよう、怒られたらどうしよう」
と思ったことは皆さんにも少なからずあるでしょう。
わたしも散々でした。
特にわたしは文章や説明が苦手でしたから
頭ごなしに怒られたりご指導を頂くことが頻繁でした。
自分にも非はあると思います。
グループの成績も良くありませんでしたから
ただ、ここでお伝えしたいことは
「こうなったらどうしよう」
と事前に考えていることが大事ということです。
不安はあるかも知れません。
しかし、とは言えそれでもやらなければならない。
しなければ事は必ず発生しますよね。
この「予測」ができているだけで素晴らしく
半分は既に救われている状態ということです。
なぜなら、考えている事の半分は「起きない」可能性が
あるからです。
わたしもいざ不安のまま報告しに行って
以外に何もなく、むしろ褒められた事さえありました。
あらゆる本や動画でも言われていますが
不安とは人間の本能であり、防御行動です。
防御ができているのだということを
心から受け止めてあげましょう。

この記事をご覧いただきありがとうございます。
明日から取り入れられる考え方はありましたか?
少しでも皆さんの共感やひらめきが得られる記事になっていたらとても嬉しく思います。
共に今を生きる者同士
より良く生活していきましょうね!
地元で和傘のイベントがあったので
へたくそな写真ですが楽しんで頂けたら幸いです!




いいなと思ったら応援しよう!

