
塩分を摂らないとどうなるのか?その壱
松本永光 先生の著書から考える
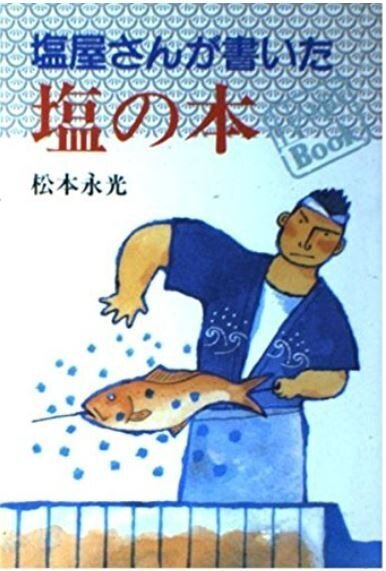
松本先生は、「伯方の塩」でお馴染みの、株式会社 三栄の創業者であられます。
先生のご功績については、株式会社 三栄 様のホームページの、「創業者」の項からご覧ください。
江戸時代の飢饉の時の塩分不足の例
最近は、砂糖も塩も、健康の敵として嫌われてしまいます。
しかし、砂糖はなくても生きていけますが、塩はそういう訳には
いきません。
江戸時代の飢饉の時に、塩があれば、まだ助かったというエピソードが
あります。
①果物・野菜類など植物はカリウムの塊
カリウムは、植物の肥料の三要素( チッソ・燐酸・カリ)にも含まれます。
果物、野菜類など植物はカリウムの塊で、マグネシウムも多く含んでいます。
②塩分不足で何が起こったか?
松本先生の著書にもありましたが、飢饉で塩が無く、そこらの野草・草根を手当たり次第に食べた為に、そのカリウム、マグネシウム過多の毒性で中毒を起こして、人びとが亡くなっていきました。
食糧不足より、草の毒を消す塩分(ナトリウム)不足で亡くなった例であり、究極の人体実験と言えるでしょう。
飢饉の体験から生まれた飢饉対策の書物には、
『塩さえ絶やさなければ、草や葉ばかり食ベても死ぬことばないようだ』、と記されています。
塩は、草ばかり食ベるときの毒消しになるということで、山野を歩き回って苦行を積む僧侶修験者たちも、竹筒に塩を入れていつも持っていたそうです。
スイカに塩を振って食ベると甘味が増し美味しくなりますが、スイカがまだ珍しいころは毒消しのために塩が使われていたともいわれています。
③カリウム過多の危険性
高純度科学研究所 公式ブログ様より「安楽死とカリウム」
>最終的に心停止につながる。

https://www.kojundo.blog/legalmedicine/2883/
体液の話とリンゲル液の組成
大体、私たちの体そのものが、塩漬けのようなものなのです。
そこから塩を抜いてしまえば、生きていけないのは当然のことです。
私たちの体に塩分が必要なのは、また血液を舐めてみて、しょっぱい事でも分かります。
体液そのものが塩水でできているのです。
そして、その成分は、太古からの海水組成に非常に類似しているというのはよく知られています。
また、体液だけではありません。人間の体には約85グラムの塩が含まれているといわれますが、そのうちの半分は骨に含まれているのです。
動物の血液は母なる海の水からできあがった如く、よく以ています。
地球上の生命は、まず海に誕生したといわれますが、その時の単細胞のような原始的な生物の内容物は、ほとんどが海水でした。
やがて、進化を統けた原始生物たちの中には、陸に上がる事を選ぶ種も出てきました。
その種は、陸ヘ上がる時にも、体内の海水のような成分を持ってきたという訳です。
以来、何十億年もの年月を経て人類が誕生し、今日に至る訳ですが、
依然として陸上の生物にとっては、この海水の成分が欠かせない重要な要素となっています。
このとても長い生命の歴史に背いて、塩を摂らずに生きる事など、
私達にできる訳がないのです。
これをよく表しているのが、リンゲル液という医薬品でしょう。
塩は点滴に使われるリンゲル液の原料にもなります。
リンゲル液は代用血液、生理食塩水などとも呼ばれるもので、
1リットルに、
塩化ナトリウム 0.86g
塩化カリウム 0.30g
塩化カルシウム 0.33g
が含まれています。
水分の補給には、この液体が一番良いのです。
また、出血多量で輸血が必要な時、体内の毒素を薄めて排泄させたい時、
重病で食事が出来ない時など、この液体は無くてはならないものなのです。
①血液・体液
血液・体液・鼻水・涙・汗・尿までもが、しょっぱい液体です。
②羊水の塩分濃度
赤ちゃんは、お母さんのお腹の中で、羊水(ようすい)に浮かんで育ちます。
羊水の塩分濃度は、0.9%で、海水の成分に酷似しているのですが、決定的に海水と違うのは、塩分濃度とマグネシウム等のにがりの含有比率です。
海水のマグネシウムの含有量は、人の50倍です。

③塩漬けは腐らない / 人体の塩分濃度
塩漬けの食品が腐り難いのは、既知の事実です。
逆に、塩不足の漬物が腐りやすいように、人間の細胞も減塩では腐りやすい体、すなわち、病原菌に犯されやすい体となります。
人体では、体内の塩分濃度を、0.9%の塩漬け状態(腐らないように)を保とうと、働きます。
それが「恒常性(ホメオスタシス)」と呼ばれています。
ナトリウム(塩の主成分)の体内での働きについて
先に挙げた、リンゲル液に一番多く含まれているものが、塩化ナトリウムでした。
松本先生が述べておられるように、人体の代謝、吸収、消化に、ナトリウムが不可欠という事が言えるでしょう。
では、このナトリウムは、体内でどういう働きをしているのでしょうか。
塩は、体内でナトリウムイオンに分解されて、いわば情報メディアのような働きをしています。
例えば、頭で考えたことを筋肉に伝える時、その情報を運んでくれるのが
ナトリウムイオンという事です。
筋肉が動くメカニズムでも、重要な役割を果たしています。
また、唾液、胃液、腸液などの消化液は、1日に約8リットルも分泌されていますが、これにも塩分が必要です。
血液を浄化して、その大切な部分は再吸収するという腎臓の働きも、
ナトリウムなどのイオンが活躍します。
あるいは、糖分やタンパク質を腸から吸収する時にも、ナトリウムはなくてはならない成分です。
塩分摂取の必要性とは?
・菜食が多い日本人にとって、カリウムの摂取が多くなりがち。
ナトリウムとカリウムのバランスが崩れないようにする為にも、
塩分摂取は必要。
・塩不足の漬物が腐りやすいように、人間の細胞も減塩では腐りやすい体、
すなわち、病原菌に犯されやすい体となります。
・人体の代謝、吸収、消化に必要なのが、ナトリウム。
塩分摂取を控えると、それらの働きに影響を及ぼします。
-------------------------------------------------------------------------------
塩爺ぃ 講演会 オンライン(Zoom使用)のご案内

【ZOOMを使用した講演会です】
お申込みの際に、希望日時をお伝えください。
テキスト版「未知への道」をお手元に届ける日数もございますので、
余裕を持って、お申込みください。
ZOOMの案内をメールにてお伝え致します。
【ご紹介動画】
【開催日程】月曜と木曜に開催予定
●16日(月)20時~22時
●19日(木)20時~22時
●23日(月)20時~22時
●26日(木)20時~22時
●30日(月)20時~22時
【お申込み】
テキスト版「未知への道」をお持ちの方:参加費2千円(税込)
https://50goen.shop/items/6364b70e211ac36abc6f2552
テキスト版「未知への道」をお持ちでない方(参加費+テキスト+送料込み):参加費3千円(税込)
https://50goen.shop/items/6364b797f3de5c66532429b0
-------------------------------------------------------------------------------
新刊「未知への道」のお知らせ
笹谷達朗の新刊、60頁フルカラーです。
お塩に関する、約60テーマを、豊富な図解と共に、解説しています。

