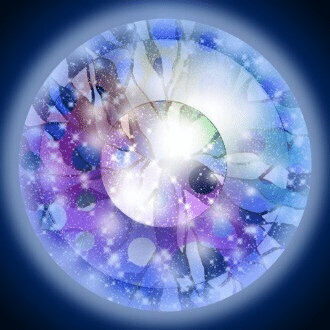◆“お金”について考える1/結局お金は物事を都合良く動かせるほどのツールではない
1:お金に限った話ではない
お金にまつわる発信をシリーズで1回5000文字程度で語っていこうと思います。各回サブテーマ2つについて語っていきます。
◆人は何を扱うでも時々間違える
今月8日、Softbankグループの第1四半期決算発表のライブ中継を観たのですが、グループ全体で5兆円を超す創業来最大赤字が公表されたことについて、昨今の国内外の情勢を鑑みるにある程度の納得と、それでもこの規模の巨額赤字への驚きといった印象を受けたんですよね。
会長兼社長である孫正義氏は、決算説明から質疑応答に至るまで「反省」という言葉を度々口にし、終始その表情には痛恨の極みを滲ませているように見えました。
実質的に投資会社となったSoftbankグループは、出資金調達による10兆円第一ファンドに加え、現在では自社100%出資の第二ファンドを構え、AI関連に特化した累計470社以上への投資をしてきているということで、一般人には到底理解に及ぶことのない巨額投資であることはなんとなくわかりますね。
今回の巨額赤字決算において深く反省をするとともに、今後はコスト削減や純負債比率の拡大を抑えるべく、グループ全体で人員削減をしていき守りに徹していくとの姿勢を示していました。
コロナ禍に加え、ロシアのウクライナ侵攻、加速する円安や物価高騰などといった複数のことが重なって直撃した今回の決算は、当然第2第3四半期決算の見通しを不透明なものにしたことは言うまでもありません。孫氏も決算説明中にこうした不安定な情勢であることが影響したことは間違いないけれども、そのせいにして言い訳にするのは憚れるほど、前年下半期が絶好調に推移したことに有頂天になってしまったことが最大の失敗であると言っていました。
優秀な経営者であっても、未来に何が起こるかはわからないもので、世界情勢や世界経済の不安定化に適時対処していくことは至難と言えるでしょう。結果論としてどうすべきだったかを後付けで言うことはできてもそのことに意味はないこともきっと痛感していたことだろうと思います。
度々私が言うことの一つに「人は何を扱うでも時々間違える」というものがあります。ハサミやトンカチなどの工具、私たちが普段からコミュニケーションに使っている言葉、様々な集団組織で掲げられている信念・理念などといった思想、教育の源であるあらゆる知識、そこから生まれてきた様々な技術や仕組み、果ては条例、規約、法律などといった決め事に至るまで、人が決めて扱うものは全て完璧ではないんですよね。
昨今議論になっている軍事利用される可能性のある製品や技術の海外への輸出についても批判する人たちは大勢いますが、では反対に、軍事利用されないと断言できるものがどれほどあるかを想像してみて欲しいんですよね。どんなことでも軍事利用が可能だということがウクライナ戦争で証明されていますよね。
スマホやドローンも存分に軍事利用されています。偵察用ドローン、専守防衛のためのミサイル搭載ドローンには、エンジン部品製造のSAITOという企業のものが使用されているとの報道がありましたが、レーシングカーに搭載されていたものを転用しているケースもあるとかで、同企業の意図しないところで自社製品が軍事利用されていることなど寝耳に水といった様子。
プロパガンダはどうでしょう。SNSで拡散されるあらゆる情報の中にウソを混ぜて発信しているケースもありますね。映像や画像と共に付け加えられる言葉だってジャブジャブと軍事利用されています。軍事利用される可能性のあるものの輸出をすべて禁止するなんて元から無理なんですよね。
軍事資金はどこから調達しているんでしょうね。これについては終始お金が軍事利用されています。戦争を助長するような機会となり得る物資や兵器、医療体制支援や難民受け入れに至るまで、戦争に関連するすべてのことが、“正しいか間違いか”ではいちいち測っていられないような逼迫した状況で展開されています。
混沌とした状況が長引くにつれ、人の感覚は麻痺してくるのかもしれません。最初のうちは間違った行為、良い結果には至らない、などといったことを感じつつも、そうした感覚が徐々に麻痺していき、常態化していくのかもしれません。
時々間違える程度なら誰にでもあることです。トンカチで釘打ちをしていて、普段はしないのにある時自分の手を打ってしまったり、人と話していて時に感情の高ぶりから自分でも思っていない言葉を口に出してしまったり、言い合いではすまずに相手を殴ってしまったりといった話はよく聞くものです。
どこぞの市議のように、医療福祉施設に補助金申請の仕方をレクチャーするためのセミナーを開催して、国に申請して振り込まれた補助金を半々で折半するといった話を持ち掛け、億単位の詐欺行為を繰り返して逮捕された事件がありましたね。その他にも、とある店舗のアルバイト店員がレジでの会計操作を偽装し、1回あたりは少額の搾取でも、これを600回以上も繰り返してしまい逮捕されたという事件も起きていたり、タクシー代金を払わないどころか殴る蹴るの暴行を加えて逃走した者や無銭飲食した挙句店長へ暴行を加えて現行犯逮捕された者など、国内でもこうした事件が増加しているように感じられます。
感覚が麻痺してしまうと、悪いことだとわかっていてもそうした行動が繰り返される度に歯止めが利かなくなるのかもしれません。
◆元より不確実性に満ちているこの世界
前にも書いたことなんですけれども、“何かを心の底から信じることができる人”への理解が私には難しいと感じるんですよね。その“何か”とは、今回のテーマでもあるお金であったり、何かしらの思想だったり、成功者の格言だったり、心理学者のあれやこれやだったり、陰謀論や都市伝説的なものだったりするんですけれども、“心の底から信じられる何かがあるということが人間にとって素晴らしいことである”みたいな先入観を私は持ってないんですよね。
だからと言って、何でもかんでも疑うばかりでもないんですよ。信じるか疑うかの二択で何でもかんでも仕分けをするほど慎重な性格でもありません。私が一番大事にしていることは「自分がどう感じているか」ということなんです。
世間では起きたあらゆる出来事について批判してみたり共感してみたりと、その都度変わるターゲットが誰であれ、多くの人たちが自らのポジションを賛成か反対かのどちらかに立とうとしているように見えます。そういう景色は、私からすれば非常に慌ただしく、煩わしいものであり、両極端な意見ばかりが目立つ一方、大して建設的な議論が交わされているでもない、その程度のことがこの国の日常として繰り返されているんだなと映っています。
ここまでの文章表現でもお分かりかもしれませんが、私は世間のことを遠くから眺めているような感覚でいろんな物事に目を向け思考を回転させていますから、自身がどのポジションに立つべきか、または自身がどのポジションに立ちたいか、といった前提認識はないんですよね。自分の立ち位置を決めたところで考え方が変わればコロコロと立ち位置も変わり、言うことも変わるのが人間だからです。
間違いなく、自分も社会の当事者の一人ではあるんですけれども、わざわざそんなふうにしか映らない世間のあれこれと自分とをいちいちリンクさせて腹を立てたり悲しい気持ちになったり、時には傷付いたりと、現代においてはそういう人たちが異常なほど多いということにも“疑問”しかないんですよね。
ほら、よく“炎上騒動”みたいな感じで騒がれる人たちがいますよね。これ自体が日本経済の生産性を著しく停滞低下させているようにしか見えないんですよね。言い方悪くすると「一般人にはまるで関係ないよね?」という当事者間の問題でもネットユーザーがやんややんやと騒いで火に油を注ぐ作業に貴重な時間を費やしているだけのことを、「このような声が殺到しています」みたいな感じでメディアが拾って報道していたりしますよね。
おそらくこういうことも民主主義が生んだある種の慣習なのかもしれませんが、いい加減に飽きないものかねと思っています。ツイッターやらLINEやら、昔は私もよく使っていて似たようなことをしたこともありますけれども、とんでもなく“無意味で無駄なことだと感じた瞬間”からアプリ自体を開くこともほとんどなくなりました。
みんながやっていることを自分もマネしてやってみよう、大体の人はおよそこれに近い感覚で始めるものですが、この点については何の問題もないんですよ。人気とかブームとかいうことも、食わず嫌いで自分はやらずして世間を批評するというのでは中身の薄い感想にしかなりませんが、とりあえずやってみる、とりあえず使ってみるというのは良いことだと思うんです。
でもですよ?それはあくまでも初動のきっかけに過ぎず、本当に自分がやりたいことなのか、本当に自分が続けたいことなのか、という点においてはどこかのタイミングで変化が起きても不思議はないはずなんですよね。長いことnoteを続けていますが、基本的に一方的な発信で、特別誰かに向けた文章を書いているわけでもありませんし、ご覧のとおりコメント欄はスッカラカンです。
誰かに共感されることも、誰かに批判されることもない、そういう文章なのだと思いますが、私自身はそれでいいと思って書いています。いつだったか、とあるnoteユーザーさんにこんなことを言われたことがあります。「あなたの文章は賛否両方の視点を踏まえて文章化されているため批判しようがない。」と。これは本人曰く誉め言葉の意味でそのように感想を述べたとのことでしたが、言われて初めて気付かされたことでもあります。
私個人としては、この世界は不確実性に満ちているのだから、偏った思想、偏った考え方はどれも正しいわけでもなければ間違っているわけでもない、ただそのように望んで考えたり信じたりする人たちがこの世界にはたくさんいる、というのが現実でもあろうと思っています。ですから、私がこうして書いている文章も正しいか間違いかでは分別できない非常に曖昧でふわっとした表現であるというのが特徴なのかもしれません。
さて、次回は本題である「お金とは何か」について触れていきます。次回投稿で、“お金とは〇〇である”という形式で箇条書きにいくつか挙げてみたいと考えています。皆さんのお金への認識とはズレたものも含まれるかもしれませんが、皆さんも箇条書きにして思い浮かぶ限り挙げてみてください。
ではまた次回お楽しみに(・∀・)
いいなと思ったら応援しよう!