
銀河フェニックス物語 <恋愛編> 第七話 彼氏とわたしと非日常(6)
* *
『あの感覚』への到達は、俺の想像以上に困難だ。
「難しいな」
思わず弱音を吐いた俺に、ティリーさんが無邪気に提案する。
「もう一度、白魔と対戦してみたら『あの感覚』をつかめるんじゃないの?」
同じことは俺も考えた。スチュワートに白魔を薦めてS1に乗せた。アフターケアと称して、何度も練習相手になった。コースでも飛んだし、小惑星帯でも対戦したが『あの感覚』は訪れなかった。
初めて白魔と対戦した時、どうして『あの感覚』に入れたのか、いくら分析しても見えてこねぇ。
かと言って、手ごたえが全くない訳じゃねぇ。S1でプロのレーサーたちと戦った経験は俺の身体に記憶として刻まれた。タイムは少しずつ伸びてる。
彼女を乗せて小惑星帯を飛ばす。
ティリーさんが『あの感覚』への触媒なんじゃねぇかと考えたこともあった。だが、そんな単純に答えがでる話じゃなかった。
『あの感覚』がもたらす、多幸感、恍惚感、全能感には及ばねぇが、ティリーさんと一緒に飛ばしていると安定した心地よさに包まれる。
ずっと求めて、手に入らなかったものを、俺は今、手にしている。
俺の夢だった。
俺の船でフローラと一緒に銀河中を飛び回ることが……
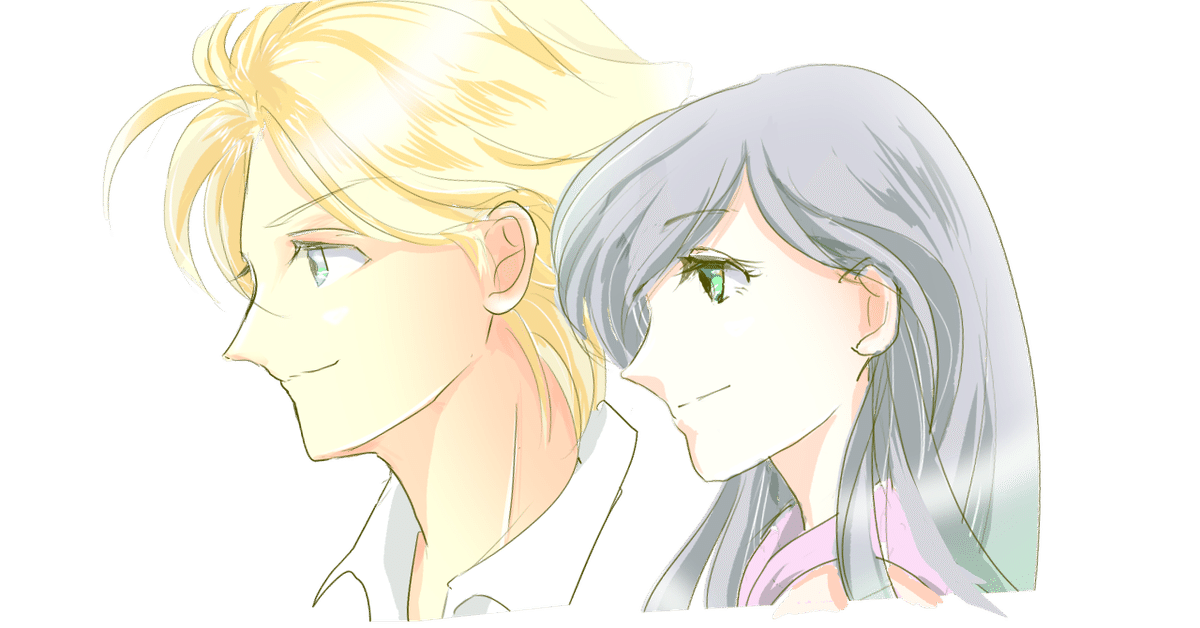
毎日毎日、フローラと他愛のない話をした。
「俺はさ『銀河一の操縦士』になるのが夢だけど、あんたは将来何になりたいんだよ?」
「レイターのお嫁さん」
「それでいいならすぐに叶うぞ。けど、ほかにやりてぇ仕事とかねぇのか?」
「お花屋さんかな」
「わかった。じゃあ、俺の船で宇宙中旅しながら花売って暮らすってのはどうだ」
「楽しみだわ」
そう言ってフローラは笑った。大きな夢ってわけじゃねぇ、手に届く未来だと思ってた。他愛のない日常、って奴はずっと続いていくもんだって疑ってなかった。
*
アステロイドの飛ばしから戻り、師匠のレース映像をティリーさんと見る。何度見てもカーペンターはすごい。その桁外れな操縦の感性をティリーさんと共有できるのがうれしい。
「師匠とレイターはどっちが速いの?」
その答えを俺も知りたい。今の俺なら師匠に勝てるのか。いや、『あの感覚』を操れない俺があいつに勝てるわけがねぇ。
「刑務所から出てきて、レイターの師匠になったということ?」
カーペンターと俺の関係をティリーさんが聞きたがってる。けど、あの頃のことを今は触れられたくねぇ。過去から人は逃げられねぇんだ、ってことを思い知る。いや、別に逃げてるわけじゃねぇけどな。うまく説明できる気がしねぇ。嫌われたくねぇって感情が俺に残ってたことに驚く。
フェニックス号にはティリーさんの調理用エプロンが置いてある。一人じゃ任せられねぇが、一緒に飯を作る。
火のコンロの扱いにも慣れてきた。芋を炒めるティリーさんが、俺に顔を向ける。
「あん? どうした?」

「こんなに弱火で大丈夫かしら」
「いいんじゃね。じっくりゆっくり頼むぜ」
コンロの火をのぞきこむティリーさんが、かわいくて仕方ねぇ。抱きしめたくなる。
向かい合って飯を食う。
「おいしい」
「当り前さ、俺が作ってんだ」
「あら、わたしの炒め方がよかったんでしょ」
会話の全てに「幸福」という言葉が刷り込まれているようだ。
日常がその「幸福」ってやつをどんどんと送り込んできて、世界を膨らませていく。
俺はこの感覚を知っている。身体中の細胞が満ち足りた世界。
そして、俺は知っている。この「幸福」って世界はシャボン玉のように一瞬で壊れてしまうことを。
膨らめば膨らむほど、俺は怖くなる。これ以上追い求めることを自制する。失う辛さを俺の身体は覚えている。
いいなと思ったら応援しよう!

