
古典ミステリー初読再読終読:The Tattoo Murder Case (高木彬光『刺青殺人事件』英訳)
高木彬光の『刺青殺人事件』は二度、というか、二種のエディションをそれぞれ少なくとも一回ずつは読んでいるし、大幅に増補した第二稿のほうは二度読んだかもしれない。
今回は英訳版を読んだのだが、比較したわけではないものの、分量から云って、これは当然、増補改訂後の第二稿、ロング・ヴァージョンの翻訳だ。
◎安吾の酷評
そう云ってはなんだが、高木彬光という人は、文章力にはまったく定評のない作家で、十代の時、読んでみなさいと薦めてくれた先達も、「文章はひどいけれど、我慢して読むだけの価値はあるよ」と笑顔で言葉を添えた。
いやはや、じっさい、その通りというしかなかった。若気の至りで、その後、わたしは何かというと、高木彬光の文章を日本語バッド・ライティングの典型例としてあげつらうようになった。

坂口安吾が「『刺青殺人事件』を評す」という長めの論評(というか、痛烈極まりない批判!)を書いているのだが、おおむね妥当、と思う。
・密室トリックなど愚の骨頂(イエス。ただ、これは作中、神津恭介も、つまらないメカニカル・トリックだと云っている)
・犯人がすぐにわかってしまう(イエス。容疑者、動機のある人間が少なすぎるし、人物像も真っ正直に犯人を示している)
以上の二点は、まったくその通りです、安吾先生! というしかない。

「この作者は、よいトリックをもち、性本来ケレンがなく、論理的な頭を持っているのだが、つまり、読者に提出して行く工夫に、策が足りなかった。そして、文章もまずい。まずいけれども、さのみ不快を与えるほどの文章でもないから、これから筆になれゝば、これで役に立つだけの文章力はある」
褒めているんだか貶しているんだか判然としない微妙な云いっぷりだが、たしかに「これから筆になれゝば、これで役に立つだけの文章力はある」という評は正鵠を射ている。
日本語の上手くない書き手は苦手なのだが、高木彬光はその後、十数冊読んだのだから、見限ってしまうほどひどいとは感じなかったことになるし、安吾の見立て通り、安定していったし、『白昼の死角』『誘拐』『破戒裁判』のような、シリアス・ノヴェル寄りの長篇には適した文章になっていった(いや、「上手くなった」とは思わないが!)。

なんというか、台詞を棒読みする俳優が、年とともに重厚になり、若いころは下手くそに感じた棒読みがえもいわれぬ「味」に変わる、ということがあるが(佐分利信、高倉健が念頭にある)、それに近い雰囲気で、小器用で中途半端に書けるよりはよほど気持がいい無骨さ、とでもいうようなものを獲得した。
◎英語で読むということ
そもそも、今回読んだのは英訳版、英語なのだから、日本語のニュアンス、言葉のディテールは消え、文章の味は蒸発し、中井英夫の口癖を借りるなら、「譚」だけがそこに残った。
謎解きミステリーのトリックというのは、わかってみれば、たいていが「なあんだ」であって、はじめからそれを承知で読むのだから、その点についての安吾の評は、微妙にアンフェアというべきかもしれない。

バラしになってしまうが、入れ替えトリックなのだということははじめから見え見えだ。何の意味もなく、遺骸からわざわざ首と四肢を切り離して、胴体だけを持ち去ったはずはないのだから、これは被害者のアイデンティティーをくらますためとわかりきっているし、ほかに候補がないのだから、誰と入れ替わったのかも一目瞭然。
これが安吾の批判の要のひとつで、ご説ごもっともなのだが、ただ、その入れ替えがどのようにおこなわれたか、その方法については、十代の初読のときは、おお、と思った(むろん、これまたわかってしまえば、どうということのないものなのだが)。
やはり、ここは多くの読者が感心するのではないだろうか。ここを否定すると、ただの愚作になってしまうし、わたし自身、次作『能面殺人事件』に手を出したほどだから、この点は謎解きミステリーとして面白く感じたのだろうと若き日の自分の胸中を想像する。乱歩が賞讃したのも、このあたり故にではないだろうか。
◎博士の異常な愛情
坂口安吾の酷評にも拘わらず、英訳出版する価値は十分にあったと思う。それは、序盤の、殺人が起こるまでのもろもろに強い熱があるからだ。英語で読むとそれがよりはっきりする。
だいたい、ふつうの読者は刺青(彫り物)のことなどろくに知らないし、好む人も多くはないだろう。公衆浴場では入場を拒否されることもあるほどで、善良な市民のすることとは思われていない。高木彬光は、そういう常人社会の偏見に抗して、これは日本にしかない芸術形態なのだと説く。

冒頭の「刺青博士」の「コレクション」への情熱(素晴らしいタトゥーの持ち主である生きている人間と、死後の「皮膚買取」契約をしてまわるので、登場人物たちは彼を「Peeler」=皮剥ぎと呼んだりする)、刺青コンテスト会場の描写、ワトソン役の松下研三の美しい彫り物をしたヒロインとの情交およびそれにつづく恋慕のさま、このへんは英語で読んでも強く惹きつけられる。この長篇の最大の美点と云っていい。
◎入れ墨、刺青、彫り物
ただし、一点だけ、言及されていないことが気になった。三田村鳶魚の本で読んだのだと思うが、「いれずみ」という言葉は使い方に気をつけなければいけないのだそうな。
「入れ墨」というのは、江戸時代にあっては罪人の顔や腕にほどこした前科者の印であり、後年「刺青」と呼ばれるようになったものは、江戸時代には「彫り物」と呼んで、截然と区別されていた。

だから、タトゥーを施すアーティストは「彫師」であり、「刺青師」とは云わなかった。彼らの名前も「彫辰」だの「彫芳」だの「彫常」というように、「彫」と名前の頭辞を組み合わせたものだった。『刺青殺人事件』に登場する昭和戦後の彫師たちも、そのような名前を持つ。
肝心なのは、アート・タトゥーは「いれずみ」ではなく、「ほりもの」と呼ばなくてはならず、この両者を混同してはいけない、ということだ。一般人はものを知らないから、どういう言葉を使ってもいい。しかし、作家がタトゥーの美を讃える小説では、一般人と同じ粗雑な言葉遣いをするのは気に入らない。

歴史を知らなかったということはないだろう。「彫り物殺人事件」では意味不明になってしまうから、「刺青」としたのだろう。それはそれでいい。しかし、その看板との不一致を嫌って、「彫り物」と「入れ墨」の関係に言及しなかったのはよろしくない。
まあ、英訳では日本語のタームの問題に立ち入っても読者にはわからないので、訳者がその部分をオミットしたのかもしれない、ということにしておく。

「しせい」とルビがふってあり、かろうじて「入れ墨」ではないことが表現されている。
◎いわゆる「戦後の混乱」
大昔の初読ではあまり意識しなかったのだが、『刺青殺人事件』は1947年に書かれ、翌年に出版された(現在流通しているものとは大きく異なる、ノヴェラ程度の枚数のファースト・エディションだが)。
当然、空襲で破壊された戦後まもない東京が描かれている。ビルはしばしば空襲で火が入った「焼けビル」だし、ワトソン役の松下研三はいつも粗末な服を着ている(神津恭介はなぜかいつもいいものを着ているのだが、戦前のものが保管されていた、と解釈しておく!)。

後年の読者からすれば、もっと町や人びとのディテールを書いてほしかったと思うが、目の前に存在しているものの歴史的価値、稀少性にはリアルタイムでは意識が及ばないものだし、風俗描写はすぐに腐る、という文芸評論家たちの妄説に配慮したのかもしれない。
みな使っているタイムスケールが短すぎるのだ。発表から半世紀もたてば、一度は腐ったと思われた風俗描写が輝きを放ちはじめるのは多くの小説が証明している。もっと長距離でものを考えてほしい。昔の本を読む最大の楽しみは、現代とは異なる時代の空気を味わうことなのだから。
◎殺しは世につれ
世相を濃厚に反映したミステリーは楽しい。歌は世につれ、世は歌につれ、人殺しは世につれ――犯罪のありようは社会のストレートな像であったり、反転した像であったりするものだ。
たとえば、「最後の『トレント最後の事件』:探偵の退場と人間の登場 」の「◎アヴァンゲールとアプレゲール」の項に書いたが、フィルポッツ『赤毛のレドメイン家』が第一次世界大戦の惨禍がもたらした人心荒廃による犯罪を描いたように、『刺青殺人事件』も、戦争がもたらしたニヒリズムを背景にした犯罪だし、彫り物をする人びと、彫り物に強い関心を抱く人びとの心性もまた、敗戦がもたらした退廃を反映している。

こちらはやくざ者の話なので、入れ墨でもかまわないようなものだが、主人公が背負っているのはむろん、アート・タトゥーで、もはや彫り物という由緒正しい言葉がすっかり忘れ去られたことがうかがわれる。
探偵小説、謎解きミステリーもまた小説である以上、やはり「時代の鏡」としての小説という側面を豊かに備えているべきだし、『刺青殺人事件』は数ある本格派謎解きミステリーの中でも、濃厚に時代の空気を反映した「小説」になっている。
◎翻訳の些末な細部
訳文自体は、通常そうであるように、ひねくれたところのない文章で、読みやすかったが、いくつか、誤解と思われる個所もあった(しかし、日本語への翻訳だったら、そんなのざらだろうが!)。
アート・タトゥーを扱っているので、その画題として「浮世絵」にも言及されていて、「浮世」にはよく使われるFloating worldという訳語を採用しているのだが、以下のセンテンスは、それでは通じないと思う。
Whoever invented the term ukiyo—floating world— knew what he was talking about. It’s like they say: Life is hell.
「浮世――「浮かび漂う世の中」という言葉を誰が発明したにせよ、ちゃんとものごとを弁えていたことになる。人生は地獄だ、ということなのだ」(高木彬光の原文ではなく、英文から逆翻訳してみた)
これは、「浮世」の語源の問題で、一説に「憂き世」から転じたとされることから来ている。「浮世」では地獄にはならない。「憂き世」=いやな世の中だから地獄なのだ。英訳者は「浮世」という言葉の背景を知らず、辞書の云うままに訳してしまったのだろう。それで意味の通らないセンテンスになってしまったのだ。
以下は思わず笑ってしまったくだり。
Tsunetaro reached up and took down a bottle of Castory whiskey with his name on it, poured a shot into a small glass
Suntoryに似ているので、一瞬、固有名詞かと思い、そんなウィスキーがあったのかなあ、と検索のためにブラウザーに切り替えそうになってしまった。カストリ=粕取りなんだから、Kasutoriとしてくれればいいのに!
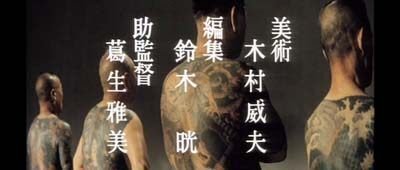
カストリ焼酎は粗悪な密造酒で、「焼酎」ですらない、危険なエタノールやメタノールの混合物もあったようで(小栗虫太郎はこれで命を落とした)、それを「whiskey」と云われてもなあ……。
そのような立派なものではないし、日本の戦後をあらわす特別なアイコンだけに、読者に違和感を与えなければいい、という事なかれ主義の翻訳にしてほしくはなかった。
アメリカの読者は訳注というものを嫌うのか、パーレンないしブラケットで挟んだ日本文化に関する注釈というのはゼロ。本文中に、地の文として、あるいは訳語として(tatami matなどというように)説明されている。まあ、よその国の習慣にああだこうだ云っても無意味ですな。
◎音楽
山田風太郎のエッセイで読んだのだが、風先生自身は音楽にはそれほど興味がないにもかかわらず、親しい高木彬光に誘われて欧州旅行をし、バイロイトまで行ったのだという。高木彬光は音楽が好きなので、もちろん、バイロイト音楽祭のために行ったのだ。
ということは、当然、ワーグナーの大ファンということになる。ここいらは、『帝国の死角』などの戦争を扱った、構えの大きな長篇のバックボーンになっているような気がする。
昔、読んだときはあまり意識していなかったが、『刺青殺人事件』にも音楽への言及がある。メモを取っておいたのは、ピアニストである松下研三の義姉が生徒に教えているFive Easy Piecesというもので、これはどうやらストラヴィンスキーのピアノ連弾曲を指すらしい。
うちのHDDを検索すると、ストラヴィンスキーは数十枚確保してあったのだが、多くはピエール・ブーレーズ全集に収録されたものだし、わたしの蒐集の方向がチェンバー・ミュージック、シンフォニー、コンチェルトなどに偏っているため、ストラヴィンスキーのピアノ曲は持っていなかった。

いま、同じ高木彬光の『能面殺人事件』英訳を読みかけているので、いずれそちらで音楽のことを検討することにして、ストラヴィンスキーは宿題にする。
なんて書いてから、IAを見たら、ちゃんとFLACがあったので聴いた。連弾曲なので、先生が難しいほうを弾き、生徒には音数の少ないパートを弾かせることができ、ピアノ教育に適している、ということで、自宅でピアノ教室をしている松下警視庁捜査一課長夫人の日常を描くのにふさわしいものとして選ばれたのだろう。
