
続々・キャロル・ケイとフィル・スペクター
(「続・キャロル・ケイとフィル・スペクター 」よりつづく)
今回は、アメリカ三大音楽都市の中で唯一、ハリウッドだけで録音されていた、映画スコアのことを書くが、本題に入る前に、ちょっと、いや、おおいに手続きが要る。
◎映画スコアと映画音楽
「映画音楽」=film musicという言葉があるが、これはここでは使えない。かつてよくあった、オリジナル・サウンドトラックではない、なんとかオーケストラの有名な映画主題曲を集めたアルバム、一種のカヴァー・アルバムがここに入ってしまうからだ。

こういうカヴァー集は「映画音楽」Film Musicであって、「映画スコア」ではない。
キャロル・ケイがプレイしたのは、そうではなく、主として映画あるいはTVドラマそのものに付属する音楽、OST、オリジナル・サウンドトラックのほうである。
これは「映画スコア」=film scoreという。日本には「劇伴」という下品な言葉が存在するらしいが、そういう俗語はここでは使わない。アメリカ音楽の話なのだから。
ということで、ここで扱うのは、「映画スコア」「フィルム・スコア」であある。「映画音楽」ではない。
◎サイケデリック・イヤーズ、前置きをもうひとつ
キャロル・ケイに関するテレビ番組では、70年代になると、彼女はポップ/ロック系の音楽から、より高度な音楽を目指して、映画スコアのほうに転身した、と説明されていた。
間違いとは云わないけれど、でも、それはやっぱりちょっと違う。どこが違うか。まず、彼女は60年代からすでに映画スコアの仕事をしていた。それはハル・ブレインなども同じだ。そして、「転身」の第一の理由は高度な音楽性ではなかった。
なぜポップ/ロック系の仕事をやめたのか。これがテレビでは云いにくいから、あの番組では、仕事の方向性を変えたというようなニュアンスにすり替えたのかもしれない。どういうことか?
まず、サイケデリックの時代というのがあった。66年後半からはじまり、67、68年と猖獗を極めた。たとえば、ジェファーソン・エアプレインやグレイトフル・デッドやクウィックシルヴァー・メッセンジャー・サーヴィス、そしてモビー・グレイプなどのサン・フランシスコのバンドに代表される、あまり身ぎれいではない連中が登場した。

ハリウッド録音で、プロデューサーはデイヴ・ハーシンガー。この時はデッドもじっと我慢したが、セカンドの録音では、プロデューサーの云うことには耳を貸さず、激しく自己主張し、最終的に全面衝突に至って、ハーシンガーを追い払った。
彼らは、それまでの芸能人タイプの音楽スターとは異なり、自分たちはミュージシャンであると自負していた。だから、スタジオに入り、自分でプレイをした。プロの助けなどいらないどころか、プロデューサーですら、邪魔な異物として排除することがあった。音楽をつくるうえで、他人の指図を受ける気などなかったのだ。
(「続・文字盤上の天使の分け前 Grateful Dead - Wake of the Flood: Angel's Share」という記事に、デッドがプロデューサーのデイヴ・ハーシンガーを追い出した経緯を書いた。)
プロデューサーですら邪魔と考える連中なので、むろん、スタジオ・プレイヤーも拒否した。上手かろうが下手だろうが、自分の音楽は自分で作る、という、ビジネスを離れて考えれば、いたって真っ当な考え方で音楽を捉えていたのだ。
これでロック系の仕事は減りはじめ、ポップ系だけが残ったのだが、サイケデリックの時代とは、すなわち薬物の時代である。ビートルズも67年ごろ、ジョージ・マーティンに隠れて、休憩時間にEMIスタジオのトイレや屋上で葉っぱをどうこうと回想していたが、当然、ハリウッドでもそうなった。

これまたデイヴ・ハーシンガーのプロデュースで、ハリウッドで録音された。
キャロル・ケイはまじめな人だ、仕事場でグラスやエルやその他の薬物を見るようになって、もうそういう人間が出入りするような仕事はやめようと考えた。そして、その時期には、もうハリウッド・ビートの黄金時代、すなわちスタジオ・プレイヤーがキングだった時代も終わろうとしていた。
◎基礎教養
映画スコアは、すぐれてプロフェショナルの仕事だった。1秒間16コマの世界、フィルムの尺数=フィート数を基準に音楽がつくられるのだ。読譜能力は必須である。したがって、弦はクラシック出身、ホーンとリズム・セクションはほぼ4ビートのプレイヤーで占められていた。
その後、ロック系でも教育を受けたプレイヤーが生まれるようになるが、昔は自己流のプレイヤーばかりだった。ハリウッドのスタジオに多かった、カントリー出身のプレイヤーもみな自己流で、譜面を読めなかった。
だから、ジョー・オズボーンは映画スコアをやっていないはずだ。やったとしても、譜面不要、タイミング合せ不要の挿入曲だろう。そういう音楽は別途録音したものを、あとから音楽編集者がシーンに合わせて編集して填め込むので、映画の場面を見ながら譜面通りに録音する必要はない。グレン・キャンベルもカントリー出身で譜面を読めなかった。

ビーバッパーだったトミー・テデスコは、もっとも読譜能力があったそうで、ポップ系のセッションでは、譜面を読めない連中のかわりに読んであげ、お前はこう弾く、などと教えていた。当然、大量の映画スコアをやっている。最晩年まで映画の仕事をしているので、総数はキャロル・ケイの数倍に達するだろう。

やはりカントリー出身だったビリー・ストレンジは、60年代なかばにバイクの事故で腕の骨を折ってギターを弾けなくなった。その療養中に譜面の読み書きを習得し、アレンジャーとしてスタジオに復帰した。そして、国内ではヒットがなく、鳴かず飛ばずだったナンシー・シナトラに、ビルボード・チャート・トッパーをもたらした。

ドラマーはどうかと云うと、アール・パーマーもハル・ブレインも(そしてナシュヴィルのバディー・ハーマンも)音楽学校を出ている。当然、譜面も読めた。
ハルはポップ/ロック系の仕事で忙殺されていたのか、それほどたくさん映画スコアをやっていないが、アール・パーマーは映画、テレビともにスコアを数多く録音している。読譜能力のおかげだ。
◎映画の仕事をするということ
ハリウッドはもちろん映画産業の町として発展してきた。1950年代半ばまでのハリウッドのメイジャーは閉鎖的で、ほとんどの従業員は縁故採用だったし、原則としてフリーランスはいなかった。すべて各撮影所の社員が内製していたのだ。

ハリウッドの歴史に関する本はいろいろあるが、これは面白かった。
音楽関係も、作曲家からプレイヤーに至るまで、全員がスタジオに所属し、週給を貰っていた。契約期間は一年だが、きちんと仕事をすれば、毎年更新された。そして、彼らはみな高給取りだった。
優秀な成績で音楽学校を出たクラシックのプレイヤーは、まずハリウッドに勤め口を見つけようと試み、駄目だったら、しかたなく、東部の有名な交響楽団に就職した。
NYやボストンなどのクラシックのプレイヤーというのは、アメリカではエリートではなく、映画会社に入れなかった二軍選手だったのだ。ハリウッドとは給料がひと桁違ったという。

映画の研究書はうんざりするほどあるが、映画音楽に関する研究書は稀。これもおおいに勉強になった好著。とくに、ジャズ・スコアの発生過程が叮嚀に描かれているのが嬉しい。
そういう業界だったのだが、第二次大戦後、テレビの普及の結果、しだいに映画人口が減り、メイジャー各社は疲弊していった。当然、固定費の圧縮を迫られ、首切りの嵐が起きた。同時に製作の外注、つまり、独立プロダクション制への移行もはじまった。
これで高給取り社員はいわば「野に放たれ」、自分で生きていかねばならなくなった。そういう状況で、フリーランスのフィルム・コンポーザーのエースとなったのが、かつてはユニヴァーサルの一社員にすぎなかったヘンリー・マンシーニだ。

何よりも、ジョゼフ・ガーシェンソンをチーフとした、ユニヴァーサル映画音楽部の家族のように和やかな日常が描かれたパートが面白かった。
社員がいなくなり、内製ができなくなれば、当然、外注しなければならない。かつてきわめて閉鎖的業界だった映画界が一般に公開され、能力があれば誰でも働ける可能性が生まれたのだ。これがプレイヤーたちをハリウッドに惹き寄せた。
アール・パーマーは伝記の中で云っている。俺がノーリンズでつまらない仕事をしているあいだに、ハリウッドの連中は映画の仕事で稼ぎまくっている、と。彼のハリウッド移住は1958年ごろ、つまり、ヘンリー・マンシーニがユニヴァーサル映画を首になったころだ。二人の動きに、映画界の変化がはっきりと見える。
アメリカの音楽家にとって、キャリアの頂点が映画スコアだった理由は、もちろん、才能豊かな選ばれた人間にしかできない、ということもあったが、そのコインの裏側、大金を稼げる、ということが重要だった。
◎「再利用」
キャロル・ケイの映画やテレビの仕事は、彼女のオフィシャルサイトのTV and Filmというページをご覧いただきたい(テレビと映画の分類が混乱しているところがあり、注意が必要)。
50~70年代のものに混じって、たとえば、Kill BillやC.S.I.やERのような、かなり新しめのものがあるが、これは、スコアの録音でプレイしたということではなく、そうした作品の中で、かつて彼女がプレイしたポップ系の曲が再利用されたということだろう。

50年代にハリウッド映画界が大不況に見舞われ、生き残るために、各社がTVドラマの制作に乗りだした過程を描いためずらしいテーマの本。おおいに勉強になった。なんだか軽いノリの表紙だが、テキサス大学出版局によるまじめな歴史研究書。
わたしが毎日、彼女の「ハリウッド音楽史講義」を受けていた(通信教育だが、教授ひとり、学生ひとりの一対一である!)時、今日も再利用の小切手が届いた、でも、わたしはバーズのMr. Tamboourine Manではプレイしなかった、ロジャー(・マグウィン)か誰かが間違えたのではないか、などと書き送ってきた。
彼らスタジオ・プレイヤーは、基本的には時間給を受けるだけで、印税が発生することはないが、その後、法律が改定されたという。映画やテレビで、かつて彼らが録音した曲が使われれば、Reuse料金というものが支払われるようになったのだという。
キャロル・ケイは60年代の多くの大ヒット曲でギターやベースをプレイした。だから、たとえば、自分の映画の中で、むやみに昔の曲を使いたがる、クエンティン・タランティーノの映画が彼女のリストにあるのは、必然なのだ。
◎Mission: Impossible(「スパイ大作戦」)1966
以上で前提、歴史、観念はおしまい。少しだけ、具体的な音楽を見ておく。
キャロル・ケイらしい音、といえるのは、やはりベースなので、そちらに限定すると、まず目立つのは、映画ではなく、テレビのMission Impossible(「スパイ大作戦」)である。

音楽監督兼コンポーザーはラロ・シフリン。アルゼンティンのピアノ・プレイヤーが、ディジー・ガレスピーと出会ってアメリカに渡り、フィルム・コンポーザーへと変身しはじめた時期のもので、このドラマのテーマでシフリンは有名になった。
5/4タイムに5度のフラットを中心にした奇妙なメロディーを組み合わせるという、変則の自乗のような非常にユニークな曲で、このドラマの大ヒットに一役買った。後年の劇場映画化でも、このテーマは依然として使われていることが、シフリンのすごさを証明している。
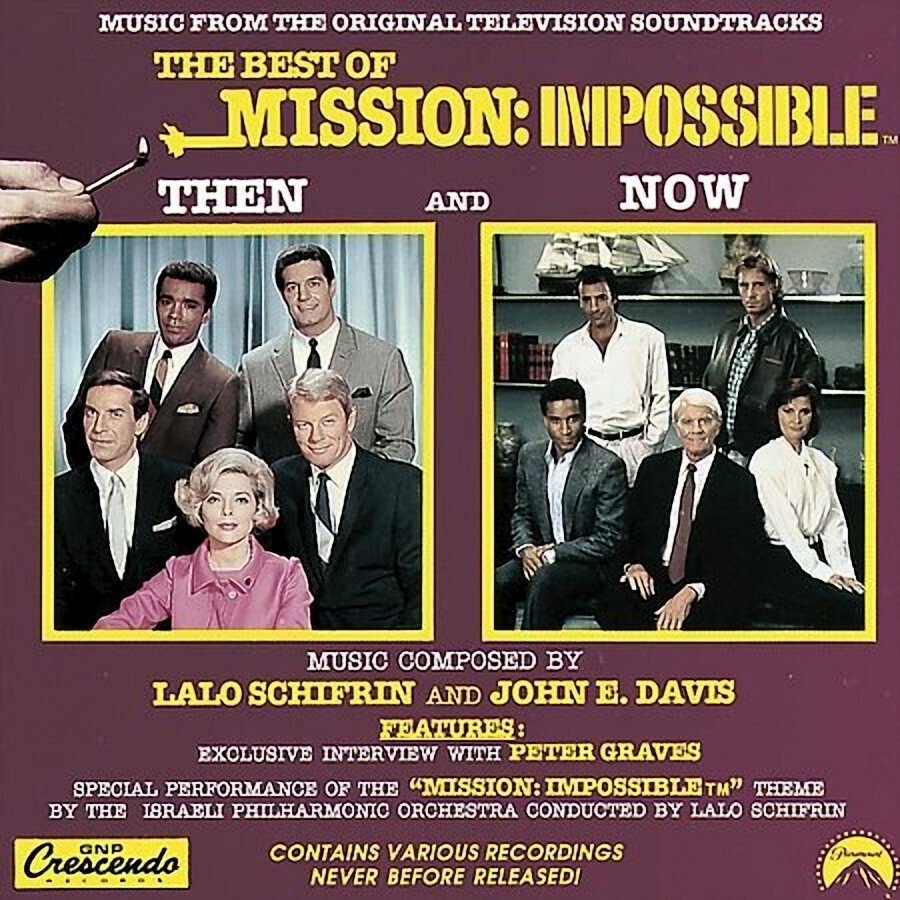
前掲のアルバムはレコード・リリース用の再録音だと思う。こちらに収録されているショート・ヴァージョンがじっさいにテレビで使われたテーマ曲。
キャロル・ケイは彼女らしい力強いプレイで、ドラムズのアール・パーマーと協力し、変拍子にも拘わらず、ソリッドなグルーヴを形作っている。
◎ノーマン・ジュイソンのIn the Heat of the Night(『夜の大捜査線』)1967年
子供の時、映画館でこれを見て、すぐにレイ・チャールズの唄った主題歌を買った。音楽も撮影も演技も演出も、すべてがハイ・レベルの映画だった。
夜汽車のショット、夜の駅というのが大好きなのだが、この映画のオープニングも素晴らしい絵で(撮影監督はハスケル・ウェクスラー、彼の代表作と云える)、そこに渋いブルーズが入ってきて、こりゃたまらん、と一発で惚れた。


亡くなったばかりなので、けなしにくくなったが、クウィンシー・ジョーンズは主題歌とスコアの両方を書いているものの、スコアのほうは、アレンジが鈍くさく、フィルム編集のリズムに合っておらず、苛々させられる。アクション・シーンの緊迫感もつくれていない。

主題歌はストリング・ベースとキャロル・ケイのフェンダー・ベースの両方が使われていると思う。ドラムはアール・パーマー。ビリー・プレストンがオルガンで素晴らしいプレイをしている。
ラスト・シーンも列車、こんどは昼間のショットで、こちらもすごい撮影。ハスケル・ウェクスラーはほんとうに素晴らしい撮影監督だった。
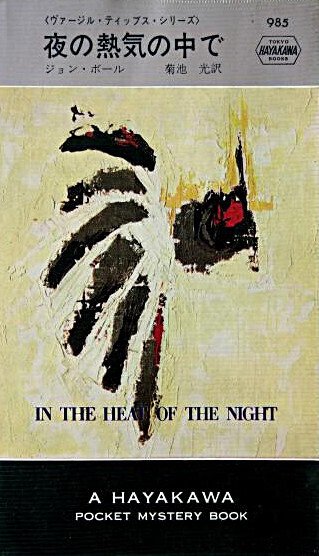
◎ピーター・イエイツのBullitt(『ブリット』)1968年
これも子供の時に見た。長者町のいまはなき横浜ピカデリー、それも指定席で見たので、アクション映画を好んだ父親に連れて行ってもらったに違いない。

これは「カー・スタント」という、その後、アメリカのアクション映画には欠かせなくなったアトラクションが誕生した映画である。われわれはこのピーター・イエイツの映画ではじめて、実車を使った高速のカー・チェイスというものを体験した。そこがわからないと、この映画の衝撃力がわからない。

In the Heat of the Night同様、この映画もオープニング・シークェンスが素晴らしい。キャロル・ケイのベースもはっきり聴こえる。彼女はグルーヴも素晴らしいからエースになった。4分を繰り返すだけというプレイでも、単調にならず、高い精度の音で、緊迫感を生んでいる。

◎ノーマン・ジュイソンのThe Thomas Crown Affair(『華麗なる賭け』)1968年
ケイパー・ストーリー、綿密な計画による泥棒物語で、いまも昔も大好物、こういうのは片端から見ていたし、ジュイソンも子供の時は好んだ。
何も調べずに、記憶で云ってしまうが、のちにちょっとブームになる(たとえば、ロバート・ワイズ監督、ギル・メレ音楽監督の1971年のAndromeda Strain)、スプリット・スクリーン手法を大々的に使った最初の映画ではないか。いや、手間も金もかかる手法で、大予算映画にしか使えないから、「ブーム」というのは云い過ぎかもしれないが。

音楽監督はミシェール・ルグランで、この映画あたりから、アメリカ映画の仕事がはじまり、ハリウッドで録音するようになったのではないかと思う。
ノエル・ハリソンが唄ってヒットした主題歌、じつにもって面妖きわまりない、5度に戻らず、ぐるぐる旋回してしまう「〝終止〟感のない」コード進行のWindmills of Your Mindは、多くのカヴァーが録音され、スタンダードになった。
それも当然という美しい曲で、この曲が流れるグライダーのシークェンスは、ロベール・アンリコ監督、フランソワ・ド・ルーベ音楽監督のLes Adventuriers(『冒険者たち』1967年)の複葉機のシークェンスに比肩する、美しい音楽による、美しい飛行ショットだ。

ベースは、フェンダーとストリングが半々ぐらいで(60年代の映画ではよくあった。In the Heat of the NightもBullittも二種類のベースの併用、ケイはフェンダー・ベースしか弾かないので、ストリング・ベースは別のプレイヤー)、主題歌はキャロル・ケイのプレイ。シンコペーションをきかせた、Cash And CarryやThe Boston Wranglerといったトラックに、彼女のベースの魅力があらわれている。

◎スティーヴン・スピールバーグのDuel(『激突!』)1971年
スピールバーグの出世作ではあるが、まだ無名だった。何も予備知識なく、目当ての映画の同時上映だったので、なんとなく見ただけ。
しかし、見てびっくり。同じように予備知識ゼロで見た、サム・ペキンパーのThe Ballad of Cable Hogue(『砂漠の流れ者』1970年)と同じぐらいに驚いた。低予算だが、みごとな演出である。

次作の『ジョーズ』を予感させる構造だが、わたしにはDuelのほうが怖い映画に感じられた。人喰い鮫なんかより、危険運転をする巨大トレーラー・トラックのほうがはるかに怖い。
トレイラーのディーゼル・エンジン音が主役、と云いたくなるほどなので、音楽はごく控えめだが、キャロル・ケイは、彼女がやったもっとも奇妙な仕事として、この映画をあげていた。それは、音楽だけでなく、トレイラー・トラックの効果音までベースでつくったからだ。
記憶ではブレーキ音もやったと書かれていたと思うが、映画を再見してみつけたのは、怪物トラックが、踏切りで停車している主人公の車をうしろから押して、通過する列車にぶつけようとするシーンの、エンジンを吹かす音だ。エンジンの回転数の上下が、ベースの上下スライドで表現されている。


まあ、ゴジラの咆哮はベースなどの楽器音をミックスしたものだそうだし、小林正樹監督、武満徹音楽監督の『怪談』(1965年)のように、効果音もすべて楽器でやった(当然、武満徹が担当した!)映画もある。数多くフィルム・スコアをやれば、そういう経験もするということだろう。
◎ピーター・イエイツのHot Rock(『ホット・ロック』1972年)
また嫌いなクウィンシー・ジョーンズだが、ピーター・イエイツは大好きだった。いや、これは、原作が大の贔屓のドナルド・ウェストレイク、そのもっとも楽しい「不遇の天才泥棒ジョン・ドートマンダー」シリーズの映画化一作目だから見たのだが。

いや、映画の内容には踏み込まない。原作とはかなり異なるプロットになっていて、「不遇の天才泥棒」ではなく、「不運に打ち克ちミッションを成し遂げた天才泥棒」だったが、まあ、いい。
映画のほうは、「失敗にめげずに挑戦を続ける泥棒のシリーズ」にするつもりはなかったのだろう。じっさい、ロバート・レドフォードがジョン・ドートマンダーを演じたのはこれ一作だけだ。
キャロル・ケイがとくにこの映画に言及していたのは、音楽の中身ではなく、エンディング・クレジットが詳細で、録音メンバー全員の名前が記録されているからだった。彼女自身は、映画の最後に自分の名前を見たのは、後にも先にもこれ一回だけだという。
いまでは、挿入曲のひとつひとつについて、作者とパーフォーマーの名前が詳しくクレジットされるが、スコアでプレイした人間の名前まで書いてあるものは、依然として少ないだろうと思う。
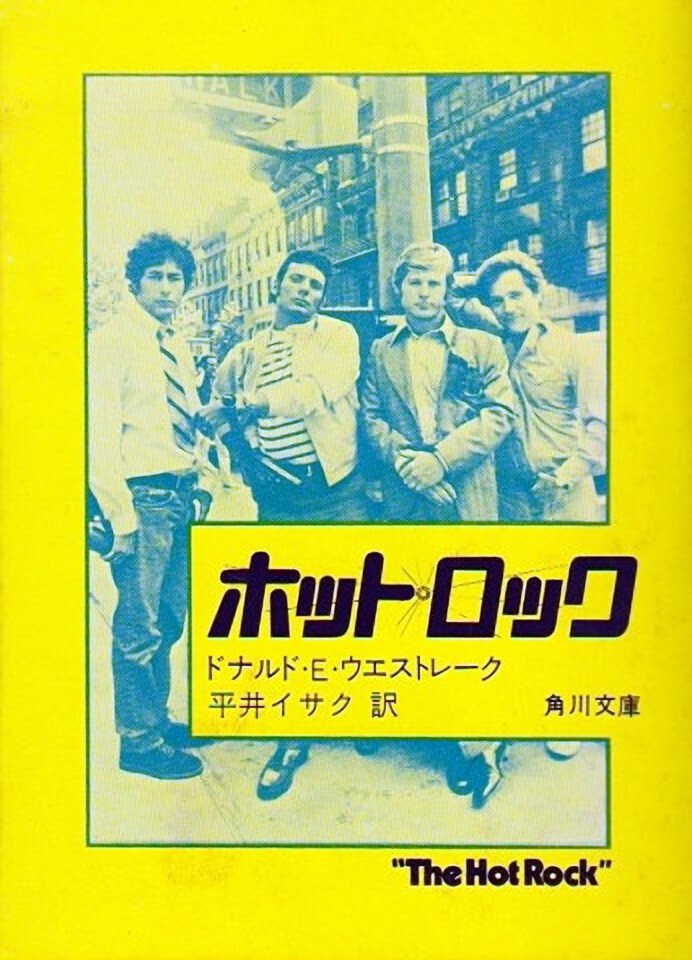
◎ジャズ・ファンク・スコア
映画スコアなので、OST盤を再聴するだけですますわけにはいかず、大急ぎで映画も再見したため、一握りしか検討できなかった。
そのわずかな映画、ドラマを並べただけでも、キャロル・ケイはポップ/ロック系の音楽ばかりでなく、映画スコアでも、わたしの子供のころに痛烈な印象を残したものでプレイしており、「俺の時代のプレイヤー」だったのだ、とつくづく思う。
いまになって子供のころを振り返ると、日本のフィルム・コンポーザーは佐藤勝と武満徹が「俺の時代の作曲家」と云える。アメリカを見ると、それに相当するのはヘンリー・マンシーニとラロ・シフリン、そしてジェリー・ゴールドスミスだった。

マンシーニはオーソドクスなタイプだが、ゴールドスミスとシフリンはイノヴェイターだった。とくにシフリンは、その後、アクション映画ではごく当たり前になる(Dirty Harryの一作目でその種のサウンドを認識した)、ジャズ・ファンク・スコアの発明者だった。その出発点はBullittだろう。
だから、キャロル・ケイのアグレシヴな、力強いフェンダー・ベースのグルーヴが必要だった。いや、むしろ、彼女のグルーヴに刺激されて、ファンク方向へとシフトして行った、とすら云えると思う。
ポップ/ロック系の代表的なプレイにも触れたかったが、これでいったん彼女の音楽については終える。そのあたりは有名なアルバムも多いので、彼女のウェブ・サイトをご覧になり、手持ちのものを聴き直せばよろしからん。
Some Recommended Listenings:
・The Beach Boys - Pet Sounds Sessions
・Brenda Holloway - The Very Best of Brenda Holloway
・Elvis Presley - Live a Little, Love a Little
・Harpers Bizarre - Anything Goes
・The Buckinghams - Mercy, Mercy, Mercy: A Collection
・Glen Campbell - Wichita Lineman
・Diana Ross & The Supremes - Anthology
・Four Tops - The Singles
・Nancy Sinatra - The Hit Years
・Barry White - All Time Greatest Hits
・Tom Scott - The Honeysuckle Breeze
・Gabor Szabo - Wind Sky and Diamonds
・Joe Cocker - Feelin' Alright (45, studio version)
・Carol Kaye - California Creamin'
