自由さはあるが、手に余る〜『CHESS The Musical』
2020年2月7日、東京国際フォーラムに『CHESS The Musical』を見てきた。
当初見にいくつもりはなかったのだけど、サマンサ・バークス大ファンの友人が大喜びしている姿に触発され、「ライヴでサマンサ見にいくか...!」という気分が盛り上がって気づいたら(ファンとは別の)友人にチケットを予約してもらっていた。
『CHESS』は、ティム・ライス原案・作詞、ABBAのベニー・アンダーソン&ビョルン・ウルヴァース作曲のコンセプト・アルバムから出発したミュージカルである。
ミュージカル史上では「目安となる『完成形』のない、ワーク・イン・プログレスの作品」として知られている。
ロンドン初演とブロードウェイ初演の間ですら脚本や楽曲が変わっている、少し毛色が特殊な作品である。
たとえば、ロンドン初演時は第一幕がイタリアはムラーノで、第二幕はタイはバンコクで展開される。ところが、ブロードウェイ初演時は第一幕がバンコクで、第二幕はハンガリーはブダペストに舞台を移す。当然楽曲の順序や登場人物も異なっている。
今回のプロダクションがロンドン初演版をベースにしていることは把握しつつも、家にブロードウェイ版の脚本があったので観劇前に目を通してから臨んだ。
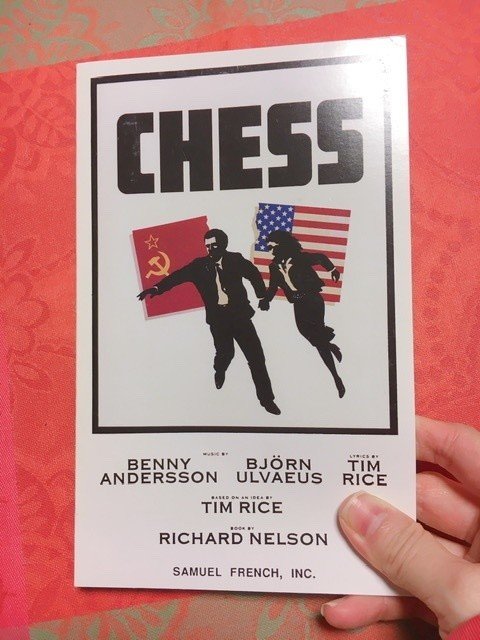
驚くくらい作品の手触りが異なっていた。
初演から30年以上経っても目安となる「完成形」がないってどういうこと?いい加減そろそろどうにかなるんじゃない?と脚本を読んだり上演を見たりする前には正直感じていた。
だが、見て読んで考えた結果、「手に余るミュージカル」ということがヒシヒシと感じたのである。
その要因は、そもそも『CHESS』という作品を構成する要素が非常に多くバルキーなことにあると思っている。
・冷戦末期に
・チェス国際大会の決勝戦で
・アメリカとソ連の選手が対決し
・アメリカ側のセコンドはハンガリー動乱から幼少期に逃れてきた女性で
・ソ連選手は彼女と恋に落ちて亡命を決断
・するものの、残された妻子や生死不明となっている恋人の父の居所を盾にとられ
・ソ連選手は生国への帰還を決意し、二人は別れる
要素が、多い。
この要素の多さは、「この作品は何を打ち出す作品なのか」を鈍らせ不明瞭にさせる危険性も帯びている。
大元のアイディアのベースにあるのはナショナリズム批判だろうが、要素の多さを持て余してしまうと、たとえば不倫の三角関係ストーリーに終始したり、「で、チェスである意味って?」という根本部分が迷子になってしまう難しい作品である。
目安となる「完成形」が未だ現れていないということは、設定や楽曲を手がかりにしつつ、作り手の創造性を思う存分発揮するチャンスが開かれているということを意味する。
だがその分、創造性自体がモロに浮かび上がって評価の俎上にあがるわけだから、シビアでもある。
今回のプロダクションは、正直なところ、パフォーマーはよかったものの脚本・演出が荒削りかつ雑駁で全く楽しめなかった。
まず、パフォーマンスについて。
少女時代にハンガリー動乱から逃れて米に移住したフローレンスを演じるサマンサ・バークスと、ソ連を背負わされてチェス国際大会の決勝に向かうアナトリー演じるラミン・カリムルーの声の相性がとてもよかった。
二人とも、丸く筋の通った力強い、けれども乱暴ではない歌声が魅力的なのだが、デュエットで声が重なる時の豊かな響きは素晴らしかった。
また本プロダクションは全編英語上演なのだけど、腹と喉と口内が繋がった音声を発してくれたおかげで聞くことへのストレスは予想以上に少なかった。(舞台上で口先だけで英語を発話されると、むちゃくちゃ聞き取りづらいのである。今回はそれを感じなかった)
だが脚本・演出となると、「粗削り」という言葉が終始ちらつく感じだった。
たとえば、アメリカ側の選手フレディと決別したフローレンスが「誰も誰の味方をしていない」"Nobody's Side"を歌った後、アナトリーと近づくかどうなるかジリジリとした距離感が"Mountain Duet"で歌われるのだが、ノータイムすぎて驚いた。
ここ以外にも、楽曲と前後の展開の接続がざっくりしていると思った瞬間はそれなりにあった。移行に際した予兆や余白を描いて欲しい。そうでなければ、コンサートという形式で上演することと変わらないではないか。
また、冒頭の"The Story of Chess"は審判(アービター)が観客に向けて作品の枠組を提示するように歌うという抽象度の高い演出だったのに(ブロードウェイ版では、ハンガリー動乱中にフローレンスの父がチェスとは何たるかをフローレンスに歌い掛ける、という設定になっている)、そして第一幕の対戦の場であるムラーノを提示する"Murano"はカットしたのに、第二幕冒頭のバンコクを紹介する"One Night in Bangkok"は映像とダンスでバンコクの歓楽街を具体的に、つまりはステレオティピックに描くという安直さがいただけなかった。
(わたしはそもそも、日本のミュージカル上演でしばしば、ストーリーの展開や進行への寄与とは関係なく装飾としてセックスワーカーの楽曲が盛り込まれる傾向があることに対して嫌気と不信感を抱いている)
加えて、本プロダクションではバックスクリーンに映像が投射されるのだが、その映像が一昔前のカラオケのイメージ映像レベルのダサさで驚いた。
チェス・プレイヤーとしての野心が国家によって知らず絡め取られた息苦しさをアナトリーが歌う"Where I Want to Be"の背景で、床がチェス盤となった廊下をカメラがひたすら進む映像であるとか、ラミン・カリムルーが高所からチェス盤へと落ちてゆくスローモーションが流れたりする。
楽曲自体で登場人物の葛藤や苛立ちが表出されているのだから、映像は蛇足と感じた。
そもそも、今回のプロダクションでは「チェス」「冷戦」「困難な恋愛」の三大柱の関係があまり愚直に突き詰められていないように感じた。
作品のオープニングを飾る"The Story of Chess"は、次のような印象的な歌詞から始まる。
チェスを打つということは、そのたび未知の手のヴァリエーションが一つ減ること
一日が終わるということは、そのたび失敗の一つ二つが減るということ
そして、チェス発祥の物語から、いかに世界へ伝播し、シンプルながら複雑なゲームとして愛好されるに至ったかが歌われる。
未知の手のヴァリエーションが一つなくなったことを知り、失敗の一つ二つが減ることを知ることは、知的な喜びをもたらす作業である。
だが同時に、猜疑的に世界を捉える見方にも発展しうる。
どんなに先達の手を学び、研鑽を重ね、相手の出方をシミュレーションし、最善の手を打っていたとしても、思いもよらなかった空白が突かれることは起こる。空白が存在していたことは、突かれた後になってからしか分からない。そして、空白を作らないようにすることは不可能である。
チェスがもたらしうる猜疑的な世界の捉え方は、冷戦下で「向こう側」の世界の人間とどのように対峙するかという劇中で(少なくともブロードウェイ版脚本で)時折表出する猜疑的スタンスと通じ合っていると感じた。
だからこそ、フローレンスとアナトリーの間や、フローレンスとスヴェトラーナの間に流れる情感や、フレディが思い出が苛む苦痛を直裁的に発露する音楽と歌が際立つ。
そして、最終局面で歌われる"Endgame"がアナトリーの被害妄想のようにも聞こえるのは、アナトリーが結局はチェスの猜疑的世界観に取り込まれたこと、同時にアナトリーとフローレンスが共に生きる選択はすでに消失したことを表していると考えられる。
チェスをプレイすることで陥る猜疑心や、異質な存在に対する疑いを描いた部分がもっと丁寧に積み重ねられていたら、つまりは、楽曲と楽曲の間がノータイムで移行するのでなく、もう少しドラマ部分に時間が割かれていたら、そして楽曲部分とドラマ部分とのつながりが丁寧に織り上げられていたら、「完成形」とまではいかなくても、三本柱が巧みに組まれた構築物ができていたのではと思われてならない。
上の方で『CHESS』は「手に余るミュージカル」と書いたが、じゃあ誰なら太刀打ちできそうだろうか。
わたしは荻田版を見ていないので、そこではどうだったのだろうか。
あるいは、脚本をトニー・クシュナーあたりが書くのはどうかな、それとも...と上演から一週間経った今もを何となく考え続けている。
