
『キリクと魔女』少しばかりの所感
ミッシェル・オスロ監督『キリクと魔女』(仏:KIRIKOU ET LA SORCIERE、日本語翻訳:高畑勲)を鑑賞した。
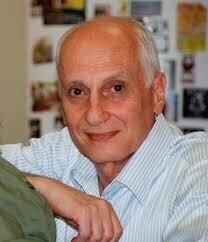
Michel Ocelot監督
以前、高畑勲のエッセイで取り上げられていたのを読んでからずっと気になっていた作品で、つい先日ようやく見ることができた。
ストーリーとしてはアフリカの村が舞台で、少年「キリク」が長年村人を苦しめていた「魔女」と戦う、という筋としては一般的な英雄物語であり、ファンタジーであり、あるいは民間伝承的な話である。
ただそのアニメーションの描き方や演出、話し方が独特で、例えばジブリのようなセルアニメーションとは違うものであった。
全体としてかなり2Dフラットで色彩も強く色とりどりであり、あたかもアンリ・ルソーの世界がそのままアニメートされているかのようだ。

アンリ・ルソー『夢』(1910)
「母さん、僕を生んで」から始まるこの映画の異質さは言葉の使い方にも表れている。
日本語吹き替え(および字幕)版ではなかなか伝わりづらい点ではあるものの、原語によればかなり耳慣れない、プリミティブな言葉の使い方をしている。上の例でいえば、そのまま忠実に翻訳すれば
「母よ、ぼくを子ども化せよ」
となるそうだ。(『アニメーション、折りにふれて』(高畑勲、岩波現代文庫)より)
自分はフランス語が全く分からないのでその言語の違いの面白さというものは十分に享受できなかったものの、しかし翻訳を通してでさえも伝わってくる空気感はあった。
ストーリーとしてはよくあるものでありつつも、こういう異質な世界を(ディズニーやジブリなどとは違った観点で)与えてくれる作品は、感覚としてとても新鮮で非常に楽しめた作品であった。
2021.6.27
