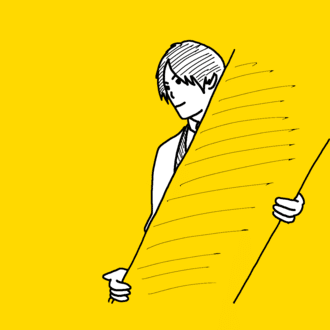ずっと残るものには理由がある
仕事部屋に休憩用の椅子が欲しくて、カリモクのKチェアを買いました。

原型の「1000番」という椅子がカリモクで作られてから今年がなんとちょうど60周年らしいです。
1962年の製品が2022年でも通用するすごさ!
座り心地や造りの良さはもちろん気に入って、当時のエピソードや現在も発展させているモノづくりを読んでさらに好きになりました。数十年ものあいだ基本的なデザインが変わらないことも、素材や造りは改良を重ねてアップデートしていることもすごいですね。

特にこの「ベンチマーク活動」から得られるものはものすごく思い当たります。
カリモクの品質管理の取り組みは挙げればキリがないが、もっともユニークなのは現場の人間が参加する「ベンチマーク活動」だ。
ベンチマークとは、基準の意味。自他ともに認めるその分野の熟練者、たとえば塗装のプロや縫製のプロなど、工場内の1番手が結集して作った1脚が目指すべきベンチマーク商品となる。同じく2番手集団、3番手集団も同様の商品を作る。そして、ベンチマーク商品とそれらとはどこが違うかを比較し、評価するのだ。
〜中略〜
また、食堂にはいつも何かしらベンチマーク商品が置かれている。それは、できるだけいいものに目をふれる機会を多くするためだ。「ベンチマーク活動は、あくまでみんなで学ぶことが目的です。だから、誰が作ったかなどの名前は出しません。『もっとよくできるんだ』ということを知ってもらえればいいのです」
〜中略〜
単にクオリティを維持するだけでなく、よりよいものを目指して、どうすればいいかを常にみんなで考える。みんなの知恵が共有され、もの作りに生かされる。それが最終的に一脚の椅子に結実し、人々のもとに届けられている。
調律の仕事もひとつひとつ教えてもらうよりも、その人の作業したピアノを見ることがなにより勉強になります。
全員が1番手の造り手ではないのを当たり前としているところもなんか良いなと思いました。
全文はこちら↓
今の家に住んでまだ6年くらいですが、思えば前の家から持ってきたもので手放さず残っているのはいわゆる「名作」と呼ばれる家具3つだけです。

どれも10年以上経ちますがまだまだ使いそうです。
ベタ中のベタとも言える家具たちですが、ずっと市場に残っているものにはそれなりの理由があるんだなと思いました。結局ベタってすごい!
この椅子も、我が家でずっと残るひとつになりそうです。
いいなと思ったら応援しよう!