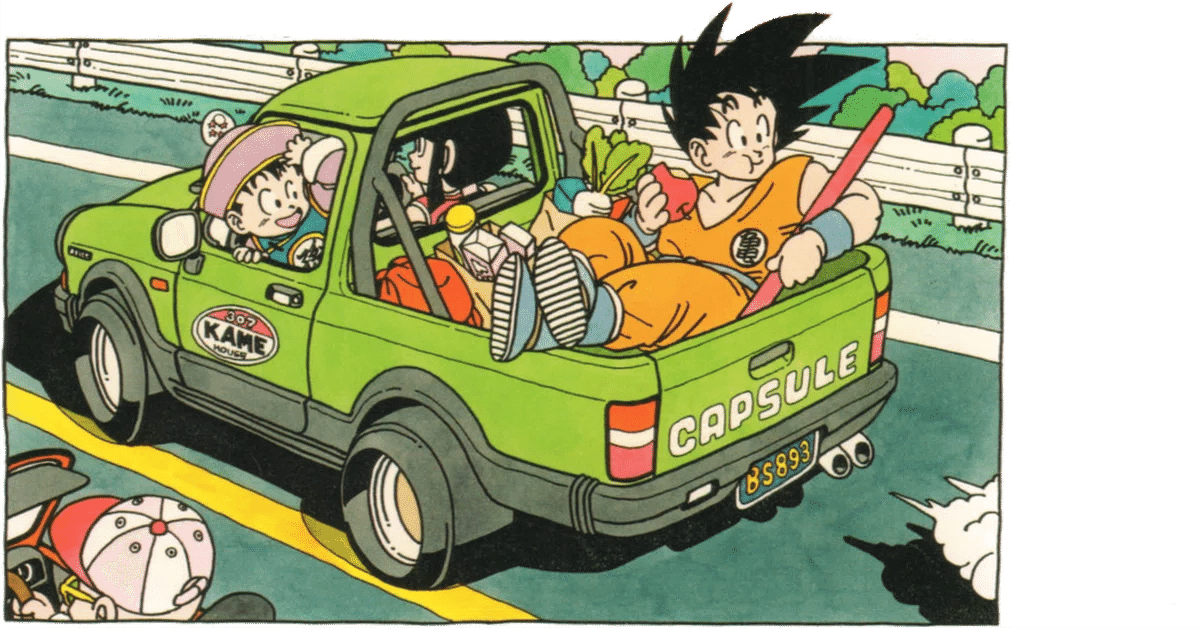モーツァルトの口述筆記をしてみよう(その1)
1月17日の日付ですね第一回ぶん ⇩
.
すると三週間かけて、たった40小節の曲を分析したことになりますね。
もしいきなりオーケストラ譜で分析していたら、もっとかかっていたと思います。
いや待てよ実際にはもっと前から、おそるおそるこの曲に手を出しているから、さらにプラス数日かかってるか。
分析を進めながら、びくびくでした。今日まではなんとか理論で語り切れたけれど、明日はうまくいかなくて、そこで折れてしまうんじゃないか…
数十秒の空白…
折れずに歩き切りました。音楽の神様は、私をお見捨てにはならなかったようです。
今回は、その行程を振り返ってみます。何か致命的なミスをしていないかの確認も兼ねて、です。
冒頭小節から順に見ていくよ
私の想像(それにこれまでの研究によると)では、この楽譜の一番下のパートにある ♪ デレレンレンレンデレレンレンレンデレレンレンレンデレレンレンレン ♪ をウォルフガングは最初に着想し、書き綴っています。

.
分散和音的なオスティナート(音型反復)。つまりここにはすでに和音が埋め込まれています。
Am → E7 つまり短調のトニック → ドミナント和音。

第3~4小節をどう見るか
ここは3~4小節目。Am → Dm つまり短調のトニック → サブドミ和音 ―— と分析するようでは半分しか点をあげられない。一応マルなんですけどね。

ウォルフガングはサブドミ和音という意識は、おそらくろくになかったのではないかと私は想像します。ここ、階名(つまりドレミ)で歌ってみてください。

"ドレミミミ、ミレドドド、ドレミミミ、ミレドドド、レミファファファ、ファミレレレ"
この上昇気流をキミは聞き取ることができるか?
さらに、先ほどの第1~2小節ぶんから通してドレミで歌ってみてください。こんな上昇ラインが浮かんできます。
.
ラ ↗ シ ↗ ド ↗ レ ↗ ミ ↗ ファ
わかりますね?
さらに5小節(の前半)を見ていくと…
.

ラ ↗ シ ↗ ド ↗ レ ↗ ミ ↗ ファ
↗ ソ♯ ↗ ラ
.
…という和声的短音階上昇ラインが(1~5小節目をとおして)浮かび上がってきます。
[⇩ の動画は5小節目の前半限定での再生演奏]
さらに、この5小節目後半が面白い。ここ、音楽理論的には変なのですよ。

どう変かというと、見てのとおり「ミ」と「ミ♭」がいっしょに鳴ってしまっているのです。ちなみに緑で括った以外の場所にも、この不一致があります。

.
この編曲者さんのシーケンサー入力ミスかなーと思って原楽譜(ジェスマイヤー補作版)に当たってみても、こういう風でした。
現代風のコードネームで記すならば Am(add♯11) とこじつけるしかありません。18世紀ウィーンの音楽家がこういうジャズともつかない響きを、計算して使うとも思えないし…
鍵盤を何度も鳴らしては首をひねり続けるうちに、謎が解けました。解けたように思います。
ウォルフガングは、弦楽器によるオスティナートを書き込んでいくにあたって、ごく素朴なやり方を取っていたにすぎない。三つの和音、具体的には Am と Dm と E7 の三つの分散和音として、だんだんと全体が和声的短音階に沿って上昇していく、そういうものを考え、実際そうやって楽譜に記していったにすぎないなって。
そこに以下の増四度音程(緑の⇔で表示した音程)が重なって、それがたまたま「ミ」と「ミ♭」の同時出現という、一見不可思議なことが偶発的に生じたにすぎないのだとみます。

.
ひとつ前に拍にも、増四度音程があります。E7 和音における③と⑦の音程。

.
それがこうやって、次の拍で、半音上にずり上げているのです。だんだんと切羽詰まっていく感じを出すために。

いいですか念押ししますよ。このオスティナートは E7 → Am つまり ドミナントセブンス ➱ マイナートニック というごく素朴な進行の分散和音にすぎない。

そこに E7 の③と⑦が響かせる増四度の不協和が、青の矢印のように半音せり上がって Am に重なったら、理論上おかしい組み合わせが生じたと、そういうことです。

いきなり物理学のお話になるぞ
アイザック・ニュートンの『自然哲学の数学的諸原理』いわゆる『プリンキピア』を思い出します。
リンゴが枝から落っこちてどうのこうのという、あの逸話(彼は実際そう自分の姪っ子に、あの本の着想について語っていたとか)の書物です。
現代の、微積によって整えられた力学体系にそってあの本を読もうとすると、どう頑張っても記述と理解に不整合が生じてくることで有名な、あの書物です。
どうしてそんなことが生じるかというと、彼は微積を使っていなかったからです。
初等幾何を駆使して、書き上げたのですアイザック。
.

ウォルフガングもそうでした。
その楽曲分析にあたって、私は20世紀に整えられた音楽理論や記法を使っていますが、彼の時代にはそういうものはなくて、和声理論ももっと素朴なものでした。("ラモー" と "和声" で検索するといろいろ出てくる)
面白いです。現代の理論との不整合ゆえに彼の作曲工程が、図らずもこうやって浮彫りになってくるのだから。
ニクいぜウォルフィー
ここで E の和音に滑り込んでますね。E7 ではなく E であるのが心憎い。
「レ」つまり⑦の音を省くことで、③と⑦で生じてしまう増四度音程をあらかじめ消しているのです。

.
E7 と思わせて E で済ませることで、A短調に収まりながらもドミナント・モーションは生じないようにしています。
そのおかげで着地感がありますね。
.
彼はなぜここで一音抜いた?
さてここでですね短三度音程が縦二連する和音が現れます。「ミ♭・ファ♯・ラ」。
E7 → Am 進行ならぬ E → Adim(no C)と解すのが順当なのですが…

.
どうして「ド」は外されているのでしょうね。試しに Adim や E♭dim を試してみたところ、違和感ないのです。ウォルフィーどうしてあなたはここで「ド」を鳴らさない決断をしたの??
その謎は、続く和音で解けます。「シ・レ・ファ」。これおそらく G7(no G) です。続く小節よりこの曲はC長調にチェンジしC和音が登場するので、その前振りと思われます。「ソ」を鳴らさないのは、鳴らすとその瞬間にC長調への転調がなされてしまうので、寸止めしたものと思われます。

ひとつ前の和音が「ラ・ミ♭・ファ♯」(の転回形)であって「ド」が鳴らないのは、C長調へのチェンジ前にCつまり「ド」を鳴らしたくなかったからと思われます。

続く和音で「シ」が鳴りますね。つまり ラ ↗ シ の上昇ラインがさりげなく埋め込まれているのです。この後 ド まで上がっていくんだよーと。

事実「シ ↗ ド」と、C長調の基音に着地するのです。

おさらいがてら、とおしで聴いてみましょう。
.
ふう。つづくのだ。
.