
法善寺にて
ぼくは浪花大助。禁忌大学三年生。経済学部にいて、流通や観光学を学んでいる。実家は株式会社浪花観光。大手ではないが、ひい爺さんの代から経営している。ぼくも卒業したら両親を手伝うつもりだった。しかし昨今のコロナ禍で会社が倒産。よって学費が払えなくなった。あと一年で卒業だというのに、なんてことだ。でも、生活費にも困るぐらいになったからね。家もボロ家に引っ越した。
両親は深夜まで金策に駆け回っているが結果はよくない。父親の涙を初めて見た。何、また羽振りがよくなったら、大学は入りなおしたらいい。ぼくも働こう。
退学届を出した翌朝、両親を起こさぬようにそっと起きた。午前六時ごろ。季節は五月のはじめでもう蝉が鳴いている。穴の開いたシャツと中学生の頃から愛用しているデニムのぼろジーンズをはいた。足元はサンダル。ちょっと肌寒いが日が昇れば暑くなってちょうどいいぐらいだろう。
前の家と段違いに低い天井と暗い玄関を出る。自転車や三輪車が置いてある共用廊下を通り、狭くてきしむエレベーターに乗って階下に降りる。ごみだらけのエントランスを出ると、ビルが林立する下層部よろしく汚いアスファルトで覆われた小さなマンションやアパートの集合体から徒歩で抜ける。
行き先は難波駅近くのハローワークだ。営業開始まで、このあたりを散歩しよう。将来のことを思えば不安だが、悪い考えを保って物事が良い方向に変わるわけがない。ネガティブなことは考えないでおく。
千日前商店街へ。この通りは難波から本町まで続く繁華街だが、さすがに朝は静かだ。ハトとスズメが通りのど真ん中で遊んでいる。キャリーバッグを引っ張るビジネス客が通るたびにどこかに飛び立っていく。ぼくはなじみのある鳥たちに癒された。
法善寺横丁の案内板を見かけ、足を向ける。幼いころは亡き祖母に手をひかれてよく参拝していた。記憶と全く変わらぬ位置に水掛不動がおわす。ここの不動は全身に美しい緑色の苔をまとっている。朝の柔らかい光につつまれてぼくは引き寄せられるように近寄る。近くに置かれていた柄杓を手に取り、水をすくって不動の足元に掛ける。水は不動像に音もなくしみこみ、緑色の鮮やかさがいや増す。それから手をあわせて不動を拝む。どうか良い仕事が見つかりますように。
そこに、猫がいた。えらくまた肥った猫だ。白い胴体に手足だけが黒い。変わったデザインだなと思った。手足だけ黒ペンキかコールタールが入った壺に漬かったようだ。目は黒いが光っている。口元は薄いピンク。しかもどうしたのだろうと思うぐらいに口角が上がっている。笑っているようだ。不思議の国のアリスに出てくるチェシャ猫を思い出すが、猫はそもそも笑わない。その猫がぼくのそばに来て、頭をこすりつけてきた。ぼくもしゃがんで頭を撫でてやった。すると猫の口が開き、日本語が聞こえた。
「兄やん、今拝んでたやろ。どないな願い事をしたんや?」
空耳だ。しかし猫はぼくの顔をじっと見て返事を待っている。
「……は?」
猫はじれったそうに再び口を開く。
「日本語わかるか」
ぼくは思わずどもってしまった。小さいころからのくせが出た。
「ね、ね猫がし、しぇ、しょべった?」
猫の口がさらに開いて正三角形になった。上に一つの角、底辺二つの角。小学校の時にコンパスを使って練習したっけ。そんなことを急に思いだす。三つの角はそれぞれ六十度なり。というより、猫ってこんな口をしていたか? 猫は正三角形の上と下を瞬間的にひっくり返した。つまり、さきほどの底辺が上になり、さらに笑っているように見えた。その三角形からは牙が見え、そこからまた日本語が聞こえてきた。
「ほおい、聞こえるか、しっかりしろ」
ぼくは唸る。
「……ぅ」
猫はじれったそうだ。
「願い事は?」
ぼくは地面に両手をついて四つん這いになった。猫に対して土下座した態勢だ。そのまま正直に言った。
「し、仕事が欲しいでふぅ」
猫の中にある正三角形が閉じた。ピンクの細い線がマキビシになった。一体この猫はなんだろう。猫の声はそれきり途絶えた。ぼくは呆然と猫を見る。
「ちょっと、すみません」
急に耳元で甲高い声がしたのでぼくは飛び上がった。リュックを背負った女性だ。ピンクの帽子をかぶったその人は小さなデジタルカメラをぼくに差し出す。
「写真とってくれる? 水掛不動と猫と私」
「は、はい」
ぼくは、その猫しゃべってたよね? とも聞けず素直にカメラを受け取りシャッターを押す。例の猫は大人しく手を舐めていた。女性は笑顔で去った。次に夫婦連れが「シャッターぷりーず」 と言うので頷く。その次は三人組だ。いつのまにか各国の観光客に囲まれていた。まるでコロナウイルスが世間を席捲する前の状態だ。だいじょうぶかと思う暇もないぐらい忙しい。
一人旅、恋人、子連れの家族の笑顔を撮っているうちにぼくの気分も晴れて楽しくなってきた。緑色の苔を纏う不動と猫は同じ配置だ。みんなの顔や体型、国籍も違うのに同じ場面を撮る。撮った後に笑顔で「アリガトウ」と言うのも同じ。ぼくは上機嫌で叫んだ。
「シャッター押しますよ、思い出にどうぞ!」
「オ~ネガイ シンマ~ス」
ぼくはその声の主の様子に目を見張る。
銀色の服を来ている。目玉も銀色だった。その後ろには長い羽で覆われた人がいた。足が八本ある。その次は目も三つ、どうかすると八個ぐらい鼻の穴がある人もいる。こんなことってあるのか。猫は被写体になりながらも、時折ぼくのほうを窺う。ぼくはシャッター押しに徹することにした。目玉だけの顔の人、首が二つある人、足が四本ある人。みんなカメラを持っている。容貌はぼくと違っていても、観光客として楽しんでいる。だから怖くはなかった。とにかくシャッターを押せばいい。
猫が大きなあくびをした。それが合図だったのか、急に誰もいなくなった。静かになった。ぼくは色々な観光客のシャッターを押したよね? 不思議がっていると、また声が聞こえた。
「夢やないデ」
猫は、ぼくに顔を向けて座った。尻尾をぐるりと巻く。
「さて、兄やんの名は?」
「ダ、ダイスケでふ」
「地球外から人間に紛れて観光してんのが、わかったか?」
「……」
「目玉がぎょうさんある観光客に驚くか?」
「はぃ」
「ワイは猫やが、地球外からの観光ガイドもしてんねん。ダイスケも手伝うか?」
「シ、シアッター押しならできまふ……」
「逃げる人は困る。その点、君は合格や。守秘義務も負うがね」
「……」
「仕事が欲しいと言うたな、君の願いはかなう」
「じゃ、給料が出るのでふね」
「日本円だろ? 完璧にカラーコピーをしたやつを好きなだけやる」
「しょれは……あかん、犯罪です」
猫は唸った。
「どこでも動いたら金がかかるのは一緒やのぉ」
ぼくは言った。
「当たり前ですよ。でもシャッターを押すぐらいなら無料でしますよ。ボランティアで」
猫はぼくの顔を見上げたままだ。ぼくは頭が冷えてきた。しゃがんで猫に話しかける。
「地球外から来る観光客てどうやってくるの? 日本で使うお金は? ホテルは? さっきのような姿でシャッターを押してと言われると、いくら大阪モンでも逃げると思う。大騒ぎになるで。それと、コロナウイルス感染対策もちゃんとしないと。さっきの客はみんなマスクをしていなかったよ、危ないよ」
猫は咳ばらいをした。
「地球滞在中だけ原住民変身チップを使うねん。さっきは君を試すためにチップなしで、そのままの姿で出てきてもろてん……美しい自然と人工的な繁華街、そして古来からの信仰があいまって日本は、地球外からでも特に人気がある。それと体の構造自体が違うから感染は気にするな。マスクの件は注意喚起しておく」
ぼくはうれしくなってきた。
「おおきに」
猫は肩をゆすった。
「ダイスケ。地球人、地球外人かかわらず、観光ガイドをしてくれ。ただ変身チップを使うときの不具合がでたら連絡をしてほしい」
「給料が出るならその分がんばります」
「一生分保証する。ダイスケは、婆ちゃんに連れられて小さいころからお参りしてたんやてな」
「なんでわかるんですか」
「この水掛不動がテレパシーで教えてくれた。彼も古来から観光ガイドやで。お前の保証人を申し出た」
「えっ?」
「悪いことをしたらバチがあたる」
ぼくは不動を振り仰いだが何も聞こえない。
「……」
白猫が急に二本足で立ち上がってきっぱりと言った。
「幸運を保証してくれたということや」
ぼくはあわてて不動に手をあわせ何度も頭を下げた。不動は一瞬だけ苔を金色に光らせた。
……というわけで、ぼくは大阪の観光ガイドになった。給料は猫の指示通りに宝くじを買ったら七億円当たった。幸運が続いて両親の会社も立ち直った。表向きは学生ボランティアガイドとしてミナミにいる。同時に猫と一緒に地球外観光客の案内もする。今日も地球内外から大阪の街を楽しむ笑顔のシャッター押しだ。GO TO プランの日本人客と外国からの観光客と地球外の観光客と。みんなまじっているけど楽しいひと時を共有できてうれしい。
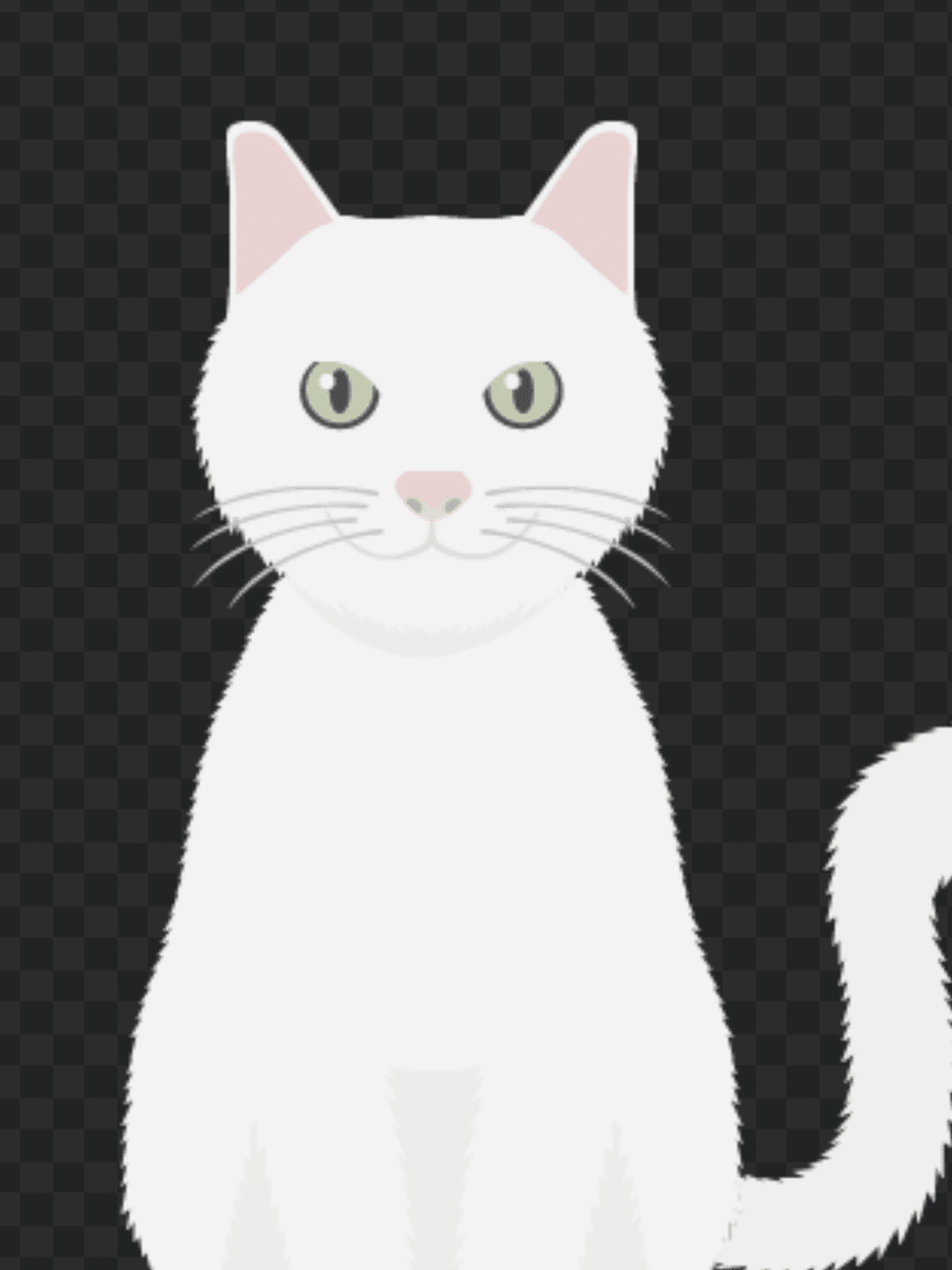
法善寺公式
法善寺Wikipedia
いいなと思ったら応援しよう!

