
昭和 風雲サバイバーが見た バッテリー残量8%の世界 昭和100年
私は「昭和 風雲サバイバー」である。(会員番号30番)
時は昭和100年。(会員番号は、現在100番まで登録済)
戦後の復興から高度経済成長を経て、数々の社会変革を乗り越えてきたまさに「サバイバー」である。困難な時代を経て強さを身につけ、昭和の文化と現代の価値観を融合させた「ハイブリッド」な存在であり、柔軟な思考と適応力が特徴だ。
しかし最近、私にも弱点が現れた。それは「視界のエレガンス」で、かつての鋭い眼力が失われ、細かい文字が見えづらくなったことだ。動物で例えるなら「風に立つ気弱なライオン」で、強さを持ちながらも不安を抱えている。
それでも、私たちの豊富な経験と知恵は今の社会にとって貴重な資源だと信じている。これからも挑戦を続け、「昭和 風雲サバイバー30号」として進化し、道を切り開いていきたいと思っている。

昭和100年の思い バッテリー残量8% 恐怖の世界
私は「昭和の風雲サバイバー30号」として、我々の生活の身近にある「電池」の変遷を見つめてきました。
いきなり心理テストです。14問あります。5段階でお答えください。
みなさんは、最近自然と、下記のような気持ちになったり、行動をとったりしたことがありますか?

自己診断結果
14問の項目の総合計からの判断です。
総合計が70~43点の方:引き続き、以下のnoteブログ購読をお勧めします。
総合計が42~14点の方:「連絡途絶不安症候群」(※後に説明します)の恐れがあります。以下のnoteブログ購読を強くお勧めします。
未記入の方:面白くないかもしれませんが、寛大なお気持ちで引き続きお付き合いください。お願いいたします。

「連絡途絶不安症候群」とは
スマホのバッテリー残量が少なくなったときに見られる、人々の一般的な行動パターンです。特に、「あと一歩で充電切れ!このままじゃ、友達もバッテリーも消える…!」という恐怖観念に駆られ、精神的に追い込まれ、普段とは異なる様々な行動をとってしまう症状全般を指しています。現在の医学では、特効薬はまだありません。
対処療法として、充電器との恋愛関係を築くことをお勧めします。自分の充電器に名前をつけ、日々の感謝を伝えるのです。例えば、「シンバちゃん、今日も私を救ってくれてありがとう!」と話しかけることで、精神的安定を図る…などです。
あくまでもフィクションの世界のことですが
この「連絡途絶不安症候群」は、あくまでもフィクションの世界のことですが、2025年の世界に近い要素も含まれているかもしれません。私も含めて、常に「バッテリー不足」の恐怖に追いかけられています。言い換えれば、我々の生活がいかにリチウムイオン電池などの蓄電機能に頼り切っているかがわかります。

さて、昭和の風雲サバイバー30号が小学生の頃の「電池」事情について振り返ってみました。あの頃は、「マンガン乾電池」の全盛期でした。(「アルカリ乾電池」が標準的な電源として広く使用されるようになったのは、1980年代のことです。)
まず、単一乾電池です。家の柱に据え付けられたSEIKOの電池式振り子時計がありました。乾電池一個で動くのです。鳩が飛び出したり、音が出たりするなどの余計なカラクリはありません。それまではゼンマイ式だったため、柱時計の大革命と言えます。
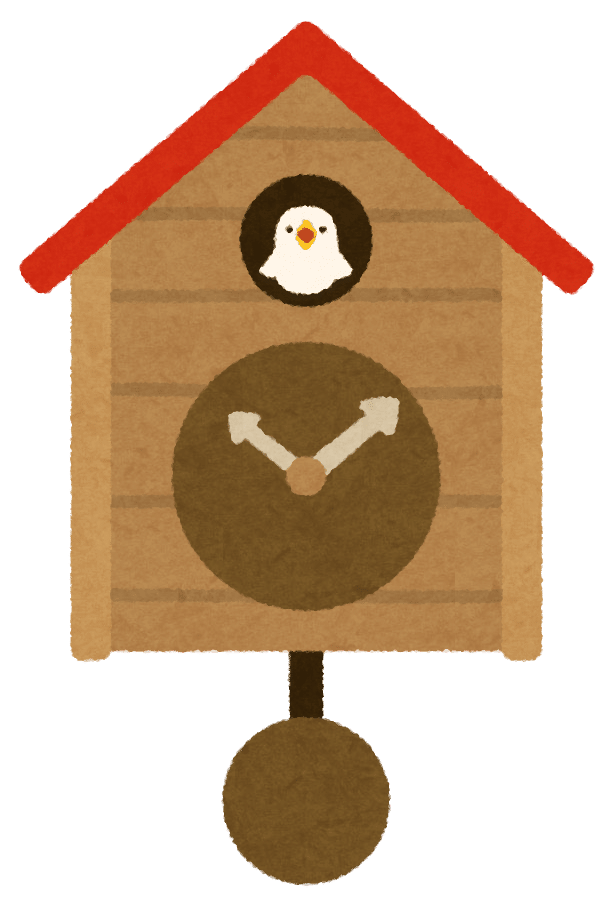
続いて、単二乾電池です。SONYのトランジスターラジオの登場により、その小さな電池にスポットライトが当たりました。10円玉でトランジスターラジオの背面のパネルのねじを開けます。そうすると、真空管の世界とは全く異なる異空間が目の前に広がります。まるで「鉄腕アトム」が飛び回る未来都市のようです。その中に透明なプラスチック製の筒があり、そこに単二電池二個を(+)と(-)極を間違えないように滑り込ませて、ラジオのセッティングが完了します。
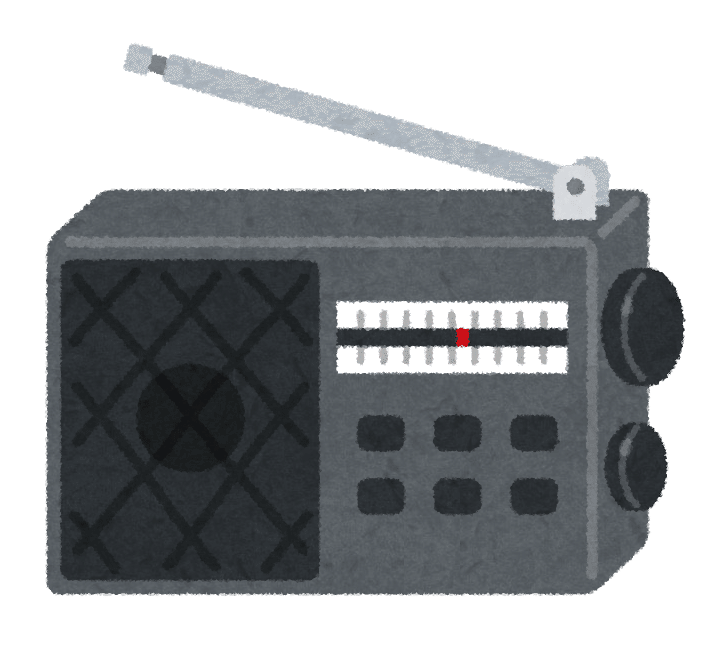
今では古くさい銀色のロッドアンテナを引き延ばして、スイッチON!チューニングダイヤルを回すと、スピーカーから橋幸夫&吉永小百合の「いつでも夢を」の曲が流れてきます。まさに乾電池が奏でる「夢の世界」でした。
連絡途絶不安症:バッテリー残量8% 恐怖の世界!
友達も消えていく…!
とは、全く別の世界のようです。充電や蓄電という概念は、一般家庭ではまだ存在していませんでした。
昭和 風雲サバイバー30号の感覚では、電池といえばせいぜい単三電池までで、プラモデルで戦艦大和を組み立て、船の底に吸盤付きの「マブチ水中モーター」をつけて風呂で遊ぶという至福の時間に、単三電池が活躍していました。当時、発売当初から子どもたちに絶大な支持を受け、ヒットとなった傑作のモーターでした。
こうして、「昭和の風雲サバイバー」は、経験的に電池の配線について学んでいったのです。豆電球もモーターの仕組みも、「並列つなぎ」「直列つなぎ」もお手の物でした。

発電のメカニズムも自転車から経験的に学びました。当時、自転車の照明は「ダイナモ発電装置」を自転車の前輪に据え付け、自転車の車輪の回転を利用して発電し、その電力で自転車の照明を点灯させるという「魔法のランプ」でした。
しかし、この装置にも欠点がありました。電力量は自転車の回転力に依存するため、上り坂では暗く、下り坂では明るいという状況が発生します。「昭和 風雲サバイバー」の世界では、電気は自転車をこいで発電するという概念です。

このシステムは今でも応用可能で、スマホの電力くらいは自転車の「ダイナモ発電装置」で賄えます。ただし、道路交通法上、自転車で発電しながらスマホを操作することは禁止されています。とはいえ、自転車の「ダイナモ発電装置」は、あなたの「連絡途絶不安症候群」にとって有効な対処方法だと言えるでしょう。試してみませんか?
別の言い方をすれば、脚力さえあれば、あなたは今、理想的な電力の世界に住んでいるということです。発電・蓄電・充電のテクノロジーと電池の未来は、あなたの目と足の先にあるのです。
昭和が懐かしいといった話だけを展開しようとしたわけではありません。このブログの根底に流れるポリシーは、昭和を振り返ることが単なるノスタルジーにとどまらず、2025年からの視点で批判と共感の両側面に触れることです。

昭和の教訓を令和に活かす視座を持ちながら、未来に何をもたらすかを考え続けていきたいと思います。私たちの過去の経験は、未来にとっての「心の温かいランプ」になるかもしれません。暗い道を照らしてくれるように、私たちの知恵や思い出が、これからの冒険を明るく照らしてくれることを願っています。
あなたは、これから「充電・蓄電・発電」の世界と「電池」とどのように付き合っていきますか?くれぐれも、「連絡途絶不安症候群」にはお気をつけください。
いかがでしたでしょうか?最後までお付き合いいただき、心より感謝申し上げます。これからも「昭和 風雲サバイバー30号」としての旅は続きます。次回の冒険もお楽しみに!


