
3分で人物史 | 《後編》シシィの姪 - エリザベート・ド・バヴィエール
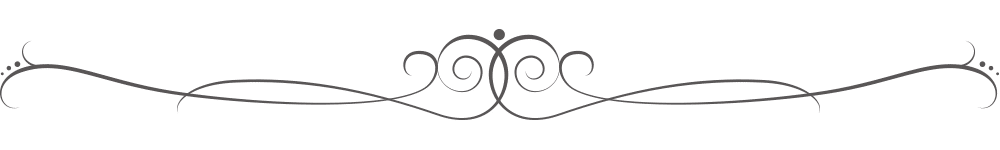
ドイツ・バイエルン公国に生まれ、ベルギー王室に嫁いだエリザベート。
(1910年代、30歳前後の頃)
夫が国王に即位した後、第一次世界大戦が起こります。
貴族にも関わらず開業医となり、身分関係なく患者を診ていた両親の下で育ったエリザベート。
そんな彼女は戦時中、宮殿やホテルを改装して病院を設立します。
また音楽や絵画、演劇などの芸術も奨励し、傷ついた兵士や国民に慰めを与えるのでした。
↓これまでのお話はこちら↓
◆第一次世界大戦後
戦後も、彼女の活動は止まりません。
戦争中 最前線の病院で負傷兵を目の当たりにした経験から、1926年クイーンエリザベス医療財団(Wikipediaに合わせて英語読みにしました)を設立。
更に ベルギー植民地コンゴには、クイーンエリザベス医療支援基金を作ります。
◇
そのように精力的に動いていたエリザベートでしたが、悲しい出来事もありました。
1934年、夫のアルベール国王が、登山事故で亡くなります。
エリザベート57歳の時でした。
アルベール国王は、エリザベートに負けず劣らず家庭的・庶民的な人柄で国民に愛されていました。
(この登山も、趣味の一環だったそうです)
大戦時エリザベートが前線で兵士たちの手当てをする間、彼は軍隊と共に戦いました。
◇
夫亡き後は、長男が後継者として即位。
この時長男には妻がいた為、エリザベートは一旦王妃としての公務から退きます。
ところが、夫が亡くなった翌年、長男の妻も事故死してしまいます。
エリザベートは長男とその家族を支え、再度公の場に返り咲くのでした。
◇
1937年には、世界三大音楽コンクールのひとつであるエリザベート王妃国際音楽コンクールを創設。
またベルギー王立図書館やエリザベス王妃音楽礼拝堂(Chapelle musicale Reine Élisabeth / Muziekkapel Koningin Elisabeth)を設立し、
学問や芸術の奨励活動を続けます。
(ベルギー王立図書館 by EmDee,
CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons)
◆第二次世界大戦〜晩年
1940年、第二次世界大戦が起こります。
この時、エリザベートは母国語であるドイツ語を利用して、ベルギー国内にいる何百人ものユダヤ人の子供達を、ナチス政権による国外追放から救い出したと伝えられています。
この事で、のちにイスラエル政府から「諸国民の中の正義の人」の称号を与えられました。
日本人では唯一、杉原千畝さんがこの称号を授与されています。
◇
第二次世界大戦が集結し、東西冷戦中だった1950年代。
エリザベートは共産主義を掲げる国々(ポーランド、ユーゴスラビア、中国、ソ連)を訪問し、ベルギー国内で物議を醸します。
この事から、「赤の女王」というあだ名がつきました。
(北京訪問中のエリザベート)
エリザベートがいわゆる「東側」を訪問した理由はよく分かりません。
考えられるのは、当時ソ連が アメリカへの対抗策として、彼女の大好きな芸術に力を入れていたからかもしれません。
(世界的に権威のあるチャイコフスキー国際コンクールも、元々はその一環です)
「私はあらゆる芸術が好きなの。
特に東の国の芸術をこの目で見るのが大好き」
と語っています。
ソ連以外の東側を訪問した理由はもっとよく分かりませんが、元々差別や偏見の目を持たない彼女ですから、招待を受けたら「あっ行く行く(軽)」みたいな感じだったのかもしれませんね。
◇
またアインシュタインやシュバイツァー、ジャンコクトーなど、人種を超えた学者や芸術家と幅広く交流を続けました。
晩年はヨガや散歩で健康を維持していましたが、1965年、心臓発作の為亡くなりました。
89歳でした。
◇
既存の枠にとらわれる事なく、学問・芸術・医療と様々な分野で功績を残したエリザベート。
親しい芸術家に、しばしば「私はただの女王です(Je ne suis qu'une reine)」と語っていたそうです。
ベルギー王室に嫁いで、窮屈な思いをする事があってのセリフだったのかもしれません。
それでも、自分の立場や能力を他人のために惜しみなく使い生きた人という印象を持ちました。

(1918年、負傷兵を見舞うエリザベート)
◆おまけ - ティアラミニストーリー
カバー画像でエリザベートが着用している、孫悟空の輪っかみたいなティアラ (←言い方よ)、気になりませんか?

これはカルティエのもので、ダイヤモンドとプラチナで出来ています。(詳しい画像はこちら)
エリザベートの死後、息子レオポルドの後妻(先妻は事故死)によって売却されてしまいますが、後にカルティエに戻り、現在でも大切に保管されているそうです。
◆参考
Wikipedia: 日本語、フランス語
Unofficial Royalty
The Royal of Sartorial Splendor









