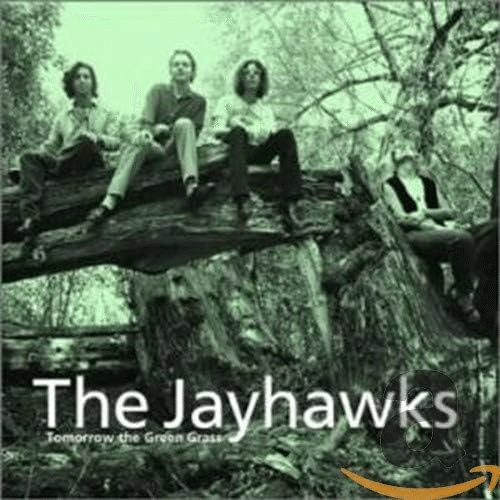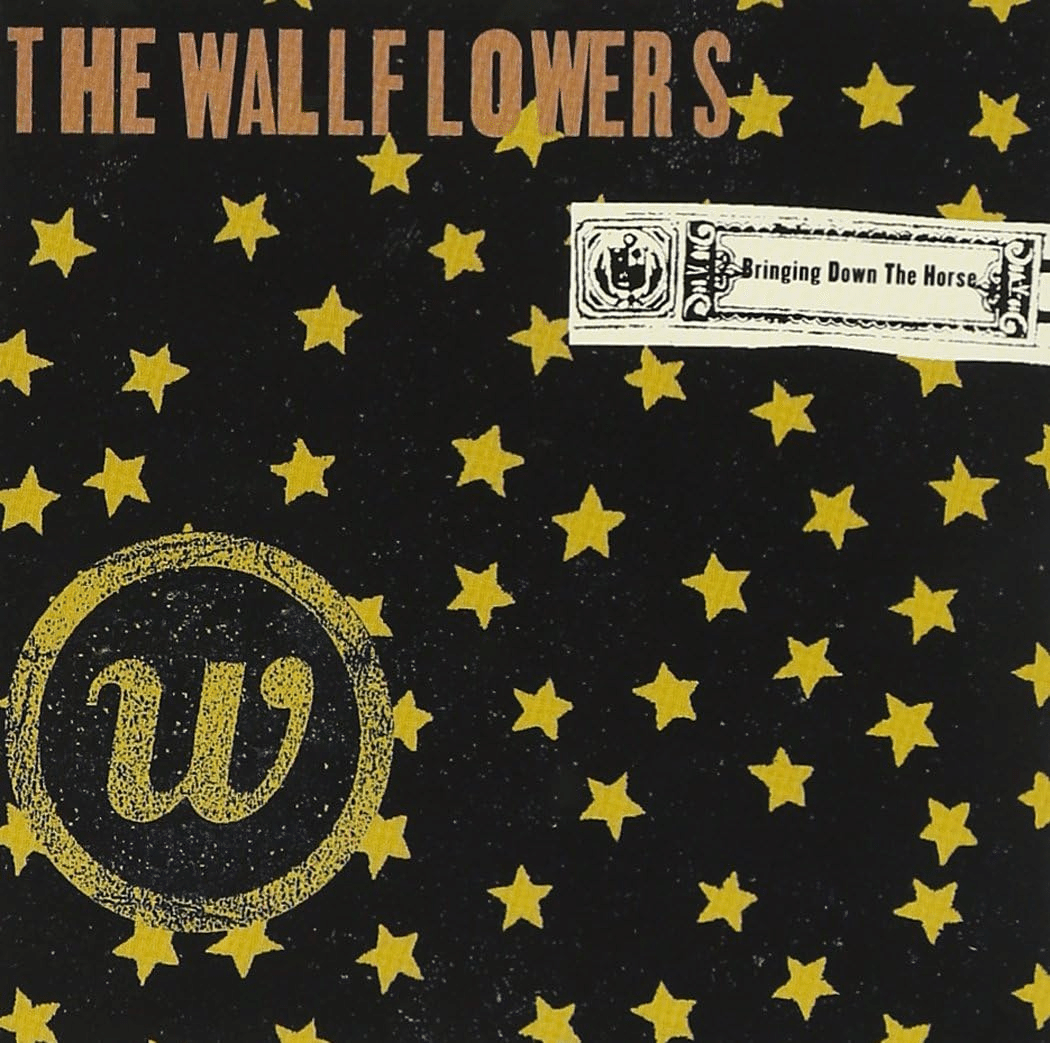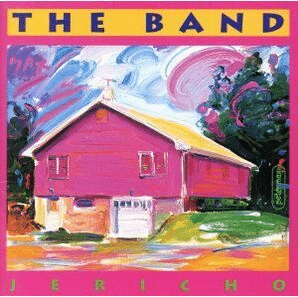アメリカン・ミュージック・ヒストリー第10章(1990年代全般・・・その4)
(4)オルタナティヴ・カントリー&ルーツ系ロックの復活
一方で、60年代~70年代にかけてアメリカン・ロックのメインストリームであったカントリー・ロックが、パンク・ロックを経験した世代によってオルタナティヴ・カントリーやアメリカン・ルーツ系ロック(この時代は、まだアメリカーナとは呼ばれていなかったと思いますが)として再び脚光を浴びることになります。
代表的グループとしては、アンクル・テュペロ、そして解散後誕生したウィルコとサン・ヴォルト、そしてジェイ・ホークス、ウイスキー・タウン(ライアン・アダムス)、BR5-49、女優ジュリア・ロバーツの元旦那としても有名なライル・ラヴェット、ボブ・ディラン2世の率いるザ・ウォールフラワーズ、同じくジム・クロウチ2世のA.J.クロウチ、80年代後半から活動しているスティーヴ・アール等が挙げられます。
更に、オクラホマ州タルサからは、グラミー賞にも輝いた、ザ・トラクターズ。リーダーのステーヴ・リプリーを初めとして、実績十分なスタジオ・ミュージシャンに加えてファーストアルバムには、JJ・ケイル、レオン・ラッセル、ボニー・レイット等をゲストに迎え、最高のタルサ・サウンドを展開しています。
もう一組、ケンタッキー州からは、ヘッド・ハンターズ。サザン・ロックテイストのカントリーミュージックが小気味良いです。この二組は、個人的に大好きで、ほとんどのアルバムを収集しました。
男性ばかりではなく、女性ルーツ系アーティストとしては、ルシンダ・ウイリアムス。90年代当時は、今まで紹介したアーティストに比べるとあまり注目されていなかったように思いますが、70才を超えた今日でも素晴らしいアルバムをリリースし続けています。
彼女は、コンポーザーとしても影響を与えていて、1988年にリリースしたアルバムからは、前項のカントリー&ブルーグラス新世代で紹介したパティ・ラブレスが「The Night’s Too Long」、メアリー・チェイピン・カーターが「Passionate Kisses」をカバーしています。
こうした動きに触発されたのか、ベテランルーツ系アーティストも復活し、次々と素晴らしいアルバムを発表していきました。
まず、ジョン・フォガティの約10年ぶりのアルバム「Blue Moon Swamp」、ボブ・ディランは「Time Out Of Mind」、サザン・ロックでは、オールマン・ブラザース・バンドが久しぶりのアルバム「Seven Turns」、もう一方の雄で飛行機事故の悲劇から復活し再結成したレイナード・スキナードの「1991」、同じく再結成したザ・バンドの「Jericho」、又、ダン・ペン、ドニー・フリッツ、ボビー・チャールス等の激渋組も健在。
80年代から引き続き好調なロス・ロボスは、その筋から評判の高い「Colossal Head」、同じく絶好調のジョニー・ウインターは、「”hey,where's your brother?"」、ジョージア・サテライツは、解散しましたが、リード・ヴォーカルだったダン・ベアードの「Love Song For The Hearing Impaired」等もなかなか良かったです。
そして、ウェストコースト3大バンドの相次ぐ再結成及びニューアルバムのリリースは、私たち世代には、特に嬉しいニュースでした。
トム・ジョンストンが完全復活したドゥービー・ブラザース(前章で1989年の再結成アルバムを紹介しました)、イーグルスは、新曲は4曲ですがホテル・カリフォルニアのアコースティック・ヴァージョンが評判となった「Hell Freezes Over」、スティーリー・ダンは、厳密には2000年発表ですが、念願の最優秀アルバムを受賞した「Two Against Nature」。
最後にもう一人、白人ではありませんが、特別枠としてブルースレジェンドのBuddy Guy。90年代は絶好調で91年、ジェフ・ベック、エリック・クラプトン、マーク・ノップラーをゲストに迎えたアルバム「Damm Right I’ve Got The Blues」で復活し、その後も立て続けに好アルバムを連発してくれました。
*カントリー・ロックの逆襲
アメリカでのそうした流れを受け、日本でも1998年に大手6社(ユニヴァーサル・ワーナー・ソニー・東芝・ポリドール・マーキュリー)によるオムニバスCDの「カントリーロックの逆襲」シリーズが相次いで発売されました。
2000年には(ユニバーサル・ワーナー・ソニー・東芝)の4社が続編を発表し、本シリーズは10作品を数えるに至りました。
内容はと言うと、1960年代後半から90年代までのカントリー・ロックやルーツ系ロックのオムニバスです。まぁ、何でこの曲が入っているの?と言う突っ込みどころもありますが、私的には90年代音楽を知るのに随分重宝しました。