
スペシャリスト?それともゼネラリスト?初期スタートアップで得られるキャリアとは
このnoteは Repro稲田宙人さんの主宰する「モバイルアプリマーケティングアドベントカレンダー2020」の13日目の投稿です。面白かったら是非ハッシュタグ「#アプリマーケアドベント」を付けてシェアをお願いします!
はじめまして。ネストエッグという会社で貯金アプリfinbeeのプロダクトグロース/マーケ周りを担当している富宇賀と申します。
Repro伊藤さんに声をかけていただきモバイルアプリマーケティングアドベントカレンダー2020の13日目記事を担当することになりました。
12月も半ばとなり、だいぶ寒くなってきましたね。僕は冬が一番嫌いな季節なのでパフォーマンスの激しい低下を感じています……。
仕事が納まる目処が見えてきた人も、まだまだ先が見えない人もいると思いますが、年末年始、いつもと少しだけ流れる時間が変わるその期間に将来のことを考える人も多いのではないでしょうか。
「このまま今の会社にずっといて大丈夫なんだろうか」
「もっと裁量権のある会社でスピード感を持って仕事をしたい」
「安定感のある会社でじっくりキャリアを積みたい」
新たな年を迎えるにあたり、そんな風に転職を考え始める人も出てくると思います。何を隠そう、数年前の僕もそうでした。この記事は、そんな人にとって何かの役に立てばと思い書いたものです。
なお、表題の問いの結論を最初に言ってしまうと、初期スタートアップで得られるキャリアとしてはやはり「ゼネラリスト」に近いものになると考えています。
ただ、一口に「ゼネラリスト」と言っても思い浮かべる像は人それぞれだと思うので、実際に僕がどんなことを考え、どんなことをしてきたのか紹介することで具体的なイメージが伝われば幸いです。
簡単な自己紹介
元々web制作会社でディレクターをしたり、支援会社でマーケティングコンサルをしたりしていた僕は、年齢を重ねるにつれ「いつか事業会社に転職してプロダクト成長に携わりたい」という想いが強くなっていきました。
あるあるだとは思いますが、制作会社や支援会社ではクライアントの事業にコミットできる範囲に限界があります。クライアントマターで企画が頓挫してしまったり、内容に大きな変更が入ったり。できるのは「提言」までで、捨て案のB案を選ばれてしまえば「ぐぬぬ……」と思いながらその捨て案をブラッシュアップするしかありません。
もちろん、全体戦略からしっかりとコミットできる案件がないわけではないですが、予算の関係で部分的な対応に留まらざるを得ないケースも多いと思います。
「事業会社だったらもっとビジネスに直結した仕事ができるんだろうな」
「事業会社だったら裁量権を持って仕事ができるんだろうな」
そんな風に思い始めた僕がネストエッグに入社したのは、貯金アプリfinbeeを立ち上げたばかりのネストエッグという会社でした。僕が入った時、ネストエッグは2期目で、メンバーはまだ1桁しかいない状態でした。
なお、finbeeは日本初の自動貯金アプリとして2016年12月にリリースされたサービスです。ご興味ある方はぜひ以下のサービス紹介動画をご覧ください。
はじめに:初期スタートアップの現実
さて、皆さん、まずこの数字は何だと思いますか?
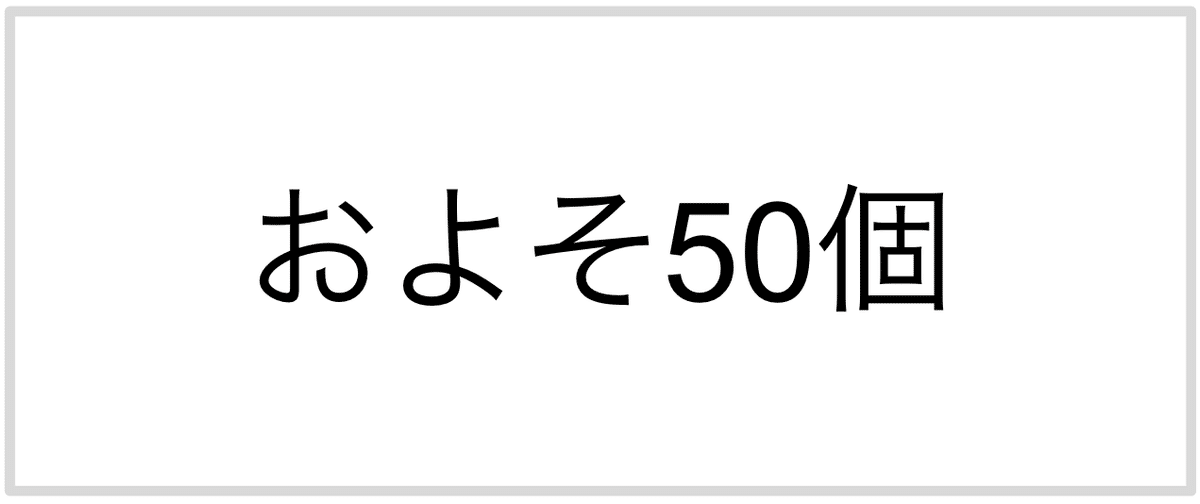
これは、僕が入社前に考えたプロダクトの改善施策案の数です。
別にこれはドヤりたいわけでもなんでもなく、単に僕が無邪気にはしゃいでいたということを伝えたいだけです。そもそもデータ分析を踏まえボトルネックなどを把握していない状態で出される施策案の精度は微妙なものでしょう。
制作会社や支援会社にいた僕は、事業会社でプロダクト/ビジネスを作っていくことに興味がありました。そしてようやく事業者のグロース担当という、まさに自分がやりたかったポジションでの内定を受けたのでした。
そのため、入社してすぐにプロダクト改善をしてグロース貢献をすべく、事前にキャッチアップできるものはキャッチアップし、考えられる限りの案出しをしたのです。
しかし、待っていたのはこれでした。

そう、現実です。いつだって現実は突然目の前を真っ暗にしてくれますよね。皆さんはスタートアップにどんなイメージを持っていますか?キラキラ?ドロドロ?イケイケ?
それらは合っているものもあれば異なっているものもあるでしょう。もちろん、会社によってもまちまちです。なので、乱暴に丸めることはできませんが、概ねこんな会社が多いとは思います。
・手が足りない
・お金ない
・時間ない
いわゆる「グロース」をすぐにやれる状態にはなさそうだとわかった僕は、早速(勝手に思い描いていた)期待を裏切られることとなったのです。
フェーズ0:キャッチアップ&現状(現実)把握期
考えていた施策の実行がすぐにはできそうにないとわかった僕は、まずキャッチアップを始めます。
・現状の各種数値はどうなっているか
・データ計測はどの粒度でやってるのか
・ツールはどんなものを使っているのか
・過去どんな施策をやってきたのか
・組織/プロダクトの課題はなにか
……etc
諸々ヒアリングの結果、以下のような状態であることがわかりました。
・DLしてもらえたはいいが、貯金開始まで至っているユーザーが少ない
・データは追える状態ではあるが、明確なプロダクトKPIがまだない
・マーケティング系のツールが未整備の状態
・リリース後のテコ入れはまだあまりできていない状態
・認知度向上&インストール増加が課題
……etc
ということで、まずは認知・流入・インストール・リテンションあたりの底上げのための土台作りを始めることにしました。
フェーズ1:土台作り&テストマーケ期
まずは全体像把握のため、
・データは追える状態ではあるが、明確なプロダクトKPIがまだない
の整備に着手します。
ファネル分析でボトルネックを特定したり、チャネル分析で獲得効率の良いチャネルはどこなのかを調べたり……。
足りないデータをかき集めたり、データ収集のためのツール導入などを行いながら、プロダクトの全体像を炙り出していきます。そうして全社KPIシートを作成し、月次での運用を開始しました。
KPIシートを眺めながら、改めて気になったのは以下です。
・認知度向上&インストール増加が課題
リリース当初は「リリース特需」の影響もありそれなりに流入があったようですが、次第にその恩恵も小さくなっていました。
ユーザー獲得のためのプロモーションアクセルを踏むフェーズではないとはいえ、データボリュームが小さいと仮説検証もしづらい状態になってしまうので、以下を実施することにしました。
・プロモ:テストマーケ(広告配信/イベント協賛など)
・オーガニック:ASO施策
テストマーケで大まかな獲得単価の目安とチャネル毎のユーザー属性・インサイトなどを検証し、ASO施策でベースインストールの積み上げを行います。
※なお、ASO施策ではReproさんに大変お世話になりました🙏
ASO施策の成功でそれなりにインストール数が増えてきた頃、KPIシートを眺めていると、以下が大きなボトルネックであることに改めて気づきます。
・DLしてもらえたはいいが、貯金開始まで至っているユーザーが少ない
しかし、このボトルネックは「提携銀行数の少なさ」が要因としては大きいため、解決には時間を要するものでした。とはいえ外部要因と割り切るには大きすぎるボトルネックです。この壁をどう乗り越えるかが一つ大きな成長因子になるという印象でした。
そこで、内部でこの壁をどうにかクリアする方法について検討を行います。
社内検討の結果、「自分の持っている銀行が連携されるまでの間、おためし(非連携)で使えるように機能開放をすべき」ということになり、「おためし貯金」機能が実装されます。
そして、それはプロモーションにおける課題の改善にも繋がりました。それまではプロモーション施策を行っても銀行口座連携で歩留まりしてしまい、肝心の貯金開始まで至らなかったからです。
しかし、銀行連携なしでも貯金開始できるようになることで、その歩留まりは大きく解消されます。
※「おためし貯金」はあくまで「バーチャルな貯金」であり、実際にお金が動くことはないため本質的な歩留まり解消ではないですが……。
「おためし貯金」のリリースは9月でした。
それまで課題だった貯金開始の歩留まりは解消され、数ヶ月後には貯金ニーズが高まる年末年始が待っています。
認知拡大を狙う数少ないチャンスだと思った僕は、それまでのテストマーケで得られたインサイトを踏まえ、プロモーション企画を検討/社内提案します。


そうして11月の末、プロモーション動画をリリースしたのでした。
動画は想定を超える評判を生み、認知だけでなく、インストール数も大きく増加しました。
ASOによるコアKWの上昇(によるオーガニック流入の増加)とプロモーション動画を用いた広告流入の増加によって、ベースインストール数の担保ができたため、僕は次のフェーズの着手に移ったのでした。
■このフェーズでやったこと
・データ収集
・ツール導入
・全社KPIの導入&運用
・テストマーケ(広告配信・イベント協賛)
・ASO対応
・おためし貯金リリース
・プロモーション用の動画作成
・サービス紹介動画作成
フェーズ2:体制整備期
ASOと動画広告の好調により、手を動かす時間を最小限にして一定の流入が見込める状態になりました。
ただ、まだ銀行数は十分なものとは言えません。プロモーションのアクセルを踏めるフェーズではなかったため、軽微なプロダクト改善を行いながらトリプルメディアの強化を行うことにします。
この時期finbeeではいわゆる「ペイドメディア」については動画広告がある程度機能していましたが、「アーンドメディア」にはそこまで力を入れられておらず、また「オウンドメディア」は存在しませんでした。
そこで、セオリーからするとかなり早いタイミングではあると思いますが、非広告の流入チャネルを整えるという意味でオウンドメディアの立ち上げを検討します。
オウンドメディア運用のメリットとしてはメインとサブで以下のようなものが考えられます。
※当然、成果が出るまでには時間がかかりますが……。
■オウンドメディア運用のメリット
《メイン》
・広告/宣伝費の抑制
・サービス(finbee)認知拡大
・リード育成&質の高いユーザーの送客
《サブ》
・ブランド構築
・コンテンツマーケとしての利用価値
・採用効果
すったもんだがありましたがそこは長くなるので割愛するとして、最終的に「be-topia」というメディアを立ち上げることができました。
また、いよいよマーケ/グロース周りを1人でやることに限界を感じ始めていたので、スムーズな連携や成果最大化のために組織としてうまくワークするような体制の整備を検討します。
■整備検討したもの
・データチームの立ち上げ
・グロースチームの立ち上げ
・マーケティング部の立ち上げ
残念ながらデータチームは1年ほどで解散してしまいましたが、その際に協力してくれたCS、エンジニアのおかげで社内にダッシュボード(Redash×slack)を導入することができ、より最新のデータを活用しやすい状態になりました。
■このフェーズでやったこと
・データチームの立ち上げ
・グロースチームの立ち上げ
・マーケティング部の立ち上げ
・Redash導入
・オウンドメデイア(be-topia)の立ち上げ
フェーズ3:プロダクト再定義期
動画広告の成果データを眺めていると、リリース初期に想定していたペルソナとは異なるユーザーが増えているようでした。
そこで、改めてクラスタやペルソナの見直しを行った方が良いと考え、検証に着手します。
まずはクラスタリング。だいぶ割愛してますがアンケート調査やデプスインタビューを踏まえこんな感じの概要をまとめて、

それをこんな感じでマッピング。

そしてターゲットクラスタを絞り込んだ上で、ペルソナの作成を行いました。
すると、やはりリリース時のターゲット像とは異なるペルソナが浮かび上がり、これを社内に展開。協議の結果、コアターゲットの見直しを行った方が良いという結論になりました。
また、コアターゲットを変えるこのタイミングでMVVについても再定義を行った方が再度メンバー間で目線を合わせられるだろうということでMVV再設計にも着手します。
議論の末に決まったMVVがこちら。


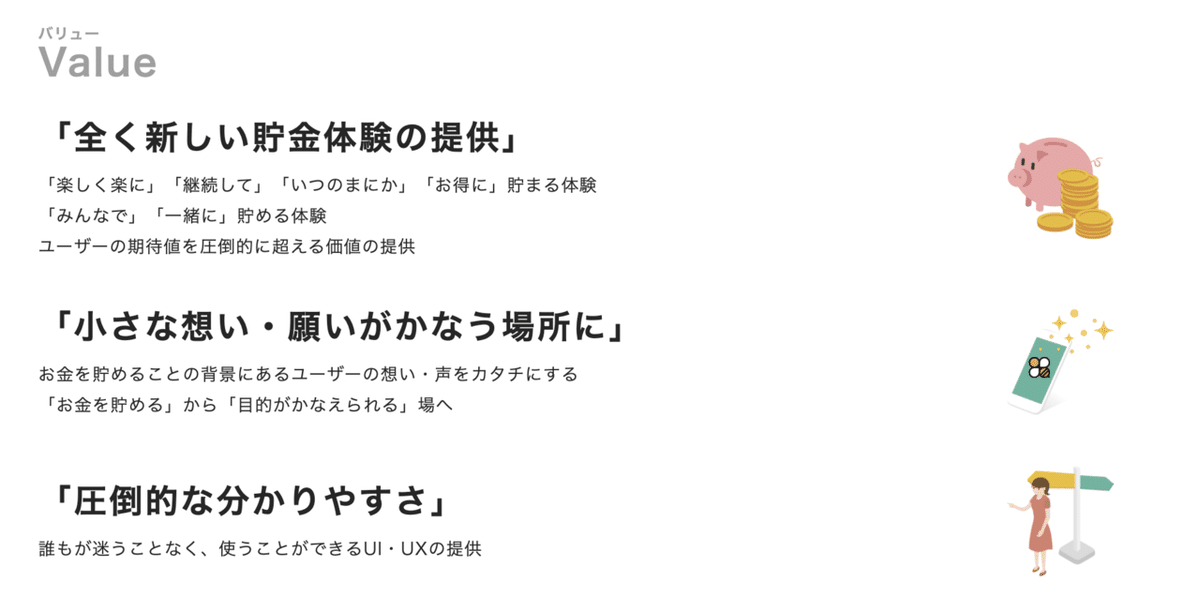
MVV再設計と並行して「どうせ変えるならこのタイミングでサイトも変えちゃう?」という話が社内で上がったのでサービスサイトのリニューアルも進行します。
個人的にはサービスサイトのトンマナが大きくズレているとは思ってはいませんでしたが、月間の流入に対するCV数としてはもう少し増やせるのではという印象はあったので、キーメッセージの刷新とCV導線の改善をメインの目的としてリニューアルを行いました。

成果としては、CVRが大きく改善し、流入母数自体はほぼ変わらずの状態でCV自体は4~5倍程度になりました。
元々のCV数を踏まえると、事業インパクトとしては大きくはないかもしれませんが、非広告経由のCVが月数百増えるというのはマーケティングメリットとしては大きいです。
例えばCPIが300円だとして、サービスサイト経由のCVが500/月増えたとしたら広告換算で15万/月になります。また、検索経由のユーザーは当然広告経由より質が高いのでそういう意味でのメリットも大きいです。
「アプリマーケ」としては見落とされがちな気はしますが、サービスサイトのCVR改善はそれなりに重要だなと感じた案件でした。
■このフェーズでやったこと
・クラスタ&ペルソナの再設計
・MVVの再設計
・サービスサイトリニューアル
フェーズ4:グロース期
そしてようやく現在です。
マーケティング部のメンバーも少しずつ増え、今期ようやくプロモーション専任のメンバーにもジョインしてもらうことができました。
開発チームも体制が強化され、新たなグロース施策も徐々に対応を開始しています。
入社当初思い描いていたキャリアとは違う結果にはなりましたが、「プロダクトを成長させる」という意味では一貫して寄与できたかなと思っています。
これからはさらなる成長に向け、あんなことやこんなことを仕込み中なので、できるだけ早く世に出せるよう頑張る所存です。
■このフェーズでやりたいこと
・機能追加&アップデート(仕込み中)
・協業プロモーション施策(仕込み中)
・XXXXXXXX(言えないやつ)
まとめ
ざっくりですが、入社してから今までやったことをフェーズに分けて紹介してみました。会社/プロダクトのフェーズにもよるので一概にどうこう言えるものでもないし言うつもりもないのですが、立ち上げ初期フェーズから数年のイメージとしては大体こんな感じなんじゃないかなと思います。
もちろん、ここには記載していない/できないアレコレがあったり、まとまりがいいような書き方をしてますが、実際にはこんなに滑らかに進んだわけではなく1歩進んで2歩下がるような時期もありましたが、それはまた別の機会に……。
また、わざわざ書いてないですが正直泥臭く地味な作業が半分くらい(以上?)なので、そういう作業をコツコツこなしながら、然るべきタイミングできちんとヒットを打てるタイプが向いてるのかなと思っています。
そして改めてキャリアの話になるんですが、自分が感じることとしては以下です。
■初期スタートアップで身につくこと
・仮説思考が強まり精度が上がる
→時間もお金も手も足りないのでできる限り最小の出力で最大の成果を出したい。ってことで常に仮説&根拠を考えるようになり仮説精度が上がる。
・全体最適思考になる
→新規流入だけでなく、リテンションやマネタイズ、マーケティングチャネルの全部を担当することになるので全体最適で考える癖がつく。
・調整力が上がる
→指示も戦略も待っててはやってこない。自分で各ステークホルダーと調整し作っていく必要があるのでそれぞれの立場を意識し調整する癖がつく。
・やり切る力が上がる
→とにもかくにもやらないと次に繋がらないし誰も助けてはくれないのでやり切る覚悟が身につく。
・マネジメント力が上がる
→基本的に「全部」やるのでCSとかプロモとかブランディングとか各メンバーの視点でフィードバックができるようになり信頼されやすい(と信じている)。
・チーム/部署立ち上げ経験を詰める
→必要なタイミングで必要なチームやメンバーの検討と採用に向けた実行を行う。自分の手でチームや部署の立ち上げができる機会はあまり多くないと思うのでいい経験になる。
わかりやすい「スキル」が身につくというよりは総合力の底上げがされるイメージが近く、マーケティングという職種でいうと、より経営視点が強まる感じです。
※やったことないことも色々やるのでやりながらスキルも身につきはしますが、「スペシャリスト」のそれとは異なるので。
昨日のタイミー中川さんの記事にも
いかに個別スキルをたくさん身に付けるかよりも、「大事な土台」をいかに強固にしていくか、という視点の方がより本質的なのかなと思い至りました。
という記載がありましたが、まさにこれに尽きるのかな、という気がします。
そして、上記を踏まえたキャリアとしては以下のあたりがあるのかな、と勝手に感じています。
・類似フェーズのスタートアップのマーケティング責任者
→初期の少数チームであればあるほど「あれもこれも」できる人が求められます。すでにそのような初期スタートアップのあれこれを経験してる人は、類似フェーズの別会社でも活躍を期待できるでしょう。
・企業のDX推進リード
→DX推進をリードするには広範なステークホルダーと対話し課題解決を行う必要があると思いますが、初期スタートアップのマーケ/グロース担当は部署横断でPJを推進していくことが多い(はず)です。そのような経験は、広範なステークホルダーがいる場でのファシリテーションにも活きると考えています。
おわりに
当たり前ですが、長々と紹介させていただいた各施策は僕一人で行ったものではありません。このどれもが社内外のメンバー/企業の協力のおかげで出来上がったものです。
正直「1人でやる」ことの方が得意だと思い小さなスタートアップに入ったというのも少しあったのですが、実際に感じたのは小さいからこそチームでやっていかないと何もできないということでした。もしかしたら一番大きな気づきはそれかもしれません。
以上、転職を考えている(特に初期toCスタートアップに)方の参考になれば幸いです🙇♂️
それでは引き続き、「モバイルアプリマーケティングアドベントカレンダー2020」をお楽しみくださいませ!
明日はkurashiru(クラシル)の小林さんです!
おまけ(PR)
finbeeは12/26で4周年を迎えます!
MVVを一新してから最初の周年ということもあり、ミッションである

を目指したものを予定しているのでまだDLしていない方はぜひDLしてキャンペーンに参加してみてください♪

https://finbee.jp/campaigns/4th_anniversary/
